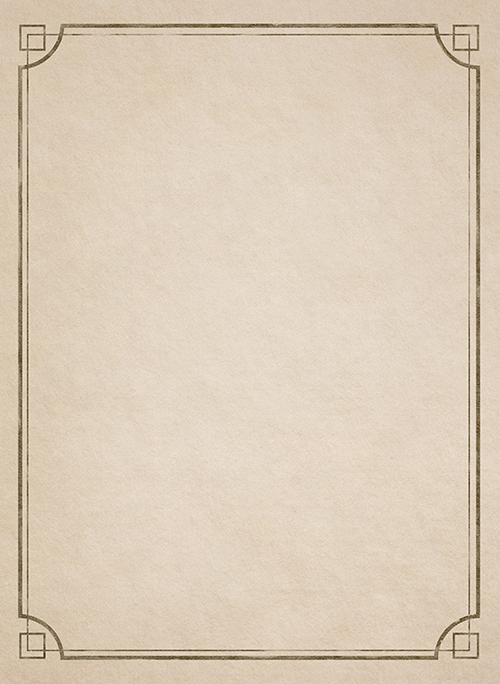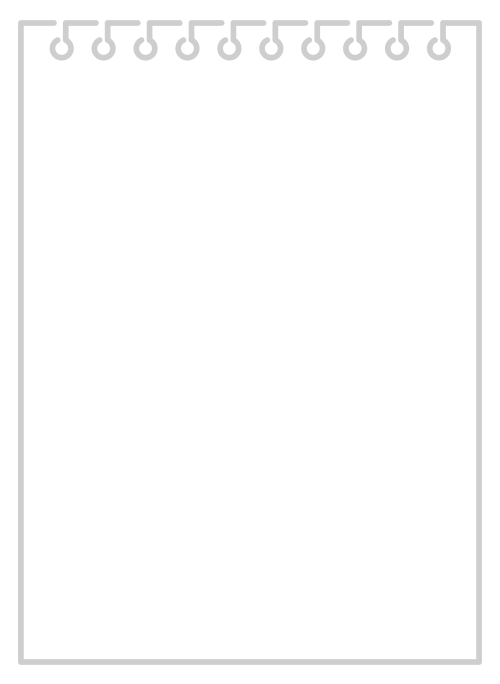データを消したのは私でもカヨラでもなく、両親だった。
私のためを思って、と言って正当化していることに腹が立った。
でも、なんとか理解しようと拳を強く握りしめる。
「…分かった」
「待って!」
背中を向けた私の腕を母が強く握る。
あの日帰ってこなかったことが本当にトラウマなのだろう。だから必死だった。
何事もなかったように、記憶を失った私が前を向けるように。
でも、と唇を噛み締める。
「広菜は死んだ」
「っ」
「でも、まだ、救えるかもしれないの」
カヨラの中には、苦しんでいる人がいる。
広菜が救おうとしていたものを救うことができるかもしれない。
まだ間に合う。
そう自分に言い聞かせた。
「…ごめんね、心配ばかりかけて。大丈夫だから、帰ってくるよ、絶対、次は何も忘れない」
母の手が緩まる。私は母の手を解いて玄関の戸をあけた。振り返ると泣きじゃくる母の顔で足が止まることが分かっていたので振り返らなかった。
外に出て、私は駆け出した。
公園までの道のりなんて分からない。
でも、広菜と私の家から遠くはないところに存在しているんだろう。
きっとどこかにあるはず。
汗をぬぐいながら、公園を見つけては絵や写真と見比べて次へと走る。
そして、
「…あった」
1時間ほどたってみつけたのは、人通りは少なく後ろには山が聳え立っているようなひっそりとした公園だった。
ブランコはピンク、黄色、青色が並んでいる。
その横には滑り台、砂場。
私は絵を持ち上げた。
ここで私と広菜はよく遊んだり、語り合ったりしていたんだろう。
もしかしたら、広菜の家で見つけたあの写真もここで私が撮ったものだったのかもしれない。
私は公園に入って、山へと続く境目のところへと向かった。
絵に描かれている陽炎の部分。
何もない。
ゆっくりと境目を歩いていけば、一度足を踏み出したところで違和感を感じ、足を止めて一歩後ろへ下がる。よく見れば、周りと比べて小さな山のように浮き出ている部分があった。
その場へしゃがみ、触ってみれば誰かが掘って何かを埋めたような跡がある。
まさかと思い、被せられている土を退けていく。
広菜が残したものが、ここにある。
そう思った。
他の場所より少しえぐれたところで見えたのは、ピンク色のブリキ缶だった。
被さっている土を手で払いのけて持ち上げる。
「…勝手にごめんね」
記憶は戻らない。過去の自分や広菜がこの場所を知っていたとしても、今の私はこの場所でこの箱を開けるのは初めてである。どこか罪悪感が生まれた。
ゆっくりと蓋を開ける。
中には折り畳まれた紙が何層にも積み重なっていた。
1番上にあるものは、色が褪せておらず比較的新しいものに見える。
束をすべて取り出して、底にあった薄黄色く変色している紙を開いた。
字は拙く、ひらがなが今より少し多いためおそらく中学生くらいの時に書かれたものだと思う。
ーーーもえかへ
1年に1度、こうやって手紙を書いてここにうめるようにしよう。
ずっと一緒にいるのにこういうのって変だけど、いつか大人になって、遠くにはなれたりしてお別れしちゃっても1年に1度だったら、ここでつながることができる。
おりひめとひこぼしみたいだね笑
いつもわたしを助けてくれてありがとう。
もえかはずっと大事な親友だよ。
ーーーーーーひろな
1年に1度でも繋がられるようになんて、ずっと一緒にいた親友なのにそんなことを考えるものなんだろうか。
広菜は、いつか自分が遠くに行ってしまうことをなんとなく分かっていたのかな。
なんともいえない悲しみが私を覆い尽くしていく。
手紙を元通りに折り曲げて、一つ上にあった紙を開いた。
私から広菜へあてた手紙だった。
ーーーひろなへ
なんだか、タイムカプセルみたいで1年に1度ここを開くのが楽しみになるね。
いっしょにこの場所に来れなくても、それぞれが書きたいとき、読みたいときに、ここに来よう。
そうすれば、わたしたちがばらばらになったとしてもどこかで会えるもんね!
ばらばらになることなんてぜったいにないけど!!
ひろな、お母さんに負けないで。
私もいっしょにたたかうからね
ーーーもえかより
幼い心がうつしだした本心は、ただお互いが大好きで離れることなんて考えられなくて、ずっとこの日々が続けばいいのにと願う毎日だった。
母親とうまくいっていなかった広菜からしてみれば、ここが救いだったのだろう。
原島先輩が言っていた美術室で、この公園での絵を描いている時に放った言葉、『過去を忘れないように』と、あれは、広菜がこの場所を必死に残していった紛れもない真実だった。
それぞれの手紙の下に日付が書いてあった。今から4年前、私たちは中学1年生。
それから、中学2年、3年と続き、この時まで私たちはずっと一緒にいて、毎日のように会っていたためか他愛もない1年間の楽しかった思い出などが綴られていた。
そして、高校1年生の冬。
それが最後の手紙となっている。
私が書いたものの下に、広菜が書いたものがある。
広菜の手紙を開いた。