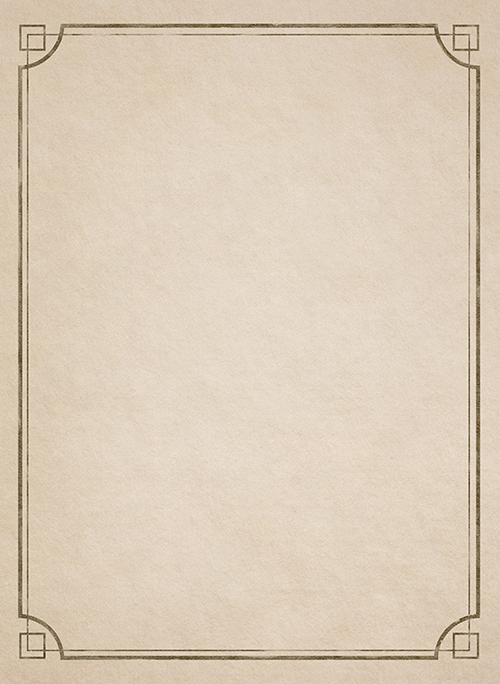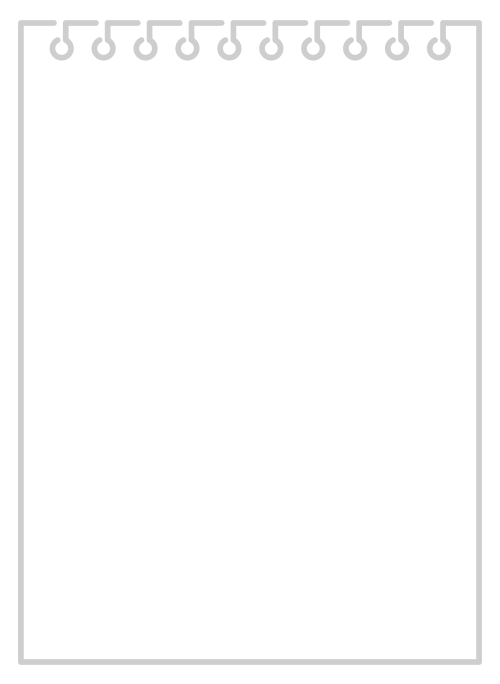絵と、手紙を綺麗に分けてテーブルの上に重なる。そしてその横に一枚の写真。
それから、私の手の平が泉さんのハンカチによって大袈裟に結ばれたあと、頼んだホットコーヒーとアイスココアが置かれた。
「これらは全部ひとつのロッカーの中に入っていたものです」
「誰のロッカーなのかは分からねえのか」
「友達はそこまでは教えてくれませんでしたが、何かあるのは確実です」
これ以上先は教えられないと線を引かれてしまったように思う。何もかもを曝け出してしまうことがまるで罪であるかのように「ごめんなさい」と謝った晴美の顔が忘れられない。
それに最後に自身に言い聞かせるように言った
ーーー「私のせいじゃない」
あれも気になる。
いったい、晴美のせいで誰がどうなったのか。
私は、そこに関係しているのだろうか。
私の失踪のことだとしたら身近な誰かに仕組まれたという可能性があるということだ。
晴美、真由、サラ、そして思い出せない友達。
『みつおひろな』
「絵の雰囲気が全て違ったり、手紙が入っていたりしているので1人の人間が使っていたロッカーではないと思うんです」
「…その中に、お前やみつおひろながいる可能性は」
「…あ、ります」
「歯切れ悪いな」
「…」
「…知りたくねえからか」
押し黙った私に、泉さんはコーヒーを飲んで「あつっ」と顔を顰めたあと気まずそうに頬杖をついた。
「私には、思い出せない友達が1人います」
「友達?」
「はい。だけど、顔も、声も、どんな性格の子だったのかも、すべて思い出せません」
「飛んでるの、失踪中の記憶だけじゃねえのかよ」
泉さんの言葉に小さく頷く。
言葉にしてしまえば、それが真実になってしまうようでこわかった。
すべてを繋げるために、可能性の話をしているのだと自分に言い聞かせる。
それでも、つらいものはつらい。
「もし、その友達が『みつおひろな』さんだとしたら」
夢に出てくる、あの少女だとしたら。
言葉に出そうとするが、荒く息がもれるだけで私は平気なフリを保つためにココアを飲んだ。
甘いそれが喉を伝ってからだにおさまっていく。
「…その思い出せない友達は、死んでることになるな」
「っ」
泉さんは真っ直ぐ私を見つめてそう言った。
そして先ほど端に置いてあるナプキンの大半を私の手のひらの傷に当てたことによってあと数枚しか残っていないそれを1枚取り出した。「ペン貸してくれ」と
私に手を差し出す。
私は少々困惑しながら鞄の中に入っているペンケースの中からボールペンを泉さんに渡した。
「お前、もうちょっと達観してやれよ」
「は?」
「思い出せねえ友達にたいして、情けなんてかけてんじゃねえ」
『立見萌香』『失踪者』『みつおひろな』『学校』『友達』と言葉を並べていき、円をつくった泉さん。
「今、この中の繋がりにお前の心情や失った記憶の辛さなんか必要ないだろ」
「…どういうことですか」
「失った自分の記憶は、他人の記憶だと思え。思い出すんじゃなくて、調べるんだ」
「調べる…?」
「みたいのは何が起こったかの真実で、こいつらの中になんの繋がりがあるのか、それだけを俺たちは追う。
じゃねえとお前の身が持たない」
そう言ってひとつひとつの言葉を丸で囲んでいく。
正直巻き込んだ側の言葉とは思えないけれど、一理あるとは思った。
達観して、自分の記憶を思い出すではなく、調べる。
ロッカーの中に眠っていたものたちをもう一度視界に入れた。
目を閉じて、息を吐く。
そして目を開いて私は、紙の上に手を置いた。
「まず、この紙たちが『みつおひろな』さんと過去の私のものだとしましょう」
「…ああ」
「私は絵は描けないので、このいくつかの手紙が私のだとします」
「字は一緒なのか」
「荒っぽい字の方は近いです」
「意外と字、きったねえのな」
「うるさいです」