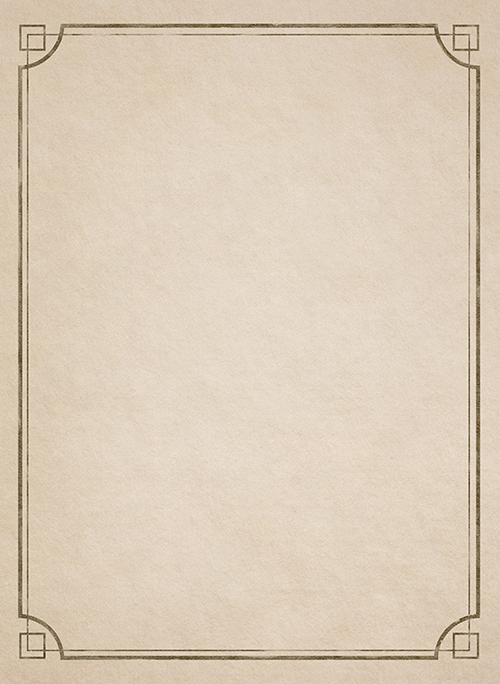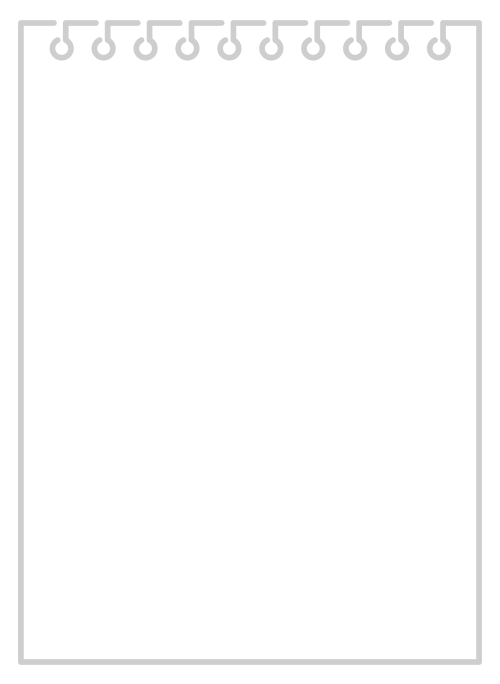「お友達にも話を聞きたかったんだけどな」
3人の背中姿を見送っていれば、隣に立っている男がそう言う。
私はため息をついて、その男に向き直った。
「何しにきたんですか、泉さん」
「この前の話の続き」
「前にも言いましたが、協力はできません」
私が歩き出せば、泉さんは追いかけるようにして私の横に並ぶ。
「話を聞けって」
「前聞きました。妹さんを探してるんですよね」
「そうだけど、今日は調べて欲しいことがあってきた」
足を止めれば、泉さんは私の正面に立った。
カーキ色パーカー。この前のようにフードを被っているが、無造作にそれを外す。
妹さんが20歳ならそれより上であることは確か。少し童顔で高校生くらいにも見えるが、眠れていないのか目の下には薄らとくまがある。
髪の毛は少し癖っ毛なのかところどころが横にはねていた。
少し長い前髪を鬱陶しそうにかきあげたあと、泉さんは険しい顔になって私を見つめる。
そしてゆっくりと口を開いた。
「失踪した女が死んだ」
「…え?」
「お前のようにしばらく行方をくらました後、死体が見つかってる」
ひゅっ、と喉がなった。
みっともなく恐怖心を抱いていた。『お前のように』と付け足したのは私を巻き込むための策略なのだということも理解していた。
私はまた逃げるように歩き始める。
しかし、泉さんはいくら歩みを早めようと着いてきた。
「死体は自殺として片付けられた」
「なんでそんなこと分かるんですか」
「友達が刑事だからな、情報を流してもらった」
「この前警察の手は借りないって」
「あいつは刑事としてじゃなく、友達として手を貸してくれてんだよ」
屁理屈だ。
「自殺ならそれでいいじゃないですか」
自らの口から溢れたそれ。
自殺なら、それでいい、
言葉というのは、吐き出されたあと回収することはできずにとどまり続ける。
自分自身の言葉なのに、黒くて、冷酷な人間だと、そう思った。
でも、即座に出たその言葉はきっと関わりたくないがゆえの本心なのだろう。
「てめえが死んでたかもしんねえんだぞ」
強く肩を掴まれて、強制的に足を止められた。
そして再度泉さんの方に向き直ってしまう。
「お前は運良く記憶喪失で帰ってきてのうのうと生きてるかもしれねえが、他の失踪者は死んでる」
「私には、関係ない」
「待てって」
手を払い歩き出そうしたがすぐに腕を掴まれた。私は自分でもどうしたらいいか分からない心情に駆られていた。
はやく、はやく、解放して、逃げたい。
「もう一度言う、お前は生きて帰ってきてるが、他の失踪者は、俺の妹は、殺されてるかもしれなくて、誰かは死んでんだよ!全部、繋がってるかもしれねえんだ」
「っ、離して」
「自分自身のために記憶に蓋して、思い出したくないって思ってんなら、人のために自分の記憶を探し出せよ。お前が鬼じゃねえならな」
自分勝手で、屁理屈で、傲慢な人。
泉さんはそう思われても知ったことかと『必死』なんだと思う。
私は自らの甲で目をこすった。こんな人の前で泣きたくないのに。
「…無茶苦茶なこと言いますね」
「どうとってもらってもかまわねえが、『お願い』をしてるだけだ」
「きついこと言って悪かった」とぎこちなく掴んでいた腕を離す。掴まれていたところがじわっと熱を帯びる。これは、どう足掻いても現実なんだ。
「…死んだ女、お前と同じ高校に通ってたらしい」
「同じ学校、ですか」
「ああ、失踪する前に退学してる」
「なんで」
「家族から行方不明届もだされてねえって話だし、学校やめて家出して自殺だろうって言われてるがどうも解せねえ。
学校を何故やめて、何故失踪したのか、どんなやつだったのか調べてきてほしい」
「でも…」
ふと、私の隣にいたかもしれない『友達』の存在が浮かんだ。何か、関係しているんだろうか。
「お前さ、記憶取り戻したくないって思ってるってことは、それくらい何かやばいことに巻き込まれてるって感じてるからじゃねえの」
「そ、れは」
「まっ、難しいことは考えずに、ひとまず俺に協力しろ。
連絡先はこの前渡した名刺に書いてあんだろ。協力できないんだったら、お前の記事書いて週刊誌に売りつけるからな『失踪後、記憶を失った女子高生』高く売れるかもな」
人差し指と親指で四角形をつくり、その枠の中に私を納めた泉さん。とことん最低だ。
「脅迫じゃん」と小さな声で呟く。
この人が、私の味方なのか敵なのかも分からないうちに私は無意識に言葉を放っていた。
「その、死んだ女の子の名前は」
そう言うと、泉さんは一歩私に近づく。
その唇がゆっくりと動いた。
「みつお、ひろな」