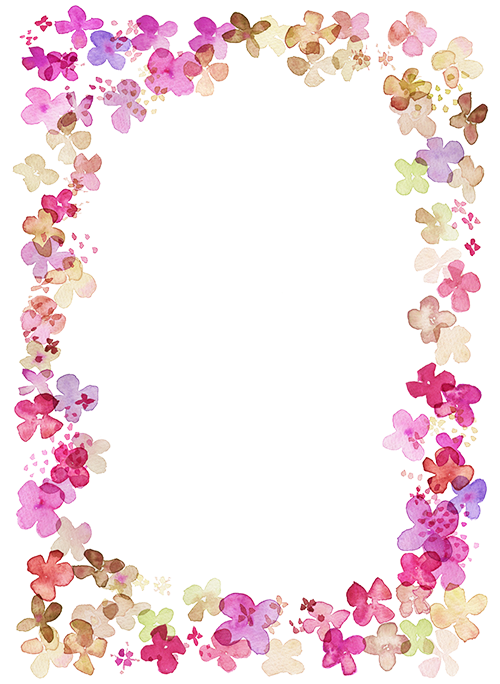それからデニスは一週間ほど体調を悪くしていて、その間は家の近くにだけ外出していた。
私はその間、デニスの代わりに大学に本を借りに行っていた。デニスは父の勤務する大学に籍を置いていて、冬の間学ぶことになっていた。
「借りてきたよ」
「ありがとう」
私がリュックに詰めて大学から持って帰ってきた本を渡すと、デニスはお礼を言ってそれを受け取った。
「すごいなぁ。細かい字がいっぱいで、私だったら眠くなっちゃいそう」
デニスはこの一週間、父の書斎の本を黙々と読んでいた。私が驚いて言うと、デニスは苦笑して返す。
「今日借りてきてもらったのは写真がほとんどだから、文字は大して重要じゃない。感覚で見るだけでも面白いと思うよ。智子も見る?」
「うん!」
私はうなずいて、彼の部屋のじゅうたんに座って横からのぞきこんだ。
デニスが来て一週間、こうして彼の部屋で本や絵を見せてもらうのは日常になっていた。デニスはさすが大学生で、私の知らない世界の話を流れるように説明してくれた。
デニスが大判の本を開くと、そこに現れたのは色鮮やかな版画だった。
「今日は浮世絵なんだね」
「ああ。よく大英博物館に見に行ったんだ」
デニスは少し憂い顔で、絵を見下ろしながら話す。
「浮世絵は明治期に大量に日本から流出してしまった。だから意外と、他国の方がまとまった数を見られることもあるんだ」
「そうなんだ。今同じものを作るのは難しいくらい、上手だよね」
じっくりみつめてみると、浮世絵はその精密さ、奇抜さに目を引かれる。昔の人はよく木彫りでここまで細かい線を自由自在に表現できたなと感心してしまう。
「デニスは絵画が好きなの?」
「とてもね」
デニスは睫毛を伏せて絵を見下ろしながら言った。
「絵画の中には、時間が残っているから」
「時間?」
「写真のように一瞬ではなく、それよりほんの少しだけ長い時間がある。なぜって、人が描いたものだから」
私はそう絵画に詳しくないけれど、そのデニスの言葉には共感を寄せた。
「そうかもしれない。一瞬、時間を忘れて見惚れちゃうときがあるもの」
「ああ」
デニスは絵画の写真を指でたどりながら言った。
「僕はその僅かな時間の流れを感じたいと、絵を見るたびに思う……」
そのとき、私の心の内側に痛みが走った。
彼には時間がない。絵が好きだというなら美術館に連れて行ってあげたいのに、体調が悪くなって外出もままならない。
私の表情が陰ったのをデニスは見て取ったのだろう。彼は話題を変えるように、別の本を開いて私の前に広げた。
「英国にはナショナルギャラリーという美術館があってね。この本にはその所蔵の絵が載っているんだ。智子に見てもらいたいと思って」
きっとそれらは、デニスにとっては見慣れたものなのだろう。けれど私のために紹介してくれるのがわかって、私は身を乗り出す。
「ダ・ヴィンチの『岩窟の聖母』、ベラスケスの『鏡のヴィーナス』……そしてゴッホの『ひまわり』」
その美術館には世界各国の名画が揃っているようだった。私はページをめくるごとに現れる、その色鮮やかな表現に目を奪われていた。
「すごい、すごい……すごい」
途中から私が手を出してページをめくっていた。そんなお行儀の悪い私を叱ることなく、デニスが横から見ている気配がしていた。
「あ、ごめん」
結局最後まで私が一人でページをめくってしまって、私は我に返って謝る。
デニスはそんな私に、首を横に振って少し笑ってくれた。
「まだ貸出期間はあるから。部屋に持って行ってもいいよ」
「ありがとう。うん、そうしたいな」
「……あと」
デニスは本の向こうに違う景色を見るような目をして言った。
「いつか英国に行って、実際に絵を見てくれるとうれしい」
「早速春休みに行っちゃおうかな」
私がわくわくして言うと、デニスはぷっと笑って答えた。
「君のアクティブさには憧れるよ」
「出たよ、英国人得意の皮肉。落ち着きがないって言いたいでしょ?」
私は冗談めいて笑い返して、デニスはそうじゃないよと苦笑していた。
私はその夜、もう一度デニスに借りた本を部屋でめくっていた。心の動くまま、楽しみでめくっていただけじゃない。
デニスと見ていたときに心に刺さった、一つの絵を探していた。
「……これだ」
衝撃的なシーンを見て、私はページをめくる手を止めた。その絵の名前をぽつりと告げる。
「『レディ・ジェーン・グレイの処刑』」
私はその絵の説明を指で辿りながら読み始めた。
それはイングランドの女王でありながら、即位してたった九日で処刑された女性の実在の悲劇を描いた絵なのだそうだ。
呆然と座りこむ侍女に、介添えをする聖職者、首切りの執行人がいて、そして白い衣装を身にまとった女王レディ・ジェーン・グレイが首切り台を探す。
それは何メートルも高さと幅がある大きな絵で、たぶん実際に見たら壁一面を覆うほどなのだろう。でもその絵の大きさ以上に、その瞬間のインパクトは強かった。
処刑なんて、現代日本では遠い出来事だ。海外でだって、今や斬首という方法を公に使っていいとは思えない。
でも過去には確かにあった。そう思うと、じわりとした恐怖感に襲われる。
私は侍女の表情を見た。生気がなくうずくまる彼女は、すべてを諦めているように見えた。聖職者も、首切りの執行人でさえ暗い表情をしているようにうかがえる。
だけどこれから処刑されるレディ・ジェーン・グレイだけはわからない。彼女は目隠しをしていて、表情が窺いにくくなっている。
当人の気持ちをはかるのは難しい。デニスと過ごして、それを強く感じるときがある。
デニスの表情には常に影がある。目の前の私を見ていないときもある。
けれど私が声をかけると、彼は途端にその影を覆って微笑してみせる。
――デニスの病気、本当に治らないの?
デニスが不在にしているとき、私は思わず母にたずねていた。
――日本で過ごしているより、大きな病院に入って治療したらいけないの? 少しでも長く生きられるように……今からだって、遅くはないんじゃないの?
デニスと過ごす日が一日、また一日と過ぎるたび、彼の慎ましやかで繊細なところが惜しかった。彼にはもっと強欲に、何が何でも生き延びようとしてほしかった。
――ともちゃん。デニス君がご家族と話し合って決めたことよ。
母はそう言って私をたしなめた。私は下を向いて、デニス本人には伝えられない言葉を飲みこんだ。
私は全然、デニスの余命を信じる気になれなかった。私には死にゆくデニスを想像できなかった。
でも今目にしている悲劇の絵を前にして、私はそこにデニスを重ねてしまう。
まるでレディ・ジェーン・グレイのように、デニスの目が見えないまま、その心がわからないまま、食い入るようにみつめてしまう。
夜のひととき、ひとり静寂の中で思う。
こんなに若くして人生を終えなければいけない。死に直面しなければならない。二度と自分の好きなことをすることができない。
……それは怖い。悲しい。悔しい。
デニスだってそう思っているに違いないと、絵をみつめながら思う。
私は彼に何ができるだろうかと考える。
私はデニスに、好き勝手にいろんなことを言っている。今日学校であったこと、喜んだり怒ったりしたことを、学校から帰ってくるたびにデニスに話して、デニスはただそれを聞いてくれている。
でも私は、デニスから自分の話を聞くことがとても少ない。彼がそうしたがらなかったし、私もどんな風にたずねたらいいのかまだわからない。
デニスは私より大人っぽくて、頭もいいし、立派な紳士なんだろう。けれどデニスだって人間なのだから、きっと色々な気持ちを持っている。
「いっぱい話そう。……いっぱい」
話して私に何ができるわけでもなくても、私は君に何かしたいから。
私は絵画の本をみつめながら、心に誓っていた。
私はその間、デニスの代わりに大学に本を借りに行っていた。デニスは父の勤務する大学に籍を置いていて、冬の間学ぶことになっていた。
「借りてきたよ」
「ありがとう」
私がリュックに詰めて大学から持って帰ってきた本を渡すと、デニスはお礼を言ってそれを受け取った。
「すごいなぁ。細かい字がいっぱいで、私だったら眠くなっちゃいそう」
デニスはこの一週間、父の書斎の本を黙々と読んでいた。私が驚いて言うと、デニスは苦笑して返す。
「今日借りてきてもらったのは写真がほとんどだから、文字は大して重要じゃない。感覚で見るだけでも面白いと思うよ。智子も見る?」
「うん!」
私はうなずいて、彼の部屋のじゅうたんに座って横からのぞきこんだ。
デニスが来て一週間、こうして彼の部屋で本や絵を見せてもらうのは日常になっていた。デニスはさすが大学生で、私の知らない世界の話を流れるように説明してくれた。
デニスが大判の本を開くと、そこに現れたのは色鮮やかな版画だった。
「今日は浮世絵なんだね」
「ああ。よく大英博物館に見に行ったんだ」
デニスは少し憂い顔で、絵を見下ろしながら話す。
「浮世絵は明治期に大量に日本から流出してしまった。だから意外と、他国の方がまとまった数を見られることもあるんだ」
「そうなんだ。今同じものを作るのは難しいくらい、上手だよね」
じっくりみつめてみると、浮世絵はその精密さ、奇抜さに目を引かれる。昔の人はよく木彫りでここまで細かい線を自由自在に表現できたなと感心してしまう。
「デニスは絵画が好きなの?」
「とてもね」
デニスは睫毛を伏せて絵を見下ろしながら言った。
「絵画の中には、時間が残っているから」
「時間?」
「写真のように一瞬ではなく、それよりほんの少しだけ長い時間がある。なぜって、人が描いたものだから」
私はそう絵画に詳しくないけれど、そのデニスの言葉には共感を寄せた。
「そうかもしれない。一瞬、時間を忘れて見惚れちゃうときがあるもの」
「ああ」
デニスは絵画の写真を指でたどりながら言った。
「僕はその僅かな時間の流れを感じたいと、絵を見るたびに思う……」
そのとき、私の心の内側に痛みが走った。
彼には時間がない。絵が好きだというなら美術館に連れて行ってあげたいのに、体調が悪くなって外出もままならない。
私の表情が陰ったのをデニスは見て取ったのだろう。彼は話題を変えるように、別の本を開いて私の前に広げた。
「英国にはナショナルギャラリーという美術館があってね。この本にはその所蔵の絵が載っているんだ。智子に見てもらいたいと思って」
きっとそれらは、デニスにとっては見慣れたものなのだろう。けれど私のために紹介してくれるのがわかって、私は身を乗り出す。
「ダ・ヴィンチの『岩窟の聖母』、ベラスケスの『鏡のヴィーナス』……そしてゴッホの『ひまわり』」
その美術館には世界各国の名画が揃っているようだった。私はページをめくるごとに現れる、その色鮮やかな表現に目を奪われていた。
「すごい、すごい……すごい」
途中から私が手を出してページをめくっていた。そんなお行儀の悪い私を叱ることなく、デニスが横から見ている気配がしていた。
「あ、ごめん」
結局最後まで私が一人でページをめくってしまって、私は我に返って謝る。
デニスはそんな私に、首を横に振って少し笑ってくれた。
「まだ貸出期間はあるから。部屋に持って行ってもいいよ」
「ありがとう。うん、そうしたいな」
「……あと」
デニスは本の向こうに違う景色を見るような目をして言った。
「いつか英国に行って、実際に絵を見てくれるとうれしい」
「早速春休みに行っちゃおうかな」
私がわくわくして言うと、デニスはぷっと笑って答えた。
「君のアクティブさには憧れるよ」
「出たよ、英国人得意の皮肉。落ち着きがないって言いたいでしょ?」
私は冗談めいて笑い返して、デニスはそうじゃないよと苦笑していた。
私はその夜、もう一度デニスに借りた本を部屋でめくっていた。心の動くまま、楽しみでめくっていただけじゃない。
デニスと見ていたときに心に刺さった、一つの絵を探していた。
「……これだ」
衝撃的なシーンを見て、私はページをめくる手を止めた。その絵の名前をぽつりと告げる。
「『レディ・ジェーン・グレイの処刑』」
私はその絵の説明を指で辿りながら読み始めた。
それはイングランドの女王でありながら、即位してたった九日で処刑された女性の実在の悲劇を描いた絵なのだそうだ。
呆然と座りこむ侍女に、介添えをする聖職者、首切りの執行人がいて、そして白い衣装を身にまとった女王レディ・ジェーン・グレイが首切り台を探す。
それは何メートルも高さと幅がある大きな絵で、たぶん実際に見たら壁一面を覆うほどなのだろう。でもその絵の大きさ以上に、その瞬間のインパクトは強かった。
処刑なんて、現代日本では遠い出来事だ。海外でだって、今や斬首という方法を公に使っていいとは思えない。
でも過去には確かにあった。そう思うと、じわりとした恐怖感に襲われる。
私は侍女の表情を見た。生気がなくうずくまる彼女は、すべてを諦めているように見えた。聖職者も、首切りの執行人でさえ暗い表情をしているようにうかがえる。
だけどこれから処刑されるレディ・ジェーン・グレイだけはわからない。彼女は目隠しをしていて、表情が窺いにくくなっている。
当人の気持ちをはかるのは難しい。デニスと過ごして、それを強く感じるときがある。
デニスの表情には常に影がある。目の前の私を見ていないときもある。
けれど私が声をかけると、彼は途端にその影を覆って微笑してみせる。
――デニスの病気、本当に治らないの?
デニスが不在にしているとき、私は思わず母にたずねていた。
――日本で過ごしているより、大きな病院に入って治療したらいけないの? 少しでも長く生きられるように……今からだって、遅くはないんじゃないの?
デニスと過ごす日が一日、また一日と過ぎるたび、彼の慎ましやかで繊細なところが惜しかった。彼にはもっと強欲に、何が何でも生き延びようとしてほしかった。
――ともちゃん。デニス君がご家族と話し合って決めたことよ。
母はそう言って私をたしなめた。私は下を向いて、デニス本人には伝えられない言葉を飲みこんだ。
私は全然、デニスの余命を信じる気になれなかった。私には死にゆくデニスを想像できなかった。
でも今目にしている悲劇の絵を前にして、私はそこにデニスを重ねてしまう。
まるでレディ・ジェーン・グレイのように、デニスの目が見えないまま、その心がわからないまま、食い入るようにみつめてしまう。
夜のひととき、ひとり静寂の中で思う。
こんなに若くして人生を終えなければいけない。死に直面しなければならない。二度と自分の好きなことをすることができない。
……それは怖い。悲しい。悔しい。
デニスだってそう思っているに違いないと、絵をみつめながら思う。
私は彼に何ができるだろうかと考える。
私はデニスに、好き勝手にいろんなことを言っている。今日学校であったこと、喜んだり怒ったりしたことを、学校から帰ってくるたびにデニスに話して、デニスはただそれを聞いてくれている。
でも私は、デニスから自分の話を聞くことがとても少ない。彼がそうしたがらなかったし、私もどんな風にたずねたらいいのかまだわからない。
デニスは私より大人っぽくて、頭もいいし、立派な紳士なんだろう。けれどデニスだって人間なのだから、きっと色々な気持ちを持っている。
「いっぱい話そう。……いっぱい」
話して私に何ができるわけでもなくても、私は君に何かしたいから。
私は絵画の本をみつめながら、心に誓っていた。