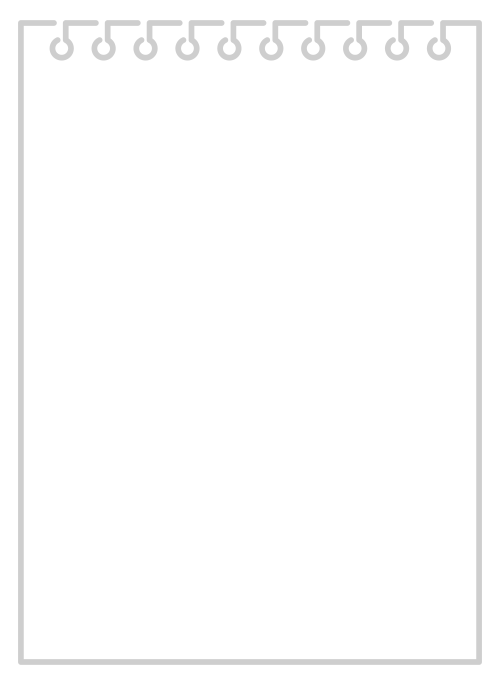「ここ」
学校から徒歩10分ほどでついた場所は老人ホームであった。
「俺、ここに入っていいのか」
「いんじゃね?孫の俺が連れてきてんだから ま、どうせ覚えてねぇけど」
そう言って音代より幾分か先に歩いていく九条を音代は眺める。
音楽で記憶が蘇ることはある。その言葉に嘘はない。だが、絶対ではない。
潜在的な記憶を呼び起こすのは、容易なことではないのに。
「先生、早く来いよ」
ポケットに手を突っ込んだまま振り返った九条。音代は「ああ」と返事をして一歩足を踏み出す。
中に入れば綺麗なロビーが広がり、九条が慣れたように受付に自分の名前と祖母との関係を伝えている。音代のことは、馬鹿正直に自分の高校の音楽の先生だと紹介した。
少し不思議そうに音代の方を見た受付の男に音代は軽く会釈をして辺りを見渡す。
ロビーの奥には大きめの部屋が広がっており、老人たちがテーブルを囲んで談笑をしていたり、テレビをみていたりなどそれぞれが好きなことをしている。
そして、部屋の奥には電子ピアノが置いてあった。
「ばあちゃん、そこの大きい部屋にいるって」
「そうか」
九条は少し雑に音代の前にスリッパを置きぶっきらぼうに「ほらよ」と言い放った。九条は何度もここにきている。
祖母に忘れられているのに、あまりつらくなさそうだと音代は思った。
だいたいの人間は、どうしようもないと思ったら取り戻そうとするのではなく理解し先に進もうとする。
ただ、九条は取り戻すことに固執しているような気がした。
ーーー態度をみているうちは、そこまで辛そうには見えないが。
「ばあちゃん」
九条がそう呼べば、数人が振り向く。そして「また来たのね」と笑顔になった。
ーーー1人を除いて。
「悪党が来たわ」
眉を顰めて九条にそう言い放ったその人は、音代がみた写真のあのおしとやかそうな祖母である。
「あら、また言ってるわ里美さん 悪党じゃなくて凪くんよ!あなたの孫じゃない」
「嘘だわ、悪党よ 私を斬り殺しにきたんだわ」
トランプをしている途中だったのか、数人が自分の持っているカードをテーブルに置き、九条の祖母を宥める。
忘れられている、より、大変なことになっているではないか、と九条をみれば、九条はなんとも言えない変な笑みを浮かべ自分の髪の毛をいじった。
「俺、こんな感じだからさ、昔みた任侠映画のやつに似てるんだと」
そう言ってため息混じりに言葉を紡ぐ九条。
「なんで映画は覚えてて、俺のこと覚えてねぇんだよって話だよなぁ」
九条に気を遣って、祖母以外の老人たちが撤収をはじめる。「ごゆっくり」とにこやかに九条に会釈をした老人に九条は「うっす」と軽く頭を下げた。
見た目や口調で勝手に、不良だ素行が悪そうだと決めつけていた自分自身を音代は少し恥じた。自分も外見などで判断されることにうんざりしていたのに。
九条は祖母の隣に座り、音代は2人の正面に座った。
「ばあちゃん、今日は音楽の先生連れてきた」
「うるさい、はやく帰ってよ悪党め」
「そんなこと言うなよ、俺ばあちゃんの孫だぜ」
祖母からの拒否に負けじと話しかける九条。心配そうに少し先の方でみている介護士に音代は気づく。
ーー何かあったらすぐに駆けつけられるようにしているのだろう。
このやりとりが何度も何度も繰り返されているのだろうと音代は思った。そして九条は何度も祖母から「悪党」だと罵られている。
「ばあちゃんさ、好きな曲とかねぇの?音代先生にピアノ弾いてもらおうぜ」
唐突にむけられた期待に音代は「え」と短く声を上げた。
突然言われてもどうしようもない。音代はこの現状に把握することに精一杯である。ただ、弾けと言われれば部屋の片隅にピアノがあったので手助けしてやりたいとは思っていたが。
「そんなのはいいわ、帰って」
「そんなこと言うなって、俺さ、タンバリン持ってきた時に思い出したんだよ、俺が小さい頃歌ってた曲」
音代は2人のやりとりを黙って見ていた。
九条はひたすら必死で、祖母はただただ不快そうに九条をみている。
混じり合わない。2人の気持ちはつながっていない。
「ホッピーラッキーシュッキーって覚えてるか、ばあちゃん
小さい頃、タンバリン叩きながらよく一緒に歌っただろ、一緒に歌おうぜあの時みたいに
みんなのにんきもの あかいおはなのホッピー いつもげんきなきいろいおはなの」
「うるさいって言ってるでしょ!!」
九条が手のひらをリズムに合わせて叩いていた。小さい頃、タンバリンでやっていたように。
その手を祖母が怒りの感情のままにはたく。
祖母の大きな声が部屋に響き渡り、見守っていた介護士が走ってきた。
九条は、困惑と焦りと、そして絶望の瞳で祖母を見つめる。
「里美さん、自分の部屋に戻りましょう」
介護士が祖母の腕を優しく掴んだが、「言われなくても戻るわ」と振り払い立ち上がる。そして九条を上から睨みつけた。
「そんな曲私は知らないわ」
吐き捨てるように放った言葉。
唇を噛み締めた九条に、祖母は顔を背け歩き出した。
九条は何かに堪えるように拳をぎゅっと握った。
「いつも来てもらってるのに本当にごめんなさい九条さん 本人も分からないことが増えてきて混乱してて 悪気があるわけじゃないんです」
介護士が九条に気を遣ってそう言葉をかけた。
九条にも分かっていた。これは誰のせいでもない。だが、いつもいつも何かを期待して今日こそは自分のことを思い出すんじゃないかと会いに来ているこの日々がすべて無駄なんじゃないかとそう思い始めてしまっていた。
「分かってます」
「九条さん」
「今日は帰ります 音代先生も付き合わせてごめんな」
立ち上がった九条は、へらりと音代に笑ってみせた。
音代は気づいた。おそらく、九条は何も平気ではない。大切な人に忘れられる苦しみに向き合うのには勇気がいる。彼は、必死に平気なふりをしているのだ。そうでもしないと忘れていく祖母から逃げ出してしまうから。
「帰ろうぜ、先生」
「ああ」
やるせない気持ちを2人は抱えながらそこを出た。とぼとぼと来た道を歩きながら、九条は長いため息をもらした。
「俺からしたら、あの曲思い出だったんだけどな」
「ホッピーラッキーシュッキー、か」
「そうそう、小さい頃ずっとばあちゃんと歌ってて きいたら思い出すかと思ったんだけどよ」
泣き出しそうな顔を一瞬して、誤魔化すように笑う九条。「無理だったわ」と消え入りそうな声をだす。
音代もこの曲が九条にとって大事な曲ということは知っていた。
音代が音楽の授業の時に生徒たちに書かせた音楽の記憶の用紙に、九条は『ホッピーラッキーシュッキー』のことを書いていたからだ。
ホッピーとラッキーとシュッキーというそれぞれ個性のあるキャラクターが主人公のアニメの曲だったらしい。
祖母と何度も何度も歌った曲と九条の用紙には記してあった。
「九条のばあちゃんは、どんな曲を聴いて育ったんだろうな」
「え?」
「大切な人だからこそ、その人が聴いていた音楽も知りたいと思わないか」
音代はオレンジ色に染まっている空を見上げて、目を細めた。
九条は音代の言葉にきゅっと胸が痛くなった。自身の胸元をくしゃりと掴む。
「俺、ずっと自分のことを思い出して欲しいってことばっかだったわ」
足を止めてそう言った九条は俯いていた顔をあげる。
「俺にとっては、生まれた時からばあちゃんはばあちゃんだったけどさ、ばあちゃんにも10代の頃とか、思春期とかさ、そういうのあったんだよな」
「そうだな」
「今の高校生とかみたいに、いろんな音楽を聴いて歌って、青春したりしてたんかな」
「そうかもな」
「なんかすげぇな」
次は変な取り繕った笑顔ではなく屈託のない笑みを浮かべた九条。
九条にとって祖母は生まれた頃から祖母という存在で確立されていて、だからこそそんな祖母にも若い頃があったということに対して不思議な感覚になっているのだろう。
その感覚を「すげぇな」と笑える少年さに音代はじんわりと胸があたたかくなった。
「ありがとよ、先生。今日は付き合ってくれて」
「半ば強制的に連れてこられたがな」
「俺、音代先生のことちょっと勘違いしてたわ。ツラがいいだけの音楽うんちく男とか思ってごめん」
そこは正直に言わなくていいのに。と音代は思ったが、勘違いをしていたのはお互い様ということで何も文句は言わなかった。