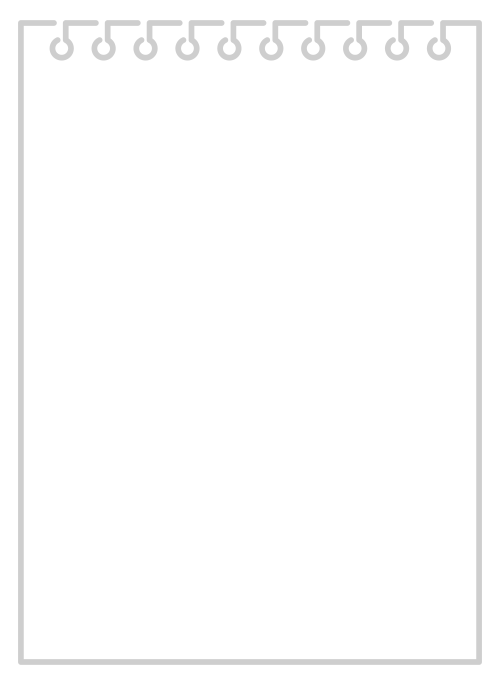ーーーー
音代のデスクに、椅子にのったまま少し心配そうにやってきたのは坂木である。
「なぜかわたし追い出されたんですが」
「なんですか急に」
怪訝な顔で坂木をみる音代。坂木は口を尖らせ足をぷらぷらさせる。
その足が音代の椅子にコツコツと当たって音代はより顔を顰めた。
「文化祭の曲決める時に大事な話あるからって九条くんに言われて追い出されたんです」
「へえ」
「まさか、『みんなで文化祭ボイコットしようぜ』的なそういうことでしょうか、やっぱり様子を」
立ち上がった坂木。音代は咄嗟にその腕を握った。
坂木は今にも飛び出していきそうなからだが引き戻され、後ろに転けそうになりながら「なんですか」と困惑の声を出す。
「いてください」
「え?」
「ここにいてください」
音代の真剣な表情に坂木は思わず目を逸らす。こういう時に音代の端正な顔や声の雰囲気はずるいと思った。おずおずと椅子に再び腰を下ろした坂木。
「音代先生、もしかして何か知ってるんですか」
「いいえ」
「嘘だ、目逸らしましたね」
そう言われ、音代はむっとなり坂木の方をみて再度「いいえ」と言い放つ。次は坂木がばっと目を逸らした。そのあからさまな態度に音代は体ごと坂木に向き直る。
「今のは腹が立ちますね」
「な、なんでですか」
「そちらが吹っかけてきたくせに、あからさまに目を逸らしました。俺の顔に何かついてますか」
「いえ、何も」
「ムカつくな」
音代は坂木の両頬を片手で掴み、強制的に顔を上げさせた。
坂木の眉が八の字になる。そしてその音代の腕をつかんだ坂木。
「シェクハラでふよ」
「すいません、ムカついたもので」
ぱ、と手を離せば坂木は両頬を撫でながら音代を睨む。
「音代先生はもう少し自覚した方がいいと思います」
「何をですか」
「よく女子生徒が騒いでます。『音代先生は顔だけはいい』って」
「その微妙に貶す感じなんとかなりませんか」
「まあ、事実なんでねえ、なんとも」
首を傾げる坂木。そのわざとらしさに音代は眉を顰めながら正面を向き頬杖をついた。
顔のことについては昔から「整っている」だの「イケメン」などとうんざりするほど言われてきていたため「言われ慣れている」と嫌味にも程がある返しをしてしまうことが多々ある。だが確かに事実なので仕方がない。
「音代先生のお父さんもイケメンでしたね」
ぱ、と驚いたように坂木の方をみた音代。
「なぜ父を知ってる」
「最近、兼山先生と久しぶりに会って教えてもらいました。ほら、音代先生の前にここで音楽の先生してた先生で、って知ってますよね。
わたし知らなかったです音代先生が兼山先生とお知り合いだったなんて」
なんてことない坂木の言葉だったが音代は少しの困惑を悟られないように「まあ」と小さな声で返事をする。
「ここも兼山先生が紹介したって」
「ああ」
「どういうお知り合いかはちゃんと聞けてないんですが、あれですか?大学の先輩とか後輩とか、あ、それか音楽関係で何か縁があったとかですか?」
悪気のない坂木の質問責めに音代は再び坂木の頬を片手で挟みたい気持ちに苛まれたがまたセクハラと訴えられてしまうため、ぐっと堪えた。
「俺に音楽を教えてくれた人の奥さんだ」
さらりとそう説明すれば、坂木が両手を叩く。
「なるほど、割とどっぷりな関係ですね」
「言い方」
こいつは本当に国語を教えている教師なのかと疑いたくなるほどの語彙力に思わずため息をついた音代。
坂木はヘラヘラと笑いながら「すいません」と軽い謝罪をする。
「でも、兼山先生言ってました。音代先生がどんなかたちであれ音楽を続けてくれて嬉しいって」
「っ」
ずっと避けていた。
あの時の輝きの中渦巻いていた人たちに会うこと。思い出、闇に触れることから。
今も、である。だがどうやっても自分は音楽をやりたいと本能的に思ってしまう。離れたいのに、やめたいのに、もう、誰も傷つけたくないのにそれでも音代を音楽という沼に沈めていくのだ。
過去からは逃げているが、今目の前に立ち塞がっている闇に立ち向かうことはできる。
「坂木先生」
「なんですか」
「2年1組、おそらく文化祭の合唱優勝しますよ」
「え!ほんとですか!なんでですか」
自分のクラスが認められることは坂木にとってこの上ない喜びである。坂木は期待の眼差しで音代に近寄った。
音代はニヒリと笑った。
「俺が全面的に協力してやるからな」
次は間違えないように。
音楽で人を救うことはできる。