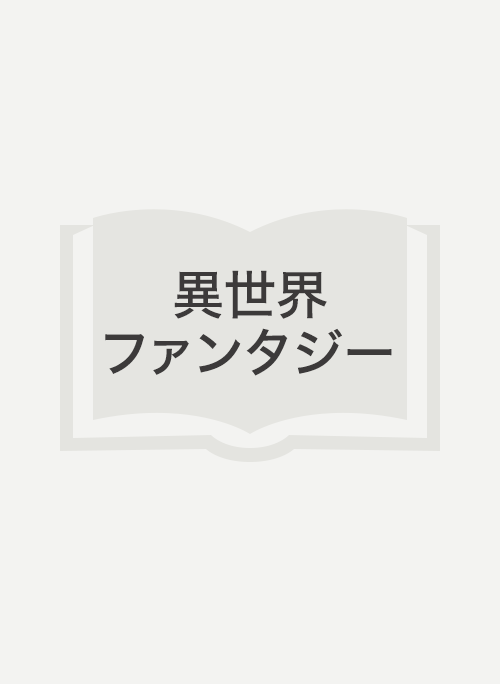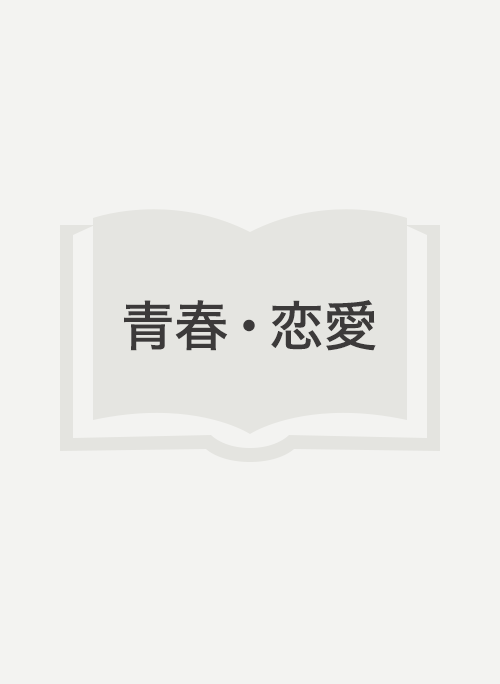◇
その夜、新久郎は城から帰宅した父小田崎規武に呼ばれた。
「座れ」
床の間を背にした父が息子の顔を見るなり畳を指さす。
新久郎は素直に前に進み出て正座をした。
「おまえ、学問所に行かなかったそうだな。方正斎先生から使いの者が来ておったそうではないか」
あれからすぐに走って行ったものの、講義はすでに終わっていたのだった。
父が静かに語り出す。
「我がご先祖は将軍家の御前において、仙台伊達家中にこの人ありと言われた片桐越中斎殿と算術仕合を行い、それを見事に打ち負かし、初代藩主規頼公の覚えめでたく、『規』の文字を拝領した名門であるぞ。『規』とはすなわち算術に欠かせぬ道具。我が家系にふさわしき文字であろう」
「はい、肝に銘じております」
実際、この話はもう何度も聞かされた、我が家に伝わる唯一の自慢話なのだ。
母の前で父の物真似をしてみせられるくらい聞き飽きている。
「それなのに、なんだ。おまえは学問を軽んじておるのか」
「いえ、決してそのような」
「黙れ!」と、一喝して父が立ち上がる。「言い訳など見苦しいわっ! 馬鹿者が!」
新久郎はただただ畳に額を擦り付けて怒りの嵐が吹き過ぎるのを待つしかなかった。
「我が小田崎家において、学問とは武芸に勝る技でなければならぬ」
それが向いてないのだから、新久郎にとっては苦痛でしかなかった。
座り直した父がまた静かに告げた。
「わしは明日から当分の間、領内の巡察へ出る。これまでに学んだことをよく習得しておくのだぞ」
「はい、申し訳ありませんでした、父上。精進いたします」
「うむ。それでこそ我が小田崎家の跡取りである。その気持ち、忘れるでないぞ」
やれやれ、明日からは怠けられるぞ、と心の中で舌を出す新久郎であった。
と、そこへ「ごめんくださいまし」と、玄関に来客があるようだった。
応対した母がやってきて、ふすまを開けた。
「あなた。お客様です」
「ほう、こんな時分に。どなたかな」
通されたのは、地味ではあるが身なりのきちんとした町人の男だった。
「夜分恐れ入ります。大黒町で大工の棟梁をしております惣兵衛と申します」
「何用であるか」
「実は、本日、わたくしどもの『娘』がこちらの若様に大変お世話になったそうでございまして」
「なんと、新久郎が?」
息子を褒められた父はさっきまでの不機嫌などどこへ行ったか、手で頬をさすりながら視線を宙へさまよわせていた。