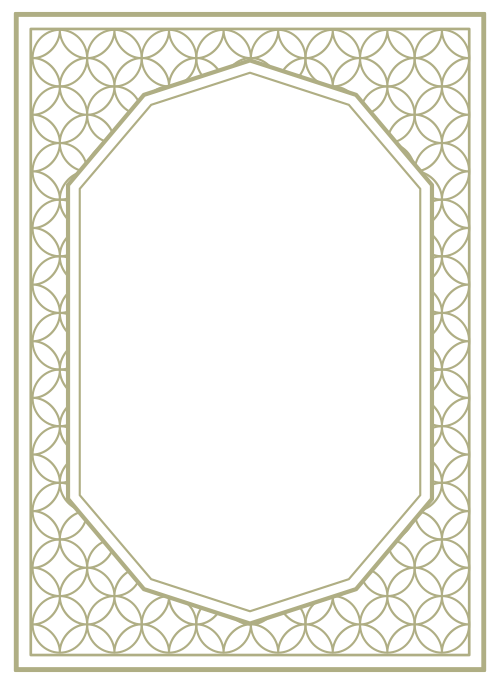あまりにも衝撃的で、鈴花はしばらくの間泣くこと以外できなかった。
スマホを操作する気力もなくなり、何度も何度もしゃくりあげながら涙を流し、そのうちに流す涙もなくなってしまった。
何度も手の中で、スマホが震えていた。おそらくは美里を初めとする観劇仲間が、心配のメッセージを送ってきてくれているのだろう。
鈴花だって逆の立場なら、友人を気遣うメッセージを送ったはずだ。
推しを推していれば、いずれ見たくないニュースを見る日も来るだろうと覚悟はしていた。不祥事、スキャンダル、はたまた引退宣言など、ファンとして見たくない情報はいろいろある。
だが、そのどれも命に別状がないだけまだマシだったのだと思い知らされた。
「……鈴花、とりあえず風呂に入ってこぬか? 身を清めれば、少しは心も軽くなるじゃろうて」
床にへたりこんだ鈴花のすぐそばまでやってきて、ジン様が言った。美しい顔に覗き込まれて、その顔が大好きな推しと同じものだと思うと胸が苦しくなって、鈴花はぐずるみたいに首を振った。
「……今そんな気分じゃないの」
「風呂は、気分で入るわけではなかろう。それに、可愛い顔が汚れておるぞ」
「……は、入ってくる」
泣きじゃくったせいで顔が涙と鼻水だらけなのに気がつき、鈴花はあわててバスルームに向かった。
本当はお風呂に入る気力なんてないのだが、ジン様に汚い顔を晒し続けるのも嫌だった。
のろのろと服を脱ぎ、シャワーを浴びると、温かなお湯の心地よさに少し体が楽になるのがわかった。それと同時に泣きすぎて頭がひどくぼんやり重いことも、喉も体も乾いていることにも気がついた。
シャワーを浴びて髪を乾かして戻ると、ジン様が今度は冷蔵庫を指差す。何か飲まなくてはと思っていたから、ミネラルウォーターを飲みながらスマホをチェックした。
「……ドラマはすべて撮り終えてるから、最終話まで予定通り放送されるんだって。舞台については、今後詳細をアナウンスするって」
『シェアハウス鍋奉行』の公式ツイッターを見に行くと、高瀬臣の事故を受けてのアナウンスが出ていた。事故の報道から数時間であれば、まだ詳しいことを決定できないのだろう。
楽しみにしている作品だから、今後のことは当然気になる。だが、本当に気になるのはそういったことではない。
情報がほしくてネットを見ているのだが、同じような見出しのニュースが乱立しているだけだ。所属事務所はまだ何もアナウンスしていなかった。
「今はまだ、何もわからぬ状況じゃろうて。ファンであるそなたたちを心配させぬよう、知らせられぬこともあるだろうしな」
取り憑かれたようにスマホを手放せずにいる鈴花に、なだめるようにジン様は言った。
言われていることはわかるが、それでも情報を追うのをやめられない。想定している最悪の事態が、あくまでただの考えすぎだと確かめたくて。
しかし、恐れていたことが文字となって鈴花の目に飛び込んできた。
「うそ……」
「どうした?」
「……臣くん、意識が戻らないんだって」
『人気俳優・高瀬臣、搬送先の病院で意識戻らず』という見出しのニュースを表示したスマホをジン様に差し出すと、彼がそれに見入っているのがわかった。
だが、ジン様は何も言わず、鈴花に目を向けた。
「ワシのお下がりの塩むすびを、雑炊にするといい。今夜はあたたかいものをおあがり。それを食べてから、ぐっすり眠るのじゃ」
触れられはしなくても、ジン様が頭を撫でようとしてくれているのがわかった。優しい眼差しを向けてくれてはいるが、うっすらと眉間に寄る皺は、鈴花を心配しているからだろう。
「……わかった」
推しが心配なときに推しの顔で心配されれば、言うことを聞くしかない。
本当は食欲などなかったが、鈴花はお下がりのおにぎりを昆布茶と梅を入れたお湯の中で煮て、お茶漬けのようにして食べた。
布団に入るまで絶対に見張っているという気合いのようなものをジン様から感じ、食べてすぐに横になった。スマホは、かじりつかないようにと少し離れたところに置いたことで、明かりを落とすと自然と眠たくなった。
「そなたまで弱ってしまっては、いかんからな。ゆっくりおやすみ」
あやすようなジン様の声を聞くと、鈴花はスッと眠りに落ちた。そして夢も見ることなく、朝まで眠った。
そして翌朝。
目覚めて真っ先にしたのは、やはりスマホを見ることだった。
だが、そこにほしい情報はなく、ニュースの見出しは代わり映えしなかった。
もしかしたら、一晩眠れば事態が好転しているかもしれない。大怪我なのは変わらなくても目が覚めているかもしれない。
そんな期待を打ち砕かれ、どうしていいかわからず、鈴花の目からはポロリと涙がこぼれた。
「……結局、どれだけ好きでも、私が臣くんにしてあげられることなんてないんだ……」
一晩経って冷静になった鈴花が得たのは、こんなときにファンが推しにしてあげられることなんて何もないという悟りだけだった。
何かできると思い上がっていたわけではないが、その事実は鈴花を打ちのめした。
「果たして、そうかの?」
布団の上で呆然とする鈴花に、ジン様が声をかけた。
高瀬臣グッズが大量に並ぶ祭壇の横で、高瀬臣にそっくりの顔で。
「こんなときに、そなたにしかできぬことがあるだろう?」
ジン様は諭すように、優しい口調で言う。だが、そんなことを言われても鈴花は希望を見い出せなかった。
「ないよ。何も……」
「鈴花、ワシに願え」
「え……?」
「こんなときにワシに願わずして、いつ願うのじゃ? ワシが何のために存在すると思っておるのか」
何かの冗談かと思ったが、ジン様の表情は真剣だった。
「ワシは、鈴花の高瀬臣に向けられる熱心な思いによって眠りから覚めた。これまで、何度もそなたの願いを叶えてきた。そんなワシとそなたが今、形にすべき願いなどひとつしかなかろう?」
「それは……」
ジン様の言っていることをようやく理解すると、鈴花は途端に不安になった。ジン様の覚悟を決めたような表情が、さらに不安をあおる。
「……ジン様、そんな顔してそんなこと言わないで」
「何を願えばいいか、わかったようだな」
「やだよ。……チケット運とか、そういう話じゃないんだよ? 無理するのわかってて、願い事なんかできないよ」
「無理もするさ。高瀬臣を救えねば、どのみちワシは存在できなくなる。ワシは自分の存在のために、あやつを助けると言っておるのじゃ」
ジン様の言葉を聞いて、やはりそういうことなのかと鈴花は納得した。
彼は、自分の力を使って高瀬臣を助けると言っているのだ。それがどれだけ無謀で大変なことなのか、鈴花にだってわかる。
「さあ、願え鈴花」
「できないよ! おにぎりで叶えていい願いじゃない!」
鈴花は子供の駄々のようにイヤイヤと首を振って抵抗した。
ジン様の顔を見れば、彼が自分の考えを翻さないことはわかっていた。というよりも、鈴花が口に出さなくても何を願っているのか知っているのだ。鈴花のことは何でもわかるから、ラジオにあんなメッセージを勝手に送ることができたのだから。
「願うのじゃ、鈴花。言葉にせずともそなたの思いは手に取るようにわかるが、口に出すことでその思いはより強いものとなる。高瀬臣を救いたいのじゃろう? それなら、ワシに願え。――ワシは、そなたの神じゃ」
どこまでも優しい笑顔で言われて、鈴花はこらえていた涙がまた目から溢れ出た。
当然、救いたい気持ちはある。目覚めてほしいに決まっている。
だが、その願いのためにジン様の存在が犠牲になるなんて嫌だった。
それでも、願わなくてはならないことも理解した。
それは、ジン様が鈴花の神様だから。神様が叶えると決めたのなら、その願いを口にするのが自分の役目なのだとわかった。
「……ジン様、お願い。臣くんを助けて。また元気に舞台に立てるようにしてあげて」
「うむ、わかった」
鈴花が振り絞るようにして言うと、ジン様は笑顔で頷いた。
そこに憂いも翳りもない。澄み切って明るい笑顔だった。
「それじゃ、ちょいと行ってくるの」
ジン様はそう言って、ひらりと手を振って祭壇の奥の壁に消えていった。
まるで朝の光にとけていったみたいに、見えなくなってしまった。
「……ちょいと行ってくるって、何それ」
散歩にでも出かけるような軽い別れの言葉に、鈴花は笑った。
そしてこの数カ月一緒に暮らしたにぎやかな神様の不在に、少しの間泣いた。
それからほどなくして、高瀬臣の意識が戻ったというニュースがネットを騒がせた。
そして数日経つと意識が戻っただけではなく、驚異のスピードで回復していることも報じられた。
最初はマネージャーによる代筆でのツイートだったが、事故の報道から十日も経つと腕と足を吊った状態の写真を投稿していたし、さらに数日経つとリハビリしている姿を動画で披露していた。
それらの行動から、意識不明の重体だったのに後遺症も麻痺も残らないらしいと、関係内外からも注目されていた。
ファンたちからは「臣くん、運動神経いいから受け身がうまかったんじゃない?」とか「日頃から体鍛えてたからかな」などという声があがっていたが、これが〝奇跡の回復〟などではないことを知っている。
偶然起きた幸運ではなく、優しくて親切な神が起こした神業なのだと、鈴花だけがわかっている。
だから、大好きな推しがみるみる回復して松葉杖で舞台に立つとわかって安心しても、手放しに喜ぶことはできなかった。
高瀬臣が鈴花の人生に欠かせない存在であるのと同じように、ジン様も、もうなくてはならない存在なのだ。
というより、あの優しい神様に願いを叶えてもらってそれっきりなんて嫌で、どうにかして取り戻せないかとか、そんなことばかり考えてしまっている。
だから鈴花は、せっせとジン様の絵を描いてネットにアップした。
ジン様の魅力を少しでもたくさんの人に知ってもらいたいと、いろんな表情やポーズのイラストを描いた。
それが功を奏したのか、ちょっとずつジン様のファンアートが投稿されるようになり、ドット絵で動くジン様を作ってくれる人や、3Dモデルを作ってくれる人まで現れた。どこかの企業から「Vtuberとしてデビューしませんか」という話まで持ちかけられるようになった。
だが、そんなふうに人気が出ても、たくさんの人から愛されるようになっても、ジン様が姿を表すことはなかった。
「もう、何よ! あんな軽く出ていったらさ、すぐに帰ってくるのかと思っちゃうじゃん……」
鈴花は、消えてしまう前のジン様の「ちょいと行ってくるの」という言葉だけを頼りに彼の不在の日々を過ごしてきた。
だが、一向に戻ってくる気配がないとわかると、時々無性に寂しくなって気持ちが荒んでしまうのだ。
だから今夜は、ちょっとした暴挙に出ることにした。
「帰ってきたら一緒に食べようと思ってたけど、なかなか帰ってこないから勝手に食べちゃうことにした!」
そう言って鈴花が食卓に用意したのは、カセットコンロと土鍋と野菜の数々とカニだ。カニ鍋にしようと奮発して1Kgのカニを通販で買ったのだ。
ボーナスが出たときに、ふと頭をよぎったのがカニ鍋を食べることだった。だから、ジン様が食べたがっていたなと思いだして、迷わず注文した。
冷凍された状態で届いたから、帰ってくるまで待っていようと思ってずっと冷凍庫に入れておいた。
だが、いくら待っても帰ってこないし、クリスマスは近づいてきているし、このままでは正月にひとりでつつくはめになるかもしれないと、慌てて今夜カニ鍋を決行することにしたのだ。
「はぁ、おいしそう。せめて気分だけでも味わってもらおう……」
そう言って鈴花は、小ロットで制作したジン様のアクリルスタンドをテーブルに置いた。自分だけが楽しめればいいと工場に発注したものだったが、意外に需要があるようで、今度増産することが決まっている。動きのある全身イラストを使用しているため、なかなか出来がよく、存在感もばっちりだ。
だが、それだけにさらに寂しさが増した。
具材と出汁を火にかけて待てば、ぐつぐつという音といい匂いが食欲をそそる。それなのに、鈴花の気分は全然盛り上がらなかった。
「うわぁ、カニ、食べ方わからん。うち、水炊き派だから子供のときからほとんどカニ鍋なんて食べたことないんだよぉ……」
食べ頃になっていざカニを手にしたものの、不慣れな鈴花はカニの硬い殻を前に悪戦苦闘するしかなかった。
いい匂いはする。食欲はそそられる。それなのにどう食べていいかわからないし、その無様な姿を一緒に笑ってくれる人もいない。
「それは、あまりにワイルド過ぎるじゃろ」
カニの食べ方をネットで検索するも手頃な情報が出てこず、たまりかねた鈴花がカニの足に殻ごと歯を立てたとき。
おかしくてたまらないという笑いを含んだ声が聞こえた。
「え……うそ……」
鈴花が視線を上げると、そこには会いたくてたまらなかったジン様の姿があった。
湯気の向こう、テーブルを挟む形で、鈴花と向かい合っていた。
湯気がちょうどいい具合に働いて、何だか異様に神々しさが増している。
何よりも、涙で滲んだ鈴花の目には、ジン様の姿が今までで一番輝いて見えた。
「ジン様……!」
「鈴花、ただいまなのじゃ」
カニの脚を握りしめたまま叫べば、ジン様が優しい笑顔を浮かべて言った。
それを見て、本当に帰ってきたのだなと実感する。
どこに行っていたのかとか何をしていたのかとか、聞きたいことはたくさんあるが、ひとまずほっとした。
「カニ鍋か、良いのぉ」
「ジン様がさ、食べたがってたから」
「そうか。高瀬臣のところにおったが、どうやら舞台『シェアハウス鍋奉行』ではカニ鍋は食べんようだがの」
「……は?」
ほくほくと言うジン様に鈴花もにっこりしたのだが、その直後にぶち込まれた唐突な発言に、ほっこりムードは一気にぶち壊しとなった。
「え? ちょっと待って? 臣くんのところにいたって何? なにちゃっかり臣くんに取り憑いてるの? ていうか、カニ鍋食べないとか、ネタバレじゃん! なんで帰ってきていきなりネタバレするの? 信じられない!」
混乱した鈴花は、ジン様が帰ってきてくれて嬉しいという気持ちが吹っ飛び、言いたいことをまくしたてた。
ジン様が自分の推しを間近で見てきたことに対する羨ましさと、何の前触れもなくネタバレされたことへの戸惑いと、ニヤニヤした顔から自分へのマウントを察知した苛立ちがないまぜになって、どうしたらいいかわからなくなっている。
そんな鈴花を見て、ジン様は笑っていた。
そのあとも、鍋を挟んで鈴花とジン様の応酬は続いた。
オタク女子と神様のにぎやかな日常が戻ってきたのだ。
スマホを操作する気力もなくなり、何度も何度もしゃくりあげながら涙を流し、そのうちに流す涙もなくなってしまった。
何度も手の中で、スマホが震えていた。おそらくは美里を初めとする観劇仲間が、心配のメッセージを送ってきてくれているのだろう。
鈴花だって逆の立場なら、友人を気遣うメッセージを送ったはずだ。
推しを推していれば、いずれ見たくないニュースを見る日も来るだろうと覚悟はしていた。不祥事、スキャンダル、はたまた引退宣言など、ファンとして見たくない情報はいろいろある。
だが、そのどれも命に別状がないだけまだマシだったのだと思い知らされた。
「……鈴花、とりあえず風呂に入ってこぬか? 身を清めれば、少しは心も軽くなるじゃろうて」
床にへたりこんだ鈴花のすぐそばまでやってきて、ジン様が言った。美しい顔に覗き込まれて、その顔が大好きな推しと同じものだと思うと胸が苦しくなって、鈴花はぐずるみたいに首を振った。
「……今そんな気分じゃないの」
「風呂は、気分で入るわけではなかろう。それに、可愛い顔が汚れておるぞ」
「……は、入ってくる」
泣きじゃくったせいで顔が涙と鼻水だらけなのに気がつき、鈴花はあわててバスルームに向かった。
本当はお風呂に入る気力なんてないのだが、ジン様に汚い顔を晒し続けるのも嫌だった。
のろのろと服を脱ぎ、シャワーを浴びると、温かなお湯の心地よさに少し体が楽になるのがわかった。それと同時に泣きすぎて頭がひどくぼんやり重いことも、喉も体も乾いていることにも気がついた。
シャワーを浴びて髪を乾かして戻ると、ジン様が今度は冷蔵庫を指差す。何か飲まなくてはと思っていたから、ミネラルウォーターを飲みながらスマホをチェックした。
「……ドラマはすべて撮り終えてるから、最終話まで予定通り放送されるんだって。舞台については、今後詳細をアナウンスするって」
『シェアハウス鍋奉行』の公式ツイッターを見に行くと、高瀬臣の事故を受けてのアナウンスが出ていた。事故の報道から数時間であれば、まだ詳しいことを決定できないのだろう。
楽しみにしている作品だから、今後のことは当然気になる。だが、本当に気になるのはそういったことではない。
情報がほしくてネットを見ているのだが、同じような見出しのニュースが乱立しているだけだ。所属事務所はまだ何もアナウンスしていなかった。
「今はまだ、何もわからぬ状況じゃろうて。ファンであるそなたたちを心配させぬよう、知らせられぬこともあるだろうしな」
取り憑かれたようにスマホを手放せずにいる鈴花に、なだめるようにジン様は言った。
言われていることはわかるが、それでも情報を追うのをやめられない。想定している最悪の事態が、あくまでただの考えすぎだと確かめたくて。
しかし、恐れていたことが文字となって鈴花の目に飛び込んできた。
「うそ……」
「どうした?」
「……臣くん、意識が戻らないんだって」
『人気俳優・高瀬臣、搬送先の病院で意識戻らず』という見出しのニュースを表示したスマホをジン様に差し出すと、彼がそれに見入っているのがわかった。
だが、ジン様は何も言わず、鈴花に目を向けた。
「ワシのお下がりの塩むすびを、雑炊にするといい。今夜はあたたかいものをおあがり。それを食べてから、ぐっすり眠るのじゃ」
触れられはしなくても、ジン様が頭を撫でようとしてくれているのがわかった。優しい眼差しを向けてくれてはいるが、うっすらと眉間に寄る皺は、鈴花を心配しているからだろう。
「……わかった」
推しが心配なときに推しの顔で心配されれば、言うことを聞くしかない。
本当は食欲などなかったが、鈴花はお下がりのおにぎりを昆布茶と梅を入れたお湯の中で煮て、お茶漬けのようにして食べた。
布団に入るまで絶対に見張っているという気合いのようなものをジン様から感じ、食べてすぐに横になった。スマホは、かじりつかないようにと少し離れたところに置いたことで、明かりを落とすと自然と眠たくなった。
「そなたまで弱ってしまっては、いかんからな。ゆっくりおやすみ」
あやすようなジン様の声を聞くと、鈴花はスッと眠りに落ちた。そして夢も見ることなく、朝まで眠った。
そして翌朝。
目覚めて真っ先にしたのは、やはりスマホを見ることだった。
だが、そこにほしい情報はなく、ニュースの見出しは代わり映えしなかった。
もしかしたら、一晩眠れば事態が好転しているかもしれない。大怪我なのは変わらなくても目が覚めているかもしれない。
そんな期待を打ち砕かれ、どうしていいかわからず、鈴花の目からはポロリと涙がこぼれた。
「……結局、どれだけ好きでも、私が臣くんにしてあげられることなんてないんだ……」
一晩経って冷静になった鈴花が得たのは、こんなときにファンが推しにしてあげられることなんて何もないという悟りだけだった。
何かできると思い上がっていたわけではないが、その事実は鈴花を打ちのめした。
「果たして、そうかの?」
布団の上で呆然とする鈴花に、ジン様が声をかけた。
高瀬臣グッズが大量に並ぶ祭壇の横で、高瀬臣にそっくりの顔で。
「こんなときに、そなたにしかできぬことがあるだろう?」
ジン様は諭すように、優しい口調で言う。だが、そんなことを言われても鈴花は希望を見い出せなかった。
「ないよ。何も……」
「鈴花、ワシに願え」
「え……?」
「こんなときにワシに願わずして、いつ願うのじゃ? ワシが何のために存在すると思っておるのか」
何かの冗談かと思ったが、ジン様の表情は真剣だった。
「ワシは、鈴花の高瀬臣に向けられる熱心な思いによって眠りから覚めた。これまで、何度もそなたの願いを叶えてきた。そんなワシとそなたが今、形にすべき願いなどひとつしかなかろう?」
「それは……」
ジン様の言っていることをようやく理解すると、鈴花は途端に不安になった。ジン様の覚悟を決めたような表情が、さらに不安をあおる。
「……ジン様、そんな顔してそんなこと言わないで」
「何を願えばいいか、わかったようだな」
「やだよ。……チケット運とか、そういう話じゃないんだよ? 無理するのわかってて、願い事なんかできないよ」
「無理もするさ。高瀬臣を救えねば、どのみちワシは存在できなくなる。ワシは自分の存在のために、あやつを助けると言っておるのじゃ」
ジン様の言葉を聞いて、やはりそういうことなのかと鈴花は納得した。
彼は、自分の力を使って高瀬臣を助けると言っているのだ。それがどれだけ無謀で大変なことなのか、鈴花にだってわかる。
「さあ、願え鈴花」
「できないよ! おにぎりで叶えていい願いじゃない!」
鈴花は子供の駄々のようにイヤイヤと首を振って抵抗した。
ジン様の顔を見れば、彼が自分の考えを翻さないことはわかっていた。というよりも、鈴花が口に出さなくても何を願っているのか知っているのだ。鈴花のことは何でもわかるから、ラジオにあんなメッセージを勝手に送ることができたのだから。
「願うのじゃ、鈴花。言葉にせずともそなたの思いは手に取るようにわかるが、口に出すことでその思いはより強いものとなる。高瀬臣を救いたいのじゃろう? それなら、ワシに願え。――ワシは、そなたの神じゃ」
どこまでも優しい笑顔で言われて、鈴花はこらえていた涙がまた目から溢れ出た。
当然、救いたい気持ちはある。目覚めてほしいに決まっている。
だが、その願いのためにジン様の存在が犠牲になるなんて嫌だった。
それでも、願わなくてはならないことも理解した。
それは、ジン様が鈴花の神様だから。神様が叶えると決めたのなら、その願いを口にするのが自分の役目なのだとわかった。
「……ジン様、お願い。臣くんを助けて。また元気に舞台に立てるようにしてあげて」
「うむ、わかった」
鈴花が振り絞るようにして言うと、ジン様は笑顔で頷いた。
そこに憂いも翳りもない。澄み切って明るい笑顔だった。
「それじゃ、ちょいと行ってくるの」
ジン様はそう言って、ひらりと手を振って祭壇の奥の壁に消えていった。
まるで朝の光にとけていったみたいに、見えなくなってしまった。
「……ちょいと行ってくるって、何それ」
散歩にでも出かけるような軽い別れの言葉に、鈴花は笑った。
そしてこの数カ月一緒に暮らしたにぎやかな神様の不在に、少しの間泣いた。
それからほどなくして、高瀬臣の意識が戻ったというニュースがネットを騒がせた。
そして数日経つと意識が戻っただけではなく、驚異のスピードで回復していることも報じられた。
最初はマネージャーによる代筆でのツイートだったが、事故の報道から十日も経つと腕と足を吊った状態の写真を投稿していたし、さらに数日経つとリハビリしている姿を動画で披露していた。
それらの行動から、意識不明の重体だったのに後遺症も麻痺も残らないらしいと、関係内外からも注目されていた。
ファンたちからは「臣くん、運動神経いいから受け身がうまかったんじゃない?」とか「日頃から体鍛えてたからかな」などという声があがっていたが、これが〝奇跡の回復〟などではないことを知っている。
偶然起きた幸運ではなく、優しくて親切な神が起こした神業なのだと、鈴花だけがわかっている。
だから、大好きな推しがみるみる回復して松葉杖で舞台に立つとわかって安心しても、手放しに喜ぶことはできなかった。
高瀬臣が鈴花の人生に欠かせない存在であるのと同じように、ジン様も、もうなくてはならない存在なのだ。
というより、あの優しい神様に願いを叶えてもらってそれっきりなんて嫌で、どうにかして取り戻せないかとか、そんなことばかり考えてしまっている。
だから鈴花は、せっせとジン様の絵を描いてネットにアップした。
ジン様の魅力を少しでもたくさんの人に知ってもらいたいと、いろんな表情やポーズのイラストを描いた。
それが功を奏したのか、ちょっとずつジン様のファンアートが投稿されるようになり、ドット絵で動くジン様を作ってくれる人や、3Dモデルを作ってくれる人まで現れた。どこかの企業から「Vtuberとしてデビューしませんか」という話まで持ちかけられるようになった。
だが、そんなふうに人気が出ても、たくさんの人から愛されるようになっても、ジン様が姿を表すことはなかった。
「もう、何よ! あんな軽く出ていったらさ、すぐに帰ってくるのかと思っちゃうじゃん……」
鈴花は、消えてしまう前のジン様の「ちょいと行ってくるの」という言葉だけを頼りに彼の不在の日々を過ごしてきた。
だが、一向に戻ってくる気配がないとわかると、時々無性に寂しくなって気持ちが荒んでしまうのだ。
だから今夜は、ちょっとした暴挙に出ることにした。
「帰ってきたら一緒に食べようと思ってたけど、なかなか帰ってこないから勝手に食べちゃうことにした!」
そう言って鈴花が食卓に用意したのは、カセットコンロと土鍋と野菜の数々とカニだ。カニ鍋にしようと奮発して1Kgのカニを通販で買ったのだ。
ボーナスが出たときに、ふと頭をよぎったのがカニ鍋を食べることだった。だから、ジン様が食べたがっていたなと思いだして、迷わず注文した。
冷凍された状態で届いたから、帰ってくるまで待っていようと思ってずっと冷凍庫に入れておいた。
だが、いくら待っても帰ってこないし、クリスマスは近づいてきているし、このままでは正月にひとりでつつくはめになるかもしれないと、慌てて今夜カニ鍋を決行することにしたのだ。
「はぁ、おいしそう。せめて気分だけでも味わってもらおう……」
そう言って鈴花は、小ロットで制作したジン様のアクリルスタンドをテーブルに置いた。自分だけが楽しめればいいと工場に発注したものだったが、意外に需要があるようで、今度増産することが決まっている。動きのある全身イラストを使用しているため、なかなか出来がよく、存在感もばっちりだ。
だが、それだけにさらに寂しさが増した。
具材と出汁を火にかけて待てば、ぐつぐつという音といい匂いが食欲をそそる。それなのに、鈴花の気分は全然盛り上がらなかった。
「うわぁ、カニ、食べ方わからん。うち、水炊き派だから子供のときからほとんどカニ鍋なんて食べたことないんだよぉ……」
食べ頃になっていざカニを手にしたものの、不慣れな鈴花はカニの硬い殻を前に悪戦苦闘するしかなかった。
いい匂いはする。食欲はそそられる。それなのにどう食べていいかわからないし、その無様な姿を一緒に笑ってくれる人もいない。
「それは、あまりにワイルド過ぎるじゃろ」
カニの食べ方をネットで検索するも手頃な情報が出てこず、たまりかねた鈴花がカニの足に殻ごと歯を立てたとき。
おかしくてたまらないという笑いを含んだ声が聞こえた。
「え……うそ……」
鈴花が視線を上げると、そこには会いたくてたまらなかったジン様の姿があった。
湯気の向こう、テーブルを挟む形で、鈴花と向かい合っていた。
湯気がちょうどいい具合に働いて、何だか異様に神々しさが増している。
何よりも、涙で滲んだ鈴花の目には、ジン様の姿が今までで一番輝いて見えた。
「ジン様……!」
「鈴花、ただいまなのじゃ」
カニの脚を握りしめたまま叫べば、ジン様が優しい笑顔を浮かべて言った。
それを見て、本当に帰ってきたのだなと実感する。
どこに行っていたのかとか何をしていたのかとか、聞きたいことはたくさんあるが、ひとまずほっとした。
「カニ鍋か、良いのぉ」
「ジン様がさ、食べたがってたから」
「そうか。高瀬臣のところにおったが、どうやら舞台『シェアハウス鍋奉行』ではカニ鍋は食べんようだがの」
「……は?」
ほくほくと言うジン様に鈴花もにっこりしたのだが、その直後にぶち込まれた唐突な発言に、ほっこりムードは一気にぶち壊しとなった。
「え? ちょっと待って? 臣くんのところにいたって何? なにちゃっかり臣くんに取り憑いてるの? ていうか、カニ鍋食べないとか、ネタバレじゃん! なんで帰ってきていきなりネタバレするの? 信じられない!」
混乱した鈴花は、ジン様が帰ってきてくれて嬉しいという気持ちが吹っ飛び、言いたいことをまくしたてた。
ジン様が自分の推しを間近で見てきたことに対する羨ましさと、何の前触れもなくネタバレされたことへの戸惑いと、ニヤニヤした顔から自分へのマウントを察知した苛立ちがないまぜになって、どうしたらいいかわからなくなっている。
そんな鈴花を見て、ジン様は笑っていた。
そのあとも、鍋を挟んで鈴花とジン様の応酬は続いた。
オタク女子と神様のにぎやかな日常が戻ってきたのだ。