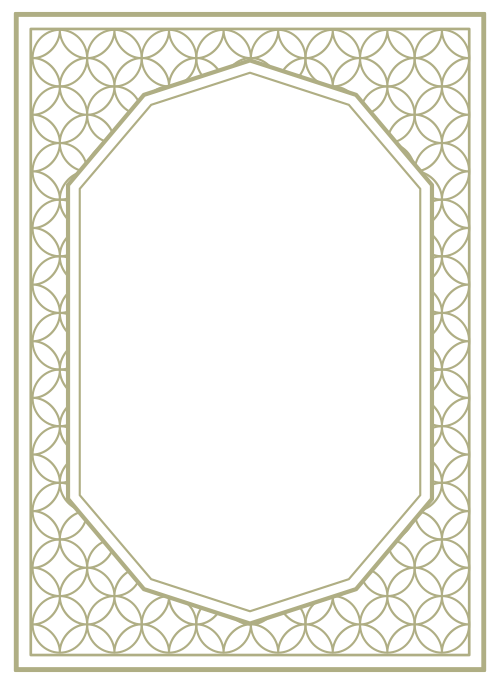「ワシ、人気者じゃのぉ」
ツイッターアカウント開設及びイラスト投稿から数日経っても、ジン様はまだご機嫌だった。タブレットを覗き込み、そこに表示された自身のイラストとそれについた〝いいね〟のハートの数を見ている。
あのイラスト自体、運よくそこそこ拡散されたし、そのあと週末に清書した完成イラストを投稿するとさらにリツイート数は伸びた。アカウントのフォロワーも増えた。
というわけで、〝高瀬臣のようにキャーキャー言われたい〟というジン様の願いは、現在進行形で叶っているというわけである。
鈴花はこれまで二次創作のイラストを描けばそれなりに評価され人に見られてきたが、それは元のキャラクターの人気にあやかってのことだと理解していた。だが、オリジナルの絵というのはそのポテンシャルがないため、純粋に絵のうまさやモチーフ選びで評価されるため、二次創作よりも人に見てもらいにくい傾向にあると感じていた。
だからこそ、ジン様のイラストをただポイっと投稿しただけでたくさんの人にリツイートされ、いいねをつけてもらえたということが、鈴花はすごく嬉しかった。絵を描きたいという気持ちが少し湧いてきて、ジン様のアカウント用にデフォルメキャラクターでも描いてみようかと考えていた。
だが、それもつい先ほどまでのこと。
「え、ちょ……うわー! 行きたい! 行きたい行きたいッ!」
仕事を終えて帰宅して、夕食を食べながらのまったりした時間に、スマホを片手に突如鈴花は叫んだ。
日中チェックできなかった推しの情報をまったり夕食を摂りながらチェックするのが毎日の日課なのだが、ツイッターで得た推しの新情報にテンションがぶち上がっている。
「何じゃ? どうしたのじゃ?」
鈴花のあまりのけたたましさに、ご機嫌でタブレットを眺めていたジン様も思わずといった様子でキッチンの食卓までやってきた。
ジン様が家に着いてきて一週間ほど経ち、最初は戸惑っていた鈴花もすっかりその存在に慣れきっていて、いちいち驚くことなく接している。
「見て見て! 臣くんが出るドラマがもうすぐ始まるでしょ。それに合わせてラジオ番組が始まるんだけど、それの公開収録が今度あるの!」
「ほぉ、良いの。そなたの好きな俳優を直接見られるというわけか」
鈴花の熱気に当てられて目覚めたからか、一緒に生活しているからか、ジン様はこの手のことはすっかり飲み込みがいい。スマホの画面を見せられただけで、鈴花が何に興奮しているのか理解した。
「うん、行きたいんだけど……五十組百名様って、すごい倍率なんだろうなぁ……」
推しを生で見られる機会とあって喜んだのも束の間、公開収録に招待されるには厳しい倍率の抽選に臨まなければならないことに早くも心が萎えていた。
「臣くんだけじゃなくてさ、共演者の人気俳優も出るんだよ。てか、そっちの人気の方がやばいな。うわぁ……」
その日の収録に参加するもう一人の俳優の名前を見て、鈴花はさらにしょんぼりする。
今度の収録に高瀬臣と一緒に出る緒形トオルという俳優は、舞台を中心に人気を集める俳優なのだが、顔がいいのはもちろんのこと声がいいことから声優やテレビCMのナレーションなど幅広く活躍していて、ファン層も広い。そのため、この公開収録の抽選も彼目当ての多数の応募者たちと争わなくてはならないのは必至だ。
「そうだ。私だけの応募じゃ不安だから、トオルくんファンの子に声かけて応募してもらおう。これで、当選倍率を少しは上げられる!」
一緒に舞台を見にいくガチめのトオルくんファンの存在を思い出し、鈴花はすぐに連絡を取った。舞台のチケットを取るのも、いつも共同戦線を張っているのだ。というよりも、この界隈は知り合いや協力者が多いに越したことはないから、運よく多めにチケットが取れた際には融通したり逆にしてもらったりということが割と当たり前で、みんな戦友みたいなものだ。
「もう応募したって! すごい! さすが! 私もしなくちゃ」
連絡を受けるより先に応募を済ませていたという友人からの返信に、鈴花は俄然気合いが入った。他の希望者たちも応募をすでに済ませたのだろうかと思うと、うかうかしていられないという気分になる。
「何じゃ。ワシに頼まなくてもいいのか?」
応募のためのエントリフォームと睨めっこしていると、つまらなそうにジン様が尋ねてきた。興奮して周りが見えなくなっていた鈴花に放置され、どうやら拗ねているようだ。
声をかけられたことでその存在を思い出した鈴花だったが、ジン様の顔とスマホを見比べて「うーん」と考え込んだ。
「これさ、何千人何万人が応募するんだよ? 舞台のチケットみたいに、席数が用意されてるわけじゃないんだよ? ジン様にできるかな。いや、できたらジン様の力は舞台のチケットまで取っておきたいんだけど」
「できるわい! だって最近ワシ、人気者じゃもん!」
どうしようか悩む鈴花に、ジン様は〝キラッ〟と目元にピースサインをかざすポーズを取りつつ言った。舌ペロもつけているあたり、高瀬臣の影響を色濃く受けすぎている気もする。高瀬臣は可愛い系かかっこい系かと問われれば圧倒的に後者なのだが、あざといポーズも変顔もやってのけるのだ。ジン様はそれをDVDを見て学んだらしい。
「くっ……かわいい。なるほど、できるのか。そっか。それなら力を貸してもらえるとありがたい」
「今のままでも十分力を発揮できそうじゃが、ワシの新しい絵を描いてくれたらもっと頑張れるかもしれん。というより、ワシの人気はそのままワシの力じゃ。ご利益のことを考えれば、ワシの人気がもっともっと増すようにするのがいいと思うんじゃがのぉ」
「描くよっ!」
そういえばこの人、神だったわと、タダでは動かないというジン様の姿勢を前に鈴花は思い出した。だが、イラスト一枚で当選確率が上がるというのなら、そんなの描くに決まっている。
公開収録の抽選に応募すると急いで夕食を済ませ、鈴花はすぐに絵に取りかかった。描くことを予定していたデフォルメキャラのラフを見せると気に入った様子だったため、それを差分を含めて数枚描き、ちょっとしたGIFアニメにしてみた。
最近は絵を描きさえすればアプリでそこそこ簡単にアニメにしてしまえるのだ。気合いの入った一枚絵を描けない分、少し手間をかけただけのつもりだったが、横で完成を見守っていたジン様はかなり気にいるものだったようだ。
「すごいの! ちっこいワシが動いておる!」
「簡単にだけどね。絵を複数枚用意すると、動いて見えるようにできるんだよ」
「かわいい! これは早く人々に見せてやらねば」
「待ってね。ウェブ投稿に適したファイル形式に変換するから」
ワクワクして急かしてくるジン様を宥めつつ、鈴花はGIFアニメのファイルを適切な形式で書き出した。それをツイッターに投稿するまで、ジン様はソワソワと鈴花の周りを飛び回った。
「え? ちょっと待って。どうなってんの? すぐリツイートされたんだけど」
アニメ付きで呟くと、すぐさまリツイートされ、いいねがいくつもついた。二次創作で人気のジャンルにいたときですら、こんなに早く反応がもらえることはなかったのに。
「ワシがかわいいからのぉ。みんなワシが好きなんじゃ」
「本当だ……『小さいジン様かわいい』『ジン様、小さくなっても麗しい』だって」
「よしよし。力がみなぎってくるのぉ」
その後もリツイートやいいねの数はポチポチと増えていき、鈴花はジン様の人気とやらを実感せざるを得なかった。いわゆるバズるというほどの拡散はないにしても、作って間もないアカウントが投稿のたびに千を超えるいいねとリツイートがつくというのは、それなりにファンを作っているということだ。
そしてその数は、確実に増えてきている。
「じゃ、じゃあ、ジン様、よろしくね……?」
ジン様人気にやや慄きつつも、鈴花は公開収録に当選するよう手を合わせてお願いした。
「……いや、本当に、当選できるもんなんだね」
電車と地下鉄を乗り継いで目的地である収録スタジオのある建物までやってきた鈴花は、ここにやって来られたという事実を改めて受け止めて呟いた。
半信半疑でジン様の新規イラストを投稿し、祈るような気持ちで公開収録の抽選に応募した鈴花だったが、なんと無事に当選したのだ。
ジン様のことを疑っていたわけではない。しかし、さすがに五十組しか選ばれないものに無事に当選するとは思っていなかった。
だから、当選のメールが来ても信じきることができず、同伴する約束をしていた友人にその文面を転送して見せたほどだ。
「鈴花さんが当選してくれてよかったー! だめだったときのこと考えて何人か友達に声かけてたけど、全滅だもんね。てか、ツイッターのフォロワーにも当選者いないってレベル」
隣にいる美里が、しみじみと感じ入るように言った。
二人がいるのは収録スタジオのある建物のエントランスホールで、受付を済ませてからエレベーターに乗るよう指示されるようだ。その受付待ちの列を見れば、その人数の少なさがわかる。
舞台の公演は、キャパが小さめの会場でも八百名、多いと二千名は収容できるわけだから、その人数と比べればどれほどの倍率を勝ち抜いたのかを実感するというものだ。
「五十組って、つまりそういうことだよね……改めて、本当によかった」
「鈴花さんの強運に感謝! 新参だから、トオルくんのこれまでのことはリアタイできなくても、これからのことはなるべくリアタイしたいんだ」
受付を済ませエレベーターに乗りこむと、美里が気合いを入れたように言う。それに対して鈴花も「わかる……!」と相槌を打った。
高瀬臣も緒形トオルも活動年数十年を越す俳優だから、昔の活動のことは追いかけるしかできない。映像化されていないものなんかは、当時を知る人から伝え聞くことしかできない。
だから、今見ることができる推しの姿は何が何でも見たいと思ってしまうのだ。
「トオルくんに臣くん、それから他にも人気ある俳優さんばっかりだから、ドラマも舞台も楽しみだよね」
「『シェアハウス鍋奉行』って、タイトルからして面白いもん。ドラマのキービジュアル見る限り、トオルくんが奉行なのかな? おたま持ってキリッとした顔、かわいいね」
「そうなのトオルくんかわいいの! でも、お箸持って食べる気満々な臣くんもかっこいいよ」
「お箸持つだけでこんなにかっこいいの、すごくない?」
エレベーターを降りて収録スタジオまで歩きながら、二人は互いの推しを称え合った。推しがいる者同士で顔を合わせると、話すことが尽きないのがいい。基本的に推しの話しかしないし、愚痴も悪口もないのだ。
「あのガラス張りのブースの中にこれから臣くんたちがくるんでしょ……!」
「やばい! 舞台よりも近い!」
収録スタジオの中に入ると、収録ブースと観覧席の近さに鈴花たちは驚いた。収録ブースの奥には音響機材が揃った部屋も見え、行き交うスタッフの姿に間もなく収録が始まるのだというのが伝わってくる。
席に着くとすぐはざわめいていたが、スタッフが制止すると静かになった。何より、これから推しが登場するのだという熱く静かな緊張感に包まれた。
そして、スタジオに高瀬臣と緒形トオルが入ってきた瞬間、その張り詰めた空気は一気に弾けた。
「やばい……生きてる……動いてる……!」
黄色い歓声に出迎えられ、それに笑顔で応える高瀬臣と緒形トオル。それを目の前にして鈴花は、語彙力を失くしたうめき声か黄色い声を上げるしかできなくなっている。
隣で美里は「メガネ……トオルくん……メガネ……」と、舞台での仕事とは違うオフっぽさを演出しつつ魅力が何割増しにもなる最強アイテムであるメガネを身につけた推しの姿に、静かに悶絶していた。確かにメガネはやばい。
歓声をうまく宥めつつ俳優二人はトークを進めていった。「シェアハウス鍋奉行」のあらすじや見所を語り、自分たちの役柄について語り、すでに始まっている撮影の様子などについて話してくれた。
ドラマと舞台についてひと通り語り終えると、今度は事前に募集していたファンたちからのメッセージを読み上げるというコーナーに移っていった。
「メール送るの、忘れてた。もし読まれたら、推しに名前を呼んでもらえるんだった……」
メッセージの前に読み上げられるラジオネームを耳にし、鈴花はそのことを思い出した。公開収録の観覧に当選することにばかり意識がいっていたが、ラジオといえばメッセージをパーソナリティに読まれるのも醍醐味。パーソナリティを務めるのが推しとなれば、それはなおさらだ。
「私はメール送ったけど、たぶん読まれないだろうな。だって、こうして観覧できてさらにメッセージまで読まれるなんて幸運、あるわけないもん」
隣の美里の冷静な意見を聞き、それもそうかと鈴花は納得した。
こうしてすごい倍率の抽選に選ばれ、推しが喋るのを生で見られているだけでも幸運なのだ。それ以上を望むのはきっとバチが当たる。
そんなふうに心を落ち着けて、目の前で高瀬臣が緒形トオルと一緒に話すのに耳を傾けていると、不意に名前を呼ばれて鈴花は驚いた。
「次のメッセージは、ラジオネーム〝鈴花〟さんから。『私は高瀬臣くんが大好きです。演技をしているときのかっこいい姿も、お茶目な変顔も、巧みなダンスやアクションも、全部全部素敵だなと思っています。ずっと見ていたいです。ドラマも舞台も楽しみにしています』だって」
緒形トオルが読み上げたメッセージに、美里が「これ送ったの鈴花さん?」とこっそり尋ねてきた。彼女はびっくりした顔をしているが、鈴花だって驚いている。
送った覚えはないものの、鈴花がいつも思っていることだ。しかし、他のファンだって同じようなことは考えているだろう。
「わぁ、嬉しい! 今日、正直トオルのファンばっかなんじゃないかと思ってたから、すげぇ嬉しい」
「そんなことないだろ。ちゃんと臣くんのファンいるって。いやー、でも、こういうストレートな応援メッセージっていうのも、嬉しいよね」
「うん、嬉しい。どの仕事もちゃんとやってるけどさ、さらにちゃんとしないとなって気持ちになる。鈴花ちゃん、ありがとう」
推しに名前を呼ばれ、鈴花は心臓を押さえて「うっ……!」とうめいてしまいたかったが、ここが公衆の面前というだけでなく推しの前であることを思い出して堪えた。
先ほどのメッセージが、何なのかはわからない。鈴花自身は送った覚えはない。
だが、喜びに震え、身の内に言い表せないほどの感情を滾らせて収録ブースの中の高瀬臣を見つめていると、不意に脳裏にジン様の顔がよぎった。
高瀬臣そっくりの姿をしているが、似て非なる、お茶目な神様。鈴花の影響ですっかり俗物に染まり切ったあの神が、「ワシじゃ」と言ってピースサインをしている姿が浮かんだ。
「……ジン様‼︎」
思いもかけないサプライズプレゼントに、鈴花はただ手を合わせて拝むことしかできなかった。
ツイッターアカウント開設及びイラスト投稿から数日経っても、ジン様はまだご機嫌だった。タブレットを覗き込み、そこに表示された自身のイラストとそれについた〝いいね〟のハートの数を見ている。
あのイラスト自体、運よくそこそこ拡散されたし、そのあと週末に清書した完成イラストを投稿するとさらにリツイート数は伸びた。アカウントのフォロワーも増えた。
というわけで、〝高瀬臣のようにキャーキャー言われたい〟というジン様の願いは、現在進行形で叶っているというわけである。
鈴花はこれまで二次創作のイラストを描けばそれなりに評価され人に見られてきたが、それは元のキャラクターの人気にあやかってのことだと理解していた。だが、オリジナルの絵というのはそのポテンシャルがないため、純粋に絵のうまさやモチーフ選びで評価されるため、二次創作よりも人に見てもらいにくい傾向にあると感じていた。
だからこそ、ジン様のイラストをただポイっと投稿しただけでたくさんの人にリツイートされ、いいねをつけてもらえたということが、鈴花はすごく嬉しかった。絵を描きたいという気持ちが少し湧いてきて、ジン様のアカウント用にデフォルメキャラクターでも描いてみようかと考えていた。
だが、それもつい先ほどまでのこと。
「え、ちょ……うわー! 行きたい! 行きたい行きたいッ!」
仕事を終えて帰宅して、夕食を食べながらのまったりした時間に、スマホを片手に突如鈴花は叫んだ。
日中チェックできなかった推しの情報をまったり夕食を摂りながらチェックするのが毎日の日課なのだが、ツイッターで得た推しの新情報にテンションがぶち上がっている。
「何じゃ? どうしたのじゃ?」
鈴花のあまりのけたたましさに、ご機嫌でタブレットを眺めていたジン様も思わずといった様子でキッチンの食卓までやってきた。
ジン様が家に着いてきて一週間ほど経ち、最初は戸惑っていた鈴花もすっかりその存在に慣れきっていて、いちいち驚くことなく接している。
「見て見て! 臣くんが出るドラマがもうすぐ始まるでしょ。それに合わせてラジオ番組が始まるんだけど、それの公開収録が今度あるの!」
「ほぉ、良いの。そなたの好きな俳優を直接見られるというわけか」
鈴花の熱気に当てられて目覚めたからか、一緒に生活しているからか、ジン様はこの手のことはすっかり飲み込みがいい。スマホの画面を見せられただけで、鈴花が何に興奮しているのか理解した。
「うん、行きたいんだけど……五十組百名様って、すごい倍率なんだろうなぁ……」
推しを生で見られる機会とあって喜んだのも束の間、公開収録に招待されるには厳しい倍率の抽選に臨まなければならないことに早くも心が萎えていた。
「臣くんだけじゃなくてさ、共演者の人気俳優も出るんだよ。てか、そっちの人気の方がやばいな。うわぁ……」
その日の収録に参加するもう一人の俳優の名前を見て、鈴花はさらにしょんぼりする。
今度の収録に高瀬臣と一緒に出る緒形トオルという俳優は、舞台を中心に人気を集める俳優なのだが、顔がいいのはもちろんのこと声がいいことから声優やテレビCMのナレーションなど幅広く活躍していて、ファン層も広い。そのため、この公開収録の抽選も彼目当ての多数の応募者たちと争わなくてはならないのは必至だ。
「そうだ。私だけの応募じゃ不安だから、トオルくんファンの子に声かけて応募してもらおう。これで、当選倍率を少しは上げられる!」
一緒に舞台を見にいくガチめのトオルくんファンの存在を思い出し、鈴花はすぐに連絡を取った。舞台のチケットを取るのも、いつも共同戦線を張っているのだ。というよりも、この界隈は知り合いや協力者が多いに越したことはないから、運よく多めにチケットが取れた際には融通したり逆にしてもらったりということが割と当たり前で、みんな戦友みたいなものだ。
「もう応募したって! すごい! さすが! 私もしなくちゃ」
連絡を受けるより先に応募を済ませていたという友人からの返信に、鈴花は俄然気合いが入った。他の希望者たちも応募をすでに済ませたのだろうかと思うと、うかうかしていられないという気分になる。
「何じゃ。ワシに頼まなくてもいいのか?」
応募のためのエントリフォームと睨めっこしていると、つまらなそうにジン様が尋ねてきた。興奮して周りが見えなくなっていた鈴花に放置され、どうやら拗ねているようだ。
声をかけられたことでその存在を思い出した鈴花だったが、ジン様の顔とスマホを見比べて「うーん」と考え込んだ。
「これさ、何千人何万人が応募するんだよ? 舞台のチケットみたいに、席数が用意されてるわけじゃないんだよ? ジン様にできるかな。いや、できたらジン様の力は舞台のチケットまで取っておきたいんだけど」
「できるわい! だって最近ワシ、人気者じゃもん!」
どうしようか悩む鈴花に、ジン様は〝キラッ〟と目元にピースサインをかざすポーズを取りつつ言った。舌ペロもつけているあたり、高瀬臣の影響を色濃く受けすぎている気もする。高瀬臣は可愛い系かかっこい系かと問われれば圧倒的に後者なのだが、あざといポーズも変顔もやってのけるのだ。ジン様はそれをDVDを見て学んだらしい。
「くっ……かわいい。なるほど、できるのか。そっか。それなら力を貸してもらえるとありがたい」
「今のままでも十分力を発揮できそうじゃが、ワシの新しい絵を描いてくれたらもっと頑張れるかもしれん。というより、ワシの人気はそのままワシの力じゃ。ご利益のことを考えれば、ワシの人気がもっともっと増すようにするのがいいと思うんじゃがのぉ」
「描くよっ!」
そういえばこの人、神だったわと、タダでは動かないというジン様の姿勢を前に鈴花は思い出した。だが、イラスト一枚で当選確率が上がるというのなら、そんなの描くに決まっている。
公開収録の抽選に応募すると急いで夕食を済ませ、鈴花はすぐに絵に取りかかった。描くことを予定していたデフォルメキャラのラフを見せると気に入った様子だったため、それを差分を含めて数枚描き、ちょっとしたGIFアニメにしてみた。
最近は絵を描きさえすればアプリでそこそこ簡単にアニメにしてしまえるのだ。気合いの入った一枚絵を描けない分、少し手間をかけただけのつもりだったが、横で完成を見守っていたジン様はかなり気にいるものだったようだ。
「すごいの! ちっこいワシが動いておる!」
「簡単にだけどね。絵を複数枚用意すると、動いて見えるようにできるんだよ」
「かわいい! これは早く人々に見せてやらねば」
「待ってね。ウェブ投稿に適したファイル形式に変換するから」
ワクワクして急かしてくるジン様を宥めつつ、鈴花はGIFアニメのファイルを適切な形式で書き出した。それをツイッターに投稿するまで、ジン様はソワソワと鈴花の周りを飛び回った。
「え? ちょっと待って。どうなってんの? すぐリツイートされたんだけど」
アニメ付きで呟くと、すぐさまリツイートされ、いいねがいくつもついた。二次創作で人気のジャンルにいたときですら、こんなに早く反応がもらえることはなかったのに。
「ワシがかわいいからのぉ。みんなワシが好きなんじゃ」
「本当だ……『小さいジン様かわいい』『ジン様、小さくなっても麗しい』だって」
「よしよし。力がみなぎってくるのぉ」
その後もリツイートやいいねの数はポチポチと増えていき、鈴花はジン様の人気とやらを実感せざるを得なかった。いわゆるバズるというほどの拡散はないにしても、作って間もないアカウントが投稿のたびに千を超えるいいねとリツイートがつくというのは、それなりにファンを作っているということだ。
そしてその数は、確実に増えてきている。
「じゃ、じゃあ、ジン様、よろしくね……?」
ジン様人気にやや慄きつつも、鈴花は公開収録に当選するよう手を合わせてお願いした。
「……いや、本当に、当選できるもんなんだね」
電車と地下鉄を乗り継いで目的地である収録スタジオのある建物までやってきた鈴花は、ここにやって来られたという事実を改めて受け止めて呟いた。
半信半疑でジン様の新規イラストを投稿し、祈るような気持ちで公開収録の抽選に応募した鈴花だったが、なんと無事に当選したのだ。
ジン様のことを疑っていたわけではない。しかし、さすがに五十組しか選ばれないものに無事に当選するとは思っていなかった。
だから、当選のメールが来ても信じきることができず、同伴する約束をしていた友人にその文面を転送して見せたほどだ。
「鈴花さんが当選してくれてよかったー! だめだったときのこと考えて何人か友達に声かけてたけど、全滅だもんね。てか、ツイッターのフォロワーにも当選者いないってレベル」
隣にいる美里が、しみじみと感じ入るように言った。
二人がいるのは収録スタジオのある建物のエントランスホールで、受付を済ませてからエレベーターに乗るよう指示されるようだ。その受付待ちの列を見れば、その人数の少なさがわかる。
舞台の公演は、キャパが小さめの会場でも八百名、多いと二千名は収容できるわけだから、その人数と比べればどれほどの倍率を勝ち抜いたのかを実感するというものだ。
「五十組って、つまりそういうことだよね……改めて、本当によかった」
「鈴花さんの強運に感謝! 新参だから、トオルくんのこれまでのことはリアタイできなくても、これからのことはなるべくリアタイしたいんだ」
受付を済ませエレベーターに乗りこむと、美里が気合いを入れたように言う。それに対して鈴花も「わかる……!」と相槌を打った。
高瀬臣も緒形トオルも活動年数十年を越す俳優だから、昔の活動のことは追いかけるしかできない。映像化されていないものなんかは、当時を知る人から伝え聞くことしかできない。
だから、今見ることができる推しの姿は何が何でも見たいと思ってしまうのだ。
「トオルくんに臣くん、それから他にも人気ある俳優さんばっかりだから、ドラマも舞台も楽しみだよね」
「『シェアハウス鍋奉行』って、タイトルからして面白いもん。ドラマのキービジュアル見る限り、トオルくんが奉行なのかな? おたま持ってキリッとした顔、かわいいね」
「そうなのトオルくんかわいいの! でも、お箸持って食べる気満々な臣くんもかっこいいよ」
「お箸持つだけでこんなにかっこいいの、すごくない?」
エレベーターを降りて収録スタジオまで歩きながら、二人は互いの推しを称え合った。推しがいる者同士で顔を合わせると、話すことが尽きないのがいい。基本的に推しの話しかしないし、愚痴も悪口もないのだ。
「あのガラス張りのブースの中にこれから臣くんたちがくるんでしょ……!」
「やばい! 舞台よりも近い!」
収録スタジオの中に入ると、収録ブースと観覧席の近さに鈴花たちは驚いた。収録ブースの奥には音響機材が揃った部屋も見え、行き交うスタッフの姿に間もなく収録が始まるのだというのが伝わってくる。
席に着くとすぐはざわめいていたが、スタッフが制止すると静かになった。何より、これから推しが登場するのだという熱く静かな緊張感に包まれた。
そして、スタジオに高瀬臣と緒形トオルが入ってきた瞬間、その張り詰めた空気は一気に弾けた。
「やばい……生きてる……動いてる……!」
黄色い歓声に出迎えられ、それに笑顔で応える高瀬臣と緒形トオル。それを目の前にして鈴花は、語彙力を失くしたうめき声か黄色い声を上げるしかできなくなっている。
隣で美里は「メガネ……トオルくん……メガネ……」と、舞台での仕事とは違うオフっぽさを演出しつつ魅力が何割増しにもなる最強アイテムであるメガネを身につけた推しの姿に、静かに悶絶していた。確かにメガネはやばい。
歓声をうまく宥めつつ俳優二人はトークを進めていった。「シェアハウス鍋奉行」のあらすじや見所を語り、自分たちの役柄について語り、すでに始まっている撮影の様子などについて話してくれた。
ドラマと舞台についてひと通り語り終えると、今度は事前に募集していたファンたちからのメッセージを読み上げるというコーナーに移っていった。
「メール送るの、忘れてた。もし読まれたら、推しに名前を呼んでもらえるんだった……」
メッセージの前に読み上げられるラジオネームを耳にし、鈴花はそのことを思い出した。公開収録の観覧に当選することにばかり意識がいっていたが、ラジオといえばメッセージをパーソナリティに読まれるのも醍醐味。パーソナリティを務めるのが推しとなれば、それはなおさらだ。
「私はメール送ったけど、たぶん読まれないだろうな。だって、こうして観覧できてさらにメッセージまで読まれるなんて幸運、あるわけないもん」
隣の美里の冷静な意見を聞き、それもそうかと鈴花は納得した。
こうしてすごい倍率の抽選に選ばれ、推しが喋るのを生で見られているだけでも幸運なのだ。それ以上を望むのはきっとバチが当たる。
そんなふうに心を落ち着けて、目の前で高瀬臣が緒形トオルと一緒に話すのに耳を傾けていると、不意に名前を呼ばれて鈴花は驚いた。
「次のメッセージは、ラジオネーム〝鈴花〟さんから。『私は高瀬臣くんが大好きです。演技をしているときのかっこいい姿も、お茶目な変顔も、巧みなダンスやアクションも、全部全部素敵だなと思っています。ずっと見ていたいです。ドラマも舞台も楽しみにしています』だって」
緒形トオルが読み上げたメッセージに、美里が「これ送ったの鈴花さん?」とこっそり尋ねてきた。彼女はびっくりした顔をしているが、鈴花だって驚いている。
送った覚えはないものの、鈴花がいつも思っていることだ。しかし、他のファンだって同じようなことは考えているだろう。
「わぁ、嬉しい! 今日、正直トオルのファンばっかなんじゃないかと思ってたから、すげぇ嬉しい」
「そんなことないだろ。ちゃんと臣くんのファンいるって。いやー、でも、こういうストレートな応援メッセージっていうのも、嬉しいよね」
「うん、嬉しい。どの仕事もちゃんとやってるけどさ、さらにちゃんとしないとなって気持ちになる。鈴花ちゃん、ありがとう」
推しに名前を呼ばれ、鈴花は心臓を押さえて「うっ……!」とうめいてしまいたかったが、ここが公衆の面前というだけでなく推しの前であることを思い出して堪えた。
先ほどのメッセージが、何なのかはわからない。鈴花自身は送った覚えはない。
だが、喜びに震え、身の内に言い表せないほどの感情を滾らせて収録ブースの中の高瀬臣を見つめていると、不意に脳裏にジン様の顔がよぎった。
高瀬臣そっくりの姿をしているが、似て非なる、お茶目な神様。鈴花の影響ですっかり俗物に染まり切ったあの神が、「ワシじゃ」と言ってピースサインをしている姿が浮かんだ。
「……ジン様‼︎」
思いもかけないサプライズプレゼントに、鈴花はただ手を合わせて拝むことしかできなかった。