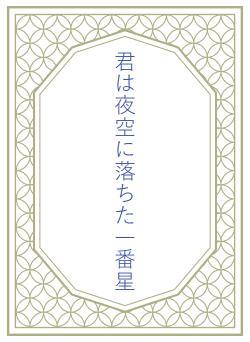数日後――僕は、放課後に美術室の隣を通りがかった。
そこは演劇部の物置にもなっていて、小道具や衣装のダンボールが積まれていて、その時何故なのかわからないけど足が止まった。
開け放たれたドアの中で人の気配はなかった。けれど、入口近くの棚に一冊のファイルが無造作に置かれているのが見えたから。
何気なく覗き込んだそのファイルには【脚本案】と書かれたラベル。思わず開いてみると、中には手書きの文章がびっしりと綴られていた。
舞台台本のような形式ではなく、モノローグや情景描写。まるで誰かの内面を吐き出したような、そんな一節。
そして、ページの中ほどに、見覚えのある筆跡で書かれた言葉があった。
**
あの人の無防備な背中を見てると、声をかけたくなる。
触れたくなる。
……でも、それはきっと、届かない想いだ。
**
僕は、その文字を読んで息を呑んでしまった。
その【あの人】が誰なのか、わからないはずなのに――なぜか、わかってしまったのだ。
これは、続きだ。あの【脚本】と称された手紙の、その先――フィクションだと言いながら、なぜ彼は、こんなにも繊細に相手の癖や存在を見ていられるんだろう。
嘘にしては、優しすぎた。
物語にしては、切なすぎた。
心の奥がじんわりと熱くなる。
僕はそっとファイルを閉じて、何もなかったフリをして、その場を離れた。
▽ ▽ ▽
僕は、もうずっと考えていた。
あの手紙の事と、【脚本】だと言い張ったあのラブレターのような文章と、図書室で見つけた続きのような独白。そして、最近の金森君のあの態度。
彼は、僕に話しかけてくるようになった。気づけば何かと理由をつけて近くに現れては少しだけくだけた言い方で笑ってくれる。
でも、もしあれが【演技】なんだとしたら?
誰にでも見せている人気者の仮面と同じだとしたら?
……それでも、僕は、彼の素顔を知りたかった。不思議と、知りたくなってしまった。
知ってしまったからには、もう戻れない。
だから、僕は屋上に彼を呼び出した。
その日の放課後、日が傾きかけた頃――冬の風がちょっとだけ冷たくて、でも空が透き通って見える時間。
金森君は、制服のままやってきた。僕を見るなり。
「えっと……何か用?」
そのように言いながら小さく笑ったけれど、その目は、冗談を言っているときのそれじゃなかった。
ちゃんと、僕を見ている目――僕は、胸ポケットに入れてきた封筒を取り出して、彼に見せた。
「あの、えっと……あのラブレー田、本当は脚本じゃなかったり、する?
風が一瞬、僕の声をさらっていった。
僕のその言葉を聞いた金森君は目を瞬かせて、そして黙った。
黙ったまま視線をそらして、静かに言う。
「……どうして、そう思う?」
「それは……えっと、これは僕が思った事、なんだけど……モデルってあの時言ってたけど、あんなに細かいところ演出で書けるわけない、と思う……誰かを、ずっと見てなきゃ気づかないことばかりだったから」
彼は視線をそらして、屋上のフェンスの向こうに目をやった。
「……一ノ瀬くん」
「嬉しかったんだ、正直。あんな風に書かれたの、初めてだったんだ……自分でも気づかないようなところ、誰かに見つけてもらってたんだって……思った」
僕の言葉を聞いた金森君はしばらく黙っていた。
そして、ぽつりと、まるで独り言のように言った。
「――俺、多分さ……本当は、誰かに気づいてほしかったんだよ」
風が吹くたびに、彼の髪が揺れた。
「誰かを見てたフリして、本当は俺の方が、見られたかった。嘘でも脚本でもいいからそうやって自分の気持ちを置いておけば、誰かに拾ってもらえる気がしてた」
僕は彼の言葉を、黙って聞いていた。
目の前にいるのは、【金森梓】という完成された像じゃない。誰かの期待に応えるために作った仮面でもない。
ちゃんと、傷ついたり、不安になったりしている一人の人間だった。
「……ねえ、一ノ瀬くん」
彼はようやく僕を見た。
「もし、あれが【本音】だったとしたら……君は、どうする?」
答えが喉元まで出かかったはずなのに。
だけど、どうしても言葉にならなかった。
――だって、僕の気持ちも、まだ答えを出せていなかったから。
戸惑いもあったし、怖さもあった。なによりこれが【恋】なのか、それともただの【憧れ】なのかも、僕にはわからなかった。
だから、僕は少しだけ笑って、首を横に振った。
「わからない……でも、嘘じゃないなら、それだけでいいと思う、よ」
それを聞いた金森君は目を伏せて、ふっと笑った。
その笑みは、これまでのどれとも違っており、まるでどこか安心したような、疲れが抜けたような――そんな、やわらかい笑顔に見えた。
金森君はそのまま、彼は何も言わずに背を向けて屋上の出入り口へと歩き出した。
遠ざかる背中に、声をかけるべきか、何度も迷ったけれど――結局、何も言えなかった。
僕の中で何かが動き出した気がしたのに、言葉にするにはまだ早すぎたと感じたから。
▽ ▽ ▽
翌日、金森梓は学校に来なかった。
最初は、ただの欠席だと思った。風邪か、用事か。彼なら、どちらでも不思議じゃない。
でも、次の日も、その次の日も、彼の席は空いたままだった。
窓際の一番後ろ。いつも誰かが集まって、笑い声が絶えなかった場所がまるで最初から誰も座っていなかったみたいに、静かだった。
「金森、どうしたんだろうな」
クラスメイトのそんな声が、他人事みたいに聞こえる。
「家庭の事情らしいよ」
「転校じゃない?」
「また戻ってくるでしょ」
どれも、はっきりしない噂ばかりだった。
僕は何も言えず、ただノートに視線を落とした。ページの上で、シャーペンの先が止まったまま、文字にならない線だけが増えていく。
(――この前、ちゃんと話したばかりなのに)
屋上での会話が、頭の中で何度も繰り返される。そして思い出したのはあの時の少しだけ安心したような彼の笑顔。
もし、あれが最後になるって知っていたら。
もし、もう会えないって分かっていたら。
……僕は、何か言えただろうか?
▽ ▽ ▽
放課後、気づけば僕は図書室にいた。
いつも通りの静けさ。でも、胸の奥が、妙に落ち着かなかった。
本棚の間を歩いていると、ふと、以前金森君が立っていた場所に目が行く。彼が、あの封筒を書いていたかもしれない席。
僕は思わず、そして無意識に、演劇部の物置のほうへ足が向いていた。
もう関係ないはずなのに、そう思いながらも体は勝手に動いていた。
扉は、少しだけ開いていた。
中に入ると、誰もいない。段ボールの隙間、積まれた小道具。その奥の棚に見覚えのあるファイルが置かれていた。
――脚本案。
僕は周囲を確認してから、そっとそれを手に取った。
ページをめくる。
そこには、以前読んだものよりも整理された文章が並んでいた。
書き直された台詞。
削られた言葉。
迷いの跡。
まるで、誰かに見せる前に、何度も自分の心を削っていったみたいだった。
そして、一番最後のページ―ーそこは、白紙だった。
……いや、よく見ると、鉛筆で薄く、消された跡が残っている。
読み取れるのは、かろうじて一行だけ、それが見えたんだ。
**
好き、って言葉じゃない何かで、伝えられたらいいのに。
**
(…………え?)
たったその一文字だけなのに、僕の胸が、ぎゅっと締めつけられた。
ああ、やっぱり。
やっぱり、あれは【脚本】なんかじゃなかった。
言葉にできない感情を、物語に逃がして、置き去りにしただけだったんだ。
僕は、ファイルを閉じると同時に、自分の指先が少し震えていた。
「……僕が、続きを書けたらいいのに」
誰に聞かせるでもなく、そう呟いた。
もし、彼がここにいたら、この言葉を、聞いてくれただろうか?
それとも、また困ったように笑って、「脚本だよ」って、嘘を重ねただろうか?
――わからない。
でも、確かなのは――金森君は、もうここにはいないという事だった。
その日の帰り道、夕焼けが校舎を赤く染めていた。
彼がいない世界は、こんなにも静かで、こんなにも色が薄かったんだと、初めて気づいた。
▽ ▽ ▽
――春が来た。
制服の上着を脱いで歩けるようになった頃、進級の発表が貼り出され、教室もクラスも変わった。周囲の顔ぶれも、少し変わった。
けれど、変わらないものもあった。
図書室の静けさと、風の抜ける屋上のフェンス。
そして、僕の胸の奥にまだ温度を持って残っている名前――金森梓。
それから、あのファイルの最後の一行。
『好き、って言葉じゃない何かで、伝えられたらいいのに』
伝えられなかった言葉は、今も僕の中で生きている。
思い出すたびに、少しだけ痛くて、少しだけ優しい。
「……金森君、元気でいるかな」
ぽつりと呟いた声が、誰にも聞かれずに教室の窓から風に流れていく。
どうやら親の都合で転校してしまった事を、のちに担任から聞いた。
あの放課後以来、僕は金森君に会っていない。
でも、僕は覚えている。
彼が笑った顔も、苦しそうに目をそらした横顔も、演技じゃないあの瞬間の瞳も。
僕だけが知っている『金森梓』がいる。
そして、校内掲示板の前を通った時、目に留まったポスターがあった。
《演劇部・春の特別公演「透明な手紙」》
脚本:Y.S
Special thanks to M.I.
脚本家の名前には見覚えがなかった。
けれど、その下に書かれた「M.I.」の文字に心臓が跳ねた。
僕の名前のイニシャル――Ichinose, Makoto。
偶然、かもしれない。深読みのしすぎかもしれない。
でも、胸の奥が熱くなった。まるで、どこか遠くから声をかけられたみたいに。
僕は教室の窓から空を見上げる。
優しい春の光の中、薄く白い雲が流れていく。
「……金森君へ」
僕は静かに笑いながら、便箋に彼の名前を書く。
いつか、再会した時に彼に読んでもらう為に、僕は描き続ける。
君の手紙の返事を必ず。
「――ぼくも、きみがすきです」
そこは演劇部の物置にもなっていて、小道具や衣装のダンボールが積まれていて、その時何故なのかわからないけど足が止まった。
開け放たれたドアの中で人の気配はなかった。けれど、入口近くの棚に一冊のファイルが無造作に置かれているのが見えたから。
何気なく覗き込んだそのファイルには【脚本案】と書かれたラベル。思わず開いてみると、中には手書きの文章がびっしりと綴られていた。
舞台台本のような形式ではなく、モノローグや情景描写。まるで誰かの内面を吐き出したような、そんな一節。
そして、ページの中ほどに、見覚えのある筆跡で書かれた言葉があった。
**
あの人の無防備な背中を見てると、声をかけたくなる。
触れたくなる。
……でも、それはきっと、届かない想いだ。
**
僕は、その文字を読んで息を呑んでしまった。
その【あの人】が誰なのか、わからないはずなのに――なぜか、わかってしまったのだ。
これは、続きだ。あの【脚本】と称された手紙の、その先――フィクションだと言いながら、なぜ彼は、こんなにも繊細に相手の癖や存在を見ていられるんだろう。
嘘にしては、優しすぎた。
物語にしては、切なすぎた。
心の奥がじんわりと熱くなる。
僕はそっとファイルを閉じて、何もなかったフリをして、その場を離れた。
▽ ▽ ▽
僕は、もうずっと考えていた。
あの手紙の事と、【脚本】だと言い張ったあのラブレターのような文章と、図書室で見つけた続きのような独白。そして、最近の金森君のあの態度。
彼は、僕に話しかけてくるようになった。気づけば何かと理由をつけて近くに現れては少しだけくだけた言い方で笑ってくれる。
でも、もしあれが【演技】なんだとしたら?
誰にでも見せている人気者の仮面と同じだとしたら?
……それでも、僕は、彼の素顔を知りたかった。不思議と、知りたくなってしまった。
知ってしまったからには、もう戻れない。
だから、僕は屋上に彼を呼び出した。
その日の放課後、日が傾きかけた頃――冬の風がちょっとだけ冷たくて、でも空が透き通って見える時間。
金森君は、制服のままやってきた。僕を見るなり。
「えっと……何か用?」
そのように言いながら小さく笑ったけれど、その目は、冗談を言っているときのそれじゃなかった。
ちゃんと、僕を見ている目――僕は、胸ポケットに入れてきた封筒を取り出して、彼に見せた。
「あの、えっと……あのラブレー田、本当は脚本じゃなかったり、する?
風が一瞬、僕の声をさらっていった。
僕のその言葉を聞いた金森君は目を瞬かせて、そして黙った。
黙ったまま視線をそらして、静かに言う。
「……どうして、そう思う?」
「それは……えっと、これは僕が思った事、なんだけど……モデルってあの時言ってたけど、あんなに細かいところ演出で書けるわけない、と思う……誰かを、ずっと見てなきゃ気づかないことばかりだったから」
彼は視線をそらして、屋上のフェンスの向こうに目をやった。
「……一ノ瀬くん」
「嬉しかったんだ、正直。あんな風に書かれたの、初めてだったんだ……自分でも気づかないようなところ、誰かに見つけてもらってたんだって……思った」
僕の言葉を聞いた金森君はしばらく黙っていた。
そして、ぽつりと、まるで独り言のように言った。
「――俺、多分さ……本当は、誰かに気づいてほしかったんだよ」
風が吹くたびに、彼の髪が揺れた。
「誰かを見てたフリして、本当は俺の方が、見られたかった。嘘でも脚本でもいいからそうやって自分の気持ちを置いておけば、誰かに拾ってもらえる気がしてた」
僕は彼の言葉を、黙って聞いていた。
目の前にいるのは、【金森梓】という完成された像じゃない。誰かの期待に応えるために作った仮面でもない。
ちゃんと、傷ついたり、不安になったりしている一人の人間だった。
「……ねえ、一ノ瀬くん」
彼はようやく僕を見た。
「もし、あれが【本音】だったとしたら……君は、どうする?」
答えが喉元まで出かかったはずなのに。
だけど、どうしても言葉にならなかった。
――だって、僕の気持ちも、まだ答えを出せていなかったから。
戸惑いもあったし、怖さもあった。なによりこれが【恋】なのか、それともただの【憧れ】なのかも、僕にはわからなかった。
だから、僕は少しだけ笑って、首を横に振った。
「わからない……でも、嘘じゃないなら、それだけでいいと思う、よ」
それを聞いた金森君は目を伏せて、ふっと笑った。
その笑みは、これまでのどれとも違っており、まるでどこか安心したような、疲れが抜けたような――そんな、やわらかい笑顔に見えた。
金森君はそのまま、彼は何も言わずに背を向けて屋上の出入り口へと歩き出した。
遠ざかる背中に、声をかけるべきか、何度も迷ったけれど――結局、何も言えなかった。
僕の中で何かが動き出した気がしたのに、言葉にするにはまだ早すぎたと感じたから。
▽ ▽ ▽
翌日、金森梓は学校に来なかった。
最初は、ただの欠席だと思った。風邪か、用事か。彼なら、どちらでも不思議じゃない。
でも、次の日も、その次の日も、彼の席は空いたままだった。
窓際の一番後ろ。いつも誰かが集まって、笑い声が絶えなかった場所がまるで最初から誰も座っていなかったみたいに、静かだった。
「金森、どうしたんだろうな」
クラスメイトのそんな声が、他人事みたいに聞こえる。
「家庭の事情らしいよ」
「転校じゃない?」
「また戻ってくるでしょ」
どれも、はっきりしない噂ばかりだった。
僕は何も言えず、ただノートに視線を落とした。ページの上で、シャーペンの先が止まったまま、文字にならない線だけが増えていく。
(――この前、ちゃんと話したばかりなのに)
屋上での会話が、頭の中で何度も繰り返される。そして思い出したのはあの時の少しだけ安心したような彼の笑顔。
もし、あれが最後になるって知っていたら。
もし、もう会えないって分かっていたら。
……僕は、何か言えただろうか?
▽ ▽ ▽
放課後、気づけば僕は図書室にいた。
いつも通りの静けさ。でも、胸の奥が、妙に落ち着かなかった。
本棚の間を歩いていると、ふと、以前金森君が立っていた場所に目が行く。彼が、あの封筒を書いていたかもしれない席。
僕は思わず、そして無意識に、演劇部の物置のほうへ足が向いていた。
もう関係ないはずなのに、そう思いながらも体は勝手に動いていた。
扉は、少しだけ開いていた。
中に入ると、誰もいない。段ボールの隙間、積まれた小道具。その奥の棚に見覚えのあるファイルが置かれていた。
――脚本案。
僕は周囲を確認してから、そっとそれを手に取った。
ページをめくる。
そこには、以前読んだものよりも整理された文章が並んでいた。
書き直された台詞。
削られた言葉。
迷いの跡。
まるで、誰かに見せる前に、何度も自分の心を削っていったみたいだった。
そして、一番最後のページ―ーそこは、白紙だった。
……いや、よく見ると、鉛筆で薄く、消された跡が残っている。
読み取れるのは、かろうじて一行だけ、それが見えたんだ。
**
好き、って言葉じゃない何かで、伝えられたらいいのに。
**
(…………え?)
たったその一文字だけなのに、僕の胸が、ぎゅっと締めつけられた。
ああ、やっぱり。
やっぱり、あれは【脚本】なんかじゃなかった。
言葉にできない感情を、物語に逃がして、置き去りにしただけだったんだ。
僕は、ファイルを閉じると同時に、自分の指先が少し震えていた。
「……僕が、続きを書けたらいいのに」
誰に聞かせるでもなく、そう呟いた。
もし、彼がここにいたら、この言葉を、聞いてくれただろうか?
それとも、また困ったように笑って、「脚本だよ」って、嘘を重ねただろうか?
――わからない。
でも、確かなのは――金森君は、もうここにはいないという事だった。
その日の帰り道、夕焼けが校舎を赤く染めていた。
彼がいない世界は、こんなにも静かで、こんなにも色が薄かったんだと、初めて気づいた。
▽ ▽ ▽
――春が来た。
制服の上着を脱いで歩けるようになった頃、進級の発表が貼り出され、教室もクラスも変わった。周囲の顔ぶれも、少し変わった。
けれど、変わらないものもあった。
図書室の静けさと、風の抜ける屋上のフェンス。
そして、僕の胸の奥にまだ温度を持って残っている名前――金森梓。
それから、あのファイルの最後の一行。
『好き、って言葉じゃない何かで、伝えられたらいいのに』
伝えられなかった言葉は、今も僕の中で生きている。
思い出すたびに、少しだけ痛くて、少しだけ優しい。
「……金森君、元気でいるかな」
ぽつりと呟いた声が、誰にも聞かれずに教室の窓から風に流れていく。
どうやら親の都合で転校してしまった事を、のちに担任から聞いた。
あの放課後以来、僕は金森君に会っていない。
でも、僕は覚えている。
彼が笑った顔も、苦しそうに目をそらした横顔も、演技じゃないあの瞬間の瞳も。
僕だけが知っている『金森梓』がいる。
そして、校内掲示板の前を通った時、目に留まったポスターがあった。
《演劇部・春の特別公演「透明な手紙」》
脚本:Y.S
Special thanks to M.I.
脚本家の名前には見覚えがなかった。
けれど、その下に書かれた「M.I.」の文字に心臓が跳ねた。
僕の名前のイニシャル――Ichinose, Makoto。
偶然、かもしれない。深読みのしすぎかもしれない。
でも、胸の奥が熱くなった。まるで、どこか遠くから声をかけられたみたいに。
僕は教室の窓から空を見上げる。
優しい春の光の中、薄く白い雲が流れていく。
「……金森君へ」
僕は静かに笑いながら、便箋に彼の名前を書く。
いつか、再会した時に彼に読んでもらう為に、僕は描き続ける。
君の手紙の返事を必ず。
「――ぼくも、きみがすきです」