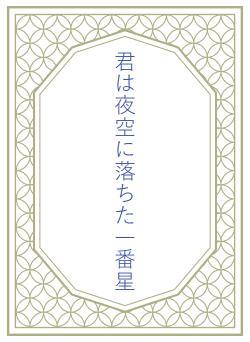その日、いつものように図書室へ寄ったのは、ただの習慣だった。
静かで、誰にも気を遣わなくて済む場所。ここは僕にとって図書室は避難所みたいなものだ。読む本も決まっておらず、目についた背表紙を適当に抜いてただ静けさを吸い込む。
けれど、その日だけは少し違った。
本棚の間を歩いていると、いつも座っている窓際の机に、何かが置かれているのが見えたので思わず視線を向けると、そきに置いてあったのは白い封筒だった。
ちょっと厚みのある便箋が入っているらしく、角が少し浮いている。図書室で手紙なんて僕は見たことがない。しかも、よく見ればその封筒の表に、何かが書かれていた。
《To:一ノ瀬まこと》
(……え?)
僕の名前が書いてあったことに驚いたので、一瞬にして体が固まってしまった。
そして思わず封筒を、そっと手に取る。
何度も確認してしまったが間違いなくそれは自分の名前だった。しかも、綺麗な筆記体のような、丁寧な手書きの文字。明らかに教師の字ではなければ女子の筆跡でもない。どこか、無機質だけど美しくて綺麗だ。
僕は周りを見渡してみてみたけれど誰もいない
どうして、自分宛の手紙がここに……?
いたずら?
それとも、間違い?
もう一度確認してみたが、封はされていなかった。少しだけためらいながら、それからそっと中を覗いてみると、中には折りたたまれた一枚の便箋。
申し訳ないなとも思いながら便箋を広げると、そこに綴られていたのは――まるで、ラブレターのような文章だった。
▽ ▽ ▽
一ノ瀬まことくん。
君の癖を、ひとつずつ拾い集めてしまう自分がいる。
授業中、無意識に左の頬を掻くこと。
教科書を読むとき、指先でページをなぞること。
笑うとき、目尻の奥が少しだけ緩むのに、自分では気づいていないこと。
▽ ▽ ▽
「ひぇっ!?」
……なんで。
なんで、そんなことまで……。
僕しか知らないはずの、癖や無意識の動作。教室の誰も見ていない僕の一部分――いたずらにしては、内容がやけに丁寧で、観察が細かすぎる。思わず叫んでしまった。
そもそも、こんなものを書く意味がある?
喉が少しだけ渇いて、舌打ちするように息を吐く。
でも――ふと、思い出した。
今日の昼休み、この席に先に誰かが座っていた気がする。あの時にちらっと見えた後ろ姿――名前は確か金森梓くんだ。
学年でも有名な、美形の男子。話したことはない。でも、クラスが近いから顔だけはよく知っている。
その彼が、この席にいた。何か書いていた。
……封筒だったかは、覚えていない。
いや……まさかね。僕なんかに、あんな人が手紙を書くわけがない。自意識過剰。偶然だ。間違いに決まってる。
僕はそっと便箋を封筒に戻し、鞄にしまう。そして気のせいだ。たぶん、何かの間違いだ、と納得つける。
つけるのだが……だけど。
その日から、僕の退屈な日常は、少しずつ音を立てて動き始めた。
▽ ▽ ▽
翌朝、教室に入ると、金森君は既に席についていた。
窓側の一番後ろ。目立つ位置だけど、彼はそれが当然というように自然にそこにいる。机に肘をつき、頬杖をついたまま、クラスメイトの話に笑顔で応じているその横顔はまるでポスターから切り抜いたように整っていた。
うん、やっぱり彼は別世界の人間だ。
それなのに、僕は彼の事を【観察する】なんて、まるで犯人探しみたいな真似をしているみたいじゃないか。
鞄の中には、昨日のあの封筒が入っており、取り出すこともできず、でも持っていないと落ち着かない。
彼の笑い声が聞こえるたびに、胸がざわついた。
この手紙は、本物なのだろうか?
でも、どうしてあんなに僕の癖や仕草を正確に書ける?
誰かのモデルって、あんなふうに細部まで書くものだろうか?
……僕が気づかない間に、誰かが、ずっと僕を見ていた?
そんな考えにたどり着きそうになって、首を振る。
違う違う。たぶん偶然だ。自意識過剰もいいところだ。
……でも、金森君が書いたものだという直感だけは、なぜか拭えなかった。
それから放課後。いつも通りに帰ろうと思って、校舎の裏手を抜けようとしただけだった。
だけど――ふと足が止まった。
視界の隅に、演劇部の部室のドアが見えたからだ。そこは普段あまり通らない場所。まして僕には縁のない空間だった。
金森君は演劇部だ。そして、その中で力を入れて部活を頑張っている姿を何度か見た事がある。
相変わらず少しだけ意識している僕がいるからなのか、つい金森君がいるのかどうか気になってしまう――いや、これは流石に僕やばいのではないだろうかと思いながら、多分青ざめた顔をしていたのかもしれない。
何気なく部室の前を横切ろうとしたその時だった。
「……あ、それ、俺の」
「え……?」
「昨日、図書室で拾った?」
突然、すぐ近くで声がして、心臓が跳ねた。
目の前から聞こえてきた声に驚いて立ち止まり、ゆっくりと顔を上げる。そこに立っていたのは、金森梓君――間違いなく、その人だった。
制服の袖をまくり、鞄を肩に掛けたまま、ドアの横に寄りかかるようにしてこちらを見ている。
びっくりしてしまった――初めて、目が合った。
教室の中で何度も見かけていたけど、こうして真正面から視線が交わるのは初めてだったから、驚いた顔をしていたかもしれない。
僕は何も答えられず、声というより息が漏れただけだった。反射的に鞄をぎゅっと抱きしめる。
彼の視線が、鞄の中に向けられていることに気づいた――たぶん、封筒の形に気づいたんだ。
「多分それ、俺のだと思うんだよね。昨日図書室の机に置きっぱにしちゃって……ちょっと恥ずかしいけど」
そう言って、金森はふっと笑っていた。僕に目を向けて。
あの笑顔――いつも教室で浮かべているような完璧な笑みと同じ。でも、何故かその時、今は僕一人に向けられているように感じた。
僕はようやく、声を振り絞るように口を開いた。
「……なんで、僕の……名前が書いてあったの」
声が震えており、いや降りえてしまっていた。けれど、訊かずにはいられなかった。昨日、僕はあの文章に触れてしまった。
名前も、癖も、誰にも見せていないはずの細かい仕草まで――まるで、全部を見られていたみたいで。他人の名前を使って、あんな手紙を書くなんて、悪質ないたずらか、もしくは……でも彼は、落ち着いた声で答えた。
「ああ……あれ、脚本の一部なんだ」
僕は一瞬、言葉の意味がうまく頭に入ってこなかった。
金森君は眉を少し下げて、困ったような笑みを浮かべる。
「演劇部で今、いくつか案を出しててさ。その中の一つにちょっとそういう……モノローグっぽい手紙のパートがあるんだよね」
彼の口調は軽かった。
でも、その目は、僕の反応をじっと観察していた。
「実は君の事、ちょっとモデルにさせてもらってた……勝手にごめん」
「……モデル?」
「うん。教室での佇まいとか、ノートの取り方とか、癖……静かで綺麗なんだ、動きが。物語にしたくなるっていうか……そういうのがあるんだよ」
穏やかに語られるその言葉に、僕は何も返せなかった。
彼が、僕のことを【綺麗】だなんて――そんな言葉、初めて言われた。しかも、それを表情ひとつ変えずに、さらりと口にする。
……嘘にしては、丁寧すぎる。そして冗談にしては、やけにまっすぐすぎる。
僕は目をそらして、唇を噛んだ。
脚本――あれは手紙ではなく、ただの創作だと言う事を。僕の名前が書かれていたのも、たまたま。深い意味なんてない。
……そう思えば、全部に説明がつく。
どうやら、僕は勘違いをしていたらしい。恥ずかしくてたまらなかった。
「……そっか、脚本……なんだ、びっくりしちゃったよ」
なんとか言葉を出して、ぎこちなく笑ってみせた。
でも、その笑顔はきっと、うまく形になっていなかったと思う。胸の奥が、ざわざわと騒がしかった。
違う。何かが、違う気がする。
あの手紙は、本当にただの【物語】だったのか?
それとも、彼が言えなかった何かの、形を変えた【何か】だったのか――答えはわからない。聞き返す勇気もなかったから。
「じゃあ……」
そう言って、僕は頭を下げて、金森君の隣をすり抜けるようにして歩き出した。
背中に、金森の小さなため息のような吐息が聞こえた気がしたけど、僕はそれに対して振り返ることはできなかった。
▽ ▽ ▽
翌日から金森君は妙に【僕】に気づくようになった。
教室に入ると、彼の視線とふと目が合う。すぐに逸らされるのかと思えば、彼はほんの少しだけ口の端を上げて、目だけで笑った。
なんでもない、当たり前の挨拶みたいに。
……けれど、僕にとってはまるで別世界のことだった。
そしてその数日後、彼は僕の名前を呼んだ。
「一ノ瀬くん、図書室また行くの?」
帰り支度をしていたとき、後ろからそんな声が飛んできて、思わず立ち止まった。思わず振り返ってみると、金森君が教室の出入り口に立っていた。
「……うん。たぶん」
「へぇ。俺も本返さなきゃなんだよね。ついでに一緒に行っていい?」
彼はそう言って、まるで友達と話すみたいな調子で笑う。友達ではないはずなのだが……。
たったそれだけの会話なのに、僕の胸はざわついていた。この距離感は、どういう意味なんだろう。
演劇部で使う【モデル】としての興味?
それとも、まだ【脚本】の延長線?
よくわからなかった。でも、少なくとも、彼が誰かと関わろうとしているのは確かだった。それが、地味で平凡な【存在】に向けられているのだとしたら――戸惑いながらも、嫌じゃないと思ってしまう自分がいた。
▽ ▽ ▽
放課後の図書室は、相変わらず静かだった。
彼と並んで歩くことにまだ慣れていない僕は、少し後ろを歩くようにして扉を開ける。すると誰もいない空間に、書棚をめくる紙の音だけが響く。
返却ボックスに本を入れたあと、金森君は手に持っていた冊子をぽんとカウンターに置いた。
「……一ノ瀬くんってさ、あの時俺に聞いたよね。『なんで僕の名前が――』って」
彼は僕の方を見ないまま、ぽつりと呟いた。
僕は一瞬、何の話か分からずに固まってしまったけれど、すぐに、あの封筒のことだと気づく。
金森君は、続ける。
「俺さ、本当は人と話すの、苦手なんだよね」
「……え?」
「でも、【金森梓】ってキャラに、周りが勝手に期待してるっていうか……笑っていれば安心されるし、誰にでも合わせておけば波風立たない」
金森君のその言葉のひとつひとつが、妙に冷たく感じたのは気のせいだろうか?
でも、その冷たさの奥にある【疲れ】みたいなものが、耳に残る。
「多分、そういうの、もう慣れちゃったんだと思う。だから誰かのこと、本当の意味でちゃんと見るのって、最近は……あんまりしてなかった」
僕は何も言えず、ただ黙ってしまった。
でも彼の声は、なぜかそこだけ、真っ直ぐで――誰にも言えなかった【本音】のように聞こえた。
僕は静かに頷いてしまった。
「……わかる、気がする……僕も、似たようなとこあるから」
そう呟いた声は、自分でも意外なほど、自然だった。
すると、金森君は僕の方を見た。
そして、少しだけ目を細めて――けれど、その表情は笑っていなかった。
まるで、見透かされたみたいで、何処か気持ち悪く感じてしまったなんて、死んでも言えない。
静かで、誰にも気を遣わなくて済む場所。ここは僕にとって図書室は避難所みたいなものだ。読む本も決まっておらず、目についた背表紙を適当に抜いてただ静けさを吸い込む。
けれど、その日だけは少し違った。
本棚の間を歩いていると、いつも座っている窓際の机に、何かが置かれているのが見えたので思わず視線を向けると、そきに置いてあったのは白い封筒だった。
ちょっと厚みのある便箋が入っているらしく、角が少し浮いている。図書室で手紙なんて僕は見たことがない。しかも、よく見ればその封筒の表に、何かが書かれていた。
《To:一ノ瀬まこと》
(……え?)
僕の名前が書いてあったことに驚いたので、一瞬にして体が固まってしまった。
そして思わず封筒を、そっと手に取る。
何度も確認してしまったが間違いなくそれは自分の名前だった。しかも、綺麗な筆記体のような、丁寧な手書きの文字。明らかに教師の字ではなければ女子の筆跡でもない。どこか、無機質だけど美しくて綺麗だ。
僕は周りを見渡してみてみたけれど誰もいない
どうして、自分宛の手紙がここに……?
いたずら?
それとも、間違い?
もう一度確認してみたが、封はされていなかった。少しだけためらいながら、それからそっと中を覗いてみると、中には折りたたまれた一枚の便箋。
申し訳ないなとも思いながら便箋を広げると、そこに綴られていたのは――まるで、ラブレターのような文章だった。
▽ ▽ ▽
一ノ瀬まことくん。
君の癖を、ひとつずつ拾い集めてしまう自分がいる。
授業中、無意識に左の頬を掻くこと。
教科書を読むとき、指先でページをなぞること。
笑うとき、目尻の奥が少しだけ緩むのに、自分では気づいていないこと。
▽ ▽ ▽
「ひぇっ!?」
……なんで。
なんで、そんなことまで……。
僕しか知らないはずの、癖や無意識の動作。教室の誰も見ていない僕の一部分――いたずらにしては、内容がやけに丁寧で、観察が細かすぎる。思わず叫んでしまった。
そもそも、こんなものを書く意味がある?
喉が少しだけ渇いて、舌打ちするように息を吐く。
でも――ふと、思い出した。
今日の昼休み、この席に先に誰かが座っていた気がする。あの時にちらっと見えた後ろ姿――名前は確か金森梓くんだ。
学年でも有名な、美形の男子。話したことはない。でも、クラスが近いから顔だけはよく知っている。
その彼が、この席にいた。何か書いていた。
……封筒だったかは、覚えていない。
いや……まさかね。僕なんかに、あんな人が手紙を書くわけがない。自意識過剰。偶然だ。間違いに決まってる。
僕はそっと便箋を封筒に戻し、鞄にしまう。そして気のせいだ。たぶん、何かの間違いだ、と納得つける。
つけるのだが……だけど。
その日から、僕の退屈な日常は、少しずつ音を立てて動き始めた。
▽ ▽ ▽
翌朝、教室に入ると、金森君は既に席についていた。
窓側の一番後ろ。目立つ位置だけど、彼はそれが当然というように自然にそこにいる。机に肘をつき、頬杖をついたまま、クラスメイトの話に笑顔で応じているその横顔はまるでポスターから切り抜いたように整っていた。
うん、やっぱり彼は別世界の人間だ。
それなのに、僕は彼の事を【観察する】なんて、まるで犯人探しみたいな真似をしているみたいじゃないか。
鞄の中には、昨日のあの封筒が入っており、取り出すこともできず、でも持っていないと落ち着かない。
彼の笑い声が聞こえるたびに、胸がざわついた。
この手紙は、本物なのだろうか?
でも、どうしてあんなに僕の癖や仕草を正確に書ける?
誰かのモデルって、あんなふうに細部まで書くものだろうか?
……僕が気づかない間に、誰かが、ずっと僕を見ていた?
そんな考えにたどり着きそうになって、首を振る。
違う違う。たぶん偶然だ。自意識過剰もいいところだ。
……でも、金森君が書いたものだという直感だけは、なぜか拭えなかった。
それから放課後。いつも通りに帰ろうと思って、校舎の裏手を抜けようとしただけだった。
だけど――ふと足が止まった。
視界の隅に、演劇部の部室のドアが見えたからだ。そこは普段あまり通らない場所。まして僕には縁のない空間だった。
金森君は演劇部だ。そして、その中で力を入れて部活を頑張っている姿を何度か見た事がある。
相変わらず少しだけ意識している僕がいるからなのか、つい金森君がいるのかどうか気になってしまう――いや、これは流石に僕やばいのではないだろうかと思いながら、多分青ざめた顔をしていたのかもしれない。
何気なく部室の前を横切ろうとしたその時だった。
「……あ、それ、俺の」
「え……?」
「昨日、図書室で拾った?」
突然、すぐ近くで声がして、心臓が跳ねた。
目の前から聞こえてきた声に驚いて立ち止まり、ゆっくりと顔を上げる。そこに立っていたのは、金森梓君――間違いなく、その人だった。
制服の袖をまくり、鞄を肩に掛けたまま、ドアの横に寄りかかるようにしてこちらを見ている。
びっくりしてしまった――初めて、目が合った。
教室の中で何度も見かけていたけど、こうして真正面から視線が交わるのは初めてだったから、驚いた顔をしていたかもしれない。
僕は何も答えられず、声というより息が漏れただけだった。反射的に鞄をぎゅっと抱きしめる。
彼の視線が、鞄の中に向けられていることに気づいた――たぶん、封筒の形に気づいたんだ。
「多分それ、俺のだと思うんだよね。昨日図書室の机に置きっぱにしちゃって……ちょっと恥ずかしいけど」
そう言って、金森はふっと笑っていた。僕に目を向けて。
あの笑顔――いつも教室で浮かべているような完璧な笑みと同じ。でも、何故かその時、今は僕一人に向けられているように感じた。
僕はようやく、声を振り絞るように口を開いた。
「……なんで、僕の……名前が書いてあったの」
声が震えており、いや降りえてしまっていた。けれど、訊かずにはいられなかった。昨日、僕はあの文章に触れてしまった。
名前も、癖も、誰にも見せていないはずの細かい仕草まで――まるで、全部を見られていたみたいで。他人の名前を使って、あんな手紙を書くなんて、悪質ないたずらか、もしくは……でも彼は、落ち着いた声で答えた。
「ああ……あれ、脚本の一部なんだ」
僕は一瞬、言葉の意味がうまく頭に入ってこなかった。
金森君は眉を少し下げて、困ったような笑みを浮かべる。
「演劇部で今、いくつか案を出しててさ。その中の一つにちょっとそういう……モノローグっぽい手紙のパートがあるんだよね」
彼の口調は軽かった。
でも、その目は、僕の反応をじっと観察していた。
「実は君の事、ちょっとモデルにさせてもらってた……勝手にごめん」
「……モデル?」
「うん。教室での佇まいとか、ノートの取り方とか、癖……静かで綺麗なんだ、動きが。物語にしたくなるっていうか……そういうのがあるんだよ」
穏やかに語られるその言葉に、僕は何も返せなかった。
彼が、僕のことを【綺麗】だなんて――そんな言葉、初めて言われた。しかも、それを表情ひとつ変えずに、さらりと口にする。
……嘘にしては、丁寧すぎる。そして冗談にしては、やけにまっすぐすぎる。
僕は目をそらして、唇を噛んだ。
脚本――あれは手紙ではなく、ただの創作だと言う事を。僕の名前が書かれていたのも、たまたま。深い意味なんてない。
……そう思えば、全部に説明がつく。
どうやら、僕は勘違いをしていたらしい。恥ずかしくてたまらなかった。
「……そっか、脚本……なんだ、びっくりしちゃったよ」
なんとか言葉を出して、ぎこちなく笑ってみせた。
でも、その笑顔はきっと、うまく形になっていなかったと思う。胸の奥が、ざわざわと騒がしかった。
違う。何かが、違う気がする。
あの手紙は、本当にただの【物語】だったのか?
それとも、彼が言えなかった何かの、形を変えた【何か】だったのか――答えはわからない。聞き返す勇気もなかったから。
「じゃあ……」
そう言って、僕は頭を下げて、金森君の隣をすり抜けるようにして歩き出した。
背中に、金森の小さなため息のような吐息が聞こえた気がしたけど、僕はそれに対して振り返ることはできなかった。
▽ ▽ ▽
翌日から金森君は妙に【僕】に気づくようになった。
教室に入ると、彼の視線とふと目が合う。すぐに逸らされるのかと思えば、彼はほんの少しだけ口の端を上げて、目だけで笑った。
なんでもない、当たり前の挨拶みたいに。
……けれど、僕にとってはまるで別世界のことだった。
そしてその数日後、彼は僕の名前を呼んだ。
「一ノ瀬くん、図書室また行くの?」
帰り支度をしていたとき、後ろからそんな声が飛んできて、思わず立ち止まった。思わず振り返ってみると、金森君が教室の出入り口に立っていた。
「……うん。たぶん」
「へぇ。俺も本返さなきゃなんだよね。ついでに一緒に行っていい?」
彼はそう言って、まるで友達と話すみたいな調子で笑う。友達ではないはずなのだが……。
たったそれだけの会話なのに、僕の胸はざわついていた。この距離感は、どういう意味なんだろう。
演劇部で使う【モデル】としての興味?
それとも、まだ【脚本】の延長線?
よくわからなかった。でも、少なくとも、彼が誰かと関わろうとしているのは確かだった。それが、地味で平凡な【存在】に向けられているのだとしたら――戸惑いながらも、嫌じゃないと思ってしまう自分がいた。
▽ ▽ ▽
放課後の図書室は、相変わらず静かだった。
彼と並んで歩くことにまだ慣れていない僕は、少し後ろを歩くようにして扉を開ける。すると誰もいない空間に、書棚をめくる紙の音だけが響く。
返却ボックスに本を入れたあと、金森君は手に持っていた冊子をぽんとカウンターに置いた。
「……一ノ瀬くんってさ、あの時俺に聞いたよね。『なんで僕の名前が――』って」
彼は僕の方を見ないまま、ぽつりと呟いた。
僕は一瞬、何の話か分からずに固まってしまったけれど、すぐに、あの封筒のことだと気づく。
金森君は、続ける。
「俺さ、本当は人と話すの、苦手なんだよね」
「……え?」
「でも、【金森梓】ってキャラに、周りが勝手に期待してるっていうか……笑っていれば安心されるし、誰にでも合わせておけば波風立たない」
金森君のその言葉のひとつひとつが、妙に冷たく感じたのは気のせいだろうか?
でも、その冷たさの奥にある【疲れ】みたいなものが、耳に残る。
「多分、そういうの、もう慣れちゃったんだと思う。だから誰かのこと、本当の意味でちゃんと見るのって、最近は……あんまりしてなかった」
僕は何も言えず、ただ黙ってしまった。
でも彼の声は、なぜかそこだけ、真っ直ぐで――誰にも言えなかった【本音】のように聞こえた。
僕は静かに頷いてしまった。
「……わかる、気がする……僕も、似たようなとこあるから」
そう呟いた声は、自分でも意外なほど、自然だった。
すると、金森君は僕の方を見た。
そして、少しだけ目を細めて――けれど、その表情は笑っていなかった。
まるで、見透かされたみたいで、何処か気持ち悪く感じてしまったなんて、死んでも言えない。