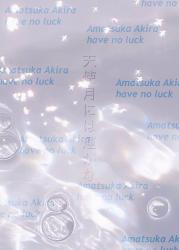◇
「もー、みつって本当にシスコンなんですよおー! 部活帰りに誘っても絶対『家帰るから』って断られるし、あおさんの話すると『お前らなんも知らねえくせに』って妬くし、おまけにケータイのパスコードはあおさんの誕生日だしー!」
「ハハ……そうなんだ」
「おいユカリ、それ以上余計なこと言ったらコロスぞおまえ」
「わー、やめてやめてっ! みつってばこわーい!」
どうやら、みつが所属するバスケ部には相当キャラの濃いマネージャーがいるらしい。
先週の土曜日、どうしてもバスケが見たいと言った私に、『来週バスケ部の奴ら家に呼ぶからそれで我慢しろ』と呆れた顔をしたみつ。私はみつがバスケをしているところが見たいんであって、別に部員さんたちのことなんて心底どうでもいいんだけれど、どうやらいらぬ勘違いをしているみたいだ。
私がバスケ部にどんな人がいるのか気になっていると本気で思っているんだろうか。それなら本当にバカな弟だ。
そして今日、部活がいつもより早く終わる火曜日。みつは律儀に同学年のバスケ部員を家に連れて帰ってきた。マネージャーまで連れて。
「ていうかいいなー、あおさんは! みつとここで毎日暮らしてるなんてずるーい」
「ずるいって、家族だからねえ……」
「えー、でもこんなにカッコいい弟いたら私だったら襲っちゃうなあー」
「襲うって」
「ユカリ、いいからオマエもう黙れよ」
ふわふわの栗色ロング、ぱっちりとした二重の目。短く折ったスカートに、鼻をくすぐるフローラルの香り。マネージャーのユカリちゃんは、とっても『オンナノコ』だ。
「つーか誰? こいつ連れてきたの」
「ユカリが来たいってうるさいから連れてきちゃった」
「倉田、テメーあとで覚えとけよ」
「だってコイツうるせえんだもん。あ、あおさんお邪魔してますー! 今日も綺麗っすね!」
「またまた、今日もお世辞が上手だねー倉田くん」
私が笑顔を向けると、みつがボコッと音が鳴るくらい勢いよく倉田くんの頭を殴った。「いってえなあ、このシスコン!」と涙目で叫ぶ短髪で背の低い倉田くんは、みつと部活もクラスも同じ友達で、よく家に遊びに来る。その度にこうやって私に挨拶してくれるから、もうほとんど知り合いみたいなものだ。
「まあとりあえず、みんなゆっくりしていってね」
「はあい」と可愛らしい返事をしたユカリちゃんと、「ウース!」っていう元気な倉田くんの声と、すでにテレビゲームを始めている数人のバスケ部員たちの返事が同時に返ってくる。
そのあと一呼吸置いてから、みつは小さな声で「……クソ」ってつぶやいた。自分で連れてきておいて、クソってなんだ、クソって。
「ねえちょっと、みつ」
倉田くんとユカリちゃんがテレビゲームに夢中になっている他の部員たちのところへ行くのを見計らって、みつの腕を引きながら小声で話しかける。
みつはちょっとビックリしたような顔をしたけれど、すぐに普段の表情に戻して「何」なんてぶっきらぼうに言ってくる。何、じゃないでしょ。
「どーしてこんなにたくさんバスケ部員なんて連れてきたの」
「あおが見に来たいっつったから、連れてきた方が早いと思って」
「はあ? 私が見たいのはバスケ部員じゃなくてみつがバスケしてるところなんですけど」
「は、部員が見たいんじゃねえの?」
「なんで私がバスケ部員を見たいのよ。どういう思考回路してんの」
「いや、つーか、何、じゃあ、あおは俺を見に来たいってこと?」
「バスケしてるとこをね」
「……」
みつがちょっと嬉しそうに口を閉じた。何その反応、意外だ。視線を上にずらしてから、再度私の方へ向けて。いつものように私の頭をクシャクシャっと撫でた。
「……ちゃんとレギュラーになったら見に来て」
「ああそっか、まだ補欠だもんね」
「ウルセー」
「じゃあ早くレギュラーになってよね」
「おーまかせろ」
「頼もしいじゃん」
「つーかさ、今日部員たち連れてきたのは外にも理由があって、」
「え?なに?」
「おまえもちょっとは他の男見た方がいいと思ったんだよ」
「え、」
思ってもいなかった言葉に驚いた。心臓が嫌な音を立てる。
「あおが、すぐ俺に他の女勧めて来るから」
「いや、それはそうだけど……」
「勧められる方の気持ちも味わってみたら。バスケ部、いい奴ばっかだよ」
ふ、って意地悪く笑って、みつは私に背を向けた。テレビゲームに夢中になってる部員たちの元へ歩いていく背中を見ながら、ぼうっと立ち尽くす。
勧められる方の気持ち、か。
『バスケ部いい奴ばっかだよ』なんて。みつの口から、私に他の男子を勧める言葉が出てきたこと、初めてじゃないかな。昔から、みつに女の子を紹介したり、みつを好きだという子の手助けをしたりしてきたけれど。……みつにこんなことを言われたのは、初めてだ。
ピコン、と。普段通知オフになっているはずのスマホがタイミングよく鳴った。いつの間に通知オンにしてたんだろう。そう不思議に思いながらスマホを手に取ると、一件の新着通知。
……伊藤くんからだ。
実は、この間の伊藤くんからの突然のLINEは『借りていた漫画を返したい』という内容だった。正直「今更?」って思ってしまったし、みかちんにも「今更?」って同じことを言われたんだけれど、返信しないのも悪いのでとりあえずのことLINEを返してしまった。
そこからメッセージのやりとりがなんとなく続いてしまって、一週間経ってもこんな感じ。少しずつ間をあけながら、コンスタントに吹き出しが2つ3つ、送られてくる。
付き合っていた時もこんな感じだったなあって、少し懐かしい気分になってみたり。伊藤くんのことを好きだったときは、この少しの間がもどかしくてたまらなかったなあ、とか。
考えたらキリがないけれど、付き合っていた期間はたぶん好きだったと思う。伊藤くんのこと、ちゃんと好きだった。それが何番目の『好き』なのかって聞かれたら、私には答えられないけれど。
「あおサーン」
突然の声に驚いてスマホから顔を上げた。
キッチンでスマホをいじっていたからか、ついさっき部員たちのところへ行ったはずのユカリちゃんがこっちへ戻ってくるのに気づかなかったらしい。
ふわふわの髪と短いスカートをかわいらしく揺らしながら、にこにこ笑ってこっちへ近づいてくる。ひとつ年下なだけなのに、なんでこんなにキラキラしてるんだろう。本当にかわいいなあ。
「ユカリちゃん、どうしたの? 喉でも乾いた?」
「いや、ちょっとあおサンとお話ししたくて……いいですか?」
低めの身長だから、きっとわざとじゃない天然の上目遣い。こういうのを自然にできる子が世の中の勝ち組なんだろうなあ。私には真似できない。
「うん、いいよ。男の子ばっかでつまんないよね」
「もうほんと、みんなゲームに夢中なんだもん。男子って意味わかんないですよねー! あのゲームの楽しさ全然わかりませんよー!」
ユカリちゃんを席に座らせてから、冷蔵庫のレモンティーをとりだしてコップに注ぐ。それを受け取ったユカリちゃんの手は指先まで綺麗に整えられていて、かわいい子は手まで綺麗なんだなあってどうでもいいことを考える。
「私、あおさんに聞きたいことがあるんですよ!」
「え、何?」
「みつのことですよー。あいつ、あんなにハイスペックなのに彼女作らないっておかしくないですか? 聞いても好きな人いるかどうかさえ教えてくれないしー」
「あー、みつ、全然彼女作ろうとしないもんね」
「ほんっと宝の持ち腐れってあいつのことですよ! ていうか今まで一度もそういうことなかったんですか? 好きな人とか彼女とか!」
「んー、バレンタインに大量のチョコ持ち帰ってきたり、家まで女の子が告白しにきたりとかは色々あったけど……みつから恋愛話って聞いたことないなあ。私も早く彼女作りなよって言ってるんだけどね」
「わー、あいつホントあり得ないですね!あんなにモテるのに!」
「ほんとにね、私もそう思うよ」
「ていうか意外だなあ、あおさんもみつに彼女作ってほしいとか思うんだ!」
レモンティーをひとくち飲むと、喉の渇きが一気に潤う。ユカリちゃんの無邪気さとキラキラ具合は、今の私にはとても眩しい。
「そりゃあ、姉だからね」
「そっかー、みつとあおさんってすっごく仲いいから、お互い彼氏彼女できたら寂しいのかなって思ってました」
「んー、まあ寂しくないって言えばウソになるけど……」
「みつ、前に言ってましたよー。あいつ部活でもシスコンシスコン言われてるから、倉田の奴が『あおさんに彼氏できたらおまえ泣いちゃうな―』って冗談で言ったんですよ! そしたらあいつなんて言ったと思います?」
「あはは、なんだろ。みつなら『泣くわけねえ』とか言いそうだなあ」
「ちっがいますよう。『泣く前にその男と話し合いだな』って! もーあいつガチのシスコンですよ! コワイコワイ」
ユカリちゃんが冗談気味に面白おかしく話してくれたその言葉に私は咄嗟に笑顔を作る。
だけど、胸の奥がドキリとした。
『泣く前にその男と話し合いだな』って。……それなら、伊藤くんの時は?
みつの真剣な顔が思い浮かぶ。私よりも自分の気持ちに真っ直ぐで、ぶれなくて、純粋で、けれどとても幼い、みつの顔。
「はは、みつってば本当、私のこと子供だと思ってるのかな」
「えー、愛されてるんですよう。私、兄弟いないので姉弟で仲いいって羨ましいですよー。それに、みつが弟なんて」
「みつ、弟っぽくないでしょ?」
「うーん、確かに……。みつとは家族になりたくないかなあ。だってそしたら、恋愛できないですもんね」
ユカリちゃんは無邪気にそう言って、笑った。
チクリと胸を刺す痛みは見えないようにグッと抑える。だって、『恋愛できない』―――それは、私とみつの間にある〝当たり前のこと〟だから。
「……ユカリちゃんは、みつのことが好きなの?」
汗をかいたレモンティーのグラスを指で軽くなぞる。一呼吸置いた後、少し頬を赤くしたユカリちゃんは照れ笑いを浮かべながら頷いた。
「へへ、やっぱわかっちゃいますよね。お姉さんに知られるなんて恥ずかしいなあ」
ふわふわで、かわいくて、指先まで綺麗な、みつと『恋愛できる』オンナノコ。おまけにバスケ部のマネージャーだって。打ってつけじゃない。みつはこういう子と、きっと恋に落ちて幸せになるんだろう。
「そっか。みつ、いい奴だから、よろしくね」
「はいっ! 私あおさんに勝てるように頑張りますっ!」
眩しいなあ、と思う。
まっすぐで純粋な気持ちが、みつに向けられたその想いが、とても眩しくて、私は時々、ひどく泣きそうになる。
「もー、みつって本当にシスコンなんですよおー! 部活帰りに誘っても絶対『家帰るから』って断られるし、あおさんの話すると『お前らなんも知らねえくせに』って妬くし、おまけにケータイのパスコードはあおさんの誕生日だしー!」
「ハハ……そうなんだ」
「おいユカリ、それ以上余計なこと言ったらコロスぞおまえ」
「わー、やめてやめてっ! みつってばこわーい!」
どうやら、みつが所属するバスケ部には相当キャラの濃いマネージャーがいるらしい。
先週の土曜日、どうしてもバスケが見たいと言った私に、『来週バスケ部の奴ら家に呼ぶからそれで我慢しろ』と呆れた顔をしたみつ。私はみつがバスケをしているところが見たいんであって、別に部員さんたちのことなんて心底どうでもいいんだけれど、どうやらいらぬ勘違いをしているみたいだ。
私がバスケ部にどんな人がいるのか気になっていると本気で思っているんだろうか。それなら本当にバカな弟だ。
そして今日、部活がいつもより早く終わる火曜日。みつは律儀に同学年のバスケ部員を家に連れて帰ってきた。マネージャーまで連れて。
「ていうかいいなー、あおさんは! みつとここで毎日暮らしてるなんてずるーい」
「ずるいって、家族だからねえ……」
「えー、でもこんなにカッコいい弟いたら私だったら襲っちゃうなあー」
「襲うって」
「ユカリ、いいからオマエもう黙れよ」
ふわふわの栗色ロング、ぱっちりとした二重の目。短く折ったスカートに、鼻をくすぐるフローラルの香り。マネージャーのユカリちゃんは、とっても『オンナノコ』だ。
「つーか誰? こいつ連れてきたの」
「ユカリが来たいってうるさいから連れてきちゃった」
「倉田、テメーあとで覚えとけよ」
「だってコイツうるせえんだもん。あ、あおさんお邪魔してますー! 今日も綺麗っすね!」
「またまた、今日もお世辞が上手だねー倉田くん」
私が笑顔を向けると、みつがボコッと音が鳴るくらい勢いよく倉田くんの頭を殴った。「いってえなあ、このシスコン!」と涙目で叫ぶ短髪で背の低い倉田くんは、みつと部活もクラスも同じ友達で、よく家に遊びに来る。その度にこうやって私に挨拶してくれるから、もうほとんど知り合いみたいなものだ。
「まあとりあえず、みんなゆっくりしていってね」
「はあい」と可愛らしい返事をしたユカリちゃんと、「ウース!」っていう元気な倉田くんの声と、すでにテレビゲームを始めている数人のバスケ部員たちの返事が同時に返ってくる。
そのあと一呼吸置いてから、みつは小さな声で「……クソ」ってつぶやいた。自分で連れてきておいて、クソってなんだ、クソって。
「ねえちょっと、みつ」
倉田くんとユカリちゃんがテレビゲームに夢中になっている他の部員たちのところへ行くのを見計らって、みつの腕を引きながら小声で話しかける。
みつはちょっとビックリしたような顔をしたけれど、すぐに普段の表情に戻して「何」なんてぶっきらぼうに言ってくる。何、じゃないでしょ。
「どーしてこんなにたくさんバスケ部員なんて連れてきたの」
「あおが見に来たいっつったから、連れてきた方が早いと思って」
「はあ? 私が見たいのはバスケ部員じゃなくてみつがバスケしてるところなんですけど」
「は、部員が見たいんじゃねえの?」
「なんで私がバスケ部員を見たいのよ。どういう思考回路してんの」
「いや、つーか、何、じゃあ、あおは俺を見に来たいってこと?」
「バスケしてるとこをね」
「……」
みつがちょっと嬉しそうに口を閉じた。何その反応、意外だ。視線を上にずらしてから、再度私の方へ向けて。いつものように私の頭をクシャクシャっと撫でた。
「……ちゃんとレギュラーになったら見に来て」
「ああそっか、まだ補欠だもんね」
「ウルセー」
「じゃあ早くレギュラーになってよね」
「おーまかせろ」
「頼もしいじゃん」
「つーかさ、今日部員たち連れてきたのは外にも理由があって、」
「え?なに?」
「おまえもちょっとは他の男見た方がいいと思ったんだよ」
「え、」
思ってもいなかった言葉に驚いた。心臓が嫌な音を立てる。
「あおが、すぐ俺に他の女勧めて来るから」
「いや、それはそうだけど……」
「勧められる方の気持ちも味わってみたら。バスケ部、いい奴ばっかだよ」
ふ、って意地悪く笑って、みつは私に背を向けた。テレビゲームに夢中になってる部員たちの元へ歩いていく背中を見ながら、ぼうっと立ち尽くす。
勧められる方の気持ち、か。
『バスケ部いい奴ばっかだよ』なんて。みつの口から、私に他の男子を勧める言葉が出てきたこと、初めてじゃないかな。昔から、みつに女の子を紹介したり、みつを好きだという子の手助けをしたりしてきたけれど。……みつにこんなことを言われたのは、初めてだ。
ピコン、と。普段通知オフになっているはずのスマホがタイミングよく鳴った。いつの間に通知オンにしてたんだろう。そう不思議に思いながらスマホを手に取ると、一件の新着通知。
……伊藤くんからだ。
実は、この間の伊藤くんからの突然のLINEは『借りていた漫画を返したい』という内容だった。正直「今更?」って思ってしまったし、みかちんにも「今更?」って同じことを言われたんだけれど、返信しないのも悪いのでとりあえずのことLINEを返してしまった。
そこからメッセージのやりとりがなんとなく続いてしまって、一週間経ってもこんな感じ。少しずつ間をあけながら、コンスタントに吹き出しが2つ3つ、送られてくる。
付き合っていた時もこんな感じだったなあって、少し懐かしい気分になってみたり。伊藤くんのことを好きだったときは、この少しの間がもどかしくてたまらなかったなあ、とか。
考えたらキリがないけれど、付き合っていた期間はたぶん好きだったと思う。伊藤くんのこと、ちゃんと好きだった。それが何番目の『好き』なのかって聞かれたら、私には答えられないけれど。
「あおサーン」
突然の声に驚いてスマホから顔を上げた。
キッチンでスマホをいじっていたからか、ついさっき部員たちのところへ行ったはずのユカリちゃんがこっちへ戻ってくるのに気づかなかったらしい。
ふわふわの髪と短いスカートをかわいらしく揺らしながら、にこにこ笑ってこっちへ近づいてくる。ひとつ年下なだけなのに、なんでこんなにキラキラしてるんだろう。本当にかわいいなあ。
「ユカリちゃん、どうしたの? 喉でも乾いた?」
「いや、ちょっとあおサンとお話ししたくて……いいですか?」
低めの身長だから、きっとわざとじゃない天然の上目遣い。こういうのを自然にできる子が世の中の勝ち組なんだろうなあ。私には真似できない。
「うん、いいよ。男の子ばっかでつまんないよね」
「もうほんと、みんなゲームに夢中なんだもん。男子って意味わかんないですよねー! あのゲームの楽しさ全然わかりませんよー!」
ユカリちゃんを席に座らせてから、冷蔵庫のレモンティーをとりだしてコップに注ぐ。それを受け取ったユカリちゃんの手は指先まで綺麗に整えられていて、かわいい子は手まで綺麗なんだなあってどうでもいいことを考える。
「私、あおさんに聞きたいことがあるんですよ!」
「え、何?」
「みつのことですよー。あいつ、あんなにハイスペックなのに彼女作らないっておかしくないですか? 聞いても好きな人いるかどうかさえ教えてくれないしー」
「あー、みつ、全然彼女作ろうとしないもんね」
「ほんっと宝の持ち腐れってあいつのことですよ! ていうか今まで一度もそういうことなかったんですか? 好きな人とか彼女とか!」
「んー、バレンタインに大量のチョコ持ち帰ってきたり、家まで女の子が告白しにきたりとかは色々あったけど……みつから恋愛話って聞いたことないなあ。私も早く彼女作りなよって言ってるんだけどね」
「わー、あいつホントあり得ないですね!あんなにモテるのに!」
「ほんとにね、私もそう思うよ」
「ていうか意外だなあ、あおさんもみつに彼女作ってほしいとか思うんだ!」
レモンティーをひとくち飲むと、喉の渇きが一気に潤う。ユカリちゃんの無邪気さとキラキラ具合は、今の私にはとても眩しい。
「そりゃあ、姉だからね」
「そっかー、みつとあおさんってすっごく仲いいから、お互い彼氏彼女できたら寂しいのかなって思ってました」
「んー、まあ寂しくないって言えばウソになるけど……」
「みつ、前に言ってましたよー。あいつ部活でもシスコンシスコン言われてるから、倉田の奴が『あおさんに彼氏できたらおまえ泣いちゃうな―』って冗談で言ったんですよ! そしたらあいつなんて言ったと思います?」
「あはは、なんだろ。みつなら『泣くわけねえ』とか言いそうだなあ」
「ちっがいますよう。『泣く前にその男と話し合いだな』って! もーあいつガチのシスコンですよ! コワイコワイ」
ユカリちゃんが冗談気味に面白おかしく話してくれたその言葉に私は咄嗟に笑顔を作る。
だけど、胸の奥がドキリとした。
『泣く前にその男と話し合いだな』って。……それなら、伊藤くんの時は?
みつの真剣な顔が思い浮かぶ。私よりも自分の気持ちに真っ直ぐで、ぶれなくて、純粋で、けれどとても幼い、みつの顔。
「はは、みつってば本当、私のこと子供だと思ってるのかな」
「えー、愛されてるんですよう。私、兄弟いないので姉弟で仲いいって羨ましいですよー。それに、みつが弟なんて」
「みつ、弟っぽくないでしょ?」
「うーん、確かに……。みつとは家族になりたくないかなあ。だってそしたら、恋愛できないですもんね」
ユカリちゃんは無邪気にそう言って、笑った。
チクリと胸を刺す痛みは見えないようにグッと抑える。だって、『恋愛できない』―――それは、私とみつの間にある〝当たり前のこと〟だから。
「……ユカリちゃんは、みつのことが好きなの?」
汗をかいたレモンティーのグラスを指で軽くなぞる。一呼吸置いた後、少し頬を赤くしたユカリちゃんは照れ笑いを浮かべながら頷いた。
「へへ、やっぱわかっちゃいますよね。お姉さんに知られるなんて恥ずかしいなあ」
ふわふわで、かわいくて、指先まで綺麗な、みつと『恋愛できる』オンナノコ。おまけにバスケ部のマネージャーだって。打ってつけじゃない。みつはこういう子と、きっと恋に落ちて幸せになるんだろう。
「そっか。みつ、いい奴だから、よろしくね」
「はいっ! 私あおさんに勝てるように頑張りますっ!」
眩しいなあ、と思う。
まっすぐで純粋な気持ちが、みつに向けられたその想いが、とても眩しくて、私は時々、ひどく泣きそうになる。