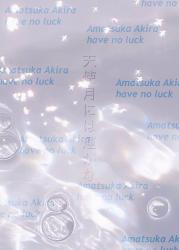◇
「みつー、今週のジャンプ買った?」
「今読んでる」
「えー、じゃあ読み終わるまでここにいよっと」
「つうか勝手に入ってくんな」
「いいじゃん別に、やましいことでもあんの」
帰宅部のわたしは大体毎日みかちんと一緒に帰る。バスケ部のみつが帰ってくるのは私よりも2時間も後だ。その間にお風呂と課題を済ませておいて、夕ご飯を家族で食べるのがうちの決まり。その後、わたしは決まってみつの部屋に行く。
理由はあんまりない。ただひとつ言えるのは、みつの部屋のベッドの方がフカフカで気持ちいいってこと。
「みつお風呂行ったらー?」
「ジャンプ読みたいだけだろ」
最新号のジャンプから目を離すことなく言うみつを通り越してベットに飛び乗る。仰向けになりながらスマホを取り出していじるのが毎日の日課。
今日はジャンプだけれど、いつもみつはベットにもたれながら本を読んだり明日の予習をしたりしている。元々そんなに頭がいいほうじゃないから、うちの高校の授業についていくのは大変みたい。
勉強だけは昔から私の方が良く出来たけれど、それが悔しかったのか、みつは苦手な勉強を努力で補っている。そういうところ、みつらしいなあと思うよ。
「あ、そういえばハルカちゃんがみつのLINE知りたいんだって」
「は? 誰だよハルカちゃんって」
しわになったベットカバーを手で直しながらみつが振り向く。さっきまでジャンプに夢中だったくせに、こういう話には飛びつくんだ。
「同じクラスの子ー。かわいいよ。色白で細くて、女の子って感じの子」
「……」
みつが一回私を睨んでからジャンプへと向き直る。私は同時に部屋の中をぐるっと見渡す。
みつの部屋は落ち着いたシンプルな色合いだ。白い壁と、黒と茶色しかない家具。もちろんベットカバーも。明確にはチャコールグレイっていうらしい。散々迷ったんだってみつが私に自慢気に話してきたから覚えてる。
「おーい、無視ですか、みつクーン」
返事がないので、起き上がってみつの頭をつついてやると、鬱陶しいと言わんばかりに手を払われてしまう。まったく可愛くない弟だ。
「もう、せっかくお姉ちゃんがカワイイ子紹介してあげようと思ったのに」
「必要ねえよ」
「なーんでそんなこと言うの」
「おまえさ、俺にそうやって女子紹介するの何回目だよ」
「何回やってもみつが頷かないからでしょ」
「何回紹介されても興味ねえよ」
「もう、いっつもそう。みつ、アンタは見た目も性格もこれっぽちも悪くないんだよ? ていうかむしろスッゴイいい男なんだよ? 姉の私が言うのもどうかと思うけど!」
一気にまくしたてると、みつがゆっくりこっちを振り返る。眉間に深いしわを寄せて、いかにも「機嫌が悪いです」って顔。
「そんなにイイ男の俺が恋愛してないのがそんなにおかしいことかよ」
「おかしいっていうか、彼女くらい、すぐ出来るのに、なんでかなって思って……」
「必要ないから作らない。なんか文句あんの?」
「いや文句っていうか、周りからよく聞かれるし、」
「聞かれるって何を」
「だって、みつ、そんなにモテるのに彼女作らないなんて……欲とかないわけ?」
みつが不機嫌そうな顔をしたまま、じっとこっちを見つめる。まじまじとその顔を見ると、本当に整った顔立ちをしているなあと思う。
丸っこい二重の目。筋の通った高い鼻。薄めの唇と綺麗な肌。我が弟ながら、どうしてこんなにも綺麗な顔の人が生まれてくるんだろうって思ってしまう。
「……あるよ」
「え?」
「あるよ、欲」
床に座っていたみつが、ベットに手をついてゆっくりと上がってくる。私は同じ高さまであがってきたみつの目線をずっと見つめながら、右側に沈むベットにぐっと力を入れた。
「……欲だらけだよ、俺」
真っ直ぐに私を見つめるみつの視線は、ゆらゆらと揺れているようで軸はしっかりとした直線だ。この瞳《め》をするとき、みつはいつも少しだけ泣きそうな顔をする。
「……ふうん、みつもやっぱり男だもんね」
ふいっと。
その視線から逃れるのは、私の特技だ。
「……まあな」
私がわざと視線をずらしたことを、みつは気づいていて知らないふりをする。時々ある、こんな瞬間。
みつが床に置いたジャンプを再び手に取って、私の横に座ったまま読み始める。私はそんなみつの横顔を再びチラッと盗み見してから、スマホを手に取った。 私とみつの間にある、よく見えない色が時々とてもこわい。いろんなものを全部壊してしまいそうなその色の正体を、知ったらきっともう後戻りできないんじゃないかと思う。
「……伊藤?」
ふと横から、驚いたような声がした。普段の声色に、少し黒色を混ぜたみたいな音だ。今ジャンプを読み始めたくせに、いつの間にか首を伸ばして、私が手にしているスマホを覗き込んでいる。
「伊藤?」
「……それ。通知」
「え?」
みつの眉間のしわが深くなったことにドキリとして、視線を手元のスマホにうつす。
自分の目を疑ったけれど、みつが「伊藤?」と言ったから、これは現実のことらしい。
LINEの通知。春に別れてから一度も連絡をとっていない、見慣れなくなった『伊藤くん』の文字。
「何、まだ連絡とってんの?」
「え、まってまって、私も今驚いてるんだけど……」
「それにしてはやけに冷静だな」
みつの手が横からのびてきて、ヒョイっと私のスマホを奪った。私はそれに「あ」と小さな声を出す。無駄な抵抗だ。
「なになに? ……久しぶり、元気にしてる?……あおは元気だろうけど俺は……」
「ちょっと! 読み上げないでよ」
「俺は、の続き読めないんだけど。ロック解除して」
「読まなくていいし!」
みつが私に背を向けるから、スマホを奪い返そうとみつの背中に飛びついた。
まだお風呂に入っていないみつは、部活のあとで汗をかいたはずなのに、なぜだかいい匂いがする。同じシャンプーとボディソープを使ってるなんてウソなんじゃないかって思うくらい。なんて、弟に何を思っているんだろう、と首を振る。
「パスワード何? 誕生日?」
「ちょっと、むやみに数字打ち込まないでよ。一時間くらい使えなくなったらどうしてくれるの」
「誕生日じゃない、身長でもない、これも違う……あとは、」
「あ、」
みつが器用に私の邪魔を遮って数字を打ち込む。早くてよく見えなかったけれど、スマホのロック画面がホーム画面に一瞬で切り替わった。つまりそれは、みつが私のパスワードを当ててしまったということ。
普段、指紋認証でスマホのロックを開けているから、パスワードなんて忘れかけていたけれど。
これは結構、まずいことになった。
「いや、これは違うよ、みつ。変えるのが面倒くさくて、そのままにしてあっただけだから……」
「……ふうん。あおって、意外と伊藤のこと好きだったんだ」
低くなったみつの声。
やっぱり、と私は口を噤む。
変えるのが面倒くさくて、伊藤くんと付き合っていた時から使っている『記念日』のパスワード。登録した時、たまたま伊藤くんと付き合っていて、たまたま一緒にいたのが彼だったものだから、付き合った記念日である数字をパスワードに設定していた。
そんなこと、いまの今まで忘れていたけれど。
「いや、本当に違うよ? 変えるのが単にめんどくさかっただけだし、このパスワードが記念日だなんて今の今まで忘れてたっていうか……」
「あお」
「え、はい……何」
「俺のパスコード、解いてみて」
私は何を必死にこんなに弁解してるんだろうと思いながら、みつが背を向けたままこっちへ放り投げたスマホを受け取る。
みつのパスコードなんて知るわけがない。それに、そんなに簡単に当ててしまえるものなら、設定なんてしなくていいはず。
「何それ……全然わかんないし、」
振り向かないみつの後ろで、私は渋々テキトウに数字を並べる。みつの誕生日、身長、ケータイ番号の下四桁、みつのすきな「1」の羅列。どれもハズレで、打ち込むたびにブーってスマホが揺れる。
「もう、こんなのわかんないよ……いきなり意味わかんな……あ、」
やけくそでテキトウにいろんな数字を打ち込んでいたら、突然みつのスマホのロックが解けた。それはつまり、私が今打ち込んだ数字がみつのパスコードだということ。
「解けた?」
「え、ああ……うん」
みつがゆっくり振り返って、私の手にある自分のスマホを見ながら「ほんとだ」って笑った。
「俺のパスコード、なんだった?」
「なんだった、って……」
「解いたんだろ?」
「……私の誕生日」
「うん、そーだよ」
今度はみつの顔を見れなくて、開いたままのみつのスマホをずっと見つめる私の頭に、みつが優しく手のひらをのせた。
いつからだろう。みつの頭を撫でていたのは私の方だったのに、いつの間にかみつのほうが、私を撫でることの方が多くなってしまった。
「なあ」
「……何?」
「伊藤とより戻すの?」
「戻さないよ」
「じゃあパスコード変えろよ」
「……みつの誕生日に?」
「それは、あおに任せるけど」
みつの骨ばった大きな手が、頭からするりと私の頬に落ちて来る。その手つきに胸が鳴る私はおかしいのかもしれない。
みつは弟だ。血は繋がっていないけれど、幼い頃からずっと一緒にこの家で育ってきた。
「……みつの、誕生日にする」
私とみつの間にある、よく見えない色。いろんなものをすべて壊してしまいそうなその色は、このベットカバーとよく似ている気がする。不安とか、そういうものを、全て詰めたような色。わたしはなぜかひどく泣きたくなって、ぎゅっとしわになるくらいそれを握りしめた。