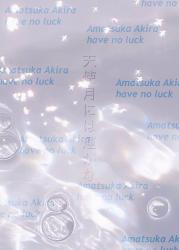ひどく冷たい声だった。
誰もいない、昼間の平日。インフルエンザ以外で学校を休んだことのない私がこんな時間に家にいるのはほとんど初めてだ。それも、みつとふたりきりで。
……急に思った。みつも、男だっていうこと、その声色と捕まれた力の強さで、急に実感してしまった。
「嫌いってなんだよ、全然そんな風には聞こえねーよ、」
「うるさい、もうどっかいってよ……」
「泣いてるあおのこと、放っておけると思ってんのかよ」
「やめてよ、もう乱すようなこと言わないで」
「なあ、乱すって何? 俺があおに向けてる感情が、何かを乱すことがあんのかよ」
「やめて、みつは素直すぎるよ、」
「素直で何がワリイんだよ!」
グッと、私の手をつかんでいるみつの力がさっきより強くなって、そのままぐっと後ろへ押された。いきなりのことで抵抗出来なかった私はそのままベットへと倒れ込む。強制的に、みつに押し倒されている状態だ。
涙は止まらないのに、見上げた先にいるみつの悔しそうな顔がどうしようもなく大切で、離せなくなってしまう。
「なあ、俺のこと嫌い?」
「……きらい、だよ」
「ほんと素直じゃねえ奴」
「うるさいってば……」
「本当にきらいなら、俺が今からすること、拒めよ」
「何、言って、」
みつの瞳は思ったよりも真剣で、溢れていた涙が思わず引っ込む。
ゆっくりと、みつの右手が私の頬に伸びてきて、まるで割れ物を扱うみたいにそっと、指先で触れた。
「あおは知らないだろうけど」
「……」
「ずっと触れたいと思ってた」
「な、」
「正直、あおが思ってるよりも俺ってずっと欲まみれで、めちゃくちゃにしてやりたいとさえ思ってた。すぐそこにいるのに指一本触れることさえ躊躇ってさ、俺の気持ちも考えねえで風呂上がりにいつも無防備に部屋に来て」
「やめてよ、変なこと言わないで……」
「ずっと、我慢してたけど、限界ってあるもんだな」
「……」
「……キスしていい?」
勝手にしない。みつはそういうひとだ。
真っ直ぐな瞳の奥を、みつが揺らした。迷ってる。躊躇ってる。一線を越えたらわたしたちは姉弟じゃいられなくなる。
急に実感する、みつが、男だっていうこと。
「バカなこと、言わないで……」
「はは、ホントな」
「やめてよ、」
「こんなに欲しいのに、傷つけたくない、俺ってほんと弱いよ」
スッと、みつが私から身体を起こす。同時に私も、それを追うように起き上がった。
「なあ、あお。俺さ、自分のこと本当に子どもだと思うよ。あおが姉ちゃんでいてくれることに甘えて、自分の気持ちおまえに押し付けるようなことして。……あの日、あおが俺に『弟だ』って言った日。……いい加減この気持ち、捨てなきゃって思った」
それは、みつがユカリちゃんと付き合うほんの少し前。
「……でも、」
みつの背中が弱々しく震えた。私に顔を見せないように背を向けてうつむいて。
「捨てらんねえ、どうやっても、あおのこと。だから、……俺に向けてるその感情、捨てんな」
まっすぐ、見た。
捨てんな、と言ったみつの背中にまた涙が溢れてくる。それでも、まっすぐ、みつを見た。
ゆっくりと振り返って私を見たみつの視線とわたしのそれが絡み合う。
私もみつも、お互いの顔をしっかり見ていた。絡み合った視線はほどけなくて、まるで時が止まったんじゃないかと思う。
ねえ、みつ。こんなこと許されるかな。
私がきみに対して持っているこの感情に素直になることを、世界は許してくれるのかな。
「……あおのこと、諦めたくない」
「み、つ、」
「ずっとだよ。ずっと、ずっと想ってたんだ。こんなに近くにいるのに言えなかった俺の気持ち、わかるか。……触れられないもどかしさ、わかる?」
「……そんな、の」
「なあ、あお」
突然、ぐっと強く両手を引かれた。
ぐらりと揺れた視界はすぐに真っ暗になる。みつの胸の中に倒れこんだんだってわかるのに数秒、抱きしめられてるって気づくのに、数十秒。
─────はじめて、みつが私を抱きしめた。
「世間とか、親とか、とりあえず今は置いといて。全部抜きにして、俺のこと、どう思ってる?」
みつの吐息が、鼓動が、温度が、全部直接伝わってくる。今まで感じたことのない暖かさが、私を包むことにさらに涙が溢れてくる。
ドクドクと、私と同じ速さで鳴るみつの鼓動。私を抱きしめる手は少しだけ震えていた。
ねえ、みつ。こんな姉でごめんね。
「……すき。みつが、すき……」