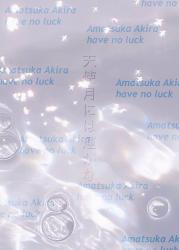顔を見なくてもわかる。いや、本当は玄関が開いたときからわかっていたけれど。
─────みつの、声だ。
「別に、なにもしてない」
「ガッコー休むなんて珍しいじゃん」
「私だって体調不良になることくらいある」
素直じゃない私は布団にくるまって、みつのことを見ることが出来ない。言葉もなんだか攻撃的で、うまく笑えない。上手に出来ない。何年も何年も、隠して嘘をついてやり過ごしてきたのに、肝心なときに上手くいかないよ。
こんな自分、誰にも見せたくない。
「へー、土曜は伊藤と会ってたくせにな」
「……なにそれ」
さすがにカチンときた。
だって、何それ。伊藤と会ってたくせに、って? みつが、伊藤と付き合えよって言ったんじゃん。意味わかんない。みつも、私も、周りも。みんないい加減で、何も考えてない。
「なにそれって、言葉のままだけど」
「会ってたくせに、って何それ、意味わかんない」
「はあ?」
「みつが、みつが、伊藤と付き合えって言ったんじゃん! あいつなら幸せにしてくれるって、そう言ったんじゃん!」
「おい、あお」
「ていうか、入学式に伊藤くんに会いに行ったんだって? 私のこと頼んだんだってね。エラソーな弟。そんなの私頼んでないのにね」
「おい、ちょっと聞けって、」
「だいたい、いつもいつもみつはズルいんだ。私の気持ちかき乱して、必死に守ろうとしてきた関係を簡単に壊すようなことばっかり言って、それでいて、簡単に人のものになった」
「人のもの、って」
「自分は、ユカリちゃんと付き合ったくせに!」
そう言った瞬間。
グッと強く腕を引っ張られた。布団に隠れていた私はみつの手に引かれて横になっていた体を強制的に起こすことになる。一瞬何が起きたのかわからなかった。
ベットに座った状態になった私の目の前に、同じように座るみつの顔があった。私の手首を掴んだままのみつの手のひらは、少し汗ばんでいて熱い。
「……なあ、なんで泣いてんの」
私の手首を掴んだ手と反対のみつの手が、ゆっくりと私の頬に触れた。私はそれを、首を振って拒む。今、みつに触られたくない。
もう、振り回されたくない。
「あお」
「うるさい」
「聞けって」
「聞きたくない」
下を向いたまま答えると、上から「はあ」ってため息が落ちて来る。みつ、呆れてる。私、今まで、こんな子供じみたことなんてしたことないもんね。
だいたい、ユカリちゃんと付き合うってことは、みつは彼女が好きだってことだ。いつかくるってわかっていたけれど、こんなに自分が子供っぽい態度をとってしまうとは思わなかった。私が彼氏を作ったとき、みつはいつも普通だったのにな。
本当は、ずっと自惚れていたんだろう。みつのトクベツはわたしだって、そんな風に。
「それは、何の涙?」
「泣いてない」
「泣いてるだろ」
「……もう、やめたい」
「はあ?」
「もう、こんな感情、捨てちゃいたい」
言った瞬間、ボロボロと涙がこぼれ落ちてきた。さっき頬を伝っていたのとは比べ物にならないくらい大きな粒が、ポトリポトリとベットに落ちてシミをつくっていく。
止めたいのに、止められなかった。止め方さえわからないなんて、もういやだ、恥ずかしくて消えてしまいたい。
「あお」
みつの手が。
私の右手と左手を合わせて、それを両手で包み込んだ。抵抗するのも疲れてしまって、私はそれを泣きながら受け入れる。みつの声は優しかった。
「……俺のせいで泣いてる?」
ふるふると首を横に振る。みつのためなんかじゃない。不安と、嫉妬と、葛藤と、いろんなものがせめぎ合って苦しい。それが、涙になって溢れてるだけ。
……みつのせいなんかじゃ、ない。
「じゃあなんで泣いてる? どうして学校休んだ?」
「泣いてない」
「泣いてるよ。ほんと強がり」
「みつなんか嫌い」
「……」
「振り回して、かき乱して、たくさん悩ませておいて、自分から離れていくんだ。……みつなんて、嫌いだよ。……だいっきらい……」
下を向いてボロボロ泣いているせいで、みつの顔は見えなかった。握られた手のひらは段々汗をかいてきて、みつの手の温度がまた苦しい。
どうして止まらないんだろう。こんな姿見せたいわけじゃなかった。こんな風に何かを伝えたいわけじゃなかった。
「俺がユカリと付き合ったから? その感情、捨てんの?」