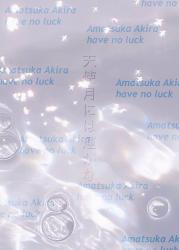◇
「あお!」
久しぶりに聞いた声。数メートル先で手を振る伊藤くんが満面の笑みで私の名前を呼んだ。面と向かって顔を合わせるのはいったいいつ以来だろうと考えて、思わず足がすくむ。
昨日─────みつが『伊藤と付き合え』と言葉を残して部屋を出て行った。
一晩中布団に埋まって、これからみつと顔を合わせる時どうしようかと悩んでいたけれど、朝起きたらみつはすでに部活に行っていた。代わりに、スマホには伊藤くんから「今日会える?」というLINE。そのとき今日が土曜日だと思い出した私は、なんてタイミングがいいLINEだろうかってちょっと怖くなった。
伊藤くんのことは嫌いじゃない。けれど好きでもない。
みつが、付き合え、と言った。あいつなら幸せにしてくれると思うと、言った。
もっと簡単だったのにな、と思う。
伊藤くんと付き合ったとき、私はもっと簡単に物事を考えていた気がする。軽く、付き合うことを了承した気がする。なんとなく好意を抱かれていることはわかっていて、それに悪い気持ちもなくて、どちらかと言えば嬉しかった。そんな単純な気持ちで、伊藤くんからの告白を受け入れた。
でも、今は違う。みつに彼女ができた。その事実をうまく飲み込めないでいる今の私は、昔の私と、きっと違う。
「─────聞いてる?」
「え、」
「あお、さっきから上の空だね」
困ったように伊藤くんがわらった。あ、付き合ってた時もこんな顔、いつもしてたって思う。
きっと私が、させてたんだ。
「ゴメン、ちょっと寝不足で」
「目、赤いもんね」
「はは……」
カフェオレをひとくち口に含む。いつの間にかおしゃれなカフェにつれてこられていた。伊藤くんってこんな場所知っているような人だったけ。付き合っている時どんな場所にデートに行ったのか、もうあんまり覚えていない。
「伊藤くんは、なんで私を誘ったの?」
「なんでって……」
ブラックコーヒーかな。角砂糖は何個いれたのかな。いれてないのかな。黒い液体を伏せ目がちに飲み込んだ伊藤くんを見つめる。
私、彼のこと、意外と何も知らない。
「弟のみつくん、彼女できたんだって?」
コトン、と。伊藤くんがカップをテーブルに置いたのと、そんな言葉を発したのはほぼ同時だった。
手先が一気に冷たくなったんじゃないかと思う。右手で左手を握ってみるとそんなことはなくて、胸の奥がつっかえる。どうしちゃったんだろう。こんな話題、普段なら笑ってやり過ごせたはずなのに。
上手く笑えない。こんなんじゃ、ダメなのに。
「はは、よく知ってるね、」
「すっごい噂だよ。ついに彼女作ったって。さすがだなあって感じ」
「へえ、みつって結構有名人なんだね」
「あおも知ってるでしょ。入学してきた時から騒がれてたし。同い年も先輩もみつくんのこと狙ってた」
「顔だけはいいからね、あいつ」
「でも今まで彼女出来たことなかったでしょ? 男の俺にまで彼の噂は回ってくるくらいだよ」
「ね、ほんと、モテるのに理想が高いみたい」
「……理想、ね」
笑った伊藤くんの目は笑ってない。そこだけは、私でもわかった。
「あおの"弟"が入学してきたときの話、俺、あおにしてなかったよね」
「え?」
「あいつは真っ先に俺のところへ来たよ。入学式が終わった後だった」
みつのこと、突然『あいつ』と行った伊藤くんの目線が鋭くなる。声色はやけに真剣で、初めて聞く話に心拍数が上がっていく。
「2年になって文理校舎が分かれたから、あおは知らないだろうけど。俺の教室まで来て、『姉ちゃんの彼氏っておまえ?』って。なんて生意気な弟だって正直思った」
懐かしそうに目を細める伊藤くんを見ながら、頭の中が混乱する。わたし、そんな話全然知らない。
みつが入学してきた今年の春。伊藤くんとまだ付き合っていて、わたしが伊藤くんに別れを切り出される少し前。『あおさんに彼氏が出来たらどうする?』と聞いたバスケ部員に、みつが返した言葉はなんだっけ?
─────『話し合いだろ』ユカリちゃんが、みつがそう言ったと、教えてくれたことを思い出した。
「あの時はビックリしたな。すっごい怖い顔しててさ。『話がある』って。あおに弟がいることも知らなかったし、なんだコイツ? って感じだった」
「ごめん、」
何故伊藤くんにみつのことを話さなかったのか、あまりよく覚えていない。兄弟がいるかどうかなんて聞かれなかったし、自分からわざわざ話す話でもないと思ったのかもしれない。
もし私が伊藤くんと付き合っていたとき、『兄弟がいるか』と聞かれていたら、私はちゃんと『弟がいる』と答えていたと思う。でもそれを、自分から言う勇気はきっとなかった。みつという存在が、どこかで自分の中にいること、ずっと本当は気づいていた。
「入学式から3日後くらい。ふたりでハンバーガー食べに行ったんだ」
「え、みつと?」
「うん。年下だし彼女の弟だし、奢ってやるって言うのに頑なに『嫌です』って。生意気だよなあ、あいつ」
「う、そうだよね……」
「でも、お姉ちゃんっ子なんだろうなあって思った」
「お姉ちゃんっ子、か」
「彼女の弟なのに、全然かわいいとか思えなくてさ、俺も大人げないけど」
「ううん、そんなことないよ。それで、何を話したの? ……みつ、変なこと言ってない?」
「変なことっていうか、あのとき、まっすぐ俺のこと見て、『姉ちゃんのこと幸せにできんの?』って、そう言われた」
手が止まった。伊藤くんがため息をつきながら、「絶対にあおには言わないでおこうと思ったんだけど」と付け加える。
みつ、伊藤くんとふたりで会っていたんだ。私、全然知らなかった。何も知らなかった。
「俺さ、そのとき思ってもいなかった言葉に声も出なくて。そしたらアイツ俺のことめちゃくちゃ睨んでさ。次に何を言われるかと思えば、『あいつ、いつも自分の気持ち押し殺すから、ちゃんと見てやって』って。……本当に弟? って思ったよ。まあ、その後、みつくんから血は繋がってないって聞いたんだけど」
頭の中が痺れたようで、何も答えられなかった。私だって予想外だ。みつが伊藤くんに、そんなことを言ったなんて。
『伊藤と付き合えよ』と言ったみつの震えた声がまた私の中でぐるぐる渦巻いて落ちていく。姉ちゃん、なんて普段呼ばないくせに、伊藤くんの前ではそう呼んだんだね。
……みつ、本当は、ずっと前から、私から距離を取ろうとしてた?
「なあ、あお」
伊藤くんの声に顔を上げる。いつの間にか下を向いていたらしい。一気に現実に戻ってきたみたいな変な感覚。
「先に言っておきたいんだけど」
「うん」
「俺は、たぶんまだあおのこと好きだと思う」
「……うん」
「連絡したのも、あおを忘れられなかったからだし、別れてからずっと後悔してた。あのとき、みつくんを見て話をしたあと、馬鹿みたいに焦って。―――あおとみつくんは姉弟なのにな。勝手に嫉妬して、俺、本当に馬鹿だったと思う」
「……それは、」
「─────でも」
カラン、と氷がぶつかる音がした。
伊藤くんが真っ直ぐ私を見つめるから、私も伊藤くんから目を離したらいけないと思った。これから言われる言葉を、きちんと聞かなくちゃならないと思った。
「俺は、あおが幸せになれたらいいと思うけど、幸せって、結局本人が決めることだと思うんだ」
手先が震えた。喉から水分がすべて吸い取られていってしまうような感覚だった。
「1回くらい、自分の気持ちに素直になってもいいんじゃないの? って、俺はそう思うよ。あおが幸せだと感じるなら、それでいいと思う」
いろんなものがぐるぐると渦巻いて私に降ってきて、先の見えない大きな洞窟にでもひとりで取り残されてしまったみたいに感じる。
─────『自分の気持ちに素直になっても』
伊藤くんの言いたいことは痛いほどわかった。彼がすべて気づいていて、言葉を選んでくれていることも、私のことをとても大切に考えていてくれたことも、全部全部、わかった。
でも─────弟、だ。
みつは、私の家族で、大切な『弟』。血は繋がっていないけれど、同じものを食べて、同じ家に帰って、同じシャンプーを使って、同じ時間を共に過ごしてきた。お父さんとお義母さんの幸せそうな顔を、ふたりで見ながら笑い合った。大切な家族。大切な弟。だいじな、大事な、……『弟』の、みつ。
『大丈夫?』と言ったみかちんの声を思い出す。私って案外気持ちを隠すのが下手なのかもしれない。みかちんだってきっとずっと色んなことを察していたんだろう。
素直になるって、何?
みつに対する家族以上の気持ち? みつが私に向けるベクトルが姉のそれではないこと? わかっているのに認めちゃいけないって、わたしが自分の気持ちを制限するのはそんなにダメなこと? 年上で、お姉ちゃんで、みつよりしっかりしていなきゃいけないのは、私の方なんだよ。
どれだけ足掻いたって、私とみつは家族だ。姉と、弟以上にはなれない。なっちゃいけない。
どれだけ考えたって、わたしの気持ちは無駄でしかない。それなら、認めるなんてそんなこと、したくない。
素直になんて、なれるわけない。
「あお!」
久しぶりに聞いた声。数メートル先で手を振る伊藤くんが満面の笑みで私の名前を呼んだ。面と向かって顔を合わせるのはいったいいつ以来だろうと考えて、思わず足がすくむ。
昨日─────みつが『伊藤と付き合え』と言葉を残して部屋を出て行った。
一晩中布団に埋まって、これからみつと顔を合わせる時どうしようかと悩んでいたけれど、朝起きたらみつはすでに部活に行っていた。代わりに、スマホには伊藤くんから「今日会える?」というLINE。そのとき今日が土曜日だと思い出した私は、なんてタイミングがいいLINEだろうかってちょっと怖くなった。
伊藤くんのことは嫌いじゃない。けれど好きでもない。
みつが、付き合え、と言った。あいつなら幸せにしてくれると思うと、言った。
もっと簡単だったのにな、と思う。
伊藤くんと付き合ったとき、私はもっと簡単に物事を考えていた気がする。軽く、付き合うことを了承した気がする。なんとなく好意を抱かれていることはわかっていて、それに悪い気持ちもなくて、どちらかと言えば嬉しかった。そんな単純な気持ちで、伊藤くんからの告白を受け入れた。
でも、今は違う。みつに彼女ができた。その事実をうまく飲み込めないでいる今の私は、昔の私と、きっと違う。
「─────聞いてる?」
「え、」
「あお、さっきから上の空だね」
困ったように伊藤くんがわらった。あ、付き合ってた時もこんな顔、いつもしてたって思う。
きっと私が、させてたんだ。
「ゴメン、ちょっと寝不足で」
「目、赤いもんね」
「はは……」
カフェオレをひとくち口に含む。いつの間にかおしゃれなカフェにつれてこられていた。伊藤くんってこんな場所知っているような人だったけ。付き合っている時どんな場所にデートに行ったのか、もうあんまり覚えていない。
「伊藤くんは、なんで私を誘ったの?」
「なんでって……」
ブラックコーヒーかな。角砂糖は何個いれたのかな。いれてないのかな。黒い液体を伏せ目がちに飲み込んだ伊藤くんを見つめる。
私、彼のこと、意外と何も知らない。
「弟のみつくん、彼女できたんだって?」
コトン、と。伊藤くんがカップをテーブルに置いたのと、そんな言葉を発したのはほぼ同時だった。
手先が一気に冷たくなったんじゃないかと思う。右手で左手を握ってみるとそんなことはなくて、胸の奥がつっかえる。どうしちゃったんだろう。こんな話題、普段なら笑ってやり過ごせたはずなのに。
上手く笑えない。こんなんじゃ、ダメなのに。
「はは、よく知ってるね、」
「すっごい噂だよ。ついに彼女作ったって。さすがだなあって感じ」
「へえ、みつって結構有名人なんだね」
「あおも知ってるでしょ。入学してきた時から騒がれてたし。同い年も先輩もみつくんのこと狙ってた」
「顔だけはいいからね、あいつ」
「でも今まで彼女出来たことなかったでしょ? 男の俺にまで彼の噂は回ってくるくらいだよ」
「ね、ほんと、モテるのに理想が高いみたい」
「……理想、ね」
笑った伊藤くんの目は笑ってない。そこだけは、私でもわかった。
「あおの"弟"が入学してきたときの話、俺、あおにしてなかったよね」
「え?」
「あいつは真っ先に俺のところへ来たよ。入学式が終わった後だった」
みつのこと、突然『あいつ』と行った伊藤くんの目線が鋭くなる。声色はやけに真剣で、初めて聞く話に心拍数が上がっていく。
「2年になって文理校舎が分かれたから、あおは知らないだろうけど。俺の教室まで来て、『姉ちゃんの彼氏っておまえ?』って。なんて生意気な弟だって正直思った」
懐かしそうに目を細める伊藤くんを見ながら、頭の中が混乱する。わたし、そんな話全然知らない。
みつが入学してきた今年の春。伊藤くんとまだ付き合っていて、わたしが伊藤くんに別れを切り出される少し前。『あおさんに彼氏が出来たらどうする?』と聞いたバスケ部員に、みつが返した言葉はなんだっけ?
─────『話し合いだろ』ユカリちゃんが、みつがそう言ったと、教えてくれたことを思い出した。
「あの時はビックリしたな。すっごい怖い顔しててさ。『話がある』って。あおに弟がいることも知らなかったし、なんだコイツ? って感じだった」
「ごめん、」
何故伊藤くんにみつのことを話さなかったのか、あまりよく覚えていない。兄弟がいるかどうかなんて聞かれなかったし、自分からわざわざ話す話でもないと思ったのかもしれない。
もし私が伊藤くんと付き合っていたとき、『兄弟がいるか』と聞かれていたら、私はちゃんと『弟がいる』と答えていたと思う。でもそれを、自分から言う勇気はきっとなかった。みつという存在が、どこかで自分の中にいること、ずっと本当は気づいていた。
「入学式から3日後くらい。ふたりでハンバーガー食べに行ったんだ」
「え、みつと?」
「うん。年下だし彼女の弟だし、奢ってやるって言うのに頑なに『嫌です』って。生意気だよなあ、あいつ」
「う、そうだよね……」
「でも、お姉ちゃんっ子なんだろうなあって思った」
「お姉ちゃんっ子、か」
「彼女の弟なのに、全然かわいいとか思えなくてさ、俺も大人げないけど」
「ううん、そんなことないよ。それで、何を話したの? ……みつ、変なこと言ってない?」
「変なことっていうか、あのとき、まっすぐ俺のこと見て、『姉ちゃんのこと幸せにできんの?』って、そう言われた」
手が止まった。伊藤くんがため息をつきながら、「絶対にあおには言わないでおこうと思ったんだけど」と付け加える。
みつ、伊藤くんとふたりで会っていたんだ。私、全然知らなかった。何も知らなかった。
「俺さ、そのとき思ってもいなかった言葉に声も出なくて。そしたらアイツ俺のことめちゃくちゃ睨んでさ。次に何を言われるかと思えば、『あいつ、いつも自分の気持ち押し殺すから、ちゃんと見てやって』って。……本当に弟? って思ったよ。まあ、その後、みつくんから血は繋がってないって聞いたんだけど」
頭の中が痺れたようで、何も答えられなかった。私だって予想外だ。みつが伊藤くんに、そんなことを言ったなんて。
『伊藤と付き合えよ』と言ったみつの震えた声がまた私の中でぐるぐる渦巻いて落ちていく。姉ちゃん、なんて普段呼ばないくせに、伊藤くんの前ではそう呼んだんだね。
……みつ、本当は、ずっと前から、私から距離を取ろうとしてた?
「なあ、あお」
伊藤くんの声に顔を上げる。いつの間にか下を向いていたらしい。一気に現実に戻ってきたみたいな変な感覚。
「先に言っておきたいんだけど」
「うん」
「俺は、たぶんまだあおのこと好きだと思う」
「……うん」
「連絡したのも、あおを忘れられなかったからだし、別れてからずっと後悔してた。あのとき、みつくんを見て話をしたあと、馬鹿みたいに焦って。―――あおとみつくんは姉弟なのにな。勝手に嫉妬して、俺、本当に馬鹿だったと思う」
「……それは、」
「─────でも」
カラン、と氷がぶつかる音がした。
伊藤くんが真っ直ぐ私を見つめるから、私も伊藤くんから目を離したらいけないと思った。これから言われる言葉を、きちんと聞かなくちゃならないと思った。
「俺は、あおが幸せになれたらいいと思うけど、幸せって、結局本人が決めることだと思うんだ」
手先が震えた。喉から水分がすべて吸い取られていってしまうような感覚だった。
「1回くらい、自分の気持ちに素直になってもいいんじゃないの? って、俺はそう思うよ。あおが幸せだと感じるなら、それでいいと思う」
いろんなものがぐるぐると渦巻いて私に降ってきて、先の見えない大きな洞窟にでもひとりで取り残されてしまったみたいに感じる。
─────『自分の気持ちに素直になっても』
伊藤くんの言いたいことは痛いほどわかった。彼がすべて気づいていて、言葉を選んでくれていることも、私のことをとても大切に考えていてくれたことも、全部全部、わかった。
でも─────弟、だ。
みつは、私の家族で、大切な『弟』。血は繋がっていないけれど、同じものを食べて、同じ家に帰って、同じシャンプーを使って、同じ時間を共に過ごしてきた。お父さんとお義母さんの幸せそうな顔を、ふたりで見ながら笑い合った。大切な家族。大切な弟。だいじな、大事な、……『弟』の、みつ。
『大丈夫?』と言ったみかちんの声を思い出す。私って案外気持ちを隠すのが下手なのかもしれない。みかちんだってきっとずっと色んなことを察していたんだろう。
素直になるって、何?
みつに対する家族以上の気持ち? みつが私に向けるベクトルが姉のそれではないこと? わかっているのに認めちゃいけないって、わたしが自分の気持ちを制限するのはそんなにダメなこと? 年上で、お姉ちゃんで、みつよりしっかりしていなきゃいけないのは、私の方なんだよ。
どれだけ足掻いたって、私とみつは家族だ。姉と、弟以上にはなれない。なっちゃいけない。
どれだけ考えたって、わたしの気持ちは無駄でしかない。それなら、認めるなんてそんなこと、したくない。
素直になんて、なれるわけない。