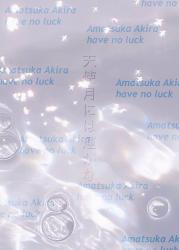◇
コンコン、と乾いたノック音がした後、私の返事を待たずに部屋の扉が開いた。
「あお? いんの?」
─────みつの声。
自分の部屋のベットに横になっている私は、扉には背を向けている。みつが今どんな表情なのかは全然わからない。わかりたくもないけれど。
お風呂から上がってもみつの部屋に行かなかった私を心配してやってきたんだろう。みつの部屋に行くことは私の日課だから。
「……寝てる?」
ふわりと。シャンプーの香りがした。同じものを使っているはずなのに、相変わらず私の元は全く別のような気がしてしまう。香りに誘われて頬を寄せる仕草をカブトムシに例えた歌を思い出して、私のことかな、なんて馬鹿げたことを考える。
みつがこちらへ近づいてくる足音。返事をしないで目を瞑るずるい私。私の名前を呼んだみつ。お風呂上がりの香りがするみつ。部屋に行かないだけで心配するみつ。弟の、みつ。─────彼女ができた、みつ。
「なあ、あお」
ギシ、とベットがきしんだ音と同時に、私の背中あたりが少し沈んだ。みつがベットに手をついたんだろう。
目を開けてないからわからない。けれどきっとみつは、両手をベットについて、私に覆いかぶさるように顔を覗き込んでいる。
「……目、開けろよ」
ああ、やっぱり。
恐る恐る、うっすらと、ゆっくり目を開けて視界のピントを合わせると、思った通りみつが私の顔を覗き込んでいた。その瞳が真っ直ぐすぎて、私の胸はぎゅっと苦しくなる。まるで何かを射貫くみたいな目線。
……私がみつの行動を読めるように。
きっとみつも、私の行動なんてお見通しなんだろう。部屋に入って来た時から、私が寝ていないを知っていて近づいてきたんだろう。そんなのわかっていたし、きっとみつも、全部わかってる。
私はずるい。でも、みつもとてもずるいね。
「……ユカリちゃん、彼女にしたんだ?」
自分でもビックリするくらい、弱弱しくて震えた声が出た。こんなはずじゃ、なかったのに。
見上げたみつの顔は揺れも歪みもしなかった。何かを決めたように、まっすぐ私を見下ろしている。その表情は今まで見たことが無いくらい感情が無くて、少し怖い。みつのことを怖いと思う自分が、信じられないけれど。
「……情報早いじゃん」
「はは、みかちんから電話きたよ。ビックリしちゃった。いつ作るんだろうとは思っていたけど、まさかユカリちゃん彼女にするなんて思ってなかったよ。あー、やっぱりみつも男だもんねえ。あんなにかわいい子に言い寄られたら、そりゃあ好きになっちゃうようね。もー、早く言ってよ。そしたら私だって応援したのに」
「あお、聞いて」
私の話を遮るように、みつが静かに呟いた。
そこで、気づく。話している最中、私が一度もみつの目を見ていなかったことに。否定しないみつに、愕然としていることに。
……よくもまあ、こんなに想ってないことがペラペラ口から出て来るものだなあ、と思う。いつから私、こんな風になってしまったんだろう。いつから、本音とか、自分の気持ちとか、将来とか、いろんなものに嘘をついて、蓋をするようになってしまったんだろう。
「やだ、聞きたくない」
「何で?」
「みつからそんなこと、聞きたくない」
「……」
「……聞きたくない……」
今にも溢れてしまいそうな何かを、私はグッとこらえる。
胸の奥がつっかえて、目頭が熱い。鼻はツンとして、唇は硬く結ぶ。言葉とは裏腹に、溢れそうな想いはこんなにも積もっている。でも言えない。誰にも言わない。自分自身だって、肯定なんてしてやるもんか。
こんなところ、みつに見せたくなかった。
どうして私、寝たふりなんてしたんだろう。みつが入ってくること、わかっていて。……きっと、試した。みつのこと。
「……おまえは、ずりいんだよ」
鈍器で頭を殴られたみたい。衝撃、不安、葛藤、後悔、失望。どんな言葉を使ったって、私の今の気持ちを表すのには不十分だ。
ずるいよね。わかってるよ。私はとてもずるいし、弱いよ。
今、みつの顔を見れない。いつも背けてきたみつのその顔を、私は見ることが出来ない。見たら、いけない。
『みつに彼女ができた』─────普通の姉弟なら些細で小さなこと。けれどそんな小さな出来事に、自分でもびっくりするくらいダメージを食らっている。いつかくるってわかっていた日だ。でもきっと、心のどこかで一生こないことを、願っていた日だ。
気を張っていないと、泣いてしまいそうだった。
認めたくない感情がある。認めちゃいけない感情がある。
それに気づいていて気づかないふりをするの、私の得意技のはずなのに。みつの真っ直ぐさから目を逸らすことなんて、日常茶飯事のはず。私はお姉ちゃんで、みつより真っ直ぐには生きていけない。私が間違った選択をしたら、ぜんぶ、─────ぜんぶ、壊れる。
わかってる。そんなのとっくの昔に、この感情に、みつとわたしの間にある何かに、名前をつけちゃいけないって、わかってる。それなのにどうして、こんなに胸が苦しくなるんだろう。どうしてこんなに、息をするのが辛いんだろう。
「泣くくらいなら、一回くらい俺を受け入れろよ」
私をまっすぐに見下ろしたみつから、弱々しいようで力強い、矛盾した声色の言葉が落ちてくる。それと同時に、みつの骨ばった長くて細い指が、私の頰に優しく触れた。
こらえきれなかったものが、一粒頰を伝ってしまったんだろう。みつはそれを見逃さなかったんだ。
表面をなぞるだけかのように軽く、そっと触れるみつの指先が少しだけ震えているのを感じて、私はまた胸が苦しくなる。
どうして私たち、こんな関係なんだろうね。出逢い方も生まれた場所も、もっと違ったら、って。
いつもそう考えてるよ。もしかしたらみつも、そう思っているかもね。
「みつは私の、弟だよ」
背けた視線。見ることのできないみつの顔。
ずるい私の口から咄嗟に零れ落ちたのはそんな〝当たり前の〟こと。姉である私が言わなきゃならない普通のこと。
ねえ、みつ。
私はみつのお姉ちゃんで、みつは私の弟だよ。これからもずっと、きっと一生変わることのない、変えることのできない現実だよ。みつもわかってるでしょう。わかってるから、肝心な一言は絶対に言わないようにしてるんでしょう。
「……」
何も言わなかった。
返事が落ちて来るより先に、私の頬に触れていたみつの手が、私に覆いかぶさっていたみつの身体が、離れていくのを感じた。同時に気持ちも、離れていけばいいのに、なんて思う。バカみたいだね。
私は顔を布団にうずめて、みつがベットから降りて扉の方へと歩いていく音を聞いていた。聞く事しか出来ないから。
見たらきっと、ダメだと思った。
「伊藤と付き合えよ。あいつ、きっと幸せにしてくれると思う」
扉が開く音と同時に、冷たくて鋭い言葉が私の背中に届く。
ゆっくりと閉められた扉の音が、まるで全部終わりみたいに悲しい音だったから、私はもっと強く布団に顔を擦り付けた。ミント色でお気に入りのシーツが、深い緑色に染まっていく。
みつ。─────みつ。私の弟の、みつ。
私もみつも、ずるいよ。私もみつも矛盾してるよ。でもそうやってしか、生きていけないよ。
どこで間違えたんだろう。どうしてこうなってしまったんだろう。こんなはずじゃなかったのに。
みつが家にやってきたあの日、“いいお姉ちゃんになろう〟って決めたのに。ずっと、みつにとっていいお姉ちゃんでいられるように、程よい距離を保っていたのに。
もしかしたら、私の方がずっと、みつのこと、必要としていたのかもしれない。
コンコン、と乾いたノック音がした後、私の返事を待たずに部屋の扉が開いた。
「あお? いんの?」
─────みつの声。
自分の部屋のベットに横になっている私は、扉には背を向けている。みつが今どんな表情なのかは全然わからない。わかりたくもないけれど。
お風呂から上がってもみつの部屋に行かなかった私を心配してやってきたんだろう。みつの部屋に行くことは私の日課だから。
「……寝てる?」
ふわりと。シャンプーの香りがした。同じものを使っているはずなのに、相変わらず私の元は全く別のような気がしてしまう。香りに誘われて頬を寄せる仕草をカブトムシに例えた歌を思い出して、私のことかな、なんて馬鹿げたことを考える。
みつがこちらへ近づいてくる足音。返事をしないで目を瞑るずるい私。私の名前を呼んだみつ。お風呂上がりの香りがするみつ。部屋に行かないだけで心配するみつ。弟の、みつ。─────彼女ができた、みつ。
「なあ、あお」
ギシ、とベットがきしんだ音と同時に、私の背中あたりが少し沈んだ。みつがベットに手をついたんだろう。
目を開けてないからわからない。けれどきっとみつは、両手をベットについて、私に覆いかぶさるように顔を覗き込んでいる。
「……目、開けろよ」
ああ、やっぱり。
恐る恐る、うっすらと、ゆっくり目を開けて視界のピントを合わせると、思った通りみつが私の顔を覗き込んでいた。その瞳が真っ直ぐすぎて、私の胸はぎゅっと苦しくなる。まるで何かを射貫くみたいな目線。
……私がみつの行動を読めるように。
きっとみつも、私の行動なんてお見通しなんだろう。部屋に入って来た時から、私が寝ていないを知っていて近づいてきたんだろう。そんなのわかっていたし、きっとみつも、全部わかってる。
私はずるい。でも、みつもとてもずるいね。
「……ユカリちゃん、彼女にしたんだ?」
自分でもビックリするくらい、弱弱しくて震えた声が出た。こんなはずじゃ、なかったのに。
見上げたみつの顔は揺れも歪みもしなかった。何かを決めたように、まっすぐ私を見下ろしている。その表情は今まで見たことが無いくらい感情が無くて、少し怖い。みつのことを怖いと思う自分が、信じられないけれど。
「……情報早いじゃん」
「はは、みかちんから電話きたよ。ビックリしちゃった。いつ作るんだろうとは思っていたけど、まさかユカリちゃん彼女にするなんて思ってなかったよ。あー、やっぱりみつも男だもんねえ。あんなにかわいい子に言い寄られたら、そりゃあ好きになっちゃうようね。もー、早く言ってよ。そしたら私だって応援したのに」
「あお、聞いて」
私の話を遮るように、みつが静かに呟いた。
そこで、気づく。話している最中、私が一度もみつの目を見ていなかったことに。否定しないみつに、愕然としていることに。
……よくもまあ、こんなに想ってないことがペラペラ口から出て来るものだなあ、と思う。いつから私、こんな風になってしまったんだろう。いつから、本音とか、自分の気持ちとか、将来とか、いろんなものに嘘をついて、蓋をするようになってしまったんだろう。
「やだ、聞きたくない」
「何で?」
「みつからそんなこと、聞きたくない」
「……」
「……聞きたくない……」
今にも溢れてしまいそうな何かを、私はグッとこらえる。
胸の奥がつっかえて、目頭が熱い。鼻はツンとして、唇は硬く結ぶ。言葉とは裏腹に、溢れそうな想いはこんなにも積もっている。でも言えない。誰にも言わない。自分自身だって、肯定なんてしてやるもんか。
こんなところ、みつに見せたくなかった。
どうして私、寝たふりなんてしたんだろう。みつが入ってくること、わかっていて。……きっと、試した。みつのこと。
「……おまえは、ずりいんだよ」
鈍器で頭を殴られたみたい。衝撃、不安、葛藤、後悔、失望。どんな言葉を使ったって、私の今の気持ちを表すのには不十分だ。
ずるいよね。わかってるよ。私はとてもずるいし、弱いよ。
今、みつの顔を見れない。いつも背けてきたみつのその顔を、私は見ることが出来ない。見たら、いけない。
『みつに彼女ができた』─────普通の姉弟なら些細で小さなこと。けれどそんな小さな出来事に、自分でもびっくりするくらいダメージを食らっている。いつかくるってわかっていた日だ。でもきっと、心のどこかで一生こないことを、願っていた日だ。
気を張っていないと、泣いてしまいそうだった。
認めたくない感情がある。認めちゃいけない感情がある。
それに気づいていて気づかないふりをするの、私の得意技のはずなのに。みつの真っ直ぐさから目を逸らすことなんて、日常茶飯事のはず。私はお姉ちゃんで、みつより真っ直ぐには生きていけない。私が間違った選択をしたら、ぜんぶ、─────ぜんぶ、壊れる。
わかってる。そんなのとっくの昔に、この感情に、みつとわたしの間にある何かに、名前をつけちゃいけないって、わかってる。それなのにどうして、こんなに胸が苦しくなるんだろう。どうしてこんなに、息をするのが辛いんだろう。
「泣くくらいなら、一回くらい俺を受け入れろよ」
私をまっすぐに見下ろしたみつから、弱々しいようで力強い、矛盾した声色の言葉が落ちてくる。それと同時に、みつの骨ばった長くて細い指が、私の頰に優しく触れた。
こらえきれなかったものが、一粒頰を伝ってしまったんだろう。みつはそれを見逃さなかったんだ。
表面をなぞるだけかのように軽く、そっと触れるみつの指先が少しだけ震えているのを感じて、私はまた胸が苦しくなる。
どうして私たち、こんな関係なんだろうね。出逢い方も生まれた場所も、もっと違ったら、って。
いつもそう考えてるよ。もしかしたらみつも、そう思っているかもね。
「みつは私の、弟だよ」
背けた視線。見ることのできないみつの顔。
ずるい私の口から咄嗟に零れ落ちたのはそんな〝当たり前の〟こと。姉である私が言わなきゃならない普通のこと。
ねえ、みつ。
私はみつのお姉ちゃんで、みつは私の弟だよ。これからもずっと、きっと一生変わることのない、変えることのできない現実だよ。みつもわかってるでしょう。わかってるから、肝心な一言は絶対に言わないようにしてるんでしょう。
「……」
何も言わなかった。
返事が落ちて来るより先に、私の頬に触れていたみつの手が、私に覆いかぶさっていたみつの身体が、離れていくのを感じた。同時に気持ちも、離れていけばいいのに、なんて思う。バカみたいだね。
私は顔を布団にうずめて、みつがベットから降りて扉の方へと歩いていく音を聞いていた。聞く事しか出来ないから。
見たらきっと、ダメだと思った。
「伊藤と付き合えよ。あいつ、きっと幸せにしてくれると思う」
扉が開く音と同時に、冷たくて鋭い言葉が私の背中に届く。
ゆっくりと閉められた扉の音が、まるで全部終わりみたいに悲しい音だったから、私はもっと強く布団に顔を擦り付けた。ミント色でお気に入りのシーツが、深い緑色に染まっていく。
みつ。─────みつ。私の弟の、みつ。
私もみつも、ずるいよ。私もみつも矛盾してるよ。でもそうやってしか、生きていけないよ。
どこで間違えたんだろう。どうしてこうなってしまったんだろう。こんなはずじゃなかったのに。
みつが家にやってきたあの日、“いいお姉ちゃんになろう〟って決めたのに。ずっと、みつにとっていいお姉ちゃんでいられるように、程よい距離を保っていたのに。
もしかしたら、私の方がずっと、みつのこと、必要としていたのかもしれない。