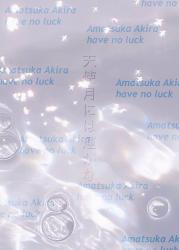あおがやってきた日のことは今でも鮮明に思い出せる。
やっと物心がついたような小学校低学年の俺は、母さんが連れてきた新しい父親と初めての〝お姉ちゃん〟を正直きちんと受け止めきれなくて、狭いアパートの一室で大声をあげて泣いていた。
母さんは『ごめんね』と言った。『でも、みつは絶対幸せになれるよ』と、俺の頭をやさしくなでた。
俺の幸せを勝手に決めるな、とその時はひどく憤りを感じたものだ。幼いながらに、俺は母さんが違う人に愛情を注いでしまうことが怖かったんだろう。何せ、生まれた時から家族というものを知らないのだから。
今でも、覚えている。
馬鹿みたいに泣いて、いやだいやだと駄々を捏ね、部屋から出ない俺の頭を、母さんの手よりも幾分か小さな手が、ゆっくりと優しくなでた、あのときのこと。
『———みつ』
初めて聞いた声だった。色に例えたら水色のような、緑のような、またはそれらを混ぜたような、そんな雨上がりの空の色のようだと思った。
『大丈夫だよ、わたし、今日からみつの味方だから』
顔を上げた先にいた、丸っこい目をした俺と同い年くらいの女の子が、歯を見せて笑っていた。それがなぜか、あまりに眩しくて、涙が思わず引っ込んでしまったのを覚えている。
『わたし、あおって言うの。よろしくね、みつ』
水色のような、緑のような、またはそれらを混ぜたような、そんな声をして、名前は“あお”だなんて出来過ぎてる。
自分だって初対面の、家族になろうとしている赤の他人に、不安や葛藤を抱えているはずなのに。それを全部押し殺して、必死に『お姉ちゃん』になろうとしている彼女がそのときとても———きれいだと、おもった。