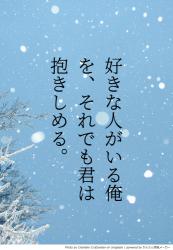エクレアをごちそうになって以来、ほたるは時々、部活帰りの僕を家庭科室に誘うようになった。
「え! 夏休みも部活なの。樹さん」
各種スイーツを食べさせてもらった後に、ほたると並んで電車に揺られることにもすっかり慣れた。
「ああ、うん。八月の初めに大会があってさ。それの調整もあるし」
「大会? え、この間、県大会優勝してた……って、全国⁉」
電車の中なのに声がでかい。僕は隣に立つほたるの脇腹を肘で突いて黙らせてから、小声で言った。
「そうだけど。まあ、全国ではそうもいかないよ。予選通過も多分無理」
「あれだけ練習してるのに?」
納得がいかない、とその顔が言っている。思わず笑ってしまいながら、僕は肩をすくめた。
「勝ちたいけど、どっちかっていうと僕はさ、完璧な射形を見つけることが目標だから」
「しゃけい?」
「射るときの姿」
混んだ車内では大きくアクションはできないけれど、両手で少しだけ弓を引き絞る動作をしてみせると、ほたるが細かく頷いた。
「確かに樹さんの弓持ってる恰好はかっこいいと思った」
「見たこと、あったっけ?」
弓道場にほたるは今もお菓子を差し入れてくれているが、誰にも姿を見られぬようこっそりと靴箱の上に置いていくのは相変わらずで、部活中に彼が弓道場にいたことはない。
ほたるはちょっと迷うように目を彷徨わせてから、投げ捨てるように言った。
「見た。中学のとき。何度か」
「え、うそ」
「だって。樹さん、突然、コンビニにも顔、出さなくなったじゃん」
ほたるの拗ねたような口ぶりに、僕は声を失う。
確かにそうだった。あのころ、家にも満足に帰ってこない僕のことを、両親は随分気に病んでいた。ごくごく普通の家で、特別虐げられて育ったわけでもない。しいて言うならふたつ年上の兄が優秀過ぎたことくらいだろうか。勝手にいじけて、勝手に閉じて、学校にも馴染めなくて。そんな黒雲が折り重なったような心に手を焼いていた僕を、両親は叔母の家へと連れて行った。
叔母は、弓道の師範として教室を営んでいた。
正直、弓道なんて意味がわからないと思った。こんな前時代的な武具、使う機会もなく、意識高い系のおすまし野郎の自意識を満足させるだけの、つまんない玩具だとすら思っていた。はっきりと叔母にそう言いさえした。
にもかかわらず、無理やり取り組まされた弓道に僕は、はまった。
誰かに左右されず、自分だけで、技をひたすらに磨く。その弓道独特の世界に僕は虜になった。
弓を引けば引くほど、自分の中に立ち込めていた靄が晴れていく気がした。
鬱屈した思いに取りつかれ、闇雲に人を傷つけてきた自分を恥じもした。
だから、学校にはほぼ行かなかったが、叔母の家にだけは毎日通った。
結果、これまでうろついていた街からも、ほたると並んで時間を潰していたコンビニからも、足は遠のいた。
「めちゃくちゃショックだったんだ。樹さん、来なくなっちゃって。でも樹さんと同じ中学のやつが樹さん、今、弓道してるって教えてくれて。俺、こっそり覗きに行っちゃったんだ。そんなんやめて俺とまた遊ぼうぜって言いたくて。でも」
ほたるの目がすっと車外へと向けられる。黒く沈んだ窓ガラスの向こう、ぽつりぽつりと灯る民家の明かりが、星のように流れていく。
「見てたら、連れ戻そうなんて気、なくなっちゃったよ。だって樹さん、びっくりするくらい真剣なんだもん。あんな目、できるんだなあって思ったらなんていうか、すげえ応援したくなって」
「そう、なんだ」
まったく気付いていなかった。ごめん、と言いかけた僕をほたるが見下ろす。そのとき、電車が大きく揺れた。少しふらついた僕の肘を、ほたるの手がくい、と掴んで支える。
「樹さん、弓道、出会えてよかったね。本当に、よかった」
低い声に言われて、胸がぐっと押された気がした。
と同時に、訊きたくなった。
お前はなんで、僕と同じ高校へ通おうと思ったんだ? と。
訊こうと思えば訊ける。けれど、あの日から引っかかっているのだ。
――付き合ってる人、いる?
ほたるが僕に向かって投げかけた問いがずっと。
付き合ってる人。
ほたるはなんであんなことを訊いてきたのだろう。
中学時代、並んで夜を明かした。コンビニでアイスを半分にして食べた。どうでもいい話をして笑って、時間が経つのをじっとふたりで待った。
あそこにあったのだろうか。答えがなにか。
返事を求めるように見返すと、ほたるが長い首をふっと傾げる。
「樹さん? どした?」
「……いや、なんでもない」
首を振る僕をほたるはしばらく眺めてから、再び車窓に目を向けて言った。
「今日さ、家庭科室の冷蔵庫にプリン仕込んできたんだ。明日にはできるから、部活終わったら家庭科室来てよ、樹さん」
「え! 夏休みも部活なの。樹さん」
各種スイーツを食べさせてもらった後に、ほたると並んで電車に揺られることにもすっかり慣れた。
「ああ、うん。八月の初めに大会があってさ。それの調整もあるし」
「大会? え、この間、県大会優勝してた……って、全国⁉」
電車の中なのに声がでかい。僕は隣に立つほたるの脇腹を肘で突いて黙らせてから、小声で言った。
「そうだけど。まあ、全国ではそうもいかないよ。予選通過も多分無理」
「あれだけ練習してるのに?」
納得がいかない、とその顔が言っている。思わず笑ってしまいながら、僕は肩をすくめた。
「勝ちたいけど、どっちかっていうと僕はさ、完璧な射形を見つけることが目標だから」
「しゃけい?」
「射るときの姿」
混んだ車内では大きくアクションはできないけれど、両手で少しだけ弓を引き絞る動作をしてみせると、ほたるが細かく頷いた。
「確かに樹さんの弓持ってる恰好はかっこいいと思った」
「見たこと、あったっけ?」
弓道場にほたるは今もお菓子を差し入れてくれているが、誰にも姿を見られぬようこっそりと靴箱の上に置いていくのは相変わらずで、部活中に彼が弓道場にいたことはない。
ほたるはちょっと迷うように目を彷徨わせてから、投げ捨てるように言った。
「見た。中学のとき。何度か」
「え、うそ」
「だって。樹さん、突然、コンビニにも顔、出さなくなったじゃん」
ほたるの拗ねたような口ぶりに、僕は声を失う。
確かにそうだった。あのころ、家にも満足に帰ってこない僕のことを、両親は随分気に病んでいた。ごくごく普通の家で、特別虐げられて育ったわけでもない。しいて言うならふたつ年上の兄が優秀過ぎたことくらいだろうか。勝手にいじけて、勝手に閉じて、学校にも馴染めなくて。そんな黒雲が折り重なったような心に手を焼いていた僕を、両親は叔母の家へと連れて行った。
叔母は、弓道の師範として教室を営んでいた。
正直、弓道なんて意味がわからないと思った。こんな前時代的な武具、使う機会もなく、意識高い系のおすまし野郎の自意識を満足させるだけの、つまんない玩具だとすら思っていた。はっきりと叔母にそう言いさえした。
にもかかわらず、無理やり取り組まされた弓道に僕は、はまった。
誰かに左右されず、自分だけで、技をひたすらに磨く。その弓道独特の世界に僕は虜になった。
弓を引けば引くほど、自分の中に立ち込めていた靄が晴れていく気がした。
鬱屈した思いに取りつかれ、闇雲に人を傷つけてきた自分を恥じもした。
だから、学校にはほぼ行かなかったが、叔母の家にだけは毎日通った。
結果、これまでうろついていた街からも、ほたると並んで時間を潰していたコンビニからも、足は遠のいた。
「めちゃくちゃショックだったんだ。樹さん、来なくなっちゃって。でも樹さんと同じ中学のやつが樹さん、今、弓道してるって教えてくれて。俺、こっそり覗きに行っちゃったんだ。そんなんやめて俺とまた遊ぼうぜって言いたくて。でも」
ほたるの目がすっと車外へと向けられる。黒く沈んだ窓ガラスの向こう、ぽつりぽつりと灯る民家の明かりが、星のように流れていく。
「見てたら、連れ戻そうなんて気、なくなっちゃったよ。だって樹さん、びっくりするくらい真剣なんだもん。あんな目、できるんだなあって思ったらなんていうか、すげえ応援したくなって」
「そう、なんだ」
まったく気付いていなかった。ごめん、と言いかけた僕をほたるが見下ろす。そのとき、電車が大きく揺れた。少しふらついた僕の肘を、ほたるの手がくい、と掴んで支える。
「樹さん、弓道、出会えてよかったね。本当に、よかった」
低い声に言われて、胸がぐっと押された気がした。
と同時に、訊きたくなった。
お前はなんで、僕と同じ高校へ通おうと思ったんだ? と。
訊こうと思えば訊ける。けれど、あの日から引っかかっているのだ。
――付き合ってる人、いる?
ほたるが僕に向かって投げかけた問いがずっと。
付き合ってる人。
ほたるはなんであんなことを訊いてきたのだろう。
中学時代、並んで夜を明かした。コンビニでアイスを半分にして食べた。どうでもいい話をして笑って、時間が経つのをじっとふたりで待った。
あそこにあったのだろうか。答えがなにか。
返事を求めるように見返すと、ほたるが長い首をふっと傾げる。
「樹さん? どした?」
「……いや、なんでもない」
首を振る僕をほたるはしばらく眺めてから、再び車窓に目を向けて言った。
「今日さ、家庭科室の冷蔵庫にプリン仕込んできたんだ。明日にはできるから、部活終わったら家庭科室来てよ、樹さん」
プリンがあるから帰りに寄ってくれ、と昨夜ほたるは言っていた。
ほたるが作ったプリンだ。さぞかし美味いだろう。
それは楽しみではあるのだ。あるのだが、昨日、電車で会話をして以来、なにかが引っかかって集中できない。
「部長、調子悪そうですねえ」
弓道場を出て、気分転換にランニングをしていると、後ろから追いついてきた宮池くんに声をかけられた。
「そう見える?」
グラウンド脇のベンチに腰を下した僕の横に、宮池くんも座る。
「見えますね。前、部長言ってたけど、射形には心が表れてしまうっていうの、あれ、本当なんだなあと、今日の部長見て、初めてわかりました」
「初めて……」
宮池くんが弓道部に入って三か月以上になる。熱心に指導してきたのに、今になって初めてと言われるのは複雑だ。
けれど問題はもちろん、彼の成長速度がどうこうではなく、彼から見てもはっきりわかるほど、自分が的に集中できていないということだ。
そんなに思い悩むことではないのだ。昔の話をした、ほたるが応援してくれていた、それが事実のすべてだ。
にもかかわらず、妙に気にかかるのはなんでだろう。
ホイッスルの音と共にグラウンドに散っていた陸上部らしき生徒たちがさああっと集まっていく。あんなふうに音ひとつで切り換えられたらいいのに、とぼんやり思っていると、目の前にぬっとなにかが突き出された。と同時に、ふわっと人工的な甘い香りが鼻をくすぐった。
「なに?」
「残り、あげまふ」
赤いパッケージに包まれたチョコレート菓子だった。中央で折って食べられるタイプのもので、折られた半分はすでに宮池くんの口の端からぶら下がっていた。
「どしたの、これ」
「今日、同じクラスの子にもらったんですけど、忘れてて。おすそわけ。良かったらどーぞ」
「はあ……」
今日は三十度を超える暑さだ。少し溶けているのが目で見てもわかる。どうしようかな、と思ったけれど、無邪気に差し出してくる宮池くんを見ていたら断るのも憚られた。
心配してくれているようなのだから。
「ありがとう」
礼を言い、チョコレートを受け取る。頬張ると、甘ったるさで口が粘ついた。
「甘いね」
「まあ、チョコですからねえ」
のんびりと宮池くんが言う。あまりにも当たり前のことを当たり前に言うので、少し笑ってしまった。この素直さを見習って、気になることは臆せず訊けばいいのだろうか。
けれど。
――付き合ってる人、いる?
「樹さん」
脳内に過った声と、リアルの声が重なる。はっとして現実に意識を戻して振り向くと、つられたように宮池くんもそちらを見た。
視線の先に、ほたるがいた。
通学鞄を肩に負い、佇んでいる。ああ、と手を上げようとした僕を、ほたるはまじまじと見ている。
「ほたる?」
呼びかけてベンチから腰を上げたのと同時だった。ほたるの顔が歪んだ。そのままくるりと背中を向けて歩き出す。
大股で歩み去っていくほたるを、僕はぽかんとして見送った。
ほたるは表情が少ない。笑顔を見せることはあるけれど、すべての表情がどこか淡い。
ただ、そんな温度の低い表情しか見せないほたるではあっても、今過ったものがどんな感情によるものなのかは、僕にも想像がついた。
あれは、怒っている顔だ。
「部長、速水とやっぱり知り合いなんですか? え、部長? ちょっと!」
宮池くんがなにかを言っていたけれど、構わず僕は走り出した。
「ほたる! ほたるって!」
走って追いかけるが、ほたるは止まらない。早足だったはずが、いつの間にか全力で僕を突き放しにかかっている。
「おい! こら! なんなんだよ! はっきり言えって! 止まれ、この野郎!」
普段の僕なら絶対にない口の悪さで呼び止めると、肩越しに振り返ったほたるが応酬してきた。
「狂犬出てるけど! 樹さん、いいの?!」
「うるせえよ! だったら止まれってんだよ! クソが!」
「止まってやるかよ! バーカ!」
馬鹿だと。
かっとなって足を早める僕から顔を背け、ほたるが吠えた。
「俺がなんで怒ってるか、自分の胸に手当ててよく考えてみろよ!」
「は……?!」
とっさに立ち止まる。数メートル先でほたるも足を止めた。
肩を上下させ、ほたるは腰を折る。
「約束、したのに」
切れ切れの息の間に声が落ちた。
「他のやつとはしないって、約束したのに!」
――他のやつとさ、半分こは、しないでほしい。
甘さがじりりと口の中を刺す。蘇ったほたるの声に息を呑む僕を、ばっとほたるが振り返った。
「いっつもそうだよ。樹さんはいっつも俺のこと見てない。気にしてない。中学のときもそうだよ。突然、いなくなって。なかったことみたいに全部封じ込めて。でも、俺は、俺はさ!」
声が跳ね上がる。蝉の声に喧嘩を売るように、ほたるは叫んだ。
「樹さんと一緒にいる時間、すごく……大事に思ってるのに!」
ほたる、と呼びかけたかった。けれど、僕に名前を呼ばれる前に、ほたるは走り去った。もう後ろを振り向くことなく全力で。
「あいつ、相変わらず、足はや……」
どんどん遠ざかる彼を見送りながら僕は呟く。苦笑いが出るかと思った。でも、笑えなかった。
お前のせいだと言わんばかりに降ってくる蝉の声が、痛かった。
ほたるが作ったプリンだ。さぞかし美味いだろう。
それは楽しみではあるのだ。あるのだが、昨日、電車で会話をして以来、なにかが引っかかって集中できない。
「部長、調子悪そうですねえ」
弓道場を出て、気分転換にランニングをしていると、後ろから追いついてきた宮池くんに声をかけられた。
「そう見える?」
グラウンド脇のベンチに腰を下した僕の横に、宮池くんも座る。
「見えますね。前、部長言ってたけど、射形には心が表れてしまうっていうの、あれ、本当なんだなあと、今日の部長見て、初めてわかりました」
「初めて……」
宮池くんが弓道部に入って三か月以上になる。熱心に指導してきたのに、今になって初めてと言われるのは複雑だ。
けれど問題はもちろん、彼の成長速度がどうこうではなく、彼から見てもはっきりわかるほど、自分が的に集中できていないということだ。
そんなに思い悩むことではないのだ。昔の話をした、ほたるが応援してくれていた、それが事実のすべてだ。
にもかかわらず、妙に気にかかるのはなんでだろう。
ホイッスルの音と共にグラウンドに散っていた陸上部らしき生徒たちがさああっと集まっていく。あんなふうに音ひとつで切り換えられたらいいのに、とぼんやり思っていると、目の前にぬっとなにかが突き出された。と同時に、ふわっと人工的な甘い香りが鼻をくすぐった。
「なに?」
「残り、あげまふ」
赤いパッケージに包まれたチョコレート菓子だった。中央で折って食べられるタイプのもので、折られた半分はすでに宮池くんの口の端からぶら下がっていた。
「どしたの、これ」
「今日、同じクラスの子にもらったんですけど、忘れてて。おすそわけ。良かったらどーぞ」
「はあ……」
今日は三十度を超える暑さだ。少し溶けているのが目で見てもわかる。どうしようかな、と思ったけれど、無邪気に差し出してくる宮池くんを見ていたら断るのも憚られた。
心配してくれているようなのだから。
「ありがとう」
礼を言い、チョコレートを受け取る。頬張ると、甘ったるさで口が粘ついた。
「甘いね」
「まあ、チョコですからねえ」
のんびりと宮池くんが言う。あまりにも当たり前のことを当たり前に言うので、少し笑ってしまった。この素直さを見習って、気になることは臆せず訊けばいいのだろうか。
けれど。
――付き合ってる人、いる?
「樹さん」
脳内に過った声と、リアルの声が重なる。はっとして現実に意識を戻して振り向くと、つられたように宮池くんもそちらを見た。
視線の先に、ほたるがいた。
通学鞄を肩に負い、佇んでいる。ああ、と手を上げようとした僕を、ほたるはまじまじと見ている。
「ほたる?」
呼びかけてベンチから腰を上げたのと同時だった。ほたるの顔が歪んだ。そのままくるりと背中を向けて歩き出す。
大股で歩み去っていくほたるを、僕はぽかんとして見送った。
ほたるは表情が少ない。笑顔を見せることはあるけれど、すべての表情がどこか淡い。
ただ、そんな温度の低い表情しか見せないほたるではあっても、今過ったものがどんな感情によるものなのかは、僕にも想像がついた。
あれは、怒っている顔だ。
「部長、速水とやっぱり知り合いなんですか? え、部長? ちょっと!」
宮池くんがなにかを言っていたけれど、構わず僕は走り出した。
「ほたる! ほたるって!」
走って追いかけるが、ほたるは止まらない。早足だったはずが、いつの間にか全力で僕を突き放しにかかっている。
「おい! こら! なんなんだよ! はっきり言えって! 止まれ、この野郎!」
普段の僕なら絶対にない口の悪さで呼び止めると、肩越しに振り返ったほたるが応酬してきた。
「狂犬出てるけど! 樹さん、いいの?!」
「うるせえよ! だったら止まれってんだよ! クソが!」
「止まってやるかよ! バーカ!」
馬鹿だと。
かっとなって足を早める僕から顔を背け、ほたるが吠えた。
「俺がなんで怒ってるか、自分の胸に手当ててよく考えてみろよ!」
「は……?!」
とっさに立ち止まる。数メートル先でほたるも足を止めた。
肩を上下させ、ほたるは腰を折る。
「約束、したのに」
切れ切れの息の間に声が落ちた。
「他のやつとはしないって、約束したのに!」
――他のやつとさ、半分こは、しないでほしい。
甘さがじりりと口の中を刺す。蘇ったほたるの声に息を呑む僕を、ばっとほたるが振り返った。
「いっつもそうだよ。樹さんはいっつも俺のこと見てない。気にしてない。中学のときもそうだよ。突然、いなくなって。なかったことみたいに全部封じ込めて。でも、俺は、俺はさ!」
声が跳ね上がる。蝉の声に喧嘩を売るように、ほたるは叫んだ。
「樹さんと一緒にいる時間、すごく……大事に思ってるのに!」
ほたる、と呼びかけたかった。けれど、僕に名前を呼ばれる前に、ほたるは走り去った。もう後ろを振り向くことなく全力で。
「あいつ、相変わらず、足はや……」
どんどん遠ざかる彼を見送りながら僕は呟く。苦笑いが出るかと思った。でも、笑えなかった。
お前のせいだと言わんばかりに降ってくる蝉の声が、痛かった。
「木曜日の差し入れ、今日も来ないねえ」
靴箱の上を確かめた畑中さんが、寂しそうに肩を落とす。
「ね〜。どうしたんだろうね。毎週来てたのに。休みなのかなあ。それとも、飽きちゃったのかなあ……」
「ちょ、琴子、飽きたとか、そんな言い方……」
呟いた永井さんの腕を、谷本さんが肘で小突く。すみません、と言いたげに頭を下げられ、僕は曖昧に笑い返す。
飽きたかどうかは知らないが、絶対に許す気がないのは確かだ。
あれから二週間、ほたるは僕に近づいてこなくなった。声もかけてこないし、目も合わせない。こちらが近づこうとしても、足早に逃げていく。
完全に嫌われたと言っていいのかもしれない。
そう思うたび、なんでだか胸が疼く。
――樹さんに食べてもらえたらなあって思ってたから。
そっぽを向きながら、口許だけでうっすらと微笑むほたる。
――大人みたいな顔するくせに、エクレア食べてるときはほんっと子ども丸出しだよな。
心底呆れたという声を出すくせに、細められた目元。
――樹さんと一緒にいる時間、すごく……大事に思ってるのに!
絞り出された叫び。
謝りたいのに、どう言っていいかもわからなくて、時間ばかりが過ぎてしまう。
練習にも、全然身が入らない。
「今日も調子、悪いですか? 無理しないほうがいいですよ」
宮池くんが僕を覗き込む。この子は相変わらず周りの空気に鈍感だ。なくなった木曜日の差し入れのことにも触れないし、あの日、僕がほたるを追いかけていったことにも言及してこない。
ただ、この日は少し違った。
「部長、ちょっと訊いていいですか」
部活終わり、着替えていたときだった。改まった声で宮池くんが声をかけてきた。
「どうかした?」
「うーんと……」
自分で話しかけてきたくせに、言い淀んでいる。辛抱強く言葉を待っていると、ちょっと、と言って宮池くんがスマホを取り出した。
「部長って、これ、知ってます?」
表示されていたのは、とあるSNSツールのトーク画面だった。『菊塚高校のみんな、集まれ!』とトップに文字が見える。
「これ、うちの学校の生徒同士で作ってるグループなんです。お互い招待しあってどんどん拡がってる、まあ、非公式の」
「そうなんだ。ごめん、やってないや」
スマホは持っているが、SNSは苦手だ。いろんな情報が流れて来過ぎて、いちいち処理するのもかったるいから。
とはいえ、もちろん使っているかもしれない宮池くんを前にしてそうは言えず、首を振るに留める。宮池くんは、ですよね、と呟いてから画面をスクロールさせた。
「ここで最近、ちょっと噂になってることがあるんです」
「噂?」
「元星名中学の狂犬が紛れ込んでいるらしい。気をつけろ」
さらさらっと読み上げられた文言に、体が強張った。
星名中学。
狂犬。
「個人を特定できるものなんてないんで、誰が書いたのかもわかんないんですけどね。その後もぽろぽろそいつから書き込みがあって、狂犬っていうのが伝説のヤンキーで、めちゃくちゃ喧嘩が強くて星名中学の辺り一帯を牛耳っていたらしいとか、とにかくキレると手がつけられない要注意人物って話とかまあ、いろいろ」
「……それで?」
宮池くんはなにが言いたいのだろう。狂犬が僕だと勘づいて、先輩が狂犬ですか? とでも訊きたいのだろうか。
せっかく平穏に弓道部の部長を続けてこられたというのに、まさか後輩に知られてしまうとは。
だが、ばれてしまったのなら……仕方ない。
「宮池くん、驚いただろうけど、それ……」
「部長って速水と仲いいんですよね?」
遮られ、言葉が変な形で止まる。口を半分開けたまま、ああ、まあ、と頷く。
「地元は同じだけど」
「じゃあ、知ってますよね。この狂犬が速水だっていうの、本当ですか?」
「は?!」
今、なんて言った?
唖然とした僕を宮池くんは凝視したまま黙っている。どうやら冗談で言ったわけではなさそうだった。
「それ、え、なんで、そんな」
「最初、星名中学なんて、この辺りじゃ聞いたこともない名前だし、どこだよってなってたんですよ。けど、伝説のなんて名前のつくヤンキーなんてどんなやつなのか興味あるってだんだん盛り上がってきちゃって。こう、言い方悪いですけど、懸賞首探すみたいなノリで。そしたら」
言いつつ、宮池くんはするするとスマホを操作する。ずいと突き出された画面を見て僕は固まった。
『狂犬は俺だ。文句があるやつは俺のところまで来い。全員相手してやる。一年A組速水ほたる』
「これ……」
「本人の書き込みかどうかまではこれだけだとわかんないです。けど、直接、速水に訊いたやつが何人かいたらしいです。本当に狂犬はお前かって。そしたらあいつ、『そうだ。でもこれ以上がたがた抜かしたら、その鼻へし折るけどいいか』ってすごんだとかなんとか」
あいつはなにを言っているのだ。
額を押さえた僕の顔を、宮池くんが探るように見つめている気配を感じる。
その彼に向かい、僕は低い声で訊ねた。
「それで? 君はなにを知りたいの。真実をみんなに言って回って、情報通でも気取りたいの」
自分でもこれほど冷たい声が出るとは思っていなかった。内心驚きながらも出てしまった声は止められない。宮池くんもさぞや驚いただろうが、取り繕う気はまるで起きなかった。
「知って君はなにをするの?」
「先輩と同じです」
すぱっと言われ、張りつめていた怒りの糸がわずかに緩む。え、と目を上げると、宮池くんはスマホをつらつらと眺めていた。
「速水、この件で今、結構叩かれてるんです。裏で」
言いつつ、宮池くんは再びぐい、と僕の前にスマホを突き出した。
『狂犬とか呼ばれていい気になってるとこ、ウケる』
『時代錯誤も甚だしいってこういうやつに言うんじゃね? オワコン』
『うち進学校じゃん。こういうのいるのってどうなの? 価値下がる』
『事件起こす前にどうにかしてもらったほうがいいですよね、せんせー!』
そこまで読んで、見る気が失せた。片手でスマホを押し戻すと、宮池くんは画面を一瞥した後、スマホを鞄に滑り込ませ、ため息をついた。
「俺、別に速水と仲がいいわけでもないし、お節介なのはわかってるんです。でもこういうのは気分悪い。みんなで寄ってたかって陰で叩くのは、あまりにも卑怯です」
きっぱりとした口調に少し驚いた。普段の彼はおっとりとしていて、あまりはっきりものを言うタイプではなかったから。
僕の驚きをよそに、宮池くんは苦い顔で、でも、と続けた。
「速水も悪いと思うんです。挑発的な態度を取って周りを刺激するのはよくない。別に過去がどうとか、俺はどうでもいいけど、そういう態度取っちゃってるのは今だから。もともと速水って友達少ないし、こんなことになったらますます孤立してしまう。そういうの、なんか俺、嫌なんです」
「宮池くんて……」
ぽろっと言葉が落ちる。え? とこちらを見た彼に、僕は思わず笑いかけてしまった。
「いい子だね」
「……馬鹿にしてるんですか」
「あ、いや、そういうことではないけど、なんか」
うれしい、と言いかけて口を噤み、気を取り直すように咳払いする。
「で、その話、僕にしたのはなんで?」
「速水、学校だと完全にシールド作っててまったく相手にしてくれないから。部長、速水の知り合いっぽいし、少しは話聞くかな〜って。すみません、勝手なことを」
「いや、むしろ、話してくれて助かった」
言いつつ、僕は鞄を手に取る。からり、と更衣室の引き戸を開け、宮池くんを振り返る。
「ほたるのとこ行ってくるから。悪いけど今日、戸締り頼める?」
「お願いします」
こくん、と頷く宮池くんに微笑んで扉を閉めると、僕は走り出した。
あそこにいてくれるといいな、と思いつつ。
靴箱の上を確かめた畑中さんが、寂しそうに肩を落とす。
「ね〜。どうしたんだろうね。毎週来てたのに。休みなのかなあ。それとも、飽きちゃったのかなあ……」
「ちょ、琴子、飽きたとか、そんな言い方……」
呟いた永井さんの腕を、谷本さんが肘で小突く。すみません、と言いたげに頭を下げられ、僕は曖昧に笑い返す。
飽きたかどうかは知らないが、絶対に許す気がないのは確かだ。
あれから二週間、ほたるは僕に近づいてこなくなった。声もかけてこないし、目も合わせない。こちらが近づこうとしても、足早に逃げていく。
完全に嫌われたと言っていいのかもしれない。
そう思うたび、なんでだか胸が疼く。
――樹さんに食べてもらえたらなあって思ってたから。
そっぽを向きながら、口許だけでうっすらと微笑むほたる。
――大人みたいな顔するくせに、エクレア食べてるときはほんっと子ども丸出しだよな。
心底呆れたという声を出すくせに、細められた目元。
――樹さんと一緒にいる時間、すごく……大事に思ってるのに!
絞り出された叫び。
謝りたいのに、どう言っていいかもわからなくて、時間ばかりが過ぎてしまう。
練習にも、全然身が入らない。
「今日も調子、悪いですか? 無理しないほうがいいですよ」
宮池くんが僕を覗き込む。この子は相変わらず周りの空気に鈍感だ。なくなった木曜日の差し入れのことにも触れないし、あの日、僕がほたるを追いかけていったことにも言及してこない。
ただ、この日は少し違った。
「部長、ちょっと訊いていいですか」
部活終わり、着替えていたときだった。改まった声で宮池くんが声をかけてきた。
「どうかした?」
「うーんと……」
自分で話しかけてきたくせに、言い淀んでいる。辛抱強く言葉を待っていると、ちょっと、と言って宮池くんがスマホを取り出した。
「部長って、これ、知ってます?」
表示されていたのは、とあるSNSツールのトーク画面だった。『菊塚高校のみんな、集まれ!』とトップに文字が見える。
「これ、うちの学校の生徒同士で作ってるグループなんです。お互い招待しあってどんどん拡がってる、まあ、非公式の」
「そうなんだ。ごめん、やってないや」
スマホは持っているが、SNSは苦手だ。いろんな情報が流れて来過ぎて、いちいち処理するのもかったるいから。
とはいえ、もちろん使っているかもしれない宮池くんを前にしてそうは言えず、首を振るに留める。宮池くんは、ですよね、と呟いてから画面をスクロールさせた。
「ここで最近、ちょっと噂になってることがあるんです」
「噂?」
「元星名中学の狂犬が紛れ込んでいるらしい。気をつけろ」
さらさらっと読み上げられた文言に、体が強張った。
星名中学。
狂犬。
「個人を特定できるものなんてないんで、誰が書いたのかもわかんないんですけどね。その後もぽろぽろそいつから書き込みがあって、狂犬っていうのが伝説のヤンキーで、めちゃくちゃ喧嘩が強くて星名中学の辺り一帯を牛耳っていたらしいとか、とにかくキレると手がつけられない要注意人物って話とかまあ、いろいろ」
「……それで?」
宮池くんはなにが言いたいのだろう。狂犬が僕だと勘づいて、先輩が狂犬ですか? とでも訊きたいのだろうか。
せっかく平穏に弓道部の部長を続けてこられたというのに、まさか後輩に知られてしまうとは。
だが、ばれてしまったのなら……仕方ない。
「宮池くん、驚いただろうけど、それ……」
「部長って速水と仲いいんですよね?」
遮られ、言葉が変な形で止まる。口を半分開けたまま、ああ、まあ、と頷く。
「地元は同じだけど」
「じゃあ、知ってますよね。この狂犬が速水だっていうの、本当ですか?」
「は?!」
今、なんて言った?
唖然とした僕を宮池くんは凝視したまま黙っている。どうやら冗談で言ったわけではなさそうだった。
「それ、え、なんで、そんな」
「最初、星名中学なんて、この辺りじゃ聞いたこともない名前だし、どこだよってなってたんですよ。けど、伝説のなんて名前のつくヤンキーなんてどんなやつなのか興味あるってだんだん盛り上がってきちゃって。こう、言い方悪いですけど、懸賞首探すみたいなノリで。そしたら」
言いつつ、宮池くんはするするとスマホを操作する。ずいと突き出された画面を見て僕は固まった。
『狂犬は俺だ。文句があるやつは俺のところまで来い。全員相手してやる。一年A組速水ほたる』
「これ……」
「本人の書き込みかどうかまではこれだけだとわかんないです。けど、直接、速水に訊いたやつが何人かいたらしいです。本当に狂犬はお前かって。そしたらあいつ、『そうだ。でもこれ以上がたがた抜かしたら、その鼻へし折るけどいいか』ってすごんだとかなんとか」
あいつはなにを言っているのだ。
額を押さえた僕の顔を、宮池くんが探るように見つめている気配を感じる。
その彼に向かい、僕は低い声で訊ねた。
「それで? 君はなにを知りたいの。真実をみんなに言って回って、情報通でも気取りたいの」
自分でもこれほど冷たい声が出るとは思っていなかった。内心驚きながらも出てしまった声は止められない。宮池くんもさぞや驚いただろうが、取り繕う気はまるで起きなかった。
「知って君はなにをするの?」
「先輩と同じです」
すぱっと言われ、張りつめていた怒りの糸がわずかに緩む。え、と目を上げると、宮池くんはスマホをつらつらと眺めていた。
「速水、この件で今、結構叩かれてるんです。裏で」
言いつつ、宮池くんは再びぐい、と僕の前にスマホを突き出した。
『狂犬とか呼ばれていい気になってるとこ、ウケる』
『時代錯誤も甚だしいってこういうやつに言うんじゃね? オワコン』
『うち進学校じゃん。こういうのいるのってどうなの? 価値下がる』
『事件起こす前にどうにかしてもらったほうがいいですよね、せんせー!』
そこまで読んで、見る気が失せた。片手でスマホを押し戻すと、宮池くんは画面を一瞥した後、スマホを鞄に滑り込ませ、ため息をついた。
「俺、別に速水と仲がいいわけでもないし、お節介なのはわかってるんです。でもこういうのは気分悪い。みんなで寄ってたかって陰で叩くのは、あまりにも卑怯です」
きっぱりとした口調に少し驚いた。普段の彼はおっとりとしていて、あまりはっきりものを言うタイプではなかったから。
僕の驚きをよそに、宮池くんは苦い顔で、でも、と続けた。
「速水も悪いと思うんです。挑発的な態度を取って周りを刺激するのはよくない。別に過去がどうとか、俺はどうでもいいけど、そういう態度取っちゃってるのは今だから。もともと速水って友達少ないし、こんなことになったらますます孤立してしまう。そういうの、なんか俺、嫌なんです」
「宮池くんて……」
ぽろっと言葉が落ちる。え? とこちらを見た彼に、僕は思わず笑いかけてしまった。
「いい子だね」
「……馬鹿にしてるんですか」
「あ、いや、そういうことではないけど、なんか」
うれしい、と言いかけて口を噤み、気を取り直すように咳払いする。
「で、その話、僕にしたのはなんで?」
「速水、学校だと完全にシールド作っててまったく相手にしてくれないから。部長、速水の知り合いっぽいし、少しは話聞くかな〜って。すみません、勝手なことを」
「いや、むしろ、話してくれて助かった」
言いつつ、僕は鞄を手に取る。からり、と更衣室の引き戸を開け、宮池くんを振り返る。
「ほたるのとこ行ってくるから。悪いけど今日、戸締り頼める?」
「お願いします」
こくん、と頷く宮池くんに微笑んで扉を閉めると、僕は走り出した。
あそこにいてくれるといいな、と思いつつ。
特別教室棟を見上げると、家庭科室にはまだ明かりが見えた。誰かいるらしい。
昇降口に回るのが面倒で、またも靴下のまま階段を駆け上がる。下校時刻を迎えた校舎は静まり返っていて、靴下履きの自分の足音さえ、鮮明に響いた。
家庭科室があるのは最上階の一番奥。しかし、近づいても人の声は聞こえない。
電気を点けっぱなしで帰ってしまっていたりしないよな、と不安になりつつ引き戸を開けると、中にいた人物が億劫そうに振り返った。
黒いエプロンをしたほたるだった。
彼はわずかに唇を開いてこちらを見つめてから、くるっと後ろを向く。そのまま何事もなかったかのように調理台を片付け始める彼に、さすがにいらっとした。
「幽霊見えたけど見えてるとばれたら祟られるみたいな顔、やめろ」
室内へ踏み入りながら言うが、ほたるは背中を向けたままだ。手も止めない。
本気で幽霊扱いか。
だが、幽霊だって実力行使することもあるのだ。
流し台でボウルを洗っている彼の横に並び、容赦なく水を止めると、ほたるの顔が歪んだ。
「そっちこそ、ガチで幽霊みたいな真似、やめろよ」
「ほー? 幽霊見えてるんだねえ、ほたるくん。それならお話しようか」
腕組みをして睨んだ僕の横で、ほたるが長い長い息を吐く。エプロンでぞんざいに手を拭き、調理台にだらしなく体重を預けた彼は、面倒臭そうにこちらを睨んだ。
「なに。あんたと話すことないんだけど」
「こっちはあるんだよ。勝手に自己完結すんな。タコが」
「……樹さん、口、どうしたの。タイム風呂敷で口だけ過去に戻ったかなんか?」
気だるげに言われますます苛立つ。
放っておくと荒っぽい声が際限なく出てしまいそうだけれど、そこで僕は自分にブレーキをかける。
僕はこいつと喧嘩したくてここに来たわけじゃない。
「まず、いくつか話したい案件がある」
「案件って。ビジネスかよ」
「うるさい。黙れ。まず、一つ目」
ようやく耳を傾ける気になったらしいほたるにほっとしつつ、僕はがばりと頭を下げた。
「え、なに」
戸惑ったような声が頭の上からする。だがそれに構わず、僕は頭を下げ続けた。
「謝らないと駄目って思ってた。ごめん、ほたる」
「なにが?」
「約束破って、宮池くんとチョコレートを食べた。ごめん」
「は……」
――他のやつとさ、半分こは、しないでほしい。
正直、ほたるのこの言葉を僕はそれほど重く受け止めてはいなかった。よくわからないけれどまあいいか、と軽い気持ちで頷いてしまった。
だが、言葉とはそんなに適当に扱っていいはずがなかったのだ。
「傷つけて、ごめん」
ほたるは黙っている。それでも頭を下げたままでいると、ほたるの口からふううっとため息が漏れた。
「案件、他にもあんの?」
「ある」
「聞くから。頭、上げて」
促され、そろそろと姿勢を戻すと、ほたるは困ったように僕から目を逸らす。相変わらずのだらしない立ち姿のまま彼は、で、なに、と言った。
「狂犬のこと」
ほたるの横顔がはっきりと引き攣った。その顔を僕は視線に力を込めて見上げる。
「どうして自分が狂犬だなんて名乗った?」
「なんのことだか」
「しらばっくれるな。俺に嘘は通用しない」
「俺って。樹さん、完全に狂犬……」
「茶化すな」
ぴしゃりと言い、僕は手を伸ばす。ぐい、と彼の腕を掴むと、手の中でほたるの腕が震えた。
「なんでそんな嘘つく? そのせいでお前、ひどいこと言われてるって聞いた。なんでそんなことする? お前は狂犬じゃない。狂犬って言われてたのは……」
「樹さんはもう、狂犬じゃないじゃん」
ばっとこちらを向き、ほたるが吠えた。気を呑まれ言葉を途切れさせると、ほたるは片手でぐしゃりと自身の前髪を掴んだ。
「もういいだろ。狂犬の称号なんて俺に預けとけよ」
「称号って! 今となったら汚名だよ。そんなもの……」
「だったら! なおのこと、あんたが背負っちゃ駄目だろ!」
怒鳴られ、背中を反らす。樹ははあっと息を吐き言った。掠れた声だった。
「せっかくさ、弓道頑張って、全国まで行くんだよ。毎日毎日、ひたすら弓持って……。そのあんたの努力を、過去のやんちゃしてた時代のせいでいろいろ言われるの、駄目だろ」
「ちょ、は? 待って。それ」
全国に行くから?
僕が?
頭がぐるぐるする。混乱し、目を見開く僕の前で、ほたるが髪から手を解く。
「わかってよ、樹さん」
ほたるの声が、揺れた。
「俺はさ、樹さんが頑張れなくなるの、嫌なんだよ。なんも知らないやつらに、好きな人が踏みつけられるなんて、絶対許せないんだ」
薄い唇が苦しげに歪むのを、僕は見つめることしかできない。
「そうさせないためなら、俺はなんでもする」
声が、出ない。
ほたるの腕を掴んでいた手から、力が、抜ける。
その僕を、ほたるの目がゆらり、と捉える。彼は細めた目で僕をしばらく見つめてから、ああ、そうだ、と呟き、通学鞄が置かれている棚へと向かった。
鞄を探ってそこから出した小袋を手に戻ってきたほたるは、それを僕の前に突き出す。
「クッキー、焼いたから。あげる」
ブリザードを連想させるほたるの見た目とはそぐわない、桜模様の紙袋に入ったそれを、僕は声もなく、瞬きすらできずに見つめる。数秒そのままでいると、手がそろそろと伸びてきた。遠慮がちな手によって、手が掴まれる。
開かされた掌に、すとん、と紙袋が置かれた。
袋越し、ほわりと熱が掌に伝わってくる。
はっとして見上げた僕の前で、ほたるは薄く……笑った。
「もう、ここには来ないで。俺に関わっちゃ、駄目だ」
言葉と共に手が引かれる。そのとたん、弾かれたように体が動いた。
「アホか! そんなことできるか!」
掌の中の袋を両手で握り、僕は叫ぶ。だが、ほたるはこちらを見ずに言い捨てた。
「できなくても、俺はもう樹さんとは口を利かない」
「そんなの……!」
怒鳴る僕を無視し、ほたるは再び、調理台の片付けを始めた。その間、いくら声をかけても一切返事をせず、彼がようやく口を開いたのはすべての作業が終わった後。
「帰るから出て」
だけだった。
昇降口に回るのが面倒で、またも靴下のまま階段を駆け上がる。下校時刻を迎えた校舎は静まり返っていて、靴下履きの自分の足音さえ、鮮明に響いた。
家庭科室があるのは最上階の一番奥。しかし、近づいても人の声は聞こえない。
電気を点けっぱなしで帰ってしまっていたりしないよな、と不安になりつつ引き戸を開けると、中にいた人物が億劫そうに振り返った。
黒いエプロンをしたほたるだった。
彼はわずかに唇を開いてこちらを見つめてから、くるっと後ろを向く。そのまま何事もなかったかのように調理台を片付け始める彼に、さすがにいらっとした。
「幽霊見えたけど見えてるとばれたら祟られるみたいな顔、やめろ」
室内へ踏み入りながら言うが、ほたるは背中を向けたままだ。手も止めない。
本気で幽霊扱いか。
だが、幽霊だって実力行使することもあるのだ。
流し台でボウルを洗っている彼の横に並び、容赦なく水を止めると、ほたるの顔が歪んだ。
「そっちこそ、ガチで幽霊みたいな真似、やめろよ」
「ほー? 幽霊見えてるんだねえ、ほたるくん。それならお話しようか」
腕組みをして睨んだ僕の横で、ほたるが長い長い息を吐く。エプロンでぞんざいに手を拭き、調理台にだらしなく体重を預けた彼は、面倒臭そうにこちらを睨んだ。
「なに。あんたと話すことないんだけど」
「こっちはあるんだよ。勝手に自己完結すんな。タコが」
「……樹さん、口、どうしたの。タイム風呂敷で口だけ過去に戻ったかなんか?」
気だるげに言われますます苛立つ。
放っておくと荒っぽい声が際限なく出てしまいそうだけれど、そこで僕は自分にブレーキをかける。
僕はこいつと喧嘩したくてここに来たわけじゃない。
「まず、いくつか話したい案件がある」
「案件って。ビジネスかよ」
「うるさい。黙れ。まず、一つ目」
ようやく耳を傾ける気になったらしいほたるにほっとしつつ、僕はがばりと頭を下げた。
「え、なに」
戸惑ったような声が頭の上からする。だがそれに構わず、僕は頭を下げ続けた。
「謝らないと駄目って思ってた。ごめん、ほたる」
「なにが?」
「約束破って、宮池くんとチョコレートを食べた。ごめん」
「は……」
――他のやつとさ、半分こは、しないでほしい。
正直、ほたるのこの言葉を僕はそれほど重く受け止めてはいなかった。よくわからないけれどまあいいか、と軽い気持ちで頷いてしまった。
だが、言葉とはそんなに適当に扱っていいはずがなかったのだ。
「傷つけて、ごめん」
ほたるは黙っている。それでも頭を下げたままでいると、ほたるの口からふううっとため息が漏れた。
「案件、他にもあんの?」
「ある」
「聞くから。頭、上げて」
促され、そろそろと姿勢を戻すと、ほたるは困ったように僕から目を逸らす。相変わらずのだらしない立ち姿のまま彼は、で、なに、と言った。
「狂犬のこと」
ほたるの横顔がはっきりと引き攣った。その顔を僕は視線に力を込めて見上げる。
「どうして自分が狂犬だなんて名乗った?」
「なんのことだか」
「しらばっくれるな。俺に嘘は通用しない」
「俺って。樹さん、完全に狂犬……」
「茶化すな」
ぴしゃりと言い、僕は手を伸ばす。ぐい、と彼の腕を掴むと、手の中でほたるの腕が震えた。
「なんでそんな嘘つく? そのせいでお前、ひどいこと言われてるって聞いた。なんでそんなことする? お前は狂犬じゃない。狂犬って言われてたのは……」
「樹さんはもう、狂犬じゃないじゃん」
ばっとこちらを向き、ほたるが吠えた。気を呑まれ言葉を途切れさせると、ほたるは片手でぐしゃりと自身の前髪を掴んだ。
「もういいだろ。狂犬の称号なんて俺に預けとけよ」
「称号って! 今となったら汚名だよ。そんなもの……」
「だったら! なおのこと、あんたが背負っちゃ駄目だろ!」
怒鳴られ、背中を反らす。樹ははあっと息を吐き言った。掠れた声だった。
「せっかくさ、弓道頑張って、全国まで行くんだよ。毎日毎日、ひたすら弓持って……。そのあんたの努力を、過去のやんちゃしてた時代のせいでいろいろ言われるの、駄目だろ」
「ちょ、は? 待って。それ」
全国に行くから?
僕が?
頭がぐるぐるする。混乱し、目を見開く僕の前で、ほたるが髪から手を解く。
「わかってよ、樹さん」
ほたるの声が、揺れた。
「俺はさ、樹さんが頑張れなくなるの、嫌なんだよ。なんも知らないやつらに、好きな人が踏みつけられるなんて、絶対許せないんだ」
薄い唇が苦しげに歪むのを、僕は見つめることしかできない。
「そうさせないためなら、俺はなんでもする」
声が、出ない。
ほたるの腕を掴んでいた手から、力が、抜ける。
その僕を、ほたるの目がゆらり、と捉える。彼は細めた目で僕をしばらく見つめてから、ああ、そうだ、と呟き、通学鞄が置かれている棚へと向かった。
鞄を探ってそこから出した小袋を手に戻ってきたほたるは、それを僕の前に突き出す。
「クッキー、焼いたから。あげる」
ブリザードを連想させるほたるの見た目とはそぐわない、桜模様の紙袋に入ったそれを、僕は声もなく、瞬きすらできずに見つめる。数秒そのままでいると、手がそろそろと伸びてきた。遠慮がちな手によって、手が掴まれる。
開かされた掌に、すとん、と紙袋が置かれた。
袋越し、ほわりと熱が掌に伝わってくる。
はっとして見上げた僕の前で、ほたるは薄く……笑った。
「もう、ここには来ないで。俺に関わっちゃ、駄目だ」
言葉と共に手が引かれる。そのとたん、弾かれたように体が動いた。
「アホか! そんなことできるか!」
掌の中の袋を両手で握り、僕は叫ぶ。だが、ほたるはこちらを見ずに言い捨てた。
「できなくても、俺はもう樹さんとは口を利かない」
「そんなの……!」
怒鳴る僕を無視し、ほたるは再び、調理台の片付けを始めた。その間、いくら声をかけても一切返事をせず、彼がようやく口を開いたのはすべての作業が終わった後。
「帰るから出て」
だけだった。
中学時代、ほたるとこんな会話をしたことがある。
「俺、学校行くの嫌になっちゃったの、自転車のせいなんですよね」
いつも通りコンビニの前でアイスをふたりで食べているときだった。不意にほたるが言い出した。
「樹さんは自転車、乗れる?」
「乗れるけど。え、お前、乗れないの?」
言うと、そうなんすよ、とほたるは肩をすくめた。
「自転車練習するきっかけって、自分からじゃないじゃん? 親が教えようって思うか、友だち同士で乗ろうって話になるか、まあ、そんな感じで。樹さんはどうだった?」
「俺は……」
確か、教えてくれたのは兄だ。ふたつ年上の兄に教えられて乗れるようになった。自転車くらい乗れないと後々大変だぞ、仲間外れにされるぞ、と脅されて。
ただ当時、出来がよすぎる兄と僕の関係は芳しくなくて、感謝の気持ちは微塵も湧いてこなかった。
ほたるは僕の微妙な顔に気付く由もなく、淡々と語っていた。
「俺、結局誰にも教えてもらえないまま中学入って。ただ俺の家、学区の端っこで自転車じゃないと毎日きつい感じの場所で。でも俺、乗れないじゃないですか。今更、学校行くために練習するのも腹立つし。で」
学校行かなくなっちゃった。
とにっこり笑ったほたるに、当時の僕は爆笑した。
お前、そんな理由で行くのやめちゃったのかよ、と。
でも今は、あのとき笑ったことを後悔している。
明るい口ぶりで言いながらも、ほたるはどことなく寂しそうだったから。
ほたるにもちゃんと両親はいる。ただ、どちらも共働きで帰宅は遅い。ほたるが小学生のころからふらふらと街を徘徊していたことにも、気付いてすらいないようだった。
そのことを……ほたるは自転車のことで言おうと思ったのかもしれない。
そして、そんなほたるにとって、僕と過ごす時間は、僕が思う以上に大事なものであったのかもしれない。
なのに、僕はほたるを置き去りにした。
「狂犬」と呼ばれた過去が嫌で、それを払拭したいがためだけに、全部なかったことにしようとした。
その僕を、ほたるは庇った。
――あんたの努力を、過去のやんちゃしてた時代のせいでいろいろ言われるの、駄目だろ。
ほたるの声が、耳からずっと離れない。
あの日受け取ったクッキーの味も、ずっと忘れられない。
甘くて、優しくて。舌を包むさくり、とした感触に労りが見えて。
食べながら、涙が止まらなかった。
あれ以来、ほたるは完全に僕の前から姿を消した。調理部にも何度か顔を出したけれど、部活にも出ていないようだった。
速水くんの作るお菓子、すっごく美味しいし、楽しみだったのに、と調理部の部長は言い、同調するように部員も頷いていた。
狂犬のことを知っているのかどうかまではわからないけれど、少なくともここではほたるは大事にされていたのだと思えて、心底ほっとした。
ただ、SNSでは相変わらず狂犬の噂はされているようで、教室でもほたるは遠巻きにされている、と宮池くんが教えてくれた。
「話しかけるんですけどね。速水自身がこう、話しかけるなオーラすごくて」
このままではいけない。
何度もそう思って、休憩時間のたびに教室を覗いた。しかし、ほたるを捕まえることはできなかった。
――俺はもう樹さんとは口を利かない。
あれは、やはり本気なのだ。
本気で、ほたるはもうこちらを見ないつもりでいる。
いいや、そうじゃない。彼は、完全に僕の目の前から消えようとしている。
「俺、学校行くの嫌になっちゃったの、自転車のせいなんですよね」
いつも通りコンビニの前でアイスをふたりで食べているときだった。不意にほたるが言い出した。
「樹さんは自転車、乗れる?」
「乗れるけど。え、お前、乗れないの?」
言うと、そうなんすよ、とほたるは肩をすくめた。
「自転車練習するきっかけって、自分からじゃないじゃん? 親が教えようって思うか、友だち同士で乗ろうって話になるか、まあ、そんな感じで。樹さんはどうだった?」
「俺は……」
確か、教えてくれたのは兄だ。ふたつ年上の兄に教えられて乗れるようになった。自転車くらい乗れないと後々大変だぞ、仲間外れにされるぞ、と脅されて。
ただ当時、出来がよすぎる兄と僕の関係は芳しくなくて、感謝の気持ちは微塵も湧いてこなかった。
ほたるは僕の微妙な顔に気付く由もなく、淡々と語っていた。
「俺、結局誰にも教えてもらえないまま中学入って。ただ俺の家、学区の端っこで自転車じゃないと毎日きつい感じの場所で。でも俺、乗れないじゃないですか。今更、学校行くために練習するのも腹立つし。で」
学校行かなくなっちゃった。
とにっこり笑ったほたるに、当時の僕は爆笑した。
お前、そんな理由で行くのやめちゃったのかよ、と。
でも今は、あのとき笑ったことを後悔している。
明るい口ぶりで言いながらも、ほたるはどことなく寂しそうだったから。
ほたるにもちゃんと両親はいる。ただ、どちらも共働きで帰宅は遅い。ほたるが小学生のころからふらふらと街を徘徊していたことにも、気付いてすらいないようだった。
そのことを……ほたるは自転車のことで言おうと思ったのかもしれない。
そして、そんなほたるにとって、僕と過ごす時間は、僕が思う以上に大事なものであったのかもしれない。
なのに、僕はほたるを置き去りにした。
「狂犬」と呼ばれた過去が嫌で、それを払拭したいがためだけに、全部なかったことにしようとした。
その僕を、ほたるは庇った。
――あんたの努力を、過去のやんちゃしてた時代のせいでいろいろ言われるの、駄目だろ。
ほたるの声が、耳からずっと離れない。
あの日受け取ったクッキーの味も、ずっと忘れられない。
甘くて、優しくて。舌を包むさくり、とした感触に労りが見えて。
食べながら、涙が止まらなかった。
あれ以来、ほたるは完全に僕の前から姿を消した。調理部にも何度か顔を出したけれど、部活にも出ていないようだった。
速水くんの作るお菓子、すっごく美味しいし、楽しみだったのに、と調理部の部長は言い、同調するように部員も頷いていた。
狂犬のことを知っているのかどうかまではわからないけれど、少なくともここではほたるは大事にされていたのだと思えて、心底ほっとした。
ただ、SNSでは相変わらず狂犬の噂はされているようで、教室でもほたるは遠巻きにされている、と宮池くんが教えてくれた。
「話しかけるんですけどね。速水自身がこう、話しかけるなオーラすごくて」
このままではいけない。
何度もそう思って、休憩時間のたびに教室を覗いた。しかし、ほたるを捕まえることはできなかった。
――俺はもう樹さんとは口を利かない。
あれは、やはり本気なのだ。
本気で、ほたるはもうこちらを見ないつもりでいる。
いいや、そうじゃない。彼は、完全に僕の目の前から消えようとしている。
逃げようとする相手を捕まえることがこれほど大変だなんて思いもしなかった。結局、一週間経った今もほたると話はできていない。
しかも今日はもう終業式だ。夏休みに入ったら、どうしたらいいのだろう。
暗澹たる気持ちを抱え、僕は昇降口へと向かう。
連日のむしゃくしゃを晴らそうと、弓道場で朝から弓を引いていたせいで、始業時間をすっかり過ぎてしまっていた。
当然皆、体育館へ移動している時間で昇降口に人影はない。焦りながら上履きに履き替えていた僕だったが、かすかな笑い声が聞こえ、ふと目を上げた。声を辿って視線を向けると、靴箱を挟んだ向こう側から二人組の男子が駆け去っていくのが見えた。
一瞬だったし、見間違いかもしれない。でも彼らのうちのひとりの手にあったものが、意識に嫌なざらつきを残した。
彼らの手にあったのは……油性マジック。
中途半端に踵が折れた状態だったけれど、上履きをつっかけるようにして僕は、彼らが駆けだしてきた側の靴箱へと回り込む。砂埃と靴箱特有の金臭い匂いに混じり、つん、と鼻を突いたのは……シンナー臭だった。
臭いの元を辿り、僕は立ちすくむ。
靴箱の中央。味も素っ気もないグレー一色の中、誰かの靴箱の扉に黒々とした文字が刻まれていた。
『狂犬。出て行け』
名札を確かめるまでもなくわかった。これがほたるの靴箱だということが。
ふるふると、手が震えた。
ああ、確かに、狂犬なんて呼ばれる伝説のヤンキーが身近にいたとして、面と向かって喧嘩を売ろうとするやつもそうそういないだろう。
過去の僕のような人種に不快な思いをさせられた人間にとって、狂犬は嫌な記憶を呼び起こす忌むべき存在なのかもしれない。
物申したくもなるだろう。
だが、だからといって、これは許されていいことなのか?
見えない場所から投石をするような行為が、認められていいのか?
しかも、ほたるは関係ない。
彼は僕の身代わりになっただけだ。この僕の。
――あんたの努力を、過去のやんちゃしてた時代のせいでいろいろ言われるの、駄目だろ。
そうだ。でも、これを背負うのは僕じゃなきゃいけない。
いけないのに。
なんでほたるは、こんなことをされてもなにも言わないんだろう。
なんで僕は、こんなに腹が立って腹が立って仕方ないのだろう。
なんで。
頭の奥で、ほたるが囁く。
――あんたが怪我したりするの、嫌なんだよ。
困ったように眉を寄せる、ほたるの顔。
面影が過った瞬間、心の奥に沈んでいたなにかがふっと僕の前に立ち上がってきた気がした。
ずっともやもやしていた。でも、今、わかった。
書き殴られた文字に埋もれた「速水」と書かれたプレートに視線を当て、唇を噛む。
なあ、ほたる。
プレートに向かい、僕は心の内で呼びかける。
俺だって、嫌だよ。
ほたるが傷つくの、俺だって嫌なんだよ。
いつも俺のことばかり考えてくれたお前が、こんなふうに傷つけられるの、絶対、嫌なんだよ。
だって、俺はさ。
――樹さんと一緒にいる時間、すごく……大事に思ってるのに!
気が付いたら、僕は握りしめた拳で、殴り書きされた「狂犬」を殴りつけていた。
がしゃん、と鋭い音が無人の昇降口の空気を震わせる。
けれどそれ以上に、体が震えることを止められなかった。
許せなかった。
ほたるにこんなことをするやつらを、絶対に許さないと思った。
遠く、体育館からマイク越しの声が聞こえてくる。校長の挨拶中かもしれない。
それを耳に収めながら、僕はふらつく足を踏みしめて体育館へ向かった。
校舎と体育館を繋ぐ渡り廊下をゆっくり、ゆっくり、踏みしめるように進む。すると、開放された体育館の扉付近にいた教師が僕に気付いて眉を顰めた。
クラス担任の吉井先生だった。
「遅い! 早く列に並びなさい」
小言を喰らっても、ここまで狂犬を捨ててやってきた僕ならにこやかに、申し訳ありません、と返せるはずだった。が、今日の僕はそれがどうしてもできなかった。無言で頷くので精一杯だった。
吉井先生はそんな僕に怪訝そうな顔をしてから、ああ、そうだった、と潜めた声で早口に告げてきた。
「今日、この後、壇上に上がってもらうから」
「は? なんで」
敬語もうまく使えなくなっている。つっけんどんに返す僕を、吉井先生はますます気味悪そうに眺める。
「弓道。全国大会出るだろ。壮行会ってことで、意気込みを語ってもらうことになってるから。その話したかったのに、今日に限って遅刻なんだからなあ」
しっかりしてくれよ、と吉井先生の手が僕の背中を叩く。だが、僕としてはそれどころではなかった。
意気込みなんて語っていられる心境じゃ断じてないのだ。けれど、それをこの人に言ってなんになるだろう。仕方なく頷いて、僕は自分のクラスの列へと向かう。
道すがら、視線を滑らせ、ほたるの姿を探した。
周りよりも抜きん出て背の高いほたるの姿は、すぐに見つけられた。
いつも通り、感情の薄い、凪いだ横顔をしている。
が、僕には、ほたるの周りが凍ってみえた。
氷が軋むみたいに、心が張りつめているのが、わかった。
『続きまして、壮行会に移ります。来る八月三日全国高等学校総合体育大会におきまして、わが校の弓道部から三年の水原樹さんが個人戦にて出場することが決定いたしました。水原さんより一言、挨拶をお願いしようと思います。水原さん、檀上へお願いします』
生徒会長が僕の名前を呼ぶ。ゆらり、と目を向けると、生徒会の役員が手招いているのが見えた。
挨拶なんてしたい気分じゃまったくない。が、急かすようにさらに手招かれ、苦い息が漏れる。くそ、と口の中で呟き、壇上へと向かう。
普段、滅多に上がることがないその場所からほたるの姿を探すと、こちらを見る彼と目が合った。
背が高いからすぐわかる。
いいや、そうではなくても、あんなにまっすぐ僕を見るのは、きっとほたるくらいだろう。
そう思ったら、どんどん胸が苦しくなってきた。
「水原さん、お願いします」
落ち着かなければいけない。
舞台の袖から司会役の生徒会役員が促してくる。
一度息を吐き、顔を上げ、スタンドマイクに向き直った僕の視界に、見覚えのある顔が飛び込んできたのはそのときだった。
整列する生徒たちの中、おそらく、あの列は一年のどこかのクラスのものだろう。その中ほどにそいつはいた。昇降口から笑いながら走り出ていったやつのひとりが。
前に並んだ生徒の肩を叩き、何事か囁き交わしながら体を震わせ、笑っている。
悩みも、なにもなさそうに……笑っている。
瞬間、かっとなった。檀上から走り下りたくなった。
でも。
――なんも知らないやつらに、好きな人が踏みつけられるなんて、絶対許せないんだ。
――そうさせないためなら、俺はなんでもする。
「あー……」
マイクに向かって僕は声を吐く。
走り出したがる僕の足を壇上に縫い留めるのは……ほたるの視線だった。
駄目だよ、樹さん、とほたるに諭されたように感じた。
「水原樹です」
呼吸を整え、僕はマイクに声を落とす。
そうだ。穢してはならないのだろう。これまでの自分の頑張りを。
ほたるが守ってくれた、水原樹を。
自分自身、黒歴史だと封印し、誰にも語ってこなかった。中学時代の僕は人を傷つけたこともあったし、傷つけたその過去が恐ろしくもあったから。
だから蓋をして、自分とだけ向き合ってきた。
それが間違いだったとまでは言わない。自分を見つめるため、逃げるように始めた弓道だったけれど、弓は確かに僕を強くしてくれたから。
それでも、このままでいることはやはり違う。
今頃、気付いた。
狂犬なんて呼ばれてしまったけれど、あの時間にだって、黒歴史と一括りにして捨てていいことばかりがあったわけじゃないということを。
だってそうじゃないか。
あの時間がなければ、僕は。
「この場で意気込みをとのことなのですが、まず僕から皆さんにお話したいことがあります」
あれ? なんだか様子がおかしくない? という顔を舞台の袖で生徒会役員がしている。構わず僕は続けた。
「今、ひとつの噂が流れていますね。星名中学出身の狂犬がこの菊塚にいる、という」
ざわり、と舞台の下、居並ぶ生徒たちがざわめく。なに、なんの話? 狂犬ってあの? と囁き合う声が耳を刺す。
ふうっと息を吐き、僕はマイクに向かって告げた。
「噂の狂犬は、僕です」
ざわめきが大きくなる。嘘、え、狂犬? 嘘でしょ、全然、そんなふうに見えないのに? 等々声が渦巻いている。
内心、やっちゃったなあ、という気持ちはあった。が、不思議と落ち着いてもいた。
「僕は昔、狂犬と呼ばれるような人間でした。家に帰らないなんて当たり前だったし、学校にも行っていなかった。喧嘩も売り買いどっちもしました。それが今は弓道部の部長です。笑っちゃいますよね」
水原くん、と壇の下から弓道部顧問の飯田先生が呼びかけてくる。丸顔の中で、小さな眼鏡がずり落ちそうだ。その彼に向かい、すみません、と目礼する。しかし、話を中断するつもりはなかった。
「黙っていれば済むことなんでしょう。今の自分は昔とは違うのだから、と。でも過去はそんな簡単に脱ぎ去れないものなんですよね。僕が人を傷つけた事実は消えない。やったことはどこまでも追いかけてくる。どれだけ真剣に弓を引こうと、ずっと」
だから、と言ったところで、僕は声を平板に保とうとそっと呼吸を整える。
「ちゃんと自分で責任を取らなきゃと思いました。そうでなければ、僕の今を守ろうとしてくれた大事な人が傷つけられてしまうから。謂れのない陰口を叩かれ、貶められてしまうから。僕はそれがどうしたって我慢できない」
ざわざわ、と再び人声が熱を持つ。揺れる人と人の頭の波の中、ほたるが立ち尽くしているのが見えた。
その彼に向かって微笑みかけてから、僕はおもむろにマイクを引っ掴む。ふうっと大きく息を吸い込む。そして、怒鳴った。
「わかったか! 狂犬は俺なんだよ! お前ら、落書きする場所、間違ってんだよ! するなら俺のところにしろ! いいか、全員に言っとくぞ! 今度、俺の舎弟になめた真似してみろ。ただじゃおかねえからな!」
瞳に力を込めて見据えると、一年の列の中ほどにいた男子生徒の顔がさあっと青くなった。
はあ、と肩で息を吐き、僕は声のトーンを落とす。
「全力を以って、成績は残すつもりですので。以上」
言い捨ててマイクから手を離す。やり過ぎたあ、と肩を落としつつステージを横切り、階段に足を掛ける。ざわめきは囁き声へと変わり、僕を囲む。目を伏せて歩を進める僕の耳を、そのとき、囁き以外の音が掠めた。
それは、拍手だった。
え、と顔を上げて、視線を彷徨わせる。
拍手は一年の、ほたるのクラスの列から聞こえた。
「勝ってください! 部長!」
拍手の主である宮池くんが叫ぶ。え、なになに、と宮池くんの周りの生徒たちが顔を見合わせる。ややあって、数人がつられたように手を叩き始めた。
徐々に徐々に拍手は拡がる。大喝采というわけでは当然なかった。でも、ささやかな拍手を送ってくれる中には、弓道部の他の部員も、調理部の面々も、顧問の飯田先生もいた。
それが無性に、沁みた。
しかも今日はもう終業式だ。夏休みに入ったら、どうしたらいいのだろう。
暗澹たる気持ちを抱え、僕は昇降口へと向かう。
連日のむしゃくしゃを晴らそうと、弓道場で朝から弓を引いていたせいで、始業時間をすっかり過ぎてしまっていた。
当然皆、体育館へ移動している時間で昇降口に人影はない。焦りながら上履きに履き替えていた僕だったが、かすかな笑い声が聞こえ、ふと目を上げた。声を辿って視線を向けると、靴箱を挟んだ向こう側から二人組の男子が駆け去っていくのが見えた。
一瞬だったし、見間違いかもしれない。でも彼らのうちのひとりの手にあったものが、意識に嫌なざらつきを残した。
彼らの手にあったのは……油性マジック。
中途半端に踵が折れた状態だったけれど、上履きをつっかけるようにして僕は、彼らが駆けだしてきた側の靴箱へと回り込む。砂埃と靴箱特有の金臭い匂いに混じり、つん、と鼻を突いたのは……シンナー臭だった。
臭いの元を辿り、僕は立ちすくむ。
靴箱の中央。味も素っ気もないグレー一色の中、誰かの靴箱の扉に黒々とした文字が刻まれていた。
『狂犬。出て行け』
名札を確かめるまでもなくわかった。これがほたるの靴箱だということが。
ふるふると、手が震えた。
ああ、確かに、狂犬なんて呼ばれる伝説のヤンキーが身近にいたとして、面と向かって喧嘩を売ろうとするやつもそうそういないだろう。
過去の僕のような人種に不快な思いをさせられた人間にとって、狂犬は嫌な記憶を呼び起こす忌むべき存在なのかもしれない。
物申したくもなるだろう。
だが、だからといって、これは許されていいことなのか?
見えない場所から投石をするような行為が、認められていいのか?
しかも、ほたるは関係ない。
彼は僕の身代わりになっただけだ。この僕の。
――あんたの努力を、過去のやんちゃしてた時代のせいでいろいろ言われるの、駄目だろ。
そうだ。でも、これを背負うのは僕じゃなきゃいけない。
いけないのに。
なんでほたるは、こんなことをされてもなにも言わないんだろう。
なんで僕は、こんなに腹が立って腹が立って仕方ないのだろう。
なんで。
頭の奥で、ほたるが囁く。
――あんたが怪我したりするの、嫌なんだよ。
困ったように眉を寄せる、ほたるの顔。
面影が過った瞬間、心の奥に沈んでいたなにかがふっと僕の前に立ち上がってきた気がした。
ずっともやもやしていた。でも、今、わかった。
書き殴られた文字に埋もれた「速水」と書かれたプレートに視線を当て、唇を噛む。
なあ、ほたる。
プレートに向かい、僕は心の内で呼びかける。
俺だって、嫌だよ。
ほたるが傷つくの、俺だって嫌なんだよ。
いつも俺のことばかり考えてくれたお前が、こんなふうに傷つけられるの、絶対、嫌なんだよ。
だって、俺はさ。
――樹さんと一緒にいる時間、すごく……大事に思ってるのに!
気が付いたら、僕は握りしめた拳で、殴り書きされた「狂犬」を殴りつけていた。
がしゃん、と鋭い音が無人の昇降口の空気を震わせる。
けれどそれ以上に、体が震えることを止められなかった。
許せなかった。
ほたるにこんなことをするやつらを、絶対に許さないと思った。
遠く、体育館からマイク越しの声が聞こえてくる。校長の挨拶中かもしれない。
それを耳に収めながら、僕はふらつく足を踏みしめて体育館へ向かった。
校舎と体育館を繋ぐ渡り廊下をゆっくり、ゆっくり、踏みしめるように進む。すると、開放された体育館の扉付近にいた教師が僕に気付いて眉を顰めた。
クラス担任の吉井先生だった。
「遅い! 早く列に並びなさい」
小言を喰らっても、ここまで狂犬を捨ててやってきた僕ならにこやかに、申し訳ありません、と返せるはずだった。が、今日の僕はそれがどうしてもできなかった。無言で頷くので精一杯だった。
吉井先生はそんな僕に怪訝そうな顔をしてから、ああ、そうだった、と潜めた声で早口に告げてきた。
「今日、この後、壇上に上がってもらうから」
「は? なんで」
敬語もうまく使えなくなっている。つっけんどんに返す僕を、吉井先生はますます気味悪そうに眺める。
「弓道。全国大会出るだろ。壮行会ってことで、意気込みを語ってもらうことになってるから。その話したかったのに、今日に限って遅刻なんだからなあ」
しっかりしてくれよ、と吉井先生の手が僕の背中を叩く。だが、僕としてはそれどころではなかった。
意気込みなんて語っていられる心境じゃ断じてないのだ。けれど、それをこの人に言ってなんになるだろう。仕方なく頷いて、僕は自分のクラスの列へと向かう。
道すがら、視線を滑らせ、ほたるの姿を探した。
周りよりも抜きん出て背の高いほたるの姿は、すぐに見つけられた。
いつも通り、感情の薄い、凪いだ横顔をしている。
が、僕には、ほたるの周りが凍ってみえた。
氷が軋むみたいに、心が張りつめているのが、わかった。
『続きまして、壮行会に移ります。来る八月三日全国高等学校総合体育大会におきまして、わが校の弓道部から三年の水原樹さんが個人戦にて出場することが決定いたしました。水原さんより一言、挨拶をお願いしようと思います。水原さん、檀上へお願いします』
生徒会長が僕の名前を呼ぶ。ゆらり、と目を向けると、生徒会の役員が手招いているのが見えた。
挨拶なんてしたい気分じゃまったくない。が、急かすようにさらに手招かれ、苦い息が漏れる。くそ、と口の中で呟き、壇上へと向かう。
普段、滅多に上がることがないその場所からほたるの姿を探すと、こちらを見る彼と目が合った。
背が高いからすぐわかる。
いいや、そうではなくても、あんなにまっすぐ僕を見るのは、きっとほたるくらいだろう。
そう思ったら、どんどん胸が苦しくなってきた。
「水原さん、お願いします」
落ち着かなければいけない。
舞台の袖から司会役の生徒会役員が促してくる。
一度息を吐き、顔を上げ、スタンドマイクに向き直った僕の視界に、見覚えのある顔が飛び込んできたのはそのときだった。
整列する生徒たちの中、おそらく、あの列は一年のどこかのクラスのものだろう。その中ほどにそいつはいた。昇降口から笑いながら走り出ていったやつのひとりが。
前に並んだ生徒の肩を叩き、何事か囁き交わしながら体を震わせ、笑っている。
悩みも、なにもなさそうに……笑っている。
瞬間、かっとなった。檀上から走り下りたくなった。
でも。
――なんも知らないやつらに、好きな人が踏みつけられるなんて、絶対許せないんだ。
――そうさせないためなら、俺はなんでもする。
「あー……」
マイクに向かって僕は声を吐く。
走り出したがる僕の足を壇上に縫い留めるのは……ほたるの視線だった。
駄目だよ、樹さん、とほたるに諭されたように感じた。
「水原樹です」
呼吸を整え、僕はマイクに声を落とす。
そうだ。穢してはならないのだろう。これまでの自分の頑張りを。
ほたるが守ってくれた、水原樹を。
自分自身、黒歴史だと封印し、誰にも語ってこなかった。中学時代の僕は人を傷つけたこともあったし、傷つけたその過去が恐ろしくもあったから。
だから蓋をして、自分とだけ向き合ってきた。
それが間違いだったとまでは言わない。自分を見つめるため、逃げるように始めた弓道だったけれど、弓は確かに僕を強くしてくれたから。
それでも、このままでいることはやはり違う。
今頃、気付いた。
狂犬なんて呼ばれてしまったけれど、あの時間にだって、黒歴史と一括りにして捨てていいことばかりがあったわけじゃないということを。
だってそうじゃないか。
あの時間がなければ、僕は。
「この場で意気込みをとのことなのですが、まず僕から皆さんにお話したいことがあります」
あれ? なんだか様子がおかしくない? という顔を舞台の袖で生徒会役員がしている。構わず僕は続けた。
「今、ひとつの噂が流れていますね。星名中学出身の狂犬がこの菊塚にいる、という」
ざわり、と舞台の下、居並ぶ生徒たちがざわめく。なに、なんの話? 狂犬ってあの? と囁き合う声が耳を刺す。
ふうっと息を吐き、僕はマイクに向かって告げた。
「噂の狂犬は、僕です」
ざわめきが大きくなる。嘘、え、狂犬? 嘘でしょ、全然、そんなふうに見えないのに? 等々声が渦巻いている。
内心、やっちゃったなあ、という気持ちはあった。が、不思議と落ち着いてもいた。
「僕は昔、狂犬と呼ばれるような人間でした。家に帰らないなんて当たり前だったし、学校にも行っていなかった。喧嘩も売り買いどっちもしました。それが今は弓道部の部長です。笑っちゃいますよね」
水原くん、と壇の下から弓道部顧問の飯田先生が呼びかけてくる。丸顔の中で、小さな眼鏡がずり落ちそうだ。その彼に向かい、すみません、と目礼する。しかし、話を中断するつもりはなかった。
「黙っていれば済むことなんでしょう。今の自分は昔とは違うのだから、と。でも過去はそんな簡単に脱ぎ去れないものなんですよね。僕が人を傷つけた事実は消えない。やったことはどこまでも追いかけてくる。どれだけ真剣に弓を引こうと、ずっと」
だから、と言ったところで、僕は声を平板に保とうとそっと呼吸を整える。
「ちゃんと自分で責任を取らなきゃと思いました。そうでなければ、僕の今を守ろうとしてくれた大事な人が傷つけられてしまうから。謂れのない陰口を叩かれ、貶められてしまうから。僕はそれがどうしたって我慢できない」
ざわざわ、と再び人声が熱を持つ。揺れる人と人の頭の波の中、ほたるが立ち尽くしているのが見えた。
その彼に向かって微笑みかけてから、僕はおもむろにマイクを引っ掴む。ふうっと大きく息を吸い込む。そして、怒鳴った。
「わかったか! 狂犬は俺なんだよ! お前ら、落書きする場所、間違ってんだよ! するなら俺のところにしろ! いいか、全員に言っとくぞ! 今度、俺の舎弟になめた真似してみろ。ただじゃおかねえからな!」
瞳に力を込めて見据えると、一年の列の中ほどにいた男子生徒の顔がさあっと青くなった。
はあ、と肩で息を吐き、僕は声のトーンを落とす。
「全力を以って、成績は残すつもりですので。以上」
言い捨ててマイクから手を離す。やり過ぎたあ、と肩を落としつつステージを横切り、階段に足を掛ける。ざわめきは囁き声へと変わり、僕を囲む。目を伏せて歩を進める僕の耳を、そのとき、囁き以外の音が掠めた。
それは、拍手だった。
え、と顔を上げて、視線を彷徨わせる。
拍手は一年の、ほたるのクラスの列から聞こえた。
「勝ってください! 部長!」
拍手の主である宮池くんが叫ぶ。え、なになに、と宮池くんの周りの生徒たちが顔を見合わせる。ややあって、数人がつられたように手を叩き始めた。
徐々に徐々に拍手は拡がる。大喝采というわけでは当然なかった。でも、ささやかな拍手を送ってくれる中には、弓道部の他の部員も、調理部の面々も、顧問の飯田先生もいた。
それが無性に、沁みた。
「まったく、やらかしてくれるねえ」
壮行会が終わった後、僕は弓道部顧問の飯田先生に呼び出され、こってり絞られた。場所は普段なら先生が滅多に来ない、弓道場だった。
「伝説のヤンキーは僕ですって檀上で告白って。漫画かよって思わずのけぞったよ。ああいうことはもうちょっと早く教えておいてもらいたかった」
「いや、あ、はい。すみません。ただ、その……入部当時は卒業まで隠し通すつもりでいたので……」
「それをまあ、センセーショナルに発表しちゃったね」
ははは、と飯田先生が笑う。その先生の前で僕は左手で右手首をぐっと掴む。
自分の勝手な思いで、飯田先生にも迷惑がかかってしまうかもしれない。今頃その可能性に気付き、目の前が暗くなっていた。
「わかっては、います。あんな啖呵を切りましたが、こういう人間ですし、全国へ行くこともできなくなるかもしれませんね」
「なんで?」
飯田先生がきょとんとした顔をする。
「そんな規定あったっけ? 大体、君が狂犬である証拠は? いや、そもそも狂犬って。君に似合わな過ぎ」
丸い肩を揺らして飯田先生が笑う。笑いごとだろうか、と僕は顔をしかめる。けれどもあまりにもおかしそうに笑われるので、だんだんこちらまで頬が緩んできてしまった。
飯田先生にはこんなところがある。飄々としていてつかみどころがない。
ひとしきり笑ってから、先生は顔を上げた。
「狂犬がどうとかはともかくさ、僕はね、感動しちゃったんだよ。君のスピーチ」
「感動、ですか?」
「だってそうだろ。君があそこで自分が狂犬、ああ、だめだ、やっぱり狂犬って言うと笑っちゃう……ごめん。ともかく、狂犬だって言い出したのって、誰かを守りたいなあって思ったからなんだろ」
さらっと、守りたい、と言われて頬が熱くなった。
そんな大層なものではない。ただ許せなかった。それだけなのだ。美化されても困る。
「狂犬の血が騒いだとか、そんなレベルの話です」
「君は僕を笑い死にさせたいのか」
ああ、苦しい、と言って飯田先生は眼鏡を外して目元を拭った後、ふっと真顔になった。
「弓道はさ、ひとりで閉じてひとりで進んでいく孤独な武道だよね。でもさ、弓ってもともとは命をかけて戦うための武器としてあったんだよね」
「そう、ですね」
頷く僕の前で飯田先生は、ふうっと眼鏡に息を吹きかけてこしこしとハンカチで拭く。
「もちろん当時もさ、弓は自分のために使われただろうと思うよ。けれど……誰かを守りたい、そんな思いを抱いて弓を構えた人だって絶対にいたはずだよね」
汚れがなくなったか確認するように、飯田先生は眼鏡をかざす。眼鏡のレンズ越し、先生の目が僕を見つめた。
「君にとっても弓ってそういうものなのかもしれないなあ、って思ったらすごく胸が熱くなった」
水原くん、と顔に眼鏡を戻しながら先生が僕を呼ぶ。
「僕は、君は素敵だと思ったよ。いろいろ言う人もいる。でもそれを跳ね返すくらい、今の力を見せてやりなさい。君ならできるよ」
じりり、と瞼が熱を帯びる。思わず唇を噛みしめる僕に気付かぬふうに、飯田先生は弓道場を見回した。
「君を見てたら僕もまた引きたくなってきたな。水原くんさ、教えてくれる? もう結構忘れちゃっててさ」
「僕で、よければ」
なんとかそう返すと、飯田先生はにこりと笑って、練習、頑張らないとな、と丸い声で言った。
壮行会が終わった後、僕は弓道部顧問の飯田先生に呼び出され、こってり絞られた。場所は普段なら先生が滅多に来ない、弓道場だった。
「伝説のヤンキーは僕ですって檀上で告白って。漫画かよって思わずのけぞったよ。ああいうことはもうちょっと早く教えておいてもらいたかった」
「いや、あ、はい。すみません。ただ、その……入部当時は卒業まで隠し通すつもりでいたので……」
「それをまあ、センセーショナルに発表しちゃったね」
ははは、と飯田先生が笑う。その先生の前で僕は左手で右手首をぐっと掴む。
自分の勝手な思いで、飯田先生にも迷惑がかかってしまうかもしれない。今頃その可能性に気付き、目の前が暗くなっていた。
「わかっては、います。あんな啖呵を切りましたが、こういう人間ですし、全国へ行くこともできなくなるかもしれませんね」
「なんで?」
飯田先生がきょとんとした顔をする。
「そんな規定あったっけ? 大体、君が狂犬である証拠は? いや、そもそも狂犬って。君に似合わな過ぎ」
丸い肩を揺らして飯田先生が笑う。笑いごとだろうか、と僕は顔をしかめる。けれどもあまりにもおかしそうに笑われるので、だんだんこちらまで頬が緩んできてしまった。
飯田先生にはこんなところがある。飄々としていてつかみどころがない。
ひとしきり笑ってから、先生は顔を上げた。
「狂犬がどうとかはともかくさ、僕はね、感動しちゃったんだよ。君のスピーチ」
「感動、ですか?」
「だってそうだろ。君があそこで自分が狂犬、ああ、だめだ、やっぱり狂犬って言うと笑っちゃう……ごめん。ともかく、狂犬だって言い出したのって、誰かを守りたいなあって思ったからなんだろ」
さらっと、守りたい、と言われて頬が熱くなった。
そんな大層なものではない。ただ許せなかった。それだけなのだ。美化されても困る。
「狂犬の血が騒いだとか、そんなレベルの話です」
「君は僕を笑い死にさせたいのか」
ああ、苦しい、と言って飯田先生は眼鏡を外して目元を拭った後、ふっと真顔になった。
「弓道はさ、ひとりで閉じてひとりで進んでいく孤独な武道だよね。でもさ、弓ってもともとは命をかけて戦うための武器としてあったんだよね」
「そう、ですね」
頷く僕の前で飯田先生は、ふうっと眼鏡に息を吹きかけてこしこしとハンカチで拭く。
「もちろん当時もさ、弓は自分のために使われただろうと思うよ。けれど……誰かを守りたい、そんな思いを抱いて弓を構えた人だって絶対にいたはずだよね」
汚れがなくなったか確認するように、飯田先生は眼鏡をかざす。眼鏡のレンズ越し、先生の目が僕を見つめた。
「君にとっても弓ってそういうものなのかもしれないなあ、って思ったらすごく胸が熱くなった」
水原くん、と顔に眼鏡を戻しながら先生が僕を呼ぶ。
「僕は、君は素敵だと思ったよ。いろいろ言う人もいる。でもそれを跳ね返すくらい、今の力を見せてやりなさい。君ならできるよ」
じりり、と瞼が熱を帯びる。思わず唇を噛みしめる僕に気付かぬふうに、飯田先生は弓道場を見回した。
「君を見てたら僕もまた引きたくなってきたな。水原くんさ、教えてくれる? もう結構忘れちゃっててさ」
「僕で、よければ」
なんとかそう返すと、飯田先生はにこりと笑って、練習、頑張らないとな、と丸い声で言った。
弓道場を出てぶらぶらと歩く。終業式が終わって時間も経っているから人影はそれほどない。そのことにほっとしながら校門に差し掛かったとき、ぐい、と横合いから腕を掴まれた。そのままその人物は、ぐいぐいと僕の腕を引いて歩いていく。
僕を連行していたのは、やっぱりほたるだった。
「なにしてくれてんの、樹さん。これじゃ全部、台無しだ」
ほたるの顔は強張っている。通りがかった数人の生徒の視線を背中で撥ねつけるようにしてほたるは歩き、駐輪場の陰でようやく僕の腕を離して小言を再開した。
「俺はいいって言ったよね。なのに、なんであんなことすんの」
「俺は嫌だから」
きっぱりと言う。僕の勢いに圧されたように、ほたるがたじろいだ。
「は? 狂犬でいたかったってこと? 意味わかんない。樹さんにはやりたいことがある。狂犬でいた時間なんて無駄だろ。だから俺が」
「無駄なんて決めつけるな。俺にとってあの時間はなきゃ駄目な時間なんだよ」
そこで僕はそっと呼吸を整える。狂犬なんて言われていたくせに、心臓がおかしな具合に緊張している。でも言わなきゃ、いけない。
「あの時間があったから、俺はお前に会えた」
ほたるの目が見開かれる。その彼の顔を見上げながら僕は今一度深呼吸をする。そうしてからそうっと声を落とす。届いてほしい、と願いながら。
「お前とコンビニにいた時間も、一緒にエクレア食べた時間も、俺は絶対なかったことにしたくない。今、こうして話している時間も」
少し、怖い、と思った。こんなことを今更自分が言っていいのか、と躊躇う気持ちもあった。
でも決めたのだ。もうほたるに甘えてばかりではいられない、と。だから僕は言う。
今、一番、言いたいことを。
「俺はさ、お前のこと、好きだなって思うんだけど。お前は、どう、思ってる?」
ああ、やっぱり駄目だ。顔を見ていられない。恥ずかしくて消えたくなる。引導を渡されるなら、光の速さで渡されたい。
などと、心中で悶えつつ返事を待つが、ほたるからの答えは返ってこない。あまりにも長く黙っているので、さすがに焦れてそろそろとほたるの様子を窺った僕は仰天した。
ほたるが片手で目元を覆い、顔を伏せていた。
「ちょっと、なに。まさか泣いて……」
「泣いてないし」
返ってきた声は完全に鼻声だ。それでも気丈に顔を上げたほたるは、振り切るように指先で目尻を払ってから、はあっと深い息を吐いた。
「樹さんってさ、馬鹿なの?」
「は⁉ なんだよ、馬鹿って。前々から思ってたけど、お前、生意気。先輩に敬意示せってば」
「いや、馬鹿でしょ。だってさ、普通わかるよな」
涙の名残りのある声で言い、ぷい、とほたるはそっぽを向く。
その頬は、これまで見たことがないほど赤かった。
「好きでもない相手のためにスイーツ作るかよ。学校だってここ選んだりしない。遠すぎるわ、偏差値高いわ。俺、どれだけ勉強したと思ってんの。頭、沸騰するかと思った」
「お……」
淀みなく言われ、今度はこちらが言葉を失う。ほたるは頬を染めたまま、ふっと目を伏せた。
「でも、樹さんは過去を消したいんだって思ったから、こっそり応援しようって思ってたんだ。なのに、狂犬丸出しで追いかけてくるし。猫かぶって過ごしてるくせに、俺のこと邪険にもしないで昔みたいに相手してくれるし。大事な人、とか、みんなの前で言っちゃう、し。大体、俺はこの間、好きって……伝えたつもりだったのに、確認してくるとことか、なんかもう」
はああ、と息を吐いてから、ほたるはそうっと目を開ける。
じっとこちらを見つめてくる目に、呼吸が止まった。
「馬鹿」
馬鹿馬鹿言うな、と言い返そうとしたが言えなかった。熱くなる頬を持て余しながら僕は横を向きつつ、ごめん、と言う。その僕の頭の上でほたるが呆れたようにまた息を吐いた。
「いいよ。そういう空気読めないとこも樹さんらしいし」
「いや、あの、それは言い過ぎだろ……ってか、そこじゃなくて」
へどもどする僕にほたるが怪訝そうに首を傾げる。その彼の前で僕は目を閉じる。
「俺、ちゃんと言わなかったから。中学のとき、お前にさ、弓道やるから会えなくなるって。すごくひどいことしたと思う。なのになんで、お前、こんな俺のこと」
「自転車」
遮られ、僕は言葉を止める。え、と目を開けると、ほたるは前髪をいじりながら駐輪場の自転車を見ていた。
「俺、あのころ、自転車乗れなくてさ。そしたら樹さんが、俺が教えてやるよ、って笑って教えてくれただろ」
「え、あ……うん」
確かにそうだ。自転車のせいで学校へ行くのをやめてしまったと言うほたるを笑った後、僕はほたると公園で自転車の練習をした。
「あれ、俺、すごくうれしかったんだ。何度失敗しても、頑張れ頑張れって言ってくれた。こけても起こしてくれてさ。それがずっと忘れられなくて。だから、頑張ってる樹さんを俺だって応援したいって思ったんだ。その……樹さんに自転車の乗り方教えてもらったおかげで、俺も学校、行くようになったし」
「そ、か」
単なる気まぐれだったのだ。ほたるはつらい顔も苦しい顔も見せなかったけれど、寂しそうに見えて。笑わせてやりたくて。ただ、それだけで。
でもそれをほたるは大事な思い出のように語る。目を細めて。
なんだかもう、本当にどうしていいかわからない。
「困ったことあったら……言えよ。自転車みたいに教えてやる、から」
照れ隠しでそう言うと、ほたるは一瞬、気を呑まれたような顔をしてから笑った。
いつもの淡い微笑ではない、温かい顔で。
その顔を見て思い出す。
乗れたよ、樹さん、と笑った彼の顔は、今、目の前で咲いたこの顔と確かに同じものだった。
目頭を熱くした僕に、柔らかい声が訊いた。
「樹さんさ、エクレア以外だと甘いもの、なにが好き?」
「え、エクレア以外? なんで?」
「だって、大会の会場で食べるにはあれ、食べにくいだろ。袴、べとべとになっちゃうよ」
ふざけた口調で言われ、僕は顔を赤らめる。その僕の腕をそうっとほたるが掴んだ。
「応援、行きたいけど、俺も行っていい?」
駄目だと言うと思っているのか、この野郎は。
憤然とほたるの手を振りほどく。ふっと目を見張る彼の手を逆にぐいと掴んだ僕は、赤い顔で言い放った。
「かっこいいところ、見せてやるから、来い」
「おお、言った。そうだよな。全校生徒の前で宣言しちゃったもんな。やるしかないよな」
言われて青ざめた。ああああ、と呻いた僕に、ほたるはくつくつと笑ってから問いを繰り返す。
「で、エクレア以外だったら、なに食べたい?」
「……マカロン」
うなだれながら答えると、マカロン、と繰り返し、ほたるはますます笑った。
「狂犬らしくなさすぎてウケる」
「うるさい。好きなんだからいいだろ」
「うん」
切り返す僕にほたるの優しい返事が寄り添う。見上げると、今度はほたるのほうが照れ臭そうに目を逸らした。
「美味しいって言ってもらえるよう頑張って作るから。樹さん、絶対勝って」
「……任せとけ」
そっと微笑み返すと、ほたるは恥じらうように前髪を掻き上げた。掴まれたままだった手がきゅっと強く握られる。
「帰ろ。樹さん」
くい、と手が引かれる。その力に引っ張られて僕は歩き出す。
蝉が鳴く。空へ届けと言わんばかりに。その声を吸いこんで輝く青空を瞳に映す。
昔からこの色が苦手だった。なんとなく正しすぎる色に思えたから。でも、今年はそう思わないでいられそうな気がする。
こいつのおかげで。
そっと繋いだ手に力を込めると、こちらに背中を向けていたほたるの耳が赤くなったのがわかった。
その赤にこちらも赤面を誘われながら、僕は小さく拳を握った。
勝ってみせる、見てろよ、と、僕らの上に広がる青に向かって誓う。
雲ひとつない青空は、大きな腕で僕らを包むようにして、笑顔で広がり続けていた。
―――了―――
僕を連行していたのは、やっぱりほたるだった。
「なにしてくれてんの、樹さん。これじゃ全部、台無しだ」
ほたるの顔は強張っている。通りがかった数人の生徒の視線を背中で撥ねつけるようにしてほたるは歩き、駐輪場の陰でようやく僕の腕を離して小言を再開した。
「俺はいいって言ったよね。なのに、なんであんなことすんの」
「俺は嫌だから」
きっぱりと言う。僕の勢いに圧されたように、ほたるがたじろいだ。
「は? 狂犬でいたかったってこと? 意味わかんない。樹さんにはやりたいことがある。狂犬でいた時間なんて無駄だろ。だから俺が」
「無駄なんて決めつけるな。俺にとってあの時間はなきゃ駄目な時間なんだよ」
そこで僕はそっと呼吸を整える。狂犬なんて言われていたくせに、心臓がおかしな具合に緊張している。でも言わなきゃ、いけない。
「あの時間があったから、俺はお前に会えた」
ほたるの目が見開かれる。その彼の顔を見上げながら僕は今一度深呼吸をする。そうしてからそうっと声を落とす。届いてほしい、と願いながら。
「お前とコンビニにいた時間も、一緒にエクレア食べた時間も、俺は絶対なかったことにしたくない。今、こうして話している時間も」
少し、怖い、と思った。こんなことを今更自分が言っていいのか、と躊躇う気持ちもあった。
でも決めたのだ。もうほたるに甘えてばかりではいられない、と。だから僕は言う。
今、一番、言いたいことを。
「俺はさ、お前のこと、好きだなって思うんだけど。お前は、どう、思ってる?」
ああ、やっぱり駄目だ。顔を見ていられない。恥ずかしくて消えたくなる。引導を渡されるなら、光の速さで渡されたい。
などと、心中で悶えつつ返事を待つが、ほたるからの答えは返ってこない。あまりにも長く黙っているので、さすがに焦れてそろそろとほたるの様子を窺った僕は仰天した。
ほたるが片手で目元を覆い、顔を伏せていた。
「ちょっと、なに。まさか泣いて……」
「泣いてないし」
返ってきた声は完全に鼻声だ。それでも気丈に顔を上げたほたるは、振り切るように指先で目尻を払ってから、はあっと深い息を吐いた。
「樹さんってさ、馬鹿なの?」
「は⁉ なんだよ、馬鹿って。前々から思ってたけど、お前、生意気。先輩に敬意示せってば」
「いや、馬鹿でしょ。だってさ、普通わかるよな」
涙の名残りのある声で言い、ぷい、とほたるはそっぽを向く。
その頬は、これまで見たことがないほど赤かった。
「好きでもない相手のためにスイーツ作るかよ。学校だってここ選んだりしない。遠すぎるわ、偏差値高いわ。俺、どれだけ勉強したと思ってんの。頭、沸騰するかと思った」
「お……」
淀みなく言われ、今度はこちらが言葉を失う。ほたるは頬を染めたまま、ふっと目を伏せた。
「でも、樹さんは過去を消したいんだって思ったから、こっそり応援しようって思ってたんだ。なのに、狂犬丸出しで追いかけてくるし。猫かぶって過ごしてるくせに、俺のこと邪険にもしないで昔みたいに相手してくれるし。大事な人、とか、みんなの前で言っちゃう、し。大体、俺はこの間、好きって……伝えたつもりだったのに、確認してくるとことか、なんかもう」
はああ、と息を吐いてから、ほたるはそうっと目を開ける。
じっとこちらを見つめてくる目に、呼吸が止まった。
「馬鹿」
馬鹿馬鹿言うな、と言い返そうとしたが言えなかった。熱くなる頬を持て余しながら僕は横を向きつつ、ごめん、と言う。その僕の頭の上でほたるが呆れたようにまた息を吐いた。
「いいよ。そういう空気読めないとこも樹さんらしいし」
「いや、あの、それは言い過ぎだろ……ってか、そこじゃなくて」
へどもどする僕にほたるが怪訝そうに首を傾げる。その彼の前で僕は目を閉じる。
「俺、ちゃんと言わなかったから。中学のとき、お前にさ、弓道やるから会えなくなるって。すごくひどいことしたと思う。なのになんで、お前、こんな俺のこと」
「自転車」
遮られ、僕は言葉を止める。え、と目を開けると、ほたるは前髪をいじりながら駐輪場の自転車を見ていた。
「俺、あのころ、自転車乗れなくてさ。そしたら樹さんが、俺が教えてやるよ、って笑って教えてくれただろ」
「え、あ……うん」
確かにそうだ。自転車のせいで学校へ行くのをやめてしまったと言うほたるを笑った後、僕はほたると公園で自転車の練習をした。
「あれ、俺、すごくうれしかったんだ。何度失敗しても、頑張れ頑張れって言ってくれた。こけても起こしてくれてさ。それがずっと忘れられなくて。だから、頑張ってる樹さんを俺だって応援したいって思ったんだ。その……樹さんに自転車の乗り方教えてもらったおかげで、俺も学校、行くようになったし」
「そ、か」
単なる気まぐれだったのだ。ほたるはつらい顔も苦しい顔も見せなかったけれど、寂しそうに見えて。笑わせてやりたくて。ただ、それだけで。
でもそれをほたるは大事な思い出のように語る。目を細めて。
なんだかもう、本当にどうしていいかわからない。
「困ったことあったら……言えよ。自転車みたいに教えてやる、から」
照れ隠しでそう言うと、ほたるは一瞬、気を呑まれたような顔をしてから笑った。
いつもの淡い微笑ではない、温かい顔で。
その顔を見て思い出す。
乗れたよ、樹さん、と笑った彼の顔は、今、目の前で咲いたこの顔と確かに同じものだった。
目頭を熱くした僕に、柔らかい声が訊いた。
「樹さんさ、エクレア以外だと甘いもの、なにが好き?」
「え、エクレア以外? なんで?」
「だって、大会の会場で食べるにはあれ、食べにくいだろ。袴、べとべとになっちゃうよ」
ふざけた口調で言われ、僕は顔を赤らめる。その僕の腕をそうっとほたるが掴んだ。
「応援、行きたいけど、俺も行っていい?」
駄目だと言うと思っているのか、この野郎は。
憤然とほたるの手を振りほどく。ふっと目を見張る彼の手を逆にぐいと掴んだ僕は、赤い顔で言い放った。
「かっこいいところ、見せてやるから、来い」
「おお、言った。そうだよな。全校生徒の前で宣言しちゃったもんな。やるしかないよな」
言われて青ざめた。ああああ、と呻いた僕に、ほたるはくつくつと笑ってから問いを繰り返す。
「で、エクレア以外だったら、なに食べたい?」
「……マカロン」
うなだれながら答えると、マカロン、と繰り返し、ほたるはますます笑った。
「狂犬らしくなさすぎてウケる」
「うるさい。好きなんだからいいだろ」
「うん」
切り返す僕にほたるの優しい返事が寄り添う。見上げると、今度はほたるのほうが照れ臭そうに目を逸らした。
「美味しいって言ってもらえるよう頑張って作るから。樹さん、絶対勝って」
「……任せとけ」
そっと微笑み返すと、ほたるは恥じらうように前髪を掻き上げた。掴まれたままだった手がきゅっと強く握られる。
「帰ろ。樹さん」
くい、と手が引かれる。その力に引っ張られて僕は歩き出す。
蝉が鳴く。空へ届けと言わんばかりに。その声を吸いこんで輝く青空を瞳に映す。
昔からこの色が苦手だった。なんとなく正しすぎる色に思えたから。でも、今年はそう思わないでいられそうな気がする。
こいつのおかげで。
そっと繋いだ手に力を込めると、こちらに背中を向けていたほたるの耳が赤くなったのがわかった。
その赤にこちらも赤面を誘われながら、僕は小さく拳を握った。
勝ってみせる、見てろよ、と、僕らの上に広がる青に向かって誓う。
雲ひとつない青空は、大きな腕で僕らを包むようにして、笑顔で広がり続けていた。
―――了―――
この作家の他の作品
表紙を見る
ある日の夜、取引先、株式会社プッシュのサーバー保守に来ていた大城博也は、電気系統のトラブルでサーバールームに閉じ込められてしまう。共に閉じ込められたのはプッシュのシステム部課長、松崎冬里。
三年前、博也はプッシュの最終面接に臨んでいた。そのとき面接官の中にいたのが冬里だ。このとき、冬里に言われた言葉により、自分を変えることができた博也にとって冬里は特別な存在だが、彼は博也のことを覚えていない様子。もやもやしながら閉じ込められていたのだが、突然冬里が言う。
「変わらないね、博也」と。
表紙画像はかんたん表紙メーカー様にて。
https://sscard.monokakitools.net/covermaker_view.php
表紙を見る
東雲圭人には片想いをしている相手がいる。同じ野球部でキャッチャーの桜沢慎太郎だ。
しかしある日、慎太郎に彼女ができる。長年の片想いが破れ、悲嘆にくれる中、圭人に声をかけるのは、後輩の結城春歌だった。
ピッチャーである圭人の控え投手でもある彼は、現在はサードを守っている。正直、自分よりずっと速い球を投げられる彼にピッチャーを交代してほしいと圭人は願うが、春歌はそれを退け、代わりに言う。
「先輩が怪我をしないでいてくれたら控え投手の俺も安心です。だから俺が先輩を見張ります」
宣言通り、圭人が怪我をしないよう、見張るようになった春歌。しかしその守備範囲は体だけではなく、心にもおよび、彼は言う。
「先輩って心が痛がりですね」
そうして彼は、なぜか圭人を抱きしめる。
しかもそれは一度や二度ではなく、圭人が苦しいと感じると必ずハグしてきて……。
こだわり強めの無口男子×一途で不器用男子
表紙はかんたん表紙メーカーさまにて
https://sscard.monokakitools.net/covermaker_view.php
表紙を見る
「今ここで俺にキスされるか、俺にはっきり嫌いって言うか、どっちか選んで」
ある日、自分より頭半分低い場所から、彼はそう言った……。
きっかけは高1の春、
「今日は友人の顔を描いてもらおうと思う。適当にペアになって」
美術教師に言われ、多賀暁史(たがあきふみ)は困惑していた。
ぼっちの自分にとって難易度高過ぎだと肩を落とす暁史に声をかけてくれたのは、華奢で小柄なお姫様のような見た目の時任紅(ときとうくれない)。
明るく朗らかだが押しが強い彼になぜか懐かれるようになった暁史は、いつしか彼のペースに巻き込まれていく……。
小柄強気男子×地味イケボ男子の猫鍋物語
表紙はPhotoACにて
https://www.photo-ac.com/main/detail/1299876&title=%E3%81%BB%E3%81%A3%E3%81%93%E3%82%8A%E3%83%8D%E3%82%B3%E3%83%8A%E3%83%9911
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…