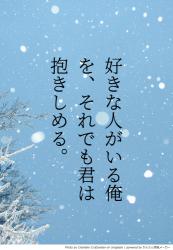この作家の他の作品
表紙を見る
ある日の夜、取引先、株式会社プッシュのサーバー保守に来ていた大城博也は、電気系統のトラブルでサーバールームに閉じ込められてしまう。共に閉じ込められたのはプッシュのシステム部課長、松崎冬里。
三年前、博也はプッシュの最終面接に臨んでいた。そのとき面接官の中にいたのが冬里だ。このとき、冬里に言われた言葉により、自分を変えることができた博也にとって冬里は特別な存在だが、彼は博也のことを覚えていない様子。もやもやしながら閉じ込められていたのだが、突然冬里が言う。
「変わらないね、博也」と。
表紙画像はかんたん表紙メーカー様にて。
https://sscard.monokakitools.net/covermaker_view.php
表紙を見る
東雲圭人には片想いをしている相手がいる。同じ野球部でキャッチャーの桜沢慎太郎だ。
しかしある日、慎太郎に彼女ができる。長年の片想いが破れ、悲嘆にくれる中、圭人に声をかけるのは、後輩の結城春歌だった。
ピッチャーである圭人の控え投手でもある彼は、現在はサードを守っている。正直、自分よりずっと速い球を投げられる彼にピッチャーを交代してほしいと圭人は願うが、春歌はそれを退け、代わりに言う。
「先輩が怪我をしないでいてくれたら控え投手の俺も安心です。だから俺が先輩を見張ります」
宣言通り、圭人が怪我をしないよう、見張るようになった春歌。しかしその守備範囲は体だけではなく、心にもおよび、彼は言う。
「先輩って心が痛がりですね」
そうして彼は、なぜか圭人を抱きしめる。
しかもそれは一度や二度ではなく、圭人が苦しいと感じると必ずハグしてきて……。
こだわり強めの無口男子×一途で不器用男子
表紙はかんたん表紙メーカーさまにて
https://sscard.monokakitools.net/covermaker_view.php
表紙を見る
「今ここで俺にキスされるか、俺にはっきり嫌いって言うか、どっちか選んで」
ある日、自分より頭半分低い場所から、彼はそう言った……。
きっかけは高1の春、
「今日は友人の顔を描いてもらおうと思う。適当にペアになって」
美術教師に言われ、多賀暁史(たがあきふみ)は困惑していた。
ぼっちの自分にとって難易度高過ぎだと肩を落とす暁史に声をかけてくれたのは、華奢で小柄なお姫様のような見た目の時任紅(ときとうくれない)。
明るく朗らかだが押しが強い彼になぜか懐かれるようになった暁史は、いつしか彼のペースに巻き込まれていく……。
小柄強気男子×地味イケボ男子の猫鍋物語
表紙はPhotoACにて
https://www.photo-ac.com/main/detail/1299876&title=%E3%81%BB%E3%81%A3%E3%81%93%E3%82%8A%E3%83%8D%E3%82%B3%E3%83%8A%E3%83%9911
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…
この作品をシェア
狂犬とハーフエクレア
を読み込んでいます