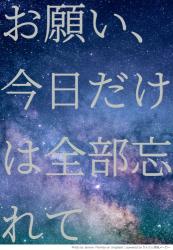僕が所属している菊塚高校の弓道部は、ぶっちゃけ弱小だ。部員は五人だし、女子三人、男子二人という組み合わせだから、団体戦へのエントリーも難しい。顧問の先生がいるにはいるが、弓の経験は高校時代にかじった程度らしく、中学から始めた僕のほうがまだ引ける。上を目指すなら、ここじゃないのだろう。
けれど、僕のようにひとりで黙々と弓を引きたい人間にとって、ここは天国みたいな場所だった。
勝負なんてどうでもいい。ただ、自分と向き合えればそれでいい。
そんなふうだから、応援している、とか、おめでとう、とか言われてもどうにもぴんとこないのだ。
毎週毎週、来られても。
今日は木曜日だ。もうすでに届いているのかもしれないな、と妙な緊張感を覚えながら弓道場へと向かっていた僕は、ふと足を止めた。
角を曲がったすぐのところに弓道場の入り口はある。その入り口の扉が、からり、と開いて閉まる音が響いた。部員のひとりかな、と思った矢先、再び扉が滑り、また閉まる。
足を早め、僕は弓道場へと向かう。
その僕の目線の先、弓道場の前から離れていく人影が見えた。
背の高い、後ろ姿。
それは、部員の誰とも違うものだった。
「待って!」
怒鳴って追いかけると、歩み去ろうとしていた誰かの肩がひゅっと跳ねる。だから、声は届いていたはずだ。だが、その人物は呼び止める僕を振り切るように走り始めた。
「待ってって!」
叫んでも止まらない。
「なあ、おい!」
そこまで必死に逃げるのはなんでだ?
待てと頼んでいるのに。
全力過ぎる走り方に、だんだんいらいらしてきた。
「待てって言ってんだろうが! この野郎!」
怒鳴りながら手にした鞄を振りかぶる。当たると思っていなかったが、それはまっすぐに飛び、逃げる相手の背中にクリーンヒットした。
どわっ! と奇妙な叫び声を上げてつんのめった相手に追いつき、僕はむんずとその腕を捕まえる。
顔を確かめて、驚いた。
「は……え? あれ? ほ、たる? だよな。え、なんで、こ、こに……」
速水ほたる。平仮名で、ほたると書く彼のことを、僕は知っていた。
腕を僕に引っ掴まれたまま、彼が細く息を吐く。ゆるゆると顔が上がり、鋭い目が僕をすうっと捉えた。
「そんなことより、まずは謝ってほしいんだけど。めちゃくちゃ痛かった」
「あ、え、うん、ごめん」
確かにいきなり鞄を投げるのはやり過ぎだった。口の中で謝ってから、僕はそろそろと相手の顔を窺う。
髪型も変わっているし、以前より大人っぽくなってはいる。でも、あのころの面影は消えていない。
ほたる、という柔らかな名前の響きとは対照的な、鋭い顔立ちは昔のままだ。
「命中率やばすぎ。もう」
顔をしかめながら彼は、僕に捕まえられていないほうの手で髪を掻き上げる。
長い指で押さえられたさらさらの髪は、白に近い金色だったあのころとは違う、アッシュブラウン。当時は、キューティクルなんていらねえ! と言わんばかりに傷み切っていたのに、今はちゃんと天使の輪がある。
「俺のこと、覚えてたんだ、樹さん」
うっすらと笑って言う彼の腕から、僕はそろそろと手を離す。
「それは、まあ……でも、あの、え? なんで、ほたるが?」
「なんでって。今年からここに通ってるから。樹さんの後輩です。俺」
「…………は?」
いや、そういうことがないわけじゃないだろう。県違いだって通えないわけじゃない。ないが、しかし……。
混乱している僕を面白そうに見下ろしていたほたるが、ふいと腰を屈めた。
「それにしてもひどいよな。いきなり鞄投げつけるとかさ。さすが、狂犬」
耳元で言われ、ぎょっとする。思わず振り仰ぐと、ほたるはほんのりと笑みらしいものを浮かべながらこちらを見下ろしてきた。
昔はちびだったくせに、なんたることか、今は頭半分以上僕より背が高い。ぎっと睨みつけるが、ほたるは動じる様子をまったくみせない。
「安心してよ。樹さんの黒歴史のことは俺、誰にも言わないから」
黒歴史。
頭をがつんと殴られたような衝撃を受けながら、僕は押し殺した声で訊ねる。
「……目的はなに」
「ないよ、そんなん。学力に合わせて学校選んだらここだっただけ」
本当だろうか。疑わしい顔をすると、ひどいなあ、とほたるは肩をすくめた。
「仮に、俺が目的持ってここに来たとして、それ樹さんにとやかく言われる筋合いある? 自由意志じゃん。そんなの」
「そりゃ、そうだけど……」
「ってことで、これからよろしくです、先輩」
んじゃ、これで、と言ってほたるは背中を向ける。が、なにを思ったのか、つとしゃがみこんだ。長い腕が僕の投げた鞄に伸びる。
「駄目ですよ、もう狂犬の水原樹じゃないんだから。出ちゃってるよ、もろもろ」
おかしそうに言いながら、ぽんぽん、と鞄についた砂が彼によって払われた。
「はい、どうぞ」
「あ、うん、ありがとう」
そろそろと手を伸ばして鞄を受け取ったとき、鼻先をなにかの香りが撫でた。
彼の服に移り香していたのだろうか。漂ってきたのは……甘い、香り。
「ちょっと待って」
じゃあ、本当にこれにて、と手を上げて去っていこうとしていた彼の通学鞄を後ろから掴むと、意表を突かれたようにほたるがたたらを踏んだ。
「毎週木曜日に弓道場にお菓子持ってきてたの、ほたる?」
ほたるの少し吊り気味の目が見開かれる。数秒こちらを見つめてから、彼はなぜかふっと口許を綻ばせた。
「そりゃまあ、このタイミングだし、ばれるよな」
照れ臭そうに呟いてから、彼はつい、と目を逸らす。
「食べて、くれた?」
「は……あ、うん。その、美味かった、けど」
でもなんで、と言いかけた僕を遮るように、ほたるは息を吐く。
「よかった。捨てられても仕方ないかなとは思ってたから、うれしい」
「いや、まあ、正直どうしたらいいかわかんなかったけど。あのさ、あれ」
「ああ、違う違う」
不意にほたるは片手を上げ、ふるふると振る。
「特別な意味とかじゃなくて。俺、調理部だから。無駄にしたくなかっただけ」
「は?! え、お前、調理部?!」
「お前呼ばわり。樹さん、出てる出てる。狂犬が出てる」
たしなめられ、僕ははっと口を押さえる。ほたるはにやりと笑い、軽い手つきで僕の手を解いた。
「樹さん、昔から好きだったから。甘いもの」
「よく覚えてるね」
「覚えてるよ、そりゃあ。だって」
そのとき、ざああっと風が吹いた。ほたるの唇がなにかを紡いでいる。え、と耳を寄せようとしたが、ほたるは笑みを閃かせ、身を引いた。
「また持ってくから。よかったら食べてね、樹さん」
言って、ほたるはひらひらと手を振って去っていった。こちらの返事も聞かずに。
けれど、僕のようにひとりで黙々と弓を引きたい人間にとって、ここは天国みたいな場所だった。
勝負なんてどうでもいい。ただ、自分と向き合えればそれでいい。
そんなふうだから、応援している、とか、おめでとう、とか言われてもどうにもぴんとこないのだ。
毎週毎週、来られても。
今日は木曜日だ。もうすでに届いているのかもしれないな、と妙な緊張感を覚えながら弓道場へと向かっていた僕は、ふと足を止めた。
角を曲がったすぐのところに弓道場の入り口はある。その入り口の扉が、からり、と開いて閉まる音が響いた。部員のひとりかな、と思った矢先、再び扉が滑り、また閉まる。
足を早め、僕は弓道場へと向かう。
その僕の目線の先、弓道場の前から離れていく人影が見えた。
背の高い、後ろ姿。
それは、部員の誰とも違うものだった。
「待って!」
怒鳴って追いかけると、歩み去ろうとしていた誰かの肩がひゅっと跳ねる。だから、声は届いていたはずだ。だが、その人物は呼び止める僕を振り切るように走り始めた。
「待ってって!」
叫んでも止まらない。
「なあ、おい!」
そこまで必死に逃げるのはなんでだ?
待てと頼んでいるのに。
全力過ぎる走り方に、だんだんいらいらしてきた。
「待てって言ってんだろうが! この野郎!」
怒鳴りながら手にした鞄を振りかぶる。当たると思っていなかったが、それはまっすぐに飛び、逃げる相手の背中にクリーンヒットした。
どわっ! と奇妙な叫び声を上げてつんのめった相手に追いつき、僕はむんずとその腕を捕まえる。
顔を確かめて、驚いた。
「は……え? あれ? ほ、たる? だよな。え、なんで、こ、こに……」
速水ほたる。平仮名で、ほたると書く彼のことを、僕は知っていた。
腕を僕に引っ掴まれたまま、彼が細く息を吐く。ゆるゆると顔が上がり、鋭い目が僕をすうっと捉えた。
「そんなことより、まずは謝ってほしいんだけど。めちゃくちゃ痛かった」
「あ、え、うん、ごめん」
確かにいきなり鞄を投げるのはやり過ぎだった。口の中で謝ってから、僕はそろそろと相手の顔を窺う。
髪型も変わっているし、以前より大人っぽくなってはいる。でも、あのころの面影は消えていない。
ほたる、という柔らかな名前の響きとは対照的な、鋭い顔立ちは昔のままだ。
「命中率やばすぎ。もう」
顔をしかめながら彼は、僕に捕まえられていないほうの手で髪を掻き上げる。
長い指で押さえられたさらさらの髪は、白に近い金色だったあのころとは違う、アッシュブラウン。当時は、キューティクルなんていらねえ! と言わんばかりに傷み切っていたのに、今はちゃんと天使の輪がある。
「俺のこと、覚えてたんだ、樹さん」
うっすらと笑って言う彼の腕から、僕はそろそろと手を離す。
「それは、まあ……でも、あの、え? なんで、ほたるが?」
「なんでって。今年からここに通ってるから。樹さんの後輩です。俺」
「…………は?」
いや、そういうことがないわけじゃないだろう。県違いだって通えないわけじゃない。ないが、しかし……。
混乱している僕を面白そうに見下ろしていたほたるが、ふいと腰を屈めた。
「それにしてもひどいよな。いきなり鞄投げつけるとかさ。さすが、狂犬」
耳元で言われ、ぎょっとする。思わず振り仰ぐと、ほたるはほんのりと笑みらしいものを浮かべながらこちらを見下ろしてきた。
昔はちびだったくせに、なんたることか、今は頭半分以上僕より背が高い。ぎっと睨みつけるが、ほたるは動じる様子をまったくみせない。
「安心してよ。樹さんの黒歴史のことは俺、誰にも言わないから」
黒歴史。
頭をがつんと殴られたような衝撃を受けながら、僕は押し殺した声で訊ねる。
「……目的はなに」
「ないよ、そんなん。学力に合わせて学校選んだらここだっただけ」
本当だろうか。疑わしい顔をすると、ひどいなあ、とほたるは肩をすくめた。
「仮に、俺が目的持ってここに来たとして、それ樹さんにとやかく言われる筋合いある? 自由意志じゃん。そんなの」
「そりゃ、そうだけど……」
「ってことで、これからよろしくです、先輩」
んじゃ、これで、と言ってほたるは背中を向ける。が、なにを思ったのか、つとしゃがみこんだ。長い腕が僕の投げた鞄に伸びる。
「駄目ですよ、もう狂犬の水原樹じゃないんだから。出ちゃってるよ、もろもろ」
おかしそうに言いながら、ぽんぽん、と鞄についた砂が彼によって払われた。
「はい、どうぞ」
「あ、うん、ありがとう」
そろそろと手を伸ばして鞄を受け取ったとき、鼻先をなにかの香りが撫でた。
彼の服に移り香していたのだろうか。漂ってきたのは……甘い、香り。
「ちょっと待って」
じゃあ、本当にこれにて、と手を上げて去っていこうとしていた彼の通学鞄を後ろから掴むと、意表を突かれたようにほたるがたたらを踏んだ。
「毎週木曜日に弓道場にお菓子持ってきてたの、ほたる?」
ほたるの少し吊り気味の目が見開かれる。数秒こちらを見つめてから、彼はなぜかふっと口許を綻ばせた。
「そりゃまあ、このタイミングだし、ばれるよな」
照れ臭そうに呟いてから、彼はつい、と目を逸らす。
「食べて、くれた?」
「は……あ、うん。その、美味かった、けど」
でもなんで、と言いかけた僕を遮るように、ほたるは息を吐く。
「よかった。捨てられても仕方ないかなとは思ってたから、うれしい」
「いや、まあ、正直どうしたらいいかわかんなかったけど。あのさ、あれ」
「ああ、違う違う」
不意にほたるは片手を上げ、ふるふると振る。
「特別な意味とかじゃなくて。俺、調理部だから。無駄にしたくなかっただけ」
「は?! え、お前、調理部?!」
「お前呼ばわり。樹さん、出てる出てる。狂犬が出てる」
たしなめられ、僕ははっと口を押さえる。ほたるはにやりと笑い、軽い手つきで僕の手を解いた。
「樹さん、昔から好きだったから。甘いもの」
「よく覚えてるね」
「覚えてるよ、そりゃあ。だって」
そのとき、ざああっと風が吹いた。ほたるの唇がなにかを紡いでいる。え、と耳を寄せようとしたが、ほたるは笑みを閃かせ、身を引いた。
「また持ってくから。よかったら食べてね、樹さん」
言って、ほたるはひらひらと手を振って去っていった。こちらの返事も聞かずに。