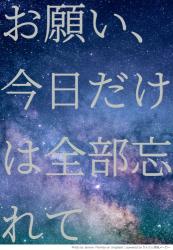「まったく、やらかしてくれるねえ」
壮行会が終わった後、僕は弓道部顧問の飯田先生に呼び出され、こってり絞られた。場所は普段なら先生が滅多に来ない、弓道場だった。
「伝説のヤンキーは僕ですって檀上で告白って。漫画かよって思わずのけぞったよ。ああいうことはもうちょっと早く教えておいてもらいたかった」
「いや、あ、はい。すみません。ただ、その……入部当時は卒業まで隠し通すつもりでいたので……」
「それをまあ、センセーショナルに発表しちゃったね」
ははは、と飯田先生が笑う。その先生の前で僕は左手で右手首をぐっと掴む。
自分の勝手な思いで、飯田先生にも迷惑がかかってしまうかもしれない。今頃その可能性に気付き、目の前が暗くなっていた。
「わかっては、います。あんな啖呵を切りましたが、こういう人間ですし、全国へ行くこともできなくなるかもしれませんね」
「なんで?」
飯田先生がきょとんとした顔をする。
「そんな規定あったっけ? 大体、君が狂犬である証拠は? いや、そもそも狂犬って。君に似合わな過ぎ」
丸い肩を揺らして飯田先生が笑う。笑いごとだろうか、と僕は顔をしかめる。けれどもあまりにもおかしそうに笑われるので、だんだんこちらまで頬が緩んできてしまった。
飯田先生にはこんなところがある。飄々としていてつかみどころがない。
ひとしきり笑ってから、先生は顔を上げた。
「狂犬がどうとかはともかくさ、僕はね、感動しちゃったんだよ。君のスピーチ」
「感動、ですか?」
「だってそうだろ。君があそこで自分が狂犬、ああ、だめだ、やっぱり狂犬って言うと笑っちゃう……ごめん。ともかく、狂犬だって言い出したのって、誰かを守りたいなあって思ったからなんだろ」
さらっと、守りたい、と言われて頬が熱くなった。
そんな大層なものではない。ただ許せなかった。それだけなのだ。美化されても困る。
「狂犬の血が騒いだとか、そんなレベルの話です」
「君は僕を笑い死にさせたいのか」
ああ、苦しい、と言って飯田先生は眼鏡を外して目元を拭った後、ふっと真顔になった。
「弓道はさ、ひとりで閉じてひとりで進んでいく孤独な武道だよね。でもさ、弓ってもともとは命をかけて戦うための武器としてあったんだよね」
「そう、ですね」
頷く僕の前で飯田先生は、ふうっと眼鏡に息を吹きかけてこしこしとハンカチで拭く。
「もちろん当時もさ、弓は自分のために使われただろうと思うよ。けれど……誰かを守りたい、そんな思いを抱いて弓を構えた人だって絶対にいたはずだよね」
汚れがなくなったか確認するように、飯田先生は眼鏡をかざす。眼鏡のレンズ越し、先生の目が僕を見つめた。
「君にとっても弓ってそういうものなのかもしれないなあ、って思ったらすごく胸が熱くなった」
水原くん、と顔に眼鏡を戻しながら先生が僕を呼ぶ。
「僕は、君は素敵だと思ったよ。いろいろ言う人もいる。でもそれを跳ね返すくらい、今の力を見せてやりなさい。君ならできるよ」
じりり、と瞼が熱を帯びる。思わず唇を噛みしめる僕に気付かぬふうに、飯田先生は弓道場を見回した。
「君を見てたら僕もまた引きたくなってきたな。水原くんさ、教えてくれる? もう結構忘れちゃっててさ」
「僕で、よければ」
なんとかそう返すと、飯田先生はにこりと笑って、練習、頑張らないとな、と丸い声で言った。
壮行会が終わった後、僕は弓道部顧問の飯田先生に呼び出され、こってり絞られた。場所は普段なら先生が滅多に来ない、弓道場だった。
「伝説のヤンキーは僕ですって檀上で告白って。漫画かよって思わずのけぞったよ。ああいうことはもうちょっと早く教えておいてもらいたかった」
「いや、あ、はい。すみません。ただ、その……入部当時は卒業まで隠し通すつもりでいたので……」
「それをまあ、センセーショナルに発表しちゃったね」
ははは、と飯田先生が笑う。その先生の前で僕は左手で右手首をぐっと掴む。
自分の勝手な思いで、飯田先生にも迷惑がかかってしまうかもしれない。今頃その可能性に気付き、目の前が暗くなっていた。
「わかっては、います。あんな啖呵を切りましたが、こういう人間ですし、全国へ行くこともできなくなるかもしれませんね」
「なんで?」
飯田先生がきょとんとした顔をする。
「そんな規定あったっけ? 大体、君が狂犬である証拠は? いや、そもそも狂犬って。君に似合わな過ぎ」
丸い肩を揺らして飯田先生が笑う。笑いごとだろうか、と僕は顔をしかめる。けれどもあまりにもおかしそうに笑われるので、だんだんこちらまで頬が緩んできてしまった。
飯田先生にはこんなところがある。飄々としていてつかみどころがない。
ひとしきり笑ってから、先生は顔を上げた。
「狂犬がどうとかはともかくさ、僕はね、感動しちゃったんだよ。君のスピーチ」
「感動、ですか?」
「だってそうだろ。君があそこで自分が狂犬、ああ、だめだ、やっぱり狂犬って言うと笑っちゃう……ごめん。ともかく、狂犬だって言い出したのって、誰かを守りたいなあって思ったからなんだろ」
さらっと、守りたい、と言われて頬が熱くなった。
そんな大層なものではない。ただ許せなかった。それだけなのだ。美化されても困る。
「狂犬の血が騒いだとか、そんなレベルの話です」
「君は僕を笑い死にさせたいのか」
ああ、苦しい、と言って飯田先生は眼鏡を外して目元を拭った後、ふっと真顔になった。
「弓道はさ、ひとりで閉じてひとりで進んでいく孤独な武道だよね。でもさ、弓ってもともとは命をかけて戦うための武器としてあったんだよね」
「そう、ですね」
頷く僕の前で飯田先生は、ふうっと眼鏡に息を吹きかけてこしこしとハンカチで拭く。
「もちろん当時もさ、弓は自分のために使われただろうと思うよ。けれど……誰かを守りたい、そんな思いを抱いて弓を構えた人だって絶対にいたはずだよね」
汚れがなくなったか確認するように、飯田先生は眼鏡をかざす。眼鏡のレンズ越し、先生の目が僕を見つめた。
「君にとっても弓ってそういうものなのかもしれないなあ、って思ったらすごく胸が熱くなった」
水原くん、と顔に眼鏡を戻しながら先生が僕を呼ぶ。
「僕は、君は素敵だと思ったよ。いろいろ言う人もいる。でもそれを跳ね返すくらい、今の力を見せてやりなさい。君ならできるよ」
じりり、と瞼が熱を帯びる。思わず唇を噛みしめる僕に気付かぬふうに、飯田先生は弓道場を見回した。
「君を見てたら僕もまた引きたくなってきたな。水原くんさ、教えてくれる? もう結構忘れちゃっててさ」
「僕で、よければ」
なんとかそう返すと、飯田先生はにこりと笑って、練習、頑張らないとな、と丸い声で言った。