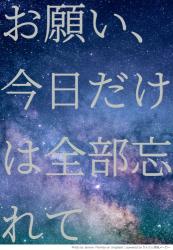きりり、と耳の端で張りつめた音を立てる弦。
白砂の向こう、僕をまっすぐに見返してくる霞的。
傲然と顎を上げるように、的が僕に向かって笑う。
さあ、放ってみなよ。私を射抜いてご覧。
見ていてあげるから。
もちろん、的はそんなことを言いはしない。ただ静かにこちらを見返すだけだ。
だからこれは全部、僕の心の声。
負けてたまるか、と唇を噛みしめ続けてきた僕自身が生み出した、僕の、声。
諦めるな。
絶対に自ら投げ捨てるな。
背筋を伸ばして立ち続けろ。
そうすれば、中る。
く、と指先に走る確信に押され、僕の指は弦から解き放たれる。しゅん、と鋭い音を立て、僕の横を通り過ぎていく、軌跡。
ぱすん、と高い音を立てて的の中心へと吸い込まれていくそれを認めてから、僕は腕を下ろす。
一連の所作を忠実にこなし、的前で振り向くと、弓道部の面々が音を立てないよう、掌を擦り合わせるようにしてささやかな拍手をしてくれていた。
「水原部長ってやっぱり綺麗ですよねえ。射形」
「顧問、弓引けないけど、部長がいてくれれば私たちも上手くなりそうな予感……」
「お願い、部長、私たちが卒業するまでここにいて〜」
「……いや、卒業はするよ」
軽口を言い合う部員たちに苦笑いしながら言い返したとき、一年生の宮池くんが思い出したように言った。
「部長って中学時代から弓、習われてたんでしたよね?」
「ああ、うーん、まあ。習うっていうかまあ」
放り込まれたんです、とは言えず、僕は曖昧に笑いながら、Tシャツの袖で額の汗を拭う。
弓道は好きだ。それだけは間違いない。
だが、弓道に関わるきっかけとなったかつての自分のことは、思い出したくないし、語りたくもない。
過去に触れられたくないから、自宅から遠く離れた県違いの高校に進学したのだ。
どう言おうかな、と迷っていると、そういえば、と部員のひとり、永井さんがこちらに顔を向けてきた。
「今日も届いてましたよ、部長宛のあれ」
「え! 例のやつ?」
「そうそう」
女子部員三人が楽しげに顔を見合わせた後、ばっと一斉にこちらを向く。
「え、届いてるってなんですか?」
ひとりだけ事情がわかっていないらしい宮池くんに、永井さんが呆れた顔をした。
「気付いてなかったの? 四月からこっち、毎週木曜日に、弓道場の靴箱のとこにクッキーやらマフィンやらが置いてあるの! 超可愛くラッピングされたやつが!」
「……でもあれ、僕個人宛ではないよね。弓道部の皆さんで、って書いてあったこともあったし」
やんわりと否定してみる。とたんに、眉を逆立てた女子全員から強烈な反発が返ってきた。
「いやいや、あれ、食べてほしい本命は部長でしょ〜! 部長が大会で優勝したとき『おめでとう』ってメモ入ってたし!」
「ビスケットにチョコペンで部長の似顔絵描いてあったし! しかも激似のやつ!」
「あれで自分宛じゃないなんて思うの、さすがに鈍感すぎると思います!」
「そんなのあったんですか」
宮池くんが、すげえな、という顔でこちらを見る。なんだか猛烈に恥ずかしい。
「まあ、私たちもみんなであれ、食べちゃってるんで、さすがにどうかとは思いますけどね」
「でもほら、弓道部の皆さんでって書いてあったし。ねえ?」
「落とし物として届けても捨てられちゃうし」
「って、それ、ストーカーからなんじゃ。俺からすると、誰が作ったかわかんないもんを、先輩たちよく食べるなって思いますけどね」
宮池くんが気味悪そうに女子たちを見る。彼女たちは再び顔を見合わせてから口々に応戦し始めた。
「そりゃ確かに最初はどうかと思ったよ? でもさあ、捨てるほうが怖くない?」
「そうそう。大体、あれは愛情がないと作れない類のやつ。むしろ捨てたら祟られそう」
「お腹も壊してないし。大丈夫大丈夫」
……大丈夫で済ませていい話なのだろうか。
うんうん、と頷き合っている彼女たちを眺めながら、僕は腕を組む。
正直なところ、僕としては困惑していた。誰だか知らないが、毎週毎週ひっそりと来られても対処ができない。
はっきり言えば、うれしいというよりも……不気味だ。
届けられるクッキーやマフィン、マカロンもあったが、どれもが驚くほど美味いこともまた問題だった。
初めのうちは恐る恐るだったにも関わらず、いつの間にかつい美味い美味いと食べてしまうほどに、それらは美味過ぎたのだ。
誰の手によるものかわからないのに、ちょっと楽しみになってしまうほどに。
これが悪意ある誰かの手によるものだとしたら、弓道部全員あっさりあの世行きだろう。
二か月経った今も異常がないところをみると、そうした悪意はないのかもしれないが、やっぱり気になる。
あんな手の込んだものを毎週毎週届ける意図とはなんなのか。
しかし、今は部活だ。
「ほら、話してないで練習」
にっこりと笑って促すと、部員たちはそれぞれ、はあい、と声を上げながら的へと向き直った。
白砂の向こう、僕をまっすぐに見返してくる霞的。
傲然と顎を上げるように、的が僕に向かって笑う。
さあ、放ってみなよ。私を射抜いてご覧。
見ていてあげるから。
もちろん、的はそんなことを言いはしない。ただ静かにこちらを見返すだけだ。
だからこれは全部、僕の心の声。
負けてたまるか、と唇を噛みしめ続けてきた僕自身が生み出した、僕の、声。
諦めるな。
絶対に自ら投げ捨てるな。
背筋を伸ばして立ち続けろ。
そうすれば、中る。
く、と指先に走る確信に押され、僕の指は弦から解き放たれる。しゅん、と鋭い音を立て、僕の横を通り過ぎていく、軌跡。
ぱすん、と高い音を立てて的の中心へと吸い込まれていくそれを認めてから、僕は腕を下ろす。
一連の所作を忠実にこなし、的前で振り向くと、弓道部の面々が音を立てないよう、掌を擦り合わせるようにしてささやかな拍手をしてくれていた。
「水原部長ってやっぱり綺麗ですよねえ。射形」
「顧問、弓引けないけど、部長がいてくれれば私たちも上手くなりそうな予感……」
「お願い、部長、私たちが卒業するまでここにいて〜」
「……いや、卒業はするよ」
軽口を言い合う部員たちに苦笑いしながら言い返したとき、一年生の宮池くんが思い出したように言った。
「部長って中学時代から弓、習われてたんでしたよね?」
「ああ、うーん、まあ。習うっていうかまあ」
放り込まれたんです、とは言えず、僕は曖昧に笑いながら、Tシャツの袖で額の汗を拭う。
弓道は好きだ。それだけは間違いない。
だが、弓道に関わるきっかけとなったかつての自分のことは、思い出したくないし、語りたくもない。
過去に触れられたくないから、自宅から遠く離れた県違いの高校に進学したのだ。
どう言おうかな、と迷っていると、そういえば、と部員のひとり、永井さんがこちらに顔を向けてきた。
「今日も届いてましたよ、部長宛のあれ」
「え! 例のやつ?」
「そうそう」
女子部員三人が楽しげに顔を見合わせた後、ばっと一斉にこちらを向く。
「え、届いてるってなんですか?」
ひとりだけ事情がわかっていないらしい宮池くんに、永井さんが呆れた顔をした。
「気付いてなかったの? 四月からこっち、毎週木曜日に、弓道場の靴箱のとこにクッキーやらマフィンやらが置いてあるの! 超可愛くラッピングされたやつが!」
「……でもあれ、僕個人宛ではないよね。弓道部の皆さんで、って書いてあったこともあったし」
やんわりと否定してみる。とたんに、眉を逆立てた女子全員から強烈な反発が返ってきた。
「いやいや、あれ、食べてほしい本命は部長でしょ〜! 部長が大会で優勝したとき『おめでとう』ってメモ入ってたし!」
「ビスケットにチョコペンで部長の似顔絵描いてあったし! しかも激似のやつ!」
「あれで自分宛じゃないなんて思うの、さすがに鈍感すぎると思います!」
「そんなのあったんですか」
宮池くんが、すげえな、という顔でこちらを見る。なんだか猛烈に恥ずかしい。
「まあ、私たちもみんなであれ、食べちゃってるんで、さすがにどうかとは思いますけどね」
「でもほら、弓道部の皆さんでって書いてあったし。ねえ?」
「落とし物として届けても捨てられちゃうし」
「って、それ、ストーカーからなんじゃ。俺からすると、誰が作ったかわかんないもんを、先輩たちよく食べるなって思いますけどね」
宮池くんが気味悪そうに女子たちを見る。彼女たちは再び顔を見合わせてから口々に応戦し始めた。
「そりゃ確かに最初はどうかと思ったよ? でもさあ、捨てるほうが怖くない?」
「そうそう。大体、あれは愛情がないと作れない類のやつ。むしろ捨てたら祟られそう」
「お腹も壊してないし。大丈夫大丈夫」
……大丈夫で済ませていい話なのだろうか。
うんうん、と頷き合っている彼女たちを眺めながら、僕は腕を組む。
正直なところ、僕としては困惑していた。誰だか知らないが、毎週毎週ひっそりと来られても対処ができない。
はっきり言えば、うれしいというよりも……不気味だ。
届けられるクッキーやマフィン、マカロンもあったが、どれもが驚くほど美味いこともまた問題だった。
初めのうちは恐る恐るだったにも関わらず、いつの間にかつい美味い美味いと食べてしまうほどに、それらは美味過ぎたのだ。
誰の手によるものかわからないのに、ちょっと楽しみになってしまうほどに。
これが悪意ある誰かの手によるものだとしたら、弓道部全員あっさりあの世行きだろう。
二か月経った今も異常がないところをみると、そうした悪意はないのかもしれないが、やっぱり気になる。
あんな手の込んだものを毎週毎週届ける意図とはなんなのか。
しかし、今は部活だ。
「ほら、話してないで練習」
にっこりと笑って促すと、部員たちはそれぞれ、はあい、と声を上げながら的へと向き直った。