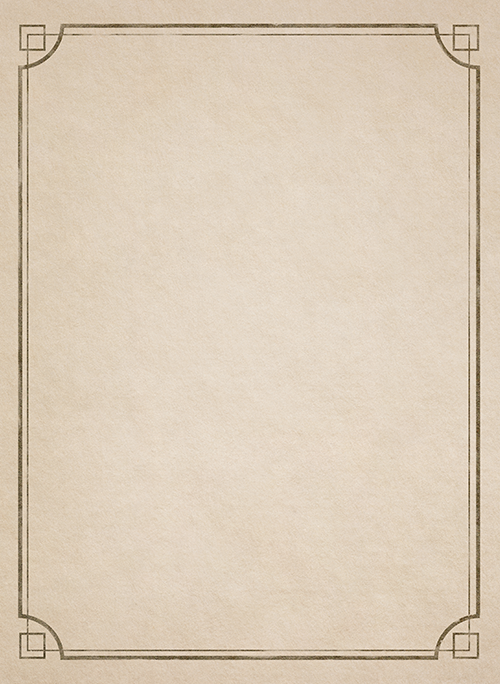第九話
次の日。
私は、昨日と同じ時間に学校へ来ていた。
すると、もう先にカリンちゃんがいた。
「おはようございます。」
「カリンちゃん、おはよう。」
私はカリンちゃんの方へ微笑みながら、あいさつをした。
彼女からは、真面目さといえばいいのだろうか?
まだ他人行儀な感じが伺えた。
「ホームルームの進行をお願いね?」
「はい。」
私とカリンちゃんの会話は、それだけだった。
私がそう言って、自席に近づいていると。
カリンちゃんは、教室から出て行った。
私もそれを引き留めるようなこともしない。
学校に早く来たのに、深い意味はないのだ。
もちろん、クラス委員の仕事とも関係ない。
しいて言えば、カリンちゃんが何時に来るのか気になったからだ。
目的は果たされた。
そう思った私は、学校へ持ち込んでいる本を鞄から取り出した。
その本は、最近読み始めた心理学の入門書だった。
人間の行動や思考のパターンについて書かれていた。
ページをめくりながら、ふと、私は窓の外を見た。
朝日が校庭を明るく照らし始めていた。
まだ早い時間だが、運動部の生徒たちが朝練習を始めているのが見えた。
私は、本の内容と目の前の光景を重ね合わせていた。
人々の行動パターン、集団の中での個人の振る舞い方。
それらが、この小さな学校という社会の中でどのように現れているのか。
特に気になったのは、「同調性バイアス」という内容だった。
人は無意識のうちに周囲の意見や行動に合わせようとする傾向がある、というものだ。
ふと、カリンちゃんのことを考えた。
彼女は、このクラスの中で孤立している。
ということは、同調性がないということだろうか?
つまりバイアスのない、自由な存在?
だとすれば、私がカリンちゃんとクラス委員として一緒に活動していくと…
彼女は、同調性バイアスで変わっていくのだろうか。
そんなことを考えながら、私は読書を続ける。
やがて、教室に生徒たちが徐々に集まり始めていた。
たぶん、そろそろ、ヒナコちゃんとハナちゃんが教室に来るだろう、と思った。
賑やかになっていく教室の中で、私は本を読み進めていた。
「アイリちゃん!」
ハナちゃんの声が聞こえた。
私は本を閉じた。
「おはよう、ハナちゃん」
私は優しく微笑みながら答えた。
ハナちゃんの元気な声は、いつも周囲の雰囲気に活気をもたらす。
それからなんということもない、朝の時間が過ぎていった。
教室には徐々に生徒たちが集まり始め、ガヤガヤとした喧騒が広がっていく。
やがて、ヒナコちゃんも私の席の周辺に来て、とりとめのない話をする。
「おはよう、アイリ」
ヒナコちゃんの声には、いつもの凛とした響きがあった。
「おはよう、ヒナコちゃん」
私は穏やかに返事をした。
三人で話をしていると、日々の些細な出来事が次々と話題に上がる。
ハナちゃんの明るい笑い声、ヒナコちゃんの的確なツッコミ。
私はその二人の会話に聞いていた。
そして、チャイムが鳴った。
いつものようにヒナコちゃんとハナちゃんというメンバーで会話をしていた私たちは、授業に備える。
「またな、アイリ」
「アイリちゃん、クラス委員がんばってー」
能天気な様子のハナちゃんと、凛々しいヒナコちゃんへ手を振る。
二人は自席へと戻っていった。
さて、これから朝のホームルーム。
今日は、カリンちゃんが司会進行をする番だ。
私は、いつもの席に座りながら、カリンちゃんの様子を観察していた。
カリンちゃんは、少し緊張した様子だった。
彼女は、ホームルームの進行を書いたファイルを握りしめ、ゆっくりと席から立ち上がった。
「起立」
カリンちゃんの声が、教室に響いた。
その声は小さい。
彼女の号令で、一部のクラスメイトたちが立ち上がる。
というのは、カリンちゃんの声が小さすぎて、後ろの方の生徒たちには聞こえなかったらしい。
クラス全体で立つタイミングがずれる。
それは、まるで不揃いな足音のような、疎らな音を生んだ。
教室全体に、何か失敗してしまったような空気が漂う。
しかし、カリンちゃんは必死に次の言葉を発しようとしている。
彼女の目は前方を見つめたまま、周囲の状況を把握する余裕はないようだ。
おそらく、今の彼女の中では、何が起こっているのか理解できていないのだろう。
ただ機械的に、次の言葉を発そうとしているだけに見える。
「…礼」
カリンちゃんの声は、さらに小さくなっていた。
本来なら、教室の生徒全員が同じタイミングで礼をしなければならない。
しかし、カリンちゃんの声が聞こえたわずかな生徒だけが礼をしている。
他の生徒たちは、周囲の様子を見て適当に合わせたり、まったく無視したりと、反応は様々だ。
担任の先生が、困ったような表情を浮かべている。
たぶん、この場面での最善の策は、もう一度大きな声で「礼」という号令をかけ直すことだろう。
しかし、完全にパニックに陥っているカリンちゃんには、そんな余裕はない。
「ち、ちち。ちゃ…着…着席」
カリンちゃんの声は、もはやほとんど聞こえないほど小さくなっていた。
そして、耳を澄まして聞いている私には、彼女が吃音であることが分かった。
教室内はざわついており、カリンちゃんの声など誰も聞いていないようだった。
私は、カリンちゃんの様子を見つめていた。
彼女の表情は完全にパニックに陥っている。
今の彼女に冷静な判断を期待するのは難しいだろう。
「みなさん、静かに。藤原さん、もう一度お願いできるかな?」
先生へカリンちゃんへ優しく声を掛ける。
その穏やかな声に、教室内に静けさが戻った。
もっとも先生から声を掛けられているカリンちゃんは、浅い呼吸を繰り返すだけで、返事をする余裕さえないようだった。
「あっ、じゃあ。桔梗さん。代わりにお願いしてもいいかな?」
先生の視線が私に向けられる。
私は一瞬、躊躇した。
カリンちゃんの気持ちを考えると、代わりに号令をかけることで彼女を傷つけてしまうのではないかと心配になった。
しかし、このまま放置することもできない。
「…はい。分かりました。」
私は担任の教師に従うことにした。
立ち上がりながら、カリンちゃんの方をちらりと見る。彼女は、まだ放心状態のようだった。
「起立」
教室の生徒が、私の声に従って一斉に立ち上がる。
立ったままのカリンちゃんはそのままだ。
「礼」
先生に向かってお辞儀をする。
カリンちゃんも私の号令に従っていた。
たぶん、パニック状態である彼女が無意識に行動している、と私は思った。
「着席」
私がそう号令を掛けると。
カリンちゃんを含んだクラスの全員が、自席に着いた。
私としては、これは難しい状況だ、と思った。
もしかしたら、繊細なカリンちゃんの心を傷つけてしまったかもしれない、と思った。
ふと、カリンちゃんを見る。
放心した様子で、じっと席についているカリンちゃんが見えた。
もはや、今の彼女には考える余裕すらないようだ。
ホームルームの残りの時間、私が進行をしていた。
正直、適当にやっていたこともあったが、特に問題もなくホームルームは終わった。
ホームルームが終わり、罰の悪そうな様子で自席にいるカリンちゃんが見えた。
そして、教室の先生が入れ替わり、1時間目の授業が始まる。
数学の先生が教室に入ってきた。
しかし、私には、カリンちゃんのことが離れなかった。
授業中、何度か後ろを振り返ってみた。
カリンちゃんは、うつむいたまま動かない。
教科書を開いているわけでもなく、ただぼんやりと机を見つめている。
私は、何かできることはないかと考えていた。
でも、今はまだ何もできない。
授業が終わり、休み時間になった。
私は、声をかけようか迷った。
しかし、なんて声を掛けるのが最適なのだろうか?
今は何も言わないという選択肢もある。
そんなことを思っていると、ヒナコちゃんが私を見ていることに気がついた。
ヒナコちゃんのほうを見ると、目が合った。
すると、こちらを見ていたヒナコちゃんが、目配せをしてきた。
カリンちゃんの席の方へとちらりと動き、そしてまた私に戻る。
『カリンちゃんの方へ行け』とヒナコちゃんは私に言っているのだ。
私は、ヒナコちゃんに従うことにした。
自席から立った私は、さりげなくカリンちゃんの席に近づいた。
「カリンちゃん」
私は、優しく声をかけた。
「あっ、あの。桔梗さん。朝は…。ごめんなさい。」
カリンちゃんの表情は暗い。
本当に悪いと思っているようだ。
「カリンちゃん、そんなに謝らなくていいわ。」
私は、できるだけ優しく声を掛けた。
カリンちゃんは暗い。
「あの。…でも。…こんなことも…。」
カリンちゃんは、ポツリポツリという感じで話している。
その様子からは、自分への失望が垣間見える。
「何も…できなくて…。」
そこまで言って、カリンちゃんの声が途切れた。
彼女が話しているうちに、自分の感情が高ぶってきたみたいだった。
その感情とは、悲しみの感情だ。
「失敗は誰でもあるものよ。」
私は、彼女を傷つけないように慎重に言葉を選ぶ。
「ごめんなさい。」
カリンちゃんの顔が歪んでいた。
涙が出そうだ。
「そんなこと言わないで。人それぞれ、できることは違うわ。それに、カリンちゃんは頑張ったじゃない。」
私の慰めに、カリンちゃんは黙った。
彼女は俯いたままだ。
たぶん、泣きそうになっている気持ちでいっぱいなのだろう。
私はどうすればいいのかと、考えていると。
その時、チャイムが鳴った。
次の授業が始まる合図だ。
「また後で話しましょう。」
私はそう言って、自分の席に戻った。
席に着きながら、ヒナコちゃんの方を見ると、彼女は小さく頷いてくれた。
授業が始まり、先生が教室に入ってきた。
私は、時々後ろを振り返ってカリンちゃんの様子を確認した。
カリンちゃんは、少しずつだが、授業に集中し始めているようだった。
私は、カリンちゃんのことを考えながら、ノートを取っていた。
これからどうすればいいのだろうか。
授業が進む中、私の頭の中は、カリンちゃんのことでいっぱいだった。
この状況を、どのように進めて行けばいいのだろうか。
私には、まだその答えが見えてこなかった。
その後の授業中。
私はカリンちゃんと話すことはなかった。
彼女と何を話せばいいのか、分からない。
何よりも、カリンちゃんが誰とも話したくなさそうにしていた、ということもあった。
そっとしておこう。
そういう判断を下した。
そして、昼休みになった。
いつものように、ハナちゃんとヒナコちゃんと一緒にお弁当を食べる準備をする。
そして、私はカリンちゃんの方をちらりと見た。
まだ少し元気がなさそうだった。
「ねえねえ、アイリちゃん」
ハナちゃんが、小声で私に話しかけてきた。
「何かしら?」
私は、ハナちゃんの方を見た。
「今朝のカリンちゃん、大丈夫かな?」
ハナちゃんの目に、心配の色が浮かんでいる。
「あれは辛かっただろうな。」
ヒナコちゃんも、真剣な表情で言った。
「何か…。もっとこう、お話ししたほうがいいのかな?」
「いや、ハナ。そっとしておくことも大事だ。」
「そーかな。」
「そうだ。」
二人が、二人なりの議論をしていた。
「私は、放課後に一緒に話をしようと思っているわ。」
「そうか。アイリがそうするなら、それがいいんだろうな。」
ヒナコちゃんは気を使っているようだった。
もちろん、ハナちゃんもだ。
朝のホームルームから始まったカリンちゃんの問題。
それはある意味で、クラス委員である私とカリンちゃんの問題でもあるのだ。
たしかに、気を使ってくるのは自然な流れなのかもしれない。
昼食を終え、午後の授業が始まった。
私は、授業を聞きながらも、時々カリンちゃんの方を見ていた。
彼女は、少しずつ普段の表情を取り戻しているように見えた。
ということは、放課後には、普段通りに話が出来そうだ、と私は思った。
放課後。
私とカリンちゃんは、クラス委員の仕事をする。
黒板を消したり、机を整頓したりという簡単なものだ。
ハナちゃんやヒナコちゃんを筆頭とした生徒たちがいなくなった教室。
その静かな教室の中で、私はカリンちゃんと二人で作業を進めていく。
黒板を書き換えた私とカリンちゃんは、机の位置を整頓することになった。
ちなみにそれまでの間に、私とカリンちゃんは朝のことについて、特に話をしていない。
触れるのが難しい話題というところだ。
「カリンちゃん。」
私は、さりげなく話しかけた。
「はい、なんでしょうか?桔梗さん。」
「机の位置を綺麗に整列させましょう?」
「はい。…でも、どうしましょう?」
カリンちゃんは、私に聞いてきた。
どうやら、机の位置をどこに合わせるのか、そういう意味らしい。
「カリンちゃん。一番前の机に合わせましょう。」
「はい。」
どこか表情の変化に乏しいカリンちゃんは、まるでロボットのようだ。
カリンちゃんは私に従って作業を始めた。
私たちは黙々と机を動かし始めた。
カリンちゃんの動きは慎重で、まるで机を壊してしまうのではないかと恐れているかのようだった。
その姿を見ていると、今朝の出来事が彼女の心に深く刻まれているのだろうと感じた。
とはいえ、作業自体は誰でもできる。
机を引く音。
足音。
淡々と作業が進んでいく。
そのとき、カリンちゃんがある机を重そうにしていた。
「あっ、手伝うわ。」
「えっ?いえ…。」
カリンちゃんは、そう言って、やんわりと断ろうとしてきた。
しかし、私は、それを無視して手伝うように近づいた。
私は、カリンちゃんの隣で机の前に立った。
そして、ちょっとだけ机を確認で動かそうとする。
「やっぱり重いわ、この机。」
一人だと、引きずることすら難しい。
一体、机の中に何を入れているのだろうか?
もちろん、各生徒の持ち物なので、確認することはない。
「一緒に動かしましょう?」
「はい。」
カリンちゃんは、なにか言いたげだった。
しかし、私と一緒に机を動かし始めた。
そのまま、カリンちゃんと私はうまく机を整列させた。
「良かったわね。これを運べて。」
「いえ、その。すいません。桔梗さん。」
カリンちゃんは、申し訳ないように謝ってきた。
「謝ることじゃないわ。」
「だって。その…。今朝のだって…。」
そこまでいうと、カリンちゃんは悲しそうな表情を浮かべた。
「二人で出来ることは二人でやりましょう?」
私は言葉を選びながら、会話を続ける。
「…。」
カリンちゃんは、黙ってしまった。
しかし、私は言葉を続けることにした。
「例えば、明日からは私が号令をかけて、カリンちゃんは他の仕事を担当するのはどうかしら?」
私は、ここで思い切った提案をする。
切り出すには、今、ここしかない。
そう思ったからだ。
カリンちゃんは、驚いたような顔をした。
「そんな…。私が何もしないなんて…。」
「それは違うわ。クラス委員の仕事は号令だけじゃないの。カリンちゃんが他の仕事をすることも大事なのよ?」
私は、できるだけ明るい声で言った。
カリンちゃんはどこか困惑した様子だ。
返事はない。
「カリンちゃん。クラス委員は、二人なんだから。お互いができるところを助け合うことがいいと思うわよ?」
「…。」
カリンちゃんは、黙ってしまった。
じっと、何かを考えているような感じだ。
彼女は心底、人前での活動が嫌なのだろう。
しかし、人に仕事を押し付けることも、嫌な性格なのかもしれない。
あるいは、クラスの他の生徒からの目線を気にしているのかもしれない。
なぜか、私だけがいつもホームルームの進行役をしている。
そんな噂が立つのが嫌だとか?
そういった、彼女のプライドもあるのかもしれない。
実質、クラス委員の仕事なんて、ホームルームの進行くらいなのだから。
しかし、結局のところ、カリンちゃんがホームルームの進行役をすることは不可能だ。
カリンちゃんは、私の提案を飲むだろう、と思った。
「…。桔梗さん。本当にごめんなさい。」
「カリンちゃん、謝ることなんてないのよ?」
「ありがとうございます、桔梗さん」
どこか気が楽になったのか、カリンちゃんはそう言った。
一方で、仕事を押しつける罪悪感といったものがごちゃ混ぜになっている、そんな雰囲気だ。
「いいえ、こちらこそ。これからもよろしくね。カリンちゃん。」
私は、社交儀礼な言葉を言った。
その後も、私とカリンちゃんは黙々と仕事を続けた。
でも、空気が少し変わった気がした。
ちょっとだけ、彼女の心の内に触れることができたような。
そんな気がした。
全ての仕事を終えて、私たちは教室を出ることになった。
「じゃあ、明日ね。カリンちゃん。」
私は、優しく微笑んだ。
「はい。明日も、よろしくお願いします。」
カリンちゃんも、小さく微笑み返した。
カリンちゃんと別れた私は、手芸部の部室へ向かった。
部室のドアを開けると、ハナちゃんが刺繍を編んでいた。
「アイリちゃん!」
ドアを開ける音で気が付いたようだ。
ハナちゃんがこちらを見て、そう言った。
ニコニコとした表情を浮かべている。
ハナちゃんの隣には、既に私の刺繍や道具が置かれていた。
「ハナちゃん。いつも、準備をさせてごめんね。」
「うん、大丈夫だよ!だって、アイリちゃん、クラス委員だもん。しょうがないよ!」
「そうかしら?」
私はそう言いながら、席に着いた。
「カリンちゃんとはどうなったの?」
ハナちゃんが聞いてきた。
「さっき、ちょっとだけ話をしたの。」
「へっー!それでカリンちゃんは?」
ハナちゃんの目に、純粋な心配の色が浮かんでいる。
「ええ、少しずつだけど…」
それから、私は放課後のことをハナちゃんに話し始めた。
「そうなんだ。でも、カリンちゃんは頑張ったんだね」
ハナちゃんは、真剣な表情で私の話を聞いていた。
彼女の目には、カリンちゃんへの心配と同時に、安堵の色も浮かんでいる。
「ええ。でも、まだまだこれからよ」
私は、カリンちゃんの様子を思い出しながら、これからどうすればいいか考えていた。
「アイリちゃんならきっと大丈夫だよ!」
ハナちゃんの明るい声が、私の思考を中断させた。
彼女の無邪気な信頼に、私は少し難しい気持ちになった。
「そうね。頑張るわ」
私は微笑みながら答えた。
そして、刺繍を始める。
針を動かしながら、今日一日のことを思い返す。
カリンちゃんのこと、クラス委員の仕事のこと。
そして、これから。
私の頭の中では、様々な思考が巡っていた。
一方で、私の手は自動的に針を動かしていた。
静かな部室の中で、私たちは黙々と刺繍を続けた。
窓からは夕暮れの光が差し込み、針を動かす音だけが響いている。
「よし、ここまで出来た!」
ハナちゃんの声で、私は我に返った。
彼女は出来上がった刺繍を嬉しそうに掲げている。
「綺麗ね、ハナちゃん」
私は穏やかに笑いかけた。
ハナちゃんの無邪気な喜びを見ながら、私は自分の刺繍を見つめた。
赤いバラの模様。
まだ完成には程遠い。
でも、焦る必要はない。
ゆっくりと、確実に。
私とカリンちゃんの関係も、この刺繍と同じように、少しずつ形になっていくのだろう。
部室の窓から見える夕焼け空を眺めながら、私は微笑んでいた。
次の日。
私は、昨日と同じ時間に学校へ来ていた。
すると、もう先にカリンちゃんがいた。
「おはようございます。」
「カリンちゃん、おはよう。」
私はカリンちゃんの方へ微笑みながら、あいさつをした。
彼女からは、真面目さといえばいいのだろうか?
まだ他人行儀な感じが伺えた。
「ホームルームの進行をお願いね?」
「はい。」
私とカリンちゃんの会話は、それだけだった。
私がそう言って、自席に近づいていると。
カリンちゃんは、教室から出て行った。
私もそれを引き留めるようなこともしない。
学校に早く来たのに、深い意味はないのだ。
もちろん、クラス委員の仕事とも関係ない。
しいて言えば、カリンちゃんが何時に来るのか気になったからだ。
目的は果たされた。
そう思った私は、学校へ持ち込んでいる本を鞄から取り出した。
その本は、最近読み始めた心理学の入門書だった。
人間の行動や思考のパターンについて書かれていた。
ページをめくりながら、ふと、私は窓の外を見た。
朝日が校庭を明るく照らし始めていた。
まだ早い時間だが、運動部の生徒たちが朝練習を始めているのが見えた。
私は、本の内容と目の前の光景を重ね合わせていた。
人々の行動パターン、集団の中での個人の振る舞い方。
それらが、この小さな学校という社会の中でどのように現れているのか。
特に気になったのは、「同調性バイアス」という内容だった。
人は無意識のうちに周囲の意見や行動に合わせようとする傾向がある、というものだ。
ふと、カリンちゃんのことを考えた。
彼女は、このクラスの中で孤立している。
ということは、同調性がないということだろうか?
つまりバイアスのない、自由な存在?
だとすれば、私がカリンちゃんとクラス委員として一緒に活動していくと…
彼女は、同調性バイアスで変わっていくのだろうか。
そんなことを考えながら、私は読書を続ける。
やがて、教室に生徒たちが徐々に集まり始めていた。
たぶん、そろそろ、ヒナコちゃんとハナちゃんが教室に来るだろう、と思った。
賑やかになっていく教室の中で、私は本を読み進めていた。
「アイリちゃん!」
ハナちゃんの声が聞こえた。
私は本を閉じた。
「おはよう、ハナちゃん」
私は優しく微笑みながら答えた。
ハナちゃんの元気な声は、いつも周囲の雰囲気に活気をもたらす。
それからなんということもない、朝の時間が過ぎていった。
教室には徐々に生徒たちが集まり始め、ガヤガヤとした喧騒が広がっていく。
やがて、ヒナコちゃんも私の席の周辺に来て、とりとめのない話をする。
「おはよう、アイリ」
ヒナコちゃんの声には、いつもの凛とした響きがあった。
「おはよう、ヒナコちゃん」
私は穏やかに返事をした。
三人で話をしていると、日々の些細な出来事が次々と話題に上がる。
ハナちゃんの明るい笑い声、ヒナコちゃんの的確なツッコミ。
私はその二人の会話に聞いていた。
そして、チャイムが鳴った。
いつものようにヒナコちゃんとハナちゃんというメンバーで会話をしていた私たちは、授業に備える。
「またな、アイリ」
「アイリちゃん、クラス委員がんばってー」
能天気な様子のハナちゃんと、凛々しいヒナコちゃんへ手を振る。
二人は自席へと戻っていった。
さて、これから朝のホームルーム。
今日は、カリンちゃんが司会進行をする番だ。
私は、いつもの席に座りながら、カリンちゃんの様子を観察していた。
カリンちゃんは、少し緊張した様子だった。
彼女は、ホームルームの進行を書いたファイルを握りしめ、ゆっくりと席から立ち上がった。
「起立」
カリンちゃんの声が、教室に響いた。
その声は小さい。
彼女の号令で、一部のクラスメイトたちが立ち上がる。
というのは、カリンちゃんの声が小さすぎて、後ろの方の生徒たちには聞こえなかったらしい。
クラス全体で立つタイミングがずれる。
それは、まるで不揃いな足音のような、疎らな音を生んだ。
教室全体に、何か失敗してしまったような空気が漂う。
しかし、カリンちゃんは必死に次の言葉を発しようとしている。
彼女の目は前方を見つめたまま、周囲の状況を把握する余裕はないようだ。
おそらく、今の彼女の中では、何が起こっているのか理解できていないのだろう。
ただ機械的に、次の言葉を発そうとしているだけに見える。
「…礼」
カリンちゃんの声は、さらに小さくなっていた。
本来なら、教室の生徒全員が同じタイミングで礼をしなければならない。
しかし、カリンちゃんの声が聞こえたわずかな生徒だけが礼をしている。
他の生徒たちは、周囲の様子を見て適当に合わせたり、まったく無視したりと、反応は様々だ。
担任の先生が、困ったような表情を浮かべている。
たぶん、この場面での最善の策は、もう一度大きな声で「礼」という号令をかけ直すことだろう。
しかし、完全にパニックに陥っているカリンちゃんには、そんな余裕はない。
「ち、ちち。ちゃ…着…着席」
カリンちゃんの声は、もはやほとんど聞こえないほど小さくなっていた。
そして、耳を澄まして聞いている私には、彼女が吃音であることが分かった。
教室内はざわついており、カリンちゃんの声など誰も聞いていないようだった。
私は、カリンちゃんの様子を見つめていた。
彼女の表情は完全にパニックに陥っている。
今の彼女に冷静な判断を期待するのは難しいだろう。
「みなさん、静かに。藤原さん、もう一度お願いできるかな?」
先生へカリンちゃんへ優しく声を掛ける。
その穏やかな声に、教室内に静けさが戻った。
もっとも先生から声を掛けられているカリンちゃんは、浅い呼吸を繰り返すだけで、返事をする余裕さえないようだった。
「あっ、じゃあ。桔梗さん。代わりにお願いしてもいいかな?」
先生の視線が私に向けられる。
私は一瞬、躊躇した。
カリンちゃんの気持ちを考えると、代わりに号令をかけることで彼女を傷つけてしまうのではないかと心配になった。
しかし、このまま放置することもできない。
「…はい。分かりました。」
私は担任の教師に従うことにした。
立ち上がりながら、カリンちゃんの方をちらりと見る。彼女は、まだ放心状態のようだった。
「起立」
教室の生徒が、私の声に従って一斉に立ち上がる。
立ったままのカリンちゃんはそのままだ。
「礼」
先生に向かってお辞儀をする。
カリンちゃんも私の号令に従っていた。
たぶん、パニック状態である彼女が無意識に行動している、と私は思った。
「着席」
私がそう号令を掛けると。
カリンちゃんを含んだクラスの全員が、自席に着いた。
私としては、これは難しい状況だ、と思った。
もしかしたら、繊細なカリンちゃんの心を傷つけてしまったかもしれない、と思った。
ふと、カリンちゃんを見る。
放心した様子で、じっと席についているカリンちゃんが見えた。
もはや、今の彼女には考える余裕すらないようだ。
ホームルームの残りの時間、私が進行をしていた。
正直、適当にやっていたこともあったが、特に問題もなくホームルームは終わった。
ホームルームが終わり、罰の悪そうな様子で自席にいるカリンちゃんが見えた。
そして、教室の先生が入れ替わり、1時間目の授業が始まる。
数学の先生が教室に入ってきた。
しかし、私には、カリンちゃんのことが離れなかった。
授業中、何度か後ろを振り返ってみた。
カリンちゃんは、うつむいたまま動かない。
教科書を開いているわけでもなく、ただぼんやりと机を見つめている。
私は、何かできることはないかと考えていた。
でも、今はまだ何もできない。
授業が終わり、休み時間になった。
私は、声をかけようか迷った。
しかし、なんて声を掛けるのが最適なのだろうか?
今は何も言わないという選択肢もある。
そんなことを思っていると、ヒナコちゃんが私を見ていることに気がついた。
ヒナコちゃんのほうを見ると、目が合った。
すると、こちらを見ていたヒナコちゃんが、目配せをしてきた。
カリンちゃんの席の方へとちらりと動き、そしてまた私に戻る。
『カリンちゃんの方へ行け』とヒナコちゃんは私に言っているのだ。
私は、ヒナコちゃんに従うことにした。
自席から立った私は、さりげなくカリンちゃんの席に近づいた。
「カリンちゃん」
私は、優しく声をかけた。
「あっ、あの。桔梗さん。朝は…。ごめんなさい。」
カリンちゃんの表情は暗い。
本当に悪いと思っているようだ。
「カリンちゃん、そんなに謝らなくていいわ。」
私は、できるだけ優しく声を掛けた。
カリンちゃんは暗い。
「あの。…でも。…こんなことも…。」
カリンちゃんは、ポツリポツリという感じで話している。
その様子からは、自分への失望が垣間見える。
「何も…できなくて…。」
そこまで言って、カリンちゃんの声が途切れた。
彼女が話しているうちに、自分の感情が高ぶってきたみたいだった。
その感情とは、悲しみの感情だ。
「失敗は誰でもあるものよ。」
私は、彼女を傷つけないように慎重に言葉を選ぶ。
「ごめんなさい。」
カリンちゃんの顔が歪んでいた。
涙が出そうだ。
「そんなこと言わないで。人それぞれ、できることは違うわ。それに、カリンちゃんは頑張ったじゃない。」
私の慰めに、カリンちゃんは黙った。
彼女は俯いたままだ。
たぶん、泣きそうになっている気持ちでいっぱいなのだろう。
私はどうすればいいのかと、考えていると。
その時、チャイムが鳴った。
次の授業が始まる合図だ。
「また後で話しましょう。」
私はそう言って、自分の席に戻った。
席に着きながら、ヒナコちゃんの方を見ると、彼女は小さく頷いてくれた。
授業が始まり、先生が教室に入ってきた。
私は、時々後ろを振り返ってカリンちゃんの様子を確認した。
カリンちゃんは、少しずつだが、授業に集中し始めているようだった。
私は、カリンちゃんのことを考えながら、ノートを取っていた。
これからどうすればいいのだろうか。
授業が進む中、私の頭の中は、カリンちゃんのことでいっぱいだった。
この状況を、どのように進めて行けばいいのだろうか。
私には、まだその答えが見えてこなかった。
その後の授業中。
私はカリンちゃんと話すことはなかった。
彼女と何を話せばいいのか、分からない。
何よりも、カリンちゃんが誰とも話したくなさそうにしていた、ということもあった。
そっとしておこう。
そういう判断を下した。
そして、昼休みになった。
いつものように、ハナちゃんとヒナコちゃんと一緒にお弁当を食べる準備をする。
そして、私はカリンちゃんの方をちらりと見た。
まだ少し元気がなさそうだった。
「ねえねえ、アイリちゃん」
ハナちゃんが、小声で私に話しかけてきた。
「何かしら?」
私は、ハナちゃんの方を見た。
「今朝のカリンちゃん、大丈夫かな?」
ハナちゃんの目に、心配の色が浮かんでいる。
「あれは辛かっただろうな。」
ヒナコちゃんも、真剣な表情で言った。
「何か…。もっとこう、お話ししたほうがいいのかな?」
「いや、ハナ。そっとしておくことも大事だ。」
「そーかな。」
「そうだ。」
二人が、二人なりの議論をしていた。
「私は、放課後に一緒に話をしようと思っているわ。」
「そうか。アイリがそうするなら、それがいいんだろうな。」
ヒナコちゃんは気を使っているようだった。
もちろん、ハナちゃんもだ。
朝のホームルームから始まったカリンちゃんの問題。
それはある意味で、クラス委員である私とカリンちゃんの問題でもあるのだ。
たしかに、気を使ってくるのは自然な流れなのかもしれない。
昼食を終え、午後の授業が始まった。
私は、授業を聞きながらも、時々カリンちゃんの方を見ていた。
彼女は、少しずつ普段の表情を取り戻しているように見えた。
ということは、放課後には、普段通りに話が出来そうだ、と私は思った。
放課後。
私とカリンちゃんは、クラス委員の仕事をする。
黒板を消したり、机を整頓したりという簡単なものだ。
ハナちゃんやヒナコちゃんを筆頭とした生徒たちがいなくなった教室。
その静かな教室の中で、私はカリンちゃんと二人で作業を進めていく。
黒板を書き換えた私とカリンちゃんは、机の位置を整頓することになった。
ちなみにそれまでの間に、私とカリンちゃんは朝のことについて、特に話をしていない。
触れるのが難しい話題というところだ。
「カリンちゃん。」
私は、さりげなく話しかけた。
「はい、なんでしょうか?桔梗さん。」
「机の位置を綺麗に整列させましょう?」
「はい。…でも、どうしましょう?」
カリンちゃんは、私に聞いてきた。
どうやら、机の位置をどこに合わせるのか、そういう意味らしい。
「カリンちゃん。一番前の机に合わせましょう。」
「はい。」
どこか表情の変化に乏しいカリンちゃんは、まるでロボットのようだ。
カリンちゃんは私に従って作業を始めた。
私たちは黙々と机を動かし始めた。
カリンちゃんの動きは慎重で、まるで机を壊してしまうのではないかと恐れているかのようだった。
その姿を見ていると、今朝の出来事が彼女の心に深く刻まれているのだろうと感じた。
とはいえ、作業自体は誰でもできる。
机を引く音。
足音。
淡々と作業が進んでいく。
そのとき、カリンちゃんがある机を重そうにしていた。
「あっ、手伝うわ。」
「えっ?いえ…。」
カリンちゃんは、そう言って、やんわりと断ろうとしてきた。
しかし、私は、それを無視して手伝うように近づいた。
私は、カリンちゃんの隣で机の前に立った。
そして、ちょっとだけ机を確認で動かそうとする。
「やっぱり重いわ、この机。」
一人だと、引きずることすら難しい。
一体、机の中に何を入れているのだろうか?
もちろん、各生徒の持ち物なので、確認することはない。
「一緒に動かしましょう?」
「はい。」
カリンちゃんは、なにか言いたげだった。
しかし、私と一緒に机を動かし始めた。
そのまま、カリンちゃんと私はうまく机を整列させた。
「良かったわね。これを運べて。」
「いえ、その。すいません。桔梗さん。」
カリンちゃんは、申し訳ないように謝ってきた。
「謝ることじゃないわ。」
「だって。その…。今朝のだって…。」
そこまでいうと、カリンちゃんは悲しそうな表情を浮かべた。
「二人で出来ることは二人でやりましょう?」
私は言葉を選びながら、会話を続ける。
「…。」
カリンちゃんは、黙ってしまった。
しかし、私は言葉を続けることにした。
「例えば、明日からは私が号令をかけて、カリンちゃんは他の仕事を担当するのはどうかしら?」
私は、ここで思い切った提案をする。
切り出すには、今、ここしかない。
そう思ったからだ。
カリンちゃんは、驚いたような顔をした。
「そんな…。私が何もしないなんて…。」
「それは違うわ。クラス委員の仕事は号令だけじゃないの。カリンちゃんが他の仕事をすることも大事なのよ?」
私は、できるだけ明るい声で言った。
カリンちゃんはどこか困惑した様子だ。
返事はない。
「カリンちゃん。クラス委員は、二人なんだから。お互いができるところを助け合うことがいいと思うわよ?」
「…。」
カリンちゃんは、黙ってしまった。
じっと、何かを考えているような感じだ。
彼女は心底、人前での活動が嫌なのだろう。
しかし、人に仕事を押し付けることも、嫌な性格なのかもしれない。
あるいは、クラスの他の生徒からの目線を気にしているのかもしれない。
なぜか、私だけがいつもホームルームの進行役をしている。
そんな噂が立つのが嫌だとか?
そういった、彼女のプライドもあるのかもしれない。
実質、クラス委員の仕事なんて、ホームルームの進行くらいなのだから。
しかし、結局のところ、カリンちゃんがホームルームの進行役をすることは不可能だ。
カリンちゃんは、私の提案を飲むだろう、と思った。
「…。桔梗さん。本当にごめんなさい。」
「カリンちゃん、謝ることなんてないのよ?」
「ありがとうございます、桔梗さん」
どこか気が楽になったのか、カリンちゃんはそう言った。
一方で、仕事を押しつける罪悪感といったものがごちゃ混ぜになっている、そんな雰囲気だ。
「いいえ、こちらこそ。これからもよろしくね。カリンちゃん。」
私は、社交儀礼な言葉を言った。
その後も、私とカリンちゃんは黙々と仕事を続けた。
でも、空気が少し変わった気がした。
ちょっとだけ、彼女の心の内に触れることができたような。
そんな気がした。
全ての仕事を終えて、私たちは教室を出ることになった。
「じゃあ、明日ね。カリンちゃん。」
私は、優しく微笑んだ。
「はい。明日も、よろしくお願いします。」
カリンちゃんも、小さく微笑み返した。
カリンちゃんと別れた私は、手芸部の部室へ向かった。
部室のドアを開けると、ハナちゃんが刺繍を編んでいた。
「アイリちゃん!」
ドアを開ける音で気が付いたようだ。
ハナちゃんがこちらを見て、そう言った。
ニコニコとした表情を浮かべている。
ハナちゃんの隣には、既に私の刺繍や道具が置かれていた。
「ハナちゃん。いつも、準備をさせてごめんね。」
「うん、大丈夫だよ!だって、アイリちゃん、クラス委員だもん。しょうがないよ!」
「そうかしら?」
私はそう言いながら、席に着いた。
「カリンちゃんとはどうなったの?」
ハナちゃんが聞いてきた。
「さっき、ちょっとだけ話をしたの。」
「へっー!それでカリンちゃんは?」
ハナちゃんの目に、純粋な心配の色が浮かんでいる。
「ええ、少しずつだけど…」
それから、私は放課後のことをハナちゃんに話し始めた。
「そうなんだ。でも、カリンちゃんは頑張ったんだね」
ハナちゃんは、真剣な表情で私の話を聞いていた。
彼女の目には、カリンちゃんへの心配と同時に、安堵の色も浮かんでいる。
「ええ。でも、まだまだこれからよ」
私は、カリンちゃんの様子を思い出しながら、これからどうすればいいか考えていた。
「アイリちゃんならきっと大丈夫だよ!」
ハナちゃんの明るい声が、私の思考を中断させた。
彼女の無邪気な信頼に、私は少し難しい気持ちになった。
「そうね。頑張るわ」
私は微笑みながら答えた。
そして、刺繍を始める。
針を動かしながら、今日一日のことを思い返す。
カリンちゃんのこと、クラス委員の仕事のこと。
そして、これから。
私の頭の中では、様々な思考が巡っていた。
一方で、私の手は自動的に針を動かしていた。
静かな部室の中で、私たちは黙々と刺繍を続けた。
窓からは夕暮れの光が差し込み、針を動かす音だけが響いている。
「よし、ここまで出来た!」
ハナちゃんの声で、私は我に返った。
彼女は出来上がった刺繍を嬉しそうに掲げている。
「綺麗ね、ハナちゃん」
私は穏やかに笑いかけた。
ハナちゃんの無邪気な喜びを見ながら、私は自分の刺繍を見つめた。
赤いバラの模様。
まだ完成には程遠い。
でも、焦る必要はない。
ゆっくりと、確実に。
私とカリンちゃんの関係も、この刺繍と同じように、少しずつ形になっていくのだろう。
部室の窓から見える夕焼け空を眺めながら、私は微笑んでいた。