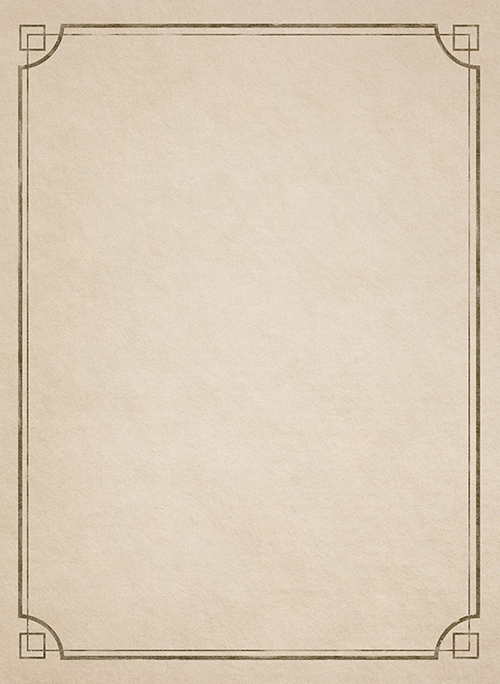第十一話
クラス委員として藤原カリンと活動を始めてから、数週間が経過した。
私とカリンちゃんは、日々、一緒にクラス委員としての仕事を行っていた。
ホームルームの進行は私が行い、放課後の雑用は一緒に行う。
時折、先生から渡される臨時の仕事もある。
とはいえ、それらは先生から見ても、私たちが行う事が出来る雑用を選んでいるみたいで。
そのため、私とカリンちゃんは特に問題もなく、クラス委員を全うしていた。
そして、その活動を行っていく中で、私は少しずつカリンちゃんと打ち解けてきたと思っていた。
その時までは。
その日の朝、いつものように教室に入ると、カリンちゃんの姿が目に入った。
「おはよう、カリンちゃん」
私はいつも通り、柔らかく微笑みかけた。
しかし、カリンちゃんの反応は、これまでとは全く違うものだった。
彼女は一瞬だけ冷たい眼差しを向けると、すぐに目をそらし、完全に私を無視した。
私は一瞬、自分の目を疑った。
カリンちゃんが、私の挨拶を無視するなんて。
これまで、どんなに気まずい雰囲気の時でも、必ず返事をしてくれていたのに。
「カリンちゃん?どうかしたの?」
私は、少し心配になって声をかけた。
しかし、カリンちゃんは相変わらず私の方を見ようともしない。
私は困惑しながらも、自分の席に向かった。
座りながら、ふとカリンちゃんの方を見ると、彼女はスマホを見ているふりをしているようだった。
(何か、私が悪いことしたのかな…)
私は、自問自答を始めた。
この数週間、私たちの関係は順調に進んでいたはずだ。
少なくとも、私はそう思っていた。
でも、今朝のカリンちゃんの態度は、まるで別人のようだった。
チャイムが鳴り、授業が始まった。
私は、授業に集中しようとしたが、どうしてもカリンちゃんのことが気になって仕方がなかった。
時折、後ろを振り返ってカリンちゃんの様子を確認しようとした。
でも、彼女は一度も私の方を見ようとしなかった。
むしろ、私が振り返るたびに、意図的に顔を背けているように見えた。
この態度の急変。
私には、そのカリンちゃんの挙動を完全に理解できなかった。
昼休みになり、いつものようにハナちゃんとヒナコちゃんが私の席に集まってきた。
「アイリちゃん、お昼ごはん一緒に食べよう!」
ハナちゃんが、いつもの明るい声で言った。
「ええ、そうね」
私は、できるだけ普通の声で答えた。
しかし、その声はどこか不自然だったのかもしれない。
「どうした、アイリ?何かあったのか?」
ヒナコちゃんは、鋭い。
「ううん、何でもないわ」
私は、なんでもないように笑みを浮かべる。
しかし、二人は、私の様子がいつもと違うことに気づいたようだった。
「アイリちゃん、本当に大丈夫?」
ハナちゃんが、優しく尋ねてきた。
その声には、純粋な心配から聞いているようだ。
「ええ、大丈夫よ。」
私は、できるだけ自然な笑みを浮かべている。
「アイリ、何か隠してるだろ。」
しかし、ヒナコちゃんの鋭い目が、私を見抜いているようだった。
「そんなことないわ。」
「…カリンとなにかあったのか?」
ヒナコちゃんの洞察力は鋭い。
「えっ、カリンちゃんと何かあったの?」
ハナちゃんが、驚いた様子で聞いてきた。
私は黙ったまま、お弁当箱を見つめた。
何と答えればいいのか、言葉が見つからない。
「アイリ、話してくれてもいいんだぞ」
ヒナコちゃんの声は、いつもより柔らかかった。
「そうだよ、アイリちゃん。私たち、友達でしょ?」
ハナちゃんも、優しく話しかけてくれる。
「実は…」
私は、ゆっくりと口を開いた。
「今朝、カリンちゃんが私を無視したの。」
そして、私は事実を述べる。
「えっ?どういうこと?」
ハナちゃんが、驚いた様子で聞いてきた。
「おはようって声をかけたのに、カリンちゃんは冷たい目で私を見て、それから完全に無視されているの。」
私は、朝のことを思い出しながら話した。
「急に?理由もなく?」
ヒナコちゃんが、聞いてきた。
その様子は、少しでも情報を得ようとしている雰囲気だ。
「ええ。私にも分からないの。昨日までは普通だったのに…」
私は思い出しながら、事実を述べる。
「アイリちゃん…」
ハナちゃんが、私の手を握ってくれた。
そのハナちゃんの優しさが手先から伝わってきた。
「何か、誤解があったのかもしれないな。」
ヒナコちゃんが、私の証言から冷静に分析しようとしているみたいだ。
「でも、私には何も思い当たることがないの。」
「アイリちゃん、カリンちゃんに直接聞いてみたら?」
ハナちゃんが提案してきた。
「そうだな。話し合えば、何か分かるかもしれない。」
ヒナコちゃんも同意した。
私は二人の言葉に頷いた。
でも、カリンちゃんは、私の話を聞いてくれるだろうか。
「ありがとう、二人とも」
私は、感謝の気持ちを込めて言った。
二人がいてくれて、本当に良かった、と。
その後も、私たちは普段通りおしゃべりを続けた。
そして、昼休みが終わり、午後の授業が始まった。
私は、カリンちゃんと話をする機会を探していた。
休み時間に見る彼女の姿。
その姿は、これまでと変わらないように見えた。
でも、何かが決定的に違っていた。
それは何とも言えないが、憎しみや悲しみといった負の雰囲気を感じた。
そして、カリンちゃんは、相変わらず私を避けているようだった。
休み時間が終わり、授業が始まる。
でも、私の心の中では、カリンちゃんのことが離れない。
そう、これは繊細な出来事なのだ。
慎重に事を運ばなければならないことなのだ。
私は思考の渦に囚われていると。
いつの間にか、時間が過ぎ去る。
そして、最後の授業が終わった。
となれば、放課後のクラス委員の仕事の時間だ。
私は少し緊張しながら、カリンちゃんの方に向かった。
「カリンちゃん、今日の仕事を始めましょうか」
私は、できるだけ明るく声をかけた。
「…」
カリンちゃんは、無言で立ち上がった。
私たちは黙々と作業を始めた。
黒板を消し、机を整頓する。
いつもなら、ちょっとした会話を交わしながら進める作業だった。
「ねえ、カリンちゃん。この机の配置、少し変えてみない?」
私は、気まずい沈黙を破ろうと提案してみた。
「そんなの意味ないでしょ。」
カリンちゃんの声は冷たい。
それから感じるのは拒絶だ。
そして、その根底にあるのは怒り、憎しみ。
「え?でも…」
「一人でやればいいんじゃないですか?」
カリンちゃんは、私の言葉を遮るように言った。
私は、一瞬言葉を失った。
こんな風にカリンちゃんに言われたのは初めてだった。
「ごめんね、カリンちゃん。私、言い方が悪かったみたい。」
私は、できるだけ優しく謝った。
しかし、カリンちゃんは何も答えず、一人で黙々と作業を続けていた。
呆気にとられる私だったが、カリンちゃんから少し距離を置いて作業をする。
どうすればいいのか?
そう考えていると、席の整頓、黒板の書き直しといった日課は終わる。
その間、私とカリンちゃんの間に会話はない。
そんな状況で仕事を終える。
「カリンちゃん。ごめんなさい。」
私は、別れ際、カリンちゃんへそう言った。
彼女はその言葉を無視して、立ち去っていく。
取り付く島もないもない、とは、このことだ。
私はカリンちゃんに続いて、一人教室を後にした。
手芸部の部室へ向かう。
部室はすでに空いていた。
ドアを開けると、ハナちゃんが笑顔で迎えてくれた。
「アイリちゃん、お疲れ様!」
ハナちゃんの明るい声が、少し痛々しく聞こえた。
「ありがとう、ハナちゃん」
私は、先ほどのこともあったが、そう答えた。
それについて気にしないかのように振る舞うことにした。
「アイリちゃん、大丈夫?」
ハナちゃんは、私に心配そうに尋ねてきた。
やはり、私の様子がいつもと違うからだろうか?
ハナちゃんの無邪気な優しさだ。
「うん、大丈夫よ。ちょっと疲れてるだけ。」
私は、ハナちゃんに安心させるかのように笑顔を見せる。
その意味を分かったのか、そうでないのか。
ハナちゃんは、それ以上、私に問いかけてこなかった。
私はハナちゃんの横で、いつものように刺繍を始めることにした。
準備を行った後、刺繍作業を始める。
赤いバラの刺繍を作成しながら、私は今日一日のことを思い返していた。
カリンちゃんの冷たい態度。
理由も分からず拒絶される。
私は思案しながらも、針を動かす。
人間関係も、この刺繍作業と同じようなものなら…。
私は心底、そう思った。
「アイリちゃん、赤いバラの模様、綺麗に出来てるね!」
気が付くと、ハナちゃんが、横から私の作品を見ていた。
「ありがとう、ハナちゃん。」
私は、微かに笑顔を作った。
でも、その笑顔が上手く作れているのか、自信がなかった。
「ねえ、アイリちゃん。カリンちゃんと話せた?」
ハナちゃんが、少し遠慮がちに聞いてきた。
「ううんと。」
私は、なんて言えばいいのかと思った。
ハナちゃんは、こちらをじっと見ていた。
「私、カリンちゃんと、うまく話せなかったわ。」
「そっか…。」
ハナちゃんは、悲しそうにそういった。
それから、ハナちゃんは何も言ってこなかった。
しばらくの間、私とハナちゃんは、無言で刺繍の作業を続けた。
「アイリちゃん。」
ハナちゃんが、突然声をかけてきた。
「何?」
「明日、もう一度カリンちゃんと話してみたら?」
ハナちゃんなりに気を使った言葉だ。
「…そうね。もう一度、試してみるわ。」
私は、そう答える。
「大丈夫だよ。そのうち、きっとカリンちゃんも分かってくれるよ。たぶん…。」
ハナちゃんは、まるで自分に言い聞かせているかのように、そう言った。
私は、小さく頷いた。
しばらくしていると、下校のチャイムが鳴る。
私たちは、手芸部の活動を終える。
そして、学校を出た。
天気は晴れだ。
夕暮れの空が、オレンジ色に染まっている。
私とハナちゃんは、校舎を出る。
すると、校門でヒナコちゃんらしき人影が見えた。
「アイリちゃん、ヒナコちゃんが待っているよ!」
そういって、ハナちゃんは私の手を取り、ヒナコちゃんへ走っていく。
「ハナ。アイリ。待っていたぞ。」
近づくと、やはりヒナコちゃんが、校門の前で私たちを待ってくれていた。
いつもの集合スタイルだ。
だから、今日もいつものメンバーが揃った。
私たちは並んで歩き始める。
最初は誰も何も言わなかった。
でも、この沈黙がちょっといつもとは違うモノを感じさせた。
「ねえ、アイリちゃん。」
ハナちゃんが、少し遠慮がちに話しかけてきた。
「何?」
「カリンちゃんのこと、どうしてだと思う?」
その質問に、私は足を止めそうになった。
しかし、私の歩みは止まらなかった。
その代わりに思考が始まっていた。
「そうね…」
私は言葉を選びながら、ゆっくりと話し始めた。
「カリンちゃんには、何か理由があるのかもしれないわ。でも、私には分からない。」
「そっか…」
ハナちゃんの声には、そこか悲しさの感情があった。
「アイリ、お前が悪いわけじゃないんだぞ?」
ヒナコちゃんが、真剣な表情で言った。
「分かってる。でも…」
私の言葉はそこで途切れた。
「アイリちゃん、きっと何かの間違いだよ。カリンちゃんも、本当はアイリちゃんのこと嫌いじゃないと思うよ!」
ハナちゃんが、一生懸命励ましてくれる。
「そうだな。やっぱり、何か勘違いしてるんじゃないか?」
ヒナコちゃんも、冷静に分析しようとしていた。
私は二人の言葉に頷きながら、カリンちゃんのことを考えていた。
「そうね。明日、もう一度カリンちゃんと話してみるわ」
私の言葉に、ハナちゃんとヒナコちゃんは安心したように笑顔を見せた。
「そうだよ!アイリちゃんなら、きっと上手くいくよ!」
「ああ、私たちも応援してるからな。」
二人の言葉に、私は少し勇気づけられた気がした。
そのまま歩いていると、いつもの別れ道に着いた。
「じゃあ、また明日ね」
私は二人に手を振った。
「うん、またね!」
「また明日な」
ハナちゃんとヒナコちゃんは、いつものように元気に別れの挨拶をした。
私は一人で家路につきながら、もう一度カリンちゃんのことを考えた。
明日こそは、きっと…。
そう自分に言い聞かせながら、私は家に向かった。
クラス委員として藤原カリンと活動を始めてから、数週間が経過した。
私とカリンちゃんは、日々、一緒にクラス委員としての仕事を行っていた。
ホームルームの進行は私が行い、放課後の雑用は一緒に行う。
時折、先生から渡される臨時の仕事もある。
とはいえ、それらは先生から見ても、私たちが行う事が出来る雑用を選んでいるみたいで。
そのため、私とカリンちゃんは特に問題もなく、クラス委員を全うしていた。
そして、その活動を行っていく中で、私は少しずつカリンちゃんと打ち解けてきたと思っていた。
その時までは。
その日の朝、いつものように教室に入ると、カリンちゃんの姿が目に入った。
「おはよう、カリンちゃん」
私はいつも通り、柔らかく微笑みかけた。
しかし、カリンちゃんの反応は、これまでとは全く違うものだった。
彼女は一瞬だけ冷たい眼差しを向けると、すぐに目をそらし、完全に私を無視した。
私は一瞬、自分の目を疑った。
カリンちゃんが、私の挨拶を無視するなんて。
これまで、どんなに気まずい雰囲気の時でも、必ず返事をしてくれていたのに。
「カリンちゃん?どうかしたの?」
私は、少し心配になって声をかけた。
しかし、カリンちゃんは相変わらず私の方を見ようともしない。
私は困惑しながらも、自分の席に向かった。
座りながら、ふとカリンちゃんの方を見ると、彼女はスマホを見ているふりをしているようだった。
(何か、私が悪いことしたのかな…)
私は、自問自答を始めた。
この数週間、私たちの関係は順調に進んでいたはずだ。
少なくとも、私はそう思っていた。
でも、今朝のカリンちゃんの態度は、まるで別人のようだった。
チャイムが鳴り、授業が始まった。
私は、授業に集中しようとしたが、どうしてもカリンちゃんのことが気になって仕方がなかった。
時折、後ろを振り返ってカリンちゃんの様子を確認しようとした。
でも、彼女は一度も私の方を見ようとしなかった。
むしろ、私が振り返るたびに、意図的に顔を背けているように見えた。
この態度の急変。
私には、そのカリンちゃんの挙動を完全に理解できなかった。
昼休みになり、いつものようにハナちゃんとヒナコちゃんが私の席に集まってきた。
「アイリちゃん、お昼ごはん一緒に食べよう!」
ハナちゃんが、いつもの明るい声で言った。
「ええ、そうね」
私は、できるだけ普通の声で答えた。
しかし、その声はどこか不自然だったのかもしれない。
「どうした、アイリ?何かあったのか?」
ヒナコちゃんは、鋭い。
「ううん、何でもないわ」
私は、なんでもないように笑みを浮かべる。
しかし、二人は、私の様子がいつもと違うことに気づいたようだった。
「アイリちゃん、本当に大丈夫?」
ハナちゃんが、優しく尋ねてきた。
その声には、純粋な心配から聞いているようだ。
「ええ、大丈夫よ。」
私は、できるだけ自然な笑みを浮かべている。
「アイリ、何か隠してるだろ。」
しかし、ヒナコちゃんの鋭い目が、私を見抜いているようだった。
「そんなことないわ。」
「…カリンとなにかあったのか?」
ヒナコちゃんの洞察力は鋭い。
「えっ、カリンちゃんと何かあったの?」
ハナちゃんが、驚いた様子で聞いてきた。
私は黙ったまま、お弁当箱を見つめた。
何と答えればいいのか、言葉が見つからない。
「アイリ、話してくれてもいいんだぞ」
ヒナコちゃんの声は、いつもより柔らかかった。
「そうだよ、アイリちゃん。私たち、友達でしょ?」
ハナちゃんも、優しく話しかけてくれる。
「実は…」
私は、ゆっくりと口を開いた。
「今朝、カリンちゃんが私を無視したの。」
そして、私は事実を述べる。
「えっ?どういうこと?」
ハナちゃんが、驚いた様子で聞いてきた。
「おはようって声をかけたのに、カリンちゃんは冷たい目で私を見て、それから完全に無視されているの。」
私は、朝のことを思い出しながら話した。
「急に?理由もなく?」
ヒナコちゃんが、聞いてきた。
その様子は、少しでも情報を得ようとしている雰囲気だ。
「ええ。私にも分からないの。昨日までは普通だったのに…」
私は思い出しながら、事実を述べる。
「アイリちゃん…」
ハナちゃんが、私の手を握ってくれた。
そのハナちゃんの優しさが手先から伝わってきた。
「何か、誤解があったのかもしれないな。」
ヒナコちゃんが、私の証言から冷静に分析しようとしているみたいだ。
「でも、私には何も思い当たることがないの。」
「アイリちゃん、カリンちゃんに直接聞いてみたら?」
ハナちゃんが提案してきた。
「そうだな。話し合えば、何か分かるかもしれない。」
ヒナコちゃんも同意した。
私は二人の言葉に頷いた。
でも、カリンちゃんは、私の話を聞いてくれるだろうか。
「ありがとう、二人とも」
私は、感謝の気持ちを込めて言った。
二人がいてくれて、本当に良かった、と。
その後も、私たちは普段通りおしゃべりを続けた。
そして、昼休みが終わり、午後の授業が始まった。
私は、カリンちゃんと話をする機会を探していた。
休み時間に見る彼女の姿。
その姿は、これまでと変わらないように見えた。
でも、何かが決定的に違っていた。
それは何とも言えないが、憎しみや悲しみといった負の雰囲気を感じた。
そして、カリンちゃんは、相変わらず私を避けているようだった。
休み時間が終わり、授業が始まる。
でも、私の心の中では、カリンちゃんのことが離れない。
そう、これは繊細な出来事なのだ。
慎重に事を運ばなければならないことなのだ。
私は思考の渦に囚われていると。
いつの間にか、時間が過ぎ去る。
そして、最後の授業が終わった。
となれば、放課後のクラス委員の仕事の時間だ。
私は少し緊張しながら、カリンちゃんの方に向かった。
「カリンちゃん、今日の仕事を始めましょうか」
私は、できるだけ明るく声をかけた。
「…」
カリンちゃんは、無言で立ち上がった。
私たちは黙々と作業を始めた。
黒板を消し、机を整頓する。
いつもなら、ちょっとした会話を交わしながら進める作業だった。
「ねえ、カリンちゃん。この机の配置、少し変えてみない?」
私は、気まずい沈黙を破ろうと提案してみた。
「そんなの意味ないでしょ。」
カリンちゃんの声は冷たい。
それから感じるのは拒絶だ。
そして、その根底にあるのは怒り、憎しみ。
「え?でも…」
「一人でやればいいんじゃないですか?」
カリンちゃんは、私の言葉を遮るように言った。
私は、一瞬言葉を失った。
こんな風にカリンちゃんに言われたのは初めてだった。
「ごめんね、カリンちゃん。私、言い方が悪かったみたい。」
私は、できるだけ優しく謝った。
しかし、カリンちゃんは何も答えず、一人で黙々と作業を続けていた。
呆気にとられる私だったが、カリンちゃんから少し距離を置いて作業をする。
どうすればいいのか?
そう考えていると、席の整頓、黒板の書き直しといった日課は終わる。
その間、私とカリンちゃんの間に会話はない。
そんな状況で仕事を終える。
「カリンちゃん。ごめんなさい。」
私は、別れ際、カリンちゃんへそう言った。
彼女はその言葉を無視して、立ち去っていく。
取り付く島もないもない、とは、このことだ。
私はカリンちゃんに続いて、一人教室を後にした。
手芸部の部室へ向かう。
部室はすでに空いていた。
ドアを開けると、ハナちゃんが笑顔で迎えてくれた。
「アイリちゃん、お疲れ様!」
ハナちゃんの明るい声が、少し痛々しく聞こえた。
「ありがとう、ハナちゃん」
私は、先ほどのこともあったが、そう答えた。
それについて気にしないかのように振る舞うことにした。
「アイリちゃん、大丈夫?」
ハナちゃんは、私に心配そうに尋ねてきた。
やはり、私の様子がいつもと違うからだろうか?
ハナちゃんの無邪気な優しさだ。
「うん、大丈夫よ。ちょっと疲れてるだけ。」
私は、ハナちゃんに安心させるかのように笑顔を見せる。
その意味を分かったのか、そうでないのか。
ハナちゃんは、それ以上、私に問いかけてこなかった。
私はハナちゃんの横で、いつものように刺繍を始めることにした。
準備を行った後、刺繍作業を始める。
赤いバラの刺繍を作成しながら、私は今日一日のことを思い返していた。
カリンちゃんの冷たい態度。
理由も分からず拒絶される。
私は思案しながらも、針を動かす。
人間関係も、この刺繍作業と同じようなものなら…。
私は心底、そう思った。
「アイリちゃん、赤いバラの模様、綺麗に出来てるね!」
気が付くと、ハナちゃんが、横から私の作品を見ていた。
「ありがとう、ハナちゃん。」
私は、微かに笑顔を作った。
でも、その笑顔が上手く作れているのか、自信がなかった。
「ねえ、アイリちゃん。カリンちゃんと話せた?」
ハナちゃんが、少し遠慮がちに聞いてきた。
「ううんと。」
私は、なんて言えばいいのかと思った。
ハナちゃんは、こちらをじっと見ていた。
「私、カリンちゃんと、うまく話せなかったわ。」
「そっか…。」
ハナちゃんは、悲しそうにそういった。
それから、ハナちゃんは何も言ってこなかった。
しばらくの間、私とハナちゃんは、無言で刺繍の作業を続けた。
「アイリちゃん。」
ハナちゃんが、突然声をかけてきた。
「何?」
「明日、もう一度カリンちゃんと話してみたら?」
ハナちゃんなりに気を使った言葉だ。
「…そうね。もう一度、試してみるわ。」
私は、そう答える。
「大丈夫だよ。そのうち、きっとカリンちゃんも分かってくれるよ。たぶん…。」
ハナちゃんは、まるで自分に言い聞かせているかのように、そう言った。
私は、小さく頷いた。
しばらくしていると、下校のチャイムが鳴る。
私たちは、手芸部の活動を終える。
そして、学校を出た。
天気は晴れだ。
夕暮れの空が、オレンジ色に染まっている。
私とハナちゃんは、校舎を出る。
すると、校門でヒナコちゃんらしき人影が見えた。
「アイリちゃん、ヒナコちゃんが待っているよ!」
そういって、ハナちゃんは私の手を取り、ヒナコちゃんへ走っていく。
「ハナ。アイリ。待っていたぞ。」
近づくと、やはりヒナコちゃんが、校門の前で私たちを待ってくれていた。
いつもの集合スタイルだ。
だから、今日もいつものメンバーが揃った。
私たちは並んで歩き始める。
最初は誰も何も言わなかった。
でも、この沈黙がちょっといつもとは違うモノを感じさせた。
「ねえ、アイリちゃん。」
ハナちゃんが、少し遠慮がちに話しかけてきた。
「何?」
「カリンちゃんのこと、どうしてだと思う?」
その質問に、私は足を止めそうになった。
しかし、私の歩みは止まらなかった。
その代わりに思考が始まっていた。
「そうね…」
私は言葉を選びながら、ゆっくりと話し始めた。
「カリンちゃんには、何か理由があるのかもしれないわ。でも、私には分からない。」
「そっか…」
ハナちゃんの声には、そこか悲しさの感情があった。
「アイリ、お前が悪いわけじゃないんだぞ?」
ヒナコちゃんが、真剣な表情で言った。
「分かってる。でも…」
私の言葉はそこで途切れた。
「アイリちゃん、きっと何かの間違いだよ。カリンちゃんも、本当はアイリちゃんのこと嫌いじゃないと思うよ!」
ハナちゃんが、一生懸命励ましてくれる。
「そうだな。やっぱり、何か勘違いしてるんじゃないか?」
ヒナコちゃんも、冷静に分析しようとしていた。
私は二人の言葉に頷きながら、カリンちゃんのことを考えていた。
「そうね。明日、もう一度カリンちゃんと話してみるわ」
私の言葉に、ハナちゃんとヒナコちゃんは安心したように笑顔を見せた。
「そうだよ!アイリちゃんなら、きっと上手くいくよ!」
「ああ、私たちも応援してるからな。」
二人の言葉に、私は少し勇気づけられた気がした。
そのまま歩いていると、いつもの別れ道に着いた。
「じゃあ、また明日ね」
私は二人に手を振った。
「うん、またね!」
「また明日な」
ハナちゃんとヒナコちゃんは、いつものように元気に別れの挨拶をした。
私は一人で家路につきながら、もう一度カリンちゃんのことを考えた。
明日こそは、きっと…。
そう自分に言い聞かせながら、私は家に向かった。