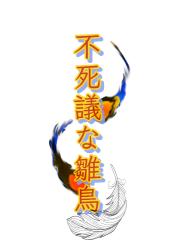* * *
夜の始まりを感じる5限終わり。傾いた陽光がキャンパスを照らす。紫とも橙ともつかない宵空。いつもは喧騒で包まれている大学も、この時間になると生徒が疎らに帰路につくのみだった。
僕もそんな生徒たちに混じり正門へ向かう。視界に入った桜の木は既に花を散らしている。もうすぐ春が終わろうとしていた。
「…もうそろそろ2ヶ月か」
こっちに越してきた月日を数えて、独りごつ。
マリーさんの元で働き始めて数週間。仕事には徐々に慣れてきたから、それはよかったと思う。不慣れが原因で迷惑をかけていたら立つ瀬がない。
連日働いてみてわかったことだが、「願いの叶う喫茶店」と噂になっている割にはお客さんは全く来ない。来たとしても、羊さんと歩夢。それ以外にお客さんは見た事がない。見つけにくいというのは本当なようだ。
ただ、働いていて気が紛れるのも確かだった。元来真面目な性格だったことが幸いもしている。
「…おーい!」
そんなことを考えながら正門を出ると、後ろから聞き馴染みのある声がした。
「やっぱり魁人だ」
「歩夢」
そういって軽い駆け足で近づいてきたのは歩夢だった。
「よっ」
「こんばんは」
「後ろ姿を見かけてさ。人違いだったらどうしようかと思ったよ」
「大学同じだけどなんだかんだ顔合わせないしね。その気持ちはわかるよ」
僕なら見かけたとしても顔を見るまで声はかけなかっただろう。知り合って間もない人ほど、服装や歩き姿だけで判断するのはなかなかに難しい。そういう葛藤を抱えながらも声をかけてくれたのは素直に嬉しい気持ちになった。
「歩夢も5限目まで授業受けてたんだ」
「あぁ、薬学部は5限に必修が入っててさ。…というかあれ?敬語は?」
「あー、今は店員じゃないし。馴れ馴れしかったかな?」
「そんなことない!というかそうやって切り分けてるの本当に真面目だな」
「普通じゃないかな」
「日本人みたいだぞ」
「いや、マリーさんと同じジョークやめてよ」
はははっと歩夢が笑う。新しく出会った人はこうして軽い冗談を言う人たちばかりだ。僕はそれにうまく返せているか疑問に思うときもあるが、彼らの反応を見るに問題はないのだろう。都会の人たちはみな社交的なんだなと思った。
「魁人はこの後なんか予定あるの?」
「今日もバイトかなぁ。マリーさんと一緒に買い出しを頼まれてるんだ」
「あ、ほんとに?俺も今日はバイトだから、終わったらMärchenに行くよ」
「いつもありがとうございます」
「ははっ、店員モードじゃん」
意図せず切り分けたのを笑いながら、一緒に行こうと誘われたのでそのまま駅まで歩く。
「そういえば聞いてなかったけどなんのバイトしてるの?」
「あー…ドライバーだよ」
「深夜の?タクシー?」
「まぁ…いや、魁人なら話してもいっか」
そう言って歩夢は言葉を続ける。
「俺、女の子をお客さんの元に届ける仕事してるんだよ。いわゆるその…そういう夜のお店のドライバー」
「…あ、なるほど」
言い淀みをなんとなく理解出来た。そういえば、初めて話した時も友達と話してて言葉を濁していたような気がする。
「結構高時給でさ。妹の治療方法が見つかったら少しでも足しになるようにって始めたんだ」
「そういうことか…妹さんは肺の病気なんだよね?」
「うん。元々空気のいいところに連れて行けるようにって取った運転免許だけど、それを活かしてる感じ」
歩夢の妹は特発性間質性肺炎という病気だと聞いた。指定難病で本当に命に関わるものらしい。空気のいいところで療養するといいため、澄んだ空気の田舎町に連れていくことも多いそうだ。
僕のいた小さな町も山々に囲まれていて空気は良かったので、聞いた時はそれを思い出した。
「いつも夜通しなの?」
「ううん。だいたい夕方から深夜には終わることが多いよ。週3くらいで働いてるかな」
「大変だね…」
「いや、魁人の方が大変じゃないか?俺がMärchenに行くといつも居るけど。どれくらい働いてるの?」
「ほぼ毎日かなぁ」
「え、いつ寝てるんだ!?」
「授業始まる前に1,2時間くらい…後は空きコマとかお昼とか…」
「睡眠時間足りないだろ」
「…僕、不眠症なんだよね」
なんとなくその続きは言わなかった。やはりまだ公にするのは気乗りしない。
歩夢はもちろん友達と言ってもいい関係だが、それと自分の過去の話はまた違うような気がした。話せる時が来たらきちんと伝えたいとは思う。
「そうか…なにか辛いことあったら教えてくれ。俺もたくさん助けられているから」
「え、助けているかな?」
「魁人的には助けているなんて意外かもだけど、Märchenで過ごす夜は心地いいんだよ。一瞬でも、妹のこととかで心痛める時間が減るんだ」
それを聞いて驚いた。僕があそこで働いていて、歩夢の心に少し余裕を持たせてあげられているという事実は意外だったからだ。マリーさんに僕が助けられた時と同じ感情を、僕自身が他の人に与えられていたという実感はない。
歩夢の言葉は嘘偽りなく聞こえ、意外に思いつつそれがどこか嬉しかった。
「魁人が話せるようになったらいつでも聞くよ」
「…ありがとう」
僕の表情を読み歩夢はそう言う。人の心の機微に気がつける人なんだと思った。
気がつけばもう大学の最寄り駅。僕らは2人並び、同じ改札を通り抜けた。
───
──
─
「魁人くん、こんばんは」
「こんばんは、マリーさん」
歩夢と別れて数時間後。カフェで適当に暇を潰し、新宿でマリーさんと合流する。
「ごめんね、飲み物の類を買わないといけないんだけど、独りじゃちょっと重くて」
「いえ、それくらいお安い御用です」
「時給はつけておくよ」
「悪いですよ。出勤時間までなにしようか悩んでましたし」
他愛もない話をしながら夜の街を歩く。近くの業務スーパーまでゆるゆると。
「そういえば今日は私服なのですね」
「業務時間外だからね」
白のブラウスにふわりと広がるロング丈のスカートを合わせた服装。熟れた濃い林檎のようなボルドーのスカートが夜風に靡く。気品溢れるコーディネート。彼女の色白の素肌にそんな上品さが映えていた。
「似合う?」
「はい、とても」
「ありがとう。…でもそれは出会ってすぐに言うものよ?」
「す、すみません…」
「ふふっ、冗談よ。でも魁人くんのそんな着飾らないところ、私は好きだよ」
彼女はそう言って微笑んだ。好きという言葉に少し照れくさくなる。勝手な偏見だが、外国の方はそういった気持ちを言葉に表すのが上手な気がする。であれば自分も紳士的にした方が良かったかもしれない。しかし生憎、そんな機転の利く振る舞いは僕にはできなかった。
改めて見ると彼女は紛うことなき美人だ。そんな人の隣を歩いているという事実は、まるで夢のように現実感がない。ただの買い出しが、御伽噺の一節のよう。街ゆく人から僕らはいったいどのように見えているのだろうか。
──
─
「うん、飲み物はこんなところかな」
少し肌寒い冷気で充ちている業務スーパーを一頻り練り歩いて必要なものを揃えていく。買い物カゴいっぱいの飲み物と製菓用品。ずっしりとした重みを手に感じながら、喫茶店営業は大変だなと思った。
「そういえば…」
「ん?」
レジの列に並びながら、気になったことをふと聞いてみる。
「よく使う林檎ってどこから仕入れてるのですか?」
「あー…んー、そこは業者に頼んでるかなぁ」
「買い出しだけでなく、発注とかも覚えた方がいいですか?」
「え!?…そ、それはいいよ!必要な分は私で用意するから」
「それなら…。いや、気になってたんですよ。よく使う割にはバックヤードに在庫がないなと思っていて」
Märchenではマリーさんがよく林檎のお菓子を作っている。その在庫を全くと言っていいほど見かけないのが少し疑問だった。
「…魁人くんは細かいところに気がつくよね」
「そうでしょうか?…でも林檎についてはたまたまです。置き場所にどれくらい使うか知ってたので」
「ん?なんで?」
「…実は、僕の実家が林檎農園でして」
「え、そうなの!?」
マリーさんが目を丸くして驚く。
「僕が住んでいた長野県って林檎が有名なんです。実家は細々と農園を経営していて。幼い頃から見ていたので目に入ったと言いますか…」
話しながら過去の日々を思い返す。
僕は生まれてから小さな町で林檎農園を営む父と母を見てきた。幼い頃は手伝っていた記憶がある。しかし大きくなるにつれ、力仕事と僕自身が合わないなと感じていた。段々と手伝わなくなった僕に、父は少し不安を感じていたようだった。
「林檎の在庫なんて、目の付け所がピンポイントすぎるなと思ったけどそういうことかぁ。…在庫は調整して入れてるから大丈夫だよ」
「なるほど」
関心したようにマリーさんが頷く。
個数にもよるが、林檎を抱えるとなるとかなり幅を取るので、あの狭いバックヤードではない場所にあるんだろうと会話の中で推測した。
「でも意外な共通点もう一つ追加だね。私は林檎が好きで、魁人くんは林檎農園の息子さん」
「共通点と言えますかね、それ」
「いいのいいの。こういうのはちょっとした繋がりがあればいいんだから」
レジの列が1人分進む。それに合わせて、1歩だけ僕らは前に歩いた。
「…私も1つ、魁人くんのことを教えて貰っていい?」
「はい」
マリーさんがレジを向きながら僕に問いかけた。
「魁人くんは東京に出てきた理由はあるの?」
「理由ですか?」
「うん。ご実家のことを話す魁人くんの表情が気になって」
「え…」
彼女のその言葉に、スーパーに流れる喧騒が少し遠のいた気がした。
「…どんな表情ですか?」
「不安とか迷いとか、そんな感じ」
紡ぐ言葉は心の底に触れられたようで動揺が走る。
「……」
「話したくなかったら、大丈夫」
興味本位の問いただしではないと、そんな気遣いに心が動く。きっと今の一瞬で、マリーさんが僕の中にあるなにかを見透したんだ。
「…元々僕は内向的な性格でした。1人で部屋にいる方が好きなタイプです」
彼女の気遣いに甘える形で過去を話す。天涯孤独になる前の、僕のこと。誰かに話すのは初めてだった。
「林檎農園を営む父と母のことは尊敬していましたが、僕は1人で本を読む方が好きだったんです。だから自分が将来、小さな地元で林檎農園を継いだ未来が少し億劫でした。自分のやりたいことではなかったんです」
「……」
小さな町。働き口などほとんどなく、皆家を継ぐ子がほとんどだった。そんな中で僕の未来が農園だったことがなんとなく嫌に感じた。その未来は、僕の思い描いたものではなかったからだ。
それが理由で今、僕は独りでここにいる。縛られた世界から逃げるために、自分の生きたい未来のために。
「前、初めて会った時に、上京した理由は縛られたくなかったからって言ってたよね?」
「はい…僕は本が好きだったので製本とか執筆とかそういう仕事がしたいと思ってました。そう遠くない大学の文学部でも学べましたが、そこにいたら父と母と顔を合わせることになるので東京に行きたいと。半ば無理矢理探した進学先です。そしたら父は家のことはどうするんだと言って──」
そこから先はもう大喧嘩だ。家のこと、自分のこと、跡継ぎのこと。田舎でよくある遠く離れた地に行くことへの抵抗と、家業を継ぐ周りの子達との比較など。声を荒らげて言い合った。喉が枯れるほどの言い合いは今でも覚えている。
僕はそれを端的に話した。親以外に誰にも言ったことのない話。誰かに聞いてもらいたかった話。
「魁人くんは後悔してる?」
「…もっと言いようがあったのではとか、自分がもっと違う人間性を持っていれば上京することもなかったとか…これが後悔と言えばそうなのかもしれません。僕が自分勝手に生きたばかりに、父と母はきっと僕を恨んでいるとさえ思います」
全て失ってしまうのなら東京になんて出なければ、と思ったことはある。仲違いしたまま終わってしまったこと、それはやはり後悔に近い。
彼女は僕の言葉を聞き、考えるように瞳を閉じた。
「魁人くんは、魁人くんらしく生きた方がいいと思う」
「えっ?」
そしてゆっくり、口を開きそう言った。
「ご両親が災禍に見舞われたのは魁人くんのせいじゃない。魁人くんがやりたかったこと、きっとご両親も否定していないと思う」
「でも大喧嘩してしまって…父と母が望んだ生き方ができない僕は親不孝で──」
「私、ここ1ヶ月くらいであなたが真面目なのも、言葉遣いが丁寧なこともわかった。それは魁人くんを近くで見ていたご両親が一番わかっていると思う」
ずっと心に引っかかっていた戸惑い。彼女の言葉でそれが徐々に解けていく。
「魁人くん自身が自分で決めた道を否定してあげないで。それじゃ本当に独りになっちゃう」
両親に会いたいとか独りじゃないと思いたいとか、そんな雪降る前の曇天のようなモヤモヤの根幹。なんでこんなにも孤独だったのか。それは他でもない、自分が自分を否定していたからだ。
「もし叶うのなら…」
気がついたから、涙が出た。スーパーの喧騒の中、一筋の涙が頬を伝う。でもそれは悲しみだけの涙ではなかった。
「父と母にもう一度会いたいです。墓前でもなんでもいい…もう居ないかもしれなくても、親不孝の謝罪と自分がやりたかったことを伝えられれば…」
今の今まで家族がまだ見つかると思っていた。悲しいという大きな感情の中に隠れていたもの。心の奥底で薄々感じていた既に両親がこの世にいない可能性を認めてしまったら、現世からだけでなく、自ら選んだ両親に認められなかった生き方からも独りになってしまう。
だからきっと人にそれを求めたんだ。でも結局自分の中にしか答えはなくて…これからを生きるために、自身の選んだ道に自信を持つために前を向きたい。
「…なんだか気が晴れました」
「魁人くんは偉いね」
あやすように僕にそう言う彼女。羊さんやメリーさんの言う通りだ。話すことで、スッキリする。抱え込むだけでは何も変わらなかったかもしれない。
「マリーさんといるとなんでも話せてしまいます。不思議です。なんでなんでしょうか」
「…私が魅力的だからかな?」
「……ははっ、そうかもしれませんね」
「…今、笑えたね」
「そうですね」
「そっちの方が素敵だよ」
「…ありがとうございます」
自然と笑みが出た。決して今までのやり取りが面白くなかったわけではないが、いろいろ考えすぎて笑ってこなかった。
レジの列が1歩進む。ごくごく当たり前に笑えたことで、また1つ前に進めた気がした。
「逆にマリーさんはなんで日本に来たんですか?」
だから少し彼女のことについて踏み込んでみる。マリーさんのことを知りたいと、単純にそう思った。
「……恩返しなんだ」
「恩返し?」
「昔ね、日本の人に救われたことがあるの」
少しの沈黙の後、彼女はそう答えた。
「独りぼっちでいた時に、声をかけてくれた人がたまたま日本人でね。ほら、私って黒髪じゃない?それで昔、忌み嫌われることがあって」
「あぁ…やっぱり向こうだと珍しいんですか?」
「…そうね。珍しかったわ。…魔女なんて呼ばれてた」
「それはまた…」
思わず言葉がつっかえる。とても酷いことだ。
綺麗な黒髪は日本人特有だとも聞く。国によっては物珍しいのだろうな。…魔女とはまた随分と古風な忌み名。外国とはいえ髪色だけでそうまで言われるなんて、まるで中世の頃の話みたいだ。
「冬が始まるくらいの秋終わりだったよ。森の中で独りで途方に暮れてた私に、大丈夫かって声をかけてくれたの」
彼女が苦い顔をする。時たま見せる彼女の辛そうな表情。凄惨な過去であったことがそれだけで窺えた。
なんとなく、彼女が眠れない所以となっていそうなお話なんだろうと思った
「マリーさんが…眠れなくなったのと関係してますか?」
「……」
「マリーさん?」
僕の問いにまた少し沈黙が流れたので、努めて優しく声をかける。彼女は前を向いたまま、どこか遠い目をしていた。
「…あのね、私──」
そしてその沈黙を自身で破った瞬間──
「次の方どうぞー」
「あっ…」
レジの店員さんが僕らにそう声をかけた。気がつけば僕らが先頭だった。
「また今度、必ず話すよ」
「…はい」
なんとももどかしいタイミング。彼女がなんと言葉を紡ごうとしたのか気になったが、マリーさんはフッと笑ってそう言い、レジへ歩を進めた。
彼女はなにを抱えているんだろうか…。救われたからと言った理由ではなく、一人の人間としてマリーさんに接したい。
どんどんと彼女に惹かれている自分がいた。
───
──
─
「…それでさ、同じ卓についた女の子がこれまた面白くって──」
買い出しを終えて、開店早々から羊さんが来てくれていた。カウンターで今日あった出来事について嬉々として話す。
「もうカラオケでおじさんウケする懐メロ歌ってはっちゃけちゃって」
「…そういえば、日本の曲はあまり聞いてないからその辺りは少し疎いわ」
「……」
楽しそうに話す二人を横目に、僕は静かにグラスを拭いていた。話に入れないというわけではなく、単純に先程の買い出しの時に話していたことで頭がいっぱいだった。
「おっ!大のカラオケ好きの私の前でそんなこと言うとは!布教活動に精出しちゃうよー?」
「ふふっ、いろいろ教えてください。羊さん」
「……」
きちんと起きたことに向き合いたい。安否は不明だが、ひとまずは両親を探すところから。とはいったものの、現状は被災地へ赴くことは原則禁止されている。できることはあまりないのかもしれない。
「えぇ〜?メリーさんに頼られるの嬉しい〜。ボトル開けようか?」
「お生憎、うちはそういうシステムじゃないのよ」
「いけずだなぁ〜」
「……」
被災者の会などがあれば、諸々の情報は手に入るのだろうか。そもそも戻ったところでどう探すべきか…分からないことはまだまだ多い。
「魁人くん」
「……」
「魁人くーん!」
「……あっ、すみません。お呼びでしょうか?」
ながら聞きしていた片耳に、羊さんのやや大きめの声に気がつく。ワンテンポ、反応が遅れた。
「いつも見たく真面目な感じで突っ込んでくれないと。おじさんみたいだよって」
「えっ?…あ、おじさんみたいですよ?」
「いや、遅っ!でも面白い」
楽しそうに羊さんが笑った。考え事で疎かになるのは良くないな…反省。
「でも歌いすぎて喉ガラガラなのよ…」
「たしかにいつもと声が違いますね」
「あ、それならいいものがあるわ」
マリーさんがパンっと手を合わせ、幾つかの飲み物瓶を手に取る。
「日本では風邪の時とか生姜湯を飲むって聞いてね…アップルジンジャー作ってあげる」
「え、ほんとに!?ありがとー!」
すりおろした生姜を温めたお湯に溶かしていく。ゆっくりと黄金色に染る白湯が明かりに照らされて映える。フワッと生姜の馨しい香りが森のような喫茶店に広がった。
カランカラン
「こんばんはー」
「あっ!歩夢くん!いいところに〜」
心地よくも感じるその様子を眺めていると、呼び鈴が鳴って歩夢が入ってくる。羊さんが嬉しそうに声をかけた。
「おぉ、いい香りですね」
「メリーさんがアップルジンジャー作ってくれるんだって!」
「なるほど」
「ふふっ、歩夢くんもいる?」
「はい、いただきます」
歩夢はバーチェアにトートバッグを置きながら羊さんの右隣に腰かけた。最早この二人の定位置となっている。
そうこうしているうちにマリーさんがグラスに氷を入れ、生姜湯とアップルシロップを流し入れた。パキパキと熱で割れる氷の音が綺麗だ。
「……はい、お待たせしました」
林檎型のコースターの上に細長いグラスが2つ。グラスの結露に光が屈折して黄金に輝いている。
「なんの話ししてたんですか?」
「私がカラオケで喉ガラガラになったっていう話」
「それで生姜系の飲み物ですか。喉にいいですもんね」
「えぇ、日本では生姜は風邪に効くって聞いたものだからね」
「羊さんは風邪を引いてるわけでは…」
「魁人、細かいことはいいんだよ」
「そうそう、なんとかは風邪ひかないって言うし」
「その場合だと羊さんがそのなんとかってことになりますが…」
「なにをー!…なんとかって何?」
「いやぁー…」
「…ふふふ」
脱線に脱線を重ねる眠れない人達のお茶会。夜だと言うのに店内の空気はお昼のように明るい。
「…あ、そうそう。最近流行ってる話をしてもいいですか?」
来たばかりの歩夢がアップルジンジャーを喉に流しながら話を変える。
「迷惑な配信者の話なんですけど…」
「あ、それもしかして今炎上してるやつ?」
「はい」
「炎上ですか?」
「魁人くん、炎上ってなに?」
「インフルエンサーが迷惑行為なんかで視聴者から怒られるみたいなやつです」
「へぇ…」
昨今ではSNSの普及により、配信者や有名人などの距離が近いという。一般人が言うと許されることでも、多くの人の目に付く彼ら彼女らが言うと反感を買うなんてことが多いようだ。
「二人ともSNSやってないの?」
「僕はやってないですね。発信したいこともないですし…」
「私も…いんふるえんさー?が何を指してるかイマイチ…日本文化はよくわからないわ」
「SNSは世界的に普及してますよ」
「返し真面目だな!SNSやってないとこも含めて」
「日本人みたい」
「羊さん、それ私のセリフ」
「どちらかと言うと魁人もマリーさんも年寄りみたいですけどね。SNSやってないのは割とびっくり」
歩夢にまるで魔法でも見たかのように驚かれる。自分が異端だとは思ってないが、たしかにSNSをやっていないのは珍しいとは思う。とは言っても年寄りは流石に言い過ぎでは?と思うが…
「…はははっ、年寄りねぇ」
普段なら微笑んで流すマリーさんが乾いた笑いをした。そういえば前も年齢の話で不自然な間があった気がする。意外とタブーなのだろうか。
「それで、その配信者がどうかしたの?」
「あ、そうそう。んーとね」
「動画見てもらった方が早いんじゃない?」
「そうですね」
羊さんにそう促され、歩夢はタッタッと軽快にスマートフォンを操作した。
「これなんだけど…」
動画は再生数が3桁万ほど。流れた冒頭の映像には、少しやんちゃをしてそうな男性と片田舎の風景が映っていた。
「…っ!」
その田舎の風景には見覚えがあった。ちらりと映る町の建物は軒並み半壊している。凄惨な現場、それはまるで──
「これ、この前あった被災地なんだって」
紛うことなく、それは僕が生まれ育った町だった。
「そ、そこって…」
僕の事情を知っているマリーさんの声が上擦る。彼女の綺麗な声がキンとした音に聞こえた。ぐにゃりと床が傾いて、地に足が着いていないような感覚に陥った。倒れないように、バーカウンターに手を着く。
「この配信者の人、東京から被災地まで行ったんだけど──って大丈夫か!?」
「か、魁人くん!?どうしたの!?すごい汗っ…」
そう言われて僕は額に触れる。ものすごい量の汗が指先を濡らした。
だがそれより、僕は歩夢の発言が気になった。
「ち、ちょっと待ってください…東京からって言いました?」
僕は羊さんの心配を遮るように食い気味に歩夢に問う。呼吸が激しくハッハッと乱れるのを感じた。
僕の剣幕に押され、歩夢が引き気味に答えた。
「あ、あぁ…今被災地に行くのが禁止されてる中での行動だから炎上しちゃってるんだけど…」
「な、なんで…!」
「名目は被災支援だと思うよ。実際ボランティアしてる画像も出てる。けど、向こうの人たちもどこか困った表情の人もいたり、十分な支援体制整ってなかったりで…実際のところは売名目当てなところもあるだろうね」
ガンッと頭を何かで打ち付けられたような衝撃。そんな、そんなことがあるのか…。当事者の僕ですら、その土地を赴けていないというのに…。
ベストの胸元を握り締める。激しく鳴る心臓の鼓動すら痛い。
「…うっ……うぅ」
泣いた。馬鹿みたいに涙が出た。声が漏れる。口元に手を当て吐き気を抑える。苦しいとかおかしいとか…いろんな感情と一緒に父や母やその土地での記憶がグルグルと頭を巡る。
催した吐き気を抱えながら動画に映る男を目に焼きつける。悪戯に、心の底に土足で足を踏み入れたその男が浮かべる笑みは、まるで嘲笑うかのような気持ちの悪いものに見えた。
なんだ…なんなんだ…。いったいなんなんだこれ…。
「……っ」
マリーさんが僕を見る。僕はこれ以上、口を開けそうになかった。
「か、魁人くんはね…被災地出身の子なの」
「え!?」
「大震災が起きる前にこっちに越してきて…いろんなものをそこに置いたまま帰れてないの、一度も…」
「嘘っ…じゃあ…」
マリーさんの代わりの説明に、驚いた二人が画面を見て…そして青ざめる。それはそうだ…。この人が炎上している理由…その最たる影響を受けている存在が目の前にいるのだから。
「この人が行けて…僕がそこに帰れない理由はなんなんですか…」
「そ、それは…」
「裏話だけど…私この人に会ったことある。うちのお店に来たんだけど、どんな形であれ注目されればって言ってた…」
羊さんがそう言う。なんだその理由…と思った。黒い黒い感情がふつふつと沸き上がる。人道がないとかそう言う次元じゃない。
「復旧の妨害をしてるわけじゃないけど、規制は強くなるかも」
「また帰れなくなるってこと!?」
「こんなのがバズってしまったら…同じことをする人ができてもおかしくないですから…」
この喫茶店は願いを叶えたい人が集まる場所と噂されているのに、僕の抱えた願いからはどんどん遠ざかる。落ち着くはずの喫茶店の空気がズンと重い。
「…魁人くん」
マリーさんが不安そうに僕を見る。その先を話していいか…迷っているような表情。僕は静かに頷く。二人にはもう話していいと思っているが、今思い出しながら話すのはつらい。
「…魁人くんは、3月の頭にね──」
彼女はそんな僕の様子を見て、経緯を話し始める。御伽噺を読み聞かせるように、1つずつ、綺麗な声で緩やかに。だけどそれは決して夢物語ではない。紛うことのない現実。
徐々に顔色を変えていく羊さんと歩夢。言葉を失う彼らに、いかに自分の置かれた境遇が稀有なものか理解する。
「…じゃあ、お母さんたちには会えてないんだね」
「魁人、もしかして眠れなくなった理由って──」
一頻り聞き終えた歩夢の言葉に、僕は黙って頷いた。
「魁人くんは毎日悪夢を見るんだって。地震の夢、それは今も…」
「…だから毎日働いてるんだ」
「はい…でも久々に見た悪夢じゃない地元が炎上してる配信者でなんて…皮肉なものですね」
自嘲気味に口から言葉がこぼれる。僕の言葉に、皆なにも言えなくなっていた。
「ごめん、こんな動画見せて」
「いえ、大丈夫…です」
敬語すら忘れかける。今の僕は本当に余裕がないんだなと思った。
「魁人くん…」
マリーさんが僕に声をかける。俯いた顔を上げ、彼女を見た。
「…っ」
僕の表情を見て、マリーさんが息を飲んだ。目を丸くする彼女。
僕は今どんな顔をしているのだろう。きっと、新宿の街で独り俯いていた時と同じなんだろう。
「魁人くん!」
すると彼女は意を決したように僕の手を取った。
「私、貴方の住んでいたところに行きたい」
「え?」
夜の始まりを感じる5限終わり。傾いた陽光がキャンパスを照らす。紫とも橙ともつかない宵空。いつもは喧騒で包まれている大学も、この時間になると生徒が疎らに帰路につくのみだった。
僕もそんな生徒たちに混じり正門へ向かう。視界に入った桜の木は既に花を散らしている。もうすぐ春が終わろうとしていた。
「…もうそろそろ2ヶ月か」
こっちに越してきた月日を数えて、独りごつ。
マリーさんの元で働き始めて数週間。仕事には徐々に慣れてきたから、それはよかったと思う。不慣れが原因で迷惑をかけていたら立つ瀬がない。
連日働いてみてわかったことだが、「願いの叶う喫茶店」と噂になっている割にはお客さんは全く来ない。来たとしても、羊さんと歩夢。それ以外にお客さんは見た事がない。見つけにくいというのは本当なようだ。
ただ、働いていて気が紛れるのも確かだった。元来真面目な性格だったことが幸いもしている。
「…おーい!」
そんなことを考えながら正門を出ると、後ろから聞き馴染みのある声がした。
「やっぱり魁人だ」
「歩夢」
そういって軽い駆け足で近づいてきたのは歩夢だった。
「よっ」
「こんばんは」
「後ろ姿を見かけてさ。人違いだったらどうしようかと思ったよ」
「大学同じだけどなんだかんだ顔合わせないしね。その気持ちはわかるよ」
僕なら見かけたとしても顔を見るまで声はかけなかっただろう。知り合って間もない人ほど、服装や歩き姿だけで判断するのはなかなかに難しい。そういう葛藤を抱えながらも声をかけてくれたのは素直に嬉しい気持ちになった。
「歩夢も5限目まで授業受けてたんだ」
「あぁ、薬学部は5限に必修が入っててさ。…というかあれ?敬語は?」
「あー、今は店員じゃないし。馴れ馴れしかったかな?」
「そんなことない!というかそうやって切り分けてるの本当に真面目だな」
「普通じゃないかな」
「日本人みたいだぞ」
「いや、マリーさんと同じジョークやめてよ」
はははっと歩夢が笑う。新しく出会った人はこうして軽い冗談を言う人たちばかりだ。僕はそれにうまく返せているか疑問に思うときもあるが、彼らの反応を見るに問題はないのだろう。都会の人たちはみな社交的なんだなと思った。
「魁人はこの後なんか予定あるの?」
「今日もバイトかなぁ。マリーさんと一緒に買い出しを頼まれてるんだ」
「あ、ほんとに?俺も今日はバイトだから、終わったらMärchenに行くよ」
「いつもありがとうございます」
「ははっ、店員モードじゃん」
意図せず切り分けたのを笑いながら、一緒に行こうと誘われたのでそのまま駅まで歩く。
「そういえば聞いてなかったけどなんのバイトしてるの?」
「あー…ドライバーだよ」
「深夜の?タクシー?」
「まぁ…いや、魁人なら話してもいっか」
そう言って歩夢は言葉を続ける。
「俺、女の子をお客さんの元に届ける仕事してるんだよ。いわゆるその…そういう夜のお店のドライバー」
「…あ、なるほど」
言い淀みをなんとなく理解出来た。そういえば、初めて話した時も友達と話してて言葉を濁していたような気がする。
「結構高時給でさ。妹の治療方法が見つかったら少しでも足しになるようにって始めたんだ」
「そういうことか…妹さんは肺の病気なんだよね?」
「うん。元々空気のいいところに連れて行けるようにって取った運転免許だけど、それを活かしてる感じ」
歩夢の妹は特発性間質性肺炎という病気だと聞いた。指定難病で本当に命に関わるものらしい。空気のいいところで療養するといいため、澄んだ空気の田舎町に連れていくことも多いそうだ。
僕のいた小さな町も山々に囲まれていて空気は良かったので、聞いた時はそれを思い出した。
「いつも夜通しなの?」
「ううん。だいたい夕方から深夜には終わることが多いよ。週3くらいで働いてるかな」
「大変だね…」
「いや、魁人の方が大変じゃないか?俺がMärchenに行くといつも居るけど。どれくらい働いてるの?」
「ほぼ毎日かなぁ」
「え、いつ寝てるんだ!?」
「授業始まる前に1,2時間くらい…後は空きコマとかお昼とか…」
「睡眠時間足りないだろ」
「…僕、不眠症なんだよね」
なんとなくその続きは言わなかった。やはりまだ公にするのは気乗りしない。
歩夢はもちろん友達と言ってもいい関係だが、それと自分の過去の話はまた違うような気がした。話せる時が来たらきちんと伝えたいとは思う。
「そうか…なにか辛いことあったら教えてくれ。俺もたくさん助けられているから」
「え、助けているかな?」
「魁人的には助けているなんて意外かもだけど、Märchenで過ごす夜は心地いいんだよ。一瞬でも、妹のこととかで心痛める時間が減るんだ」
それを聞いて驚いた。僕があそこで働いていて、歩夢の心に少し余裕を持たせてあげられているという事実は意外だったからだ。マリーさんに僕が助けられた時と同じ感情を、僕自身が他の人に与えられていたという実感はない。
歩夢の言葉は嘘偽りなく聞こえ、意外に思いつつそれがどこか嬉しかった。
「魁人が話せるようになったらいつでも聞くよ」
「…ありがとう」
僕の表情を読み歩夢はそう言う。人の心の機微に気がつける人なんだと思った。
気がつけばもう大学の最寄り駅。僕らは2人並び、同じ改札を通り抜けた。
───
──
─
「魁人くん、こんばんは」
「こんばんは、マリーさん」
歩夢と別れて数時間後。カフェで適当に暇を潰し、新宿でマリーさんと合流する。
「ごめんね、飲み物の類を買わないといけないんだけど、独りじゃちょっと重くて」
「いえ、それくらいお安い御用です」
「時給はつけておくよ」
「悪いですよ。出勤時間までなにしようか悩んでましたし」
他愛もない話をしながら夜の街を歩く。近くの業務スーパーまでゆるゆると。
「そういえば今日は私服なのですね」
「業務時間外だからね」
白のブラウスにふわりと広がるロング丈のスカートを合わせた服装。熟れた濃い林檎のようなボルドーのスカートが夜風に靡く。気品溢れるコーディネート。彼女の色白の素肌にそんな上品さが映えていた。
「似合う?」
「はい、とても」
「ありがとう。…でもそれは出会ってすぐに言うものよ?」
「す、すみません…」
「ふふっ、冗談よ。でも魁人くんのそんな着飾らないところ、私は好きだよ」
彼女はそう言って微笑んだ。好きという言葉に少し照れくさくなる。勝手な偏見だが、外国の方はそういった気持ちを言葉に表すのが上手な気がする。であれば自分も紳士的にした方が良かったかもしれない。しかし生憎、そんな機転の利く振る舞いは僕にはできなかった。
改めて見ると彼女は紛うことなき美人だ。そんな人の隣を歩いているという事実は、まるで夢のように現実感がない。ただの買い出しが、御伽噺の一節のよう。街ゆく人から僕らはいったいどのように見えているのだろうか。
──
─
「うん、飲み物はこんなところかな」
少し肌寒い冷気で充ちている業務スーパーを一頻り練り歩いて必要なものを揃えていく。買い物カゴいっぱいの飲み物と製菓用品。ずっしりとした重みを手に感じながら、喫茶店営業は大変だなと思った。
「そういえば…」
「ん?」
レジの列に並びながら、気になったことをふと聞いてみる。
「よく使う林檎ってどこから仕入れてるのですか?」
「あー…んー、そこは業者に頼んでるかなぁ」
「買い出しだけでなく、発注とかも覚えた方がいいですか?」
「え!?…そ、それはいいよ!必要な分は私で用意するから」
「それなら…。いや、気になってたんですよ。よく使う割にはバックヤードに在庫がないなと思っていて」
Märchenではマリーさんがよく林檎のお菓子を作っている。その在庫を全くと言っていいほど見かけないのが少し疑問だった。
「…魁人くんは細かいところに気がつくよね」
「そうでしょうか?…でも林檎についてはたまたまです。置き場所にどれくらい使うか知ってたので」
「ん?なんで?」
「…実は、僕の実家が林檎農園でして」
「え、そうなの!?」
マリーさんが目を丸くして驚く。
「僕が住んでいた長野県って林檎が有名なんです。実家は細々と農園を経営していて。幼い頃から見ていたので目に入ったと言いますか…」
話しながら過去の日々を思い返す。
僕は生まれてから小さな町で林檎農園を営む父と母を見てきた。幼い頃は手伝っていた記憶がある。しかし大きくなるにつれ、力仕事と僕自身が合わないなと感じていた。段々と手伝わなくなった僕に、父は少し不安を感じていたようだった。
「林檎の在庫なんて、目の付け所がピンポイントすぎるなと思ったけどそういうことかぁ。…在庫は調整して入れてるから大丈夫だよ」
「なるほど」
関心したようにマリーさんが頷く。
個数にもよるが、林檎を抱えるとなるとかなり幅を取るので、あの狭いバックヤードではない場所にあるんだろうと会話の中で推測した。
「でも意外な共通点もう一つ追加だね。私は林檎が好きで、魁人くんは林檎農園の息子さん」
「共通点と言えますかね、それ」
「いいのいいの。こういうのはちょっとした繋がりがあればいいんだから」
レジの列が1人分進む。それに合わせて、1歩だけ僕らは前に歩いた。
「…私も1つ、魁人くんのことを教えて貰っていい?」
「はい」
マリーさんがレジを向きながら僕に問いかけた。
「魁人くんは東京に出てきた理由はあるの?」
「理由ですか?」
「うん。ご実家のことを話す魁人くんの表情が気になって」
「え…」
彼女のその言葉に、スーパーに流れる喧騒が少し遠のいた気がした。
「…どんな表情ですか?」
「不安とか迷いとか、そんな感じ」
紡ぐ言葉は心の底に触れられたようで動揺が走る。
「……」
「話したくなかったら、大丈夫」
興味本位の問いただしではないと、そんな気遣いに心が動く。きっと今の一瞬で、マリーさんが僕の中にあるなにかを見透したんだ。
「…元々僕は内向的な性格でした。1人で部屋にいる方が好きなタイプです」
彼女の気遣いに甘える形で過去を話す。天涯孤独になる前の、僕のこと。誰かに話すのは初めてだった。
「林檎農園を営む父と母のことは尊敬していましたが、僕は1人で本を読む方が好きだったんです。だから自分が将来、小さな地元で林檎農園を継いだ未来が少し億劫でした。自分のやりたいことではなかったんです」
「……」
小さな町。働き口などほとんどなく、皆家を継ぐ子がほとんどだった。そんな中で僕の未来が農園だったことがなんとなく嫌に感じた。その未来は、僕の思い描いたものではなかったからだ。
それが理由で今、僕は独りでここにいる。縛られた世界から逃げるために、自分の生きたい未来のために。
「前、初めて会った時に、上京した理由は縛られたくなかったからって言ってたよね?」
「はい…僕は本が好きだったので製本とか執筆とかそういう仕事がしたいと思ってました。そう遠くない大学の文学部でも学べましたが、そこにいたら父と母と顔を合わせることになるので東京に行きたいと。半ば無理矢理探した進学先です。そしたら父は家のことはどうするんだと言って──」
そこから先はもう大喧嘩だ。家のこと、自分のこと、跡継ぎのこと。田舎でよくある遠く離れた地に行くことへの抵抗と、家業を継ぐ周りの子達との比較など。声を荒らげて言い合った。喉が枯れるほどの言い合いは今でも覚えている。
僕はそれを端的に話した。親以外に誰にも言ったことのない話。誰かに聞いてもらいたかった話。
「魁人くんは後悔してる?」
「…もっと言いようがあったのではとか、自分がもっと違う人間性を持っていれば上京することもなかったとか…これが後悔と言えばそうなのかもしれません。僕が自分勝手に生きたばかりに、父と母はきっと僕を恨んでいるとさえ思います」
全て失ってしまうのなら東京になんて出なければ、と思ったことはある。仲違いしたまま終わってしまったこと、それはやはり後悔に近い。
彼女は僕の言葉を聞き、考えるように瞳を閉じた。
「魁人くんは、魁人くんらしく生きた方がいいと思う」
「えっ?」
そしてゆっくり、口を開きそう言った。
「ご両親が災禍に見舞われたのは魁人くんのせいじゃない。魁人くんがやりたかったこと、きっとご両親も否定していないと思う」
「でも大喧嘩してしまって…父と母が望んだ生き方ができない僕は親不孝で──」
「私、ここ1ヶ月くらいであなたが真面目なのも、言葉遣いが丁寧なこともわかった。それは魁人くんを近くで見ていたご両親が一番わかっていると思う」
ずっと心に引っかかっていた戸惑い。彼女の言葉でそれが徐々に解けていく。
「魁人くん自身が自分で決めた道を否定してあげないで。それじゃ本当に独りになっちゃう」
両親に会いたいとか独りじゃないと思いたいとか、そんな雪降る前の曇天のようなモヤモヤの根幹。なんでこんなにも孤独だったのか。それは他でもない、自分が自分を否定していたからだ。
「もし叶うのなら…」
気がついたから、涙が出た。スーパーの喧騒の中、一筋の涙が頬を伝う。でもそれは悲しみだけの涙ではなかった。
「父と母にもう一度会いたいです。墓前でもなんでもいい…もう居ないかもしれなくても、親不孝の謝罪と自分がやりたかったことを伝えられれば…」
今の今まで家族がまだ見つかると思っていた。悲しいという大きな感情の中に隠れていたもの。心の奥底で薄々感じていた既に両親がこの世にいない可能性を認めてしまったら、現世からだけでなく、自ら選んだ両親に認められなかった生き方からも独りになってしまう。
だからきっと人にそれを求めたんだ。でも結局自分の中にしか答えはなくて…これからを生きるために、自身の選んだ道に自信を持つために前を向きたい。
「…なんだか気が晴れました」
「魁人くんは偉いね」
あやすように僕にそう言う彼女。羊さんやメリーさんの言う通りだ。話すことで、スッキリする。抱え込むだけでは何も変わらなかったかもしれない。
「マリーさんといるとなんでも話せてしまいます。不思議です。なんでなんでしょうか」
「…私が魅力的だからかな?」
「……ははっ、そうかもしれませんね」
「…今、笑えたね」
「そうですね」
「そっちの方が素敵だよ」
「…ありがとうございます」
自然と笑みが出た。決して今までのやり取りが面白くなかったわけではないが、いろいろ考えすぎて笑ってこなかった。
レジの列が1歩進む。ごくごく当たり前に笑えたことで、また1つ前に進めた気がした。
「逆にマリーさんはなんで日本に来たんですか?」
だから少し彼女のことについて踏み込んでみる。マリーさんのことを知りたいと、単純にそう思った。
「……恩返しなんだ」
「恩返し?」
「昔ね、日本の人に救われたことがあるの」
少しの沈黙の後、彼女はそう答えた。
「独りぼっちでいた時に、声をかけてくれた人がたまたま日本人でね。ほら、私って黒髪じゃない?それで昔、忌み嫌われることがあって」
「あぁ…やっぱり向こうだと珍しいんですか?」
「…そうね。珍しかったわ。…魔女なんて呼ばれてた」
「それはまた…」
思わず言葉がつっかえる。とても酷いことだ。
綺麗な黒髪は日本人特有だとも聞く。国によっては物珍しいのだろうな。…魔女とはまた随分と古風な忌み名。外国とはいえ髪色だけでそうまで言われるなんて、まるで中世の頃の話みたいだ。
「冬が始まるくらいの秋終わりだったよ。森の中で独りで途方に暮れてた私に、大丈夫かって声をかけてくれたの」
彼女が苦い顔をする。時たま見せる彼女の辛そうな表情。凄惨な過去であったことがそれだけで窺えた。
なんとなく、彼女が眠れない所以となっていそうなお話なんだろうと思った
「マリーさんが…眠れなくなったのと関係してますか?」
「……」
「マリーさん?」
僕の問いにまた少し沈黙が流れたので、努めて優しく声をかける。彼女は前を向いたまま、どこか遠い目をしていた。
「…あのね、私──」
そしてその沈黙を自身で破った瞬間──
「次の方どうぞー」
「あっ…」
レジの店員さんが僕らにそう声をかけた。気がつけば僕らが先頭だった。
「また今度、必ず話すよ」
「…はい」
なんとももどかしいタイミング。彼女がなんと言葉を紡ごうとしたのか気になったが、マリーさんはフッと笑ってそう言い、レジへ歩を進めた。
彼女はなにを抱えているんだろうか…。救われたからと言った理由ではなく、一人の人間としてマリーさんに接したい。
どんどんと彼女に惹かれている自分がいた。
───
──
─
「…それでさ、同じ卓についた女の子がこれまた面白くって──」
買い出しを終えて、開店早々から羊さんが来てくれていた。カウンターで今日あった出来事について嬉々として話す。
「もうカラオケでおじさんウケする懐メロ歌ってはっちゃけちゃって」
「…そういえば、日本の曲はあまり聞いてないからその辺りは少し疎いわ」
「……」
楽しそうに話す二人を横目に、僕は静かにグラスを拭いていた。話に入れないというわけではなく、単純に先程の買い出しの時に話していたことで頭がいっぱいだった。
「おっ!大のカラオケ好きの私の前でそんなこと言うとは!布教活動に精出しちゃうよー?」
「ふふっ、いろいろ教えてください。羊さん」
「……」
きちんと起きたことに向き合いたい。安否は不明だが、ひとまずは両親を探すところから。とはいったものの、現状は被災地へ赴くことは原則禁止されている。できることはあまりないのかもしれない。
「えぇ〜?メリーさんに頼られるの嬉しい〜。ボトル開けようか?」
「お生憎、うちはそういうシステムじゃないのよ」
「いけずだなぁ〜」
「……」
被災者の会などがあれば、諸々の情報は手に入るのだろうか。そもそも戻ったところでどう探すべきか…分からないことはまだまだ多い。
「魁人くん」
「……」
「魁人くーん!」
「……あっ、すみません。お呼びでしょうか?」
ながら聞きしていた片耳に、羊さんのやや大きめの声に気がつく。ワンテンポ、反応が遅れた。
「いつも見たく真面目な感じで突っ込んでくれないと。おじさんみたいだよって」
「えっ?…あ、おじさんみたいですよ?」
「いや、遅っ!でも面白い」
楽しそうに羊さんが笑った。考え事で疎かになるのは良くないな…反省。
「でも歌いすぎて喉ガラガラなのよ…」
「たしかにいつもと声が違いますね」
「あ、それならいいものがあるわ」
マリーさんがパンっと手を合わせ、幾つかの飲み物瓶を手に取る。
「日本では風邪の時とか生姜湯を飲むって聞いてね…アップルジンジャー作ってあげる」
「え、ほんとに!?ありがとー!」
すりおろした生姜を温めたお湯に溶かしていく。ゆっくりと黄金色に染る白湯が明かりに照らされて映える。フワッと生姜の馨しい香りが森のような喫茶店に広がった。
カランカラン
「こんばんはー」
「あっ!歩夢くん!いいところに〜」
心地よくも感じるその様子を眺めていると、呼び鈴が鳴って歩夢が入ってくる。羊さんが嬉しそうに声をかけた。
「おぉ、いい香りですね」
「メリーさんがアップルジンジャー作ってくれるんだって!」
「なるほど」
「ふふっ、歩夢くんもいる?」
「はい、いただきます」
歩夢はバーチェアにトートバッグを置きながら羊さんの右隣に腰かけた。最早この二人の定位置となっている。
そうこうしているうちにマリーさんがグラスに氷を入れ、生姜湯とアップルシロップを流し入れた。パキパキと熱で割れる氷の音が綺麗だ。
「……はい、お待たせしました」
林檎型のコースターの上に細長いグラスが2つ。グラスの結露に光が屈折して黄金に輝いている。
「なんの話ししてたんですか?」
「私がカラオケで喉ガラガラになったっていう話」
「それで生姜系の飲み物ですか。喉にいいですもんね」
「えぇ、日本では生姜は風邪に効くって聞いたものだからね」
「羊さんは風邪を引いてるわけでは…」
「魁人、細かいことはいいんだよ」
「そうそう、なんとかは風邪ひかないって言うし」
「その場合だと羊さんがそのなんとかってことになりますが…」
「なにをー!…なんとかって何?」
「いやぁー…」
「…ふふふ」
脱線に脱線を重ねる眠れない人達のお茶会。夜だと言うのに店内の空気はお昼のように明るい。
「…あ、そうそう。最近流行ってる話をしてもいいですか?」
来たばかりの歩夢がアップルジンジャーを喉に流しながら話を変える。
「迷惑な配信者の話なんですけど…」
「あ、それもしかして今炎上してるやつ?」
「はい」
「炎上ですか?」
「魁人くん、炎上ってなに?」
「インフルエンサーが迷惑行為なんかで視聴者から怒られるみたいなやつです」
「へぇ…」
昨今ではSNSの普及により、配信者や有名人などの距離が近いという。一般人が言うと許されることでも、多くの人の目に付く彼ら彼女らが言うと反感を買うなんてことが多いようだ。
「二人ともSNSやってないの?」
「僕はやってないですね。発信したいこともないですし…」
「私も…いんふるえんさー?が何を指してるかイマイチ…日本文化はよくわからないわ」
「SNSは世界的に普及してますよ」
「返し真面目だな!SNSやってないとこも含めて」
「日本人みたい」
「羊さん、それ私のセリフ」
「どちらかと言うと魁人もマリーさんも年寄りみたいですけどね。SNSやってないのは割とびっくり」
歩夢にまるで魔法でも見たかのように驚かれる。自分が異端だとは思ってないが、たしかにSNSをやっていないのは珍しいとは思う。とは言っても年寄りは流石に言い過ぎでは?と思うが…
「…はははっ、年寄りねぇ」
普段なら微笑んで流すマリーさんが乾いた笑いをした。そういえば前も年齢の話で不自然な間があった気がする。意外とタブーなのだろうか。
「それで、その配信者がどうかしたの?」
「あ、そうそう。んーとね」
「動画見てもらった方が早いんじゃない?」
「そうですね」
羊さんにそう促され、歩夢はタッタッと軽快にスマートフォンを操作した。
「これなんだけど…」
動画は再生数が3桁万ほど。流れた冒頭の映像には、少しやんちゃをしてそうな男性と片田舎の風景が映っていた。
「…っ!」
その田舎の風景には見覚えがあった。ちらりと映る町の建物は軒並み半壊している。凄惨な現場、それはまるで──
「これ、この前あった被災地なんだって」
紛うことなく、それは僕が生まれ育った町だった。
「そ、そこって…」
僕の事情を知っているマリーさんの声が上擦る。彼女の綺麗な声がキンとした音に聞こえた。ぐにゃりと床が傾いて、地に足が着いていないような感覚に陥った。倒れないように、バーカウンターに手を着く。
「この配信者の人、東京から被災地まで行ったんだけど──って大丈夫か!?」
「か、魁人くん!?どうしたの!?すごい汗っ…」
そう言われて僕は額に触れる。ものすごい量の汗が指先を濡らした。
だがそれより、僕は歩夢の発言が気になった。
「ち、ちょっと待ってください…東京からって言いました?」
僕は羊さんの心配を遮るように食い気味に歩夢に問う。呼吸が激しくハッハッと乱れるのを感じた。
僕の剣幕に押され、歩夢が引き気味に答えた。
「あ、あぁ…今被災地に行くのが禁止されてる中での行動だから炎上しちゃってるんだけど…」
「な、なんで…!」
「名目は被災支援だと思うよ。実際ボランティアしてる画像も出てる。けど、向こうの人たちもどこか困った表情の人もいたり、十分な支援体制整ってなかったりで…実際のところは売名目当てなところもあるだろうね」
ガンッと頭を何かで打ち付けられたような衝撃。そんな、そんなことがあるのか…。当事者の僕ですら、その土地を赴けていないというのに…。
ベストの胸元を握り締める。激しく鳴る心臓の鼓動すら痛い。
「…うっ……うぅ」
泣いた。馬鹿みたいに涙が出た。声が漏れる。口元に手を当て吐き気を抑える。苦しいとかおかしいとか…いろんな感情と一緒に父や母やその土地での記憶がグルグルと頭を巡る。
催した吐き気を抱えながら動画に映る男を目に焼きつける。悪戯に、心の底に土足で足を踏み入れたその男が浮かべる笑みは、まるで嘲笑うかのような気持ちの悪いものに見えた。
なんだ…なんなんだ…。いったいなんなんだこれ…。
「……っ」
マリーさんが僕を見る。僕はこれ以上、口を開けそうになかった。
「か、魁人くんはね…被災地出身の子なの」
「え!?」
「大震災が起きる前にこっちに越してきて…いろんなものをそこに置いたまま帰れてないの、一度も…」
「嘘っ…じゃあ…」
マリーさんの代わりの説明に、驚いた二人が画面を見て…そして青ざめる。それはそうだ…。この人が炎上している理由…その最たる影響を受けている存在が目の前にいるのだから。
「この人が行けて…僕がそこに帰れない理由はなんなんですか…」
「そ、それは…」
「裏話だけど…私この人に会ったことある。うちのお店に来たんだけど、どんな形であれ注目されればって言ってた…」
羊さんがそう言う。なんだその理由…と思った。黒い黒い感情がふつふつと沸き上がる。人道がないとかそう言う次元じゃない。
「復旧の妨害をしてるわけじゃないけど、規制は強くなるかも」
「また帰れなくなるってこと!?」
「こんなのがバズってしまったら…同じことをする人ができてもおかしくないですから…」
この喫茶店は願いを叶えたい人が集まる場所と噂されているのに、僕の抱えた願いからはどんどん遠ざかる。落ち着くはずの喫茶店の空気がズンと重い。
「…魁人くん」
マリーさんが不安そうに僕を見る。その先を話していいか…迷っているような表情。僕は静かに頷く。二人にはもう話していいと思っているが、今思い出しながら話すのはつらい。
「…魁人くんは、3月の頭にね──」
彼女はそんな僕の様子を見て、経緯を話し始める。御伽噺を読み聞かせるように、1つずつ、綺麗な声で緩やかに。だけどそれは決して夢物語ではない。紛うことのない現実。
徐々に顔色を変えていく羊さんと歩夢。言葉を失う彼らに、いかに自分の置かれた境遇が稀有なものか理解する。
「…じゃあ、お母さんたちには会えてないんだね」
「魁人、もしかして眠れなくなった理由って──」
一頻り聞き終えた歩夢の言葉に、僕は黙って頷いた。
「魁人くんは毎日悪夢を見るんだって。地震の夢、それは今も…」
「…だから毎日働いてるんだ」
「はい…でも久々に見た悪夢じゃない地元が炎上してる配信者でなんて…皮肉なものですね」
自嘲気味に口から言葉がこぼれる。僕の言葉に、皆なにも言えなくなっていた。
「ごめん、こんな動画見せて」
「いえ、大丈夫…です」
敬語すら忘れかける。今の僕は本当に余裕がないんだなと思った。
「魁人くん…」
マリーさんが僕に声をかける。俯いた顔を上げ、彼女を見た。
「…っ」
僕の表情を見て、マリーさんが息を飲んだ。目を丸くする彼女。
僕は今どんな顔をしているのだろう。きっと、新宿の街で独り俯いていた時と同じなんだろう。
「魁人くん!」
すると彼女は意を決したように僕の手を取った。
「私、貴方の住んでいたところに行きたい」
「え?」