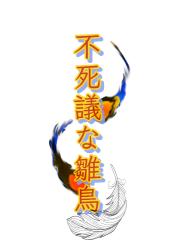* * *
「……うん、よかった!サイズぴったり!」
僕は身に纏った彼女と同じ制服をまじまじと見つめた。
赤を基調としたベストにネクタイ。下に着ている白のYシャツにアクセントとして映える。全国展開しているお店で買った安物の黒のズボンと靴も、喫茶店の制服の一式として非常に馴染んでいた。生まれて初めて飲食店の制服を着たがなかなか様になっているように見えた。
「男物の制服あったのですね」
「ううん、これは私のお古」
「あっ、そうなのですか?」
通りで微かに甘い香りがすると思った。そう聞かされると、喫茶店の香りとはまた違った良い匂いがする。
「嗅いでる?」
「嗅いでません」
「別にいいのに」
「……嗅いでません」
「今少し言い淀んだね」
「そんなことないです」
少し鼻に意識を寄せていたが、からかわれたのですぐにやめた。
偶然再会した翌日の深夜0時。僕は再びマリーさんのお店、Märchenに来ていた。しかし今日は客としてではなく働くため。バイト初日ということになる。喫茶店で働いた経験を持ち合わせていないので、少し緊張していたが、それもだいぶ解れてきた。
「でも…うん。似合ってるよ」
「ありがとうございます」
彼女のおかげもあってか温和な雰囲気だ。話しやすい空間を作る彼女は、喫茶店のオーナーに向いているんだなと思った。
ただ、そんな喫茶店には1つ気になることがあった。
「…気になったんですけど」
「ん?」
「この喫茶店、鏡ないですよね?」
バックヤードの広さは8畳ほど。机やパイプ椅子、オーブンや小さな棚などがある。簡単なキッチンと裏手を兼ね備えている空間。
しかし鏡がないので着替えた姿を見ることはできなかった。
「あー…まぁなんていうか。従業員も私一人しかいないから気にしてなかった」
「でもマリーさんも着替えますよね」
「……覗きたいの?」
「覗きませんし、そういう意味じゃないです。更衣室も兼ねたバックヤードに鏡ないんだなぁと思って」
「…つれないねぇ」
ゆるりと脱線する会話を元に戻しながら問い直す。茶化すときに間が空いたことに、ほんの少しだけ違和感を抱いた。
「…まぁほら、私の家ここの2階だからさ。そっちで着替えるし鏡は置いてないの」
少し目線を外しながら、彼女はそう答えた。どこか歯切れが悪い気がする。なんとなくそう思った。
「……それに鏡は怖いからね」
「怖い?…あ、夜通し営業してるし不意に写り込んだ自分の姿が怖いみたいなことですか?」
「まぁ、そんな感じ」
それなら納得だ。夜に鏡を見るのがなんとなく怖いのはわかる。オーナーをしていたり話し方だったり、大人っぽいところを感じる彼女だったが、案外子供っぽいところもあるんだなと思った。
「…そんなことよりほら!もうシフトの時間なんだから表に行って行って!」
僕を振り向かせながら背中をグイグイと押す。表に出る瞬間ちらりと彼女を見ると、白雪のような顔色がさらに蒼白になっていたような気がした。
──
─
「お酒はこの棚の中に入ってて、紅茶はこっちの茶葉を使って」
「…なるほど」
メモ帳にボールペンで文字を走らせながら、彼女の言葉を拾っていく。
「別にメモ取らなくてもいいのに。たぶん自然と覚えていくものだし」
「いえ、そういうわけには…」
「真面目だねぇ」
そう言ってマリーさんは大袈裟に肩を竦めた。西洋っぽいその仕草はとても自然だ。
「オーナー。これは…ティーポットですか?」
林檎の形をした陶器を指さして訪ねる。
「そう。林檎の形してるの。可愛いでしょ」
そう言って手に取り、顔の前に掲げる。ニコッとした笑顔が照明に映えた。なるほど、ヘタの部分が蓋になっているのか。
「…というかオーナーって呼び方やめてよ」
「そう言われましても。オーナーですし」
「固いってば。あと敬語も気になるなぁ。私たち歳近いし」
「歳上ですから」
「1つしか違わないじゃない」
「学年なら先輩ですよ」
「律儀だなぁ…日本人みたい」
「日本人です」
あははっと朗らかに笑う。茶目っ気の効いたジョークだ。
「でも実際若くしてオーナーなところとか、1つしか違わないとは思えないです」
「老けてるってこと?」
「いい意味で、ですよ。本当はもう少し上だったりしますか?」
「……400歳くらいかな」
「またジョークですかね?そんなわけないじゃないですか」
僕は彼女の冗談にツッコミながら、メモ帳に『オーナーは400歳』と書く。すると──
「っ!」
彼女が僕の頬に手を当てる。ひんやりとした手のひらの感覚。初めて彼女と会った時にもこんな風にされたと思い出しつつ、突然のことだったので驚く。
「な、なにを──」
「本当だよ」
「え?」
「私、ものすごく長く生きてるの」
思わず心臓が跳ねるほど、彼女の表情は真剣そのものだった。吸い込まれそうなほどの黒い髪と瞳。きめ細やかな白い肌。目いっぱいに目に映る彼女の全てが、嘘じゃない、そう言っているような気がした。
「え、いやっ…どういう…」
「……」
「えっ…あ…」
「……ぷっ」
目線を右往左往していると、彼女が声を漏らした。
「ふふふっ…あははっ」
そして目の前にあった目元をふにゃりと歪めて笑った。あまりにも可笑しいという様子で1粒の涙を浮かべている。
「そんな…そんな吃るなんて…ふっ」
「か、からかったんですか!?」
「…当たり前じゃない!そんな生きてるわけないでしょ!くくくっ」
恥ずかしくて頬が熱くなるのを感じる。彼女に触れられていた頬から耳にまで熱がさぁっと伝播した。
「いや、だって!すごい真剣な顔するからっ…!」
「あー、おもしろい。でもやっと表情柔らかくなったね?」
「……え?」
そう言って彼女の表情が、爆笑から優しい微笑みに変わる。
「だって私、魁人くんの悲しい顔か、淡々とした顔しか知らなかったもの。寄り添ってもジョークを言っても、表情は固いまま」
「それは…」
「接客業の基本は笑顔だよ、笑顔」
彼女は自分の口角を指で吊上げて笑顔を作る。にぃーっと声を出しながら。
「わかるよ。魁人くんにとって笑うのが難しいの。今すぐになんて無理なことも知ってる」
「……」
「無神経に言ったんじゃなくてさ、魁人くんが笑えるといいなと思ったの。一緒にいて、笑ってくれたら私は嬉しいなって」
本当にこの人は、一体どこまで優しいのだろうか。慈愛に満ちたそんな姿があまりにも眩しい。
「…ありがとうございます」
「ふふふっ、私がしたいからしてるだけだよ」
彼女の優しさの大元は一体なんなのだろうか。なぜここまで、僕のことがわかるのだろう。歳も生まれも違うのに、彼女には僕の考えていることや抱えていることが手に取るようにわかっているみたいだった。
「…ひとまず、オーナーではなくマリーさんと呼ぶことにします」
「敬語は?」
「それはもう少し経ってからで…」
春先に僕に起きた出来事は、まるで冷え固まった雪のようで…。それを溶かすような彼女の優しさに、できることから1つずつ、きちんと返していこうと思った。
カランカラン…
そんなことを思っていると、喫茶店の扉に着いたベルが鳴った。お客さんが入ってきた合図だ。
「いらっしゃいませ」
「いらっしゃいませ…あっ!」
バイト初日の第一歩。僕は意気込んでいの一番に出迎える。それとほぼ同時、マリーさんも挨拶をしたが、お客さんを見て小さくそんな反応をした。
「メリーさん!久しぶり!来たよ〜!」
「羊さん!」
入ってきたのは華やかに髪を結った金髪の女性だった。ルビー色のドレスに黒のファーのついたコートを身に纏っている。
「最近アフターばっかりで来れなかったの!ごめんねぇ!」
「全然!来てくれるだけで嬉しいもの!」
マリーさんを見るやいなやすぐに彼女の元へ駆け寄り、手を握り合う。きゃいきゃいと盛り上がる女性2人。姦しいと言うと聞こえが悪いが、とても楽しそうだった。
「ささ、魁人くん!ご案内して!」
「は、はい。こちらへどうぞ」
喫茶店に似つかわしくない雰囲気に少し圧倒されながらもお客さん第1号をカウンターにご案内した。
──
─
「初めまして。皇 魁人と申します」
「初めましてー、羊です」
席に案内するとヒラヒラ手を振りながら挨拶してくれる。華やかな格好に似合う明るい女性だなと思った。
「新人さん?メリーさん以外の従業員、初めて見たよ」
「それはそうよ。だって初めて雇ったもの。うちとしても従業員1人目よ」
「へぇ、珍しい!メリーさんが従業員雇うなんて」
彼女の口ぶりから、幾度かここに訪れたことがある様子。常連さんなのだろうか。
というか──
「あの…メリーさんって?マリーさんのことですか?」
羊と名乗るその女性が、マリーさんを呼ぶときの呼び名に違和感を持った。名前、間違ってないか?
「あー、私のニックネームみたいなものなの。そう呼んでくれるのは羊さんだけだけど」
「あだ名ですか、なるほど。…なんでメリーさんなんですか?」
「初めて名前聞いた時そう聞こえたから!」
僕の問いに羊さんが答える。
「Marie…メリー…。確かに聞こえなくもないですね」
「でしょ?それにほら、私の羊って名前とメリーって繋がりあるじゃない?」
「メリーさんのひつじ的な?」
「そうそう!わかるねぇ、君。えーっと、魁人くん!」
羊さんが親指を立ててサムズアップ。ノリが軽い、というか若い。僕よりは上に見え、マリーさんともそう歳は遠くなく見えるが、彼女とはまた違った明るさだ。なんというか、陽の者という印象。
「友達みたいで私は嬉しいわ。…魁人くんも呼んでいいよ?」
「いえ、やめときます」
「なんで?」
「あだ名で呼ぶのは…オーナーですし」
「だからそんなの気にしなくていいってば」
「魁人くんは真面目な人なんだね」
「でしょ?日本人みたい」
「ほんとね」
「そりゃ日本人ですから」
先程披露したばかりの小粋なジョークにも即座に乗っかれる羊さん。コミュニケーション能力はものすごく高いようだ。僕は昔から交友関係も広くないので、そういう社交性は純粋に羨ましい。
「羊さんって名前も珍しいですよね」
「まぁ、源氏名だからね」
「源氏名…」
「彼女は近くのキャバクラで働いてるの」
「なるほど」
だからさっきアフターがどうとかと言っていたのか。お酒が飲める年齢でもないし、その辺の知識にはどうも疎かった。
「…すごいですね。初めましての人とお酒飲みながら話すのは…純粋に僕は尊敬します」
「……おぉ」
「え?」
「いや、キャバ嬢って偏見持たれがちだからさ。お店以外の場所でそんな風に言ってくれるのは嬉しいなと思って」
「そうでしょうか?」
「君は優しいねぇ」
「きっと普通ですよ」
「若いのに人たらしだ」
「わかるわ、魁人くんはこう…邪気がないのよね」
それは褒められてるのだろうか。見ようによっては漢気がないとも見える気もする。
「あ、漢気がないとかじゃないからね」
「…なんでわかったんですか」
「ははっ、魁人くんめっちゃ面白い。あ、メリーさん、私いつもの頂戴」
「ふふふっ。かしこまりました」
マリーさんにそう言われ、僕は思わず頬を触った。心をあっさり読まれて驚く。僕は顔に出やすいのか、気をつけよう。
そんな会話の最中、羊さんはいつものと何かを頼んだ。
「…私の名前の由来ね、苗字から取ってるの」
「苗字?」
「そういえば私も聞いたことなかったわ」
「そうだっけ?…本当の名前は、日辻 洋花っていうの」
「珍しい苗字ですね」
「魁人くん、そうなの?」
「はい、あまり聞かないとは思います」
マリーさんが背にした棚に向きつつ、僕にそう尋ねる。喫茶店だがバーの側面も兼ねているようで、ズラっと並んだお酒の瓶から彼女は1本を手に取った。
「言うてもスメラギって苗字も珍しくない?」
「まぁ…そうですね」
「漢字でどう書くの?」
「白に王って書きます。皇族の『コウ』の字ですね」
「皇族…?」
馴れた手つきでシャンパングラスにお酒を注ぎながら、マリーさんがピクリと反応する。
「魁人くん、王子様なの?」
「字的にはそうかもですけど、一般人です」
「高貴な人が夜更かしかぁー?」
「違いますよ」
「王子様、お忍びで働きに来てくれてる?」
「だから違いますって」
「ツッコミ早っ。めっちゃ面白い」
2人の女性にからかわれる。まぁ名前負けしてるのはわかるが…本当に王族ならからかいは不敬だと思いますよ。
「…お待たせました。シードルです」
「ありがとー」
マリーさんは僕をからかいながらも手は止めずに、しっかりご提供する。手馴れている。
「それ、お酒ですよね?お店でも飲んできたのではないですか?」
「そりゃあ飲んだけど、あーいうのじゃ全然酔えないのよ。魁人くんも大人になったらわかるよ」
「僕、歳言いましたっけ?」
「言ってないけどわかるわ。これでもたくさんの人に接客してるからねぇ」
羊さんは経験から僕が年下だとすぐ見抜いていたようだ。そういう言わなくても察して把握するところは、大学生になりたての僕には大きな存在に思えた。大人ってすごい、そう思う。
「シードルってどんなお酒なんですか?」
「飲む?」
「羊さん?うちの未成年の従業員拐かすのやめてくれるかしら?」
「嘘嘘、冗談。わかってるってば」
羊さんがクッとグラスを煽る。優雅、そんな言葉が似合った。
ここの喫茶店の雰囲気は、新宿という夜の街とは少し違っていた。緩やかに流れる時間は心地の良い雰囲気を持っている。不思議だ。
「シードルはね、林檎のお酒なの」
「ここのはすごく美味しいんだよ。銘柄は見た事ないやつだけど」
「Märchen特製なの。美味しいと言ってくれて何よりだわ」
「初めて来た時からずっとこれ飲んでるから、もうメリーさんに胃袋掴まれちゃったなぁ」
「結婚する?」
「幸せにしてくれるなら」
仲がいいんだな。お客さんと店員の関係じゃないみたいだ。
「羊さんは常連さんなんですね」
「毎日来てるわけじゃないから常連って響きが合ってるかはわからないけどね」
「えー、羊さんは紛うことなく常連よ。このお店の初めてのお客さんだし」
「そうなのですか?」
「えぇ、そうよ。だから羊さんとはかれこれ2ヶ月くらいの仲になるわ」
「あの頃のメリーさんは初々しかったねぇ」
「…いや、想像できませんね。というかたぶんそれは羊さんの嘘ですよね」
「なんでわかるのよ」
マリーさんはなんとなく、初めての喫茶店経営でも卒なくこなすと思う。彼女にはそんな安心感があるのだ。
「じゃあここが願いの叶う喫茶店って呼ばれていることもご存知なのですか?」
「そうね、噂になってるわ。私のお店でも聞くもの」
「そんなに広まってるのね」
「僕もその噂がきっかけでここに来れましたからね」
「でもなかなか場所が見つからないって言ってたよ。ゴールデン街を抜けた先にあるよーって言うんだけどね」
現に僕もいつの間にか着いていたお店だ。見つけるのは難しいかもしれない。僕自身気がついたらお店にいたようなものだ。
昨日お客としてきて退店したとき、マリーさんに「外に出て路地を右手に出ると帰れる」と教えられた。明るくなった明け方に店を出て言われた通りに進むと、ゴールデン街と呼ばれる飲み屋が立ち並ぶ通りに出ることができた。僕が来た四季の路とどう繋がってるのか実はまだよくわかっていない。
「私も贔屓にしてるお店だから少しでも売上に貢献したくて宣伝するんだけど、着かないんだってさ」
「……不思議なものね」
少しの間を空け、マリーさんが子首を傾げる。
「…こうやってお店は有名になってくものなんですかね?」
「どうかしらね?」
「んー、有名になって欲しい反面、一客の私としてはこのままでいて欲しいとも思ったりするかなぁ」
羊さんが顎に指を添えてそう言う。
「この静かな雰囲気がなくなっちゃうのはちょっと寂しい気もするからね」
「…わかる気はしますね」
「あら、魁人くん。従業員としてその発言はどうなの?」
「そうなんですけど、いい意味で夜の街らしくないので…。ゆったり流れる時間は大切にしたいなと思って」
「魁人くん、いいこと言うじゃん」
僕の発言にマリーさんと羊さんが微笑む。優しげな2人の表情は系統は違えどどちらも美しいものだった。
「…まぁ、このままでいたいと思うわね。人がたくさん来ることはないと思うわ」
「どうしてですか?」
「んー、なんとなく、かな」
マリーさんは何かを含みながらそう答えた。きっとオーナーとして大切にしたいお店の雰囲気とかあるんだろうな。
カランカラン
「あら?」
そう言った矢先、また扉のベルがなった。
「……ごめんください」
「あれ、君は…」
入って来た人に、僕は見覚えがあった
「あっ!…えーっとあの、願いが叶う喫茶店ってここですか?」
一人の男性。彼は僕を見て声を漏らし、戸惑いながらそう言った。
──
─
「…まさか君が働いているなんて」
「僕も驚きました」
羊さんの隣に案内された彼は座ってそう話す。入る瞬間は少し強ばっていたが、僕の顔を見て安心したような顔つきになった。
「魁人くん、お知り合い?」
「同じ大学の人です。…知り合いと言っても話したのはつい昨日ですけど」
背格好が同じくらいの男の子。それは僕にここのお店を教えてくれた張本人だった。
「そうだよね。まさかこんなところで会えると思わなかったから…ごめん、名前は──」
「皇 魁人って言います。えっと、大学一年生で…」
「あ、じゃあ俺と同じだ。俺は朴木 歩夢。よろしく」
「よろしく、朴木くん」
「歩夢でいいよ」
「あ、うん。わかりました」
歩夢に名前で呼ぶよう促されたが、今はあくまで店員の立場。ひとまず敬語で返した。
「真面目ねぇ」
「日本人みたい」
「日本人です」
マリーさん、このネタ好きだな。
「…それでここに来た理由って──」
「願いの叶う喫茶店を探してたら偶然」
「ちょうど私達もその話題で盛り上がってたの。そんな風に呼ばれてるんだよーって」
「ということはここが…」
「まぁ、一応そう噂されてはいるわ。お飲み物はどうする?」
マリーさんはそんな会話の中で飲み物を聞く。歩夢はカフェオレでと控えめに頼んだ。こんな時間にカフェインを摂ったら眠れなくなってしまうのでは?と場違いな感想を抱いた。
「魁人も人が悪いな。昨日聞いてきた噂のお店で働いてるなんて」
「いえ、昨日初めて来て流れで働くことになったので…」
「まだ敬語。友達なんでしょ?」
「魁人くん、ウケる」
「友達という程では…あと何が面白いんですか」
マリーさんと羊さんそれぞれに返す。羊さんは全部拾うじゃんと言ってまた笑った。
「友達でいいじゃんか。同い年だし同じ大学だし」
「まだそんなに会話してないのにですか?」
「会話の量なんて関係ある?大学でも話したし、ここでも会えたしそれはもう友達だよ。嫌ならやめるけど」
「嫌じゃないですよ」
「じゃあ学校でもよろしくな」
「…うん」
大学で話した時はわからなかったが、歩夢はかなり気さくな人なようだ。ここに迷い込んでから、なんだかトントンと交友関係が広がっている。独りじゃないと思ってもいいような暖かさ。ここで働けてよかった。
「あの…それで、願いを叶えるって噂は…」
「残念ながら眉唾物ね…」
「そうですよね…」
彼が本題をと言った具合で切り込むも、マリーさんの言葉を聞いて俯いた。その姿を反射するミルクの入ったカフェオレが少し汚れて見えた。
「叶えられるかわからないけど、歩夢くんの願いってどんなことなの?」
マリーさんがそう尋ねる。森のような店内の空気が彼女の一言で澄んだような気がした。まるで木々が呼吸をするように。
「俺、妹がいるんです。妹は少し難しい病気なんです」
「あら…それは…」
「治らない病気なの?」
「完治は難しくて、改善しても病気と付き合って生きていくしかないそうです。薬ができればとはお医者さんは言っていたのですが…」
「そうなんだ…」
緩やかな空間にどんよりとした空気が滲む。大雪前の曇天のような鈍色だった。
「それもあって、俺は薬学部なんです。本当は医学部が良かったんですけど…」
「あ、そっか。僕たちの大学、理系も同じキャンパスですよね。妹さんは入院とかしてるんですか?」
「ううん。今は容態が安定してるから実家にいるよ。でも5年生きられる確率は3割くらいで、10年になると2割くらいになるらしい」
「そんな…」
彼の抱える願いは想像以上に大きなものだった。家族がいなくなるのを止められない無力感はなによりも辛いことだろう。僕もそうだったのだから…。
「…願いは妹さんの病気を治すこと?」
マリーさんがそんな沈んだ空気に切込む。彼女のその口ぶりは、まるで本当に願いを叶えてくれるかのようだった。
「……」
彼女の問いに、歩夢は少し黙ってしまった。
「…自分でもよくわからないです。もちろん治って欲しいのに間違いはないです。それこそ、噂に縋ってしまうくらいには」
「……」
「……」
なんとなく言い淀む気持ちがわかった。僕も家族が見つかって欲しいのは間違いないが、それが全てかと言ったら少し疑問が残る。独りじゃないと思いたい気持ちもあり、感情がごちゃ混ぜになっている。僕自身がどうしたいのかも、自分のことなのに真意はわからない。
羊さんも同じように黙っていた。彼女が僕と同じ思いを持っているのかはわからないが、神妙な面持ちではあった。
「…願い、はっきりするといいね」
マリーさんは悲しそうにそう呟く。歩夢の複雑な感情を知り、自分まで心を痛めているようだった。まるで、願いが叶うというのが本当だと錯覚するほどに、彼女の苦い顔が喫茶店の照明が、夜の雪明りのように侘しく彼女を照らす。
「…でも今は落ち着いてるんだよね?」
「そうですね」
暗くなった空気の中で羊さんが歩夢に尋ねる。声色はふわりと柔らかい。
「そしたらさ。妹さんのこと、もっと聞かせてよ」
「もっとですか?」
「そ。できれば暗い話じゃなくて、何が好きとかどんな性格でとか、いろんな話」
「大雑把ですね」
「あははっ、そうかも。でもよくない?たまたま集まった人たちがする四方山話なんてそのくらいでさ」
彼女の言葉に、喫茶店の空気がほんの少し明るくなる。
「どうせ話すなら楽しい話なんて無責任に言ってるんじゃなくて、そういう真剣な話こそ、なんでもないことに目を向けたいなーって」
「……」
「大切な人をどう思うか、話してるとまとまってくると思うし!どれだけ想い、どうしたいのか。……その方が腹も決まると思うから」
羊さんがグラスを傾けてシードルを飲み干す。最後の一言はどこか遠い目をしていて、歩夢だけでなく自分にも言っているように聞こえた。
「…そうですね。聞いてくれますか?」
「えぇ、もちろん」
「妹は昔から──」
羊さんの放つ心地よい空気に当てられ、歩夢が微笑みながら話し始める。キャバ嬢は偏見で見られるなんて卑下していたが、今の彼女にそんな言葉をかけるのは失礼だと思う。きっといろんな人にこうして優しく接しているのだろうな。
「羊さん、素敵な人ですね」
「…でしょ?」
ぽつりと僕の口からこぼれた言葉に、マリーさんが空いたグラスを下げながら微笑んで反応した。
「……うん、よかった!サイズぴったり!」
僕は身に纏った彼女と同じ制服をまじまじと見つめた。
赤を基調としたベストにネクタイ。下に着ている白のYシャツにアクセントとして映える。全国展開しているお店で買った安物の黒のズボンと靴も、喫茶店の制服の一式として非常に馴染んでいた。生まれて初めて飲食店の制服を着たがなかなか様になっているように見えた。
「男物の制服あったのですね」
「ううん、これは私のお古」
「あっ、そうなのですか?」
通りで微かに甘い香りがすると思った。そう聞かされると、喫茶店の香りとはまた違った良い匂いがする。
「嗅いでる?」
「嗅いでません」
「別にいいのに」
「……嗅いでません」
「今少し言い淀んだね」
「そんなことないです」
少し鼻に意識を寄せていたが、からかわれたのですぐにやめた。
偶然再会した翌日の深夜0時。僕は再びマリーさんのお店、Märchenに来ていた。しかし今日は客としてではなく働くため。バイト初日ということになる。喫茶店で働いた経験を持ち合わせていないので、少し緊張していたが、それもだいぶ解れてきた。
「でも…うん。似合ってるよ」
「ありがとうございます」
彼女のおかげもあってか温和な雰囲気だ。話しやすい空間を作る彼女は、喫茶店のオーナーに向いているんだなと思った。
ただ、そんな喫茶店には1つ気になることがあった。
「…気になったんですけど」
「ん?」
「この喫茶店、鏡ないですよね?」
バックヤードの広さは8畳ほど。机やパイプ椅子、オーブンや小さな棚などがある。簡単なキッチンと裏手を兼ね備えている空間。
しかし鏡がないので着替えた姿を見ることはできなかった。
「あー…まぁなんていうか。従業員も私一人しかいないから気にしてなかった」
「でもマリーさんも着替えますよね」
「……覗きたいの?」
「覗きませんし、そういう意味じゃないです。更衣室も兼ねたバックヤードに鏡ないんだなぁと思って」
「…つれないねぇ」
ゆるりと脱線する会話を元に戻しながら問い直す。茶化すときに間が空いたことに、ほんの少しだけ違和感を抱いた。
「…まぁほら、私の家ここの2階だからさ。そっちで着替えるし鏡は置いてないの」
少し目線を外しながら、彼女はそう答えた。どこか歯切れが悪い気がする。なんとなくそう思った。
「……それに鏡は怖いからね」
「怖い?…あ、夜通し営業してるし不意に写り込んだ自分の姿が怖いみたいなことですか?」
「まぁ、そんな感じ」
それなら納得だ。夜に鏡を見るのがなんとなく怖いのはわかる。オーナーをしていたり話し方だったり、大人っぽいところを感じる彼女だったが、案外子供っぽいところもあるんだなと思った。
「…そんなことよりほら!もうシフトの時間なんだから表に行って行って!」
僕を振り向かせながら背中をグイグイと押す。表に出る瞬間ちらりと彼女を見ると、白雪のような顔色がさらに蒼白になっていたような気がした。
──
─
「お酒はこの棚の中に入ってて、紅茶はこっちの茶葉を使って」
「…なるほど」
メモ帳にボールペンで文字を走らせながら、彼女の言葉を拾っていく。
「別にメモ取らなくてもいいのに。たぶん自然と覚えていくものだし」
「いえ、そういうわけには…」
「真面目だねぇ」
そう言ってマリーさんは大袈裟に肩を竦めた。西洋っぽいその仕草はとても自然だ。
「オーナー。これは…ティーポットですか?」
林檎の形をした陶器を指さして訪ねる。
「そう。林檎の形してるの。可愛いでしょ」
そう言って手に取り、顔の前に掲げる。ニコッとした笑顔が照明に映えた。なるほど、ヘタの部分が蓋になっているのか。
「…というかオーナーって呼び方やめてよ」
「そう言われましても。オーナーですし」
「固いってば。あと敬語も気になるなぁ。私たち歳近いし」
「歳上ですから」
「1つしか違わないじゃない」
「学年なら先輩ですよ」
「律儀だなぁ…日本人みたい」
「日本人です」
あははっと朗らかに笑う。茶目っ気の効いたジョークだ。
「でも実際若くしてオーナーなところとか、1つしか違わないとは思えないです」
「老けてるってこと?」
「いい意味で、ですよ。本当はもう少し上だったりしますか?」
「……400歳くらいかな」
「またジョークですかね?そんなわけないじゃないですか」
僕は彼女の冗談にツッコミながら、メモ帳に『オーナーは400歳』と書く。すると──
「っ!」
彼女が僕の頬に手を当てる。ひんやりとした手のひらの感覚。初めて彼女と会った時にもこんな風にされたと思い出しつつ、突然のことだったので驚く。
「な、なにを──」
「本当だよ」
「え?」
「私、ものすごく長く生きてるの」
思わず心臓が跳ねるほど、彼女の表情は真剣そのものだった。吸い込まれそうなほどの黒い髪と瞳。きめ細やかな白い肌。目いっぱいに目に映る彼女の全てが、嘘じゃない、そう言っているような気がした。
「え、いやっ…どういう…」
「……」
「えっ…あ…」
「……ぷっ」
目線を右往左往していると、彼女が声を漏らした。
「ふふふっ…あははっ」
そして目の前にあった目元をふにゃりと歪めて笑った。あまりにも可笑しいという様子で1粒の涙を浮かべている。
「そんな…そんな吃るなんて…ふっ」
「か、からかったんですか!?」
「…当たり前じゃない!そんな生きてるわけないでしょ!くくくっ」
恥ずかしくて頬が熱くなるのを感じる。彼女に触れられていた頬から耳にまで熱がさぁっと伝播した。
「いや、だって!すごい真剣な顔するからっ…!」
「あー、おもしろい。でもやっと表情柔らかくなったね?」
「……え?」
そう言って彼女の表情が、爆笑から優しい微笑みに変わる。
「だって私、魁人くんの悲しい顔か、淡々とした顔しか知らなかったもの。寄り添ってもジョークを言っても、表情は固いまま」
「それは…」
「接客業の基本は笑顔だよ、笑顔」
彼女は自分の口角を指で吊上げて笑顔を作る。にぃーっと声を出しながら。
「わかるよ。魁人くんにとって笑うのが難しいの。今すぐになんて無理なことも知ってる」
「……」
「無神経に言ったんじゃなくてさ、魁人くんが笑えるといいなと思ったの。一緒にいて、笑ってくれたら私は嬉しいなって」
本当にこの人は、一体どこまで優しいのだろうか。慈愛に満ちたそんな姿があまりにも眩しい。
「…ありがとうございます」
「ふふふっ、私がしたいからしてるだけだよ」
彼女の優しさの大元は一体なんなのだろうか。なぜここまで、僕のことがわかるのだろう。歳も生まれも違うのに、彼女には僕の考えていることや抱えていることが手に取るようにわかっているみたいだった。
「…ひとまず、オーナーではなくマリーさんと呼ぶことにします」
「敬語は?」
「それはもう少し経ってからで…」
春先に僕に起きた出来事は、まるで冷え固まった雪のようで…。それを溶かすような彼女の優しさに、できることから1つずつ、きちんと返していこうと思った。
カランカラン…
そんなことを思っていると、喫茶店の扉に着いたベルが鳴った。お客さんが入ってきた合図だ。
「いらっしゃいませ」
「いらっしゃいませ…あっ!」
バイト初日の第一歩。僕は意気込んでいの一番に出迎える。それとほぼ同時、マリーさんも挨拶をしたが、お客さんを見て小さくそんな反応をした。
「メリーさん!久しぶり!来たよ〜!」
「羊さん!」
入ってきたのは華やかに髪を結った金髪の女性だった。ルビー色のドレスに黒のファーのついたコートを身に纏っている。
「最近アフターばっかりで来れなかったの!ごめんねぇ!」
「全然!来てくれるだけで嬉しいもの!」
マリーさんを見るやいなやすぐに彼女の元へ駆け寄り、手を握り合う。きゃいきゃいと盛り上がる女性2人。姦しいと言うと聞こえが悪いが、とても楽しそうだった。
「ささ、魁人くん!ご案内して!」
「は、はい。こちらへどうぞ」
喫茶店に似つかわしくない雰囲気に少し圧倒されながらもお客さん第1号をカウンターにご案内した。
──
─
「初めまして。皇 魁人と申します」
「初めましてー、羊です」
席に案内するとヒラヒラ手を振りながら挨拶してくれる。華やかな格好に似合う明るい女性だなと思った。
「新人さん?メリーさん以外の従業員、初めて見たよ」
「それはそうよ。だって初めて雇ったもの。うちとしても従業員1人目よ」
「へぇ、珍しい!メリーさんが従業員雇うなんて」
彼女の口ぶりから、幾度かここに訪れたことがある様子。常連さんなのだろうか。
というか──
「あの…メリーさんって?マリーさんのことですか?」
羊と名乗るその女性が、マリーさんを呼ぶときの呼び名に違和感を持った。名前、間違ってないか?
「あー、私のニックネームみたいなものなの。そう呼んでくれるのは羊さんだけだけど」
「あだ名ですか、なるほど。…なんでメリーさんなんですか?」
「初めて名前聞いた時そう聞こえたから!」
僕の問いに羊さんが答える。
「Marie…メリー…。確かに聞こえなくもないですね」
「でしょ?それにほら、私の羊って名前とメリーって繋がりあるじゃない?」
「メリーさんのひつじ的な?」
「そうそう!わかるねぇ、君。えーっと、魁人くん!」
羊さんが親指を立ててサムズアップ。ノリが軽い、というか若い。僕よりは上に見え、マリーさんともそう歳は遠くなく見えるが、彼女とはまた違った明るさだ。なんというか、陽の者という印象。
「友達みたいで私は嬉しいわ。…魁人くんも呼んでいいよ?」
「いえ、やめときます」
「なんで?」
「あだ名で呼ぶのは…オーナーですし」
「だからそんなの気にしなくていいってば」
「魁人くんは真面目な人なんだね」
「でしょ?日本人みたい」
「ほんとね」
「そりゃ日本人ですから」
先程披露したばかりの小粋なジョークにも即座に乗っかれる羊さん。コミュニケーション能力はものすごく高いようだ。僕は昔から交友関係も広くないので、そういう社交性は純粋に羨ましい。
「羊さんって名前も珍しいですよね」
「まぁ、源氏名だからね」
「源氏名…」
「彼女は近くのキャバクラで働いてるの」
「なるほど」
だからさっきアフターがどうとかと言っていたのか。お酒が飲める年齢でもないし、その辺の知識にはどうも疎かった。
「…すごいですね。初めましての人とお酒飲みながら話すのは…純粋に僕は尊敬します」
「……おぉ」
「え?」
「いや、キャバ嬢って偏見持たれがちだからさ。お店以外の場所でそんな風に言ってくれるのは嬉しいなと思って」
「そうでしょうか?」
「君は優しいねぇ」
「きっと普通ですよ」
「若いのに人たらしだ」
「わかるわ、魁人くんはこう…邪気がないのよね」
それは褒められてるのだろうか。見ようによっては漢気がないとも見える気もする。
「あ、漢気がないとかじゃないからね」
「…なんでわかったんですか」
「ははっ、魁人くんめっちゃ面白い。あ、メリーさん、私いつもの頂戴」
「ふふふっ。かしこまりました」
マリーさんにそう言われ、僕は思わず頬を触った。心をあっさり読まれて驚く。僕は顔に出やすいのか、気をつけよう。
そんな会話の最中、羊さんはいつものと何かを頼んだ。
「…私の名前の由来ね、苗字から取ってるの」
「苗字?」
「そういえば私も聞いたことなかったわ」
「そうだっけ?…本当の名前は、日辻 洋花っていうの」
「珍しい苗字ですね」
「魁人くん、そうなの?」
「はい、あまり聞かないとは思います」
マリーさんが背にした棚に向きつつ、僕にそう尋ねる。喫茶店だがバーの側面も兼ねているようで、ズラっと並んだお酒の瓶から彼女は1本を手に取った。
「言うてもスメラギって苗字も珍しくない?」
「まぁ…そうですね」
「漢字でどう書くの?」
「白に王って書きます。皇族の『コウ』の字ですね」
「皇族…?」
馴れた手つきでシャンパングラスにお酒を注ぎながら、マリーさんがピクリと反応する。
「魁人くん、王子様なの?」
「字的にはそうかもですけど、一般人です」
「高貴な人が夜更かしかぁー?」
「違いますよ」
「王子様、お忍びで働きに来てくれてる?」
「だから違いますって」
「ツッコミ早っ。めっちゃ面白い」
2人の女性にからかわれる。まぁ名前負けしてるのはわかるが…本当に王族ならからかいは不敬だと思いますよ。
「…お待たせました。シードルです」
「ありがとー」
マリーさんは僕をからかいながらも手は止めずに、しっかりご提供する。手馴れている。
「それ、お酒ですよね?お店でも飲んできたのではないですか?」
「そりゃあ飲んだけど、あーいうのじゃ全然酔えないのよ。魁人くんも大人になったらわかるよ」
「僕、歳言いましたっけ?」
「言ってないけどわかるわ。これでもたくさんの人に接客してるからねぇ」
羊さんは経験から僕が年下だとすぐ見抜いていたようだ。そういう言わなくても察して把握するところは、大学生になりたての僕には大きな存在に思えた。大人ってすごい、そう思う。
「シードルってどんなお酒なんですか?」
「飲む?」
「羊さん?うちの未成年の従業員拐かすのやめてくれるかしら?」
「嘘嘘、冗談。わかってるってば」
羊さんがクッとグラスを煽る。優雅、そんな言葉が似合った。
ここの喫茶店の雰囲気は、新宿という夜の街とは少し違っていた。緩やかに流れる時間は心地の良い雰囲気を持っている。不思議だ。
「シードルはね、林檎のお酒なの」
「ここのはすごく美味しいんだよ。銘柄は見た事ないやつだけど」
「Märchen特製なの。美味しいと言ってくれて何よりだわ」
「初めて来た時からずっとこれ飲んでるから、もうメリーさんに胃袋掴まれちゃったなぁ」
「結婚する?」
「幸せにしてくれるなら」
仲がいいんだな。お客さんと店員の関係じゃないみたいだ。
「羊さんは常連さんなんですね」
「毎日来てるわけじゃないから常連って響きが合ってるかはわからないけどね」
「えー、羊さんは紛うことなく常連よ。このお店の初めてのお客さんだし」
「そうなのですか?」
「えぇ、そうよ。だから羊さんとはかれこれ2ヶ月くらいの仲になるわ」
「あの頃のメリーさんは初々しかったねぇ」
「…いや、想像できませんね。というかたぶんそれは羊さんの嘘ですよね」
「なんでわかるのよ」
マリーさんはなんとなく、初めての喫茶店経営でも卒なくこなすと思う。彼女にはそんな安心感があるのだ。
「じゃあここが願いの叶う喫茶店って呼ばれていることもご存知なのですか?」
「そうね、噂になってるわ。私のお店でも聞くもの」
「そんなに広まってるのね」
「僕もその噂がきっかけでここに来れましたからね」
「でもなかなか場所が見つからないって言ってたよ。ゴールデン街を抜けた先にあるよーって言うんだけどね」
現に僕もいつの間にか着いていたお店だ。見つけるのは難しいかもしれない。僕自身気がついたらお店にいたようなものだ。
昨日お客としてきて退店したとき、マリーさんに「外に出て路地を右手に出ると帰れる」と教えられた。明るくなった明け方に店を出て言われた通りに進むと、ゴールデン街と呼ばれる飲み屋が立ち並ぶ通りに出ることができた。僕が来た四季の路とどう繋がってるのか実はまだよくわかっていない。
「私も贔屓にしてるお店だから少しでも売上に貢献したくて宣伝するんだけど、着かないんだってさ」
「……不思議なものね」
少しの間を空け、マリーさんが子首を傾げる。
「…こうやってお店は有名になってくものなんですかね?」
「どうかしらね?」
「んー、有名になって欲しい反面、一客の私としてはこのままでいて欲しいとも思ったりするかなぁ」
羊さんが顎に指を添えてそう言う。
「この静かな雰囲気がなくなっちゃうのはちょっと寂しい気もするからね」
「…わかる気はしますね」
「あら、魁人くん。従業員としてその発言はどうなの?」
「そうなんですけど、いい意味で夜の街らしくないので…。ゆったり流れる時間は大切にしたいなと思って」
「魁人くん、いいこと言うじゃん」
僕の発言にマリーさんと羊さんが微笑む。優しげな2人の表情は系統は違えどどちらも美しいものだった。
「…まぁ、このままでいたいと思うわね。人がたくさん来ることはないと思うわ」
「どうしてですか?」
「んー、なんとなく、かな」
マリーさんは何かを含みながらそう答えた。きっとオーナーとして大切にしたいお店の雰囲気とかあるんだろうな。
カランカラン
「あら?」
そう言った矢先、また扉のベルがなった。
「……ごめんください」
「あれ、君は…」
入って来た人に、僕は見覚えがあった
「あっ!…えーっとあの、願いが叶う喫茶店ってここですか?」
一人の男性。彼は僕を見て声を漏らし、戸惑いながらそう言った。
──
─
「…まさか君が働いているなんて」
「僕も驚きました」
羊さんの隣に案内された彼は座ってそう話す。入る瞬間は少し強ばっていたが、僕の顔を見て安心したような顔つきになった。
「魁人くん、お知り合い?」
「同じ大学の人です。…知り合いと言っても話したのはつい昨日ですけど」
背格好が同じくらいの男の子。それは僕にここのお店を教えてくれた張本人だった。
「そうだよね。まさかこんなところで会えると思わなかったから…ごめん、名前は──」
「皇 魁人って言います。えっと、大学一年生で…」
「あ、じゃあ俺と同じだ。俺は朴木 歩夢。よろしく」
「よろしく、朴木くん」
「歩夢でいいよ」
「あ、うん。わかりました」
歩夢に名前で呼ぶよう促されたが、今はあくまで店員の立場。ひとまず敬語で返した。
「真面目ねぇ」
「日本人みたい」
「日本人です」
マリーさん、このネタ好きだな。
「…それでここに来た理由って──」
「願いの叶う喫茶店を探してたら偶然」
「ちょうど私達もその話題で盛り上がってたの。そんな風に呼ばれてるんだよーって」
「ということはここが…」
「まぁ、一応そう噂されてはいるわ。お飲み物はどうする?」
マリーさんはそんな会話の中で飲み物を聞く。歩夢はカフェオレでと控えめに頼んだ。こんな時間にカフェインを摂ったら眠れなくなってしまうのでは?と場違いな感想を抱いた。
「魁人も人が悪いな。昨日聞いてきた噂のお店で働いてるなんて」
「いえ、昨日初めて来て流れで働くことになったので…」
「まだ敬語。友達なんでしょ?」
「魁人くん、ウケる」
「友達という程では…あと何が面白いんですか」
マリーさんと羊さんそれぞれに返す。羊さんは全部拾うじゃんと言ってまた笑った。
「友達でいいじゃんか。同い年だし同じ大学だし」
「まだそんなに会話してないのにですか?」
「会話の量なんて関係ある?大学でも話したし、ここでも会えたしそれはもう友達だよ。嫌ならやめるけど」
「嫌じゃないですよ」
「じゃあ学校でもよろしくな」
「…うん」
大学で話した時はわからなかったが、歩夢はかなり気さくな人なようだ。ここに迷い込んでから、なんだかトントンと交友関係が広がっている。独りじゃないと思ってもいいような暖かさ。ここで働けてよかった。
「あの…それで、願いを叶えるって噂は…」
「残念ながら眉唾物ね…」
「そうですよね…」
彼が本題をと言った具合で切り込むも、マリーさんの言葉を聞いて俯いた。その姿を反射するミルクの入ったカフェオレが少し汚れて見えた。
「叶えられるかわからないけど、歩夢くんの願いってどんなことなの?」
マリーさんがそう尋ねる。森のような店内の空気が彼女の一言で澄んだような気がした。まるで木々が呼吸をするように。
「俺、妹がいるんです。妹は少し難しい病気なんです」
「あら…それは…」
「治らない病気なの?」
「完治は難しくて、改善しても病気と付き合って生きていくしかないそうです。薬ができればとはお医者さんは言っていたのですが…」
「そうなんだ…」
緩やかな空間にどんよりとした空気が滲む。大雪前の曇天のような鈍色だった。
「それもあって、俺は薬学部なんです。本当は医学部が良かったんですけど…」
「あ、そっか。僕たちの大学、理系も同じキャンパスですよね。妹さんは入院とかしてるんですか?」
「ううん。今は容態が安定してるから実家にいるよ。でも5年生きられる確率は3割くらいで、10年になると2割くらいになるらしい」
「そんな…」
彼の抱える願いは想像以上に大きなものだった。家族がいなくなるのを止められない無力感はなによりも辛いことだろう。僕もそうだったのだから…。
「…願いは妹さんの病気を治すこと?」
マリーさんがそんな沈んだ空気に切込む。彼女のその口ぶりは、まるで本当に願いを叶えてくれるかのようだった。
「……」
彼女の問いに、歩夢は少し黙ってしまった。
「…自分でもよくわからないです。もちろん治って欲しいのに間違いはないです。それこそ、噂に縋ってしまうくらいには」
「……」
「……」
なんとなく言い淀む気持ちがわかった。僕も家族が見つかって欲しいのは間違いないが、それが全てかと言ったら少し疑問が残る。独りじゃないと思いたい気持ちもあり、感情がごちゃ混ぜになっている。僕自身がどうしたいのかも、自分のことなのに真意はわからない。
羊さんも同じように黙っていた。彼女が僕と同じ思いを持っているのかはわからないが、神妙な面持ちではあった。
「…願い、はっきりするといいね」
マリーさんは悲しそうにそう呟く。歩夢の複雑な感情を知り、自分まで心を痛めているようだった。まるで、願いが叶うというのが本当だと錯覚するほどに、彼女の苦い顔が喫茶店の照明が、夜の雪明りのように侘しく彼女を照らす。
「…でも今は落ち着いてるんだよね?」
「そうですね」
暗くなった空気の中で羊さんが歩夢に尋ねる。声色はふわりと柔らかい。
「そしたらさ。妹さんのこと、もっと聞かせてよ」
「もっとですか?」
「そ。できれば暗い話じゃなくて、何が好きとかどんな性格でとか、いろんな話」
「大雑把ですね」
「あははっ、そうかも。でもよくない?たまたま集まった人たちがする四方山話なんてそのくらいでさ」
彼女の言葉に、喫茶店の空気がほんの少し明るくなる。
「どうせ話すなら楽しい話なんて無責任に言ってるんじゃなくて、そういう真剣な話こそ、なんでもないことに目を向けたいなーって」
「……」
「大切な人をどう思うか、話してるとまとまってくると思うし!どれだけ想い、どうしたいのか。……その方が腹も決まると思うから」
羊さんがグラスを傾けてシードルを飲み干す。最後の一言はどこか遠い目をしていて、歩夢だけでなく自分にも言っているように聞こえた。
「…そうですね。聞いてくれますか?」
「えぇ、もちろん」
「妹は昔から──」
羊さんの放つ心地よい空気に当てられ、歩夢が微笑みながら話し始める。キャバ嬢は偏見で見られるなんて卑下していたが、今の彼女にそんな言葉をかけるのは失礼だと思う。きっといろんな人にこうして優しく接しているのだろうな。
「羊さん、素敵な人ですね」
「…でしょ?」
ぽつりと僕の口からこぼれた言葉に、マリーさんが空いたグラスを下げながら微笑んで反応した。