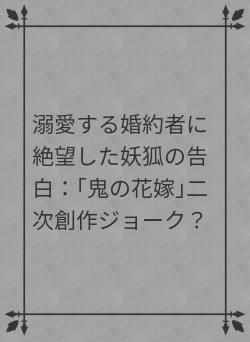1
「困ったことになったな」
ボンデホンからやってきたジョナス大尉は、クリュエルに書類を手渡して頭を搔いた。お互いにあらましはとうに知っている。
親魔族のギャング・腐敗の勢力は、偽装や浸透工作を得意とするだけでなく、それらと相まって既存の社会システムや人間の善意を逆手にとった策略も得意なのだ。議会の買収や言論操作はお手のものだが、法律や司法の悪用も重大問題だった。
たとえば、「魔法石器は危険で倫理観に問題があるから制限しよう」という政治プロパガンダ活動がある。実際に地方条例や推奨規格基準などとして圧力をかけようとしていたが、中央の有力都市などを動かして、そちらからも手を回してきている。辺境都市の反魔族レジスタンスやリベリオ屯田兵村にとっては武器・防衛力と共に資金源でもある生命線であるから、明らかに政治的に足を掬おうとする画策であった。
これが正面から襲いかかってくる敵の魔族やギャングであれば、正当防衛で片付けられる。しかし相手が腐敗・卑劣とはいえ人間側の者たちで、しかも形式的に合法を装って小細工されると非常に厄介なのだった。
本来は法律というのは、正義や秩序のためのものなのだけれども、人間が定めて人間が運用するものだから、やろうと思えばいくらでも悪用できてしまう。特に腐敗や悪意の者がシステムを動かす内部にいれば、わざと間違った恣意的な使い方をして無茶苦茶できてしまう。
「完全に嵌めにきてやがるな」
当事者のクリュエルが吐き捨てるのも無理はなかった。
クリュエルに対して「違反行為の恐れあり」と遠方の中央部の有力都市で告発して、「査問と裁判のために出頭せよ」。そもそもが嵌め込みや陥れが目的であるからまともに取り合うのが不毛かつ危険であるだけでなく、長期間に渡って遠方で裁判に拘束されればその間は屯田兵村の防衛力が低下してしまい(資金や武器ストックになる魔法石器の製造もストップする)、その隙に近くに進駐してきている敵の魔族勢力から奇襲されて壊滅されかねない。
ひとまずは信頼のおける代理人を立てて答弁させたのだが、「回答するのは出頭したクリュエル本人でなければならない」と強弁して、買収されている裁判官が命令書まで送ってきた。最初から罠にかけるための悪意でやっていることだから、まともな議論などできるわけがない。拒否や無視すれば敗訴や有罪になってしまい、行政措置による強制執行や官憲による身柄拘束さえ可能になるという寸法だった。下っ端の役人たちや巡査などは上の命令を拒否するのは困難であるし、買収されているスパイや一味の者たちもいるから、形の上で合法に繕えばどんなことでもできる。
こういう卑劣なやり方は今回に始まったことではない。
以前に、都市ボンデホンなどで親魔族ギャングが毒を散布して、サキが解毒剤を調合したことがあった。そのときにも、薬事法違反やら毒殺容疑やらでサキへの告発・政治的な攻撃が行われた。そのときは救われた都市ボンデホンの参事会と防衛軍が「身柄拘束命令」を頑として無視した(その後に中央の反魔族強硬派の政治家などから、命令の無効と破却にこぎつけたが)。
サキは「本当に人間寄りの魔族ハーフ」であるために、親魔族利権の腐敗勢力からは目の仇のように嫌われて常時に誹謗中傷されている。理由は反社会的な策謀による利得に役に立たず妨害になるからで、反対に適当に裏切り行為している魔族混血は黙認されるし、アビスエルフ(鮮魚人などの魔族寄りのエルフ部族)などは盛んに擁護されている始末である(あべこべに、卑劣の迎合や加担しないと同胞からリンチされることすらあるらしい)。
2
「どうなさったんです? ご主人様?」
鮮魚姫メイドのペーシャは、安楽椅子で頬杖した魔術者アルチェットに訊ねた。あのピエロ風の衣装ではなく、部屋着でくつろぎつつも浮かぬ顔をしていたため。
「ちょっと、厄介な話なんだ。リベリオ屯田兵村のクリュエルのことは知っているだろ? あいつを嵌めるのを手伝え、との魔術協会の仰せなのさ」
「よろしいじゃありませんか」
ペーシャはケロリとして言った。可愛らしい顔立ちに、ほんの少し邪悪な微笑が走るのは、一方的にライバル視するサキへの打撃が嬉しいのか。
「あいつらと直接に完全に敵対してしまうってのは、あんまり好都合じゃない。リスクばっかり大きくて旨味もない。こんなことやっていたら、本気で人間側が危なくなったりして、こんな工作に関わったら後で俺自身も危ない。人間のまともな連中だったらブーイングどころか石投げられたり刺されかねない」
「よろしいじゃありませんか、人間どもなんて。あんな低級な愚民どもがどうなったって」
ペーシャからすれば、人間は見下す対象で、憎んでさえいるのかもしれない。
「おいおい、俺だって半分は人間の血筋だぞ?」
「ご主人様はご主人様ですよ! ちょっとくらい人間の血が入っていても、いずれは魔族の男爵になられる方です」
気色ばむペーシャは真剣そのものだ。
アビスエルフである彼女からすれば、アルチェットは「仕える価値ある魔族の貴公子」ということになるらしく、「人間どもに混ざって身をやつして雌伏している、お労しい」という同情や共感と崇拝・敬慕の対象なのだそうな。
たしかにアルチェットは便宜主義・ご都合主義ではあるのだけれども、自身の父親が人間の魔術者であることや人間社会で人間として育ったことから、ペーシャほど割り切れない。第一に、魔族側からすればアルチェットは「部分的に魔族の血を引いた人間」であって、確実に差別されることだろう。たとえ力量で勝ってもやっかみは受けるだろうし、魔族が上辺で親しげに「血族同胞」などと言ってきても完全に信頼できるわけではない。
「お前は、物事を偏って考えすぎ。魔族だって、お前の種族を虐待することもあるだろ? 人間よりマシだなんて、幻想だと思うぞ」
この娘には「魔族が支配する世界秩序なら、自分たち鮮魚人エルフは次席ランクの上級市民になれる」という、漠然とした固定観念がある。生まれ育ちで人間との確執や、同胞の伝統的な価値からから人間を憎んでいるらしい。アルチェットに向けられた特別な感情は、境遇が似ていることも一因なのだろう。
「でも、人間なんて!」
「そんな顔しないの」
そうは言いつつも、この特異な出自で歪んだ価値観の娘は自分に対しては忠実で慕ってくるのだから、私情では嫌うどころか愛情すら覚えているのだから余計に複雑なのだった。
聞くところでは、鮮魚人や親魔族ギャングたちは、現在に係争中の辺境を売り飛ばすためのプロパガンダ工作や買収などで躍起になっているらしいのだけれど。アルチェットとしては、ペーシャにそんなリスキーな行動にはあまり関わらせたくない。自分自身への飛び火の恐れもあったし、反魔族の強硬派からペーシャが目を付けられれば庇いきれなくなるかもしれない。
「二人でどっか、遠くところに行きたい。おとぎ話の楽園とか南の島とかさあ」
「それって、愛の告白ですか?」
アルチェットがつい漏らした本音の愚痴とぼやきから、ペーシャはパッと無邪気なまでの笑顔を咲かせる。そういうときには、ごく普通の女の子に見えてくる。人間か鮮魚姫かというよりは、きっとアルチェットとしては「このペーシャ」という個体が好きなだけなのだろう。
「困ったことになったな」
ボンデホンからやってきたジョナス大尉は、クリュエルに書類を手渡して頭を搔いた。お互いにあらましはとうに知っている。
親魔族のギャング・腐敗の勢力は、偽装や浸透工作を得意とするだけでなく、それらと相まって既存の社会システムや人間の善意を逆手にとった策略も得意なのだ。議会の買収や言論操作はお手のものだが、法律や司法の悪用も重大問題だった。
たとえば、「魔法石器は危険で倫理観に問題があるから制限しよう」という政治プロパガンダ活動がある。実際に地方条例や推奨規格基準などとして圧力をかけようとしていたが、中央の有力都市などを動かして、そちらからも手を回してきている。辺境都市の反魔族レジスタンスやリベリオ屯田兵村にとっては武器・防衛力と共に資金源でもある生命線であるから、明らかに政治的に足を掬おうとする画策であった。
これが正面から襲いかかってくる敵の魔族やギャングであれば、正当防衛で片付けられる。しかし相手が腐敗・卑劣とはいえ人間側の者たちで、しかも形式的に合法を装って小細工されると非常に厄介なのだった。
本来は法律というのは、正義や秩序のためのものなのだけれども、人間が定めて人間が運用するものだから、やろうと思えばいくらでも悪用できてしまう。特に腐敗や悪意の者がシステムを動かす内部にいれば、わざと間違った恣意的な使い方をして無茶苦茶できてしまう。
「完全に嵌めにきてやがるな」
当事者のクリュエルが吐き捨てるのも無理はなかった。
クリュエルに対して「違反行為の恐れあり」と遠方の中央部の有力都市で告発して、「査問と裁判のために出頭せよ」。そもそもが嵌め込みや陥れが目的であるからまともに取り合うのが不毛かつ危険であるだけでなく、長期間に渡って遠方で裁判に拘束されればその間は屯田兵村の防衛力が低下してしまい(資金や武器ストックになる魔法石器の製造もストップする)、その隙に近くに進駐してきている敵の魔族勢力から奇襲されて壊滅されかねない。
ひとまずは信頼のおける代理人を立てて答弁させたのだが、「回答するのは出頭したクリュエル本人でなければならない」と強弁して、買収されている裁判官が命令書まで送ってきた。最初から罠にかけるための悪意でやっていることだから、まともな議論などできるわけがない。拒否や無視すれば敗訴や有罪になってしまい、行政措置による強制執行や官憲による身柄拘束さえ可能になるという寸法だった。下っ端の役人たちや巡査などは上の命令を拒否するのは困難であるし、買収されているスパイや一味の者たちもいるから、形の上で合法に繕えばどんなことでもできる。
こういう卑劣なやり方は今回に始まったことではない。
以前に、都市ボンデホンなどで親魔族ギャングが毒を散布して、サキが解毒剤を調合したことがあった。そのときにも、薬事法違反やら毒殺容疑やらでサキへの告発・政治的な攻撃が行われた。そのときは救われた都市ボンデホンの参事会と防衛軍が「身柄拘束命令」を頑として無視した(その後に中央の反魔族強硬派の政治家などから、命令の無効と破却にこぎつけたが)。
サキは「本当に人間寄りの魔族ハーフ」であるために、親魔族利権の腐敗勢力からは目の仇のように嫌われて常時に誹謗中傷されている。理由は反社会的な策謀による利得に役に立たず妨害になるからで、反対に適当に裏切り行為している魔族混血は黙認されるし、アビスエルフ(鮮魚人などの魔族寄りのエルフ部族)などは盛んに擁護されている始末である(あべこべに、卑劣の迎合や加担しないと同胞からリンチされることすらあるらしい)。
2
「どうなさったんです? ご主人様?」
鮮魚姫メイドのペーシャは、安楽椅子で頬杖した魔術者アルチェットに訊ねた。あのピエロ風の衣装ではなく、部屋着でくつろぎつつも浮かぬ顔をしていたため。
「ちょっと、厄介な話なんだ。リベリオ屯田兵村のクリュエルのことは知っているだろ? あいつを嵌めるのを手伝え、との魔術協会の仰せなのさ」
「よろしいじゃありませんか」
ペーシャはケロリとして言った。可愛らしい顔立ちに、ほんの少し邪悪な微笑が走るのは、一方的にライバル視するサキへの打撃が嬉しいのか。
「あいつらと直接に完全に敵対してしまうってのは、あんまり好都合じゃない。リスクばっかり大きくて旨味もない。こんなことやっていたら、本気で人間側が危なくなったりして、こんな工作に関わったら後で俺自身も危ない。人間のまともな連中だったらブーイングどころか石投げられたり刺されかねない」
「よろしいじゃありませんか、人間どもなんて。あんな低級な愚民どもがどうなったって」
ペーシャからすれば、人間は見下す対象で、憎んでさえいるのかもしれない。
「おいおい、俺だって半分は人間の血筋だぞ?」
「ご主人様はご主人様ですよ! ちょっとくらい人間の血が入っていても、いずれは魔族の男爵になられる方です」
気色ばむペーシャは真剣そのものだ。
アビスエルフである彼女からすれば、アルチェットは「仕える価値ある魔族の貴公子」ということになるらしく、「人間どもに混ざって身をやつして雌伏している、お労しい」という同情や共感と崇拝・敬慕の対象なのだそうな。
たしかにアルチェットは便宜主義・ご都合主義ではあるのだけれども、自身の父親が人間の魔術者であることや人間社会で人間として育ったことから、ペーシャほど割り切れない。第一に、魔族側からすればアルチェットは「部分的に魔族の血を引いた人間」であって、確実に差別されることだろう。たとえ力量で勝ってもやっかみは受けるだろうし、魔族が上辺で親しげに「血族同胞」などと言ってきても完全に信頼できるわけではない。
「お前は、物事を偏って考えすぎ。魔族だって、お前の種族を虐待することもあるだろ? 人間よりマシだなんて、幻想だと思うぞ」
この娘には「魔族が支配する世界秩序なら、自分たち鮮魚人エルフは次席ランクの上級市民になれる」という、漠然とした固定観念がある。生まれ育ちで人間との確執や、同胞の伝統的な価値からから人間を憎んでいるらしい。アルチェットに向けられた特別な感情は、境遇が似ていることも一因なのだろう。
「でも、人間なんて!」
「そんな顔しないの」
そうは言いつつも、この特異な出自で歪んだ価値観の娘は自分に対しては忠実で慕ってくるのだから、私情では嫌うどころか愛情すら覚えているのだから余計に複雑なのだった。
聞くところでは、鮮魚人や親魔族ギャングたちは、現在に係争中の辺境を売り飛ばすためのプロパガンダ工作や買収などで躍起になっているらしいのだけれど。アルチェットとしては、ペーシャにそんなリスキーな行動にはあまり関わらせたくない。自分自身への飛び火の恐れもあったし、反魔族の強硬派からペーシャが目を付けられれば庇いきれなくなるかもしれない。
「二人でどっか、遠くところに行きたい。おとぎ話の楽園とか南の島とかさあ」
「それって、愛の告白ですか?」
アルチェットがつい漏らした本音の愚痴とぼやきから、ペーシャはパッと無邪気なまでの笑顔を咲かせる。そういうときには、ごく普通の女の子に見えてくる。人間か鮮魚姫かというよりは、きっとアルチェットとしては「このペーシャ」という個体が好きなだけなのだろう。