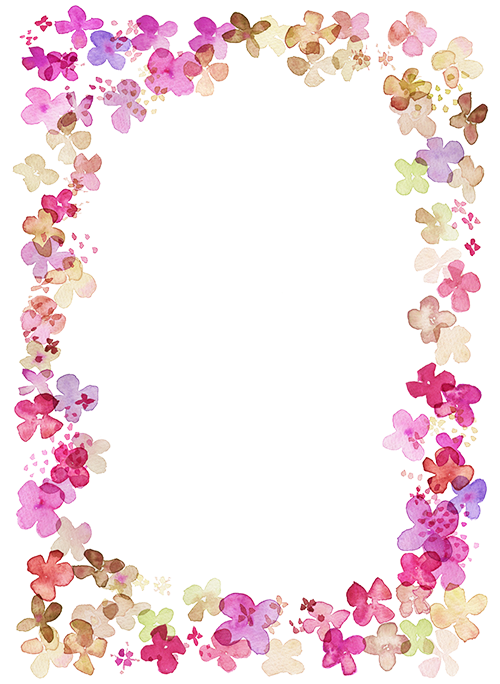デニスの体調が戻ってきたとき、彼は旅行に行きたいと言った。
ある日の夕食の場で、デニスは私の父に言葉をかける。
「では、教授。ご迷惑もかけると思いますが、明日からよろしくお願いします」
「むしろ計画を立ててくれてありがたく思っているよ。無理をしなくていいから、ゆっくり行こう」
父は朗らかにうなずいて、母も優しく言葉を返した。
「明日は一泊するのね。明後日の夕食は要るかしら?」
「たぶん遅くなると思いますので、用意いただかなくて大丈夫です」
私は首を傾げて父に問いかけた。
「どこに行くの?」
「島根県、出雲大社だよ」
「ずいぶん遠いね」
住んでいる地方も違って、格別歴史好きでもない私には、デニスの望んだ旅行先にただきょとんとしていた。
出雲退社は観光名所ではあるけれど、外国の人にそれほど知られているわけじゃない。そこに二日間もかけて行くのは少し不思議だった。
食器を片付けた後にデニスの部屋を訪ねたら、彼は塵一つ落ちていない床にたくさんの資料を並べて見下ろしていた。
私は驚いて立ちすくみながら言った。
「これ、全部出雲大社の資料?」
足の踏み場もない紙の束を前に、デニスはうなずいた。
デニスは一応私が座る場所だけは空けてくれて、私は何とか部屋の中に立ち入る。
私は驚きのため息をつきながらデニスに言った。
「観光するって聞いてたから、京都とかに行くのかと思ってた」
「京都は古い歴史を持っている都だから、きっと華やかな光景が見られるんだろう」
デニスはそう答えながら、まだ資料を眺めながら答えた。
「でも僕の求めるものは地方にあってね。古き良きものが日本にたくさんあるから、僕はこの国に来たんだ」
「古き良きもの?」
「心の故郷があるところかな」
デニスの言うことは難しくて、哲学的だった。私は今日までにもそうしていたように、目を丸くして問い返す。
「それ、もっと聞きたい。どういうこと?」
私がデニスの隣に座って答えを待つと、デニスは考え込む素振りを見せた。
「そうだな……」
デニスはそんな問いばかり投げかける私に、いつも真摯に答えを探してくれた。そういうところが、彼は高貴な人間だった。
デニスは細かい字が印刷された資料を見下ろしてから、つと顔を上げて私を見た。
「自分の故郷のことを考えてみるといいかもしれない。智子、君の故郷は?」
私はそれならわかると思って、こくっとうなずいた。
「私の故郷はここだよ。今住んでいるところ。デニスはどこ?」
「僕?」
逆に問われたのが意外だったのか、デニスはふいに瞳を揺らした。
デニスは子どものように目を細めて呟く。
「コッツウォルズのボートン・オン・ザ・ウォーターかな。亡くなった祖父の家がそこにあったんだ」
デニスは目を伏せながら言う。
「そこはすっかり観光名所になってしまったけど、今でも祖父の思い出と一緒に、懐かしい思いで振り返ることができる。日本でもそういうところをたくさん心に留めて、英国に帰るつもりなんだ」
「そうなんだ……」
デニスがそう言ったものだから、私は次の日に図書館に行ってコッツウォルズの本を探した。
書架には並んでいなくて、司書さんに相談して書庫から関係する本を出してもらった。
そして私が見たのは、どこか懐かしい気配のする色合いの家々だった。
柔らかい縁取りで囲まれた、優しい肌触りを感じるところ。
作りも色彩も日本人の私には全く馴染みがないはずなのに、そこは確かに故郷の香りがしていた。
ある日の夕食の場で、デニスは私の父に言葉をかける。
「では、教授。ご迷惑もかけると思いますが、明日からよろしくお願いします」
「むしろ計画を立ててくれてありがたく思っているよ。無理をしなくていいから、ゆっくり行こう」
父は朗らかにうなずいて、母も優しく言葉を返した。
「明日は一泊するのね。明後日の夕食は要るかしら?」
「たぶん遅くなると思いますので、用意いただかなくて大丈夫です」
私は首を傾げて父に問いかけた。
「どこに行くの?」
「島根県、出雲大社だよ」
「ずいぶん遠いね」
住んでいる地方も違って、格別歴史好きでもない私には、デニスの望んだ旅行先にただきょとんとしていた。
出雲退社は観光名所ではあるけれど、外国の人にそれほど知られているわけじゃない。そこに二日間もかけて行くのは少し不思議だった。
食器を片付けた後にデニスの部屋を訪ねたら、彼は塵一つ落ちていない床にたくさんの資料を並べて見下ろしていた。
私は驚いて立ちすくみながら言った。
「これ、全部出雲大社の資料?」
足の踏み場もない紙の束を前に、デニスはうなずいた。
デニスは一応私が座る場所だけは空けてくれて、私は何とか部屋の中に立ち入る。
私は驚きのため息をつきながらデニスに言った。
「観光するって聞いてたから、京都とかに行くのかと思ってた」
「京都は古い歴史を持っている都だから、きっと華やかな光景が見られるんだろう」
デニスはそう答えながら、まだ資料を眺めながら答えた。
「でも僕の求めるものは地方にあってね。古き良きものが日本にたくさんあるから、僕はこの国に来たんだ」
「古き良きもの?」
「心の故郷があるところかな」
デニスの言うことは難しくて、哲学的だった。私は今日までにもそうしていたように、目を丸くして問い返す。
「それ、もっと聞きたい。どういうこと?」
私がデニスの隣に座って答えを待つと、デニスは考え込む素振りを見せた。
「そうだな……」
デニスはそんな問いばかり投げかける私に、いつも真摯に答えを探してくれた。そういうところが、彼は高貴な人間だった。
デニスは細かい字が印刷された資料を見下ろしてから、つと顔を上げて私を見た。
「自分の故郷のことを考えてみるといいかもしれない。智子、君の故郷は?」
私はそれならわかると思って、こくっとうなずいた。
「私の故郷はここだよ。今住んでいるところ。デニスはどこ?」
「僕?」
逆に問われたのが意外だったのか、デニスはふいに瞳を揺らした。
デニスは子どものように目を細めて呟く。
「コッツウォルズのボートン・オン・ザ・ウォーターかな。亡くなった祖父の家がそこにあったんだ」
デニスは目を伏せながら言う。
「そこはすっかり観光名所になってしまったけど、今でも祖父の思い出と一緒に、懐かしい思いで振り返ることができる。日本でもそういうところをたくさん心に留めて、英国に帰るつもりなんだ」
「そうなんだ……」
デニスがそう言ったものだから、私は次の日に図書館に行ってコッツウォルズの本を探した。
書架には並んでいなくて、司書さんに相談して書庫から関係する本を出してもらった。
そして私が見たのは、どこか懐かしい気配のする色合いの家々だった。
柔らかい縁取りで囲まれた、優しい肌触りを感じるところ。
作りも色彩も日本人の私には全く馴染みがないはずなのに、そこは確かに故郷の香りがしていた。