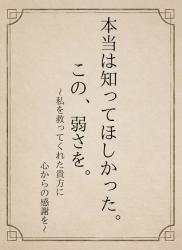「おはよー」
「春瀬さんおはよう」
「春瀬さん、おはようございます!」
次の日、学校に行ったら何故かものすごく話し掛けられた。
「おっはよー、玉藻ちゃん! 今日も可愛いねー!」
教室に入ると、那古ちゃんが抱きついてきた。
「おはよう、春瀬。今日も可愛いね」
目が合うと、煌雅までやってきて髪を一筋すくうと、軽くキスをした。
クラスの女子が絶叫した。
耳が痛い。
「あ、ぁの……朝霧、くん?」
「ごめん、嫌だった?」
びっくりして名前を呼ぶと、シュン、と肩を落とした。
「ぁ、いや、そういうことじゃなくて………。ここ、教室なんですけどぉ」
チラッと煌雅を見上げると、ほんのりと頬を朱に染めていた。
「あ゙ー。可愛い。可愛いね、可愛すぎる。好き」
煌雅は甘い言葉を取り繕うともしない。
「ねぇ、それ、2人だけだったらいいってこと? 俺にはそう聞こえたんだけど」
「う、ぁ………。にゃ、あ……」
「猫? 可愛いね。それは肯定ってことでいいの?」
煌雅への気持ちは消さなきゃいけないのに、全然消えてくれない。
こういうところは、前の煌雅と全然違う。
もう少しぶっきらぼうで、ちょっと嫉妬深くて、すぐに抱きついてきて、いつも余裕じゃないのは私だけで。
そう考えると、背筋が凍りついたみたいに感じた。
改めて“孤独”を感じる。
みんなはみんななのに、私だけ違うから。
私が知ってるみんなを、知らないみんながいる。
「? 春瀬、大丈夫?」
不意に煌雅が顔を覗き込んできた。
あまりの近さについ後ずさる。
「ごめん。嫌だったな」
私の頭をポンポンと軽く撫でると、煌雅は離れていく。
「こー、がっ。嫌じゃ、ないよ………っ」
反射的にそ煌雅の制服を掴む。
「ねえ、そういうのやめない? 可愛すぎる」
煌雅は呆れたように微笑むと、私を抱きしめた。
これは、私の好きな煌雅だけど、私の好きな煌雅じゃない。
それでも、彼は私のそばにいてくれる。
煌雅の甘い囁きは私の孤独を加速させた。
「春瀬さんおはよう」
「春瀬さん、おはようございます!」
次の日、学校に行ったら何故かものすごく話し掛けられた。
「おっはよー、玉藻ちゃん! 今日も可愛いねー!」
教室に入ると、那古ちゃんが抱きついてきた。
「おはよう、春瀬。今日も可愛いね」
目が合うと、煌雅までやってきて髪を一筋すくうと、軽くキスをした。
クラスの女子が絶叫した。
耳が痛い。
「あ、ぁの……朝霧、くん?」
「ごめん、嫌だった?」
びっくりして名前を呼ぶと、シュン、と肩を落とした。
「ぁ、いや、そういうことじゃなくて………。ここ、教室なんですけどぉ」
チラッと煌雅を見上げると、ほんのりと頬を朱に染めていた。
「あ゙ー。可愛い。可愛いね、可愛すぎる。好き」
煌雅は甘い言葉を取り繕うともしない。
「ねぇ、それ、2人だけだったらいいってこと? 俺にはそう聞こえたんだけど」
「う、ぁ………。にゃ、あ……」
「猫? 可愛いね。それは肯定ってことでいいの?」
煌雅への気持ちは消さなきゃいけないのに、全然消えてくれない。
こういうところは、前の煌雅と全然違う。
もう少しぶっきらぼうで、ちょっと嫉妬深くて、すぐに抱きついてきて、いつも余裕じゃないのは私だけで。
そう考えると、背筋が凍りついたみたいに感じた。
改めて“孤独”を感じる。
みんなはみんななのに、私だけ違うから。
私が知ってるみんなを、知らないみんながいる。
「? 春瀬、大丈夫?」
不意に煌雅が顔を覗き込んできた。
あまりの近さについ後ずさる。
「ごめん。嫌だったな」
私の頭をポンポンと軽く撫でると、煌雅は離れていく。
「こー、がっ。嫌じゃ、ないよ………っ」
反射的にそ煌雅の制服を掴む。
「ねえ、そういうのやめない? 可愛すぎる」
煌雅は呆れたように微笑むと、私を抱きしめた。
これは、私の好きな煌雅だけど、私の好きな煌雅じゃない。
それでも、彼は私のそばにいてくれる。
煌雅の甘い囁きは私の孤独を加速させた。