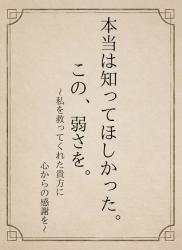もう、私にとってぼっち症候群になる前の記憶は『思い出』だった。
いつまでも引きずっていたら、ずっとずっと苦しいから。
みんなが私のことを忘れてから3日が経った。
今日は体育がある。
体育館で、男子はバスケ、女子はバレーだ。
知っていたけど、煌雅はバスケが上手で、休憩する女子たちが見て騒いでいる。
「危ないっ!!」
その時、バレーコートで練習をしていたチームのボールが煌雅を見て騒ぐ女子たちのもとへ飛んできた。
すぐ近くだったこともあり、私はボールと女子の間にさっと入るとレシーブでボールの衝突を防いだ。
誰かが大声で注意喚起をしていたからか、視線が集まった。
「………お、男前♡」
第一声は、ボールと衝突しそうになった女子だった。
「春瀬さんありがとう。もう、マジ好き♡」
目がハートになっている。
煌雅が私のもとに駆け寄ってきて、勢いよく頭をクシャクシャに撫でてきた。
「春瀬、すごいね。ヒーローみたいだったよ」
ちょっと興奮気味ににっこり笑顔で私を抱き締める。
「ひゃっ。朝霧く、あの……!」
突然抱き締められた私はもう大パニック。
「もうっ、分かったから、離してっ。こんな人前、恥ずかしっ」
少し遠くでは那古ちゃんがニヤニヤしながら見ている。
「那古ちゃんっ、たす、助けてっ」
「え〜? 顔真っ赤にして、嬉しいようにしか見えないけどー?」
「ん、にゃ、そんなことないからぁ!!」
「『にゃ』だって、カーワーイーイー。玉藻ちゃん可愛すぎー」
那古ちゃんは助けてはくれない。
「朝霧くん、春瀬さんのこと離してくれない? 嫌がってるじゃない」
「は? お前の春瀬じゃねぇし」
「でも朝霧くんの春瀬さんでもありませんー。離してくださいー」
私を挟んで言い合いをしないでほしい。
ぐるぐる困っていると、やっと那古ちゃんが助けてくれた。
「ほら、あんた達! 本人挟んで喧嘩しない! 玉藻ちゃんが困ってるじゃない。分からないようじゃふたりとも近付くな!」
そんな言葉でふたりを撃退していた。
いつまでも引きずっていたら、ずっとずっと苦しいから。
みんなが私のことを忘れてから3日が経った。
今日は体育がある。
体育館で、男子はバスケ、女子はバレーだ。
知っていたけど、煌雅はバスケが上手で、休憩する女子たちが見て騒いでいる。
「危ないっ!!」
その時、バレーコートで練習をしていたチームのボールが煌雅を見て騒ぐ女子たちのもとへ飛んできた。
すぐ近くだったこともあり、私はボールと女子の間にさっと入るとレシーブでボールの衝突を防いだ。
誰かが大声で注意喚起をしていたからか、視線が集まった。
「………お、男前♡」
第一声は、ボールと衝突しそうになった女子だった。
「春瀬さんありがとう。もう、マジ好き♡」
目がハートになっている。
煌雅が私のもとに駆け寄ってきて、勢いよく頭をクシャクシャに撫でてきた。
「春瀬、すごいね。ヒーローみたいだったよ」
ちょっと興奮気味ににっこり笑顔で私を抱き締める。
「ひゃっ。朝霧く、あの……!」
突然抱き締められた私はもう大パニック。
「もうっ、分かったから、離してっ。こんな人前、恥ずかしっ」
少し遠くでは那古ちゃんがニヤニヤしながら見ている。
「那古ちゃんっ、たす、助けてっ」
「え〜? 顔真っ赤にして、嬉しいようにしか見えないけどー?」
「ん、にゃ、そんなことないからぁ!!」
「『にゃ』だって、カーワーイーイー。玉藻ちゃん可愛すぎー」
那古ちゃんは助けてはくれない。
「朝霧くん、春瀬さんのこと離してくれない? 嫌がってるじゃない」
「は? お前の春瀬じゃねぇし」
「でも朝霧くんの春瀬さんでもありませんー。離してくださいー」
私を挟んで言い合いをしないでほしい。
ぐるぐる困っていると、やっと那古ちゃんが助けてくれた。
「ほら、あんた達! 本人挟んで喧嘩しない! 玉藻ちゃんが困ってるじゃない。分からないようじゃふたりとも近付くな!」
そんな言葉でふたりを撃退していた。