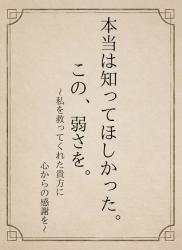「春瀬、大丈夫?」
煌雅の問いかけに首をかしげる。
「…………泣いてる。俺、なんかだめなこと言った?」
言われて初めて気付いた。
“孤独”が私の心を蝕んでいく。
「保健室行く?」
煌雅の腕が私の肩口まで伸びてきて、反射で避けてしまった。
「っ、ごめんっ」
こんな気持ちになるくらいなら、誰とも関わりたくない。
走って走って走って、ついたのは屋上だった。
頭がいたい。
心臓がいたい。
気分が悪い。
これは、私がいけないの?
私がこんな環境で生き続けられるわけない。
パタパタと走ってくる足音がして、自然と下を向いていた顔をあげる。
「っ、春瀬。本当に大丈夫? 俺が何かしたなら謝る。だから、なにがあったのか教えて」
あなたのせいですよ。
そう心の中で呟いて、さらに虚しくなる。
いや、私のせいか、と自分を納得させる。
「なにもない。大丈夫」
不自然な笑みだっただろう。
煌雅の表情が歪む。
「ね、大丈夫じゃないよね。そんな顔して」
その手が頬に触れそうになった瞬間、私は煌雅を見上げる。
「大丈夫。何があっても朝霧くんには関係ない。もういいから、ほっといて」
自分の瞳から大きな雫がこぼれ落ちる感覚があった。
これ以上、耐えられない。
私がいけない。
なのに、私にはなにもできない。
せめて、誰か一人でも私のこと知っていてくれれば、それだけでもっと気が楽になったのかな?
あーあ、やる気でない。
私は煌雅の横を通りすぎると、一直線で保健室へと向かった。
煌雅の問いかけに首をかしげる。
「…………泣いてる。俺、なんかだめなこと言った?」
言われて初めて気付いた。
“孤独”が私の心を蝕んでいく。
「保健室行く?」
煌雅の腕が私の肩口まで伸びてきて、反射で避けてしまった。
「っ、ごめんっ」
こんな気持ちになるくらいなら、誰とも関わりたくない。
走って走って走って、ついたのは屋上だった。
頭がいたい。
心臓がいたい。
気分が悪い。
これは、私がいけないの?
私がこんな環境で生き続けられるわけない。
パタパタと走ってくる足音がして、自然と下を向いていた顔をあげる。
「っ、春瀬。本当に大丈夫? 俺が何かしたなら謝る。だから、なにがあったのか教えて」
あなたのせいですよ。
そう心の中で呟いて、さらに虚しくなる。
いや、私のせいか、と自分を納得させる。
「なにもない。大丈夫」
不自然な笑みだっただろう。
煌雅の表情が歪む。
「ね、大丈夫じゃないよね。そんな顔して」
その手が頬に触れそうになった瞬間、私は煌雅を見上げる。
「大丈夫。何があっても朝霧くんには関係ない。もういいから、ほっといて」
自分の瞳から大きな雫がこぼれ落ちる感覚があった。
これ以上、耐えられない。
私がいけない。
なのに、私にはなにもできない。
せめて、誰か一人でも私のこと知っていてくれれば、それだけでもっと気が楽になったのかな?
あーあ、やる気でない。
私は煌雅の横を通りすぎると、一直線で保健室へと向かった。