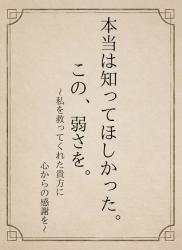この間は、煌雅のおかげか一日でよくなり、次の日には帰ることができた。
そして月曜日───
「春瀬おはよう。体調大丈夫? 無理してない?」
前以上に煌雅が構ってくる。
「うん。この間はありがとう。いろいろ世話焼いてくれて」
なんて話していると、那古ちゃんが飛んできた。
「それ、詳しく───」
目がキラキラ輝いている。
「は? 意味なくない。べつに狩谷に関係ねーし」
だが、そんな那古ちゃんを煌雅は一蹴した。
「ふふっ。ふたりは相変わらずだね」
“つい”そう言ってしまった。
でも、私の記憶の中は以前のふたり。
サァ、と緊張が全身を伝う。
「“相変わらず”………? えーっと、玉藻ちゃんの前じゃ初めてな気がしなくもないんだけど…………」
那古ちゃんが首をかしげる。
やってしまった、という後悔とやっぱり、この空間において私だけが異常なんだ、という感情とが襲ってくる。
私が知っているふたりを、ふたりは知らない。
ふたりが知っているふたりを、私は知らない。
現実を目の前に突きつけられる。
やっぱり、だめなんだ。
私は、恵まれてなんかなかった。
負の感情がどっと押し寄せてきて、心臓がきゅっ、と切なく跳ねる。
「えっ、ちょ、玉藻ちゃん!?」
「春瀬………?」
この悪夢はどうすれば断ち切れるのだろうか。
そもそも、これが夢か現実か、まるで判断がつかない。
怖いよ、私だって。
“孤独”という言葉が、胸にぽっかりと空いた大きな穴を、さらに大きく深く、抉っていく。
これは、紛れもない事実であった。
これが夢でも現実でも、今の私からしたら“現実”である。
やっぱり、私は孤独だったんだ。
そして月曜日───
「春瀬おはよう。体調大丈夫? 無理してない?」
前以上に煌雅が構ってくる。
「うん。この間はありがとう。いろいろ世話焼いてくれて」
なんて話していると、那古ちゃんが飛んできた。
「それ、詳しく───」
目がキラキラ輝いている。
「は? 意味なくない。べつに狩谷に関係ねーし」
だが、そんな那古ちゃんを煌雅は一蹴した。
「ふふっ。ふたりは相変わらずだね」
“つい”そう言ってしまった。
でも、私の記憶の中は以前のふたり。
サァ、と緊張が全身を伝う。
「“相変わらず”………? えーっと、玉藻ちゃんの前じゃ初めてな気がしなくもないんだけど…………」
那古ちゃんが首をかしげる。
やってしまった、という後悔とやっぱり、この空間において私だけが異常なんだ、という感情とが襲ってくる。
私が知っているふたりを、ふたりは知らない。
ふたりが知っているふたりを、私は知らない。
現実を目の前に突きつけられる。
やっぱり、だめなんだ。
私は、恵まれてなんかなかった。
負の感情がどっと押し寄せてきて、心臓がきゅっ、と切なく跳ねる。
「えっ、ちょ、玉藻ちゃん!?」
「春瀬………?」
この悪夢はどうすれば断ち切れるのだろうか。
そもそも、これが夢か現実か、まるで判断がつかない。
怖いよ、私だって。
“孤独”という言葉が、胸にぽっかりと空いた大きな穴を、さらに大きく深く、抉っていく。
これは、紛れもない事実であった。
これが夢でも現実でも、今の私からしたら“現実”である。
やっぱり、私は孤独だったんだ。