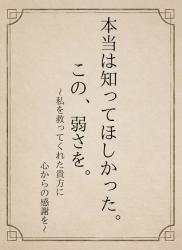結局、私が押しきってふたりで寝ることになった。
煌雅の顔は終始真っ赤だった。
「お互いの方を見ないこと。お互いすぐに寝ること。お互いに絶対に触れないこと」
煌雅は淡々と告げた。
「え………一緒にお話ししようよ」
「だめ。風邪引いてんだから大人しくしてて」
「もう治ったよ」
「念のため」
先に部屋行ってて、という煌雅の言葉に素直に頷く。
「おやすみ、春瀬」
「うん。おやすみ、朝霧くん」
勝手に人のベッドに入るというのを考えると、少し気が引ける。
そう思いながら煌雅の部屋に行って、やっぱり入ることができなくて、ベッドのはしっこにちょこんと座る。
「早く、来ないかなぁ………」
30分くらいすると、廊下に足音が響いた。
ガチャ、とドアが開いて、煌雅が入ってくる。
そして、私を見て固まった。
「………春瀬、俺のこと殺す気?」
意味が分からない。
「なんのために俺が時間ずらしてきたか分かってんの?」
知るわけがない。
「いいから、早く寝な。悪化したら困るから」
「だから、もう治ったよ………?」
すると、煌雅は大きなため息をついて私を見た。
「好きな女が自分のベッドの上にいるのに手を出せないっていうこの状況理解してる? 俺は、いつでも春瀬を襲えるよ」
今までに一度だって見たことのない“男”の目。
顔に熱が集まる。
「ぁ………ごめん、なさい」
「そう可愛い顔をするな」
煌雅の顔が近寄ってきて、唇に柔らかいものが触れる。
「おやすみ、春瀬」
私は煌雅の笑みを視界から追いやるために、全力で布団にもぐった。
煌雅の顔は終始真っ赤だった。
「お互いの方を見ないこと。お互いすぐに寝ること。お互いに絶対に触れないこと」
煌雅は淡々と告げた。
「え………一緒にお話ししようよ」
「だめ。風邪引いてんだから大人しくしてて」
「もう治ったよ」
「念のため」
先に部屋行ってて、という煌雅の言葉に素直に頷く。
「おやすみ、春瀬」
「うん。おやすみ、朝霧くん」
勝手に人のベッドに入るというのを考えると、少し気が引ける。
そう思いながら煌雅の部屋に行って、やっぱり入ることができなくて、ベッドのはしっこにちょこんと座る。
「早く、来ないかなぁ………」
30分くらいすると、廊下に足音が響いた。
ガチャ、とドアが開いて、煌雅が入ってくる。
そして、私を見て固まった。
「………春瀬、俺のこと殺す気?」
意味が分からない。
「なんのために俺が時間ずらしてきたか分かってんの?」
知るわけがない。
「いいから、早く寝な。悪化したら困るから」
「だから、もう治ったよ………?」
すると、煌雅は大きなため息をついて私を見た。
「好きな女が自分のベッドの上にいるのに手を出せないっていうこの状況理解してる? 俺は、いつでも春瀬を襲えるよ」
今までに一度だって見たことのない“男”の目。
顔に熱が集まる。
「ぁ………ごめん、なさい」
「そう可愛い顔をするな」
煌雅の顔が近寄ってきて、唇に柔らかいものが触れる。
「おやすみ、春瀬」
私は煌雅の笑みを視界から追いやるために、全力で布団にもぐった。