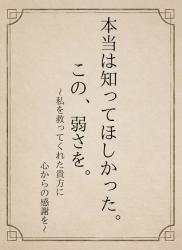「ん………」
目を開けると、そこは自分の部屋ではなかった。
でも、知ってる部屋。
基本的に灰色で統一されていて、極端に物の少ない広い部屋。
煌雅の部屋。
ガチャ、と扉が開いた。
「………! ごめん。家分かんなかったからかってに俺の家連れてきた。起こした?」
煌雅の手にはお皿と小さなお鍋が乗ったお盆。
「食べられそう? 一応お粥持ってきたんだけど」
お鍋からはとても食欲を誘う匂いが漂ってくる。
「うん、ごめんね。ありがとう」
煌雅は無闇やたらに謝られるのが嫌いだ。
だから、ごめんの後にはありがとう。
「いいや、大丈夫だよ。春瀬こそ大丈夫? 熱測ってみ?」
サイドテーブルの上に置いてあったらしい体温計を渡される。
私が体温を測っている間に、お粥をお皿にとりわけてくれた。
できる男だ。
ピピピピッ
体温計が鳴り、その数値を見ると[37.9℃]。
「まだ熱あるから休んでって。家に電話して迎えに来てもらおう?」
「私、一人暮らし。親の連絡先は知らない。住所しか」
「あー……。じゃあ、今日泊まってきなよ。そんなフラフラのままひとりで過ごされる方が怖いし」
突然の誘いに私は煌雅を見る。
「大丈夫。変な心配はしなくても、何もしないって誓うから。着替えはどうする?」
どんどん話が進んでいく。
「でも、あの、迷惑だし……」
「いや、むしろ俺のほうが邪魔だよ」
そういいながら渡されたお粥。
「あ。食べさせたげる」
「えっ、大丈夫」
「はい、口開けて。あー」
その声に、つい口を開けてしまった。
口の中に、温かい味が広がる。
「ん…、美味しい……」
「……っ! ふっ、よかった」
私が素直に感想を漏らすと、煌雅は少し驚いたように目を見開いてから微笑んだ。
お粥を食べ終わると、片付けるために煌雅は部屋から出ていった。
こうしていると、緊張してきた。
ずっと、ずっと煌雅の匂いに包まれてる。
シトラスのさっぱりとした香りに少し混じる、バニラのような甘い香り。
そのふたつの香りがうまくバランスを保っている。
この匂いに包まれているだけで幸せだ。
目を開けると、そこは自分の部屋ではなかった。
でも、知ってる部屋。
基本的に灰色で統一されていて、極端に物の少ない広い部屋。
煌雅の部屋。
ガチャ、と扉が開いた。
「………! ごめん。家分かんなかったからかってに俺の家連れてきた。起こした?」
煌雅の手にはお皿と小さなお鍋が乗ったお盆。
「食べられそう? 一応お粥持ってきたんだけど」
お鍋からはとても食欲を誘う匂いが漂ってくる。
「うん、ごめんね。ありがとう」
煌雅は無闇やたらに謝られるのが嫌いだ。
だから、ごめんの後にはありがとう。
「いいや、大丈夫だよ。春瀬こそ大丈夫? 熱測ってみ?」
サイドテーブルの上に置いてあったらしい体温計を渡される。
私が体温を測っている間に、お粥をお皿にとりわけてくれた。
できる男だ。
ピピピピッ
体温計が鳴り、その数値を見ると[37.9℃]。
「まだ熱あるから休んでって。家に電話して迎えに来てもらおう?」
「私、一人暮らし。親の連絡先は知らない。住所しか」
「あー……。じゃあ、今日泊まってきなよ。そんなフラフラのままひとりで過ごされる方が怖いし」
突然の誘いに私は煌雅を見る。
「大丈夫。変な心配はしなくても、何もしないって誓うから。着替えはどうする?」
どんどん話が進んでいく。
「でも、あの、迷惑だし……」
「いや、むしろ俺のほうが邪魔だよ」
そういいながら渡されたお粥。
「あ。食べさせたげる」
「えっ、大丈夫」
「はい、口開けて。あー」
その声に、つい口を開けてしまった。
口の中に、温かい味が広がる。
「ん…、美味しい……」
「……っ! ふっ、よかった」
私が素直に感想を漏らすと、煌雅は少し驚いたように目を見開いてから微笑んだ。
お粥を食べ終わると、片付けるために煌雅は部屋から出ていった。
こうしていると、緊張してきた。
ずっと、ずっと煌雅の匂いに包まれてる。
シトラスのさっぱりとした香りに少し混じる、バニラのような甘い香り。
そのふたつの香りがうまくバランスを保っている。
この匂いに包まれているだけで幸せだ。