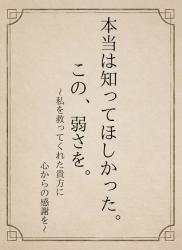みんなが私を忘れてから初めての週末。
私は新しい文房具を買うためにショッピングモールへと来ていた。
雑貨屋で目当てのものを買い、ついでに本屋に寄る。
何か面白そうな本はないかな、と探していると、一瞬頭がくらくらした。
そこへ、本屋の店員さんがやってきた。
イケメンのお兄さんだった。
「君、大丈夫? 具合悪そうだけど」
私が大っ嫌いなナンパをしてくるような人じゃない。
これは、彼の良心だった。
「あの、大丈夫です………」
「でも、君、すごく顔色悪いよ。バックヤードで休みな。途中で倒れちゃうよ」
お兄さんは、ちょっと触れるね、と言いながら私のおでこに手をやった。
「熱あるよ。親御さんに連絡するから休んでていいよ。家の番号分かる?」
お兄さんは私を支えるように肩に手を回す。
その時───
「痛っ」
お兄さんが小さく悲鳴を上げた。
「ねぇ、あんた何やってんの? 大人が未成年に欲情してんじゃねーよ。触んな。俺の連れだ」
お兄さんの手を掴みながらそう言ったのは、煌雅だった。
「え、あ、そうなの? じゃあ、この子、家まで送り届けてあげられる? とりあえず離して、痛い」
煌雅は怪訝そうにお兄さんを見てから、その手を離した。
「別にこの子を取って食おうってわけじゃないよ。具合悪そうだったから横にしてあげようと思っただけ。ごめんね、君の大切な子に手出しちゃって」
「………いや、すみません。春瀬、大丈夫? 送ってくから家教えて」
煌雅の優しい声に包まれて、全身から力が抜ける。
「!? 春瀬! おい、春瀬!」
煌雅の腕が私を強く抱きしめた感覚を最後に、私は意識を手放した。
私は新しい文房具を買うためにショッピングモールへと来ていた。
雑貨屋で目当てのものを買い、ついでに本屋に寄る。
何か面白そうな本はないかな、と探していると、一瞬頭がくらくらした。
そこへ、本屋の店員さんがやってきた。
イケメンのお兄さんだった。
「君、大丈夫? 具合悪そうだけど」
私が大っ嫌いなナンパをしてくるような人じゃない。
これは、彼の良心だった。
「あの、大丈夫です………」
「でも、君、すごく顔色悪いよ。バックヤードで休みな。途中で倒れちゃうよ」
お兄さんは、ちょっと触れるね、と言いながら私のおでこに手をやった。
「熱あるよ。親御さんに連絡するから休んでていいよ。家の番号分かる?」
お兄さんは私を支えるように肩に手を回す。
その時───
「痛っ」
お兄さんが小さく悲鳴を上げた。
「ねぇ、あんた何やってんの? 大人が未成年に欲情してんじゃねーよ。触んな。俺の連れだ」
お兄さんの手を掴みながらそう言ったのは、煌雅だった。
「え、あ、そうなの? じゃあ、この子、家まで送り届けてあげられる? とりあえず離して、痛い」
煌雅は怪訝そうにお兄さんを見てから、その手を離した。
「別にこの子を取って食おうってわけじゃないよ。具合悪そうだったから横にしてあげようと思っただけ。ごめんね、君の大切な子に手出しちゃって」
「………いや、すみません。春瀬、大丈夫? 送ってくから家教えて」
煌雅の優しい声に包まれて、全身から力が抜ける。
「!? 春瀬! おい、春瀬!」
煌雅の腕が私を強く抱きしめた感覚を最後に、私は意識を手放した。