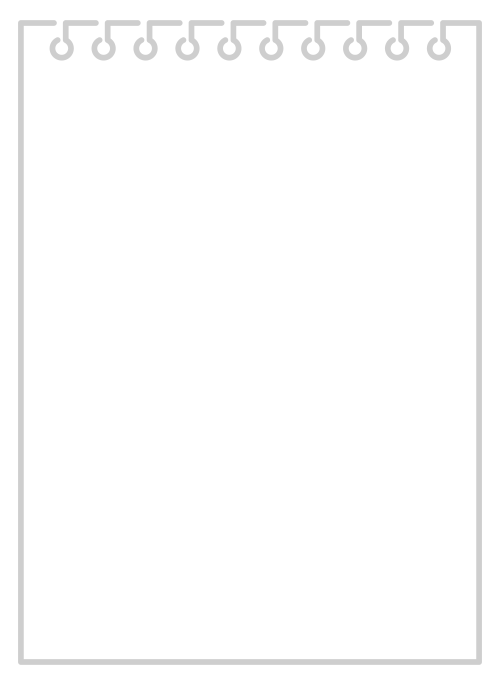ーーーー
好き勝手に書かれたそれは、流行りのJPOPや海外の曲。音代は1人1人の顔や性格を思い浮かべしっかりとその音楽を聴いた。
「なるほどな」
そう1人の音楽室で呟いてみたが、正直生徒のことが分かったかというとそうでもない。だが、曲の横にかかれた懐かしい思い出話などを読んでクスリと笑う。
存外、知るという作業は悪くないかも知れない。距離の縮め方は未知ではあるが。
そして、
「白紙が1人か」
名前だけ書かれており、その下は白紙だった。まあ、そういう生徒がいてもおかしくないだろうとは思う。
ーーー2年1組 間宮 仁穂
お手本のような綺麗な字でそう書いてある。
音代はその女子生徒のことを薄い記憶の底からほじくり出す。
胸元まで伸びた髪、あまり人とはつるまずそして音代は彼女の声を聞いたことがない。
歌唱の時、彼女は口は皆んなと同じように動いているが声が出ていないのを音代は知っている。
知っているが、それについて音代から間宮仁穂に声をかけたことはない。
そして、この白紙。彼女はどうして音楽を選択したのだろうか。
音代が抱えている謎がひとつ増えてしまった。
ーーータンバリンを盗む不良、自殺を促す曲を発信する女、それから、
音楽が好きそうに見えない女子生徒。
再び頭を抱える。
その項垂れた頭は、扉が荒々しくノックされたことによって上がる。
音代が「どうぞ」という前に開けられた先にいたのは顰めっ面の九条だ。
無言のまま音代の方に歩いてくる。
「なんだ」
その圧にさすがの音代も少し身を後ろに持っていく。
九条は、ポケットをあさり何かを取り出して音代に差し出した。
「これは?」
身構えていた音代は恐る恐るその手元に視線を落とす。それは写真だった。
少し色褪せており、そこに写っているのは幼い男の子とその祖母とみられる女性。
「これ俺とばあちゃん」
写真を持っている反対の手で指を差しながらそう言った九条にとりあえず「そうか」と返事をした音代。
それがなんだ、と言ってしまえば突き放すことになってしまうことは分かっていたので正解をなんとか探り出す。
「か、かわいらしいじゃないか」
「かわいいばあちゃんだろ」
そっちか。誰だって幼い頃は可愛げがあるものだという一般論で発した言葉の返しがまさかの返答で戸惑いながらも「そうだな」と頷く。
音代はどうにも噛みわない会話にむず痒くなりながらももう一度写真に目を落とした。
「持っているのはタンバリンか」
幼い頃の九条の手に収まっているのは子供用の小さなタンバリンであった。
「うん」
返事をした九条が前の席の椅子を1つ引きずり、音代が座っている前に持っていく。
そして座った。
「宝物だったんだけど、なくしちまって親に聞いたら親戚の子供にあげたってさ」
「だから必要だったのか」
その問いに九条は瞳を少し泳がせて俯く。
「タンバリンは、どうでもいいんだ」
低く、しぼりだすような声でそう言う九条。
音代は九条が発する言葉を急かさないように「ああ」と小さく返事をした。
音代は九条の心の開きを待つべきだと思ったからだ。内心困惑の嵐だったが、今は待つしかない。
ーーーどういう意味だ。じゃあ、なぜ盗んだ。
「ばあちゃん、俺のこと忘れちまって」
「忘れた? まさか」
「認知症だってよ」
だから、授業中あの質問をしたのかと音代は納得した。認知症の祖母の記憶を取り戻す為に九条は動いている。
「小さい頃みたいに俺がタンバリン叩いてるとこみたら、何か思い出してくれるんじゃないかと思って試したけどダメだった」
「そうか」
人間の記憶を取り戻すのに絶対的な正解はない。だが、九条のやろうとしていることはあながち間違った方法ではないと音代は思った。タンバリンを盗んだ理由が理解できた満足感が音代の中に満ちていくが、それと同時にどうにかしてやりたいという気持ちが芽生える。
「発想は悪くない そもそも人間の耳による一種のプルースト現象を引き起こすには、あー、プルースト現象というのは特定の香りから過去の記憶を呼び覚ますような心理現象のことなんだが、それは音楽にも同じ現象が起こる そしてそれを起こすには、本人の無意識の部分を刺激しないとダメだ。つまり、耳から入る聞き慣れた情報というのは、話す言葉、歯を磨く、スマホをいじったりと人間が自分が自分だと分からなくなっても残るものだと考えていい
つまり、音楽の記憶は潜在記憶の中にあり、それを刺激すればいい
分かるか?」
「ぐだぐだ何喋ってんだよ、分かるわけねぇだろ」
音代の力説はあえなく撃沈であった。
ストップをかけない限り相手が分かろうが分からまいが喋り続けてしまうのは音代の悪い癖である。
熱が入り上げかけていた腰をピアノの椅子に戻す。
そして、仕切り直すように咳払いをした。
「つまり、音楽の記憶は思い入れが深いほど本人の意思や病気に関係なく、永遠に残るものだ
音楽で記憶を刺激することはできる」
「まじ?」
九条の瞳が期待の文字が浮かぶように光る。
音代は数回頷いた。
人の記憶に絶対なんてものはないが、人は話す言葉や当たり前の日常を送る一種として音をきいている。
九条はなんとなくだが理解し、それを使って祖母の記憶を取り戻そうと奮起する。
その気持ちが音代の腕を掴んだ手に込められていた。
「え、なに」
「一緒に行こうぜ、俺のばあちゃんのところ」
なんで、と音代が問う前に九条にひっぱられる。
ーーー力強すぎないか。ふりほどけない。
こういうのは許可をとってから行くべきじゃないのか。
その言葉は心中に留まり、困惑と動揺で出てくる言葉は「おい、こら、まて、九条」で終わり。
なかば引きずられながら音代は諦めた。