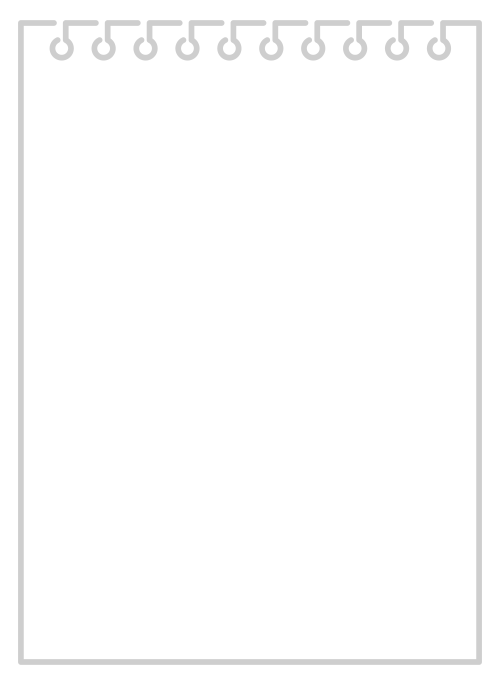ーーーーー
「自殺幇助?」
音代は顔を顰めた。
喫茶店では周りの会話が聞こえないようにという効果も兼ね備えている音楽が流れているが、音代の声の大きさに神城が人差し指を顔の前にもってきて「静かにしろ」と音代に言う。
音代は軽く咳払いをして、「続きを話せ」と神城をせかした。
「最初の発端になった自殺者のことを調べていると、どうやら自殺を手助けしたやつがいるらしい」
「どうやって分かった」
テーブルの上に写真が置かれた。
暗闇の中にうつっている人間2人。それを音代は持って自分の方へ近づける。
そして顔2人のうち1人を視界に入れ音代は顔を顰めた。
神城は音代が見ている人物とは違う方の人物に指をさした。
「自殺した日の現場近くの監視カメラに写っていた映像だ。自殺したのはこっちで、そんでもう1人は」
「自殺幇助の疑いがある人物」
「そういうことだ」
神城が頷いて音代の手から写真を抜き取る。
ため息混じりに「そして」ともう一枚の写真をとりだした。
「こいつが自殺した時に投稿したSNSの画面だ」
音代はその写真を覗き込んだ。スマホの画面を写真に撮っているそれ。うつっているスマホの画面には音代が何度も見てきた自殺を促す曲の動画を引用して発信されており、文面が添えられている。
『この曲を聴いたら死ぬ勇気がわいてきました。みなさん、さようなら』
そんな淡々とした文面。音代は1度目を逸らしコーヒーを一口飲んだ。
「こいつが本当に死んでしまった事実を突き止めたやつらがこの曲を拡散し始めて今に至るわけだ」
いつになくコーヒーが苦い気がして音代はカップに砂糖をいれながら、口を開く。
「つまり、自殺したやつか、自殺幇助の疑いがあるやつどちらかがこの曲を意図的に拡散させたってことか」
「まあそうだが、おそらく自殺幇助の疑いがあるやつが何か企んでる」
「どこまで調べた」
「そのきき方はやはりお前も何か知ってるんだな」
音代は何も反応しないまま糖分が濃くなったコーヒーを再び口に含む。次は甘すぎた。
軽く咳をしたあと、水を飲んだ音代に神城はため息をついた。
「まだ調べている最中だが、お前も何か分かったらすぐに連絡しろ」
「はやくとっ捕まえればいいだろ」
「そう簡単じゃないんだよ」
音代も少し焦っていた。この写真に写っている者がどんどんと闇へ落ちてしまうことに。
自殺幇助までしてこの男は音楽をどうしたいのだろうか。
ーーー「音楽で人は死なない」
ーーー「あはは、先生がそれ言う?」
音代がコーヒーカップを置けば、カシャンと華奢な音をたてた。中身が揺れる。そこにうつっている音代の顔もどんどん歪んでいるように見えた。
「俺は、音楽で人を殺したんだろうか」
音代のそんな低い声がそこに響く。言葉にしてしまえば背中に大きな錘がのしかかるような息苦しさを感じた。
神城は驚いたように見開いた。
「何言ってんだよ」
音代の口から溢れでたそれを飲み込む前にその言葉を反射的に否定するように強くそう返す神城。
もうやめろ、と制御したつもりだったが音代はとまらなかった。
「俺がピアノを極めるほど父はピアノから離れたし、俺が作曲をすれば父は曲を作らなくなった。俺が音楽をすればするほど父は死にむかっていった」
「音代」
「俺も、この曲と変わらない。人を殺してる」
「違う」
「違わない。この男を逮捕するならこの男をつくりあげた俺を捕まえるべきだ」
顔を歪ませてそう言った音代。
神城は言葉が出ないが、何度も首を横に振った。
違う、何もかもが。
「音代、きけ」
「性懲りも無く音楽の先生なんてやってるが、結局俺は逃げてるんだ。父からも、音楽からも、過去からも」
「音代!」
ぱん!と神城が音代の顔の前で手を叩いた。
我に返ったように音代がうつむかせていた顔を上げる。
神城はあげた腰を椅子に落として、ため息をついて頬杖をついた。そして窓の外へ視線を向ける。
「死んだお前の父親のことで、俺は一度たりともお前を恨んだことはないよ」
「神城さん」
「お、久しぶりに俺の名前呼んだな」
「じじい」
「ひねくれてんなあ」
無精髭をなでながら笑う神城。荒ぶっていた波風を落ち着かせるように音代はふうっと息を吐いた。
「その写真に写っているのは晴葉高校の2年1組、橋田奏馬だ」
「ああ」
当然神城は調べていた。この男のことも、どんな思想をもっているのかも。苦い顔をして頷く。
「おそらく自殺を促す曲を意図的に拡散させている張本人だ。そして、俺に憧れているとよく言っている」
「憧れている?」
解せない。そんな顔をして神城が音代をみた。音代はテーブルの上でぎゅっと拳を握る。
音楽で人を殺せるか、殺したい。音楽の闇をもっと知りたいとそんな危ない好奇心にあふれた顔をして音代に近づくその男を音代は少しこわいと思ってしまった。
できれば関わりたくない、だが音楽への恐怖心を植え付けさせる強制的なやり方を認めるわけにはいかない。しかし自分が、音楽で父を闇におとしいれた自分が橋田をせめる権利はあるのだろうか。そんな思いがずっと渦巻いている。
「前に言っていた、『音代みたいに音楽で身内を殺してみたい』とお前に言ったのはこいつか?」
神城が写真の男を人差し指で何度か叩く。
音代は小さな声で「ああ」と頷いた。
「ふざけてやがる」
「どの程度俺のことを調べているのかは分からないが、すくなくとも俺のせいで橋田の思想が歪んだんだろう」
どのタイミングでなんて音代には分からなかった。正直分かりたくもない。
「音代、お前あんまり自分をせめるなよ」
「勘違いするな、落ち込んでるんじゃない。俺は俺の責務を果たす」
「責務?」
「俺は音楽の先生だ。名の通り、音を楽しみ、分かち合うことを教える」
神城は音代の言葉に「そうかそうか」と言って笑った。音楽から背を向けたと思っていた男がこうやって音楽を教える『先生』として少しずつだが前を向き始めていることにほっとしていた。親友の息子が父親と同じようにこのまま消えてしまって誰もいない遠いところにいってしまうのではないかとずっと不安だったからだ。
「そういえば、お前あそこの喫茶店にはもう行ってないのか?」
「どこのことだ」
「音楽喫茶HASU。マスターがお前が来ないって嘆いてたよ」
「ああ」
苦い顔で返事した音代。父のことがあってから一度も顔をだしていなかった。
「お前のところの生徒はしょっちゅう来るがな。ほら、飛び降りた女子生徒いただろ」
そう言われ、音代の頭の中にすぐに記憶が蘇る。畑愛子のことだ。本人からも後日お礼を言われた。
喫茶店で演奏もさせてもらったと言っていたが、話の感じだとおそらく神城にも会っているのだろう。と音代は少し嬉しくなり、笑みを隠すかのように残り少ないコーヒーを飲み干す。
「ちょいちょいセッションして楽しんでるよ。今度顔出せよ、みんな心配してる」
「分かった」
そう返事はしたものの当分行かないだろうな、と音代自身も神城も分かっている。あそこには思い出がありすぎるからだ。
「コーヒーのおかわりいかがですか〜」
頭上から気の抜けた声が聞こえ、顔を上げた2人。
神城は「お願いします」とカップを差し出したが、音代は驚いて返事をせず固まっている。
「お前なんでいるんだ」
「先生こそ、こんな地味な喫茶店に何しに来てんだよ」
店内のBGMでおそらく他の店員には聞こえてないだろう声量でそう言った金髪。できれば店長か誰かにきこえてクビになってしまえばいいのにとそう思った。
「知り合いか?音代」
「タンバリン窃盗者だ」
「ああ、あの時の犯人か」
「紹介がひどすぎるだろ先生」
「事実だろ」と小さく笑う音代。現れたのは金髪には似合わないウエイター姿の九条であった。
「高校にバイト申請ちゃんと出してるのか九条」
「出してるわ、そういうのちゃんとしてっから俺」
「そうか」
そう言って空になったコーヒーカップを九条に差し出す。
「おかわりはいりましたー!」と居酒屋の店員のような声をあげた九条が奥に歩いていく。絶対クビになるだろうと音代は顔を歪めた。しかし縁とはこわいものだ、と音代は思う。自分が繋いだ音楽の縁がどんどん繋がっていく。
1人で打ち込んでいた時とはまた違った感触であった。
「お前のとこの生徒たちは本当にバラエティ豊かだな」
「そうだろう」
「褒めてないけどな」
そう言って神城が苦笑いを浮かべているとおもむろに音代が腕時計をみて立ち上がった。
「俺はそろそろ行くぞ」
「え、」
「最近軽音楽部に色々教えていてな。そろそろ部活が始まる頃だ」
「先生は忙しいんだな」
「まったくだ。俺は一ミリたりともやりたいとは思っていない」
言葉と表情が合っていない音代に神城は「そうかいそうかい」と笑って手を振る。
音代はシワのない千円札をテーブルに置き颯爽と店を出て行った。