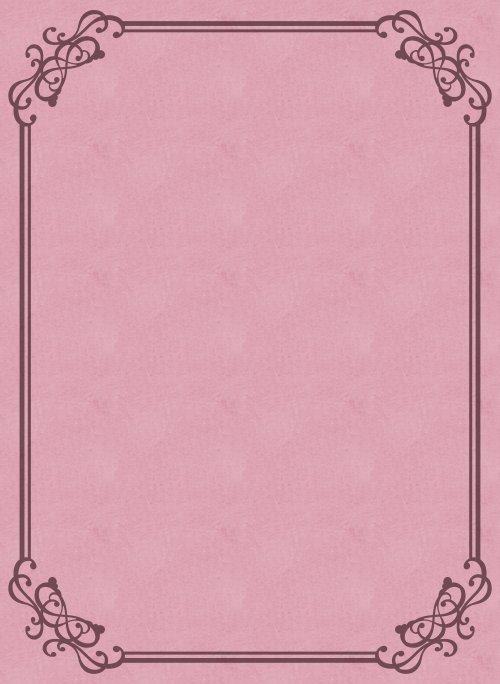「おい、岡島太一! ちょっと来い!」
とある日の放課後、僕は教室の外へと呼び出された。相手は桜田明美である。
「よお、どうした」
「どうしたじゃない! 今日は来ないのか、その……屋上」
屋上だけ小声で言う。周りを見ながら。
「だって、雨だから。大雨だから。いや、それより」
僕も小声になって言う。
「いいのか、こっちに来て。不登校なんだろ?」
「だって、仕方ないじゃない。連絡先知らないんだから」
「そうだっけ」
「そうだよ」
そっか。まあ、それなら仕方ないか。
「明日晴れたら行くよ」
「じゃあ、明日ね。晴れたらね」
「ああ」
それだけ言うと彼女は逃げるようにいなくなった。人目を避けるように消えていった。
僕もその日は、何をするわけでもなく家へと帰っていった。
※ ※ ※
それからしばらく、彼女と過ごす日々が続いた。彼女は隣で黙って座っていて、僕は放課後にギターを弾く。時々拍手が起こるけど、だいたいの場合一人きりのオーディエンスはこころの中で拍手している。いつも四六時中呼びかけていたナナとの会話時間は減り、ナナとの会話も明美の話が大半を占めるようになった。彼女は名実共に友人となっていた。同時に、ナナへの依存度は減っていたのも確かであった。
ある時、明美がしばらく姿を見せないことがあった。何日もいなかった。屋上にいないということは、学校にすら来ていないということなのだろう。何かあったのだろうかと、普通に心配した。
僕は職員室の山田先生のところを訪ね、明美の話をした。ふたりで屋上で会って友達になったことを話し、そして最近姿を見ないことを話した。
「桜田さんは、風邪ですよ。君ならば住所を教えても構わないだろう。いや、君たちが友達になれたというのは、先生にとって嬉しい話だ。ああ、何か起きるかもしれないと思って引き合わせてみたけど、そうかそうか。それは、良かった。ああ、彼女も学校に慣れてきただろうか。自分の居場所を作ることができたであろうか。学校だけが全てではないと、彼女がわかっているからこそ学校に来て欲しいと思う私の願いは、届いただろうか」
「先生、ありがとうございます」
「今日も屋上かい?」
「はい。日課ですから」
その日も、今日も変わらず、ギターを持って屋上に来た。いつもの場所で、壁を背にしてギターケースを開き、ギターを取り出す。チューナーを取り出し、電源をつけて、ギターを抱えて、ペグを回してチューニングを始める。
「いいのかい? お見舞いに行かなくて」
「ナナ、そんなの言わなくてもわかるじゃないか。風邪がうつったら、お互いに良くないだろう?」
「そうか、まあ、君がそう言うならいいんだけど」
僕はギターのチューナーを外して、それから一曲歌った。いつもの、いつも歌っている歌を、弾いて歌った。眠りにつくまで傍にいて欲しいだけという、それだけの歌だった。
「そういえば、僕が呼び出されるのは久しぶりだね。彼女が休んでいても、君は僕にすぐ頼ることはしなかった。彼女の心配はすれども、寂しさを埋めることはしなかった」
「関係ないよ。彼女も友達だからっていう、それだけだ。ナナも変わらず友達だろ?」
「うん。でも、僕はリアリティには存在しない。イマジナリーフレンドだ。架空の、想像上の、君の空想上にしか存在しない存在。それと違って、明美さんはリアルに、現実にいる友達。この違いは大きく違うよ。そして、同時にとても素晴らしいことだ。僕とは違う。うん、君はもう卒業できたんだ。イマジナリーフレンドから卒業して、リアルのフレンドを作ったんだ。おめでとう」
「卒業、か」
「なんだい? 不服なのかい?」
「不服と言うか、ナナは、なないろは、消えていなくなったりしないよな」
「もちろん。いつでも君に会うことができるし、話をすることができるだろうさ。ただ、現実の人間関係が増えて複雑になっていくうちに、そのうち僕の存在は必要なくなるんじゃないかと、そう思うけどね。そうであって欲しいと、そう思うよ」
「それこそ、卒業しろってことか。夢なんて見ていないで。夢想なんてしないで。大人になれって、そういうのか」
「時々思い出して懐かしいと思える。それぐらいがちょうどいいのさ。完全に忘れてしまうのは、それは僕だってさみしいからね」
「ナナ……そうだね、そうかもしれない」
僕はギターを触る。軽くアルペジオを弾いた。哀愁の漂うコード進行で。
「よし。やっぱり行くよ」
「そうか。それがいいと、僕も思うよ」
僕は片付けを始めた。ギターをギターケースに入れて肩に掛けて、担いで立ち上がった。
「行こう」
「僕も行くのかい?」
「もちろん。もうしばらくは一緒だよ」
僕はそう言って彼と共に屋上を飛び出した。大切な友人に会いに行くために。
とある日の放課後、僕は教室の外へと呼び出された。相手は桜田明美である。
「よお、どうした」
「どうしたじゃない! 今日は来ないのか、その……屋上」
屋上だけ小声で言う。周りを見ながら。
「だって、雨だから。大雨だから。いや、それより」
僕も小声になって言う。
「いいのか、こっちに来て。不登校なんだろ?」
「だって、仕方ないじゃない。連絡先知らないんだから」
「そうだっけ」
「そうだよ」
そっか。まあ、それなら仕方ないか。
「明日晴れたら行くよ」
「じゃあ、明日ね。晴れたらね」
「ああ」
それだけ言うと彼女は逃げるようにいなくなった。人目を避けるように消えていった。
僕もその日は、何をするわけでもなく家へと帰っていった。
※ ※ ※
それからしばらく、彼女と過ごす日々が続いた。彼女は隣で黙って座っていて、僕は放課後にギターを弾く。時々拍手が起こるけど、だいたいの場合一人きりのオーディエンスはこころの中で拍手している。いつも四六時中呼びかけていたナナとの会話時間は減り、ナナとの会話も明美の話が大半を占めるようになった。彼女は名実共に友人となっていた。同時に、ナナへの依存度は減っていたのも確かであった。
ある時、明美がしばらく姿を見せないことがあった。何日もいなかった。屋上にいないということは、学校にすら来ていないということなのだろう。何かあったのだろうかと、普通に心配した。
僕は職員室の山田先生のところを訪ね、明美の話をした。ふたりで屋上で会って友達になったことを話し、そして最近姿を見ないことを話した。
「桜田さんは、風邪ですよ。君ならば住所を教えても構わないだろう。いや、君たちが友達になれたというのは、先生にとって嬉しい話だ。ああ、何か起きるかもしれないと思って引き合わせてみたけど、そうかそうか。それは、良かった。ああ、彼女も学校に慣れてきただろうか。自分の居場所を作ることができたであろうか。学校だけが全てではないと、彼女がわかっているからこそ学校に来て欲しいと思う私の願いは、届いただろうか」
「先生、ありがとうございます」
「今日も屋上かい?」
「はい。日課ですから」
その日も、今日も変わらず、ギターを持って屋上に来た。いつもの場所で、壁を背にしてギターケースを開き、ギターを取り出す。チューナーを取り出し、電源をつけて、ギターを抱えて、ペグを回してチューニングを始める。
「いいのかい? お見舞いに行かなくて」
「ナナ、そんなの言わなくてもわかるじゃないか。風邪がうつったら、お互いに良くないだろう?」
「そうか、まあ、君がそう言うならいいんだけど」
僕はギターのチューナーを外して、それから一曲歌った。いつもの、いつも歌っている歌を、弾いて歌った。眠りにつくまで傍にいて欲しいだけという、それだけの歌だった。
「そういえば、僕が呼び出されるのは久しぶりだね。彼女が休んでいても、君は僕にすぐ頼ることはしなかった。彼女の心配はすれども、寂しさを埋めることはしなかった」
「関係ないよ。彼女も友達だからっていう、それだけだ。ナナも変わらず友達だろ?」
「うん。でも、僕はリアリティには存在しない。イマジナリーフレンドだ。架空の、想像上の、君の空想上にしか存在しない存在。それと違って、明美さんはリアルに、現実にいる友達。この違いは大きく違うよ。そして、同時にとても素晴らしいことだ。僕とは違う。うん、君はもう卒業できたんだ。イマジナリーフレンドから卒業して、リアルのフレンドを作ったんだ。おめでとう」
「卒業、か」
「なんだい? 不服なのかい?」
「不服と言うか、ナナは、なないろは、消えていなくなったりしないよな」
「もちろん。いつでも君に会うことができるし、話をすることができるだろうさ。ただ、現実の人間関係が増えて複雑になっていくうちに、そのうち僕の存在は必要なくなるんじゃないかと、そう思うけどね。そうであって欲しいと、そう思うよ」
「それこそ、卒業しろってことか。夢なんて見ていないで。夢想なんてしないで。大人になれって、そういうのか」
「時々思い出して懐かしいと思える。それぐらいがちょうどいいのさ。完全に忘れてしまうのは、それは僕だってさみしいからね」
「ナナ……そうだね、そうかもしれない」
僕はギターを触る。軽くアルペジオを弾いた。哀愁の漂うコード進行で。
「よし。やっぱり行くよ」
「そうか。それがいいと、僕も思うよ」
僕は片付けを始めた。ギターをギターケースに入れて肩に掛けて、担いで立ち上がった。
「行こう」
「僕も行くのかい?」
「もちろん。もうしばらくは一緒だよ」
僕はそう言って彼と共に屋上を飛び出した。大切な友人に会いに行くために。