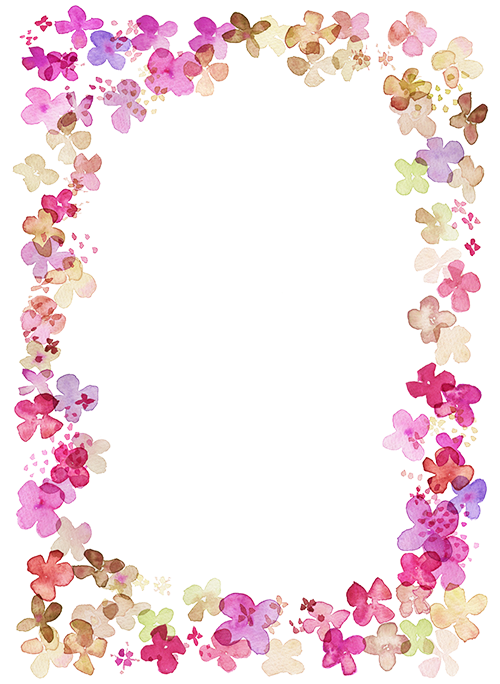海藤の葬儀は翌々日に行われた。
警察署というある意味一番安全と思われる場所で警官が殺されたという事実は世間を騒がせることになった。
マスコミ関係者の立ち入りは断っていたが、殉職ということで上司や同僚たちは大勢訪れていた。
海藤を殺したのが霧島向聖か、そして正義の刃かということは誰も口にしなかったが、多くの人々には頭によぎった一つの事件があったに違いない。
三年前、銃を持った男が小学校に押し入って、生徒と教師を人質に立てこもったことがあった。
追い詰められた犯人が発砲して子どもが怪我を負い、駆けつけた海藤が犯人を射殺した。
正当行為として法で処罰はされなかったが、確かに海藤は人を殺したことがある。正義の刃の対象に入る。
……だがそれは、と俺は歯噛みする。
「みことさん。立ちっぱなしで辛いでしょう。少し休憩してください」
憔悴した様子のみことさんをみつけて、俺はベンチに座らせた。
葬儀の主催者は海藤の奥さんだが、警察関係者への挨拶や対応はほとんどみことさんが行っていた。
「どうぞ」
俺は自販機で飲み物を買ってきてみことさんに渡す。
「はい、純君も」
みことさんの隣にちょこんと座った、彼女の息子の純君にもジュースを渡す。
純君を間に挟んで、俺はみことさんの様子をうかがった。よく眠れていないのか、みことさんの目の下にはクマができていた。顔色も悪く、細い体がますます細く見える。
かける言葉がみつからなくて、俺は手元の缶に目を落として黙った。その俺の袖を、くい、と小さな手が引っ張る。
「おじさん、おかあさんのお仕事の人だよね?」
「そうだよ。検事といって……そうだな、警察の仲間だ」
確かまだ八歳だったと聞く。俺が簡単に答えると、純君は丸い大きな目でじっと俺を見上げてきた。
「どうして、挑おじさんは殺されちゃったの?」
俺が説明に迷うと、純君はなお続けてくる。
「おじさんは強いんだよ。ぼくのこと、片手でえいって持ちあげちゃうの。それに大きいんだ。おじさんより大きい男の人見たことない」
「うん」
「でもすごく優しいんだ」
子どものいない海藤は、甥の純君をとても可愛がっていたと聞く。
「ああ。強くて大きくて、優しいな」
海藤は厳しい警官だったが、弱いものに優しい男だった。
「それで、おじさんは警察で、警察は正義の味方なんでしょ?」
「純。やめなさい」
「いいんです、みことさん。純君、続けて」
止めようとしたみことさんに声をかけて、俺は純君に向きなおる。
「おじさんは、いい人だよ。それなのに、どうしていい人を殺した犯人が、「正義の刃」なの?」
こんな小さな子どもの耳にも正義の刃の話が届いているのかと、俺は悔しく思う。
「それは、わるい人なんじゃないの?」
真っ直ぐな黒い瞳を見て、俺は考える。
たとえ子どもでも、大切な叔父を奪われた彼にその場しのぎのことは言えない。
俺は一つ頷いて、ゆっくりと言った。
「悪い人かどうかは、おじさんたちが法の前に犯人を連れていくまでは、まだわからない」
純君の前に指を立てて、俺は告げる。
「だけどこれだけは覚えておいで。挑おじさんは悪い人じゃない」
一つだけ、はっきりしていることがある。海藤は殺されるべき人間じゃなかった。法だって、海藤は処罰しなかった。
みことさんと純君が去っていった後、俺は葬儀場の中を歩いて陽介を探していた。今日まだ一度も見かけていなかったのだ。
「陽介」
弟は裏手のコンクリートに座り込んで、顔を両手で覆っていた。
「つらいな」
俺は肩を抱いて隣に座った。陽介の肩は震えて、顔を覆った指の間から涙がこぼれおちていく。
「海藤……う、ぐ」
いつも底抜けに明るい弟も、十年以上コンビを組んできた相棒の死の前には弱り切ってしまったようだった。
「しばらく仕事を休んでもいい。俺の家に来るか?」
力なく下がった肩を掴んで揺さぶる。そうしたら、陽介は光のない目で俺を見上げた。
「俺、ガキみたい」
「いいんだよ。俺はお前の兄だぞ。いくつになったってお前を守るさ」
「うん……」
しばらく二人並んで、無言で座っていた。
ふいに建物の扉が開いて、小柄な女性がためらいがちに顔を覗かせる。
海藤の奥さんの姿をみとめて、俺は慌てて立ち上がる。隣で陽介も立って、会釈した。
「お悔やみを申し上げます。旦那様には大変お世話になりました」
「いえ……こちらこそ。気難しい主人でしたが、陽介さんのおかげで仕事ができたと聞いておりますし」
「そんな。俺はご迷惑をおかけしたことの方が多かったです」
陽介はまだしゃくりあげながら、目を真っ赤にしてうつむいた。
気の弱そうな奥さんは、そっと俺を見上げて言葉に詰まる。
「あの……あなたは」
「陽介の兄の氷牙貴正です。検事で、一緒にお仕事をしたことがあります」
彼女は少しの間の後にぽつりと言う。
「氷牙さんのお話は、主人からよく伺っていました」
俺は彼女のためらいの意味を察して言う。
「俺のこと、気に食わないと言っておられたでしょう。喧嘩もよくしました」
「ええと……」
彼女は目を伏せて、それから顔を上げた。
「お気を悪くなさるかもしれませんが」
「いいえ。どうぞなんでも仰ってください」
恨み事の一つでも言って気持ちが少しでも楽になるのなら、それで構わなかった。
彼女は少し黙って、意を決したように顔を上げた。
「「氷牙は検事の分をわきまえてない。事件を調べるのは俺たち警察の仕事、それを使って考えるのが検事の仕事なのに」と、よく愚痴っていました」
俺ははっとして息を呑む。
正義の刃事件の現場や痕跡を追って、俺はどこにでも行った。だがそういう場に居合わせるたび、海藤は俺を睨んでいた。
「「あいつは俺たちを信用してないんじゃないか」と言って……たぶん、主人はあなたに信用されたかったのだと思います」
あの何かを押し殺したような視線は、俺を責めていたのだ。敵意ややっかみなどではなかった。それを今になって気づく。
「それで主人は、万が一自分に何かあった時は……氷牙さんにこれを渡してほしいと」
奥さんは俺に、封筒からチップを取り出して差し出す。
「これは?」
「主人が個人的に調べた、氷牙さんのご家族の殺人事件についてのデータだそうです」
本来なら、職務上の機密情報をいくら被害者の家族である俺にも与えるわけにはいかない。
それを覆しても、自分の死と同時に葬ってはいけない情報があったのだ。
「……ありがとうございます」
俺はチップを握り締めて頭を下げる。奥さんに、そして海藤に感謝する。
悲しみの渦の中に、確かな希望が見えた気がした。
海藤の残したデータを見るため、俺は自宅に帰ってすぐにパソコンを開いた。
ファイルを開こうとしたらロックがかかっている。四ケタの数字のようだから、おそらく誕生日だろうと当たりをつける。
俺は少し考えて、「0713」と打ち込んだ。
「やっぱりな」
ロックが解除されて、ファイルが開かれる。
みことさんに聞いたことがある、海藤の甥の純君の誕生日だ。俺も自分のデータのパスワードに正子の誕生日を入れているから、すぐに思い当った。
データの中には写真や鑑識資料、関係者からの聞きこみ結果などの事件資料、そして海藤自身が作った文書が入っていた。
それらを繰り返し読みこむ内に、俺は海藤がこの事件について強い疑念を抱いていたのを感じ取った。
「『第一被害者、氷牙優子。死亡時二十七歳。女性。職業、主婦。交友関係は狭いが良好、家族仲も良好とのこと。素行にも問題は見当たらない』」
海藤は短くまとめた後、強調体で記していた。
「『彼女の死因は間違いなく自殺である』……?」
俺は眉をひそめて関連資料を引く。鑑識資料では、確かに「刃物のようなもので自らを刺して自殺」と記されていた。
「……自殺?」
俺は呼吸が止まったような気がした。
事件の前の優子のことを思い出したが、少し元気がなかっただけで相談を受けたことはなかった。
「『山根愛理からの手紙、メール、複数の留守電履歴が残っている。いずれも夫と別れるようにとの脅迫的内容と判明。』」
けれど、想像をしていないわけではなかった。愛理がしつこく俺に妻と別れるよう迫ってくるのだから、優子にも何かしらの接触はしてくるのではないかと考えてはいた。
だが優子に訊いても、彼女は微笑んで何もないと繰り返していた。だからどこかで安心してしまっていたのだ。
「『自殺の原因は、愛理からの脅迫であったと推定される。』」
俺はパソコンの前で、からからの喉に言葉を通す。しばらく身動きができなかった。
でも警察からの話では、他殺だと聞かされていた。どうして俺の知っている情報と違うのだろう?
「『遺体の場所は台所。死亡推定時刻は午後二時。当時家には彼女以外誰もおらず、来客および侵入者の痕跡もないことからも、自殺でほぼ間違いないだろう』」
そう締めくくって、海藤は次のデータを残していた。
「『第二被害者、氷牙麗子。死亡時六十二歳。女性。職業、日舞教師。元小学校校長。交友関係は多岐に渡るが、問題点は見当たらない。近所、世間等の評判は高い』」
早くに父が亡くなったので、母は女手一つで俺と陽介を育ててくれた。家庭でも仕事でも出来た人で知られていて、定年した後は日舞教室を開きながら、一緒に暮らして孫の正子の育児の手伝いをしていた。
「『彼女の死因は他殺である。刃物のようなもので胸を刺されている。しかし死因の詳細には疑問が残る』」
再び強調体で、海藤は記していた。
「『彼女は失血死、大量出血死でもショック死でもない。心臓が瞬間的に停止している。つまり、刺されたその瞬間に死亡していたと分析されている』」
検死資料を読みこんで、俺も確信する。確かにこの死因はおかしい。死亡するまでのタイムラグがまるでないのだ。機械の電源を落としたかのように心臓が停止している。
「『月並みな分析ではあるが、犯人に特殊な技能があるか、あるいは特殊な凶器によるものと考えられる』」
海藤にしては歯切れの悪い書き方をしていた。
「『遺体の場所は玄関。死亡推定時刻は午後五時半。おそらく、日舞教室から帰った直後と思われる』」
そして画面の下に見え始めた名前に、俺は指先が震えるのを感じた。
「……『第三被害者、氷牙正子』」
最後に、俺がずっと探している正子の情報が記されていた。
「『行方不明時八歳。女の子。小学三年生。学校での成績は上位。スポーツはやや苦手。明るく、人に好かれる児童だった様子』」
それでも、子どもっぽいかんしゃくを起こすこともあれば、叱られて泣くこともある、八歳の普通の子どもだった。
「『事件当日、学校を出発して、午後三時に自宅アパートの二十メートル先で友達と別れたことが確認されている。遊びの約束はしなかったとのことから、おそらくは間もなく帰宅したと思われる』」
つまり、三時過ぎには正子は家に帰っていたことになる。
そこで、俺は海藤と同じで疑問を抱いた。
「『彼女が帰宅した時間には既に第一被害者の優子は死亡していたと推定される。そして台所に正子のランドセルが残っていることから、彼女は台所に立ち入ったと見られる』」
俺は画面を見ながら眉を寄せる。
「『正子は母親の死体を発見したのか? だがその後の正子の姿を見た者はいない。彼女は怖くなって自ら家を飛び出したのか、それとも現場にいたところを犯人に捕まって誘拐されたか、あるいは殺され遺体を隠されたのかは不明』」
俺は手を置いて考えた。
正子がいなくなったのは、彼女が偶然殺人現場に居合わせてしまったのを見咎められて、犯人に連れ去られたためだと思っていた。
だがそれはおかしい。第二被害者である母が殺されるのは正子が帰ってから三時間も後のことなのだ。
正子は現場を離れて、それで何者かに連れ去られたのか。あるいは犯人は正子が帰宅した時に既に家の中にいて、正子を拘束した後に母を殺して、そして正子を連れ去ったのか。
俺はもう一つだけ考えて顔をしかめる。
最後の一つは、正子は帰宅して犯人が母を殺しに来るまで、その場に残っていたというものだ。電話か何かで脅迫されて、そこを動くなとでも言われたとしよう。
それは一番残酷な可能性で、俺はすぐにそれを打ち消したくなった。
……母親の死体がある家で、八歳の子どもを三時間も留めておくなど酷過ぎる。
「『同日午後六時、第一発見者である氷牙貴正が現場に帰宅する。』」
そこから先は、俺のよく知る通りだ。
事件の経過を記した後、海藤はおもむろに続けた。
「『これらの資料のほとんどが、公的資料に残っていない』」
俺も奇妙に思っていた。優子が自殺であること、母の死因の詳細、そして死亡推定時刻などは警察に照会した情報と食い違うのだ。
「『記録の改ざんが行われている。警察あるいは検察機関の内部者によるものだろう』」
だから海藤は個人的に調べていたのだ。仲間である警察を疑い、おそらくは一人で事件を追っていた。
「『犯人は誰か?』」
自らに問いかけるように、海藤は記す。
「『山根愛理は犯行時刻に職場にいたという証拠がある。人に依頼したとしても、そもそも現場からは被害者の家族以外の痕跡が残っていない。』」
そうなると、海藤でなくとも誰を疑うか知れようというものだ。
「『容疑が一番強いのは氷牙貴正。それは間違いない』
痕跡を多く残していて、被害者を殺すだけの力がある若年男性、被害者たちともっとも関係が深い者、それは俺だ。
「『だがもし違うとしたら、次に疑うべきなのは』……」
一人で執拗に事件を追った、海藤が導いた仮説がそこにあった。
「……『氷牙正子だ。』」
正子はまだ八歳の子どもだった。いくら六十を超しているとはいえ、大人の祖母を一突きに殺せるはずがない。
「『何者かが彼女に特殊な凶器を渡して、氷牙麗子を殺させたのではないか。』」
俺はすぐにその仮説を否定したかった。あんな小さな子に祖母を殺させるなどという惨いことは起こっていないと信じたかった。
たとえそう考えれば、すべてつじつまが合うのだとしても。
「兄貴」
ふいに声をかけられて、俺は一瞬誰かわからなかった。
すぐに、俺は自宅のアパートでパソコンを見ていたことを思い出す。陽介が近くに来たことすら気付かなかったほど、海藤のデータに没頭していたのだ。
「起きてたのか。お前は休め。明日も早いんだろ?」
心配だったので、俺はしばらく陽介を自宅のアパートに泊めることにしたのだった。
時計を見ると時刻は午前四時を表示していた。
「兄貴こそ。明日だって仕事だろ。もう寝なよ」
「気にするな。徹夜くらい慣れてる」
俺は顔をしかめた陽介を何とか追い返す。
そしてもう一度最初から読みなおそうと、俺はパソコンに向きなおった。
翌日、俺は裁判所で今日の分の公判を終えて、地検への帰路を辿っていた。
イルミネーションが日に日に色鮮やかに町を飾っていく。世間ではクリスマスムード一色だ。
宗教では信仰の対象、一般人にはお祭り騒ぎ。だが、俺にとっては毎年苦い一日になる。
十年前のクリスマスの夜、俺は珍しく仕事が早く終わって、足早に帰路を辿っていた。
その日の朝は早くに出発したから、枕元に置いておいたクリスマスプレゼントを開けた正子の反応をまだ知らなかった。だが毎年正子はサンタからのプレゼントを楽しみに待っているから、きっと今年も喜んでくれるに違いないと思っていた。
今晩の夕食は妻の優子が正子のためにエビフライを作ると決まっていた。俺はケーキを買ってくると約束したから、手には正子が大好きな丸いデコレーションケーキの箱を持っていた。
ありふれた、幸せなクリスマスになるはずだった。
だが俺を待っていたのは、妻と母の無残な遺体だけ。正子の姿は二度と見られなくなった。
毎年、俺はクリスマスが近くなると弱い思いに捕われる。
このまま犯人は一生みつかることがなくて、正子に会うこともできないとしたら、一体俺は何のために生きているのかと絶望する。
――貴正。人は誰しも生きているだけで尊いんだ。
そんな俺に穏やかに語りかけて、希望を持つように繰り返し諭してくれたのは親友の向聖だ。
――きっと正子ちゃんは生きている。君の太陽は今もどこかで輝いていると信じるんだ。
俺に信仰心はないが、向聖の言葉にどれだけ救われたかわからない。
人の命の尊さを説いていた向聖が、正義の刃などといって人を次々と殺めていくものだろうか。二十数件以上に連なる連続殺人を犯し、そして子どもを守るために人を撃った海藤を刺したりなどするのか。
とても信じられない。俺は首を横に振って、地検の建物内に入った。
「氷牙、少しいいか」
自分の部屋に向かおうとした俺を、上司が呼びとめる。
「唐突になるが、お前、教会殺人事件の担当をやる気はないか?」
俺は軽く目を見開いて動きを止める。
「霧島向聖が容疑者の、ですか」
「そうだ。今後、海藤挑の刺殺事件を含めた……一連の「正義の刃」にもつながっていくだろう」
上司は難しい顔をしながら、言葉を失った俺を見やる。
「わかってる。お前にとっては身内の事件も絡んでて、冷静な一検事としての判断は難しい。俺もできればお前には振りたくない」
そこで上司は声をひそめて、周りに他の検事がいないことを確認して続ける。
「けどな、情けないことだが、他の検事たちが今回の担当を嫌がるんだよ。取り調べ中の警官が刺されたんだ。俺たちにも刃の先が向くかもしれない。それにこの事件はまだいろいろ不確かで、犯人が他にいる可能性も高い」
俺たちの職業は恨まれることなど数えきれないほどある。そんなことは検事になった以上皆覚悟している。
だが今回の事件は奇妙な点が多く、得体の知れない恐怖がつきまとう。
「お前の仕事ぶりは知ってる。個人的な思いがあったとしても、法を扱うことに関して、お前は誰より公平だ。任せられないか?」
霧島向聖に、親友に法の刃を向けることができるか。
俺は自問して、即答する。
「できます。俺は検事です」
やってみせると、俺は強く上司を見返す。
法を犯したのならその罪を問わなければならない。たとえ親友でも家族でも、法の前ではすべて平等だ。
「頼むぞ、氷牙」
俺は頷いて、前を見据えた。
向聖は、教会殺人事件と合わせて海藤の刺殺容疑で現行犯逮捕されて拘束されていた。
俺はそれを警官殺人事件として担当が決まった直後に資料を受け取った。渡された送検資料を読みこんで、事件の詳細を把握して翌朝を迎えた。
勾留請求の期限まで一日を切っている。しかしすぐに請求できない理由があった。
警察の方から来た資料だけでは、海藤の刺殺事件についての嫌疑が確認できなかった。
事件当時取り調べ室には向聖と海藤しかいなかったといわれるが、刺した現場を誰も見ていない。向聖自身もこの事件について容疑を否認している。凶器も発見されていなければ、他の物証もない。
「このまま勾留すれば、弁護士は違法逮捕を主張してきますよ」
状況からそうと判断されただけで逮捕請求をしたと判断されかねない。俺の考えに、事務官のみことさんも同意した。
海藤の刺殺事件については、みことさんは事務官の役を外れる。被害者が弟なのだから当然だ。
「起訴するのであれば確実な証明を目指す覚悟が必要でしょう。……あとは、お願いします」
「はい」
みことさんは頭を下げて、部屋を出て行った。
向聖はまもなく係官に連れられて、警官殺人事件の件で呼び出された。
「おはようございます」
寝不足の様子もなくすっきりとした顔色で会釈して、向聖は俺の机の向こうの椅子に座った。
「まず、お名前をお願いします」
「霧島向聖です」
簡単な確認事項から始めて、事件の内容についても訊いていく。横の席で代理の事務官がタイプを打っていく。
「あなたは警官を刺してはいないと話したそうですね」
「はい。私は刺していません」
「しかしあなたの目の前で警官が胸から血を流して倒れたのは見ているそうですね。他の誰かが刺したのを見ていたのですか?」
向聖は俺を真っ直ぐに見据えたまま答える。
「知りません」
少し奇妙な答えだが、調書にも同じように記載されている。見ていない、ではなく、知らない、と向聖は言っている。
俺は少し考えて続ける。
「警官の胸に何が刺さっていたのかは見ましたか?」
「刃です。これくらいの大きさの、包丁のようなものです」
内心で俺は気を引き締める。今まで、正義の刃事件では胸から血を噴くところは見ているが、凶器自体を見た者はいないのだ。
「その刃はどこにいったのですか?」
「消えました」
思わず眉を寄せそうになって、しかし俺は調書に目を戻す。
警察の取調調書でも、向聖は刃が消えたと話している。別に目の前の俺をからかっているわけではない。
「誰かが持ち去ったのですか?」
「いいえ。なくなったのです」
「溶けたと?」
刃は氷や揮発性物質だとでもいうのか。しかし海藤の死亡推定時刻後の数分以内に警官が駆け付けて調べたが、何の反応もなかったという。
「瞬間的に消えました」
向聖はそれ以上の詳細を語らなかった。
俺はその部分での追及を諦めて、他の事項を確認していく。
向聖はいずれも丁寧に、落ち着いて答えた。無駄なことは何一つ語らず、終始紳士的に俺の質問に応じていた。
質問を終えて向聖を係官に託した後、俺は書類を見返しながらしばらく考えた。
「どうしますか?」
事務官の問いかけに、俺は一つ頷く。
「勾留請求はしません。釈放しましょう」
俺の答えに、事務官は異議を唱えることはしなかった。プロとして、送検資料と今の質問を総合して同じ結論を弾きだしたのだろう。
「ただし、警察に連絡してください。教会殺人事件の件で、現場の実況見分に彼を立ち会わせましょう」
「別件になりませんか?」
「任意で応じてもらえるならば」
たぶん、向聖は応じるはずだ。確信はないが、向聖は事件の隠ぺいやかく乱は狙っていない。
彼は何か黙っていることがある。それは俺の勘だった。
「取れました。行きましょう」
みことさんが戻ってきて、俺たちは実況見分に向かった。
霧島教会は今年の始めまで向聖が住み込みの神父をしていた。
現在は養子である聖也君が神父の役目を継いだが、今も向聖を慕っている信者は多く、聖也君が留守の場合は向聖が中心となって集会を行うそうだ。
聖也君の実父が殺された霧島教会殺人事件も、その向聖が主催した集会で起きたということだ。
「集会の間、あなたが立っていた場所を教えてください」
被害者の倒れていた場所に印が残っている以外は、教会はもう綺麗に掃除されていた。
向聖は警官の質問に応じて、自分の立ち位置や事件当時の周囲の様子などを答えていた。
「そこから私はここまで歩いて……」
実況見分には警官と向聖、俺とみことさんの他に、集会に参加していたことがわかっている信者五人や聖也君も立ち会っていた。
暖房もない石造りの教会の中は冷え切っていた。その中で、聖也君はコートも着ずに微動だにせず向聖を見守っている。
実父の葬儀は行われたそうだが、聖也君に悲しみの色は見えなかった。ただ、向聖の身の心配だけをしているように思えた。
「入口は二つ。その内の祭壇側の扉は鍵がかかっていて、それは霧島聖也君だけが持っていたそうですね」
「はい」
その事実は既に警察の調べでわかっている。集会に来た人々も向聖も、正面入り口から入って出たと考えられている。
「当日は朝から一般の方の立ち入りをお断りして、教会内には信者しかいませんでした」
信者の内誰も、向聖が被害者を刺した所を見ていない。凶器も物証もなく、向聖自身が刺したと自供しているだけだ。
だからこの事件では向聖は逮捕すらされていない。海藤の事件の方でも既に釈放してしまったから、実況見分が終われば向聖は自由の身だ。
嫌疑がなければ身柄の拘束は許されない。それは法で決まっていて、俺たちでは変えようもない。
滞りなく進んでいく実況見分を見ながら、俺は考える。
何か、見落としていることがないだろうか。もちろん捜査のプロである警察を差し置いて俺が気づくことなどごくわずかしかないだろうが、それでも引っ掛かる部分があるのだ。
「では、ここまでとしましょう」
実況見分が終了した時、俺は何気なく庭を見やった。
「……そうだ」
思わず声を上げて、俺は聖也君に目を向ける。
「事件前、教会に滞在していた旅行者の女の子がいた。彼女は今もいるのか?」
聖也君は青い目で俺を見返して頷く。
「テラさんですね。ええ、ずっと滞在していらっしゃいます」
「ここへ連れてきてもらえないか。話を聞きたい」
教会の中には信者しかいなくとも、庭には部外者がいたかもしれない。何か知っているかもしれなかった。
間もなく庭の花壇の方から、聖也君がテラさんを連れてきた。今日の彼女は明らかに実用向きではない、ベレー帽を脇に抱えていた。
「こんにちは」
愛想良く笑いかけて、黒髪の旅行者は俺たちの前にやってくる。
「この教会で殺人事件が起こったことは知っているね。君はその日どこにいた?」
テラさんはゆるりと視線を巡らせて警官の姿を確認する。
「さあ。観光に行っていたような気がします」
はぐらかされた感じがしたので、俺は言葉を重ねようとする。
「旅行者なら、まずパスポートを見せて頂けますか?」
警官が近付いてきて少し疑惑を浮かべた目で彼女を見た。
テラさんはそれに穏やかに返す。
「今手元に持っていないのです。取ってきますので、少々お待ちください」
「待って」
一礼して踵を返した彼女を、思わず俺は引きとめていた。
今行かせたら、二度と彼女はここに戻らない。そう直感で思ったのだ。
「パスポートは結構、少し話を聞くだけだから。……場所を変えよう」
おそらく警官がいる前では彼女は何も話さない。それを察して、俺は渋る警官たちを残して、テラさんを教会の裏手に連れてきた。
「君の事情は訊かない。だから、事件の日に君が見たことを正直に話してくれないか」
二人きりになってすぐ切り出した俺に、テラさんはゆっくりと言う。
「私の旅の方針として、その国の方々のお邪魔をしないというものがあります」
「邪魔にはならない。少し協力してほしいんだ」
「協力とは、誰かに肩入れするということです」
年若く見えるが、彼女の言葉には断固とした意思が見えた。
「私は旅行者です。本来、そこにはいない者です。私は何も残しませんし何も奪いません」
俺はテラさんの黒い瞳を見返して少し黙った。
「……私からもお願いできませんか」
ふいに近付いてきたのは向聖だった。話を聞いていたらしい彼は、テラさんの前に歩み寄ってくる。
「私の罪を暴く手伝いをして頂きたいのです。このままでは、私の罪は闇に葬られてしまいます」
俺は咄嗟に閃くものを感じて言葉を発していた。
「テラさん。君は与えられたものは返すかい?」
無言で俺を見たテラさんに、俺は続ける。
「君はそこの教会の酒場でビールを飲んだね。それを作ったのは彼の会社なんだ。ビール一杯分だけでいいから、協力してくれないか」
こじつけでもいいと思いながら言った俺の前で、テラさんは黙った。
「お金は払いましたけど……そうですね」
彼女の少し変わった感覚は、俺の言葉に反応を返した。
「こちらのビールは代金以上においしかったので、何かお礼をしなければいけませんね」
テラさんはぐるりと裏庭を見渡して、一点を指さす。
「あの石の下を掘ってみてください」
「は?」
怪訝な顔をした俺に、テラさんは微笑んだ。
「では」
ベレー帽を被って、不思議な少女は去っていった。
後で彼女の示した場所を掘ってみると、そこから血のついた祭服が出てきた。鑑識にかけると、教会殺人事件の被害者の血と判明した。
そこに残っていた複数の指紋は信者たちのものとわかって、事件がようやく見え始めた。
聖也君を虐待していた被害者を殺害する計画を立てたのは信者たちだったこと、事件を隠ぺいしようと信者たちが血のついた向聖の祭服を奪って埋めたことなどだ。
向聖は信者たちを庇っていたのだということも明らかになった。
ようやく現れた物証によって、向聖は教会殺人の件で逮捕された。
しかし依然として、凶器は未知のままだった。
久しぶりの休日の朝、俺は開きっぱなしになっているパソコンの方を見やって違和感に目を止めた。
慌てて机の上や引き出しの中を探して、俺は呟く。
「……ない」
海藤の残したチップがなくなっていた。昨日の夜までは、パソコンの横に置いてあったはずなのだ。
データ自体は繰り返し読みこんでいて、すべて頭の中に入っている。
それより問題はと、俺は机に手をついて一番大きな可能性を思った。
「兄貴と二人で外出なんて久しぶりだ」
俺は朝食の後、海藤の死から引きこもりがちだった陽介を連れ出して海辺の公園に来ていた。
「デートスポットに男二人っていうのも何だけどな。まあ、気晴らしにはなるだろ」
「でも昔はよく来たよね、この公園」
港が間近に見えるここは、子どもの頃は俺と陽介の遊び場だった。昔の家から近かったこともあって、天気のいい日はいつも陽介と駆けまわっていた。
喧嘩もよくしたが、元気いっぱいに飛びついてくる陽介と遊ぶのは楽しかったのを覚えている。
真冬には珍しく、空は真っ青に晴れ渡っていた。その下を、いろいろな人々が歩いていく。
ベンチに座って、しばらく二人で海を見ていた。水面が太陽の光を受けて輝いていた。
「陽介」
俺は意を決して口を開く。
「海藤のデータを隠したのはお前か?」
陽介は無言だった。俺は続けて言う。
「お前を責めてるんじゃない。俺が事件に関わり続けることを快く思ってないことくらいわかってる。俺を心配してくれてるってことも」
事件に捕われ続けて俺が自分の人生を見失うのではないかと、この弟がずっと不安そうな眼差しで見ていたことを知っているのだ。
「でもな、俺は一生、正子の父親なんだ。あの子を俺の人生から消してしまうことはできないんだ」
「知ってるよ。兄貴は優しいから」
陽介は少しうつむいた。
それからしばらく沈黙して、陽介はぽつりと問う。
「兄貴は法としょうちゃん、どっちが大事?」
俺は陽介に振り向く。
「もししょうちゃんが法に反するどうしようもなく悪いことをしちゃったら、兄貴はしょうちゃんを裁きにかけられる?」
少し驚きはしたが、俺はすぐに返した。
「正子が罪を犯したのなら、それはきちんと法の前で裁かれないといけない」
相手が誰であってもそれは変わらない。
「だがそれとは別に、俺は父親として正子を叱ってやらないといけない。何より、守ってやらなくては」
「そっか」
陽介は目を伏せたまま頷く。
「しょうちゃんでそれなら、俺は訊くまでもないね」
俺は怪訝な顔をして陽介の肩を叩く。
「何言ってる。お前も俺の大事な家族だ。俺の身に代えても守るさ」
「俺がどうしようもなく悪いことをしちゃったとしても?」
前髪に隠れて、陽介の目が見えなかった。
「警察の情報を改ざんして、しょうちゃんたちの事件を隠ぺいしたのは俺だよ」
「な」
思わず立ち上がった俺の腕を、陽介が掴む。
「そして……」
ふいに携帯電話が鳴って、俺は立ち竦む。
「兄貴の携帯だよ」
俺の腕を掴んだまま、陽介は波のない口調で告げた。
俺は空いた方の腕でポケットを探って、携帯を耳に当てる。
『氷牙!』
息を切らして、上司が通話に出た。
「どうしたんです。休日まで仕事ですか?」
『お前、今どこにいる?』
「港の公園ですけど」
『そこに弟の陽介はいるか』
俺は俯いたままの弟を見やってから返す。
「目の前にいますが」
『すぐに逃げろ。警察はもう動いてくれてる』
事態が全く読めなくて、俺は首を傾げる。
『ついさっき、氷牙陽介に対する逮捕状が出た』
目を見開いた俺に、上司の声が残酷な事実を告げる。
『返り血のついた彼の制服がみつかったんだ。……海藤を刺したのは陽介だ』
俺は思わず通話を切った。
デートらしいカップルの笑う声が近くを通り過ぎていった。
「なん、で」
立ち尽くす俺に、陽介は口を開いた。
「不思議だったよ。どうして誰も、第一発見者の俺を疑わないのかって」
「陽介。嘘だよな。お前が」
「あんなにガタイがよくて強い海藤が、何の抵抗もなく刺されるなんて変だと思わない?」
「海藤はお前の相棒じゃないか!」
声を上げた俺を、陽介はきっと睨んだ。
「あいつといると、兄貴はあいつを見るじゃないか!」
見たこともない激しい目で、陽介は俺を見る。
「弟は俺だけのはずなのに、兄貴に一番近いのは俺のはずなのに、兄貴は俺より海藤を気にしてたじゃないか」
我を失ったように、陽介は声を荒げる。
「そうだよ。ずっと殺してやりたかったさ。あいつは俺から兄貴を取った!」
まるで俺を憎んでいるように、陽介は言い放った。
海藤を殺した犯人を、俺は何度も憎んだ。もし会ったら、殺してやりたいと願うくらいに。
だが今陽介を目の前にして、俺は何の言葉も出てこなかった。憎むことも恐れることもできず、ただ見ることしかできなかった。
「……違う」
陽介は再び顔を伏せて、うめくように呟く。
「本当に殺したかったのは、しょうちゃんだ。あの子が生まれてから、兄貴はしょうちゃんを一番に思うようになった」
独白のように、陽介はぽつりぽつりと言葉を漏らす。
「でもあの子は誰も殺せなかった。兄貴は言ってたね、正子はうちの太陽だって。そうだ、太陽は誰も消せないんだ」
陽介の声が沈んでいく。
「兄貴、人の数だけ影ができるんだよ。光が眩しければ眩しいほど、影は濃くなる。真っ暗な闇ができる」
「……陽介」
俺は乾いた喉に息を通して、かろうじて声といえるものを出した。
「誰も殺せなかった、と言ったな。正子は、今も生きてるのか?」
陽介は小さく頷く。
「生きてるよ。……もう、兄貴の知ってるしょうちゃんじゃないけど」
生きている。正子が、今も。
たとえどんな姿になっていても構わない。もう一度会えるのならば。
俺はその一言が泣きたくなるほど嬉しかったが、同時に目を逸らしてはいけない現実に気づく。
「お前が、優子と母さんを殺したのか?」
「違う。俺じゃない!」
陽介は首を横に振って否定する。
「俺は誰も殺して……海藤だって殺さずに済んだはずなんだ。あんなものがなかったら、俺は……!」
陽介の頬を涙が流れていく。堰を切ったように溢れていく。
震えながら俺の胸にしがみついて、陽介は消え入りそうな声で言った。
「……助けて、兄貴」
それは簡単に振り払えそうなほどの弱い力でしかなかった。
「次は俺だ。刃は俺を殺す。逃げられない」
「落ち着け、陽介」
俺は陽介の顔を上げさせて、涙に濡れたその顔を覗き込む。
「大丈夫だ。俺がいる。お前を守る」
噛みしめるように告げた言葉に、陽介の目が微かに正気を取り戻す。
「……ああ、やっぱり兄貴だ」
陽介は涙を流しながら、ほんの少しだけ表情を和らげた。
「正しくて、強くて、優しい。俺の大好きな兄貴は、あんな魔物なんかに負けない」
「陽介?」
弟は腕を解いて自ら立ち上がる。
ふらりと俺の横を通り過ぎようとする。
「海藤、ごめん」
そう呟いた瞬間だった。
視界の隅に赤い液体が見えた。それを無意識の内に目で追って、俺は戦慄する。
陽介の胸から血が噴き出していた。
「……陽介!」
仰向けに倒れた陽介を抱き起そうとする。だが陽介は目を見開いたままぴくりとも動かない。
「誰か、救急車を呼んでください!」
陽介の服が血で染まっていく。手で押さえても、次々と血が流れ出て行く。
胸には何も刺さっていない。銃弾かと、俺は辺りを見回す。
周囲は人で溢れている。通行人たちが、何事かと見ている。わからない。誰も近付いた形跡などなかった。
どこだ。誰なんだ。
……そんなことは今考えている場合じゃないのに、頭が混乱してどうしようもない。
「陽介、陽介……!」
救急車が来て死亡が確認されるまで、俺は陽介を抱えてうずくまることしかできなかった。
警察署というある意味一番安全と思われる場所で警官が殺されたという事実は世間を騒がせることになった。
マスコミ関係者の立ち入りは断っていたが、殉職ということで上司や同僚たちは大勢訪れていた。
海藤を殺したのが霧島向聖か、そして正義の刃かということは誰も口にしなかったが、多くの人々には頭によぎった一つの事件があったに違いない。
三年前、銃を持った男が小学校に押し入って、生徒と教師を人質に立てこもったことがあった。
追い詰められた犯人が発砲して子どもが怪我を負い、駆けつけた海藤が犯人を射殺した。
正当行為として法で処罰はされなかったが、確かに海藤は人を殺したことがある。正義の刃の対象に入る。
……だがそれは、と俺は歯噛みする。
「みことさん。立ちっぱなしで辛いでしょう。少し休憩してください」
憔悴した様子のみことさんをみつけて、俺はベンチに座らせた。
葬儀の主催者は海藤の奥さんだが、警察関係者への挨拶や対応はほとんどみことさんが行っていた。
「どうぞ」
俺は自販機で飲み物を買ってきてみことさんに渡す。
「はい、純君も」
みことさんの隣にちょこんと座った、彼女の息子の純君にもジュースを渡す。
純君を間に挟んで、俺はみことさんの様子をうかがった。よく眠れていないのか、みことさんの目の下にはクマができていた。顔色も悪く、細い体がますます細く見える。
かける言葉がみつからなくて、俺は手元の缶に目を落として黙った。その俺の袖を、くい、と小さな手が引っ張る。
「おじさん、おかあさんのお仕事の人だよね?」
「そうだよ。検事といって……そうだな、警察の仲間だ」
確かまだ八歳だったと聞く。俺が簡単に答えると、純君は丸い大きな目でじっと俺を見上げてきた。
「どうして、挑おじさんは殺されちゃったの?」
俺が説明に迷うと、純君はなお続けてくる。
「おじさんは強いんだよ。ぼくのこと、片手でえいって持ちあげちゃうの。それに大きいんだ。おじさんより大きい男の人見たことない」
「うん」
「でもすごく優しいんだ」
子どものいない海藤は、甥の純君をとても可愛がっていたと聞く。
「ああ。強くて大きくて、優しいな」
海藤は厳しい警官だったが、弱いものに優しい男だった。
「それで、おじさんは警察で、警察は正義の味方なんでしょ?」
「純。やめなさい」
「いいんです、みことさん。純君、続けて」
止めようとしたみことさんに声をかけて、俺は純君に向きなおる。
「おじさんは、いい人だよ。それなのに、どうしていい人を殺した犯人が、「正義の刃」なの?」
こんな小さな子どもの耳にも正義の刃の話が届いているのかと、俺は悔しく思う。
「それは、わるい人なんじゃないの?」
真っ直ぐな黒い瞳を見て、俺は考える。
たとえ子どもでも、大切な叔父を奪われた彼にその場しのぎのことは言えない。
俺は一つ頷いて、ゆっくりと言った。
「悪い人かどうかは、おじさんたちが法の前に犯人を連れていくまでは、まだわからない」
純君の前に指を立てて、俺は告げる。
「だけどこれだけは覚えておいで。挑おじさんは悪い人じゃない」
一つだけ、はっきりしていることがある。海藤は殺されるべき人間じゃなかった。法だって、海藤は処罰しなかった。
みことさんと純君が去っていった後、俺は葬儀場の中を歩いて陽介を探していた。今日まだ一度も見かけていなかったのだ。
「陽介」
弟は裏手のコンクリートに座り込んで、顔を両手で覆っていた。
「つらいな」
俺は肩を抱いて隣に座った。陽介の肩は震えて、顔を覆った指の間から涙がこぼれおちていく。
「海藤……う、ぐ」
いつも底抜けに明るい弟も、十年以上コンビを組んできた相棒の死の前には弱り切ってしまったようだった。
「しばらく仕事を休んでもいい。俺の家に来るか?」
力なく下がった肩を掴んで揺さぶる。そうしたら、陽介は光のない目で俺を見上げた。
「俺、ガキみたい」
「いいんだよ。俺はお前の兄だぞ。いくつになったってお前を守るさ」
「うん……」
しばらく二人並んで、無言で座っていた。
ふいに建物の扉が開いて、小柄な女性がためらいがちに顔を覗かせる。
海藤の奥さんの姿をみとめて、俺は慌てて立ち上がる。隣で陽介も立って、会釈した。
「お悔やみを申し上げます。旦那様には大変お世話になりました」
「いえ……こちらこそ。気難しい主人でしたが、陽介さんのおかげで仕事ができたと聞いておりますし」
「そんな。俺はご迷惑をおかけしたことの方が多かったです」
陽介はまだしゃくりあげながら、目を真っ赤にしてうつむいた。
気の弱そうな奥さんは、そっと俺を見上げて言葉に詰まる。
「あの……あなたは」
「陽介の兄の氷牙貴正です。検事で、一緒にお仕事をしたことがあります」
彼女は少しの間の後にぽつりと言う。
「氷牙さんのお話は、主人からよく伺っていました」
俺は彼女のためらいの意味を察して言う。
「俺のこと、気に食わないと言っておられたでしょう。喧嘩もよくしました」
「ええと……」
彼女は目を伏せて、それから顔を上げた。
「お気を悪くなさるかもしれませんが」
「いいえ。どうぞなんでも仰ってください」
恨み事の一つでも言って気持ちが少しでも楽になるのなら、それで構わなかった。
彼女は少し黙って、意を決したように顔を上げた。
「「氷牙は検事の分をわきまえてない。事件を調べるのは俺たち警察の仕事、それを使って考えるのが検事の仕事なのに」と、よく愚痴っていました」
俺ははっとして息を呑む。
正義の刃事件の現場や痕跡を追って、俺はどこにでも行った。だがそういう場に居合わせるたび、海藤は俺を睨んでいた。
「「あいつは俺たちを信用してないんじゃないか」と言って……たぶん、主人はあなたに信用されたかったのだと思います」
あの何かを押し殺したような視線は、俺を責めていたのだ。敵意ややっかみなどではなかった。それを今になって気づく。
「それで主人は、万が一自分に何かあった時は……氷牙さんにこれを渡してほしいと」
奥さんは俺に、封筒からチップを取り出して差し出す。
「これは?」
「主人が個人的に調べた、氷牙さんのご家族の殺人事件についてのデータだそうです」
本来なら、職務上の機密情報をいくら被害者の家族である俺にも与えるわけにはいかない。
それを覆しても、自分の死と同時に葬ってはいけない情報があったのだ。
「……ありがとうございます」
俺はチップを握り締めて頭を下げる。奥さんに、そして海藤に感謝する。
悲しみの渦の中に、確かな希望が見えた気がした。
海藤の残したデータを見るため、俺は自宅に帰ってすぐにパソコンを開いた。
ファイルを開こうとしたらロックがかかっている。四ケタの数字のようだから、おそらく誕生日だろうと当たりをつける。
俺は少し考えて、「0713」と打ち込んだ。
「やっぱりな」
ロックが解除されて、ファイルが開かれる。
みことさんに聞いたことがある、海藤の甥の純君の誕生日だ。俺も自分のデータのパスワードに正子の誕生日を入れているから、すぐに思い当った。
データの中には写真や鑑識資料、関係者からの聞きこみ結果などの事件資料、そして海藤自身が作った文書が入っていた。
それらを繰り返し読みこむ内に、俺は海藤がこの事件について強い疑念を抱いていたのを感じ取った。
「『第一被害者、氷牙優子。死亡時二十七歳。女性。職業、主婦。交友関係は狭いが良好、家族仲も良好とのこと。素行にも問題は見当たらない』」
海藤は短くまとめた後、強調体で記していた。
「『彼女の死因は間違いなく自殺である』……?」
俺は眉をひそめて関連資料を引く。鑑識資料では、確かに「刃物のようなもので自らを刺して自殺」と記されていた。
「……自殺?」
俺は呼吸が止まったような気がした。
事件の前の優子のことを思い出したが、少し元気がなかっただけで相談を受けたことはなかった。
「『山根愛理からの手紙、メール、複数の留守電履歴が残っている。いずれも夫と別れるようにとの脅迫的内容と判明。』」
けれど、想像をしていないわけではなかった。愛理がしつこく俺に妻と別れるよう迫ってくるのだから、優子にも何かしらの接触はしてくるのではないかと考えてはいた。
だが優子に訊いても、彼女は微笑んで何もないと繰り返していた。だからどこかで安心してしまっていたのだ。
「『自殺の原因は、愛理からの脅迫であったと推定される。』」
俺はパソコンの前で、からからの喉に言葉を通す。しばらく身動きができなかった。
でも警察からの話では、他殺だと聞かされていた。どうして俺の知っている情報と違うのだろう?
「『遺体の場所は台所。死亡推定時刻は午後二時。当時家には彼女以外誰もおらず、来客および侵入者の痕跡もないことからも、自殺でほぼ間違いないだろう』」
そう締めくくって、海藤は次のデータを残していた。
「『第二被害者、氷牙麗子。死亡時六十二歳。女性。職業、日舞教師。元小学校校長。交友関係は多岐に渡るが、問題点は見当たらない。近所、世間等の評判は高い』」
早くに父が亡くなったので、母は女手一つで俺と陽介を育ててくれた。家庭でも仕事でも出来た人で知られていて、定年した後は日舞教室を開きながら、一緒に暮らして孫の正子の育児の手伝いをしていた。
「『彼女の死因は他殺である。刃物のようなもので胸を刺されている。しかし死因の詳細には疑問が残る』」
再び強調体で、海藤は記していた。
「『彼女は失血死、大量出血死でもショック死でもない。心臓が瞬間的に停止している。つまり、刺されたその瞬間に死亡していたと分析されている』」
検死資料を読みこんで、俺も確信する。確かにこの死因はおかしい。死亡するまでのタイムラグがまるでないのだ。機械の電源を落としたかのように心臓が停止している。
「『月並みな分析ではあるが、犯人に特殊な技能があるか、あるいは特殊な凶器によるものと考えられる』」
海藤にしては歯切れの悪い書き方をしていた。
「『遺体の場所は玄関。死亡推定時刻は午後五時半。おそらく、日舞教室から帰った直後と思われる』」
そして画面の下に見え始めた名前に、俺は指先が震えるのを感じた。
「……『第三被害者、氷牙正子』」
最後に、俺がずっと探している正子の情報が記されていた。
「『行方不明時八歳。女の子。小学三年生。学校での成績は上位。スポーツはやや苦手。明るく、人に好かれる児童だった様子』」
それでも、子どもっぽいかんしゃくを起こすこともあれば、叱られて泣くこともある、八歳の普通の子どもだった。
「『事件当日、学校を出発して、午後三時に自宅アパートの二十メートル先で友達と別れたことが確認されている。遊びの約束はしなかったとのことから、おそらくは間もなく帰宅したと思われる』」
つまり、三時過ぎには正子は家に帰っていたことになる。
そこで、俺は海藤と同じで疑問を抱いた。
「『彼女が帰宅した時間には既に第一被害者の優子は死亡していたと推定される。そして台所に正子のランドセルが残っていることから、彼女は台所に立ち入ったと見られる』」
俺は画面を見ながら眉を寄せる。
「『正子は母親の死体を発見したのか? だがその後の正子の姿を見た者はいない。彼女は怖くなって自ら家を飛び出したのか、それとも現場にいたところを犯人に捕まって誘拐されたか、あるいは殺され遺体を隠されたのかは不明』」
俺は手を置いて考えた。
正子がいなくなったのは、彼女が偶然殺人現場に居合わせてしまったのを見咎められて、犯人に連れ去られたためだと思っていた。
だがそれはおかしい。第二被害者である母が殺されるのは正子が帰ってから三時間も後のことなのだ。
正子は現場を離れて、それで何者かに連れ去られたのか。あるいは犯人は正子が帰宅した時に既に家の中にいて、正子を拘束した後に母を殺して、そして正子を連れ去ったのか。
俺はもう一つだけ考えて顔をしかめる。
最後の一つは、正子は帰宅して犯人が母を殺しに来るまで、その場に残っていたというものだ。電話か何かで脅迫されて、そこを動くなとでも言われたとしよう。
それは一番残酷な可能性で、俺はすぐにそれを打ち消したくなった。
……母親の死体がある家で、八歳の子どもを三時間も留めておくなど酷過ぎる。
「『同日午後六時、第一発見者である氷牙貴正が現場に帰宅する。』」
そこから先は、俺のよく知る通りだ。
事件の経過を記した後、海藤はおもむろに続けた。
「『これらの資料のほとんどが、公的資料に残っていない』」
俺も奇妙に思っていた。優子が自殺であること、母の死因の詳細、そして死亡推定時刻などは警察に照会した情報と食い違うのだ。
「『記録の改ざんが行われている。警察あるいは検察機関の内部者によるものだろう』」
だから海藤は個人的に調べていたのだ。仲間である警察を疑い、おそらくは一人で事件を追っていた。
「『犯人は誰か?』」
自らに問いかけるように、海藤は記す。
「『山根愛理は犯行時刻に職場にいたという証拠がある。人に依頼したとしても、そもそも現場からは被害者の家族以外の痕跡が残っていない。』」
そうなると、海藤でなくとも誰を疑うか知れようというものだ。
「『容疑が一番強いのは氷牙貴正。それは間違いない』
痕跡を多く残していて、被害者を殺すだけの力がある若年男性、被害者たちともっとも関係が深い者、それは俺だ。
「『だがもし違うとしたら、次に疑うべきなのは』……」
一人で執拗に事件を追った、海藤が導いた仮説がそこにあった。
「……『氷牙正子だ。』」
正子はまだ八歳の子どもだった。いくら六十を超しているとはいえ、大人の祖母を一突きに殺せるはずがない。
「『何者かが彼女に特殊な凶器を渡して、氷牙麗子を殺させたのではないか。』」
俺はすぐにその仮説を否定したかった。あんな小さな子に祖母を殺させるなどという惨いことは起こっていないと信じたかった。
たとえそう考えれば、すべてつじつまが合うのだとしても。
「兄貴」
ふいに声をかけられて、俺は一瞬誰かわからなかった。
すぐに、俺は自宅のアパートでパソコンを見ていたことを思い出す。陽介が近くに来たことすら気付かなかったほど、海藤のデータに没頭していたのだ。
「起きてたのか。お前は休め。明日も早いんだろ?」
心配だったので、俺はしばらく陽介を自宅のアパートに泊めることにしたのだった。
時計を見ると時刻は午前四時を表示していた。
「兄貴こそ。明日だって仕事だろ。もう寝なよ」
「気にするな。徹夜くらい慣れてる」
俺は顔をしかめた陽介を何とか追い返す。
そしてもう一度最初から読みなおそうと、俺はパソコンに向きなおった。
翌日、俺は裁判所で今日の分の公判を終えて、地検への帰路を辿っていた。
イルミネーションが日に日に色鮮やかに町を飾っていく。世間ではクリスマスムード一色だ。
宗教では信仰の対象、一般人にはお祭り騒ぎ。だが、俺にとっては毎年苦い一日になる。
十年前のクリスマスの夜、俺は珍しく仕事が早く終わって、足早に帰路を辿っていた。
その日の朝は早くに出発したから、枕元に置いておいたクリスマスプレゼントを開けた正子の反応をまだ知らなかった。だが毎年正子はサンタからのプレゼントを楽しみに待っているから、きっと今年も喜んでくれるに違いないと思っていた。
今晩の夕食は妻の優子が正子のためにエビフライを作ると決まっていた。俺はケーキを買ってくると約束したから、手には正子が大好きな丸いデコレーションケーキの箱を持っていた。
ありふれた、幸せなクリスマスになるはずだった。
だが俺を待っていたのは、妻と母の無残な遺体だけ。正子の姿は二度と見られなくなった。
毎年、俺はクリスマスが近くなると弱い思いに捕われる。
このまま犯人は一生みつかることがなくて、正子に会うこともできないとしたら、一体俺は何のために生きているのかと絶望する。
――貴正。人は誰しも生きているだけで尊いんだ。
そんな俺に穏やかに語りかけて、希望を持つように繰り返し諭してくれたのは親友の向聖だ。
――きっと正子ちゃんは生きている。君の太陽は今もどこかで輝いていると信じるんだ。
俺に信仰心はないが、向聖の言葉にどれだけ救われたかわからない。
人の命の尊さを説いていた向聖が、正義の刃などといって人を次々と殺めていくものだろうか。二十数件以上に連なる連続殺人を犯し、そして子どもを守るために人を撃った海藤を刺したりなどするのか。
とても信じられない。俺は首を横に振って、地検の建物内に入った。
「氷牙、少しいいか」
自分の部屋に向かおうとした俺を、上司が呼びとめる。
「唐突になるが、お前、教会殺人事件の担当をやる気はないか?」
俺は軽く目を見開いて動きを止める。
「霧島向聖が容疑者の、ですか」
「そうだ。今後、海藤挑の刺殺事件を含めた……一連の「正義の刃」にもつながっていくだろう」
上司は難しい顔をしながら、言葉を失った俺を見やる。
「わかってる。お前にとっては身内の事件も絡んでて、冷静な一検事としての判断は難しい。俺もできればお前には振りたくない」
そこで上司は声をひそめて、周りに他の検事がいないことを確認して続ける。
「けどな、情けないことだが、他の検事たちが今回の担当を嫌がるんだよ。取り調べ中の警官が刺されたんだ。俺たちにも刃の先が向くかもしれない。それにこの事件はまだいろいろ不確かで、犯人が他にいる可能性も高い」
俺たちの職業は恨まれることなど数えきれないほどある。そんなことは検事になった以上皆覚悟している。
だが今回の事件は奇妙な点が多く、得体の知れない恐怖がつきまとう。
「お前の仕事ぶりは知ってる。個人的な思いがあったとしても、法を扱うことに関して、お前は誰より公平だ。任せられないか?」
霧島向聖に、親友に法の刃を向けることができるか。
俺は自問して、即答する。
「できます。俺は検事です」
やってみせると、俺は強く上司を見返す。
法を犯したのならその罪を問わなければならない。たとえ親友でも家族でも、法の前ではすべて平等だ。
「頼むぞ、氷牙」
俺は頷いて、前を見据えた。
向聖は、教会殺人事件と合わせて海藤の刺殺容疑で現行犯逮捕されて拘束されていた。
俺はそれを警官殺人事件として担当が決まった直後に資料を受け取った。渡された送検資料を読みこんで、事件の詳細を把握して翌朝を迎えた。
勾留請求の期限まで一日を切っている。しかしすぐに請求できない理由があった。
警察の方から来た資料だけでは、海藤の刺殺事件についての嫌疑が確認できなかった。
事件当時取り調べ室には向聖と海藤しかいなかったといわれるが、刺した現場を誰も見ていない。向聖自身もこの事件について容疑を否認している。凶器も発見されていなければ、他の物証もない。
「このまま勾留すれば、弁護士は違法逮捕を主張してきますよ」
状況からそうと判断されただけで逮捕請求をしたと判断されかねない。俺の考えに、事務官のみことさんも同意した。
海藤の刺殺事件については、みことさんは事務官の役を外れる。被害者が弟なのだから当然だ。
「起訴するのであれば確実な証明を目指す覚悟が必要でしょう。……あとは、お願いします」
「はい」
みことさんは頭を下げて、部屋を出て行った。
向聖はまもなく係官に連れられて、警官殺人事件の件で呼び出された。
「おはようございます」
寝不足の様子もなくすっきりとした顔色で会釈して、向聖は俺の机の向こうの椅子に座った。
「まず、お名前をお願いします」
「霧島向聖です」
簡単な確認事項から始めて、事件の内容についても訊いていく。横の席で代理の事務官がタイプを打っていく。
「あなたは警官を刺してはいないと話したそうですね」
「はい。私は刺していません」
「しかしあなたの目の前で警官が胸から血を流して倒れたのは見ているそうですね。他の誰かが刺したのを見ていたのですか?」
向聖は俺を真っ直ぐに見据えたまま答える。
「知りません」
少し奇妙な答えだが、調書にも同じように記載されている。見ていない、ではなく、知らない、と向聖は言っている。
俺は少し考えて続ける。
「警官の胸に何が刺さっていたのかは見ましたか?」
「刃です。これくらいの大きさの、包丁のようなものです」
内心で俺は気を引き締める。今まで、正義の刃事件では胸から血を噴くところは見ているが、凶器自体を見た者はいないのだ。
「その刃はどこにいったのですか?」
「消えました」
思わず眉を寄せそうになって、しかし俺は調書に目を戻す。
警察の取調調書でも、向聖は刃が消えたと話している。別に目の前の俺をからかっているわけではない。
「誰かが持ち去ったのですか?」
「いいえ。なくなったのです」
「溶けたと?」
刃は氷や揮発性物質だとでもいうのか。しかし海藤の死亡推定時刻後の数分以内に警官が駆け付けて調べたが、何の反応もなかったという。
「瞬間的に消えました」
向聖はそれ以上の詳細を語らなかった。
俺はその部分での追及を諦めて、他の事項を確認していく。
向聖はいずれも丁寧に、落ち着いて答えた。無駄なことは何一つ語らず、終始紳士的に俺の質問に応じていた。
質問を終えて向聖を係官に託した後、俺は書類を見返しながらしばらく考えた。
「どうしますか?」
事務官の問いかけに、俺は一つ頷く。
「勾留請求はしません。釈放しましょう」
俺の答えに、事務官は異議を唱えることはしなかった。プロとして、送検資料と今の質問を総合して同じ結論を弾きだしたのだろう。
「ただし、警察に連絡してください。教会殺人事件の件で、現場の実況見分に彼を立ち会わせましょう」
「別件になりませんか?」
「任意で応じてもらえるならば」
たぶん、向聖は応じるはずだ。確信はないが、向聖は事件の隠ぺいやかく乱は狙っていない。
彼は何か黙っていることがある。それは俺の勘だった。
「取れました。行きましょう」
みことさんが戻ってきて、俺たちは実況見分に向かった。
霧島教会は今年の始めまで向聖が住み込みの神父をしていた。
現在は養子である聖也君が神父の役目を継いだが、今も向聖を慕っている信者は多く、聖也君が留守の場合は向聖が中心となって集会を行うそうだ。
聖也君の実父が殺された霧島教会殺人事件も、その向聖が主催した集会で起きたということだ。
「集会の間、あなたが立っていた場所を教えてください」
被害者の倒れていた場所に印が残っている以外は、教会はもう綺麗に掃除されていた。
向聖は警官の質問に応じて、自分の立ち位置や事件当時の周囲の様子などを答えていた。
「そこから私はここまで歩いて……」
実況見分には警官と向聖、俺とみことさんの他に、集会に参加していたことがわかっている信者五人や聖也君も立ち会っていた。
暖房もない石造りの教会の中は冷え切っていた。その中で、聖也君はコートも着ずに微動だにせず向聖を見守っている。
実父の葬儀は行われたそうだが、聖也君に悲しみの色は見えなかった。ただ、向聖の身の心配だけをしているように思えた。
「入口は二つ。その内の祭壇側の扉は鍵がかかっていて、それは霧島聖也君だけが持っていたそうですね」
「はい」
その事実は既に警察の調べでわかっている。集会に来た人々も向聖も、正面入り口から入って出たと考えられている。
「当日は朝から一般の方の立ち入りをお断りして、教会内には信者しかいませんでした」
信者の内誰も、向聖が被害者を刺した所を見ていない。凶器も物証もなく、向聖自身が刺したと自供しているだけだ。
だからこの事件では向聖は逮捕すらされていない。海藤の事件の方でも既に釈放してしまったから、実況見分が終われば向聖は自由の身だ。
嫌疑がなければ身柄の拘束は許されない。それは法で決まっていて、俺たちでは変えようもない。
滞りなく進んでいく実況見分を見ながら、俺は考える。
何か、見落としていることがないだろうか。もちろん捜査のプロである警察を差し置いて俺が気づくことなどごくわずかしかないだろうが、それでも引っ掛かる部分があるのだ。
「では、ここまでとしましょう」
実況見分が終了した時、俺は何気なく庭を見やった。
「……そうだ」
思わず声を上げて、俺は聖也君に目を向ける。
「事件前、教会に滞在していた旅行者の女の子がいた。彼女は今もいるのか?」
聖也君は青い目で俺を見返して頷く。
「テラさんですね。ええ、ずっと滞在していらっしゃいます」
「ここへ連れてきてもらえないか。話を聞きたい」
教会の中には信者しかいなくとも、庭には部外者がいたかもしれない。何か知っているかもしれなかった。
間もなく庭の花壇の方から、聖也君がテラさんを連れてきた。今日の彼女は明らかに実用向きではない、ベレー帽を脇に抱えていた。
「こんにちは」
愛想良く笑いかけて、黒髪の旅行者は俺たちの前にやってくる。
「この教会で殺人事件が起こったことは知っているね。君はその日どこにいた?」
テラさんはゆるりと視線を巡らせて警官の姿を確認する。
「さあ。観光に行っていたような気がします」
はぐらかされた感じがしたので、俺は言葉を重ねようとする。
「旅行者なら、まずパスポートを見せて頂けますか?」
警官が近付いてきて少し疑惑を浮かべた目で彼女を見た。
テラさんはそれに穏やかに返す。
「今手元に持っていないのです。取ってきますので、少々お待ちください」
「待って」
一礼して踵を返した彼女を、思わず俺は引きとめていた。
今行かせたら、二度と彼女はここに戻らない。そう直感で思ったのだ。
「パスポートは結構、少し話を聞くだけだから。……場所を変えよう」
おそらく警官がいる前では彼女は何も話さない。それを察して、俺は渋る警官たちを残して、テラさんを教会の裏手に連れてきた。
「君の事情は訊かない。だから、事件の日に君が見たことを正直に話してくれないか」
二人きりになってすぐ切り出した俺に、テラさんはゆっくりと言う。
「私の旅の方針として、その国の方々のお邪魔をしないというものがあります」
「邪魔にはならない。少し協力してほしいんだ」
「協力とは、誰かに肩入れするということです」
年若く見えるが、彼女の言葉には断固とした意思が見えた。
「私は旅行者です。本来、そこにはいない者です。私は何も残しませんし何も奪いません」
俺はテラさんの黒い瞳を見返して少し黙った。
「……私からもお願いできませんか」
ふいに近付いてきたのは向聖だった。話を聞いていたらしい彼は、テラさんの前に歩み寄ってくる。
「私の罪を暴く手伝いをして頂きたいのです。このままでは、私の罪は闇に葬られてしまいます」
俺は咄嗟に閃くものを感じて言葉を発していた。
「テラさん。君は与えられたものは返すかい?」
無言で俺を見たテラさんに、俺は続ける。
「君はそこの教会の酒場でビールを飲んだね。それを作ったのは彼の会社なんだ。ビール一杯分だけでいいから、協力してくれないか」
こじつけでもいいと思いながら言った俺の前で、テラさんは黙った。
「お金は払いましたけど……そうですね」
彼女の少し変わった感覚は、俺の言葉に反応を返した。
「こちらのビールは代金以上においしかったので、何かお礼をしなければいけませんね」
テラさんはぐるりと裏庭を見渡して、一点を指さす。
「あの石の下を掘ってみてください」
「は?」
怪訝な顔をした俺に、テラさんは微笑んだ。
「では」
ベレー帽を被って、不思議な少女は去っていった。
後で彼女の示した場所を掘ってみると、そこから血のついた祭服が出てきた。鑑識にかけると、教会殺人事件の被害者の血と判明した。
そこに残っていた複数の指紋は信者たちのものとわかって、事件がようやく見え始めた。
聖也君を虐待していた被害者を殺害する計画を立てたのは信者たちだったこと、事件を隠ぺいしようと信者たちが血のついた向聖の祭服を奪って埋めたことなどだ。
向聖は信者たちを庇っていたのだということも明らかになった。
ようやく現れた物証によって、向聖は教会殺人の件で逮捕された。
しかし依然として、凶器は未知のままだった。
久しぶりの休日の朝、俺は開きっぱなしになっているパソコンの方を見やって違和感に目を止めた。
慌てて机の上や引き出しの中を探して、俺は呟く。
「……ない」
海藤の残したチップがなくなっていた。昨日の夜までは、パソコンの横に置いてあったはずなのだ。
データ自体は繰り返し読みこんでいて、すべて頭の中に入っている。
それより問題はと、俺は机に手をついて一番大きな可能性を思った。
「兄貴と二人で外出なんて久しぶりだ」
俺は朝食の後、海藤の死から引きこもりがちだった陽介を連れ出して海辺の公園に来ていた。
「デートスポットに男二人っていうのも何だけどな。まあ、気晴らしにはなるだろ」
「でも昔はよく来たよね、この公園」
港が間近に見えるここは、子どもの頃は俺と陽介の遊び場だった。昔の家から近かったこともあって、天気のいい日はいつも陽介と駆けまわっていた。
喧嘩もよくしたが、元気いっぱいに飛びついてくる陽介と遊ぶのは楽しかったのを覚えている。
真冬には珍しく、空は真っ青に晴れ渡っていた。その下を、いろいろな人々が歩いていく。
ベンチに座って、しばらく二人で海を見ていた。水面が太陽の光を受けて輝いていた。
「陽介」
俺は意を決して口を開く。
「海藤のデータを隠したのはお前か?」
陽介は無言だった。俺は続けて言う。
「お前を責めてるんじゃない。俺が事件に関わり続けることを快く思ってないことくらいわかってる。俺を心配してくれてるってことも」
事件に捕われ続けて俺が自分の人生を見失うのではないかと、この弟がずっと不安そうな眼差しで見ていたことを知っているのだ。
「でもな、俺は一生、正子の父親なんだ。あの子を俺の人生から消してしまうことはできないんだ」
「知ってるよ。兄貴は優しいから」
陽介は少しうつむいた。
それからしばらく沈黙して、陽介はぽつりと問う。
「兄貴は法としょうちゃん、どっちが大事?」
俺は陽介に振り向く。
「もししょうちゃんが法に反するどうしようもなく悪いことをしちゃったら、兄貴はしょうちゃんを裁きにかけられる?」
少し驚きはしたが、俺はすぐに返した。
「正子が罪を犯したのなら、それはきちんと法の前で裁かれないといけない」
相手が誰であってもそれは変わらない。
「だがそれとは別に、俺は父親として正子を叱ってやらないといけない。何より、守ってやらなくては」
「そっか」
陽介は目を伏せたまま頷く。
「しょうちゃんでそれなら、俺は訊くまでもないね」
俺は怪訝な顔をして陽介の肩を叩く。
「何言ってる。お前も俺の大事な家族だ。俺の身に代えても守るさ」
「俺がどうしようもなく悪いことをしちゃったとしても?」
前髪に隠れて、陽介の目が見えなかった。
「警察の情報を改ざんして、しょうちゃんたちの事件を隠ぺいしたのは俺だよ」
「な」
思わず立ち上がった俺の腕を、陽介が掴む。
「そして……」
ふいに携帯電話が鳴って、俺は立ち竦む。
「兄貴の携帯だよ」
俺の腕を掴んだまま、陽介は波のない口調で告げた。
俺は空いた方の腕でポケットを探って、携帯を耳に当てる。
『氷牙!』
息を切らして、上司が通話に出た。
「どうしたんです。休日まで仕事ですか?」
『お前、今どこにいる?』
「港の公園ですけど」
『そこに弟の陽介はいるか』
俺は俯いたままの弟を見やってから返す。
「目の前にいますが」
『すぐに逃げろ。警察はもう動いてくれてる』
事態が全く読めなくて、俺は首を傾げる。
『ついさっき、氷牙陽介に対する逮捕状が出た』
目を見開いた俺に、上司の声が残酷な事実を告げる。
『返り血のついた彼の制服がみつかったんだ。……海藤を刺したのは陽介だ』
俺は思わず通話を切った。
デートらしいカップルの笑う声が近くを通り過ぎていった。
「なん、で」
立ち尽くす俺に、陽介は口を開いた。
「不思議だったよ。どうして誰も、第一発見者の俺を疑わないのかって」
「陽介。嘘だよな。お前が」
「あんなにガタイがよくて強い海藤が、何の抵抗もなく刺されるなんて変だと思わない?」
「海藤はお前の相棒じゃないか!」
声を上げた俺を、陽介はきっと睨んだ。
「あいつといると、兄貴はあいつを見るじゃないか!」
見たこともない激しい目で、陽介は俺を見る。
「弟は俺だけのはずなのに、兄貴に一番近いのは俺のはずなのに、兄貴は俺より海藤を気にしてたじゃないか」
我を失ったように、陽介は声を荒げる。
「そうだよ。ずっと殺してやりたかったさ。あいつは俺から兄貴を取った!」
まるで俺を憎んでいるように、陽介は言い放った。
海藤を殺した犯人を、俺は何度も憎んだ。もし会ったら、殺してやりたいと願うくらいに。
だが今陽介を目の前にして、俺は何の言葉も出てこなかった。憎むことも恐れることもできず、ただ見ることしかできなかった。
「……違う」
陽介は再び顔を伏せて、うめくように呟く。
「本当に殺したかったのは、しょうちゃんだ。あの子が生まれてから、兄貴はしょうちゃんを一番に思うようになった」
独白のように、陽介はぽつりぽつりと言葉を漏らす。
「でもあの子は誰も殺せなかった。兄貴は言ってたね、正子はうちの太陽だって。そうだ、太陽は誰も消せないんだ」
陽介の声が沈んでいく。
「兄貴、人の数だけ影ができるんだよ。光が眩しければ眩しいほど、影は濃くなる。真っ暗な闇ができる」
「……陽介」
俺は乾いた喉に息を通して、かろうじて声といえるものを出した。
「誰も殺せなかった、と言ったな。正子は、今も生きてるのか?」
陽介は小さく頷く。
「生きてるよ。……もう、兄貴の知ってるしょうちゃんじゃないけど」
生きている。正子が、今も。
たとえどんな姿になっていても構わない。もう一度会えるのならば。
俺はその一言が泣きたくなるほど嬉しかったが、同時に目を逸らしてはいけない現実に気づく。
「お前が、優子と母さんを殺したのか?」
「違う。俺じゃない!」
陽介は首を横に振って否定する。
「俺は誰も殺して……海藤だって殺さずに済んだはずなんだ。あんなものがなかったら、俺は……!」
陽介の頬を涙が流れていく。堰を切ったように溢れていく。
震えながら俺の胸にしがみついて、陽介は消え入りそうな声で言った。
「……助けて、兄貴」
それは簡単に振り払えそうなほどの弱い力でしかなかった。
「次は俺だ。刃は俺を殺す。逃げられない」
「落ち着け、陽介」
俺は陽介の顔を上げさせて、涙に濡れたその顔を覗き込む。
「大丈夫だ。俺がいる。お前を守る」
噛みしめるように告げた言葉に、陽介の目が微かに正気を取り戻す。
「……ああ、やっぱり兄貴だ」
陽介は涙を流しながら、ほんの少しだけ表情を和らげた。
「正しくて、強くて、優しい。俺の大好きな兄貴は、あんな魔物なんかに負けない」
「陽介?」
弟は腕を解いて自ら立ち上がる。
ふらりと俺の横を通り過ぎようとする。
「海藤、ごめん」
そう呟いた瞬間だった。
視界の隅に赤い液体が見えた。それを無意識の内に目で追って、俺は戦慄する。
陽介の胸から血が噴き出していた。
「……陽介!」
仰向けに倒れた陽介を抱き起そうとする。だが陽介は目を見開いたままぴくりとも動かない。
「誰か、救急車を呼んでください!」
陽介の服が血で染まっていく。手で押さえても、次々と血が流れ出て行く。
胸には何も刺さっていない。銃弾かと、俺は辺りを見回す。
周囲は人で溢れている。通行人たちが、何事かと見ている。わからない。誰も近付いた形跡などなかった。
どこだ。誰なんだ。
……そんなことは今考えている場合じゃないのに、頭が混乱してどうしようもない。
「陽介、陽介……!」
救急車が来て死亡が確認されるまで、俺は陽介を抱えてうずくまることしかできなかった。