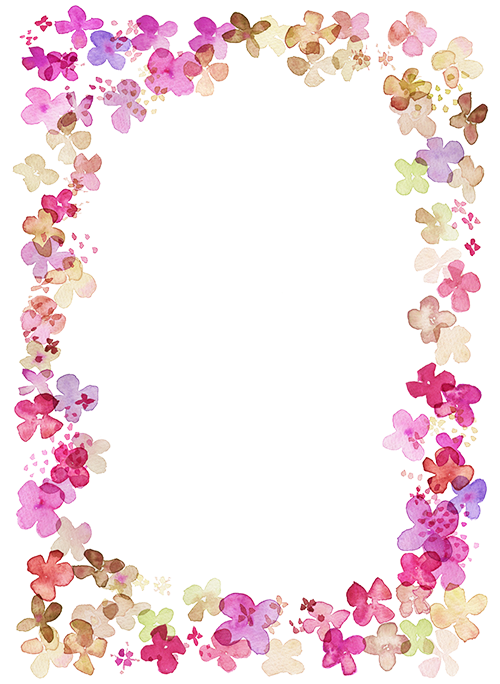取り調べで重要なのは忍耐だ。
「そろそろ何か話したらどうだ」
職業柄この場面に立ちあうことも珍しくはないが、受ける側に立つのは久々だ。
「それなら俺の人生をダイジェストで、もう一度最初からお送りしようか」
「事件と関係ないことを話すな、氷牙」
俺の取り調べをしている警官の名を、海藤挑という。大木のようにがっしりした体格と抉るような鋭い目を持つ男だ。
「海藤、今も週三でボクシングジムに行って鍛えてるんだって? よくやるな、お前」
「無駄口を叩くなと言ってるだろう」
海藤は俺が初めて起訴した事件の担当刑事だった。その時はお互い新米だったが、今となっては両方ともいい年になっている。
俺は小さな窓から差し込む朝日を見やりながら頷く。
「それもそうだ。なあ、そちらの彼をそろそろ寝かせてやれ。ハンサムが台無しじゃないか」
調書を取っている若い警官はかなりきつそうだ。おそらくまだ徹夜に慣れていないのだろう。
「お前が素直に話せばいいことなんだよ」
「これ以上素直にはなれないんだよな」
何度訊かれても、知らないことは答えられない。
俺は被害者である山根には既に五年以上会っていないし、まさか殺してもいない。そんなことは俺が誰より知っている。
「俺が犯人だという証拠があったわけじゃないんだろう」
海藤は厳つい顔をもっと険しくする。ハッタリや嘘を使わないのが海藤の美点であり欠点だ。
「そうだったら令状を取ってくるはずだ。お前のことだからな」
俺は背もたれから体を起こして言う。
「まあ事件の解明のためだ。俺でよければいくらでも取り調べくらい受けるさ。元々俺たち検事はお前たち警察と協働関係、いわば仲間だ」
海藤は冷ややかに俺を見下ろした。
「聞いて呆れる。お前は俺たちなど復讐の道具としか思ってないだろう」
俺は目だけを上げて海藤を見やる。
「お前は自分が正しいと言って権力を振りかざす」
「俺は法の通りに仕事をしているだけだよ」
職務に関して、俺は法以外の何者にも従っていない。法に反すれば、上司や親の言うことだって聞きはしない。
数秒間の睨みあいの後、取調室の扉が外から開いた。
「二人とも元気だなぁ。四十前のおじさんとは思えないね」
少し長い茶髪をした警官がひょっこりと顔を出す。
「陽介、お前今までどこ行ってた」
「やだな。ちゃんと仕事してたよ。俺だって市民の安全を守る警官ですから」
三十五になるというのに、未だに大学生のような幼さが残る刑事だ。
「で、お仕事の結果わかったんだ。任意聴取はもう終わり」
何か言おうとした海藤に、彼は手に持っていた書類をひらひらと示す。
「犯行時刻に、兄貴が現場から数十キロ離れた教会の酒場で飲んでいたっていう内容がいくつも取れたから」
海藤は渡された数枚の紙に素早く目を通すと、すぐに低く返す。
「例の教会の酒場の連中か。あいつらは神父の言いなりだろう。信用できない」
「善良な市民をそんな風に言うのはよくないよ」
陽介はガタイのいい海藤に比べるとずいぶん小柄で細いが、言い争いでは負けていない。
「兄貴は一晩取り調べに付き合ってくれたんだろう? 山根にストーカーされてた、それこそただの被害者なのにさ」
「お前は氷牙を庇いすぎる」
「海藤は貴正を敵視しすぎだよ」
机に手をついて海藤を仰ぎ見ながら、陽介はにっこりと笑いかける。
「ま、兄貴が犯人なわけないけど」
その笑い方は小さな子どものように無力でいて、人を従わせてしまうような気迫があった。
「じゃあ行くよ。いいね?」
陽介に肩を叩かれて、俺は席を立つ。取調室から出るまで海藤は俺を睨み続けていたが、それでも止めることはしなかった。
「おつかれ、兄貴!」
警察署の玄関を出ると、陽介は俺の肩を強く叩いて腕を回した。
小さい頃から俺に飛びついて来た弟の慣れた仕草に、俺は笑う。
「いいのか、こんなに早く帰して。どうせお前が海藤を俺のところに連れてきたんだろう」
「うん。さっさと取り調べ受けた方が気楽だろ?」
屈託なく笑って、陽介は頷く。
「海藤はどうしても俺を犯人にしたいみたいだがな」
十年前の母と妻の殺人事件の時だって、海藤は俺が犯人だと決めて徹底的に俺を取り調べた。同僚の刑事たちが執拗だと止めに入ったくらいだ。
海藤には元々、初めて一緒に仕事をした時から敵視されていた。検事と警察という立場の違いなのか、個人的にそりが合わないのかはわからない。
「海藤は兄貴が好きなんだよ」
軽く首を傾けて言った陽介に、俺は苦笑する。
「俺はあいつが嫌いじゃないんだがね」
海藤の実直さや正義感は高く買っている。警察官など飽きるほど見てきたが、あいつほど真剣に事件を追う奴は見たことがない。
「さて、職場まで送ろうか?」
「今日はもう休みだって連絡しちまったからな。それより、時間があるなら案内してくれ」
俺は陽介を横目で見て言う。
「被害者の山根愛理が殺された現場に」
陽介は微かに目を細める。
「そう言うと思ってたよ」
俺を連れて、陽介は地下鉄の入り口に足を向けた。
山根愛理の殺された現場は、やはり今までの事件と同様街の真ん中だった。
山の手線圏内の地下鉄を出て、目の前に広がる繁華街の中だ。過酷な生存競争を勝ち抜いてきた飲食店が並ぶ一角で、まだ午前だというのに人が波のように行きかう大通りに犯行現場はあった。
歩きながら、俺は陽介に事件について聞いた。
「被害者は刃物のようなもので心臓を一突きにされて即死。被害者が胸から血を噴いたところは目撃者が五人以上いるけど、刺されたところや犯人らしい姿は誰も見てない」
「一連の刃と手口は同じだな」
現場の通りは封鎖されてはいたが、検証活動をする警官たちは既に去っていた。
正義の刃事件は一部のマスコミが過剰に騒いでいるという側面もあるが、危機感を抱かれているのもまた事実だ。警察も大規模なチームを作って対策に当たっている。
捜査が専門ではない検事の俺が、個人的にできることなど僅かしかないとわかっているが、それでもその僅かなことを探して俺は事件を追っている。
「それで、山根は誰かを殺したのか?」
「そこはまだわかってないんだよね」
正義の刃とは公に被害者が人を殺した者とされているわけではない。その条件は後からこの奇妙な連続殺人事件の共通点として見出されただけだ。
「迅速で正確な仕事をする、いい検事だったんだが」
山根愛理は俺が支部にいた頃に同僚だった。年は確か俺の二つ下で、正義感に燃えた若き検事だった。
「いい女ではなかったけどね。彼女、兄貴が断っても断ってもつきまとってきたんだろ?」
「そう言うな。仕事と恋愛事は別だ」
確かに彼女は多少思いこみの激しいところはあった。
私は貴正のためなら何でもできると言ってはばからなかった。
度の過ぎた贈り物をしてきたり、俺の行く先々で待ち伏せしていることがよくあった。
まだ妻が生きていた頃から、俺と付き合ってくれるように、時には妻と別れて結婚してくれるように迫ったことさえあった。
期待を持たせる態度を取ったかと思って、山根との付き合いをなるべく最小限に抑えるように努力しても、彼女の押しはむしろ強くなった。
俺は妻と別れるつもりはない、娘が世界一可愛いと何度も言った。同僚としての域を踏み越えないでほしかった。
結局、山根は仕事で失敗を繰り返すようになって、五年前に地方へ転属された。以来、音沙汰を聞かなかった。
「少し引っ掛かるな。山根は確か東北の方に行ったはずで、何をしに東京へ来ていたんだろう」
今は十一月も終わりという、休暇を取るには中途半端な時期だ。
「出張か?」
「いや、個人的な用事らしいよ。昨日東京にある実家に着いたそうだ」
山根は元々東京の人間だから、こちらに家族や友達も多いだろう。俺は微かな違和感を頭の中で消した。
テープが張られた現場近くに来た時、呆然と立ちすくんでいた女性がいた。
その六十ほどの老年の女性は、俺を見るなり短く声を上げる。
「あんた、検事の氷牙貴正だね?」
見る見る内に顔に敵意を浮かべて、女性は俺に詰め寄ってくる。
「あんたが愛理をたぶらかしたんだろう! 都合が悪くなったから殺したんだ! あんな優秀で優しい子を。あんたがいなかったら……!」
俺は胸を掴まれながら記憶を掘り返す。
山根は五位以内で司法試験を合格して、裁判官になることを勧められたほどの優秀さだったそうだ。頭も切れて、おそらく順調にいけば検事の出世コースを走ったはずだ。
「娘を返してくれ!」
俺がいなければ山根は人生の脇道に逸れることはなかったのにと、思うこともあった。
「おばさん。やめなよ」
細身だがそれでも鍛えている陽介が、山根の母親を引きはがす。
「兄貴、行こう」
なおも掴みかかろうとする彼女から俺を守るように立ちふさがって、陽介は去ることを促す。
俺は唇を噛んで、痺れた体を叱咤しながら頭を下げる。
「残念でなりません」
山根が正子を連れ去ったのかもしれないと、彼女を疑ったこともある。
それでも、山根が殺されていい人間だとは今でも思っていない。
「……お世話になりました」
俺は持参した花束を現場に置いて、陽介と共にそこを去ることにした。
山根の殺人現場から駅に行って、俺と陽介は改札口にいた。
「付き合ってくれてありがとう。陽介、お前は仕事に戻れ」
「兄貴はこれからどこに?」
「せっかく時間が空いたんだ。前のアパートに行ってくる」
十年前に妻と母が殺されたアパートを、今でも俺は借り続けている。もしかしたら犯人や正子の痕跡が残っているかもしれないと信じていた。
「それから誘拐被害者の支援NPOに、正子の情報が来てないか確認を……」
やることはいくらでもある。本当は仕事だって辞めて調査に専念したいくらいだった。同僚や陽介たちが言葉を尽くして俺を留めなければそうしていた。
「兄貴」
陽介は朗らかな顔立ちをくしゃりと歪めて言う。
「もう、事件のことは忘れた方がいいよ」
弟からその一言を告げられたことは十年間で数えきれないほどになった。
「俺だって母さんや義姉さんを亡くしたことは辛いけど、しょうちゃんが帰ってきてほしいってずっと思ってるけど……きっと、戻らないことなんだ」
「馬鹿言うな!」
俺は思わず声を荒げる。
「正子は生きてる。どこかできっと俺の助けを待ってる。父親の俺が諦めるわけにはいかないだろう!」
「だって今のままじゃ、兄貴の人生までつぶれるじゃないか!」
陽介も感情を露わにして声を上げてから、俯く。
「犯人としょうちゃんだけを探し続けて、一生生きていくつもりなのか?」
ぽつりと呟いた陽介に、俺は沈黙した。
それから二人無言で電車に乗りこんで、途中で別れた。陽介の背中はひどく落ち込んでいたが、それ以上声はかけられなかった。
俺は各駅停車に乗り換えて、前のアパートへの最寄り駅で降りた。
再開発すらも諦められている、小さな町だ。けれど俺にとっては家族と共に暮らした、かけがえのないホームタウンだ。
ふと俺はアパートの向かい側にある、白い教会へと足を向けた。
馴染みの酒場はまだ昼だから閉まっている。その横にある扉から、俺は聖堂の中に入った。
学校の教室一つ分ほどもない小さな聖堂だ。金も銀もステンドグラスのような華やかな装飾もなく、ただ古びた椅子と祭壇、そして十字架だけが置かれている。
正面の天窓から差し込んでくる陽光を浴びて、祭壇の前でひざまずいている少年がいた。胸の前で手を組んで、目を閉じて静止している。
いつもこの子は静寂を身にまとっているな。俺は彼が祈りを終えるまで戸口で待っていた。
「貴正さん」
やがて聖也君が振り返って顔を上げる。俺はそちらに歩み寄りながら言う。
「邪魔をしてしまったかな」
「いえ」
まだ二十歳にもなっていない若さでありながら、彼はゆっくりと落ち着いて話す子だった。
「何についての祈りだった?」
「殺められた死者に対する哀悼を」
聖也君は長い金色の睫毛を伏せて告げる。
「悲しい事件がまた起こってしまったと聞きます」
「君も山根の事件を知ってるのか」
聖也君はこくりと頷く。
「俺がきっと犯人をみつけてみせるよ。そして正子を」
「いいえ」
普段の彼からは信じられないほど、聖也君は鋭く俺を見上げて言う。
「正子さんはきっと僕が救ってみせます」
正子のことになると、聖也君は途端に少年の意固地さを見せる。
「十年経ってもあの子を思ってくれてありがとう」
聖也君は正子と友達同士だった。教会とアパートの間にある公園で、二人はいつも楽しそうに遊んでいたものだ。
「この事件は、きっと人の手では解決できないのです」
「そんなことはない。人が起こした事件なら、人が解決できる」
俺が強く見つめ返したが、聖也君は目を逸らしたりしなかった。
「救いをもたらせるのは神だけです。人では、その人を殺すことでしか終わらせることはできません」
「人には法がある」
人の世界で起きたものは、人の法で解決する。俺の信念だ。
「ごめん。君の信仰は止めないよ」
聖也君には彼なりの信念がある。それを曲げることは許されないと、俺は言葉を収めた。
「いえ、僕こそ失礼しました」
聖也君は丁寧に頭を下げて微笑む。
氷のような美貌が、優しい陽だまりのようなものに色を変えた。
「正子さんが貴正さんのところに、一日も早く戻ることを祈っています」
俺も笑い返そうとして、その笑みを消す。
一瞬だった。けれど確かに教会の中に、俺と聖也君以外の気配を感じた。
その、たまらなく懐かしい、大切な存在。
俺は振り返って扉に走る。扉を開け放って呼ぶ。
「……正子?」
そうであってほしいという俺の切望が、そう言わせたのかもしれない。
正子はいなかった。代わりに、教会の外の小さな庭には、屈みこんで花を見ている少女がいた。
後から歩いて来た聖也君がそっと告げる。
「彼女は昨日からこの教会に泊めている旅行者の方です」
脇に抱えているのはシルクハットではないがずいぶん変わった形の帽子だった。けれど確かに、酒場で会ったテラという少女に間違いはなかった。
「観光にも行かずに、朝からずっと庭を見ていらっしゃるんですよ」
ここはさほど有名な観光地ではないのに、不思議なことだった。
「いつまで滞在する予定なんだ?」
聖也君が首を傾げる気配がした。
「魔物が消えるまで、だそうです。……どういう意味でしょうね」
テラさんは愛おしそうに、側の花に触れて笑っていた。
「そろそろ何か話したらどうだ」
職業柄この場面に立ちあうことも珍しくはないが、受ける側に立つのは久々だ。
「それなら俺の人生をダイジェストで、もう一度最初からお送りしようか」
「事件と関係ないことを話すな、氷牙」
俺の取り調べをしている警官の名を、海藤挑という。大木のようにがっしりした体格と抉るような鋭い目を持つ男だ。
「海藤、今も週三でボクシングジムに行って鍛えてるんだって? よくやるな、お前」
「無駄口を叩くなと言ってるだろう」
海藤は俺が初めて起訴した事件の担当刑事だった。その時はお互い新米だったが、今となっては両方ともいい年になっている。
俺は小さな窓から差し込む朝日を見やりながら頷く。
「それもそうだ。なあ、そちらの彼をそろそろ寝かせてやれ。ハンサムが台無しじゃないか」
調書を取っている若い警官はかなりきつそうだ。おそらくまだ徹夜に慣れていないのだろう。
「お前が素直に話せばいいことなんだよ」
「これ以上素直にはなれないんだよな」
何度訊かれても、知らないことは答えられない。
俺は被害者である山根には既に五年以上会っていないし、まさか殺してもいない。そんなことは俺が誰より知っている。
「俺が犯人だという証拠があったわけじゃないんだろう」
海藤は厳つい顔をもっと険しくする。ハッタリや嘘を使わないのが海藤の美点であり欠点だ。
「そうだったら令状を取ってくるはずだ。お前のことだからな」
俺は背もたれから体を起こして言う。
「まあ事件の解明のためだ。俺でよければいくらでも取り調べくらい受けるさ。元々俺たち検事はお前たち警察と協働関係、いわば仲間だ」
海藤は冷ややかに俺を見下ろした。
「聞いて呆れる。お前は俺たちなど復讐の道具としか思ってないだろう」
俺は目だけを上げて海藤を見やる。
「お前は自分が正しいと言って権力を振りかざす」
「俺は法の通りに仕事をしているだけだよ」
職務に関して、俺は法以外の何者にも従っていない。法に反すれば、上司や親の言うことだって聞きはしない。
数秒間の睨みあいの後、取調室の扉が外から開いた。
「二人とも元気だなぁ。四十前のおじさんとは思えないね」
少し長い茶髪をした警官がひょっこりと顔を出す。
「陽介、お前今までどこ行ってた」
「やだな。ちゃんと仕事してたよ。俺だって市民の安全を守る警官ですから」
三十五になるというのに、未だに大学生のような幼さが残る刑事だ。
「で、お仕事の結果わかったんだ。任意聴取はもう終わり」
何か言おうとした海藤に、彼は手に持っていた書類をひらひらと示す。
「犯行時刻に、兄貴が現場から数十キロ離れた教会の酒場で飲んでいたっていう内容がいくつも取れたから」
海藤は渡された数枚の紙に素早く目を通すと、すぐに低く返す。
「例の教会の酒場の連中か。あいつらは神父の言いなりだろう。信用できない」
「善良な市民をそんな風に言うのはよくないよ」
陽介はガタイのいい海藤に比べるとずいぶん小柄で細いが、言い争いでは負けていない。
「兄貴は一晩取り調べに付き合ってくれたんだろう? 山根にストーカーされてた、それこそただの被害者なのにさ」
「お前は氷牙を庇いすぎる」
「海藤は貴正を敵視しすぎだよ」
机に手をついて海藤を仰ぎ見ながら、陽介はにっこりと笑いかける。
「ま、兄貴が犯人なわけないけど」
その笑い方は小さな子どものように無力でいて、人を従わせてしまうような気迫があった。
「じゃあ行くよ。いいね?」
陽介に肩を叩かれて、俺は席を立つ。取調室から出るまで海藤は俺を睨み続けていたが、それでも止めることはしなかった。
「おつかれ、兄貴!」
警察署の玄関を出ると、陽介は俺の肩を強く叩いて腕を回した。
小さい頃から俺に飛びついて来た弟の慣れた仕草に、俺は笑う。
「いいのか、こんなに早く帰して。どうせお前が海藤を俺のところに連れてきたんだろう」
「うん。さっさと取り調べ受けた方が気楽だろ?」
屈託なく笑って、陽介は頷く。
「海藤はどうしても俺を犯人にしたいみたいだがな」
十年前の母と妻の殺人事件の時だって、海藤は俺が犯人だと決めて徹底的に俺を取り調べた。同僚の刑事たちが執拗だと止めに入ったくらいだ。
海藤には元々、初めて一緒に仕事をした時から敵視されていた。検事と警察という立場の違いなのか、個人的にそりが合わないのかはわからない。
「海藤は兄貴が好きなんだよ」
軽く首を傾けて言った陽介に、俺は苦笑する。
「俺はあいつが嫌いじゃないんだがね」
海藤の実直さや正義感は高く買っている。警察官など飽きるほど見てきたが、あいつほど真剣に事件を追う奴は見たことがない。
「さて、職場まで送ろうか?」
「今日はもう休みだって連絡しちまったからな。それより、時間があるなら案内してくれ」
俺は陽介を横目で見て言う。
「被害者の山根愛理が殺された現場に」
陽介は微かに目を細める。
「そう言うと思ってたよ」
俺を連れて、陽介は地下鉄の入り口に足を向けた。
山根愛理の殺された現場は、やはり今までの事件と同様街の真ん中だった。
山の手線圏内の地下鉄を出て、目の前に広がる繁華街の中だ。過酷な生存競争を勝ち抜いてきた飲食店が並ぶ一角で、まだ午前だというのに人が波のように行きかう大通りに犯行現場はあった。
歩きながら、俺は陽介に事件について聞いた。
「被害者は刃物のようなもので心臓を一突きにされて即死。被害者が胸から血を噴いたところは目撃者が五人以上いるけど、刺されたところや犯人らしい姿は誰も見てない」
「一連の刃と手口は同じだな」
現場の通りは封鎖されてはいたが、検証活動をする警官たちは既に去っていた。
正義の刃事件は一部のマスコミが過剰に騒いでいるという側面もあるが、危機感を抱かれているのもまた事実だ。警察も大規模なチームを作って対策に当たっている。
捜査が専門ではない検事の俺が、個人的にできることなど僅かしかないとわかっているが、それでもその僅かなことを探して俺は事件を追っている。
「それで、山根は誰かを殺したのか?」
「そこはまだわかってないんだよね」
正義の刃とは公に被害者が人を殺した者とされているわけではない。その条件は後からこの奇妙な連続殺人事件の共通点として見出されただけだ。
「迅速で正確な仕事をする、いい検事だったんだが」
山根愛理は俺が支部にいた頃に同僚だった。年は確か俺の二つ下で、正義感に燃えた若き検事だった。
「いい女ではなかったけどね。彼女、兄貴が断っても断ってもつきまとってきたんだろ?」
「そう言うな。仕事と恋愛事は別だ」
確かに彼女は多少思いこみの激しいところはあった。
私は貴正のためなら何でもできると言ってはばからなかった。
度の過ぎた贈り物をしてきたり、俺の行く先々で待ち伏せしていることがよくあった。
まだ妻が生きていた頃から、俺と付き合ってくれるように、時には妻と別れて結婚してくれるように迫ったことさえあった。
期待を持たせる態度を取ったかと思って、山根との付き合いをなるべく最小限に抑えるように努力しても、彼女の押しはむしろ強くなった。
俺は妻と別れるつもりはない、娘が世界一可愛いと何度も言った。同僚としての域を踏み越えないでほしかった。
結局、山根は仕事で失敗を繰り返すようになって、五年前に地方へ転属された。以来、音沙汰を聞かなかった。
「少し引っ掛かるな。山根は確か東北の方に行ったはずで、何をしに東京へ来ていたんだろう」
今は十一月も終わりという、休暇を取るには中途半端な時期だ。
「出張か?」
「いや、個人的な用事らしいよ。昨日東京にある実家に着いたそうだ」
山根は元々東京の人間だから、こちらに家族や友達も多いだろう。俺は微かな違和感を頭の中で消した。
テープが張られた現場近くに来た時、呆然と立ちすくんでいた女性がいた。
その六十ほどの老年の女性は、俺を見るなり短く声を上げる。
「あんた、検事の氷牙貴正だね?」
見る見る内に顔に敵意を浮かべて、女性は俺に詰め寄ってくる。
「あんたが愛理をたぶらかしたんだろう! 都合が悪くなったから殺したんだ! あんな優秀で優しい子を。あんたがいなかったら……!」
俺は胸を掴まれながら記憶を掘り返す。
山根は五位以内で司法試験を合格して、裁判官になることを勧められたほどの優秀さだったそうだ。頭も切れて、おそらく順調にいけば検事の出世コースを走ったはずだ。
「娘を返してくれ!」
俺がいなければ山根は人生の脇道に逸れることはなかったのにと、思うこともあった。
「おばさん。やめなよ」
細身だがそれでも鍛えている陽介が、山根の母親を引きはがす。
「兄貴、行こう」
なおも掴みかかろうとする彼女から俺を守るように立ちふさがって、陽介は去ることを促す。
俺は唇を噛んで、痺れた体を叱咤しながら頭を下げる。
「残念でなりません」
山根が正子を連れ去ったのかもしれないと、彼女を疑ったこともある。
それでも、山根が殺されていい人間だとは今でも思っていない。
「……お世話になりました」
俺は持参した花束を現場に置いて、陽介と共にそこを去ることにした。
山根の殺人現場から駅に行って、俺と陽介は改札口にいた。
「付き合ってくれてありがとう。陽介、お前は仕事に戻れ」
「兄貴はこれからどこに?」
「せっかく時間が空いたんだ。前のアパートに行ってくる」
十年前に妻と母が殺されたアパートを、今でも俺は借り続けている。もしかしたら犯人や正子の痕跡が残っているかもしれないと信じていた。
「それから誘拐被害者の支援NPOに、正子の情報が来てないか確認を……」
やることはいくらでもある。本当は仕事だって辞めて調査に専念したいくらいだった。同僚や陽介たちが言葉を尽くして俺を留めなければそうしていた。
「兄貴」
陽介は朗らかな顔立ちをくしゃりと歪めて言う。
「もう、事件のことは忘れた方がいいよ」
弟からその一言を告げられたことは十年間で数えきれないほどになった。
「俺だって母さんや義姉さんを亡くしたことは辛いけど、しょうちゃんが帰ってきてほしいってずっと思ってるけど……きっと、戻らないことなんだ」
「馬鹿言うな!」
俺は思わず声を荒げる。
「正子は生きてる。どこかできっと俺の助けを待ってる。父親の俺が諦めるわけにはいかないだろう!」
「だって今のままじゃ、兄貴の人生までつぶれるじゃないか!」
陽介も感情を露わにして声を上げてから、俯く。
「犯人としょうちゃんだけを探し続けて、一生生きていくつもりなのか?」
ぽつりと呟いた陽介に、俺は沈黙した。
それから二人無言で電車に乗りこんで、途中で別れた。陽介の背中はひどく落ち込んでいたが、それ以上声はかけられなかった。
俺は各駅停車に乗り換えて、前のアパートへの最寄り駅で降りた。
再開発すらも諦められている、小さな町だ。けれど俺にとっては家族と共に暮らした、かけがえのないホームタウンだ。
ふと俺はアパートの向かい側にある、白い教会へと足を向けた。
馴染みの酒場はまだ昼だから閉まっている。その横にある扉から、俺は聖堂の中に入った。
学校の教室一つ分ほどもない小さな聖堂だ。金も銀もステンドグラスのような華やかな装飾もなく、ただ古びた椅子と祭壇、そして十字架だけが置かれている。
正面の天窓から差し込んでくる陽光を浴びて、祭壇の前でひざまずいている少年がいた。胸の前で手を組んで、目を閉じて静止している。
いつもこの子は静寂を身にまとっているな。俺は彼が祈りを終えるまで戸口で待っていた。
「貴正さん」
やがて聖也君が振り返って顔を上げる。俺はそちらに歩み寄りながら言う。
「邪魔をしてしまったかな」
「いえ」
まだ二十歳にもなっていない若さでありながら、彼はゆっくりと落ち着いて話す子だった。
「何についての祈りだった?」
「殺められた死者に対する哀悼を」
聖也君は長い金色の睫毛を伏せて告げる。
「悲しい事件がまた起こってしまったと聞きます」
「君も山根の事件を知ってるのか」
聖也君はこくりと頷く。
「俺がきっと犯人をみつけてみせるよ。そして正子を」
「いいえ」
普段の彼からは信じられないほど、聖也君は鋭く俺を見上げて言う。
「正子さんはきっと僕が救ってみせます」
正子のことになると、聖也君は途端に少年の意固地さを見せる。
「十年経ってもあの子を思ってくれてありがとう」
聖也君は正子と友達同士だった。教会とアパートの間にある公園で、二人はいつも楽しそうに遊んでいたものだ。
「この事件は、きっと人の手では解決できないのです」
「そんなことはない。人が起こした事件なら、人が解決できる」
俺が強く見つめ返したが、聖也君は目を逸らしたりしなかった。
「救いをもたらせるのは神だけです。人では、その人を殺すことでしか終わらせることはできません」
「人には法がある」
人の世界で起きたものは、人の法で解決する。俺の信念だ。
「ごめん。君の信仰は止めないよ」
聖也君には彼なりの信念がある。それを曲げることは許されないと、俺は言葉を収めた。
「いえ、僕こそ失礼しました」
聖也君は丁寧に頭を下げて微笑む。
氷のような美貌が、優しい陽だまりのようなものに色を変えた。
「正子さんが貴正さんのところに、一日も早く戻ることを祈っています」
俺も笑い返そうとして、その笑みを消す。
一瞬だった。けれど確かに教会の中に、俺と聖也君以外の気配を感じた。
その、たまらなく懐かしい、大切な存在。
俺は振り返って扉に走る。扉を開け放って呼ぶ。
「……正子?」
そうであってほしいという俺の切望が、そう言わせたのかもしれない。
正子はいなかった。代わりに、教会の外の小さな庭には、屈みこんで花を見ている少女がいた。
後から歩いて来た聖也君がそっと告げる。
「彼女は昨日からこの教会に泊めている旅行者の方です」
脇に抱えているのはシルクハットではないがずいぶん変わった形の帽子だった。けれど確かに、酒場で会ったテラという少女に間違いはなかった。
「観光にも行かずに、朝からずっと庭を見ていらっしゃるんですよ」
ここはさほど有名な観光地ではないのに、不思議なことだった。
「いつまで滞在する予定なんだ?」
聖也君が首を傾げる気配がした。
「魔物が消えるまで、だそうです。……どういう意味でしょうね」
テラさんは愛おしそうに、側の花に触れて笑っていた。