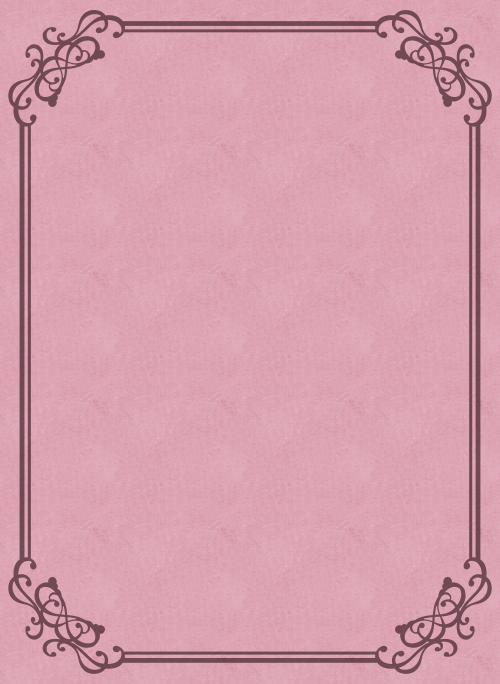無骨で機械的。青い瞳は細く、背に二重に広がる翼は深緋色と紺碧色。頭身以上の刀を帯刀し、手にはスナイパーさながらの対物ライフルが握られている。
これは空想上の兵器で、アニメーションにも未だ出てきていない。誰も知らない健だけの兵器。考え尽くせるだけの仕組み、ミサイルやら武器をこの人型空想上兵器に詰め込んだ。見えるものから隠しギミックまで。その仕組みを構築するためだと、健はせわしなく光るボタンを押しまくる。コクピットは昔見たアニメの中そのものだが、ミサイルだ兵器だとかは最新のものが多い。そういうのばかり読んでいたから。それしか知らないから。
「いいのかい、従わなくて。“全世界を敵に回す“ってのは、君の好きなアニメの言葉じゃない。現実そのものだ」
「構わないさ。全然構わない。東京じゃあガン○ムが現実に作られたんだ。創作ならなおさら。ここは自由だよ。デカいロボットぐらい作らせろ、動かさせろってんだ」
「しかしなぁ」
「最初は空想の話だって、妄言だって馬鹿にしていた連中が、今や戦闘機だ軍隊だ秘密兵器だと大騒ぎだ。宇宙からの攻撃ぐらいは対処できる世の中でも、インターネット上の攻防を文字通り秒で次々に決着をつける技術力があっても、文字通り未来からの攻撃が海から、空から、空想の世界から来るとなると見ての通り全然駄目だ。てんやわんやさ。社会的な組織がいかに駄目か、分かるんだ」
「しかし、その君の作戦はうまくいくのかい? 大人の世界には、考えには明星さんだって勝てなかった。どれだけ技術力が優れていても、タイムマシンを作るほどの未来から来たのだとしても追いやられてしまったじゃないか」
「いや、だからこそだよ」、と僕は助手席で楽しそうにしているエデンに言う。
「被害が出れば、動くところは動く。世界であれば、それは尚更だ。理屈も法律も破って、例外だ、緊急事態だって軍やら武器やらが街を練り歩けるんだ。それこそ、この機に乗じてミサイルを撃つことだってやるだろうよ」
「そうか。君はそれでいいんだね」
「構わないさ。僕だって安い考えじゃない。世の中を変えたいとか、作り変えるとか。壊してしまえ、死んでしまえ。そんなちっぽけなことのために俺は“《《こいつ》》”を動かすんじゃない。未来なんか知らない。だから、僕が守るんだ。決まりきった大人の都合なんかに屈するものか。それこそ、将来の夢を語るとか、未来に希望を持つことなんてできないだろ。どれだけ悲惨な未来が決まっていても、それで彼女が消えてなくなって言い訳がない。それと宇宙人との戦いを瀬都奈ひとりにやらせるっていうのが、一番気に入らない」
出撃前に大人達代表として佐藤が通信を行ってきた。通信方法・手段は秘匿である。
「覚悟、決まったかな」
「殺さない。瀬都奈も未来も、僕が救う」
「言うと思ったよ。まあ、あんまり面倒事、現実側に持ってこないでよ」
「わかってる」
「できればその世界をまるごと消去してくれた方が、一番いいんだけど」
「それだと、世界は守れても瀬都奈は救えない」
「ーー彼女のこと、好きなのか」
「うるせぇ! 大人に何が分かる!」
いや、それは大人だからわかるのさ、と佐藤は続ける。
「同じ経験ではないが、しかし、似たような感情はいくつも通ってきた。それを飲み込み、乗り越えて僕らは大人をやっている。仕事だ、社会のためだーー今回で言えば、未来のためだってね」
「ーーそれで、なんだ。やっぱり邪魔するのか?」
国家機密組織の諜報機関に属している彼に、覚悟を持って言う。
「いやいや。大丈夫。君の察しの通りだよ。邪魔はしないし、できないから安心したまえ。好きにしていいよ。今回の件は元々制御できるようなことじゃない。現代では理解も解明もできん。だから、明星から秘密を聞いた君を止めるすべは無い。認めよう。しかしだね、健くんだっけか。あくまで君は独断で専攻だ。こちらのやり方で私達は行動するからそのつもりで。作戦も伝えない。いいね」
「それでいい」
通信はそこで途絶えた。謎の機械音がピコンピコンと静かに鳴っている。そう、静かに。その場をやり過ごすために鳴っていた。そのすべてが空想だというのに。
「ねえ、名前決めたの?」
「ん?」
「この巨大人形ロボット。やっぱガン○ム?」
「いや、」と返して少し考えるふりをした。そしてすでに決めていた名前を口にする。
「REIWA。なんでも、次の年号らしいぜ」