四日目の朝、私たちは函館駅から新幹線の通る新函館北斗駅から北海道新幹線はやぶさに乗っていた。行き先は盛岡だ。
昨日の夜、函館山のレストランで食事をしていると、メニュー表が立っている場所に例の空色の封筒を見つけたのだ。
その封筒のあまりの神出鬼没ぶりに驚きつつ、先生はにやりと笑って封筒を開けてくれた。
そして、案の定出てきた『旅カードNo.3』に書かれていた行き先が、岩手県にある『奥中山高原』という場所だったのだ。
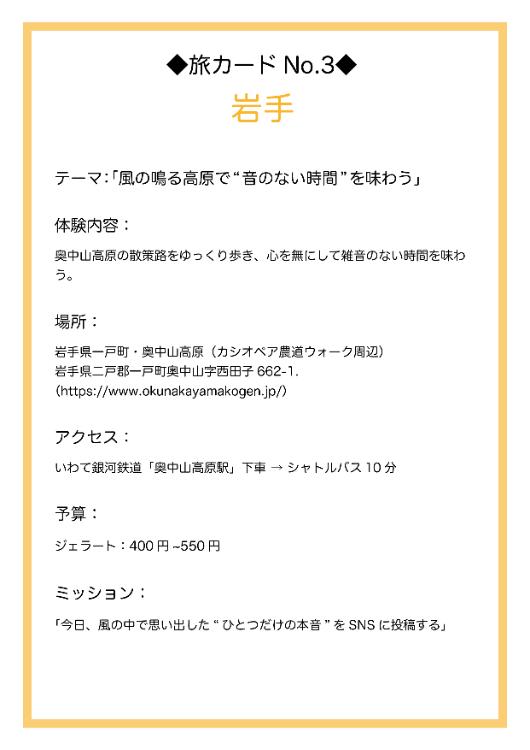
「高原というか、高原周辺をウォーキングせよ! ってことみたいですね」
「本当だ〜。書いてある通り、大自然の中を歩くって心が落ち着きそう」
「先生は常に心が忙しなさそうですもんね」
「こら! アラサー女をからかうんじゃない」
先生がぷりぷりと怒った様子でむっと唇を閉じる。でも、次の瞬間には「ぷっ」と吹き出して笑うから、本気で怒っているのではないのだと安心した。
「ねえ先生。昨日の女性の話を聞いて思ったんですけど、私も、誰かの心の声にもっと耳を傾けていたら、耳が聞こえなくなることなんてなかったのかな」
窓から移り行く景色を眺めて楽しんでいる先生の肩を叩いて、私は感じていたことを手話で話した。移動中、何もやることがないのでつい気持ちの整理をしがちだ。話し相手が先生だから、勝手に言葉があふれそうになる。
「青葉ちゃんって、中学時代に友達と何かあったんだっけ」
先生には詩織と梨花のことを、曖昧にしか伝えられていない。確か去年、担任だった彼女に「友達とトラブルがあって」とぎこちない手話で話したような気がする。
「そう……ですね。六組の相葉詩織と入谷梨花って知ってますか?」
私は思い切って先生に尋ねた。二人は今、同じクラスに所属している。先生は「ああ」と大きく頷いて「去年二人とも教えてたよ」と言った。
「そうだったんですね。その二人と、中学で仲が良かったんです。だけど、二人が“心の声”で私の悪口を言っているのを聞いてしまって……」
“青葉って可愛くないくせに、成績がいいからって調子に乗ってる”
“勉強も運動も頑張ってますアピール? うざー”
あの時のことを思い出しては、今でも胸がずきんずきんと痛くなる。
「心の声……って、前に話してくれたことか」
先生の言葉に、私はこっくりと頷く。他人のネガティブな心の声が聞こえていた過去の体質のことを、両親以外に話しているのは羽美先生だけだ。誰に話しても信じてもらえないことは分かっていたから、他に事情を知っている人はいない。
「そうです。その時の私は、大好きだった二人に裏切られたような気持ちになって、怖くて耳を塞いでしまったんです。でも今考えたら、あの時二人の口から本音を聞くのが正解だったのかなって……」
きっとその時、私たちは喧嘩をすることになっていただろう。場合によっては無視されたり二人が私を突き放してきたりした可能性だってある。そう思うと、当時は怖くて二人の口から本音を聞こうなんて、とてもじゃないけど考えられなかった。
先生は私の言葉をゆっくりと咀嚼したあと、口を開いた。
「そんなこと今考えても仕方ないよ。その時の青葉ちゃんは、いっぱいいっぱいになってたんでしょう? だったら、耳を塞ぐのが正解だったんじゃないかな」
事情を知ってくれてる先生だからこそ、心の中で揺れていた私の気持ちを真正面から受け止めてくれたのだと分かった。
「耳を塞ぐのが正解だった」と言われて、どこかほっとしている自分がいた。
私は誰かに自分の生き様を肯定してほしかったのかな……。
自分は間違っていない。友達のほうが私を傷つけるようなことをしたんだって、証明してほしかったんだろうか。
自分の本音が分からないまま、先生の言葉にただ頷くことしかできなかった。
昨日の夜、函館山のレストランで食事をしていると、メニュー表が立っている場所に例の空色の封筒を見つけたのだ。
その封筒のあまりの神出鬼没ぶりに驚きつつ、先生はにやりと笑って封筒を開けてくれた。
そして、案の定出てきた『旅カードNo.3』に書かれていた行き先が、岩手県にある『奥中山高原』という場所だったのだ。
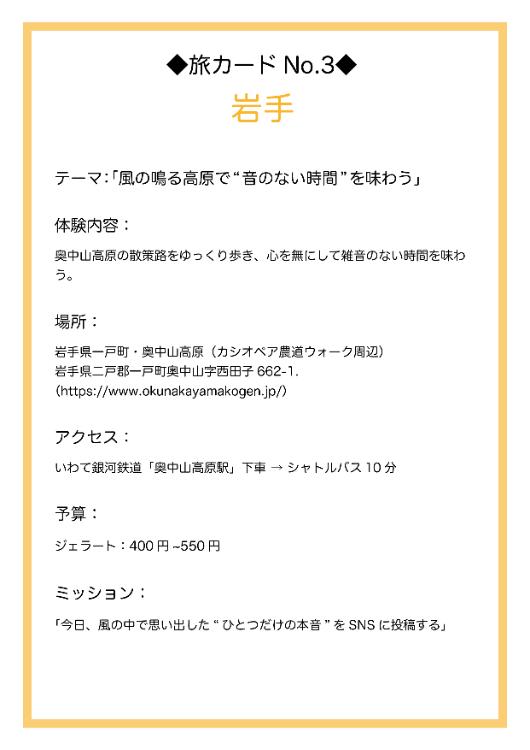
「高原というか、高原周辺をウォーキングせよ! ってことみたいですね」
「本当だ〜。書いてある通り、大自然の中を歩くって心が落ち着きそう」
「先生は常に心が忙しなさそうですもんね」
「こら! アラサー女をからかうんじゃない」
先生がぷりぷりと怒った様子でむっと唇を閉じる。でも、次の瞬間には「ぷっ」と吹き出して笑うから、本気で怒っているのではないのだと安心した。
「ねえ先生。昨日の女性の話を聞いて思ったんですけど、私も、誰かの心の声にもっと耳を傾けていたら、耳が聞こえなくなることなんてなかったのかな」
窓から移り行く景色を眺めて楽しんでいる先生の肩を叩いて、私は感じていたことを手話で話した。移動中、何もやることがないのでつい気持ちの整理をしがちだ。話し相手が先生だから、勝手に言葉があふれそうになる。
「青葉ちゃんって、中学時代に友達と何かあったんだっけ」
先生には詩織と梨花のことを、曖昧にしか伝えられていない。確か去年、担任だった彼女に「友達とトラブルがあって」とぎこちない手話で話したような気がする。
「そう……ですね。六組の相葉詩織と入谷梨花って知ってますか?」
私は思い切って先生に尋ねた。二人は今、同じクラスに所属している。先生は「ああ」と大きく頷いて「去年二人とも教えてたよ」と言った。
「そうだったんですね。その二人と、中学で仲が良かったんです。だけど、二人が“心の声”で私の悪口を言っているのを聞いてしまって……」
“青葉って可愛くないくせに、成績がいいからって調子に乗ってる”
“勉強も運動も頑張ってますアピール? うざー”
あの時のことを思い出しては、今でも胸がずきんずきんと痛くなる。
「心の声……って、前に話してくれたことか」
先生の言葉に、私はこっくりと頷く。他人のネガティブな心の声が聞こえていた過去の体質のことを、両親以外に話しているのは羽美先生だけだ。誰に話しても信じてもらえないことは分かっていたから、他に事情を知っている人はいない。
「そうです。その時の私は、大好きだった二人に裏切られたような気持ちになって、怖くて耳を塞いでしまったんです。でも今考えたら、あの時二人の口から本音を聞くのが正解だったのかなって……」
きっとその時、私たちは喧嘩をすることになっていただろう。場合によっては無視されたり二人が私を突き放してきたりした可能性だってある。そう思うと、当時は怖くて二人の口から本音を聞こうなんて、とてもじゃないけど考えられなかった。
先生は私の言葉をゆっくりと咀嚼したあと、口を開いた。
「そんなこと今考えても仕方ないよ。その時の青葉ちゃんは、いっぱいいっぱいになってたんでしょう? だったら、耳を塞ぐのが正解だったんじゃないかな」
事情を知ってくれてる先生だからこそ、心の中で揺れていた私の気持ちを真正面から受け止めてくれたのだと分かった。
「耳を塞ぐのが正解だった」と言われて、どこかほっとしている自分がいた。
私は誰かに自分の生き様を肯定してほしかったのかな……。
自分は間違っていない。友達のほうが私を傷つけるようなことをしたんだって、証明してほしかったんだろうか。
自分の本音が分からないまま、先生の言葉にただ頷くことしかできなかった。





