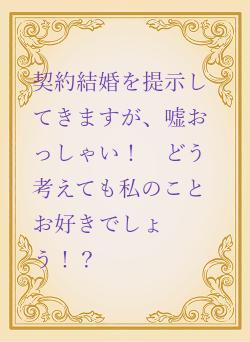わたくしが病み上がりの身体から回復した頃、わたくしと蘿月様は箱根に向かいました。十月の気温は少々肌寒かったのですが、不思議と心が温かく、歩いているだけで心が弾みました。
一歩踏み出すと、躑躅さんが半結びに結ってくれた髪が揺れて、不思議な気分です。ずっと出かける時は、結綿のような、所謂日本髪に結っていましたので、ハイカラな髪型をしていると、それだけで自分が別人になったような気分になるのでした。
「躑躅に土産を買ってやらんとな」
温泉街を歩きながら、蘿月様がぽつりと呟きます。
躑躅さんも一緒に旅行に来ないか、わたくしは尋ねたのですが、新婚旅行を邪魔しちゃいけないわァと言って、彼女は来ようとしませんでした。わたくしたちが出かけている間、少しずつ元の姿を取り戻しつつある、神社の裏の住処を整えておいてくれるつもりのようで、なおさら、お土産を買って帰らないと悪いような気がしてしまいます。躑躅さんには、そんなこと気にせず出かけてくるように言われたのですが、わたくしの気分と良識の問題です。
「躑躅さんは何を好まれるのですか」
尋ねると、蘿月様はうーんと首を傾げます。
「あれはお前が好きなことしかわからん」
「わたくし、ですか」
「躑躅はお前がいる間しか俺のところに来ないのだよ。墓の様子を見に来ることはあるが」
聞けば、彼女はわたくしの魂があの世にある間は、なかなか蘿月様の元に顔を出さないということで、二千年以上前からの知り合いである二人も、お互いの性格は知ってはいれども、移り変わり続ける世の中で、食べ物をはじめとする好きなものを知っているわけではないということでした。
「また暮らすようになれば、分かるんだがな。まだ会ったばかりだ」
「そうでしたか」
「ただ、あれはお前が選んだものなら、なんでも喜ぶよ。なんせ、二千年前に受けた恩のために、ずっとお前についているのだからな」
恩、ですか。わたくしが首を傾げると、彼は慌てたように、曖昧に微笑みました。知りたかったら躑躅に尋ねなさいと言われ、頷くと、彼は今度はほっとしたように笑うのでした。
途中までは蘿月様の神の力で飛び、途中からは人力車を乗り継いできましたので、宿で休んだ後に、蘿月様が二百年前に頼んだという刀を取りにいくことにしました。
変わっていなければ大涌谷の近くにある山の、中腹にいるとのことですので、時に蘿月様に抱えられながら、二人で歩いて山を登りますと、古い民家がぽつんと立っているのでした。蘿月様に、この場から動かないように言われ、頷くと、彼はわざと足音を立ててその民家に歩み寄ります。すると、ばきり、と音がして宙で何かが割れ、ぱらぱらと地面に降り注ぎました。それが結界であると気が付いた時、その民家から、着物に袴姿の、髷を結った男が、刀を携えて飛び出してくるのでした。がきん、と音がして、蘿月様が放った何かと刀が交わります。
「待て待て、俺だ。蘿月だ」
蘿月様が窘めるように言うと、男は刀の剣先を、蘿月様から外します。それから彼は蘿月様をまじまじと見つめて、「なんだお前か」と言うのでした。わたくしも含め、その場にほっとした、柔らかい雰囲気が流れます。
「いつまでも取りに来ないから、祟り神になって討伐されたかと思ったぜ」
「間一髪だ。新たなかんなぎに、どうにか出会えた」
「良かったなァ。おれはもうお前を諦めていたぞ」
「そう言うな」
紹介しよう、と蘿月様がわたくしを手招きします。そこに小走りで駆け寄ると、男は目を細めて、わたくしを見るのでした。
「翡翠に似ているか?」
「こころが同じだ。見た目は、肉体が違うからな。彼女は琥珀と言う」
はじめまして。わたくしが頭を下げると、彼はにこりと笑い、「おれは千子村正だ」と言うので、わたくしは思わず目を丸くして、問いかけました。
「千子村正って、あの、千子村正ですか。妖刀を打つという」
そうだとも、よく知ってるな、と彼は笑うのですが、蘿月様は彼の耳を摘まみ上げるようにして、「違うぞ」と言うのでした。
「こいつは千子村正の弟子だ。これは鬼の腕羅という。腕に羅刹の羅で、かいら」
腕羅さんは、すぐに正体を知らされてしまったことに、不服そうに唇を尖らせていたのですが、すぐに「そうさ、おれは弟子だ」と認めました。
「千子村正たちが死んでからな、あっちこっち放浪して、たどり着いたのがこの場所よ。蘿月が刀を取りに来たら、とっとと移動しようと思ったんだが、いつまでもこいつが取りに来ねえから」
「届けてくれても良かったんだぞ」
「お前の神社におれは入れないだろ、馬鹿言うんじゃない。強い結界張りやがって」
「躑躅は入れるのになぁ」
「躑躅と一緒にするな、結界すり抜けられるやつが何人もいてたまるか」
どうやら、蘿月様と腕羅さんが親しいらしいと気が付いた頃、腕羅さんはわたくしに視線を合わせるようにして、「また今は服装が変わったな」と言いました。すると、蘿月様がにやりと笑みを浮かべます。
「今は断髪、とやらが男には勧められているようだ。髷はもう古いようだぞ」
「なんだって」
理由を問われ、わたくしが江戸幕府の倒幕や明治維新、西洋の列強に追い付くための近代化、服装の変化などを伝えると、彼は大きくため息をついて、「世の中変わっちまったな」と呟くのでした。
「琥珀はつまり、最近の子と。まあ、そうだよな、新しいかんなぎだもんな」
「まだ十四だぞ、琥珀は。それにお前は人里に出なさすぎるんだ」
「おう、気を付ける」
久しぶりの再会は話が弾むらしく、しばらくお互いを揶揄うような応酬が続きましたが、わたくしが取り残されていることに蘿月様が気が付き、刀を見せてくれと言います。途端、腕羅さんが引きつった表情を浮かべました。もしや、と思い、わたくしと蘿月様が顔を見合わせます。
「お前、俺がもう死んだと思って、溶かしたんじゃないだろうな」
「そ、そんなことは」
「出せ、今すぐ。ここに」
「溶かしました、ごめんなさい」
「お前な」
すぐその場にひれ伏して、おいおい泣く真似を腕羅さんがしますので、わたくしと蘿月様はもう一度目を合わせました。「殴っても許されるだろうか」「やめてあげてください」そんな会話をしたような気がします。
一応、言い訳も聞いてあげたのですが、どうやら、彼は人の持つ妖力や神力に合わせて刀を打つのだそうで、その時々で相応しい刀が変わるのだそうです。二百年前に蘿月様に最適だった妖刀は、今は相応しくない――そんな事情だそうです。言い訳にはいい加減だな、と蘿月様にぴしゃりと言われていましたが。
「今のお前は呪いの力が強い。呪いの力に合わせた刀を打つ方が――」
「で、何日で刀を仕上げられる? 七日で終わるか?」
「終わらせます」
彼が走って民家に入るのを見送り、わたくしと蘿月様はため息をつきました。刀を受け取りがてらの新婚旅行の最初には少々ひどい話であるように思いましたが、なんだかおかしくて、でも少し、寂しいような気がしました。
一歩踏み出すと、躑躅さんが半結びに結ってくれた髪が揺れて、不思議な気分です。ずっと出かける時は、結綿のような、所謂日本髪に結っていましたので、ハイカラな髪型をしていると、それだけで自分が別人になったような気分になるのでした。
「躑躅に土産を買ってやらんとな」
温泉街を歩きながら、蘿月様がぽつりと呟きます。
躑躅さんも一緒に旅行に来ないか、わたくしは尋ねたのですが、新婚旅行を邪魔しちゃいけないわァと言って、彼女は来ようとしませんでした。わたくしたちが出かけている間、少しずつ元の姿を取り戻しつつある、神社の裏の住処を整えておいてくれるつもりのようで、なおさら、お土産を買って帰らないと悪いような気がしてしまいます。躑躅さんには、そんなこと気にせず出かけてくるように言われたのですが、わたくしの気分と良識の問題です。
「躑躅さんは何を好まれるのですか」
尋ねると、蘿月様はうーんと首を傾げます。
「あれはお前が好きなことしかわからん」
「わたくし、ですか」
「躑躅はお前がいる間しか俺のところに来ないのだよ。墓の様子を見に来ることはあるが」
聞けば、彼女はわたくしの魂があの世にある間は、なかなか蘿月様の元に顔を出さないということで、二千年以上前からの知り合いである二人も、お互いの性格は知ってはいれども、移り変わり続ける世の中で、食べ物をはじめとする好きなものを知っているわけではないということでした。
「また暮らすようになれば、分かるんだがな。まだ会ったばかりだ」
「そうでしたか」
「ただ、あれはお前が選んだものなら、なんでも喜ぶよ。なんせ、二千年前に受けた恩のために、ずっとお前についているのだからな」
恩、ですか。わたくしが首を傾げると、彼は慌てたように、曖昧に微笑みました。知りたかったら躑躅に尋ねなさいと言われ、頷くと、彼は今度はほっとしたように笑うのでした。
途中までは蘿月様の神の力で飛び、途中からは人力車を乗り継いできましたので、宿で休んだ後に、蘿月様が二百年前に頼んだという刀を取りにいくことにしました。
変わっていなければ大涌谷の近くにある山の、中腹にいるとのことですので、時に蘿月様に抱えられながら、二人で歩いて山を登りますと、古い民家がぽつんと立っているのでした。蘿月様に、この場から動かないように言われ、頷くと、彼はわざと足音を立ててその民家に歩み寄ります。すると、ばきり、と音がして宙で何かが割れ、ぱらぱらと地面に降り注ぎました。それが結界であると気が付いた時、その民家から、着物に袴姿の、髷を結った男が、刀を携えて飛び出してくるのでした。がきん、と音がして、蘿月様が放った何かと刀が交わります。
「待て待て、俺だ。蘿月だ」
蘿月様が窘めるように言うと、男は刀の剣先を、蘿月様から外します。それから彼は蘿月様をまじまじと見つめて、「なんだお前か」と言うのでした。わたくしも含め、その場にほっとした、柔らかい雰囲気が流れます。
「いつまでも取りに来ないから、祟り神になって討伐されたかと思ったぜ」
「間一髪だ。新たなかんなぎに、どうにか出会えた」
「良かったなァ。おれはもうお前を諦めていたぞ」
「そう言うな」
紹介しよう、と蘿月様がわたくしを手招きします。そこに小走りで駆け寄ると、男は目を細めて、わたくしを見るのでした。
「翡翠に似ているか?」
「こころが同じだ。見た目は、肉体が違うからな。彼女は琥珀と言う」
はじめまして。わたくしが頭を下げると、彼はにこりと笑い、「おれは千子村正だ」と言うので、わたくしは思わず目を丸くして、問いかけました。
「千子村正って、あの、千子村正ですか。妖刀を打つという」
そうだとも、よく知ってるな、と彼は笑うのですが、蘿月様は彼の耳を摘まみ上げるようにして、「違うぞ」と言うのでした。
「こいつは千子村正の弟子だ。これは鬼の腕羅という。腕に羅刹の羅で、かいら」
腕羅さんは、すぐに正体を知らされてしまったことに、不服そうに唇を尖らせていたのですが、すぐに「そうさ、おれは弟子だ」と認めました。
「千子村正たちが死んでからな、あっちこっち放浪して、たどり着いたのがこの場所よ。蘿月が刀を取りに来たら、とっとと移動しようと思ったんだが、いつまでもこいつが取りに来ねえから」
「届けてくれても良かったんだぞ」
「お前の神社におれは入れないだろ、馬鹿言うんじゃない。強い結界張りやがって」
「躑躅は入れるのになぁ」
「躑躅と一緒にするな、結界すり抜けられるやつが何人もいてたまるか」
どうやら、蘿月様と腕羅さんが親しいらしいと気が付いた頃、腕羅さんはわたくしに視線を合わせるようにして、「また今は服装が変わったな」と言いました。すると、蘿月様がにやりと笑みを浮かべます。
「今は断髪、とやらが男には勧められているようだ。髷はもう古いようだぞ」
「なんだって」
理由を問われ、わたくしが江戸幕府の倒幕や明治維新、西洋の列強に追い付くための近代化、服装の変化などを伝えると、彼は大きくため息をついて、「世の中変わっちまったな」と呟くのでした。
「琥珀はつまり、最近の子と。まあ、そうだよな、新しいかんなぎだもんな」
「まだ十四だぞ、琥珀は。それにお前は人里に出なさすぎるんだ」
「おう、気を付ける」
久しぶりの再会は話が弾むらしく、しばらくお互いを揶揄うような応酬が続きましたが、わたくしが取り残されていることに蘿月様が気が付き、刀を見せてくれと言います。途端、腕羅さんが引きつった表情を浮かべました。もしや、と思い、わたくしと蘿月様が顔を見合わせます。
「お前、俺がもう死んだと思って、溶かしたんじゃないだろうな」
「そ、そんなことは」
「出せ、今すぐ。ここに」
「溶かしました、ごめんなさい」
「お前な」
すぐその場にひれ伏して、おいおい泣く真似を腕羅さんがしますので、わたくしと蘿月様はもう一度目を合わせました。「殴っても許されるだろうか」「やめてあげてください」そんな会話をしたような気がします。
一応、言い訳も聞いてあげたのですが、どうやら、彼は人の持つ妖力や神力に合わせて刀を打つのだそうで、その時々で相応しい刀が変わるのだそうです。二百年前に蘿月様に最適だった妖刀は、今は相応しくない――そんな事情だそうです。言い訳にはいい加減だな、と蘿月様にぴしゃりと言われていましたが。
「今のお前は呪いの力が強い。呪いの力に合わせた刀を打つ方が――」
「で、何日で刀を仕上げられる? 七日で終わるか?」
「終わらせます」
彼が走って民家に入るのを見送り、わたくしと蘿月様はため息をつきました。刀を受け取りがてらの新婚旅行の最初には少々ひどい話であるように思いましたが、なんだかおかしくて、でも少し、寂しいような気がしました。