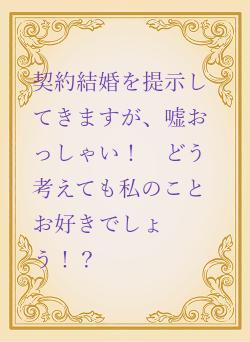わたくしは一週間ほど、高熱を出していたようです。起きては眠り、起きては眠りと繰り返していたので、その時のことははっきり覚えていないのですが、志貴様の元から助け出された次の日には、やわらかな布団が用意されていて、その中にくるまって眠りました。彼に手を握られて、額で熱を測られて、何度も、名前を呼ばれました。
どうやらわたくしの身体は、母が亡くなってからずっと虐げられていたために、ずっと悲鳴を上げ続けていたようでした。わたくしの魂に眠る記憶が、彼の元にたどり着いたことに安堵して、今のわたくしまでほっとして、もう熱を出しても良いと、気を緩めたようでした。
お母様が亡くなった日のこと。お義母様が真っ先にわたくしを虐めるようになったこと。ほたると金剛が、それに倣うようにして、わたくしを玩具だと認識し、喜ぶようになったこと。わたくしが転んでも、お父様が一度も助け起こしてくれなかったこと。志貴様はわたくしを支配し、手に入れることに執着しながらも、わたくしという存在自体を愛することはなかったこと。そういった出来事の一つひとつの記憶が波のように溢れて蘇って、わたくしは夜中に悲鳴を上げました。子どものように叫びました。つらかった、痛かった、怖かった。そう言って泣き叫ぶわたくしを、蘿月様は抱きしめて、闇の中からすくいあげるように、ただずっと、わたくしが失って、もうどうしようもなく諦めていた温もりを与えて、二度とつないだ糸が切れることのないようにと、握ってくれたのでした。
琥珀、琥珀。安心しろ。もう離さない。きっとこの生の間、俺がずっと守ってやる。翡翠。翡翠、今は安心して眠れ――。彼は時々、わたくしを翡翠と呼びました。きっとそれが、前世の名前だったのでしょう。もし、わたくしに来世というものが存在して、また彼に見つけてもらえるのなら。きっと彼は来世のわたくしを琥珀と呼び間違えるのでしょう。そう思ったらいじらしくて、ああ、愛おしい。そう思いました。ひょっとすると、わたくしは生まれる度に彼を愛するように造られているのではないかと、朦朧としながら思ったものですが、それでも良いと、思いました。
やがて、悪夢という悪夢からわたくしが追い出された頃。とろとろと目を開けると、蘿月様がわたくしの隣で、わたくしの手を握ったまま眠っていることに気が付きました。ずっと看病してくれていたのだとようやく気が付き、起き上がって、彼をそっと揺り起こします。わたくしは見たことのない浴衣を着ていたのですが、やはり熱で自分の力で動けない人間に着せるのは難しかったらしく、袖を通して、胸と足の間が見えないように、なんとか腰ひもで巻き付けてあっただけでした。
「蘿月様」
うとうとと彼も目を開け、それから、ようやくしっかり目を開けたわたくしに、微笑みました。彼の黒い靄は首のあたりまで下がっていて、その整った顔がほっと緩むのが見えました。
「それだけ汗を掻いたのなら、もう時期に良くなるだろう」
「見苦しい姿を、見せたようで」
「構わないよ。それより、腹が減ったのではないか」
あ。そう呟いた途端、ぐぅとお腹が鳴ります。恥ずかしさで顔に熱が溜まるのを感じましたが、彼は優しく笑うだけでした。
「まだ奥の住処が復活していなくてなぁ。厨房だけ、かろうじて。ああ、いや、買いに行かせる。――躑躅、躑躅、来い」
ぱんぱん。彼が手を叩くと、すっと扉が開いて、少々釣り目で鼻の高い美女が現れます。衣装は芸者と見紛うほど豪奢だったのですが、不思議と上品で、妖艶さはあれども夜の街にいそうな雰囲気はありません。わたくしは突然うつくしい女性が現れたので驚いていたのですが、彼女が九つに別れた狐の尻尾を振るのを見て、「まあ」と声を零しました。
「九尾の狐は初めてだろう。紹介する、これは躑躅だ」
「うふふ、熱を出していた時も少し面倒を見たのだけれど、覚えてないわよね」
彼女が艶やかに笑い、わたくしは小さくなって頷きました。すると躑躅さんは「いいのよぉ」と手を振りました。
「あたし、あなたのこと二千年も前から知っているから。魂をね。顔見に来たら寝込んでるのだもの、放っておけなくなってしまったの」
「わたくしは、二千年も前から、いたのですか」
「そうよ。そのあたりの話は、蘿月から聞きなさい。まあとにかく、しばらく女中みたいなことしてあげるわ。何なら食べられるかしら」
えっと。わたくしが答えに困っていると、蘿月様と躑躅さんは顔を見合わせました。
「もしや、熱の時、何も食べなかったのか?」
「え、ええ」
わたくしが頷くと、すぐに怒りだしたのは、躑躅さんでした。
「んまー、なんてお家なの。病み上がりはお粥よお粥。お粥も厳しければ、なにかもっと探すわよ」
「母は、わたくしが熱を出した時、何か出してくれたのを覚えているのですが、もう幼くて、それが何だったのかは覚えてないのです。それに母が亡くなって何年かしたら、熱を出したらいけないと思って、そうしたら、なかなか熱も出さなくなって」
苦し紛れの言い訳に、もう一度躑躅さんと蘿月様は顔を見合わせ、やっぱり躑躅さんは憤慨して、「育ての親は誰よもう! あたしが色仕掛けでころっとやってしまおうかしら!」と言うのでした。恐ろしいまでの美人の躑躅さんが言うと冗談に聞こえませんので、蘿月様と二人がかりで彼女をなだめ、とにかく料理屋でお粥を買ってきてもらおうことにしました。
躑躅さんを見送った後、わたくしも、裏に水桶を用意してあるから身体を洗っておいでと言われ、身体が汗でべたべたしていることを思い出し、大人しく身体を洗うことにしました。熱を出している間に痩せたようで、腹や足のすっと細くなった自分の姿はあまりにも弱々しく、そして同時に、今までよくもまあ、丈夫とは言い難かった身体で、あの仕打ちに耐えてきたと思いました。骨を折らずに済んできたことが不思議です。
辺りを見回すと、つい一、二週間前には境内に草は生え放題、本殿も拝殿も朽ち果てて、それが神社であると信じられるかどうか聞かれると怪しいような場所であったのに、今は荒れた草も半分になり、外れていた本殿の扉も、腐っていた木の壁も、復活しているように見えました。人の手で修理したとすれば、あまりにも期間が短すぎますので、もしかすると、この神社自体、蘿月様の状態によって、存在を左右されるものなのかもしれません。奥にある屋敷らしきものは、この前訪れた時には姿すら見た記憶がありませんので、わたくしが寝込んでいる間に、やっと輪郭だけ取り戻したのかもしれませんでした。そう思いながら身体と髪を洗うと、さっぱりして、身体の悪いものが落ちたように思いました。
新しい浴衣を纏い、今度はきちんと帯まで結びました。髪を乾かしながら躑躅さんを待っていると、しばらくして、彼女はお粥だけでなく、あんパンやら団子やらを買って帰って来たのでした。
「梅干しも乗せてもらったわ」
「あ、ありがとうございます」
さ、お食べ。蘿月様にそう言われて、そっと匙を口に運ぶと、お粥のほんのり甘い味と、梅干しの酸っぱい味が広がります。美味しい、そう呟くと、二人が顔を綻ばせます。
「ゆっくり食べていいからな」
「食べきれなかったら、また後で食べたらいいからね。お腹がびっくりするわよ」
頷きながら、一口ひとくち、大切に食べましたが、結局半分も食べきれずに、また後で食べることになりました。しかし不思議と、食べると力が湧いてくるものでして、ああ、生きているのだと思いました。
「それで、わたくしの前世と、蘿月様について、お伺いしても良いですか」
お腹が驚いて変に動いているのが落ち着いた後、わたくしは蘿月様に尋ねました。躑躅さんは「あたしお屋敷綺麗にしてくるわ」と席を立ち、二人で話すように促してきます。彼女のからからという下駄の音が裏に消えると、彼は、どこから話そうか、とでも言うように、曖昧に笑みを浮かべるのでした。
「俺はもう二千年以上を生きている神でな。守り神でもあり、同時に、荒神でもある」
「良い神様は良い神様では、ないのですか」
わたくしが首を傾げると、蘿月様はうーん、と一緒になって首を傾げます。
「荒魂と和魂、って言葉があってな。荒魂は神の荒々しい一面を、和魂は神の穏やかな面を指す。同じ神がその両方を見せることもある」
だから人は神を祀るのだな。彼はそう付け足しました。
蘿月様は、人の憎しみや恨みつらみ、災いを吸い取ることで、人に幸を与える神様であるそうです。人々はもう二千年以上、彼に自分たちの苦しみを吸い取ってもらうために神社という場所に彼を祀っていたようですが、しかし、彼はそういった負のものを吸い取っても浄化する方法を持たないのだそうで、長い年月を過ごしていると、だんだんと祟り神に近づいていくのだそうです。
ある時、祟り神となり、歩くだけで人を殺すほどの怨念を抱えた彼は、ひとりのかんなぎに救われたと言います。その者は蘿月様に触れるだけで浄化する力を持ち、そして彼の纏った、黒々とした祟りに触れても、一つも傷つくことはなかったそうです。
「それがわたくしの、魂の、最初の姿」
「そうだ。名を持たぬというから、さくや、と呼んだ」
それから、わたくしの魂は五百年に一度生を受け、彼に仕え、彼が祟り神にならぬよう、その身体の持った呪いを清めることを定めとされたようです。魂に刻まれた記憶や想いといったものが、定めを定めと知らぬ時にも理解し、彼の元へ自分から歩むように仕向けるのだそうです。
さくや、さよ、すず、翡翠。彼が丁寧に呟く名は、皆わたくしの名前のようでした。それは、彼が浄化の役目を持ったかんなぎというもの以上に、わたくしを愛しんでいたと理解するには十分な、優しい声色でした。
「ところが、五百年前のことだ。お前は、今萩原志貴と名乗っている男に大層気に入られてしまってな」
翡翠だったわたくしは、その時は鎌倉にある、神官の家に生まれたのだそうです。初経が来ることで、わたくしは己の魂に刻まれた役目を思い出し、彼もまた、わたくしの居場所に気が付くのだそうですが、その時はたまたま、十歳になる前から再開を果たすことができたようです。まだお役目を果たすには力の弱い子どもでしたが、彼の優しさに惹かれたようで、たびたび彼に会いに行き、少しずつ身体に呪いを貯めつつある、彼に寄り添いました。しかし、わたくしを恋い慕っていた志貴様は、それが気に食わなかったようでした。
志貴様はその時、特に名も持たぬような貧民であったそうですが、わたくしは時折、貧民に食事を分け与えるようなことをしていたようです。わたくしのことですから、きっと、分け隔てなく、誰にでも同じ優しさを与えたのだと思いますが、志貴様はその小さな優しさを、特別な愛に受け取ったようでした。
わたくしがはじめての月のものを迎え、己の役目をはっきりと自覚した時、わたくしとの結婚を望む志貴様に、蘿月様の元に嫁入りすると言って断ったようです。すると彼は激高し、わたくしを攫って、彼の家に閉じ込めたようでした。そして純潔を奪われました。
神への供物、というものは清らかである必要があります。古来より、生贄に選ばれた少女たちは美しい者が中心に選ばれたようですが、それと同時に、純潔であることも求められました。一度でも他の男に身体を暴かれてしまえば、神への贄としての価値を喪います。わたくしはそうして、蘿月様のかんなぎでなくなったのです。
「助けようと、したのだがな」
志貴様は、蘿月様にわたくしを奪われないように、身近にいたあやかしというあやかしを全て喰らったようでした。まずは翡翠に連なる家の者を喰らい、人ならざる者の力を手に入れ、それから鬼を食い、二又の狐を食いと、恐ろしい勢いで力をつけ、蘿月様の力に対抗したそうです。わたくしは何度も犯された末に心を壊し、衰弱してすぐに死んだそうで、蘿月様の助けの手を握ることも出来なかったそうです。志貴様は蘿月様が入れぬように結界を張り、わたくしの骨を隠しました。来世のわたくしを手に入れるためです。
「お前の魂は、残された骨に引きずられて、志貴の元にたどり着いてしまったようだ」
わたくしが初経を迎え、彼に気が付いてもらえるようになった頃には、すでにわたくしは志貴様の手の中にありました。蘿月様はやっと志貴様が骨を隠したほんとうの意味に気が付きましたが、ただ、五百年前に浄化を受けられなかったために、祟り神に近づき、弱り果て、自らの力で助け出すことが叶わなかったのだそうです。
「今世では必ず助けると誓ったのに」
彼の手が、わたくしの頬を撫でます。翡翠、助けられなくてすまなかった。琥珀、こんなに遅くなって、つらい思いをさせて、すまなかった。彼はそう言い、何度も志貴様に叩かれたわたくしの頬を、そっと、そっと、撫でるのでした。
「俺があの姿で現れた時も、お前がここに来てくれた時も。後にあれに殴られたのだろう。あれは暴力で支配する男だ」
「ですが、あなたにこうして迎えられたのだから、もう、良いのです。それにわたくしもお役目に気が付かず逃げてしまいましたので、おかげで」
わたくしの胸につかえていた、あの日の申し訳なさを吐き出すと、彼は首を振りました。あれは誰が見ても恐ろしいから仕方ないと。それよりも、彼は己の罪を吐き出すかのように、わたくしを労わります。罪なんて、そんなもの彼にはありませんのに。
「骨があの場所にあるせいで、あれが支配しやすいように、劣悪な場所に生まれたのだろう」
「ですが、わたくしは生まれました。あなたに会うために」
わたくしは母を喪ってからずっと、わたくしを愛し、慈しんでくれる人に飢えていたようでした。蘿月様に会うために生まれてきて、これまでを生きてきたのだと思ったら、苦しんでいた小さなわたくしたちが報われるようで、心の中に棲んでいた、憎しみやら恐れやらが膨れたり萎んだりを繰り返して、心の端のほうに逃げていくのです。それは確かな、救いのかたちでありました。
「初夜の前に、助けられました。志貴様が急ぐわけです」
「目を覚ましたら、お前が逃げているところが頭に浮かんでな」
目があって、わたくしたちは微笑みあいました。前世で歪められた運命が、どうにか残された糸を繋いで、やっと結ばれた瞬間であるように思いました。彼の手を取ると、やわらかく、握られます。
「これからわたくし、蘿月様のお嫁さま、ということで宜しいのでしょうか」
「ああ。そうだな。お前が嫌でなければ、だが」
「嫌なんて、そんなことありません。とても、嬉しいです」
これからよろしくな。そう呟く彼に微笑み、そっと唇を寄せたのですが、あることに気が付きました。
「もしや、口づけしなくても、浄化の力は、あるのですか?」
彼がさっと顔を逸らします。「そうだな」
「前世のわたくしも、その前もその前も、あなたに口づけしていた、ということ、ですよね?」
彼の顔がますます赤くなり、それでわたくしも察してしまいます。はわわ……と人のもののような、人のものでないような悲鳴が出て、もう今更であるのですが、生まれ変わる前のわたくしがいかに彼を愛していたのか、知るのでした。
どうやらわたくしの身体は、母が亡くなってからずっと虐げられていたために、ずっと悲鳴を上げ続けていたようでした。わたくしの魂に眠る記憶が、彼の元にたどり着いたことに安堵して、今のわたくしまでほっとして、もう熱を出しても良いと、気を緩めたようでした。
お母様が亡くなった日のこと。お義母様が真っ先にわたくしを虐めるようになったこと。ほたると金剛が、それに倣うようにして、わたくしを玩具だと認識し、喜ぶようになったこと。わたくしが転んでも、お父様が一度も助け起こしてくれなかったこと。志貴様はわたくしを支配し、手に入れることに執着しながらも、わたくしという存在自体を愛することはなかったこと。そういった出来事の一つひとつの記憶が波のように溢れて蘇って、わたくしは夜中に悲鳴を上げました。子どものように叫びました。つらかった、痛かった、怖かった。そう言って泣き叫ぶわたくしを、蘿月様は抱きしめて、闇の中からすくいあげるように、ただずっと、わたくしが失って、もうどうしようもなく諦めていた温もりを与えて、二度とつないだ糸が切れることのないようにと、握ってくれたのでした。
琥珀、琥珀。安心しろ。もう離さない。きっとこの生の間、俺がずっと守ってやる。翡翠。翡翠、今は安心して眠れ――。彼は時々、わたくしを翡翠と呼びました。きっとそれが、前世の名前だったのでしょう。もし、わたくしに来世というものが存在して、また彼に見つけてもらえるのなら。きっと彼は来世のわたくしを琥珀と呼び間違えるのでしょう。そう思ったらいじらしくて、ああ、愛おしい。そう思いました。ひょっとすると、わたくしは生まれる度に彼を愛するように造られているのではないかと、朦朧としながら思ったものですが、それでも良いと、思いました。
やがて、悪夢という悪夢からわたくしが追い出された頃。とろとろと目を開けると、蘿月様がわたくしの隣で、わたくしの手を握ったまま眠っていることに気が付きました。ずっと看病してくれていたのだとようやく気が付き、起き上がって、彼をそっと揺り起こします。わたくしは見たことのない浴衣を着ていたのですが、やはり熱で自分の力で動けない人間に着せるのは難しかったらしく、袖を通して、胸と足の間が見えないように、なんとか腰ひもで巻き付けてあっただけでした。
「蘿月様」
うとうとと彼も目を開け、それから、ようやくしっかり目を開けたわたくしに、微笑みました。彼の黒い靄は首のあたりまで下がっていて、その整った顔がほっと緩むのが見えました。
「それだけ汗を掻いたのなら、もう時期に良くなるだろう」
「見苦しい姿を、見せたようで」
「構わないよ。それより、腹が減ったのではないか」
あ。そう呟いた途端、ぐぅとお腹が鳴ります。恥ずかしさで顔に熱が溜まるのを感じましたが、彼は優しく笑うだけでした。
「まだ奥の住処が復活していなくてなぁ。厨房だけ、かろうじて。ああ、いや、買いに行かせる。――躑躅、躑躅、来い」
ぱんぱん。彼が手を叩くと、すっと扉が開いて、少々釣り目で鼻の高い美女が現れます。衣装は芸者と見紛うほど豪奢だったのですが、不思議と上品で、妖艶さはあれども夜の街にいそうな雰囲気はありません。わたくしは突然うつくしい女性が現れたので驚いていたのですが、彼女が九つに別れた狐の尻尾を振るのを見て、「まあ」と声を零しました。
「九尾の狐は初めてだろう。紹介する、これは躑躅だ」
「うふふ、熱を出していた時も少し面倒を見たのだけれど、覚えてないわよね」
彼女が艶やかに笑い、わたくしは小さくなって頷きました。すると躑躅さんは「いいのよぉ」と手を振りました。
「あたし、あなたのこと二千年も前から知っているから。魂をね。顔見に来たら寝込んでるのだもの、放っておけなくなってしまったの」
「わたくしは、二千年も前から、いたのですか」
「そうよ。そのあたりの話は、蘿月から聞きなさい。まあとにかく、しばらく女中みたいなことしてあげるわ。何なら食べられるかしら」
えっと。わたくしが答えに困っていると、蘿月様と躑躅さんは顔を見合わせました。
「もしや、熱の時、何も食べなかったのか?」
「え、ええ」
わたくしが頷くと、すぐに怒りだしたのは、躑躅さんでした。
「んまー、なんてお家なの。病み上がりはお粥よお粥。お粥も厳しければ、なにかもっと探すわよ」
「母は、わたくしが熱を出した時、何か出してくれたのを覚えているのですが、もう幼くて、それが何だったのかは覚えてないのです。それに母が亡くなって何年かしたら、熱を出したらいけないと思って、そうしたら、なかなか熱も出さなくなって」
苦し紛れの言い訳に、もう一度躑躅さんと蘿月様は顔を見合わせ、やっぱり躑躅さんは憤慨して、「育ての親は誰よもう! あたしが色仕掛けでころっとやってしまおうかしら!」と言うのでした。恐ろしいまでの美人の躑躅さんが言うと冗談に聞こえませんので、蘿月様と二人がかりで彼女をなだめ、とにかく料理屋でお粥を買ってきてもらおうことにしました。
躑躅さんを見送った後、わたくしも、裏に水桶を用意してあるから身体を洗っておいでと言われ、身体が汗でべたべたしていることを思い出し、大人しく身体を洗うことにしました。熱を出している間に痩せたようで、腹や足のすっと細くなった自分の姿はあまりにも弱々しく、そして同時に、今までよくもまあ、丈夫とは言い難かった身体で、あの仕打ちに耐えてきたと思いました。骨を折らずに済んできたことが不思議です。
辺りを見回すと、つい一、二週間前には境内に草は生え放題、本殿も拝殿も朽ち果てて、それが神社であると信じられるかどうか聞かれると怪しいような場所であったのに、今は荒れた草も半分になり、外れていた本殿の扉も、腐っていた木の壁も、復活しているように見えました。人の手で修理したとすれば、あまりにも期間が短すぎますので、もしかすると、この神社自体、蘿月様の状態によって、存在を左右されるものなのかもしれません。奥にある屋敷らしきものは、この前訪れた時には姿すら見た記憶がありませんので、わたくしが寝込んでいる間に、やっと輪郭だけ取り戻したのかもしれませんでした。そう思いながら身体と髪を洗うと、さっぱりして、身体の悪いものが落ちたように思いました。
新しい浴衣を纏い、今度はきちんと帯まで結びました。髪を乾かしながら躑躅さんを待っていると、しばらくして、彼女はお粥だけでなく、あんパンやら団子やらを買って帰って来たのでした。
「梅干しも乗せてもらったわ」
「あ、ありがとうございます」
さ、お食べ。蘿月様にそう言われて、そっと匙を口に運ぶと、お粥のほんのり甘い味と、梅干しの酸っぱい味が広がります。美味しい、そう呟くと、二人が顔を綻ばせます。
「ゆっくり食べていいからな」
「食べきれなかったら、また後で食べたらいいからね。お腹がびっくりするわよ」
頷きながら、一口ひとくち、大切に食べましたが、結局半分も食べきれずに、また後で食べることになりました。しかし不思議と、食べると力が湧いてくるものでして、ああ、生きているのだと思いました。
「それで、わたくしの前世と、蘿月様について、お伺いしても良いですか」
お腹が驚いて変に動いているのが落ち着いた後、わたくしは蘿月様に尋ねました。躑躅さんは「あたしお屋敷綺麗にしてくるわ」と席を立ち、二人で話すように促してきます。彼女のからからという下駄の音が裏に消えると、彼は、どこから話そうか、とでも言うように、曖昧に笑みを浮かべるのでした。
「俺はもう二千年以上を生きている神でな。守り神でもあり、同時に、荒神でもある」
「良い神様は良い神様では、ないのですか」
わたくしが首を傾げると、蘿月様はうーん、と一緒になって首を傾げます。
「荒魂と和魂、って言葉があってな。荒魂は神の荒々しい一面を、和魂は神の穏やかな面を指す。同じ神がその両方を見せることもある」
だから人は神を祀るのだな。彼はそう付け足しました。
蘿月様は、人の憎しみや恨みつらみ、災いを吸い取ることで、人に幸を与える神様であるそうです。人々はもう二千年以上、彼に自分たちの苦しみを吸い取ってもらうために神社という場所に彼を祀っていたようですが、しかし、彼はそういった負のものを吸い取っても浄化する方法を持たないのだそうで、長い年月を過ごしていると、だんだんと祟り神に近づいていくのだそうです。
ある時、祟り神となり、歩くだけで人を殺すほどの怨念を抱えた彼は、ひとりのかんなぎに救われたと言います。その者は蘿月様に触れるだけで浄化する力を持ち、そして彼の纏った、黒々とした祟りに触れても、一つも傷つくことはなかったそうです。
「それがわたくしの、魂の、最初の姿」
「そうだ。名を持たぬというから、さくや、と呼んだ」
それから、わたくしの魂は五百年に一度生を受け、彼に仕え、彼が祟り神にならぬよう、その身体の持った呪いを清めることを定めとされたようです。魂に刻まれた記憶や想いといったものが、定めを定めと知らぬ時にも理解し、彼の元へ自分から歩むように仕向けるのだそうです。
さくや、さよ、すず、翡翠。彼が丁寧に呟く名は、皆わたくしの名前のようでした。それは、彼が浄化の役目を持ったかんなぎというもの以上に、わたくしを愛しんでいたと理解するには十分な、優しい声色でした。
「ところが、五百年前のことだ。お前は、今萩原志貴と名乗っている男に大層気に入られてしまってな」
翡翠だったわたくしは、その時は鎌倉にある、神官の家に生まれたのだそうです。初経が来ることで、わたくしは己の魂に刻まれた役目を思い出し、彼もまた、わたくしの居場所に気が付くのだそうですが、その時はたまたま、十歳になる前から再開を果たすことができたようです。まだお役目を果たすには力の弱い子どもでしたが、彼の優しさに惹かれたようで、たびたび彼に会いに行き、少しずつ身体に呪いを貯めつつある、彼に寄り添いました。しかし、わたくしを恋い慕っていた志貴様は、それが気に食わなかったようでした。
志貴様はその時、特に名も持たぬような貧民であったそうですが、わたくしは時折、貧民に食事を分け与えるようなことをしていたようです。わたくしのことですから、きっと、分け隔てなく、誰にでも同じ優しさを与えたのだと思いますが、志貴様はその小さな優しさを、特別な愛に受け取ったようでした。
わたくしがはじめての月のものを迎え、己の役目をはっきりと自覚した時、わたくしとの結婚を望む志貴様に、蘿月様の元に嫁入りすると言って断ったようです。すると彼は激高し、わたくしを攫って、彼の家に閉じ込めたようでした。そして純潔を奪われました。
神への供物、というものは清らかである必要があります。古来より、生贄に選ばれた少女たちは美しい者が中心に選ばれたようですが、それと同時に、純潔であることも求められました。一度でも他の男に身体を暴かれてしまえば、神への贄としての価値を喪います。わたくしはそうして、蘿月様のかんなぎでなくなったのです。
「助けようと、したのだがな」
志貴様は、蘿月様にわたくしを奪われないように、身近にいたあやかしというあやかしを全て喰らったようでした。まずは翡翠に連なる家の者を喰らい、人ならざる者の力を手に入れ、それから鬼を食い、二又の狐を食いと、恐ろしい勢いで力をつけ、蘿月様の力に対抗したそうです。わたくしは何度も犯された末に心を壊し、衰弱してすぐに死んだそうで、蘿月様の助けの手を握ることも出来なかったそうです。志貴様は蘿月様が入れぬように結界を張り、わたくしの骨を隠しました。来世のわたくしを手に入れるためです。
「お前の魂は、残された骨に引きずられて、志貴の元にたどり着いてしまったようだ」
わたくしが初経を迎え、彼に気が付いてもらえるようになった頃には、すでにわたくしは志貴様の手の中にありました。蘿月様はやっと志貴様が骨を隠したほんとうの意味に気が付きましたが、ただ、五百年前に浄化を受けられなかったために、祟り神に近づき、弱り果て、自らの力で助け出すことが叶わなかったのだそうです。
「今世では必ず助けると誓ったのに」
彼の手が、わたくしの頬を撫でます。翡翠、助けられなくてすまなかった。琥珀、こんなに遅くなって、つらい思いをさせて、すまなかった。彼はそう言い、何度も志貴様に叩かれたわたくしの頬を、そっと、そっと、撫でるのでした。
「俺があの姿で現れた時も、お前がここに来てくれた時も。後にあれに殴られたのだろう。あれは暴力で支配する男だ」
「ですが、あなたにこうして迎えられたのだから、もう、良いのです。それにわたくしもお役目に気が付かず逃げてしまいましたので、おかげで」
わたくしの胸につかえていた、あの日の申し訳なさを吐き出すと、彼は首を振りました。あれは誰が見ても恐ろしいから仕方ないと。それよりも、彼は己の罪を吐き出すかのように、わたくしを労わります。罪なんて、そんなもの彼にはありませんのに。
「骨があの場所にあるせいで、あれが支配しやすいように、劣悪な場所に生まれたのだろう」
「ですが、わたくしは生まれました。あなたに会うために」
わたくしは母を喪ってからずっと、わたくしを愛し、慈しんでくれる人に飢えていたようでした。蘿月様に会うために生まれてきて、これまでを生きてきたのだと思ったら、苦しんでいた小さなわたくしたちが報われるようで、心の中に棲んでいた、憎しみやら恐れやらが膨れたり萎んだりを繰り返して、心の端のほうに逃げていくのです。それは確かな、救いのかたちでありました。
「初夜の前に、助けられました。志貴様が急ぐわけです」
「目を覚ましたら、お前が逃げているところが頭に浮かんでな」
目があって、わたくしたちは微笑みあいました。前世で歪められた運命が、どうにか残された糸を繋いで、やっと結ばれた瞬間であるように思いました。彼の手を取ると、やわらかく、握られます。
「これからわたくし、蘿月様のお嫁さま、ということで宜しいのでしょうか」
「ああ。そうだな。お前が嫌でなければ、だが」
「嫌なんて、そんなことありません。とても、嬉しいです」
これからよろしくな。そう呟く彼に微笑み、そっと唇を寄せたのですが、あることに気が付きました。
「もしや、口づけしなくても、浄化の力は、あるのですか?」
彼がさっと顔を逸らします。「そうだな」
「前世のわたくしも、その前もその前も、あなたに口づけしていた、ということ、ですよね?」
彼の顔がますます赤くなり、それでわたくしも察してしまいます。はわわ……と人のもののような、人のものでないような悲鳴が出て、もう今更であるのですが、生まれ変わる前のわたくしがいかに彼を愛していたのか、知るのでした。