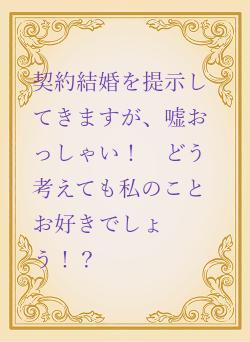蘿月様のために志貴様の言いつけを破ったことに後悔はありませんが、困ったのは、呪具で志貴様の部屋に吊り下げられるようにして囚われている間に、月のものが来ていることを知られたことでした。彼はわたくしの足の間から流れる血を知り、狂ったように喜び、これが終われば夫婦の契りを結ぼうと言いました。わたくしが怯えたのを感じ取った彼は、初夜は大切にするとうっとりとした顔で言うので、俄然わたくしは恐ろしくなって、月のものが終わらないように願いましたが、三日ほどで、流れる血は止まってしまいました。
結婚の儀式は、わたくしに手枷と足枷を嵌めた状態で行われました。白無垢を着せてもらえているとはいえ、花嫁が拘束されながら行われる儀式なんて、あまりにも乱暴です。彼がどうして、月のものが来たと知ってすぐに結婚の儀式を、初夜を急ぎたがるのかが分からず、わたくしはただ鎖と音をじゃらじゃらと鳴らしていましたが、彼との結婚自体、もう四年ほど覚悟していましたので、諦めるしかありませんでした。
儀式が終わると、褥の上に突き飛ばすように転がされ、足の鎖を解かれます。これから彼に着物を奪われ、身体を触られるのです。恐る恐る志貴様を見上げると、爛々と光る眼で、怯えるわたくしを笑っていました。
「これでお前が、僕のものになる」
その声は、普通ではありませんでした。それは愛情というよりも、長年降り積もり、執念というもので狂わされたような、醜い、醜い、叫ぶような声でした。ぞっと背筋が泡立ち、ほとんど反射的に思い立って、彼が己の着物に手をかけた瞬間、ぱっと起き上がりました。志貴様を突き飛ばして、部屋の外へ、屋敷の外へと逃げます。今逃げなければ、取り返しのつかないようなことになるような気がして、それと同時に、わたくしを優しく呼ぶ蘿月様の声が、恋しくなりました。どうせ、身体を暴かれて、夫婦となるのなら。例え化け物であったとしても、蘿月様が良いと、そう強く強く、思いました。
がしゃん、どた、ばた。障子やら花瓶やらが倒される音がして、志貴様が追いかけてきます。わたくしの足ではすぐに追いつかれてしまうと分かり、隠れる場所を探しました。
咄嗟に目についたのは、禁じられた場所である倉でした。わたくしに見られたくないものがそこにあるとすれば、何かしらの交渉の材料になり得るでしょうか。そういう縋る思いで扉に手をかけると、鍵が解けるように、かちんと音がして、ひとりでに扉が開きます。そこに身体を滑り込ませようとして、月明りの差し込んだそこにあったものに、悲鳴を堪えることができませんでした。
そこにあったのは、骨でした。頭蓋骨から、肋骨らしきもの、腰骨らしきもの、手足の長い骨も、みんな棚に乗せられています。そこに張り付けられた呪符は、ついこの前志貴様が使っていたものと同じものでした。
「わ、わた、わたくしの骨」
どうしてそれがわたくしの骨だと思ったのかは分かりませんが、それは間違えなくわたくしのものなのです。心というべきか、魂というべきものが、そう訴えているのです。手足が震えて、後ずさりしていると、後ろから髪を掴まれました。うぅ、小さく声が零れます。
「そうだよ。君の骨だ」
「か、返してください。わたくしの、骨、大事な」
「君の前世の骨なんか持ってどうするんだ。お前には要らぬ宝だよ」
「ぜ、前世なんて」
彼がわたくしの前世の、腕か足の骨を強く掴むと、腕が捻り上げられているような感覚がしました。悲鳴を堪え、腕を庇うようにして蹲ると、手枷を掴まれ、もう片方の手で帯を解かれます。今この場でわたくしを辱めるつもりなのだと気が付くと涙が止まらず、殴られる覚悟で必死に抵抗をします。いや、やめて、助けて、蘿月様。蘿月様!
「あれの名を、呼ぶなァァァァ」
彼が大きく手を振り上げた時、ふっと、辺りの空気が変わりました。重苦しい、志貴様がわたくしに向ける執念よりも、苦しいものが、肌に張り付きます。途端、夜闇を裂くようにして、人影が部屋に降り立ちました。
「俺の花嫁を、返してもらおう」
蘿月様が、そこに立っていました。彼の身体から放たれる靄が志貴様の目を覆い、わたくしの骨につけられた呪符をさっと剥がしていきます。わたくしが咄嗟に彼に手を伸ばすと、柔らかな温度で、包まれました。
「琥珀は、俺が五百年待ち望んだ花嫁だ。もう二度と、お前のような外道に渡しはせんよ」
彼はあの日とは違い、顔にかかった靄は消え、形の整った目と唇が露わになっていました。その目が鋭く志貴様を見つめ、それから慈しむような目で、わたくしを見降ろしました。
「さ、逃げよう。事情は後だ。俺も長くは保たん」
さっと抱え上げられたかと思うと、彼は倉を飛び出して、とん、と跳躍しました。ふわりと身体が浮き上がったかと思うと、みるみるうちに地面が遠ざかって、ほんの少しだけ、星が近くなりました。ひゅっ、と心臓が縮むような気がしてしまいます。
「骨も拾ってやりたいのだが、すまない」
空を飛ぶなんてことが、一生のうちであるとは思いませんでしたので、恐怖やら興奮やらで答える余裕はありませんでした。やがて朽ち果てた神社に降り立ち、おかしな音を立てる心臓と息が整うと、あの場から助けられたのだと実感が湧いて、ぽろぽろと涙が零れました。本殿の床にはまだ埃が残っていましたが、それでも、わたくしが最初に訪れた時よりもずっと綺麗でした。
「助けてくださって、ありがとう、ございます」
「俺がこんなでなければ、骨も」
「骨は、後ででいいです。ただ、ほっとして」
次第にしゃくりあげ、わあわあと泣き出すわたくしの背を彼が撫でてくれます。ずっとこうして欲しかったと、そう思いました。母を喪ってからというもの、こうして、誰かに優しくしてもらえることもなく、ただ人に怯える日々でした。泣いても傍にいてくれる人がいるだけで、どうしてこうも、安心して、もっと泣きたくなるのでしょう。ただ泣き続けてしばらくが経ち、わたくしの呼吸が落ち着き、涙が落ち着いた頃、かしゃんと手枷が外れました。手枷も何かわるい呪術がかけられていたのか、彼がうめき声をあげて、床に倒れ伏しましたので、あわてて彼を起こして、その首に腕を回しました。唇を重ねて、彼の身体に張り付いた悪いものが剥がれ落ちていくように、祈ります。やがて彼の顔色にほんの少し赤みが戻って、わたくしは身体を離しました。ほんとうは、わたくしを助けに来るだけで精一杯だったはずなのに、わたくしを慰めて、鎖まで外してくれたのだと思うと、再び涙が零れ降りて、止まりませんでした。
「今世のお前は泣き虫だな」
「涙が許されない日々だったので。泣いても良いのだと思ったら」
「すまなかった」
彼はわたくしをそっと、ただし強く強く抱き寄せて、子どもをあやすように、背を、頭をさすりました。今までつらかったな。すまなかった。やっとお前を取り戻せた。そういう言葉を聞きながら、首を縦にふり、横にふり、わたくしはただ、与えられる温もりにほっとしていました。
「早く事情を説明したいのは山々なのだが。先にお前の身体に埋め込まれた呪いを解こうと思う」
彼がそう言ったのは、わたくしが落ち着いてきた頃でした。呪い、ですか。そう尋ねるわたくしに、彼は「琥珀と骨をつなぐ呪いだ」と答えます。
「お前の前世の骨とお前の両方にかけられた呪いのせいで、骨が傷つけられるとお前の身体も痛むのだろう。きっと背中かどこかにあると思うのだ」
彼が言うには、骨から呪符を外しはしたが、一時的な処置らしく、このままでは、呪符を作り直せばまたあの呪いが発動するのだそうです。呪い自体を打ち消すためには、わたくしの身体に刻まれた呪いの印自体を壊す必要がある、とのことでした。
場所に心当たりはあるかと聞かれて、首を振ります。身体に何か、呪いがかけられていると分かるような印なんて、あった覚えはありません。しかし志貴様なら、わたくしを支配するために、わたくしの知らぬうちに呪いを仕込むだろうとも思いました。蘿月様に背中と腰の後ろなど、自分の目で確認できない場所を見てもらうように頼み、白無垢の帯を解きます。ぱさりぱさり。着物が床に落ちていきます。
不思議と、彼に肌を見せるのは、嫌ではありませんでした。恥ずかしさはあっても、怖くはありませんし、何かひどいことをされるとも思いませんでした。ただ、すべての着物を床に落としてから、背中にまだ蹴られた時の痣が残っているのではないかと思い立ち、そこだけ、隠してしまいたいような気持ちになります。
彼はまず、生々しく残っているであろう痣をなぞりました。わたくしが痛みにうめくと、指がぱっと離れていきます。それから今度は労わるように、彼の手が肩甲骨の間の、背骨のあたりに触れました。その指が強張ったことから、そこが呪いの印のある場所なのだろうと分かりました。そういえば、わたくしが萩原の家にやってきた十歳の時、彼にそのあたりを執拗に触られたことがあったと、薄っすら思い出します。
「焼いて切るのと、噛んで切るのと。琥珀はどちらがましに思う?」
「まあ。そんなにひどい呪いでしたか」
「何年苦しんだ、これに」
「かれこれ、四年ほど、でしょうか」
彼が舌打ちしたような気配がして、わたくしは慌てて、彼に志貴様に反抗しなければ、骨を使って痛めつけられはしなかったことと、むしろその場で叩かれるほうが多かったことを話したのですが、むしろ逆効果だったようでした。彼の気配にみるみる怒気が混ざっていき、どう彼をなだめようか迷うほどでした。
「か、噛んでくださいまし。火のしで火傷したことが、ありまして」
「どこだ、それは」
「もう昔に消えました」
彼はそうか、とだけ呟き、その怒気ぐっとを仕舞いこみました。白無垢だったものを床に敷き、わたくしをそこにうつ伏せに横たわらせると、「痛いが、我慢してくれ」と言います。
彼の髪がさらりと背に触れて、息が近づきました。わたくしが迫る痛みに目を瞑った途端、がりりと歯を立てられます。肉の一部を削って、そこにある呪いを彼が喰らおうとしているのだと直感して、拳を握って耐えていると、彼の手が、労わるような優しさを持ちながらも、強い力でわたくしの身体を押さえます。動けば傷が増えるからでしょう。彼のその気遣いを無駄にしないよう、必死で痛みに耐えていると、抑える力が和らいで、傷を癒すそうに、そっと舌が這わされるのでした。そうして、痛みと癒しが、何度も繰り返されました。
「よく耐えた」
終わった後は、わたくしはぐったりと彼の膝に頭を乗せて、彼にされるがままに頭を撫でられていました。時折髪の毛を梳かれ、さらりと黒が視界に落ちます。
まだ背に痛みは残っていましたが、彼はきっと、癒しの力を使うことが出来るのでしょう。皮膚が食いちぎられるような痛みではなく、その残滓だけがそこにあるようでした。痛みのせいでびっしょり汗をかいた身体を、彼がそっとそっと、拭ってくれます。それから床に敷いた白無垢をわたくしの身体に巻くようにして、わたくしの裸体を隠しました。
「印の、重要な意味を持つところは、俺が食った。もうお前は自由だ」
「自由、ですか」
自由って、いったいなんでしょう。そう呟くと、彼は驚いたような声を出しましたか、じわりじわりと眠気が襲ってきて、わたくしはそのまま、眠りの世界に落ちました。
結婚の儀式は、わたくしに手枷と足枷を嵌めた状態で行われました。白無垢を着せてもらえているとはいえ、花嫁が拘束されながら行われる儀式なんて、あまりにも乱暴です。彼がどうして、月のものが来たと知ってすぐに結婚の儀式を、初夜を急ぎたがるのかが分からず、わたくしはただ鎖と音をじゃらじゃらと鳴らしていましたが、彼との結婚自体、もう四年ほど覚悟していましたので、諦めるしかありませんでした。
儀式が終わると、褥の上に突き飛ばすように転がされ、足の鎖を解かれます。これから彼に着物を奪われ、身体を触られるのです。恐る恐る志貴様を見上げると、爛々と光る眼で、怯えるわたくしを笑っていました。
「これでお前が、僕のものになる」
その声は、普通ではありませんでした。それは愛情というよりも、長年降り積もり、執念というもので狂わされたような、醜い、醜い、叫ぶような声でした。ぞっと背筋が泡立ち、ほとんど反射的に思い立って、彼が己の着物に手をかけた瞬間、ぱっと起き上がりました。志貴様を突き飛ばして、部屋の外へ、屋敷の外へと逃げます。今逃げなければ、取り返しのつかないようなことになるような気がして、それと同時に、わたくしを優しく呼ぶ蘿月様の声が、恋しくなりました。どうせ、身体を暴かれて、夫婦となるのなら。例え化け物であったとしても、蘿月様が良いと、そう強く強く、思いました。
がしゃん、どた、ばた。障子やら花瓶やらが倒される音がして、志貴様が追いかけてきます。わたくしの足ではすぐに追いつかれてしまうと分かり、隠れる場所を探しました。
咄嗟に目についたのは、禁じられた場所である倉でした。わたくしに見られたくないものがそこにあるとすれば、何かしらの交渉の材料になり得るでしょうか。そういう縋る思いで扉に手をかけると、鍵が解けるように、かちんと音がして、ひとりでに扉が開きます。そこに身体を滑り込ませようとして、月明りの差し込んだそこにあったものに、悲鳴を堪えることができませんでした。
そこにあったのは、骨でした。頭蓋骨から、肋骨らしきもの、腰骨らしきもの、手足の長い骨も、みんな棚に乗せられています。そこに張り付けられた呪符は、ついこの前志貴様が使っていたものと同じものでした。
「わ、わた、わたくしの骨」
どうしてそれがわたくしの骨だと思ったのかは分かりませんが、それは間違えなくわたくしのものなのです。心というべきか、魂というべきものが、そう訴えているのです。手足が震えて、後ずさりしていると、後ろから髪を掴まれました。うぅ、小さく声が零れます。
「そうだよ。君の骨だ」
「か、返してください。わたくしの、骨、大事な」
「君の前世の骨なんか持ってどうするんだ。お前には要らぬ宝だよ」
「ぜ、前世なんて」
彼がわたくしの前世の、腕か足の骨を強く掴むと、腕が捻り上げられているような感覚がしました。悲鳴を堪え、腕を庇うようにして蹲ると、手枷を掴まれ、もう片方の手で帯を解かれます。今この場でわたくしを辱めるつもりなのだと気が付くと涙が止まらず、殴られる覚悟で必死に抵抗をします。いや、やめて、助けて、蘿月様。蘿月様!
「あれの名を、呼ぶなァァァァ」
彼が大きく手を振り上げた時、ふっと、辺りの空気が変わりました。重苦しい、志貴様がわたくしに向ける執念よりも、苦しいものが、肌に張り付きます。途端、夜闇を裂くようにして、人影が部屋に降り立ちました。
「俺の花嫁を、返してもらおう」
蘿月様が、そこに立っていました。彼の身体から放たれる靄が志貴様の目を覆い、わたくしの骨につけられた呪符をさっと剥がしていきます。わたくしが咄嗟に彼に手を伸ばすと、柔らかな温度で、包まれました。
「琥珀は、俺が五百年待ち望んだ花嫁だ。もう二度と、お前のような外道に渡しはせんよ」
彼はあの日とは違い、顔にかかった靄は消え、形の整った目と唇が露わになっていました。その目が鋭く志貴様を見つめ、それから慈しむような目で、わたくしを見降ろしました。
「さ、逃げよう。事情は後だ。俺も長くは保たん」
さっと抱え上げられたかと思うと、彼は倉を飛び出して、とん、と跳躍しました。ふわりと身体が浮き上がったかと思うと、みるみるうちに地面が遠ざかって、ほんの少しだけ、星が近くなりました。ひゅっ、と心臓が縮むような気がしてしまいます。
「骨も拾ってやりたいのだが、すまない」
空を飛ぶなんてことが、一生のうちであるとは思いませんでしたので、恐怖やら興奮やらで答える余裕はありませんでした。やがて朽ち果てた神社に降り立ち、おかしな音を立てる心臓と息が整うと、あの場から助けられたのだと実感が湧いて、ぽろぽろと涙が零れました。本殿の床にはまだ埃が残っていましたが、それでも、わたくしが最初に訪れた時よりもずっと綺麗でした。
「助けてくださって、ありがとう、ございます」
「俺がこんなでなければ、骨も」
「骨は、後ででいいです。ただ、ほっとして」
次第にしゃくりあげ、わあわあと泣き出すわたくしの背を彼が撫でてくれます。ずっとこうして欲しかったと、そう思いました。母を喪ってからというもの、こうして、誰かに優しくしてもらえることもなく、ただ人に怯える日々でした。泣いても傍にいてくれる人がいるだけで、どうしてこうも、安心して、もっと泣きたくなるのでしょう。ただ泣き続けてしばらくが経ち、わたくしの呼吸が落ち着き、涙が落ち着いた頃、かしゃんと手枷が外れました。手枷も何かわるい呪術がかけられていたのか、彼がうめき声をあげて、床に倒れ伏しましたので、あわてて彼を起こして、その首に腕を回しました。唇を重ねて、彼の身体に張り付いた悪いものが剥がれ落ちていくように、祈ります。やがて彼の顔色にほんの少し赤みが戻って、わたくしは身体を離しました。ほんとうは、わたくしを助けに来るだけで精一杯だったはずなのに、わたくしを慰めて、鎖まで外してくれたのだと思うと、再び涙が零れ降りて、止まりませんでした。
「今世のお前は泣き虫だな」
「涙が許されない日々だったので。泣いても良いのだと思ったら」
「すまなかった」
彼はわたくしをそっと、ただし強く強く抱き寄せて、子どもをあやすように、背を、頭をさすりました。今までつらかったな。すまなかった。やっとお前を取り戻せた。そういう言葉を聞きながら、首を縦にふり、横にふり、わたくしはただ、与えられる温もりにほっとしていました。
「早く事情を説明したいのは山々なのだが。先にお前の身体に埋め込まれた呪いを解こうと思う」
彼がそう言ったのは、わたくしが落ち着いてきた頃でした。呪い、ですか。そう尋ねるわたくしに、彼は「琥珀と骨をつなぐ呪いだ」と答えます。
「お前の前世の骨とお前の両方にかけられた呪いのせいで、骨が傷つけられるとお前の身体も痛むのだろう。きっと背中かどこかにあると思うのだ」
彼が言うには、骨から呪符を外しはしたが、一時的な処置らしく、このままでは、呪符を作り直せばまたあの呪いが発動するのだそうです。呪い自体を打ち消すためには、わたくしの身体に刻まれた呪いの印自体を壊す必要がある、とのことでした。
場所に心当たりはあるかと聞かれて、首を振ります。身体に何か、呪いがかけられていると分かるような印なんて、あった覚えはありません。しかし志貴様なら、わたくしを支配するために、わたくしの知らぬうちに呪いを仕込むだろうとも思いました。蘿月様に背中と腰の後ろなど、自分の目で確認できない場所を見てもらうように頼み、白無垢の帯を解きます。ぱさりぱさり。着物が床に落ちていきます。
不思議と、彼に肌を見せるのは、嫌ではありませんでした。恥ずかしさはあっても、怖くはありませんし、何かひどいことをされるとも思いませんでした。ただ、すべての着物を床に落としてから、背中にまだ蹴られた時の痣が残っているのではないかと思い立ち、そこだけ、隠してしまいたいような気持ちになります。
彼はまず、生々しく残っているであろう痣をなぞりました。わたくしが痛みにうめくと、指がぱっと離れていきます。それから今度は労わるように、彼の手が肩甲骨の間の、背骨のあたりに触れました。その指が強張ったことから、そこが呪いの印のある場所なのだろうと分かりました。そういえば、わたくしが萩原の家にやってきた十歳の時、彼にそのあたりを執拗に触られたことがあったと、薄っすら思い出します。
「焼いて切るのと、噛んで切るのと。琥珀はどちらがましに思う?」
「まあ。そんなにひどい呪いでしたか」
「何年苦しんだ、これに」
「かれこれ、四年ほど、でしょうか」
彼が舌打ちしたような気配がして、わたくしは慌てて、彼に志貴様に反抗しなければ、骨を使って痛めつけられはしなかったことと、むしろその場で叩かれるほうが多かったことを話したのですが、むしろ逆効果だったようでした。彼の気配にみるみる怒気が混ざっていき、どう彼をなだめようか迷うほどでした。
「か、噛んでくださいまし。火のしで火傷したことが、ありまして」
「どこだ、それは」
「もう昔に消えました」
彼はそうか、とだけ呟き、その怒気ぐっとを仕舞いこみました。白無垢だったものを床に敷き、わたくしをそこにうつ伏せに横たわらせると、「痛いが、我慢してくれ」と言います。
彼の髪がさらりと背に触れて、息が近づきました。わたくしが迫る痛みに目を瞑った途端、がりりと歯を立てられます。肉の一部を削って、そこにある呪いを彼が喰らおうとしているのだと直感して、拳を握って耐えていると、彼の手が、労わるような優しさを持ちながらも、強い力でわたくしの身体を押さえます。動けば傷が増えるからでしょう。彼のその気遣いを無駄にしないよう、必死で痛みに耐えていると、抑える力が和らいで、傷を癒すそうに、そっと舌が這わされるのでした。そうして、痛みと癒しが、何度も繰り返されました。
「よく耐えた」
終わった後は、わたくしはぐったりと彼の膝に頭を乗せて、彼にされるがままに頭を撫でられていました。時折髪の毛を梳かれ、さらりと黒が視界に落ちます。
まだ背に痛みは残っていましたが、彼はきっと、癒しの力を使うことが出来るのでしょう。皮膚が食いちぎられるような痛みではなく、その残滓だけがそこにあるようでした。痛みのせいでびっしょり汗をかいた身体を、彼がそっとそっと、拭ってくれます。それから床に敷いた白無垢をわたくしの身体に巻くようにして、わたくしの裸体を隠しました。
「印の、重要な意味を持つところは、俺が食った。もうお前は自由だ」
「自由、ですか」
自由って、いったいなんでしょう。そう呟くと、彼は驚いたような声を出しましたか、じわりじわりと眠気が襲ってきて、わたくしはそのまま、眠りの世界に落ちました。