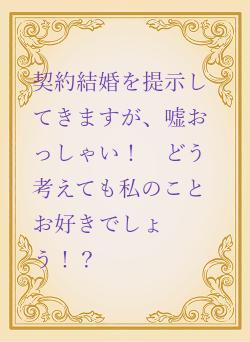蘿月様に抱えられて、蘭麝神社までひとっ跳びで帰ると、落ち着かない様子で庭をうろうろ歩いていた躑躅さんが、ぱっと顔を上げて、わたくしの元に走ってきました。ほとんど飛びつかれるようにして抱き着かれると、躑躅さんが無事であったとじわりじわりと実感して、視界が潤みます。蘿月様と躑躅さんに頭を撫でられ、お互いが無事に戻ってきたこと、それから、これからの人生を心配なく生きていけることを確かめ合いました。
「無事だったのね」
「躑躅さんこそ。撃たれたところは」
「あんなの、あたしにとっちゃかすり傷よ。二千年以上生きてる妖狐だもの」
躑躅さんはもうへっちゃらとばかりに尻尾を振って見せます。
「あいつらね、あたしらが五百年静かにしてたからって舐めすぎよ。あたしの幻術にかかるなんて、術者として下の下」
「躑躅は、こう言っているが幻術がめっぽう上手い。幻術に相手をかけ、その間に蹴り倒すのがこいつ流だ」
「足癖悪いのをわざわざ言わなくて宜しい」
「すまん、そんなつもりでは」
わあわあ言い合いをする蘿月様と躑躅さんでしたが、足癖悪いのはわたくしも一緒ですね、と言うと、二人とも驚いたようにわたくしを見て、蘿月様はわたくしが志貴を蹴りつけたのを思い出したようで、わたくしがした無理と無茶を慰めるように、無事を喜んでくれるのでした。
「他の呪術師の方は」
「逃げていったよ。這う這うの体だったから、もう来ることはないだろう。主も失ったことだし」
「それは良かった」
椎名の者も、これで大人しくなるはずです。そう言って、お義母様の大けがと、お父様を脅したことを躑躅さんにも伝え、そのことはあまり考えないようにするために、境内の隅で、小さくなって正座している芙蓉さんを見つめました。どうやらこの神社の中で起きた争いに巻き込まれたらしく、最初に会った時と同じようにぼろぼろになっていたのですが、これ以上に何かしようというつもりもないらしく、観念して座り込んでいるのでした。
「この子、さっきからずっとこうよ。うんともすんとも言わない」
「まあ」
わたくしが彼女の前にかがみこむと、しばらくの間が空いてから、やっと芙蓉さんが顔を上げました。
「大変、申し訳ありませんでした」
それは、ひどく掠れて、後悔したような声でした。ぐったりとした身体を鞭打つように、地面に頭をこすり付けて、申し訳ありませんでした、ともう一度繰り返します。
「そのように謝るくらいでしたら、最初から助けを乞うたら良かったのではありませんか」
「助けを乞うことを、このしばらくの間で、失念しておりました」
彼女の呟く声が、真っすぐにわたくしに刺さり、わたくしにもし少しでも生きる力があれば、彼女のように、助けを求められない人間になっていたかもしれない、と思いました。もとより、わたくしの家の事情に巻き込んだのですから、謝るのはこちらの方でありますから、彼女のことはこれ以上責められません。
「わたくしの生家の、椎名はもう滅びの道を辿るでしょう。椎名を欲に狂わせた者も死にました。あなたを脅す者は、もういません」
巻き込んでしまって、ごめんなさい。そのせいで、怖い思いをさせて、ごめんなさい。今度はわたくしが頭を下げると、彼女はただふるふると首を振ります。わたくしの謝罪は、彼女にとっては不要なものであるようでした。
「与えられた恩に、仇で返すような、私の生き方が恥ずかしい。どうせもう、これから先、生きられませんから。死んでお詫びいたします」
「あらまあ、わたくし、踊りを教えてくれる方がいないと、困ってしまいます」
出来るだけ軽い口調になるように努めて言うと、後ろから、躑躅さんの呆れる声が聞こえ、蘿月様がほんのり笑ったような気配がしました。芙蓉さんが驚いたように顔を上げ、呆然とわたくしを見てきますので、わたくしはそっと微笑みました。
「まだ振り付けを教えてもらっていません。あなたは仕事を半端に投げ出す人ですか?」
「いえ、それは違いますが、でも」
「これからさらにわたくしを困らせたいのであれば、それは、もう、仕方ありませんが」
わたくしが困ったような声色で、ほんの少し揶揄うように言うと、芙蓉さんが慌てて顔を横に振ります。
「でも、良いのですか」
良いでしょう、良いですよね、とわたくしが蘿月様たちを振り返ると、「好きにしたら良い」と蘿月様が笑いました。
「変な真似したら、あたしは承知しないけれど」
「ええ、決して、しません。踊りをきちんと教えた後に出ていきますので、ご安心くださいませ」
「まあまあ。その時のことは、その時考えましょう」
そう微笑みますと、芙蓉さんは涙を堪えるような声で、また御恩を受けてしまいました、と言います。こうして、芙蓉さんに優しくしているのは、先ほどわたくしの生家を地獄に落としたことの、罪滅ぼしであるようにも思いましたが、芙蓉さんのためになる話であることは確かであるように思いましたので、これは偽善ではないと、自分に言い聞かせました。
話を切り上げて、芙蓉さんに傷の手当をし、それから、わたくし自身も、手当を受けました。
「また頬が腫れている。肘も消毒しよう」
転んだり叩かれたりで擦り切れたあちこちを消毒してもらっていると、隣の部屋から、染みるとか痛いとか聞こえてきましたので、思わずぷっと吹き出しました。
「あーもー、こんくらい我慢しなさいよ。人間って弱いんだから手当はちゃんと受けなさいよ」
「まるでご自分が人間でないような口ぶり……ひぃ、染みる、勘弁して」
「ほら隣、琥珀がひとつも悲鳴あげてないでしょ。それに身体の呪い消した時よりも痛くないでしょが」
あの二人、相性良いのではないでしょうか。そう思って蘿月様を見ると、彼も同じことを思ったようで、頷いてくれました。それからわたくしも着物を脱ぎ、蘿月様に背中にあった呪いの様子を見てもらいます。彼の指がゆっくりと噛み痕がまだ残る場所をなぞり、それから静かに息を吐きだしました。
「随分薄くなったな」
「綺麗に消えるでしょうか」
「噛み痕以外はな」
「噛み痕は消えなくていいです」
「こら」
彼が何か祈るように、わたくしの背中に口づけして、それから着物を着せてくれます。おかえり、そう呟く声に、「ただいま」と返しました。
「無事だったのね」
「躑躅さんこそ。撃たれたところは」
「あんなの、あたしにとっちゃかすり傷よ。二千年以上生きてる妖狐だもの」
躑躅さんはもうへっちゃらとばかりに尻尾を振って見せます。
「あいつらね、あたしらが五百年静かにしてたからって舐めすぎよ。あたしの幻術にかかるなんて、術者として下の下」
「躑躅は、こう言っているが幻術がめっぽう上手い。幻術に相手をかけ、その間に蹴り倒すのがこいつ流だ」
「足癖悪いのをわざわざ言わなくて宜しい」
「すまん、そんなつもりでは」
わあわあ言い合いをする蘿月様と躑躅さんでしたが、足癖悪いのはわたくしも一緒ですね、と言うと、二人とも驚いたようにわたくしを見て、蘿月様はわたくしが志貴を蹴りつけたのを思い出したようで、わたくしがした無理と無茶を慰めるように、無事を喜んでくれるのでした。
「他の呪術師の方は」
「逃げていったよ。這う這うの体だったから、もう来ることはないだろう。主も失ったことだし」
「それは良かった」
椎名の者も、これで大人しくなるはずです。そう言って、お義母様の大けがと、お父様を脅したことを躑躅さんにも伝え、そのことはあまり考えないようにするために、境内の隅で、小さくなって正座している芙蓉さんを見つめました。どうやらこの神社の中で起きた争いに巻き込まれたらしく、最初に会った時と同じようにぼろぼろになっていたのですが、これ以上に何かしようというつもりもないらしく、観念して座り込んでいるのでした。
「この子、さっきからずっとこうよ。うんともすんとも言わない」
「まあ」
わたくしが彼女の前にかがみこむと、しばらくの間が空いてから、やっと芙蓉さんが顔を上げました。
「大変、申し訳ありませんでした」
それは、ひどく掠れて、後悔したような声でした。ぐったりとした身体を鞭打つように、地面に頭をこすり付けて、申し訳ありませんでした、ともう一度繰り返します。
「そのように謝るくらいでしたら、最初から助けを乞うたら良かったのではありませんか」
「助けを乞うことを、このしばらくの間で、失念しておりました」
彼女の呟く声が、真っすぐにわたくしに刺さり、わたくしにもし少しでも生きる力があれば、彼女のように、助けを求められない人間になっていたかもしれない、と思いました。もとより、わたくしの家の事情に巻き込んだのですから、謝るのはこちらの方でありますから、彼女のことはこれ以上責められません。
「わたくしの生家の、椎名はもう滅びの道を辿るでしょう。椎名を欲に狂わせた者も死にました。あなたを脅す者は、もういません」
巻き込んでしまって、ごめんなさい。そのせいで、怖い思いをさせて、ごめんなさい。今度はわたくしが頭を下げると、彼女はただふるふると首を振ります。わたくしの謝罪は、彼女にとっては不要なものであるようでした。
「与えられた恩に、仇で返すような、私の生き方が恥ずかしい。どうせもう、これから先、生きられませんから。死んでお詫びいたします」
「あらまあ、わたくし、踊りを教えてくれる方がいないと、困ってしまいます」
出来るだけ軽い口調になるように努めて言うと、後ろから、躑躅さんの呆れる声が聞こえ、蘿月様がほんのり笑ったような気配がしました。芙蓉さんが驚いたように顔を上げ、呆然とわたくしを見てきますので、わたくしはそっと微笑みました。
「まだ振り付けを教えてもらっていません。あなたは仕事を半端に投げ出す人ですか?」
「いえ、それは違いますが、でも」
「これからさらにわたくしを困らせたいのであれば、それは、もう、仕方ありませんが」
わたくしが困ったような声色で、ほんの少し揶揄うように言うと、芙蓉さんが慌てて顔を横に振ります。
「でも、良いのですか」
良いでしょう、良いですよね、とわたくしが蘿月様たちを振り返ると、「好きにしたら良い」と蘿月様が笑いました。
「変な真似したら、あたしは承知しないけれど」
「ええ、決して、しません。踊りをきちんと教えた後に出ていきますので、ご安心くださいませ」
「まあまあ。その時のことは、その時考えましょう」
そう微笑みますと、芙蓉さんは涙を堪えるような声で、また御恩を受けてしまいました、と言います。こうして、芙蓉さんに優しくしているのは、先ほどわたくしの生家を地獄に落としたことの、罪滅ぼしであるようにも思いましたが、芙蓉さんのためになる話であることは確かであるように思いましたので、これは偽善ではないと、自分に言い聞かせました。
話を切り上げて、芙蓉さんに傷の手当をし、それから、わたくし自身も、手当を受けました。
「また頬が腫れている。肘も消毒しよう」
転んだり叩かれたりで擦り切れたあちこちを消毒してもらっていると、隣の部屋から、染みるとか痛いとか聞こえてきましたので、思わずぷっと吹き出しました。
「あーもー、こんくらい我慢しなさいよ。人間って弱いんだから手当はちゃんと受けなさいよ」
「まるでご自分が人間でないような口ぶり……ひぃ、染みる、勘弁して」
「ほら隣、琥珀がひとつも悲鳴あげてないでしょ。それに身体の呪い消した時よりも痛くないでしょが」
あの二人、相性良いのではないでしょうか。そう思って蘿月様を見ると、彼も同じことを思ったようで、頷いてくれました。それからわたくしも着物を脱ぎ、蘿月様に背中にあった呪いの様子を見てもらいます。彼の指がゆっくりと噛み痕がまだ残る場所をなぞり、それから静かに息を吐きだしました。
「随分薄くなったな」
「綺麗に消えるでしょうか」
「噛み痕以外はな」
「噛み痕は消えなくていいです」
「こら」
彼が何か祈るように、わたくしの背中に口づけして、それから着物を着せてくれます。おかえり、そう呟く声に、「ただいま」と返しました。