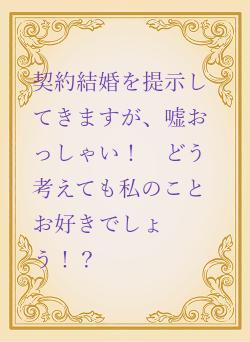あれほど乗らないために抵抗した馬車ですが、今度は馬車から降ろされないために抵抗せねばなりませんでした。じたばた暴れていると、志貴様に仕える女中が柄杓で冷水を持ってきて、ばしゃりとわたくしの顔にかけます。お清めの水のようでした。わたくしは山を下ってきたり地面に転ばされたりしたせいで、それこそ砂や泥、そして、躑躅さんの血もついていますが、そんな、悪いものを落とされるような真似はしていないはずです。心のうちからふつふつと怒りが沸き上がって、叫び出したいような気がしましたが、ここで怒りに任せて行動するようでは、彼らにとっても扱いやすいでしょう。ぎょろりと女中を睨みつけましたが、わたくしなぞが睨んでも怖くはないようで、しれっとした顔で、女中は馬車から引きずり下ろすのを手伝っていました。
担がれて運ばれ、おそらくお清めの水を張っているらしい風呂に放り込まれました。さすがに金剛とお父様はいませんでしたが、腕を縄で縛られたまま水につけられ、着物を半端に脱がせて、わたくしの身体を洗おうとするのです。足の縄が解かれ、それから猿轡を外されました。頭から冷水をかけられ、それでもなお抵抗し、ほたるの指を噛んで、口の中にじわりと血の味がにじむ中、浴室から逃げ出しました。
ほとんど裸のまま、後ろ手に縛られ、水で重たくなった着物を引きずって走ります。月のもののせいで、足の間からだらだらと血が流れていく感覚がして、気持ち悪かったのですが、縛られている時点で走りにくくて仕方ないので、気にしても仕方ありません。
「お父様、そっちよそっち、おねえさまが逃げてる」
「次琥珀が逃げたら全員打ち首だぞ、金剛、反対から回れ」
神社の出口の近い方へ走りますが、当然、椎名の家の者がそろって追いかけてきます。わたくしはあっというまに後ろの着物を踏まれ、ひっくり返りました。すると追いついたお義母様がわたくしの上に馬乗りになり、強く手を振り上げました。
「お前ッ育ててやったあたくしたちに恩はないの! あんたがまた逃げたら、あたくしたち殺されるのよッ」
バシッ、頬を打たれます。一度や二度で叩かれるのが終わったことはありませんので、いつも通り、歯を食いしばって耐えて見せます。じわりと涙が滲んできますが、この程度で屈服するようでは、蘿月様の元に帰れません。少し前のわたくしなら、過去の苦しいことが蘇って、泣き叫んでいたかもしれませんが、蘿月様と躑躅さんの元に帰ると決め込んでいる今は、不思議と、身体の奥から、逆らう勇気が沸き上がってくるのでした。
「志貴様なら、もうとっくに、あのお方に殺されている頃でしょう。あなたたちは、自分たちの行いのために滅びるのです、わたくしはあなたたちのために、人生を潰されたくはありません」
「何ですって」
「それに、あなたたちに育ててもらった覚えはありません!」
「このっ」
「わたくしを育ててくれたのは、お母様です」
あたくしたちだけでなく、萩原様を裏切るのね! お前をずっと贅沢に暮らさせていた萩原様を! お義母様がわたくしを揺さぶりながら言うので、わたくしは強く頷きました。
「わたくしは蘿月様にお仕えし、蘿月様の妻になるために生まれてきました。蘿月様の伴侶として生き、躑躅さんと友達になる。それがわたくしの望む自由です。そこにはあなたたちは要らない。志貴様も要らない。わたくしの生から、いなくなってくださいまし!」
大きな声で叫ぶと、がしゃがしゃ、と音がして、それから次にあちこちの襖や障子が倒れました。蘿月様かしら、と思い顔を上げると、お義母様が歓声を上げました。お父様も、ほたるも金剛も、みんな喜びの声を上げ、それから、その胸から吹き出し零れていく異形の者たちに、悲鳴を上げ、後ずさりしていきます。お義母様は腰が抜けたらしく、わたくしの上から動けずにいましたが、志貴様がその肩をぐいと掴むと、庭に向かって投げ捨てました。ぐしゃりと骨が折れたような音がして、お父様が駆け寄ろうとしますが、「これを傷つけるなと言ったはずだ」とひび割れた声がして、お父様も吹き飛ばされていきます。ほたると金剛は真っ青になって醜く喚きながら逃げ出し、わたくしだけが残されます。自由な足で、床を押して進もうとしますが、志貴様がわたくしを見下ろしました。ひゅっと息が止まりそうになります。
時間を稼がなければ。とっさにそう思いました。
「その様子。蘿月様に刺されましたね。それだけの傷を負えば、いずれ死ぬのではありませんか」
「お前、僕が、あれを殺したと言ったら?」
「それならば、あなたは声高らかに笑って帰ってくるでしょう。あなたがそうして、ほとんど死にかけて逃げかえってきてことが、蘿月様が無事である何よりの証拠です」
「図太くなったな」
「あなたに殴られていたら、図太くなりました」
「ふん。だが僕は、呪いの小刀をあれに刺した。いずれあれにも毒が回るよ」
志貴様――いえ、志貴の言葉の真偽は分かりませんが、今は彼はわたくしの心を折り、再び支配することに注力しているはずですから、彼の言葉に耳を傾けてはいけません。蘿月様も躑躅さんも心配ですが、今は自分の身を案じなければ、彼らに合わせる顔がありません。
「そのような呪いなど、かんなぎのわたくしの力があれば、浄化も叶いましょう」
「だがお前は今から僕が穢すよ。そんな裸体でいて、無事で済むと思うかい」
「わたくしはもうとっくに蘿月様と繋がっていますから。そのようなこと、恐れはしません」
本音を言うと、とても、怖いです。志貴のあの目が、執念ばかり籠っているあの目が恐ろしく、今も憔悴しきっている分、目ばかりが爛々と輝いていますので、わたくしの肌はざわざわと泡立っているのですが、それを悟られてはおしまいです。彼を喜ばせてしまいます。
「わたくしを支配することに喜びを見出すあなた。わたくしがそのような者に屈するとでもお思いですか。か弱い女だからといって、馬鹿にしてはいけませんよ」
こうして強がっているのも、また嗜虐心や征服欲を煽るのかもしれませんが、言いなりになるよりは良いです。わたくしが精一杯彼を睨みつけると、彼はもう良いとばかりに座って、わたくしの片足を掴みました。もう片方の足で彼の顔を蹴ると、その足も掴まれて、成す術がなくなります。肌が一層泡立って、歯がかちかち音を立てました。蘿月様、蘿月様助けて。そう心の中で叫んだ時、どすり、志貴の胸に、きっかり心臓がある位置に、刃が現れました。
「琥珀、遅くなった」
蘿月様は背側から刺した刃を抜き、再び振り上げて、すとん、と志貴の首を落としました。床に落ち、血の代わりに怨霊や小鬼やらが詰まった黒い塊を噴き出しながら、その首はまだ言葉を紡ぐのです。
「僕はこの女を、愛し――」
「わたくしは、あなたからの愛なぞ要りません。お断り申し上げます。好いた女だとしても、攫い、暴力で脅し、手籠めにするようであれば、それは愛とは呼ばぬのです」
えい、とその首を蹴とばすと、その首は宙で霧散しました。志貴の身体も粉々に消えていき、わたくしと蘿月様は、それが風に流されて消えるまで、ただそれをじっと見つめていました。
「怖い思いをさせたな。すまない、遅くなった」
先に口を開いたのは、蘿月様でした。わたくしをあまり見ないようにして抱き起して、わたくしを縛る縄を解いてくれました。自らの羽織で、まだずぶ濡れのわたくしの身体を、血がつくのも構わずに包み、水攻めにあったのかと聞いてきますので、わたくしはほんの少し笑いました。
「お義母様と妹に、水で身体を洗われまして」
「その姿でか」
「はい。この姿で、逃げてきました」
「無事で、良かった」
彼にそっと抱きしめられると、これで助かったのだという実感が湧いてきて、張りつめていた身体から、力が抜けていきます。蘿月様、ありがとうございます。お慕いしております。そう繰り返して、彼に運んでもらうようにお願いしました。やらねばならぬことが、まだ、残っています。
「お父様、いつまで寝ているのですか。このままでは、お義母様は死んでしまいますよ」
柄杓でお清めの水をすくい、お父様の顔にかけました。打ちどころが悪くなかったようで、お父様はそれで目を覚ましたのですが、わたくしを見て悲鳴を上げました。わたくしがやったとでも思っているのか、豹変した娘を恐れているのか、それは知りませんが――まあ後者でしょう。これまでのわたくしは、怯え、諦めた大人しい小娘でしたから――、お義母様を指さすと、またさらに悲鳴を上げました。お義母様の足はひどく折れているようで、足がおかしな形に曲がっていました。助かるかどうかは、医者でないわたくしには分かりませんが、まだ息はしています。助けようと思うのなら、今でしょう。
「お義母様の生死に、さほど興味が持てませんので。助けるのなら、どうぞご自由に。お父様もこのような目に遭っても、まだわたくしに縋るほどの阿呆でもないでしょう。理由もありませんし」
ほたるとお義母様はわたくしに復讐を望むかしら。躑躅さんの真似をして、妖艶に微笑んでみせます。蘿月様が空気を読んでくださって、腰に下げた刀をちらつかせてくれましたので、お父様はすっかり怯えて、もうお前に手出しはしない、だから許してくれ、と地面に頭をこすりつけて、お義母様を担いで、慌てて逃げ去っていくのでした。まだあちこちに血の残ったそこを見下ろし、わたくしはそっと息を吐きます。それから、蘿月様の首に手を回し、優しく口づけました。
「小刀で刺されたのは、本当ですか」
彼は久々にわたくしから口づけましたので、ほんの少し顔を赤らめてから頷きました。
「でも、お前に触れていれば治るよ。それで消える毒だ」
「それなら良かった」
彼にもう一度口づけをすると、急に気が緩んだようで、無理に張っていた意地がぽろりぽろりと剝がされていって、知らぬ間にわたくしは大粒の涙を流していました。涙があふれてあふれて止まらず、視界がぼやけて、ほとんどのものが見えなくなります。彼はわたくしの背をぽんぽんと撫で、あやし、随分強がったものだ、と言いました。
蘿月様の温もりだけが、すべてでした。
「お前は本来、人を虐げられるような人ではないよ」
「でも、だって」
「お義母様が助かったかどうかだけでも、躑躅に見に行かせようか」
「ええ、はい、ほんとうは、死んでいたらとおもうと」
「お前の大切な生活を守るために、無理をしたのだね」
「だって、わたくし、こわい、あの生活はいや。蘿月様の伴侶でいたいし、躑躅さんの友達でいたい」
「よく頑張ったね。辛かったな。でも、これでお前は、晴れて自由だよ」
じゆう。自由。口の中で繰り返し呟きます。涙をぬぐい、彼の姿を見ると、優しい表情で、わたくしを見下ろしていて、自由という言葉の意味を、やっと理解したような気がしました。わたくしは、自由。
「さ、服を着て、骨を取りに行こう」
女中の態度は先ほどと打って変わり、必死にわたくしたちに取り入ろうと必死でしたが、すべて無視をし、髪をふき、わたくしの部屋だった場所から、お母様の形見の着物を取り出しました。お母様にやっと会えた気がして、再び泣き出してしまいそうでしたが、手早く着物を着て、お母様のものだった帯と帯締めを使い、翡翠の骨が囚われている倉に向かいました。
骨にはいくつも呪符が張られ、多くが砕かれ、折られていました。しかしそれは、わたくしを見て、そして蘿月様を見て、会えて良かったとでも言うように笑うのです。骨ですし、それに表情というものはないのかもしれませんが、それは確かに笑っていました。目を凝らすと、そこからわたくしと歳の変わらぬ少女がふわりと浮き上がり、蘿月様の前に膝をつき、それから彼に優しく口づけをしました。彼女の魂はわたくしと同一ですし、それは気のせいと呼ばれるものなのかもしれませんが、やっと彼女が蘿月様の元に戻れたことが嬉しくて、また、わたくしの身体の一部を取り戻したような気持になり、骨を拾って袋に詰めるほどに、心が晴れていくのです。どうやら、わたくし自身も、ずっとここに囚われていたようでした。
「さ、帰ろう」
すべての骨を拾い終わると、彼が手を差し伸べてくれます。これからわたくしは、この方の元で安心して暮らしていけるのだと思うと、ほっとしました。
担がれて運ばれ、おそらくお清めの水を張っているらしい風呂に放り込まれました。さすがに金剛とお父様はいませんでしたが、腕を縄で縛られたまま水につけられ、着物を半端に脱がせて、わたくしの身体を洗おうとするのです。足の縄が解かれ、それから猿轡を外されました。頭から冷水をかけられ、それでもなお抵抗し、ほたるの指を噛んで、口の中にじわりと血の味がにじむ中、浴室から逃げ出しました。
ほとんど裸のまま、後ろ手に縛られ、水で重たくなった着物を引きずって走ります。月のもののせいで、足の間からだらだらと血が流れていく感覚がして、気持ち悪かったのですが、縛られている時点で走りにくくて仕方ないので、気にしても仕方ありません。
「お父様、そっちよそっち、おねえさまが逃げてる」
「次琥珀が逃げたら全員打ち首だぞ、金剛、反対から回れ」
神社の出口の近い方へ走りますが、当然、椎名の家の者がそろって追いかけてきます。わたくしはあっというまに後ろの着物を踏まれ、ひっくり返りました。すると追いついたお義母様がわたくしの上に馬乗りになり、強く手を振り上げました。
「お前ッ育ててやったあたくしたちに恩はないの! あんたがまた逃げたら、あたくしたち殺されるのよッ」
バシッ、頬を打たれます。一度や二度で叩かれるのが終わったことはありませんので、いつも通り、歯を食いしばって耐えて見せます。じわりと涙が滲んできますが、この程度で屈服するようでは、蘿月様の元に帰れません。少し前のわたくしなら、過去の苦しいことが蘇って、泣き叫んでいたかもしれませんが、蘿月様と躑躅さんの元に帰ると決め込んでいる今は、不思議と、身体の奥から、逆らう勇気が沸き上がってくるのでした。
「志貴様なら、もうとっくに、あのお方に殺されている頃でしょう。あなたたちは、自分たちの行いのために滅びるのです、わたくしはあなたたちのために、人生を潰されたくはありません」
「何ですって」
「それに、あなたたちに育ててもらった覚えはありません!」
「このっ」
「わたくしを育ててくれたのは、お母様です」
あたくしたちだけでなく、萩原様を裏切るのね! お前をずっと贅沢に暮らさせていた萩原様を! お義母様がわたくしを揺さぶりながら言うので、わたくしは強く頷きました。
「わたくしは蘿月様にお仕えし、蘿月様の妻になるために生まれてきました。蘿月様の伴侶として生き、躑躅さんと友達になる。それがわたくしの望む自由です。そこにはあなたたちは要らない。志貴様も要らない。わたくしの生から、いなくなってくださいまし!」
大きな声で叫ぶと、がしゃがしゃ、と音がして、それから次にあちこちの襖や障子が倒れました。蘿月様かしら、と思い顔を上げると、お義母様が歓声を上げました。お父様も、ほたるも金剛も、みんな喜びの声を上げ、それから、その胸から吹き出し零れていく異形の者たちに、悲鳴を上げ、後ずさりしていきます。お義母様は腰が抜けたらしく、わたくしの上から動けずにいましたが、志貴様がその肩をぐいと掴むと、庭に向かって投げ捨てました。ぐしゃりと骨が折れたような音がして、お父様が駆け寄ろうとしますが、「これを傷つけるなと言ったはずだ」とひび割れた声がして、お父様も吹き飛ばされていきます。ほたると金剛は真っ青になって醜く喚きながら逃げ出し、わたくしだけが残されます。自由な足で、床を押して進もうとしますが、志貴様がわたくしを見下ろしました。ひゅっと息が止まりそうになります。
時間を稼がなければ。とっさにそう思いました。
「その様子。蘿月様に刺されましたね。それだけの傷を負えば、いずれ死ぬのではありませんか」
「お前、僕が、あれを殺したと言ったら?」
「それならば、あなたは声高らかに笑って帰ってくるでしょう。あなたがそうして、ほとんど死にかけて逃げかえってきてことが、蘿月様が無事である何よりの証拠です」
「図太くなったな」
「あなたに殴られていたら、図太くなりました」
「ふん。だが僕は、呪いの小刀をあれに刺した。いずれあれにも毒が回るよ」
志貴様――いえ、志貴の言葉の真偽は分かりませんが、今は彼はわたくしの心を折り、再び支配することに注力しているはずですから、彼の言葉に耳を傾けてはいけません。蘿月様も躑躅さんも心配ですが、今は自分の身を案じなければ、彼らに合わせる顔がありません。
「そのような呪いなど、かんなぎのわたくしの力があれば、浄化も叶いましょう」
「だがお前は今から僕が穢すよ。そんな裸体でいて、無事で済むと思うかい」
「わたくしはもうとっくに蘿月様と繋がっていますから。そのようなこと、恐れはしません」
本音を言うと、とても、怖いです。志貴のあの目が、執念ばかり籠っているあの目が恐ろしく、今も憔悴しきっている分、目ばかりが爛々と輝いていますので、わたくしの肌はざわざわと泡立っているのですが、それを悟られてはおしまいです。彼を喜ばせてしまいます。
「わたくしを支配することに喜びを見出すあなた。わたくしがそのような者に屈するとでもお思いですか。か弱い女だからといって、馬鹿にしてはいけませんよ」
こうして強がっているのも、また嗜虐心や征服欲を煽るのかもしれませんが、言いなりになるよりは良いです。わたくしが精一杯彼を睨みつけると、彼はもう良いとばかりに座って、わたくしの片足を掴みました。もう片方の足で彼の顔を蹴ると、その足も掴まれて、成す術がなくなります。肌が一層泡立って、歯がかちかち音を立てました。蘿月様、蘿月様助けて。そう心の中で叫んだ時、どすり、志貴の胸に、きっかり心臓がある位置に、刃が現れました。
「琥珀、遅くなった」
蘿月様は背側から刺した刃を抜き、再び振り上げて、すとん、と志貴の首を落としました。床に落ち、血の代わりに怨霊や小鬼やらが詰まった黒い塊を噴き出しながら、その首はまだ言葉を紡ぐのです。
「僕はこの女を、愛し――」
「わたくしは、あなたからの愛なぞ要りません。お断り申し上げます。好いた女だとしても、攫い、暴力で脅し、手籠めにするようであれば、それは愛とは呼ばぬのです」
えい、とその首を蹴とばすと、その首は宙で霧散しました。志貴の身体も粉々に消えていき、わたくしと蘿月様は、それが風に流されて消えるまで、ただそれをじっと見つめていました。
「怖い思いをさせたな。すまない、遅くなった」
先に口を開いたのは、蘿月様でした。わたくしをあまり見ないようにして抱き起して、わたくしを縛る縄を解いてくれました。自らの羽織で、まだずぶ濡れのわたくしの身体を、血がつくのも構わずに包み、水攻めにあったのかと聞いてきますので、わたくしはほんの少し笑いました。
「お義母様と妹に、水で身体を洗われまして」
「その姿でか」
「はい。この姿で、逃げてきました」
「無事で、良かった」
彼にそっと抱きしめられると、これで助かったのだという実感が湧いてきて、張りつめていた身体から、力が抜けていきます。蘿月様、ありがとうございます。お慕いしております。そう繰り返して、彼に運んでもらうようにお願いしました。やらねばならぬことが、まだ、残っています。
「お父様、いつまで寝ているのですか。このままでは、お義母様は死んでしまいますよ」
柄杓でお清めの水をすくい、お父様の顔にかけました。打ちどころが悪くなかったようで、お父様はそれで目を覚ましたのですが、わたくしを見て悲鳴を上げました。わたくしがやったとでも思っているのか、豹変した娘を恐れているのか、それは知りませんが――まあ後者でしょう。これまでのわたくしは、怯え、諦めた大人しい小娘でしたから――、お義母様を指さすと、またさらに悲鳴を上げました。お義母様の足はひどく折れているようで、足がおかしな形に曲がっていました。助かるかどうかは、医者でないわたくしには分かりませんが、まだ息はしています。助けようと思うのなら、今でしょう。
「お義母様の生死に、さほど興味が持てませんので。助けるのなら、どうぞご自由に。お父様もこのような目に遭っても、まだわたくしに縋るほどの阿呆でもないでしょう。理由もありませんし」
ほたるとお義母様はわたくしに復讐を望むかしら。躑躅さんの真似をして、妖艶に微笑んでみせます。蘿月様が空気を読んでくださって、腰に下げた刀をちらつかせてくれましたので、お父様はすっかり怯えて、もうお前に手出しはしない、だから許してくれ、と地面に頭をこすりつけて、お義母様を担いで、慌てて逃げ去っていくのでした。まだあちこちに血の残ったそこを見下ろし、わたくしはそっと息を吐きます。それから、蘿月様の首に手を回し、優しく口づけました。
「小刀で刺されたのは、本当ですか」
彼は久々にわたくしから口づけましたので、ほんの少し顔を赤らめてから頷きました。
「でも、お前に触れていれば治るよ。それで消える毒だ」
「それなら良かった」
彼にもう一度口づけをすると、急に気が緩んだようで、無理に張っていた意地がぽろりぽろりと剝がされていって、知らぬ間にわたくしは大粒の涙を流していました。涙があふれてあふれて止まらず、視界がぼやけて、ほとんどのものが見えなくなります。彼はわたくしの背をぽんぽんと撫で、あやし、随分強がったものだ、と言いました。
蘿月様の温もりだけが、すべてでした。
「お前は本来、人を虐げられるような人ではないよ」
「でも、だって」
「お義母様が助かったかどうかだけでも、躑躅に見に行かせようか」
「ええ、はい、ほんとうは、死んでいたらとおもうと」
「お前の大切な生活を守るために、無理をしたのだね」
「だって、わたくし、こわい、あの生活はいや。蘿月様の伴侶でいたいし、躑躅さんの友達でいたい」
「よく頑張ったね。辛かったな。でも、これでお前は、晴れて自由だよ」
じゆう。自由。口の中で繰り返し呟きます。涙をぬぐい、彼の姿を見ると、優しい表情で、わたくしを見下ろしていて、自由という言葉の意味を、やっと理解したような気がしました。わたくしは、自由。
「さ、服を着て、骨を取りに行こう」
女中の態度は先ほどと打って変わり、必死にわたくしたちに取り入ろうと必死でしたが、すべて無視をし、髪をふき、わたくしの部屋だった場所から、お母様の形見の着物を取り出しました。お母様にやっと会えた気がして、再び泣き出してしまいそうでしたが、手早く着物を着て、お母様のものだった帯と帯締めを使い、翡翠の骨が囚われている倉に向かいました。
骨にはいくつも呪符が張られ、多くが砕かれ、折られていました。しかしそれは、わたくしを見て、そして蘿月様を見て、会えて良かったとでも言うように笑うのです。骨ですし、それに表情というものはないのかもしれませんが、それは確かに笑っていました。目を凝らすと、そこからわたくしと歳の変わらぬ少女がふわりと浮き上がり、蘿月様の前に膝をつき、それから彼に優しく口づけをしました。彼女の魂はわたくしと同一ですし、それは気のせいと呼ばれるものなのかもしれませんが、やっと彼女が蘿月様の元に戻れたことが嬉しくて、また、わたくしの身体の一部を取り戻したような気持になり、骨を拾って袋に詰めるほどに、心が晴れていくのです。どうやら、わたくし自身も、ずっとここに囚われていたようでした。
「さ、帰ろう」
すべての骨を拾い終わると、彼が手を差し伸べてくれます。これからわたくしは、この方の元で安心して暮らしていけるのだと思うと、ほっとしました。