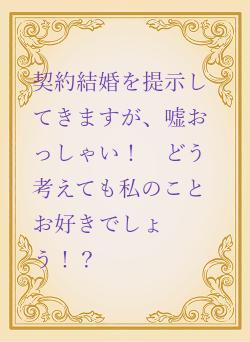琥珀は無事だろうか。そればかり、考えている。
志貴が連れてきた呪術師たちは、皆今を生きる人間でありながらも、志貴が分け与えたまやかしの力のせいで、通常のあやかしよりも厄介だった。ただ、もう、あの力を分け与えられた人間は、救えない。一生闇の世界を歩かねばならない。琥珀に知られれば悲しまれるだろうけれど、諦めて殺しはじめると、すんなり楽に終わった。首をなくした身体がごろごろ転がる境内で、首が死の間際に藻掻いて、首同士で喰い合いをしているのを横目で眺めながら、蘿月は志貴に刀の先を向けた。彼の舶来の銃は、とうに地面に散っている。
「ようやくお前を殺す時が来たな」
殺したいと思った。でもそれをしようと思うだけの強さがずっとなかった。翡翠だった頃の彼女を喪って、この痛みを抱えているのが自分だけなら、この先もずっと、ひとりで悲しみ続けたと思う。新しく生まれたかんなぎを大切に迎えて、過去に翡翠が殺されたことすら知らせずに、新しく生まれたいのちを、大切に慈しんで、守っていただろうと思う。しかし、今、新しく生まれた彼女を、彼女の自由を、あの化け物が奪おうと言うのなら、それこそ、殺さねばならない。
はっきり言って、黒橡はまだ使いこなせていない。人間に憑りついていた悪いものを吸い取っていたから、力をほとんど落とさずに済んだけれど、それでもまだ、刀が蘿月に牙をむいているのが分かる。
力を貸してくれ、黒橡。俺に従え。俺は琥珀を助けたい。もう二度と奪わせない。だからどうか、俺に従ってくれ。
「僕はあの子を愛しているんだ。僕はあの子が欲しい、だからお前を殺すよ」
「お前の愛など支配欲との間違いだ」
「別に良いだろう、女は一人では生きていけない。家に入って家に尽くすのが務めだ。家に搾取されて夫に支配されるのは、何かおかしいか」
志貴が放つ呪符を切り払いながら、蘿月は駆ける。
「そうだろうな。まだ、女は一人では生活が立ち行かん。だとしても、搾取して良い謂われはないだろう。俺は琥珀に自由を与えたい。その上で、望んで俺の元にいてくれるように、琥珀を大切にしたい」
「綺麗ごとを言う。だからお前は五百年前に僕に翡翠をとられたんだ」
「死ね」
振りかざした刃に呪符が張り付くも、刀の力で吸い込まれていくのが分かった。なるほど、腕羅屍鬼対策と言っただけある。彼が喰らってきた数多の力に適応できる、柔軟さがある。しかし蘿月への負担が大きい。
「お前さえいなくなれば、あの子はこの先永遠、僕のものだ」
消耗戦に持ち込めば、蘿月が負けるだろう。早急に決着をつけねばならない。
「僕のもの、だと。琥珀を物扱いした時点で、お前の負けよ」
刀を振りかざして、蘿月は不敵に笑った。
蘿月がずっと山の中に籠って磨いていたのは、これまで蘿月が取り込み、祟りとした呪いを、的確に急所に打ち込む訓練だった。志貴も屍鬼と呼ばれるような化け物であるが、元は人間である。急所は変わらない。打ち合いを続け、蘿月の放った一撃が彼の心臓を貫き、そして祟りの力をそこに注ぎ込んだ。
彼がその一瞬で消えなかったのは、執念のためか。這う這うの体で逃げ出していったが、蘿月もまた、血を吐き、その場に崩れ落ちた。腹に小刀が突き刺さっている。屋敷の中に身体を引きずって戻り、霊薬を取り出して、それを飲みながら、小刀を引きぬいた。こぼれ出る血をぬぐい、もう一つ霊薬を飲むと、がらがらと玄関が開いて、下駄の音が入ってくる。
「追手が来て、琥珀を逃がしたわ」
霊薬を投げると、彼女はぐいと三本それを飲み干した。血だらけの着物は、彼女と敵の激しい戦いを示しているようだったが、それの半分は返り血であるだろうというのは、匂いで分かる。
「あとは心配なのは、琥珀が人間に捕まってないか」
「この騒動で椎名が動くことだな。俺は今から志貴の持つ屋敷に行く」
「ごめんね、最後まであの子についてあげられなかった」
「良い、よくやった。お前は休んで、それから死体を片付けてくれ」
人使い――じゃない、狐使いが荒いんだからもう。彼女がそう妖艶に笑って、それからその場に崩れ落ちた。彼女の目の前に霊薬をいくつか置いてやり、蘿月も身体に鞭打って、立ち上がる。琥珀の気配を辿ると、ぼんやりしか分からず、おそらく、あの神社の結界の中にいるのだろうと思った。ぎりと奥歯が音を立てる。
俺にはじめて、愛を教えて、名前を呼んでくれたさくや。
お役目なんて知らないと言いながらも、ずっと俺の傍にいてくれたさよ。
あなたのおかげで朝が好きになれた。そう言ってくれたすず。
あなたにお仕えできるなんて幸せです。そう言ってくれたのに、翡翠。助けられなくて、すまなかった。
お前たちが繋いだ魂。愛おしい琥珀。どれだけ酷い目になっても、優しさを忘れなかった少女。いとおしい花妻。あと少しだけ、待っていてくれ。
志貴が連れてきた呪術師たちは、皆今を生きる人間でありながらも、志貴が分け与えたまやかしの力のせいで、通常のあやかしよりも厄介だった。ただ、もう、あの力を分け与えられた人間は、救えない。一生闇の世界を歩かねばならない。琥珀に知られれば悲しまれるだろうけれど、諦めて殺しはじめると、すんなり楽に終わった。首をなくした身体がごろごろ転がる境内で、首が死の間際に藻掻いて、首同士で喰い合いをしているのを横目で眺めながら、蘿月は志貴に刀の先を向けた。彼の舶来の銃は、とうに地面に散っている。
「ようやくお前を殺す時が来たな」
殺したいと思った。でもそれをしようと思うだけの強さがずっとなかった。翡翠だった頃の彼女を喪って、この痛みを抱えているのが自分だけなら、この先もずっと、ひとりで悲しみ続けたと思う。新しく生まれたかんなぎを大切に迎えて、過去に翡翠が殺されたことすら知らせずに、新しく生まれたいのちを、大切に慈しんで、守っていただろうと思う。しかし、今、新しく生まれた彼女を、彼女の自由を、あの化け物が奪おうと言うのなら、それこそ、殺さねばならない。
はっきり言って、黒橡はまだ使いこなせていない。人間に憑りついていた悪いものを吸い取っていたから、力をほとんど落とさずに済んだけれど、それでもまだ、刀が蘿月に牙をむいているのが分かる。
力を貸してくれ、黒橡。俺に従え。俺は琥珀を助けたい。もう二度と奪わせない。だからどうか、俺に従ってくれ。
「僕はあの子を愛しているんだ。僕はあの子が欲しい、だからお前を殺すよ」
「お前の愛など支配欲との間違いだ」
「別に良いだろう、女は一人では生きていけない。家に入って家に尽くすのが務めだ。家に搾取されて夫に支配されるのは、何かおかしいか」
志貴が放つ呪符を切り払いながら、蘿月は駆ける。
「そうだろうな。まだ、女は一人では生活が立ち行かん。だとしても、搾取して良い謂われはないだろう。俺は琥珀に自由を与えたい。その上で、望んで俺の元にいてくれるように、琥珀を大切にしたい」
「綺麗ごとを言う。だからお前は五百年前に僕に翡翠をとられたんだ」
「死ね」
振りかざした刃に呪符が張り付くも、刀の力で吸い込まれていくのが分かった。なるほど、腕羅屍鬼対策と言っただけある。彼が喰らってきた数多の力に適応できる、柔軟さがある。しかし蘿月への負担が大きい。
「お前さえいなくなれば、あの子はこの先永遠、僕のものだ」
消耗戦に持ち込めば、蘿月が負けるだろう。早急に決着をつけねばならない。
「僕のもの、だと。琥珀を物扱いした時点で、お前の負けよ」
刀を振りかざして、蘿月は不敵に笑った。
蘿月がずっと山の中に籠って磨いていたのは、これまで蘿月が取り込み、祟りとした呪いを、的確に急所に打ち込む訓練だった。志貴も屍鬼と呼ばれるような化け物であるが、元は人間である。急所は変わらない。打ち合いを続け、蘿月の放った一撃が彼の心臓を貫き、そして祟りの力をそこに注ぎ込んだ。
彼がその一瞬で消えなかったのは、執念のためか。這う這うの体で逃げ出していったが、蘿月もまた、血を吐き、その場に崩れ落ちた。腹に小刀が突き刺さっている。屋敷の中に身体を引きずって戻り、霊薬を取り出して、それを飲みながら、小刀を引きぬいた。こぼれ出る血をぬぐい、もう一つ霊薬を飲むと、がらがらと玄関が開いて、下駄の音が入ってくる。
「追手が来て、琥珀を逃がしたわ」
霊薬を投げると、彼女はぐいと三本それを飲み干した。血だらけの着物は、彼女と敵の激しい戦いを示しているようだったが、それの半分は返り血であるだろうというのは、匂いで分かる。
「あとは心配なのは、琥珀が人間に捕まってないか」
「この騒動で椎名が動くことだな。俺は今から志貴の持つ屋敷に行く」
「ごめんね、最後まであの子についてあげられなかった」
「良い、よくやった。お前は休んで、それから死体を片付けてくれ」
人使い――じゃない、狐使いが荒いんだからもう。彼女がそう妖艶に笑って、それからその場に崩れ落ちた。彼女の目の前に霊薬をいくつか置いてやり、蘿月も身体に鞭打って、立ち上がる。琥珀の気配を辿ると、ぼんやりしか分からず、おそらく、あの神社の結界の中にいるのだろうと思った。ぎりと奥歯が音を立てる。
俺にはじめて、愛を教えて、名前を呼んでくれたさくや。
お役目なんて知らないと言いながらも、ずっと俺の傍にいてくれたさよ。
あなたのおかげで朝が好きになれた。そう言ってくれたすず。
あなたにお仕えできるなんて幸せです。そう言ってくれたのに、翡翠。助けられなくて、すまなかった。
お前たちが繋いだ魂。愛おしい琥珀。どれだけ酷い目になっても、優しさを忘れなかった少女。いとおしい花妻。あと少しだけ、待っていてくれ。