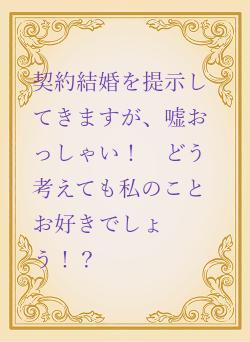芙蓉さんが神社の階段の前で立ち尽くしていたのは、翌朝のことでした。わたくしは朝、街の様子が少しでも見えないかと思い、階段のところにまだ少し熱っぽい身体を引きずって行ったのですが、そこに立ちすくむ芙蓉さんの姿が、何かおかしいことに気が付きました。頼りたいのなら頼れば良い。芙蓉さんとは仲良く話している間柄ですから、生き延びたのなら、まっすぐに走り寄ってくれるでしょう。それをしないのであれば、何か出来ない事情があるであろうことは、明白でした。
きっとこの神社の中で、一番悪意に敏感であるわたくしが、悪意に疎い蘿月様を守ってみせましょう。そう誓ったことを思い出し、わたくしは階段を一歩ずつ降りていきます。ちらと振り返って、躑躅さんが庭掃除をしていることと、蘿月様が庭であくびをしていることを確かめました。そして階段の途中で、透き通るような声色であるように気を付けて、彼女を呼びます。
「芙蓉さん」
返事はありません。これはいよいよ、何か抱えているようです。
近づくと、芙蓉さんがきっと英吉利結びにしていたであろう髪は、ひどく乱れ、あちこちに砂や煤がついていました。着物もまた乱されたのだと分かるものがあり、煤や砂で汚れたそれを、慌てて着て、逃げ出してきたのであろうことが伺えます。あれほど活発な方が、憔悴して、おびえて、わたくしのことも見ようとしないのですから、ひどい目に遭ってきたに違いありませんでした。
「もしや、椎名と名乗る者に会いましたか」
彼女がばっと顔を上げました。やはりそうでしたか、と悲しくなる一方、自分たちの存在をひけらかし、その権威を振りかざして、人を支配しようとする彼らを、憎らしく、痛々しく、恨めしく思いました。生家をこれほど憎らしく思ったのも、はじめてかもしれません。
「火事は、あなたのせいですか」
「違うわ、違います」
「あなたのせいにすると、言われたのですか」
返事がないことを見ると、その通りなのかもしれません。もしくは、住む家を工面してあげようと言われたとか、そんなことかもしれません。ただ、確かだと言えることは、椎名の家の者に、彼女が火事の件で脅されている、ということでしょうか。
「わたくしを、結界の外に連れだせ、というところでしょうか」
「違います」
彼女が嫌にきっぱり言うので、近いところに答えがあるのだろうと思いました。志貴様がすることであればたいてい分かりますので、わたくしは彼女の乱れた着物の下を想像してみます。
「巻き込んでしまって、ごめんなさい。肌に直接、呪いをかけられたのですね」
「ち、ちが」
「当たりましたか。蘿月様ならその呪い、吸い取ってくれるでしょう」
わたくしは階段を一歩、二歩、上がります。きっと、彼女がそこで立ち止まっているのなら、そこはまだ取り返しのつく場所なのでしょう。彼女に決してそこから動かないように言い聞かせ、わたくしがじりじりと神社の方へ戻ろうとしますと、彼女は突然わぁと泣き崩れて、大きな声を上げました。それからその大きな瞳が、わたくしを見据えました。これは、覚悟を決めてしまったらしい、そう気が付いたわたくしがだっと階段を駆け上がるのと、彼女がこちらに向かって、走り出したのは、ほとんど同時でした。
ばき、ぱき、ぱりん。頭上から音がして、結界が破られたのだと悟りました。
「蘿月様! 蘿月様!」
芙蓉さんの身体に刻まれたのは、結界破りの呪い。後ろ盾もなければ、お金もない、そして家をなくして彼女を、さらに追い詰め、支配して、何か条件と引き換えに、呪いを植え付けたのでしょう。失敗すれば殺すとでも言われたのでしょうか。分かりませんが、きっと、結界を破らせたということは、志貴様の手の者がそこに控えているはずです。案の定、黒い影が神社の中に飛び込んできて、わたくしの周囲を囲いました。またあの場に戻されるのかと思うと、目の前が真っ暗になるようでしたが、その闇は、蘿月様が引き裂いてくれました。蘿月様は崩れ落ちそうになるわたくしを抱きとめてすぐに、声を張り上げます。彼のこれほど緊迫した声は、初めて聞きました。
「躑躅、裏の結界はまだ生きている。琥珀を連れて逃げろ」
「あんた一人でここ止められるの?」
「分散する方が確実だ」
駆け寄った躑躅さんがわたくしの前で、ぼんと音を立てて、大きな狐の姿に変わります。わたくしが乗ることを想定していたのか、首のところに太い縄が巻かれていて、わたくしが掴めるようになっていた。
「乗って」
「でも」
「逃げろ琥珀」
蘿月様がわたくしの身体を持ち上げ、躑躅さんの背に乗せました。着物が乱れますが、気にしている場合ではありません。芙蓉さんのことも気になりましたが、彼女を連れていく余裕もありませんでした。
「蘿月様」
「早く、行け躑躅。志貴が来る」
躑躅さんの首の縄をつかむと、躑躅さんが走り出します。蘿月様、ご無事で。そうわたくしが振り返った時、見慣れた影が、舶来の小銃を抱えているのが見えました。
「躑躅さん、跳んでッ」
「跳べッ躑躅!」
躑躅さんが半身で振り返りながら跳んだ時、重たい銃声が響きます。躑躅さんが跳躍するのは想定のうちだったのか、志貴様が放った銃弾は、まっすぐに躑躅さんの腹を穿ちました。ゲホッ、そんな声が躑躅さんの口から零れましたが、彼女は決して足を止めることはありませんでした。
「躑躅さん、躑躅さん!」
「黙ってなさい、舌噛むわよ」
振り返ると、躑躅さんの走った後には血が点々と落ちていき、道を作っていきます。止血しなければ躑躅さんが危ない、と思ったのですが、振り落とされないようにしながらも止血するのはただの人間には出来ず、躑躅さん、止まって、と叫ぶしかありませんでした。
崖をとんと乗り越えた先の森の、獣道を走っていきながら、躑躅さんは一度血を吐きました。血がわたくしの顔に少しつき、涙を堪えます。
「九尾になっておいて、こんなんで死んでたまるかって話よ、くそ、志貴め」
「ごめんなさい」
「あんたが謝ることじゃないッ」
「でも、志貴様、わたくしを」
「だから舌噛むわよ! あたしはねえ、二千年前に、飢えてたところを助けてもらってるのよッ。あんたがあたしに生きてて良いって言った! 仲間殺して生き残って、妖狐になったあたしを!」
あんたがあんたでいる限り、絶対にあたしは味方でいる。絶対に助ける。蘿月と一緒に生きる道をあたしが作る。彼女はそう叫んで、獣道を走り、横道に逸れて、また獣道に入ってと繰り返しました。わたくしは無力で、ただ涙を零すしかなく、悔しく思いましたが、そんなわたくしに彼女は微笑むような声をかけるのです。
「泣かないで。妖狐だもの、霊薬飲めば平気よ。それより蘿月を祈ってあげて。そして自分の心配をしなさい」
振り落とされないで。そう言う彼女に頷いて、山を駆け抜け、やがて山の終わりが見えた頃、急に立ち止まりました。人間に化けた彼女が、宙に飛ばされたわたくしを受け止め、そして、「走って!」と叫びました。
「分かってはいたけど追手よ」
見れば、前方から鎧武者のようなものが駆けあがってきます。躑躅さんがそこに向かって、指を何か形作り、ぷうと息を吹きかけると、鎧武者に炎がつきます。
「あたしが抑える、だから走って」
「躑躅さん」
「追手が後ろにいるのよ、犯人はそいつ。早く!」
わたくしの足は竦みましたが、躑躅さんに背を押され、半ば転がるようにして山を下っていきます。転ばないためにわたくしの足は必死に動き、身体を支えます。
「危ないのはあやかし、でも一番怖いのは人間。気を付けて!」
躑躅さんの声に答える余裕はありませんでしたが、後ろから躑躅さんが何かを激しく蹴とばすような声と音がして、振り返ることもできませんでした。どうか無事でいて、どうか無事でいて。そう祈りながら、獣道を駆け下りていきます。やがて山が途絶え、平な地面にたどり着いた時、その目の前には馬車がありました。怖いのは人間。怖いのは人間。助けを乞うてはいけない――。そう直観し、人の多い街に向かって走ろうとしたところ、朝結ぶこともできなかった髪を、後ろからむんずと掴まれます。
「お父様、お父様、琥珀おねえさま捕まえたわ!」
ほたるでした。ほたるの力は弱く、突飛ばせば簡単に離してくれましたが、目の前現れた金剛に足をかけられます。あっという間に地面が近くなり、肘を大きくこすりました。すると金剛はさっとわたくしの背に馬乗りになり、持っていた縄で乱暴にわたくしを縛り上げていくのです。
「やめて、離して」
「ねえさんのせいで、どれだけ大変だったか」
「それは身から出た錆というのよ! 身の丈に合わない生活をするから!」
「わたくしなんて、せっかく婚約者見つかったのに、全部なしよ、琥珀おねえさまのせいよ」
「それはおねだりが大好きなほたるのせいだわ、ほたるがドレスを強請ったんでしょう? あなたのドレスなんてほんとはお父様のお給金じゃ買えないのよ。男の人だって、あんたのお家にお金がなくちゃ、あんたのこと欲しくないのよ、養ってもらう立場なのが分からないの?」
「金剛、おねえさまを黙らせてっ」
口に手ぬぐいを切ったものが詰め込まれ、その上から猿轡を噛まされます。これだけ騒いでも誰も人が様子を見に来ないのですから、こうなってはもう、観念する他ないのかもしれませんが、わたくしはわたくしを愛してくれる人たちの元に帰りたいのです。命がけでわたくしを逃がした蘿月様と躑躅さんの元に帰りたいのです。生きる場所はわたくしが選びたいのです。それが自由だというのなら、わたくしはもう、自由を知っています。もう二度と、わたくしを屈服させることに快感を得る人たちの元には、帰りたくありません。そのための抵抗は、惜しみたくありませんでした。
足をばたつかせると、寄ろうとしてきたお義母様を蹴とばすことができました。お父様に仰向けにされて、それから足を縛られ、馬車に運ばれます。猿轡さえ無ければ、金剛の腕を噛んでやるというのに、どれだけ藻掻いても猿轡が外れません。馬車に投げ込まれた後も闇雲に身体を動かして、金剛を馬車から一度だけ落とすのに成功しましたが、その後は押さえつけられるばかりでした。
「手間かけさせやがって。お前のせいでどれだけ苦労を」
「でもこれで萩原から支援金を貰えるわ。またドレスが着られるのよね」
「質から取り戻さないといけないね」
「でも、この子がこんなに抵抗するなんて」
こんなしぶとい子に育てた覚えはないわよ、とお義母様が言いますので、「あなたに育てられた覚えはない」と言ってやりたかったのですが、彼らは芋虫のように転がるわたくしを嗤うだけでした。やがて馬車が止まり、たどり着いたのは、案の定嶋神社でした。
きっとこの神社の中で、一番悪意に敏感であるわたくしが、悪意に疎い蘿月様を守ってみせましょう。そう誓ったことを思い出し、わたくしは階段を一歩ずつ降りていきます。ちらと振り返って、躑躅さんが庭掃除をしていることと、蘿月様が庭であくびをしていることを確かめました。そして階段の途中で、透き通るような声色であるように気を付けて、彼女を呼びます。
「芙蓉さん」
返事はありません。これはいよいよ、何か抱えているようです。
近づくと、芙蓉さんがきっと英吉利結びにしていたであろう髪は、ひどく乱れ、あちこちに砂や煤がついていました。着物もまた乱されたのだと分かるものがあり、煤や砂で汚れたそれを、慌てて着て、逃げ出してきたのであろうことが伺えます。あれほど活発な方が、憔悴して、おびえて、わたくしのことも見ようとしないのですから、ひどい目に遭ってきたに違いありませんでした。
「もしや、椎名と名乗る者に会いましたか」
彼女がばっと顔を上げました。やはりそうでしたか、と悲しくなる一方、自分たちの存在をひけらかし、その権威を振りかざして、人を支配しようとする彼らを、憎らしく、痛々しく、恨めしく思いました。生家をこれほど憎らしく思ったのも、はじめてかもしれません。
「火事は、あなたのせいですか」
「違うわ、違います」
「あなたのせいにすると、言われたのですか」
返事がないことを見ると、その通りなのかもしれません。もしくは、住む家を工面してあげようと言われたとか、そんなことかもしれません。ただ、確かだと言えることは、椎名の家の者に、彼女が火事の件で脅されている、ということでしょうか。
「わたくしを、結界の外に連れだせ、というところでしょうか」
「違います」
彼女が嫌にきっぱり言うので、近いところに答えがあるのだろうと思いました。志貴様がすることであればたいてい分かりますので、わたくしは彼女の乱れた着物の下を想像してみます。
「巻き込んでしまって、ごめんなさい。肌に直接、呪いをかけられたのですね」
「ち、ちが」
「当たりましたか。蘿月様ならその呪い、吸い取ってくれるでしょう」
わたくしは階段を一歩、二歩、上がります。きっと、彼女がそこで立ち止まっているのなら、そこはまだ取り返しのつく場所なのでしょう。彼女に決してそこから動かないように言い聞かせ、わたくしがじりじりと神社の方へ戻ろうとしますと、彼女は突然わぁと泣き崩れて、大きな声を上げました。それからその大きな瞳が、わたくしを見据えました。これは、覚悟を決めてしまったらしい、そう気が付いたわたくしがだっと階段を駆け上がるのと、彼女がこちらに向かって、走り出したのは、ほとんど同時でした。
ばき、ぱき、ぱりん。頭上から音がして、結界が破られたのだと悟りました。
「蘿月様! 蘿月様!」
芙蓉さんの身体に刻まれたのは、結界破りの呪い。後ろ盾もなければ、お金もない、そして家をなくして彼女を、さらに追い詰め、支配して、何か条件と引き換えに、呪いを植え付けたのでしょう。失敗すれば殺すとでも言われたのでしょうか。分かりませんが、きっと、結界を破らせたということは、志貴様の手の者がそこに控えているはずです。案の定、黒い影が神社の中に飛び込んできて、わたくしの周囲を囲いました。またあの場に戻されるのかと思うと、目の前が真っ暗になるようでしたが、その闇は、蘿月様が引き裂いてくれました。蘿月様は崩れ落ちそうになるわたくしを抱きとめてすぐに、声を張り上げます。彼のこれほど緊迫した声は、初めて聞きました。
「躑躅、裏の結界はまだ生きている。琥珀を連れて逃げろ」
「あんた一人でここ止められるの?」
「分散する方が確実だ」
駆け寄った躑躅さんがわたくしの前で、ぼんと音を立てて、大きな狐の姿に変わります。わたくしが乗ることを想定していたのか、首のところに太い縄が巻かれていて、わたくしが掴めるようになっていた。
「乗って」
「でも」
「逃げろ琥珀」
蘿月様がわたくしの身体を持ち上げ、躑躅さんの背に乗せました。着物が乱れますが、気にしている場合ではありません。芙蓉さんのことも気になりましたが、彼女を連れていく余裕もありませんでした。
「蘿月様」
「早く、行け躑躅。志貴が来る」
躑躅さんの首の縄をつかむと、躑躅さんが走り出します。蘿月様、ご無事で。そうわたくしが振り返った時、見慣れた影が、舶来の小銃を抱えているのが見えました。
「躑躅さん、跳んでッ」
「跳べッ躑躅!」
躑躅さんが半身で振り返りながら跳んだ時、重たい銃声が響きます。躑躅さんが跳躍するのは想定のうちだったのか、志貴様が放った銃弾は、まっすぐに躑躅さんの腹を穿ちました。ゲホッ、そんな声が躑躅さんの口から零れましたが、彼女は決して足を止めることはありませんでした。
「躑躅さん、躑躅さん!」
「黙ってなさい、舌噛むわよ」
振り返ると、躑躅さんの走った後には血が点々と落ちていき、道を作っていきます。止血しなければ躑躅さんが危ない、と思ったのですが、振り落とされないようにしながらも止血するのはただの人間には出来ず、躑躅さん、止まって、と叫ぶしかありませんでした。
崖をとんと乗り越えた先の森の、獣道を走っていきながら、躑躅さんは一度血を吐きました。血がわたくしの顔に少しつき、涙を堪えます。
「九尾になっておいて、こんなんで死んでたまるかって話よ、くそ、志貴め」
「ごめんなさい」
「あんたが謝ることじゃないッ」
「でも、志貴様、わたくしを」
「だから舌噛むわよ! あたしはねえ、二千年前に、飢えてたところを助けてもらってるのよッ。あんたがあたしに生きてて良いって言った! 仲間殺して生き残って、妖狐になったあたしを!」
あんたがあんたでいる限り、絶対にあたしは味方でいる。絶対に助ける。蘿月と一緒に生きる道をあたしが作る。彼女はそう叫んで、獣道を走り、横道に逸れて、また獣道に入ってと繰り返しました。わたくしは無力で、ただ涙を零すしかなく、悔しく思いましたが、そんなわたくしに彼女は微笑むような声をかけるのです。
「泣かないで。妖狐だもの、霊薬飲めば平気よ。それより蘿月を祈ってあげて。そして自分の心配をしなさい」
振り落とされないで。そう言う彼女に頷いて、山を駆け抜け、やがて山の終わりが見えた頃、急に立ち止まりました。人間に化けた彼女が、宙に飛ばされたわたくしを受け止め、そして、「走って!」と叫びました。
「分かってはいたけど追手よ」
見れば、前方から鎧武者のようなものが駆けあがってきます。躑躅さんがそこに向かって、指を何か形作り、ぷうと息を吹きかけると、鎧武者に炎がつきます。
「あたしが抑える、だから走って」
「躑躅さん」
「追手が後ろにいるのよ、犯人はそいつ。早く!」
わたくしの足は竦みましたが、躑躅さんに背を押され、半ば転がるようにして山を下っていきます。転ばないためにわたくしの足は必死に動き、身体を支えます。
「危ないのはあやかし、でも一番怖いのは人間。気を付けて!」
躑躅さんの声に答える余裕はありませんでしたが、後ろから躑躅さんが何かを激しく蹴とばすような声と音がして、振り返ることもできませんでした。どうか無事でいて、どうか無事でいて。そう祈りながら、獣道を駆け下りていきます。やがて山が途絶え、平な地面にたどり着いた時、その目の前には馬車がありました。怖いのは人間。怖いのは人間。助けを乞うてはいけない――。そう直観し、人の多い街に向かって走ろうとしたところ、朝結ぶこともできなかった髪を、後ろからむんずと掴まれます。
「お父様、お父様、琥珀おねえさま捕まえたわ!」
ほたるでした。ほたるの力は弱く、突飛ばせば簡単に離してくれましたが、目の前現れた金剛に足をかけられます。あっという間に地面が近くなり、肘を大きくこすりました。すると金剛はさっとわたくしの背に馬乗りになり、持っていた縄で乱暴にわたくしを縛り上げていくのです。
「やめて、離して」
「ねえさんのせいで、どれだけ大変だったか」
「それは身から出た錆というのよ! 身の丈に合わない生活をするから!」
「わたくしなんて、せっかく婚約者見つかったのに、全部なしよ、琥珀おねえさまのせいよ」
「それはおねだりが大好きなほたるのせいだわ、ほたるがドレスを強請ったんでしょう? あなたのドレスなんてほんとはお父様のお給金じゃ買えないのよ。男の人だって、あんたのお家にお金がなくちゃ、あんたのこと欲しくないのよ、養ってもらう立場なのが分からないの?」
「金剛、おねえさまを黙らせてっ」
口に手ぬぐいを切ったものが詰め込まれ、その上から猿轡を噛まされます。これだけ騒いでも誰も人が様子を見に来ないのですから、こうなってはもう、観念する他ないのかもしれませんが、わたくしはわたくしを愛してくれる人たちの元に帰りたいのです。命がけでわたくしを逃がした蘿月様と躑躅さんの元に帰りたいのです。生きる場所はわたくしが選びたいのです。それが自由だというのなら、わたくしはもう、自由を知っています。もう二度と、わたくしを屈服させることに快感を得る人たちの元には、帰りたくありません。そのための抵抗は、惜しみたくありませんでした。
足をばたつかせると、寄ろうとしてきたお義母様を蹴とばすことができました。お父様に仰向けにされて、それから足を縛られ、馬車に運ばれます。猿轡さえ無ければ、金剛の腕を噛んでやるというのに、どれだけ藻掻いても猿轡が外れません。馬車に投げ込まれた後も闇雲に身体を動かして、金剛を馬車から一度だけ落とすのに成功しましたが、その後は押さえつけられるばかりでした。
「手間かけさせやがって。お前のせいでどれだけ苦労を」
「でもこれで萩原から支援金を貰えるわ。またドレスが着られるのよね」
「質から取り戻さないといけないね」
「でも、この子がこんなに抵抗するなんて」
こんなしぶとい子に育てた覚えはないわよ、とお義母様が言いますので、「あなたに育てられた覚えはない」と言ってやりたかったのですが、彼らは芋虫のように転がるわたくしを嗤うだけでした。やがて馬車が止まり、たどり着いたのは、案の定嶋神社でした。